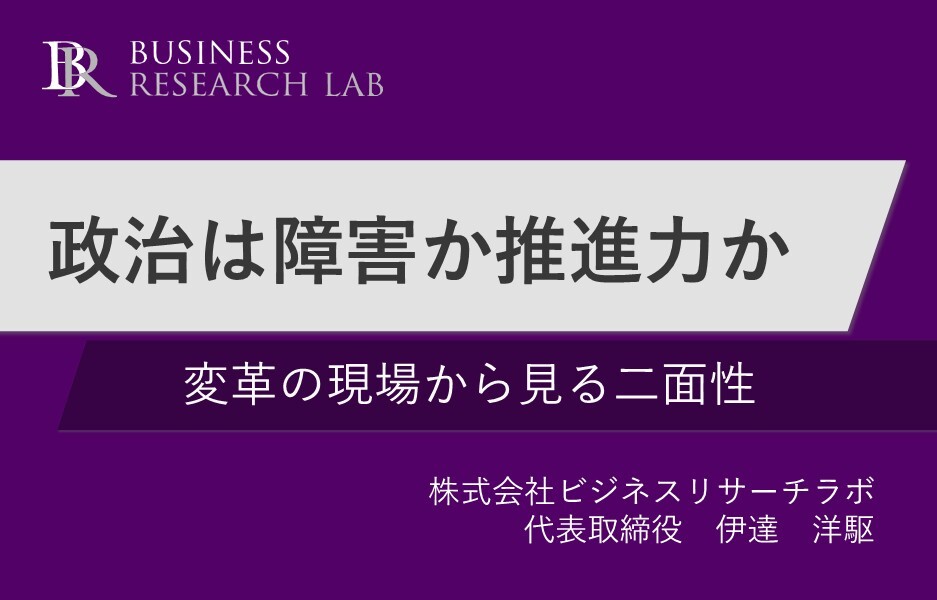2026年1月23日
政治は障害か推進力か:変革の現場から見る二面性
私たちの多くは、一日の大半を会社や学校といった「組織」という場で過ごします。そこでは、事業計画、予算配分、人事といった何らかの意思決定がなされています。私たちは、こうした決定が論理的で合理的な根拠に基づいて行われていると信じたい、あるいは、そうあるべきだと考えています。
しかし、日々の業務の中で、どこか腑に落ちない決定や、不可解な力学に首をかしげた経験はないでしょうか。「なぜ、あの部署ばかりが優遇されるのか」といった疑問の背後には、公式な組織図や規則だけでは説明のつかない、もう一つの力学が働いているのかもしれません。それは、人々が自らの利益や信条を実現するために繰り広げる駆け引きや交渉、すなわち「政治」です。
本コラムでは、組織を動かす、この目に見えない力学に光を当てていきます。個人の内面ではなく、組織全体を覆う構造として、政治がどのように生まれ、意思決定を形作っていくのか。研究知見を頼りに、その実態を解き明かします。合理的であるはずの組織の、非合理に見える側面に潜む論理を探ることで、私たちが日々直面する組織の「なぜ」を理解する一助となればと思います。
組織の意思決定は、部署が持つ政治的な権力が左右する
組織における現実的な問題の一つに、資源の配分があります。どの部署にどれだけの予算が割り当てられるかは、その後の活動を左右します。一般に、予算配分は業務量や実績といった客観的な基準で、公平に行われると考えられています。しかし、現実は本当にそうなのでしょうか。
この問いに切り込んだ、ある大学を舞台にした研究があります[1]。13年という長期間にわたり、29の学部への予算配分データが分析されました。組織の意思決定の捉え方には、効率性などの合理的な基準を想定する「官僚モデル」と、交渉や力関係といった政治的な過程を想定する「連合モデル」があります。この研究は、どちらのモデルが現実をよりよく説明できるのかを検証しようとしました。
合理的な基準として、各学部の「ワークロード」が測定されました。これは主に、授業の履修学生数と単位数を掛け合わせた「指導単位」で数値化され、学部の業務量を客観的に表します。官僚モデルが正しければ、この指導単位が多い学部ほど、多くの予算を得るはずです。
一方で、政治的な基準として、各学部が持つ「権力」が測定されました。権力という目に見えないものを測るため、二つの異なる方法が用いられました。一つは、全学部長へのインタビューに基づき、各学部の力を評価してもらう主観的な手法です。もう一つは、大学の公式記録を調べ、予算委員会といった主要な運営委員会に各学部からどれだけの教員が参加しているかを数える、客観的な手法です。
分析の結果、学部の予算獲得率は、合理的な基準である「指導単位」だけでは説明しきれず、「学部の権力」によっても左右されていることが判明しました。教育上のワークロードが同程度の二つの学部があったとしても、大学内で権力を持つ学部の方が、多くの予算を手にしていたのです。この結果は、組織の資源配分が、客観的な基準のみならず、政治的な力関係によって影響を受ける実態を明らかにしています。
この研究は、さらに踏み込んだ分析も行っています。学部の規模(教員数など)や全国的な学術ランキングといった「名声」を統計的に考慮しても、学内での権力と予算配分の間の関係は揺るぎませんでした。
注目すべきは、権力が持つ「防衛機能」です。13年間のデータで、各学部のワークロードの変動と予算額の変動の関係を調べると、権力の強い学部ほど、両者の相関が低いことが分かりました。ある権力の弱い学部では、学生の増減に予算が直結していたのに対し、ある権力の強い学部では、ワークロードが減っても予算は減らず、むしろ増えることさえありました。
このことから考えられるのは、権力を持つ部署が、外部環境の変化から自らの組織を守り、安定的に資源を確保する能力を持つということです。組織における政治的な権力は、資源を獲得する力であると同時に、獲得した資源を維持するための盾としても機能しています。
組織の政治は権力分散でなく、CEOへの権力集中から生まれる
先ほどは、部署が持つ権力が予算配分を左右する様相を見ました。このような組織全体の政治的な動きは、どこから生まれてくるのでしょうか。一般には、権力が分散している状態の方が、各々が利益のために動き、政治的な駆け引きが活発化すると考えられます。しかし、本当にそうなのでしょうか。
この通説に一石を投じる、変化の激しいマイクロコンピュータ業界の8社を対象とした研究があります[2]。トップマネジメントチームで戦略的意思決定がどう行われるかを調査したものです。ここでいう「政治」とは、派閥形成や非公式な根回し、意図的な情報操作といった、水面下での影響力行使を指します。公式な場でオープンに議論するのとは対照的な動きです。
研究者たちは各社の経営幹部全員にインタビューを行い、データの中から理論を立ち上げていきました。そこから浮かび上がってきたのは、従来の想定とは異なる構図でした。調査から導き出されたのは、「CEOへの権力集中度が高いほど、トップマネジメントチーム内での政治利用は増大する」という発見です。
政治が活発な企業では、例外なくCEOが絶大な権力を握り、独裁的に振る舞っていました。このような強力なリーダーの下では、他の役員は公式な場で意見を反映させることが困難になります。その結果、行き場を失った意見や欲求不満は、非公式な会合や裏でのロビー活動といった、政治的な行動へと向かわざるを得なかったのです。
逆に、CEOが部下と権力を分かち合う企業では、役員たちは政治的な動きを「時間の無駄」と考えていました。意見の対立が激しくても、それは会議の場で正面から議論され、最終的に責任者が判断を下すという健全なプロセスが機能していました。役員たちは、たとえ自分の意見が採用されなくても、議論の場で考えを表明できたことに納得感を得ていました。対立が政治へと転化するのは、権力がCEOに集中し、オープンな議論の場が失われた場合に限られていました。
この研究は、政治の「構造」にも迫っています。政治が活発なチームでは、固定的な派閥が形成されていました。問題が変わっても、同じメンバーが連携し、対立していました。その派閥形成の基準は、戦略や意見の一致ではなく、年齢が近い、オフィスの場所が隣同士といった、個人的な属性の類似性でした。これは、ストレスフルな状況下で、人々が身近で安心できる相手を頼ることの表れと考えられます。
ただし、こうした属性は、あくまでCEOへの権力集中という条件が整い、政治が必要とされたときに、派閥形成のための「便利な道筋」を提供するだけです。
この研究は政治が企業の業績に与える結末を追跡しています。政治が活発だった企業は業績が低迷し、中には倒産した会社もありました。対照的に、政治が少なかった企業は優れた業績を上げていました。
政治が業績を悪化させる理由は二つです。一つは、裏工作などが役員たちの時間とエネルギーを消耗させ、本来の業務から注意を逸らすこと。もう一つは、政治が組織内の情報の流れを阻害することです。この研究が描き出したのは、「CEOへの権力集中」が政治的行動を引き起こし、「固定的な派閥」を生み、情報の流れを滞らせて「企業の業績悪化」につながるという連鎖でした。
システム導入への抵抗は、政治的な権力配分の変化から生まれる
組織のトップレベルでCEOへの権力集中が政治を生み出す構図を見てきましたが、この力学は、例えば新しい情報システムを導入するような、もっと現場に近いレベルではどう現れるのでしょうか。業務効率化を目指す新しいツールが、現場の強い抵抗にあい、活用されない。この「抵抗」の正体は何なのでしょうか。
ある研究は、この問題に対し、抵抗の原因に関する考え方を三つのタイプに分類することから分析を始めます[3]。第一は、抵抗の原因を人の内面(変化への嫌悪など)に求める「人間規定論」。第二は、原因をシステムそのもの(使いにくさなど)に求める「システム規定論」。第三は、抵抗は人とシステムの「かみ合わせの悪さ」から生じると考える「相互作用論」です。この研究は、特に相互作用論の中でも、システムの設計が組織内の「権力配分」とぶつかった結果として抵抗が生まれる、という政治的な視点に光を当てます。
この理論を検証するため、ある製造企業における金融情報システムの導入事例が分析されました。この会社では、もともと各事業部の会計担当者が自部門のデータを管理し、その要約だけを本社に報告していました。要するに、情報管理権は各事業部にありました。
ところが、本社主導で新システムが導入され、各事業部のデータベースは本社が一元管理する中央データベースに置き換えられました。これによって、本社は事業部の詳細な生データをいつでも直接閲覧できるようになりました。この設計変更は、会計情報という資源へのアクセス権と管理権が、事業部から本社へと移る、権力の移動を意味していました。
案の定、導入後、事業部の会計担当者たちから強い抵抗が起きました。システムの不満を表明したり、従来の手作業を続けたり、意図的に不正確なデータを入力したりしました。一方で、権力を得た本社の担当者たちはこのシステムを歓迎し、事業部側の抵抗を理解できませんでした。
この事例を先の三理論で検証します。「人間規定論」では説明がつきません。抵抗していた事業部の人間を入れ替えても、抵抗はなくならなかったからです。次に「システム規定論」も当てはまりません。システムの技術的な欠陥を修正し、操作性を改善しても、抵抗は続きました。
最も説得力があったのが、政治的な視点を持つ「相互作用論」でした。この会社には、もともと力の強い事業部と、権限が弱かった本社会計部門との間に政治的な緊張関係がありました。このような背景を考えると、新システムは、本社が事業部から直接情報を吸い上げ、自らの権力を強化するための「武器」として設計されたと解釈できます。
この見方に立てば、権力を失う事業部が抵抗するのは当然の帰結です。そして、この権力闘争の構図が変わらない限り、担当者や技術を入れ替えても抵抗がなくならなかった理由も説明できます。抵抗の原因は、システムが組織内の権力バランスを大きく揺るがしたという事実にあったのです。
組織変革における政治は、変革を推進する多面的な実践でもある
これまで、政治が対立や抵抗といった文脈で現れることを見てきました。政治という言葉には、自己利益の追求や駆け引きといった、否定的な響きが伴います。しかし、組織の政治は「悪」や「障害」でしかないのでしょうか。変革を前に進めようと奮闘する人々にとって、政治はどのような意味を持つのでしょう。
この問いを探るため、組織変革の責任者として現場で活動した人々の語りに耳を傾けた研究があります[4]。変革と政治は切り離せないにもかかわらず、多くの変革論が政治を正面から扱わないため、担当者は実践的な知恵を得にくいという問題意識が出発点です。
研究では、コンサルタントや大学の部局長など、多様な背景を持つ5人の変革担当者にインタビューが行われました。その語りから見えてきたのは、政治が単に「変革を妨害する力」ではないという実像でした。
あるコンサルタントは、地方自治体の改革プロジェクトでの経験を語りました。依頼主である首脳は、調査前から報告書の結論を詳細に指定してきました。コンサルタントは正面から対立せず、首脳の意向を汲んだ骨子を作成しました。その上で、改革案に懐疑的な中心人物と非公式に接触し、その人物の真の懸念を突き止め、代案を盛り込むことで味方に引き入れました。公式な場では中立を装いつつ、水面下で利害を調整し合意を形成していく。これは、変革を推進するための、高度な政治的実践と言えます。
また、ある大学の部局長は、組織全体の評価に関わる決定で、少数の強硬な反対者が議論を停滞させていた経験を語りました。部局長は、事前に賛成票が多数であることを確認した上で、会議当日は反対者の議題を意図的に議論の最後に回し、採決に持ち込みました。参加と熟議という理想からは外れますが、組織全体の利益を守るために必要なことだったと語ります。
これらの事例から浮かび上がるのは、組織変革における政治の二面性です。一つひとつの行動を切り取れば、欺瞞や操作に見えるかもしれません。しかし、変革を前に進めるという組織全体の目的や、妨害する相手がいるという現実、限られた時間といった文脈の中に置くと、それらの行動は、変革担当者が組織目標を達成するために用いた一つの「スキル」や「戦術」として見えてきます。
この研究は、政治を自己利益の追求と定義する従来の見方に疑問を投げかけます。現場の担当者にとって、政治とは、組織目標の達成と私的な動機が複雑に絡み合った、グレーゾーンの広い実践です。きれいごとだけでは、利害が対立する組織で変革は動きません。組織的な目的を達成するために、根回しを行い、時には反対者を無力化する。そうした舞台裏の活動もまた、組織変革の一部です。政治は、避けるべき障害であると同時に、時として変革を前に進めるための駆動力にもなりうる、多面的な現象として存在しています。
脚注
[1] Pfeffer, J., and Salancik, G. R. (1974). Organizational decision making as a political process: The case of a university budget. Administrative Science Quarterly, 19(2), 135-151.
[2] Eisenhardt, K. M., and Bourgeois, L. J., III. (1988). Politics of strategic decision making in high-velocity environments: Toward a midrange theory. Academy of Management Journal, 31(4), 737-770.
[3] Markus, M. L. (1983). Power, politics, and MIS implementation. Communications of the ACM, 26(6), 430-444.
[4] Buchanan, D. A., and Badham, R. (1999). Politics and organizational change: The lived experience. Human Relations, 52(5), 609-629.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。