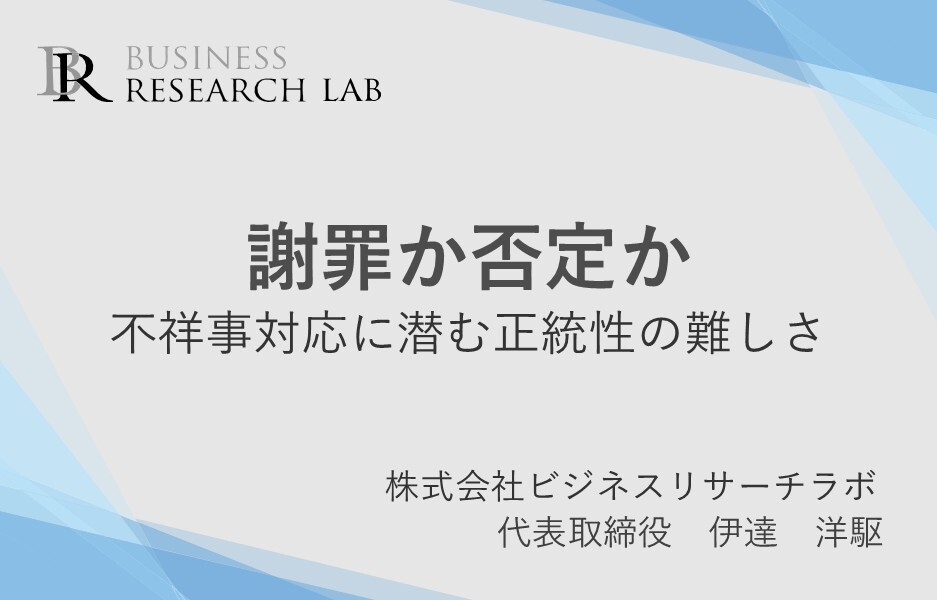2026年1月23日
謝罪か否定か:不祥事対応に潜む正統性の難しさ
組織が不祥事を起こした際、その対応は社会から厳しい視線を浴びます。ある組織の対応は人々の納得を得て事態を収束させる一方、別の組織の対応はかえって非難を増幅させ、事態を泥沼化させることがあります。この差はどこから生まれるのでしょうか。
「正統性」という考え方があります。これは、ある組織の活動や存在が、社会の価値観や規範に照らして「望ましく、適切である」と認識されている度合いを指します。組織はこの無形の資産なしに、顧客や従業員、投資家からの支持を得て存続することは困難です。
不祥事などで正統性が傷つくと、組織は様々なコミュニケーションで回復を試みます。しかし、その試みは時に意図とは裏腹の結果を招きます。良かれと思った言葉が、人々の心を逆なでしてしまいます。
本コラムでは、組織がその正統性をいかに守り、修復しようと試みるのか、その戦略の裏側にある仕組みを、いくつかの研究を手がかりに考えます。組織の語りが人々の心にどう響くのか、その複雑なプロセスを探求していきましょう。
不祥事後、問題を認め制度的慣行を語ると正統性が回復
組織が社会から批判される事態に直面した時、そのスポークスパーソンが発する言葉は、組織の運命を左右します。組織の社会的な受容性、すなわち正統性を守るために、どのような語り口が信頼をつなぎ止めるのでしょうか。この問いに答えるため、カリフォルニアの畜産業界を舞台に行われた一連の調査があります[1]。
この調査は、1980年代末から90年代初頭にかけ、ホルモン剤使用などで批判にさらされた畜産業界が、どのように自らの立場を説明したかを分析したものです。業界団体の担当者への聞き取りやメディアの記事から、266件もの「言語的説明」の事例が集められました。
分析の結果、組織の語りには一定のパターンが見えてきました。その構造は「形式」と「内容」という二つの軸で整理できます。
「形式」には二つのタイプがありました。一つは「否定」です。「我々は関与していない」といったように、問題と組織との関わりを完全に切り離そうとします。もう一つは「承認」です。好ましくない出来事が起きたこと自体は認め、そのうえで「責任の所在は別にある」などと付け加え、組織の責任を限定的にしようとします。
「内容」にも二つのタイプが見出されました。一つは「制度的特徴」への言及です。政府の規制や大学との共同研究、業界基準といった、社会的に広く認められた規範や慣行を引き合いに出します。もう一つは「技術的特徴」への言及です。組織運営の効率性や経済合理性に焦点を当て、「そのような非効率なやり方は経済的利益にならない」などと主張します。
どの組み合わせが信頼回復に有効なのでしょうか。調査の第二段階として、新聞記者や政治家、研究者といった専門家15名への聞き取りが行われました。先に分類した様々な説明を提示し、業界に対する認識の変化を尋ねたのです。
その結果は明快でした。形式については、「承認」が「否定」を上回る評価を得ました。問題を真っ向から否定する態度は、自己中心的で言い逃れをしている印象を与えました。対照的に、問題が起きたことを認める態度は、誠実に向き合おうとしていると受け取られたのです。
内容については、「制度的特徴」への言及が「技術的特徴」への言及を上回りました。政府の基準といった社会的なお墨付きに言及することは、組織の行動が独りよがりではなく、社会規範に則っていることの「証明」として機能し、信頼性を高めました。一方で、効率性を前面に出す説明は、業界の利益を優先する自己中心的な主張と見なされることが多かったのです。
これらの知見を検証するため、68名の企業管理職を対象とした実験が行われました。参加者は架空のニュース記事を読んだ後、4つの典型的な説明のいずれかに基づくプレスリリースを読み、その企業の正統性を評価しました。
実験結果は、聞き取り調査の予測を裏付けました。「承認」の形式は「否定」よりも高く評価され、「制度的特徴」を根拠とする説明は「技術的特徴」による説明より高い評価につながりました。最も評価が高かったのが、「承認」と「制度的特徴」を組み合わせた説明でした。この組み合わせは、企業が消費者の懸念に真摯に対応している印象を生み、最も説得力のある語り口として受け止められました。
この調査は、組織が危機に瀕した際、率直に問題の発生を認め、その対応が社会的に合意されたルールに則っていることを示す語りが、信頼回復の鍵となることを明らかにしました。
良い環境情報の開示は、損なわれた正統性を回復させる
組織の正統性を守る営みは、不祥事後の短期的な弁明に限りません。年次報告書などを通じた継続的な情報発信も、社会との信頼関係を築くための一環です。特に環境問題への関心が高まる現代、企業が発信する環境情報は、その社会的な評価を左右します。良い環境情報を開示することは、ネガティブな情報で損なわれた企業の正統性を回復させる力を持つのでしょうか。
この点を検証した実験研究があります[2]。舞台はアメリカの化学業界です。1970年代、有害廃棄物による健康被害が社会問題となり、業界全体の正統性が大きく揺らぎました。事態を重く見た政府は1980年、「スーパーファンド法」を制定します。これは過去の汚染にも遡及して適用され、企業に浄化責任と莫大な費用負担を義務付ける厳しい法律でした。
これにより多くの化学企業は、巨額の潜在的負債を抱えることになりました。当初、企業側はこの情報開示に後ろ向きでしたが、やがて開示が義務付けられます。義務的に開示されるネガティブな情報は、企業の正統性を脅かします。
ここで興味深い現象が観察されました。多くの企業が、このネガティブ情報の開示と歩調を合わせるように、自主的にポジティブな環境情報(汚染削減努力など)の開示も増やし始めたのです。これは、ネガティブな情報の悪影響を打ち消し、正統性を回復しようとする戦略ではないか、という推測が生まれました。
冒頭の実験研究は、この推測を確かめるために設計されました。76名の現役会計士が参加し、財務状況がほぼ同じ二つの架空の化学会社の情報をもとに、投資資金の配分を推奨するという課題が与えられました。
ただし、二社の環境負債の状況は大きく異なり、片方の会社(ミッドウェスト化学社)は負債が大きく、投資先として魅力的ではありませんでした。実験のポイントは、参加者の半数に、この状況の悪い会社の報告書に、追加のポジティブな環境情報が含まれたものを読んでもらった点です。
実験では投資の目的を「長期的な成長」と「短期的な投機的利益」の二つのシナリオに分けました。この時間軸の違いが、結果に違いを生み出します。
まず「長期的な成長」シナリオです。参加者は環境パフォーマンスの悪いミッドウェスト化学社への投資額を少なくしました。ネガティブな環境情報が長期的な投資リスクとみなされたのです。しかし、ポジティブな情報が含まれていたグループは、そうでなかったグループに比べ、ミッドウェスト化学社への投資額が有意に高くなりました。この結果は、ポジティブな情報開示が、損なわれた企業の正統性を修復する働きを持つことを示唆します。
一方、「短期的な投機的利益」シナリオでは全く異なる様相を呈しました。意外にも参加者は、環境パフォーマンスの悪いミッドウェスト化学社の方へより多くの資金を配分したのです。実験後の聞き取りから、一部の参加者が高い環境負債を「ハイリスク・ハイリターン」の印と解釈した可能性が浮かび上がりました。
この短期シナリオでは、ポジティブな情報を追加しても、投資判断に意味のある変化は見られませんでした。それどころか、環境対策への支出が短期的な利益を圧迫するコストと見なされ、投資額がわずかに減少する様子さえ観察されたのです。この実験は、企業の正統性を高めようとする情報開示が、受け手の時間的な視野によって解釈も価値も大きく変わることを教えてくれます。
正統性防衛策は、一般大衆と投資家とで評価が異なる
組織の正統性防衛策が、受け手の時間軸で異なる評価を受けることを見てきました。受け手の立場や価値観が異なれば、評価はどう変わるのでしょうか。ある組織の行動が、一方のグループからは称賛され、もう一方からは非難される事態は起こりうるのでしょうか。この問いを探求したのが、「ウォールストリート(投資家)」と「メインストリート(一般大衆)」という二つの視点から、企業の対応を分析した研究です[3]。
この研究は、1990年から2002年にかけ、アメリカ企業が「スウェットショップ(劣悪な労働環境の工場)」の使用を告発された126件の事例を対象としました。企業が告発に際し、どのような戦略をとり、それがウォールストリートとメインストリートからどう評価されたのかを分析しました。
まず分析の前提として、二つのグループがそれぞれ異なる「思考世界」を持つと設定されます。メインストリート、すなわち一般の人々は、企業の行動を社会的な影響や「公正さ」の観点から評価すると考えられます。利益だけを追求する行動には懐疑的です。一方、ウォールストリートを代表とする投資家は、企業の将来的な収益性、すなわち「利益」を最優先に考えます。
研究者たちは、企業の防衛戦略を主に四つのタイプに分類しました。「否定」「反抗」「分離」(問題を一部に限定し切り離す)「順応」(告発を認め方針を変更する)です。
これらの戦略は二つの思考世界からどう評価されたのでしょうか。
メインストリートからの評価は、告発後のメディア報道の論調で測定されました。分析の結果、「否定」や「反抗」は企業の正統性を悪化させました。これらの対応は責任逃れで不公平だと映ったのです。興味深いことに、「順応」や「分離」でさえ、失われた評価を積極的に回復させる力はありませんでした。一度告発されると、メインストリートからの信頼回復は非常に困難だったのです。告発後の評価を最も左右したのは、企業がもともと持っていた評判、すなわち「過去の正統性」でした。
次にウォールストリートからの評価を、株価の変動で見てみましょう。結果はメインストリートの反応とは異なりました。「否定」「反抗」「順応」は、株価に特に意味のある変動をもたらしませんでした。投資家はこれらを収益に直接影響しないと判断したようです。しかし、「分離」戦略だけが、株価に有意なプラスの変動をもたらしました。ウォールストリートは、この対応を「問題の範囲は限定的で、経営陣が迅速かつ低コストで事態を管理している」というシグナルとして好意的に解釈したのです。
この分析から浮かび上がるのは、企業の正統性防衛策に万人にとっての正解はないという事実です。あるステークホルダーにとっての最善策が、別のステークホルダーには悪手となりうる。組織は、誰からの、どのような価値観に基づく正統性を問題にしているのかを、慎重に見極める必要があることを、この研究は教えてくれます。
正統性を得ようとする行為自体が、逆効果になりうる
これまで、組織が正統性を守るための戦略が、状況や相手によって異なる結果を生むことを見てきました。しかし、もし正統性を得ようとする行為自体が、かえって組織の正統性を損なうとしたらどうでしょうか。良かれと思った自己弁護が墓穴を掘る結果に終わる。この皮肉な現象を理論的に分析した研究があります[4]。それは、正統化の試みが「両刃の剣」となりうることを論じたものです。
この理論の出発点は「自己宣伝のパラドックス」にあります。組織の正統性が低いと認識されるほど、その組織は躍起になって自らの正当性を主張します。しかし聴衆は、その必死のアピールを「何か裏があるのでは」と割り引いて聞いてしまう。正統性が低いという事実が、回復努力の説得力を削いでしまうのです。
このパラドックスは、組織が危機に陥った時に深刻な悪循環を生むことがあります。正統性が脅かされると、組織は厳しい監視にさらされ、時間や資源の余裕を失います。結果、事業構造の変更といった「実体的」な対応は難しくなり、弁明や謝罪といった手軽な「象徴的」な対応に頼ります。しかし、聴衆はこうした対応をその場しのぎと見抜き、さらに懐疑的になります。この不信が組織をさらに追い詰め、不適切な対応へと駆り立てるのです。
この理論では、こうした悪循環の中で組織が陥りがちな、不適切な自己弁護の姿を三つの類型に分類しています。
第一の類型は、「不器用な俳優」です。危機に狼狽するあまり、社会的に非難される手段に手を出してしまいます。例えば、批判者のプライベートを調査するなどです。こうした行動は強い反発を招き、当初の懸念を裏付ける結果となります。
第二の類型は、「神経質な俳優」です。批判に過剰に防衛的になり、硬直した対応に終始します。「模範的な外形」を繕うことに固執し、紋切り型の応答を繰り返すだけで、核心的な対話を避けようとします。
第三の類型は、「オーバーアクトする俳優」です。自社の美点や正しさを過度に誇張し、感情的な言葉で一方的にアピールします。その過剰な演技は、客観性を求める聴衆からは信頼されず、かえって信用を損ねることになります。
これらの類型が示すように、正統性を回復したいという強い動機が、かえって組織を不器用で、神経質で、過剰な振る舞いへと駆り立て、それが聴衆の不信を増幅させ、さらに正統性を低下させる。この「下方のスパイラル」が、正統化という営みが持つ「両刃の剣」の恐ろしさなのです。
脚注
[1] Elsbach, K. D. (1994). Managing organizational legitimacy in the California cattle industry: The construction and effectiveness of verbal accounts. Administrative Science Quarterly, 39(1), 57-88.
[2] Milne, M. J., and Patten, D. M. (2002). Securing organizational legitimacy: An experimental decision case examining the impact of environmental disclosures. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 15(3), 372-405.
[3] Lamin, A., and Zaheer, S. (2012). Wall Street vs. Main Street: Firm strategies for defending legitimacy and their impact on different stakeholders. Organization Science, 23(1), 47-66.
[4] Ashforth, B. E., and Gibbs, B. W. (1990). The double-edge of organizational legitimation. Organization Science, 1(2), 177-194.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。