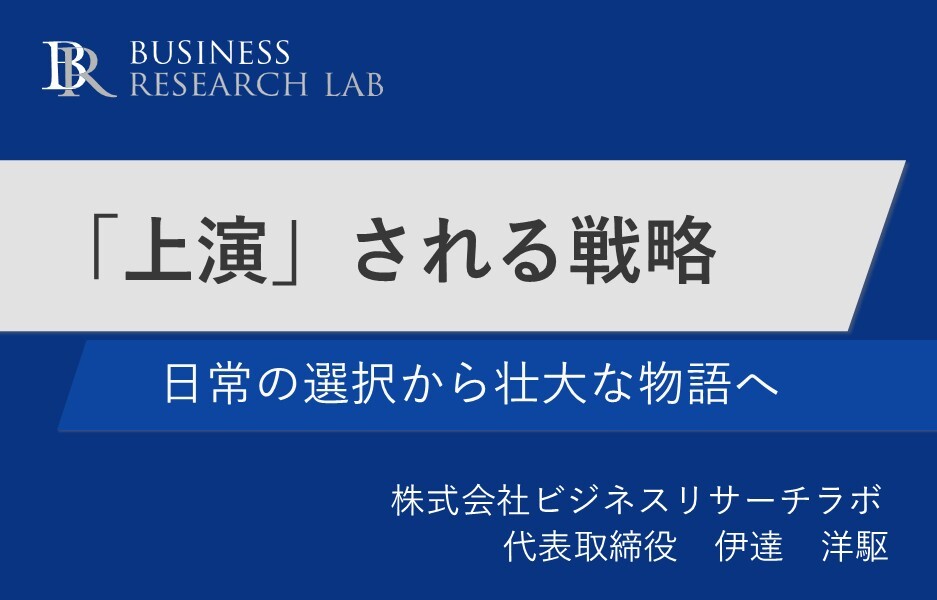2026年1月22日
「上演」される戦略:日常の選択から壮大な物語へ
経営や戦略と聞くと、どのような光景を思い浮かべるでしょうか。もしかすると、整然とした会議室で交わされる冷静な議論やデータ分析といった、無機質で論理的な世界かもしれません。しかし、経営の現場は、ある面では、熱気と緊張感に満ちた「舞台」であり、経営者やマネジャーは台本のないドラマを演じる「俳優」です。
本コラムでは、経営や戦略という営みを「舞台芸術」という視点を通して捉え直す試みを紹介します。経営を科学や技術としてだけではなく、状況を読み、解釈し、自らの身体を通して表現し、観客であるステークホルダーの反応を感じながら次の演技へとつなげていく、人間的なパフォーマンスとして見ていきます。この視点に立つと、見過ごされがちな組織の機微や、戦略が生まれる瞬間のダイナミズム、そこで演じられる人々の希望や葛藤が、生き生きとした物語として浮かび上がってきます。
経営は状況を読み演じ磨く舞台芸術である
経営者が行う仕事と、俳優が舞台で行う演技。この二つは全く異なる世界の出来事のように思えるかもしれません。しかし、両者の営みを深く見つめると、その構造に似通った点があることが分かります。これは、経営を演劇に「たとえる」という話ではありません。経営そのものが、本質的に演技という形式を持っているという考え方です[1]。
19世紀ロンドンの劇場で、俳優エドマンド・キーンは『リチャード三世』の主役を演じ、悪夢から跳ね起きる場面の迫真の演技で観客を熱狂させました。一方、20世紀後半のアメリカ。経営危機に瀕した自動車会社クライスラーの工場で、経営者リー・アイアコッカは、従業員たちを前に会社の未来をかけた交渉に臨んでいました。一方は劇場、もう一方は工場。しかし、どちらの場面も、一人の人間が与えられた状況という「テキスト」を読み解き、自らの解釈と身体を通して表現し、観客の心を動かそうとする「上演」の場であったと言えます。
舞台俳優は、脚本を渡されますが、それは完成品ではありません。セリフの言い方、声の大きさ、間の取り方、舞台上の動きなど、無数の選択肢の中から自らの解釈で選び取り、一つの演技として完成させます。テキストは解釈の余地と枠組みを同時に与えます。上演は、作者、俳優、観客の三者が一体で作り上げるものであり、観客が持つ期待や慣習の中で行われるからこそ、革新が意味を持ちます。
これに対して、経営者は「舞台に上がる前に脚本を渡されない」と言われます。市場の動向、技術の変化、組織の文化といった不完全な情報の中から、自ら状況というテキストを読み解かねばなりません。アイアコッカは、社長室が通路のように雑然と使われている光景から、組織全体の「無秩序」という問題を直感したと言います。
彼はその「読み」をもとに、組織図の再編といった具体的な行動、すなわち「上演」を通して、自らの解釈を検証しました。観客である従業員や市場の反応が芳しくなければ、即座に脚本を書き換え、別の上演を試みることになります。これは行き当たりばったりの行動ではなく、試行、評価、修正という計画的なプロセスです。
公の場でのスピーチでは即興で聴衆の心をつかみながら、労働組合との交渉といった場面では、周到な準備に基づく「見せ場」を演出する。経営者のパフォーマンスは、即興と脚本の間を行き来する中で磨かれていきます。
経営者は組織というテキストを演じると同時に、「自己」というもう一つのテキストを上演しています。俳優が役柄を通して個性を表現するように、経営者も仕事を通して自らの価値観を表現します。アイアコッカが信じていた市場原理主義は、クライスラーの危機という現実を前に見直しを迫られました。
これは、彼が組織の脚本と自己の脚本を同時に書き換える経験だったと言えるでしょう。優れた上演とは、自己の個性と社会からの期待との間の緊張感をうまくコントロールし、全体として一貫性のある物語を立ち上げることです。技術やデータだけが突出したり、自己顕示が過剰になったりすれば、その上演は説得力を失うでしょう。
組織の戦略は日常の小さな選択の積み重ねで形づくられる
一人の経営者による卓越したパフォーマンスが、組織の運命を左右することがあります。そうした個々の「上演」は、組織全体として、どのように一つの大きな流れ、すなわち「戦略」へと結実していくのでしょうか。企業の壮大な戦略と呼ばれるものも、その源流をたどれば、日々の現場で繰り返される無数の小さな選択や行動の積み重ねに行き着きます。
組織における「意思決定」という言葉は、非常に多義的に使われます。ある人は役員会での最終承認のような瞬間を、ある人は数年にわたるプロジェクト全体を指してそう呼びます。この曖昧さを解明するため、ある研究者たちは、大企業における長期的で複雑な意思決定のプロセスを、実際に長期間にわたって追いかける調査を行いました[2]。
調査の舞台は、二つの大手製造会社です。海外市場への進出や新技術の開発など、企業の根幹を揺るがす八つの重要な意思決定プロセスが、3年から20年という長い時間軸で観察されました。経営幹部へのインタビューや公式文書の分析、会議での直接観察など、多角的な方法でデータが集められました。
この調査から浮かび上がってきたのは、意思決定が時間的な長さや関わる人の数によって異なる、六つの階層からなる構造を成しているという事実でした。これは、演劇の構成に似ています。
最も小さな単位は、レベルⅠ「決定選択」です。俳優の一つのセリフや身振りのように、「イエスかノーか」といった、特定の瞬間に行われる個々の判断を指します。
この「決定選択」がいくつか集まったものが、レベルⅡ「決定行動」です。俳優同士の短い「対話」にあたり、数分から数時間続く手紙を書く、会議を開くといった行為が該当します。
レベルⅡの「決定行動」が複数組み合わさると、レベルⅢ「決定イベント」になります。演劇の一つの「シーン(場面)」に相当し、期間は数日から数週間。取締役会や顧客との交渉会議などが典型例です。
次に、レベルⅣ「ミニ決定プロセス」は、複数の「決定イベント」が連なったもので、演劇の一つの「幕(Act)」と言えるでしょう。期間は数ヶ月から一年ほどで、特定の企業を買収するプロセスなどがこれにあたります。
そして、レベルⅤ「決定プロセス」は、複数の「ミニ決定プロセス」が束ねられた、より長期的なものです。演劇の「作品」であり、期間は1年から20年にも及びます。経営幹部が「重要な決定」と語るとき、念頭にあるのはほとんどがこのレベルです。
最も壮大なレベルが、レベルⅥ「決定シアター」です。関連する複数の「決定プロセス」が大きな歴史的潮流となったもので、演劇で言えば壮大な三部作のようなものです。
この階層的なフレームワークは、組織の動きを理解する上でいくつかのことを教えてくれます。一つは、トップリーダーが壮大なビジョン(レベルⅥ)を掲げたとしても、その実現には、組織内の無数の人々による、気の遠くなるような数の小さな選択や行動(レベルⅠ~Ⅲ)の積み重ねが不可欠だということです。
もう一つは、日常の些細な出来事が、時に組織全体の方向性を大きく変える引き金になりうることです。調査では、二人の役員が化粧室で交わした何気ない会話(レベルⅡ)が、結果的に会社全体の競争戦略(レベルⅤ)を数十年方向づける、一連の企業買収(レベルⅣ)のきっかけとなった事例が報告されています。壮大な物語の序章は、しばしば予期せぬ小さなシーンから始まるのです。
戦略変更の成否は上演設計と修復技法に左右される
日々の小さな選択の積み重ねによって、組織の戦略は形づくられます。しかし、時には意識的にその方向性を大きく転換する必要に迫られることがあります。戦略の「変更」という出来事は、組織という舞台で上演される一つの大きな演目です。その上演が成功するか否かは、脚本や配役、演出といった「上演設計」と、予期せぬトラブルに対応する「修復技法」にかかっています。
戦略変更の舞台裏を明らかにするため、ある研究者たちは、英国のスポーツアパレル企業の子会社に入り込み、参与観察を行いました[3]。そこでは、ミドルマネジャー中心の新しい戦略チームが作られましたが、約1年後には解散に追い込まれました。研究者たちは、この一部始終を内側から観察し、戦略の「作り方」を変えようとする試みが、なぜ失敗したのかを記録しました。
分析には演劇論の考え方が用いられ、観客に見せる表舞台「フロントステージ」と、準備を整える舞台裏「バックステージ」という区別が役立ちました。戦略変更のプロセスは、この二つの舞台を絶えず行き来しながら進行します。
第一幕は、新しい戦略チームの導入を設計する場面、いわば「ショーの仕込み」です。バックステージでは、推進者たちが取締役会という「観客」の反応を想像し、脚本を推敲するように資料の言葉遣いを調整しました。信頼性や中立性を演出するための「稽古」が繰り返され、本番前には社長への非公式なブリーフィングも行われました。これは、社長を単なる観客ではなく、バックステージの仲間として巻き込む演出でした。この周到な準備が功を奏し、戦略チームの新設は承認されます。
しかし第二幕で、新チームが意欲的に活動し、従来の領域を超える提案を始めると、経営陣は「ミドルが権限を侵している」と警戒感を抱き始めました。ここで必要になったのが、問題に対応する「ショーの救済」という修復技法です。研究者たちはフロントステージに立ち、チームの行動は越権行為ではないと説明し、その価値を改めて訴え、事態の収拾を図りました。言葉の巧みな操作によって、打ち切りの危機を一度は回避したのです。
ところが第三幕では、バックステージが複雑化します。経営陣の一部は、外部の研究者の関与に不信感を募らせ、別の人物を介してその動向を探ろうとします。これによって、互いに腹を探り合う「二重の舞台裏」が出現し、相手を欺くための「共謀」とも言える駆け引きが行われました。
そして最終幕。新たに就任した営業担当役員が、チームの機能を大幅に縮小する方針を打ち出します。研究者たちは再びフロントステージで修復を試みますが、その場しのぎの言い換えは、かえってチームの正統性を損なう結果となりました。結局、戦略の作り方を変えるという壮大な上演は、観客の支持を得られず幕を閉じました。
この事例から分かるのは、戦略のアレンジメントを変更するプロセスは、権限をめぐる政治的な駆け引きであると同時に、印象を設計し、統御する上演の過程でもあるということです。導入前の周到な「稽古」が不足すると、後から修復するのは困難を極めます。舞台裏での健全な「稽古」と、他者を欺く「共謀」は区別されるべきであり、後者は組織の信頼を破壊する危険を伴っています。
三役は組織の希望と恐れを象徴的に演じ続ける
戦略という舞台には、様々な役者が登場します。その中でも、「リーダー」「マネジャー」「アントレプレナー(起業家)」という三つの役柄は、いつの時代も物語の中心を担ってきました。私たちはしばしば、これらの役柄の優劣を議論しがちですが、視点を変え、これらを組織という劇場で繰り返し上演される「象徴的なパフォーマンス」として捉えると、違う風景が見えてきます[4]。
これらの三役は、単なる職務内容の違いを表すだけではありません。それぞれが、組織に集う人々の集合的な希望や恐れを体現する、元型的な存在です。時代や経済状況という文脈に応じて、どの役柄にスポットライトが当たるかは変わりますが、三役が消えることはありません。
まず、「リーダー」という役柄です。この役は、人々が抱く「自らの運命をコントロールしたい」という希望を象徴します。その姿は、民を率いて約束の地を目指すモーセのイメージに重なります。危機的状況において、リーダーは混乱した出来事に意味を与え、「世界は制御可能だ」という物語を提供することで、人々に安心感をもたらします。
次に、「マネジャー」という役柄がいます。マネジャーは、秩序への願いを象徴します。時に滑稽に見えるほど秩序付けに執心する姿は、古典喜劇の登場人物のようでもあります。人をモノのように管理する危うさを持ちながらも、組織が日常業務を円滑に進める上で不可欠な「秩序の守り手」というパフォーマンスを演じます。
第三の役柄は、「アントレプレナー」です。この役は、「新しい世界を創造したい」という人々の夢を体現します。そのパフォーマンスは、強い意志と構想力によって、まだ誰も見たことのない世界を創り出す、ファウストやコロンブスのような劇的な行為です。成功すれば英雄として称賛されますが、失敗すれば破壊の痕跡だけを残すことにもなりかねません。
これらの三役の主役交代の歴史は、社会全体の大きなリズムと呼応しています。経済が混乱し先行きが見えない時代には力強い「リーダー」が、安定成長期には効率的な「マネジャー」が、大きな変革期には新しい世界を創造する「アントレプレナー」が待望される傾向があります。
この視点は、現代の組織が直面する課題にも示唆をあたえます。例えば、なぜ指導的な立場に就く女性が少ないのかという問いです。これは、組織という舞台で演じられる「リーダー」という役柄自体が、歴史的に男性的な振る舞いを前提として脚本化されてきたことと無関係ではありません。求められているのは、特定の役者を訓練することだけでなく、脚本や舞台装置を見直すことなのです。
脚注
[1] Mangham, I. L. (1990). Managing as a performing art. British Journal of Management, 1(2), 105-115.
[2] Kriger, M. P., and Barnes, L. B. (1992). Organizational decision-making as hierarchical levels of drama. Journal of Management Studies, 29(4), 439-457.
[3] Whittle, A., Gilchrist, A., Mueller, F., and Lenney, P. (2021). The art of stage-craft: A dramaturgical perspective on strategic change. Strategic Organization, 19(4), 636-666.
[4] Czarniawska-Joerges, B., and Wolff, R. (1991). Leaders, managers, entrepreneurs on and off the organizational stage. Organization Studies, 12(4), 529-546.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。