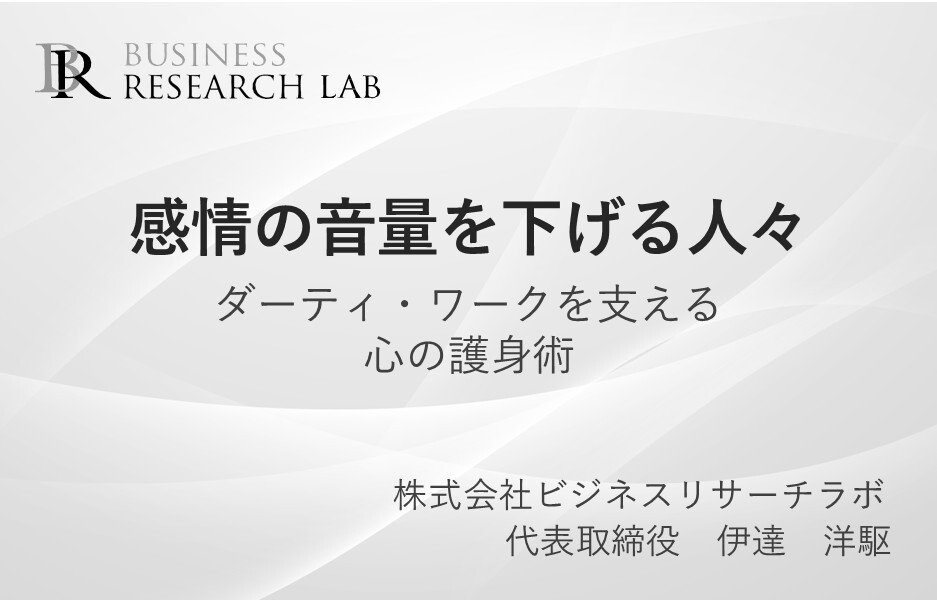2026年1月21日
感情の音量を下げる人々:ダーティ・ワークを支える心の護身術
私たちの社会は、誰かが引き受けなければ成り立たない仕事で満ちています。それは、物理的に汚れたものに触れる仕事かもしれません。あるいは、社会的な偏見の目にさらされる仕事、道徳的に割り切れない感情を抱かせる仕事かもしれません。こうした、人々が避けがちな労働は「ダーティ・ワーク」と呼ばれています。この言葉を聞いて、多くの人は単純に「大変な仕事」という印象を抱くかもしれません。しかし、その奥には、私たちが想像する以上に複雑で、深い人間的な葛藤や、高度な心理的スキルが隠されています。
本コラムでは、ダーティ・ワークの最前線で働く人々が、日々どのような現実に直面し、その中でいかに自身の尊厳を保ち、専門性を発揮しているのかを、学術調査の結果を読み解きながら探求していきます。
物理的な現実が精神的な誇りを揺さぶる現場。生命を扱う行為そのものが、汚れとは質の異なる負担となる職務。社会的な偏見の中で、特定の役割を演じ続けることの葛藤。人の深い苦悩に寄り添うために、自らの感情を巧みに調整する専門性。これらの事例を通して見えてくるのは、ダーティ・ワークが決して「単純労働」ではなく、むしろ高度な感情的知性が求められる営みであるという事実です。
ダーティ・ワークの誇りは物質に打ち砕かれる
社会を機能させるために不可欠な仕事であるにもかかわらず、人々から敬遠される仕事に従事する人々は、どのように自らの仕事に誇りを見出しているのでしょうか。一つの答えとして、仕事の社会的な意義を再認識したり、仲間との連帯感に喜びを見出したりといった、意味づけの工夫が挙げられます。しかし、そうして築き上げた誇りが、仕事の物理的な現実によって容赦なく揺さぶられることがあります。ロンドン広域の自治体で働く、ごみ収集作業員と路上清掃員を対象としたある調査は、この点を克明に描き出しています[1]。
この調査では、研究者が実際に作業チームに加わり、ごみ袋の回収やトラックへの積み込みを体験しながら、働く人々の様子を観察し、聞き取りを行いました。対象となったのは、いずれも男性の作業員21名です。分析の結果、作業員たちが自らの仕事を肯定的に捉えるための様々な工夫をしていることがわかりました。例えば、「自分たちが街を清潔に保っている」という社会貢献意識や、「屋外で体を動かして働くことの心地よさ」「気心の知れた同僚との冗談」といった点に価値を見出すことで、仕事に対する肯定的な自己像を築いていました。
しかし、こうした象徴的な意味づけは、現場の厳しい物質性によって試練にさらされます。夏のうだるような暑さの中での腐敗臭、手袋越しにも伝わるぬめりとした感触、ごみ袋に潜む割れたガラスの危険。長時間労働による身体の疲労は、日中の陽気な会話や仲間意識を蝕んでいきます。調査に参加した研究者は、作業を通して、臭いが衣服や皮膚に染みつき、腰や手首に絶え間ない負担がかかるという身体的な現実を報告しています。こうした感覚は、言葉でどれだけ仕事の意義を語っても、消し去ることのできないものです。
興味深いことに、作業員たちは「汚れ」を、作業の段取りやリズムを乱す「出来事」として捉えていました。
例えば、分別されていないごみがリサイクル施設で混入すること、あるいは、清掃を終えたばかりの場所にすぐに唾やごみが捨てられること。これらは、作業のペースを乱し、「人々の無頓着さ」を突きつけられる瞬間として経験されます。安価で破れやすいごみ袋から、腐った食べ物や汚物が路上に散乱し、それを素手で処理せざるを得ない状況も起こり得ます。ここで経験される「汚れ」は、「作業の適切なペースから逸脱した物事」として立ち現れます。
作業空間そのものが、誇りを脅かすこともあります。裕福な住宅街では、住民からの監視するような視線や、あからさまに無視されるといった経験が日常的にあります。道を譲らずに車で威圧されたり、指を鳴らして命令されたりすることさえあります。こうした対面的な侮辱は、道徳的な軽蔑と物理的な危険を伴い、作業員たちの自尊心を傷つけます。
この調査から浮かび上がるのは、ダーティ・ワークにおける誇りが、意味づけという象徴的な戦略だけで完結するものではないということです。その誇りは、臭い、触感、疲労、危険といった身体的な感覚や、器具、作業動線といった物質的な条件に支えられて成り立つものです。同時に、その同じ物質性によって、いとも簡単に打ち砕かれてしまう脆さも抱えています。言葉で紡いだ肯定的な物語は、身体が感じる不快感や疲労、他者からの侮蔑的な視線によって、その力を失ってしまうのです。
汚れ以上に心身を損なう行為がある
ダーティ・ワークが心身に及ぼす負担は、物理的な汚れや、社会的な偏見から生じるものだけなのでしょうか。仕事の内容に、汚れとは異なる、しかしながら深刻な負担の原因が潜んでいる場合があります。特に、生命を奪うことを日常的に行う仕事は、その典型例と言えるかもしれません。デンマークの屠畜場で働く人々の健康状態を、他の様々な職業と比較した量的調査は、この問いに一つの答えを与えてくれます[2]。
この調査は、デンマークの労働環境に関するコホート研究のデータを用いて行われました。約1万人の労働者を対象に、職業ごとの健康状態やウェルビーイングに関する様々な指標を比較分析したものです。分析の対象となった44の職種の中には、58名の屠畜場労働者が含まれていました。研究者たちは、各職種の「職業的な威信の高さ」と「仕事全体の汚れ度合い」を専門家に評価してもらい、これらの要因を統計的に調整したうえで、屠畜という仕事が労働者の心身に固有の何かをもたらすのかを検証しました。
分析の結果、屠畜場で働く人々は、他の職種の人々と比べて、いくつかの健康指標において不利な状態にあることがわかりました。職業の威信の低さや仕事の汚れ度合いを考慮に入れてもなお、平日および週末のアルコール摂取量が多く、仕事の翌朝に十分に休息がとれたと感じることが少なく、2年後も同じ仕事を続けられる見込みが低いと回答する傾向が確認されました。また、病気や事故によって仕事の能力が低下していると感じており、仕事から得られる意味や目的意識も低いという結果でした。
この結果が、単に仕事が汚れていて威信が低いから生じているのではないことを確かめるため、研究者たちはさらなる比較を行いました。屠畜場労働者と、職業的な威信や汚れの度合いがほぼ同じである「清掃員」や「高齢者施設の介護職員」を比較したのです。すると、清掃員や介護職員には、屠畜場労働者に見られたようなウェルビーイングの低下は見られませんでした。このことは、屠畜場で働く人々の心身の不調が、物理的な汚れや社会的な評価の低さだけでは説明できない、何か別の要因によって引き起こされている可能性を示唆しています。
研究者たちは、その要因を「意図的かつ反復的に動物の命を奪う」という仕事の核にある行為に求めています。ダーティ・ワークに関するこれまでの議論は、物理的、社会的、道徳的な「汚染」という概念を中心に展開されてきました。しかし、この調査の結果は、他者の命を意図的に、そして日常的に絶つという行為が、それ自体として独立した心理的な負担を生み出すことを物語っています。
この調査は、仕事の核にある「暴力的な行為」が、たとえそれが社会的に容認された合法的な業務であっても、遂行する当事者の内面に重い代償を強いる可能性を浮き彫りにします。アルコール摂取量の増加や休息感の欠如、将来への希望の喪失は、その内的なコストが身体的、心理的な綻びとして表出した姿なのかもしれません。仕事における「汚れ」には、目に見える物理的なものだけでなく、行為そのものに内在する、心を損なう性質のものが存在する場合があるのです。
女性らしさを演じても汚名は消えない
ダーティ・ワークが帯びる汚名(スティグマ)は、性別によってその様相を変えることがあります。とりわけ、性的なサービスが関わる仕事に従事する女性は、社会的な偏見や道徳的な非難という、特有の困難に直面します。そうした中で、どのようにしてプロフェッショナルとしての自己を確立し、肯定的なアイデンティティを築いているのでしょうか。英国の大手紳士クラブで働くエキゾチック・ダンサーを対象とした質的調査は、この複雑な過程を「ジェンダーを演じる」という視点から解き明かしています[3]。
この調査では、21人のダンサーに半構造化インタビューが行われました。分析から見えてきたのは、仕事の場で、非常に巧みに、多層的に「女性らしさ」を演じている姿です。クラブという組織は、ダンサーに対して、ドレスコード、メイク、体型、振る舞い、会話の作法に至るまで、理想化され、誇張された「女性性」を体現することを強く求めます。
この期待に応え、顧客が望む「本物らしい女性らしさ」をうまく演じることは、指名やチップといった経済的な報酬に直結します。優しさ、傾聴、気配り、性的魅力といった要素を組み合わせ、顧客との間に「製造された親密さ」を築き上げるスキルは、この仕事における専門性です。「女性らしさをうまく演じること」が、「優れた労働者であること」の証明となるのです。
しかし、問題はそれほど単純ではありません。どれほど完璧に「良き女性」を演じ、経済的な成功を収めたとしても、性的なサービスを提供するという仕事の性質上、社会的な汚名はついて回ります。売春と同一視されたり、蔑視の対象となったりする現実は、自己評価を脅かします。
ここには、「良い仕事ぶり」が、必ずしも「良い女性」という社会的な評価に結びつかないという、根深い非対称性が存在します。誇張された女性性を演じるという行為は、経済的な成功をもたらす一方で、性的な役割を固定化し、社会的な偏見を再生産してしまうという矛盾をはらんでいます。
実践は、単一の「女性らしさ」の脚本に留まりません。インタビューからは、誇張された女性性を演じると同時に、収益を最大化するための能動性、競争心、自己規律といった、一般的に「男性性」と結びつけられるコードを駆使している様子も浮かび上がってきました。同僚との売り上げ競争を意識したり、顧客を戦略的に管理したり、非生産的な接客を冷静に見切ったりする姿は、受動的な女性像とは異なります。状況に応じて複数のジェンダーの脚本を使い分け、重ね合わせることで、この厳しい世界を生き抜いています。
この調査が明らかにしたのは、ダーティ・ワークにおけるスティグマ管理が、ジェンダーという視点を通して見ると、より一層複雑な様相を呈するということです。エキゾチック・ダンサーたちは、社会が期待する「女性らしさ」を巧みに演じて経済的自立を達成するという解放的な側面と、その演技によって性的な役割に縛り付けられ、社会的な汚名から逃れられないという拘束的な側面との間で揺れ動いています。
解放と搾取、誇りと嫌悪が同居するこの仕事において、肯定的な自己を保つためには、複数のジェンダー・パフォーマンスを戦略的に使い分けるという、非常に高度なアイデンティティ・ワークが求められるのです。
ダーティ・ワークでは感情の音量を下げる
ダーティ・ワークの中には、物理的な汚れや社会的な汚名だけでなく、他者の強烈な感情に触れ続けることで生じる「情動の汚れ」とでも言うべき負担を伴うものがあります。悲惨な出来事の詳細に繰り返し向き合い、被害者や加害者の生々しい感情を受け止め、時にはそれを法廷という公の場で戦略的に利用しなくてはならない、レイプ事件を専門に扱う法廷弁護士(バリスター)の仕事は、その典型と言えるでしょう。
イングランドのバリスターを対象としたある研究は、彼ら彼女らがこの「情動の汚れ」といかに向き合い、プロフェッショナルとしての精神的な平衡を保っているのかを探っています[4]。
この研究では、レイプ事件の検察側、弁護側双方の経験を持つ39名のバリスターへのインタビューが行われました。彼ら彼女らの語りから浮かび上がってきたのは、自らの仕事が物理的・社会的・道徳的な汚れだけでなく、不快で負担の大きい感情を扱うこと自体によって「汚れている」という認識です。
証拠資料に含まれる生々しい情報、加害者という社会的に汚名を着せられた人物との密な関わり、被害者の信頼性を法廷で問わなければならないという道徳的葛藤。これらが重なり合う中で、特に被害者と被告人の恐怖、羞恥、怒り、絶望といった強い感情に日々接することが、彼ら彼女らの心に重くのしかかります。
このような過酷な環境で職務を遂行するために、バリスターたちは高度な感情管理のスキルを発揮しています。それは、感情を押し殺して無関心になることではありません。かといって、依頼人の感情に完全に同化してしまえば、客観的な判断力や法的な戦略構築が妨げられてしまいます。研究者たちは、彼ら彼女らの実践を「節度ある無関心(tempered indifference)」という言葉で表現しました。これは、感情をゼロにするのではなく、いわば「感情の音量を下げる」ような、繊細な調整作業です。
具体的には、依頼人の感情に共感し、理解を示しつつも、それに完全に飲み込まれないように意識的な距離を保ちます。そして、裁判官や陪審員の心を動かすために「情熱」を込めて弁論を行う際には、その音量を少し上げる。このように、状況に応じて感情のレベルをチューニングすることで、専門家としての客観性と、人間としての共感性という、一見矛盾する要求を両立させています。感情を完全に切り離すのでも、一体化するのでもなく、その中間でバランスを取り続けるという洗練されたスキルです。
もちろん、この「節度ある無関心」だけで、すべての情動的な負担が解消されるわけではありません。弁護士たちは、同業者間で交わすブラックジョークや、仕事の倫理的な意義を再確認すること(例えば、「誰もが弁護を受ける権利を守っている」という再定義)などを通じて、日々のストレスを和らげようとします。しかし、レイプ事件という仕事の核にある重い感情と向き合い続けるためには、この微細な感情の調整技術が不可欠であると、この研究は示しています。
感情の音量を下げ続けることは、長期的には感情そのものが鈍化してしまう危険も伴います。それでも、彼らはこの高度なスキルを駆使して、社会の最も困難な領域の一つを支えているのです。
脚注
[1] Hughes, J., Simpson, R., Slutskaya, N., Simpson, A., and Hughes, K. (2017). Beyond the symbolic: A relational approach to dirty work through a study of refuse collectors and street cleaners. Work, Employment and Society, 31(1), 106-122.
[2] Baran, B. E., Rogelberg, S. G., and Clausen, T. (2016). Routinized killing of animals: Going beyond dirty work and prestige to understand the well-being of slaughterhouse workers. Organization, 23(3), 351-369.
[3] Mavin, S., and Grandy, G. (2013). Doing gender well and differently in dirty work: The case of exotic dancing. Gender, Work & Organization, 20(3), 232-251.
[4] Gunby, C., and Carline, A. (2020). The emotional particulars of working on rape cases: Doing dirty work, managing emotional dirt and conceptualizing “tempered indifference.” The British Journal of Criminology, 60(2), 342-362.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。