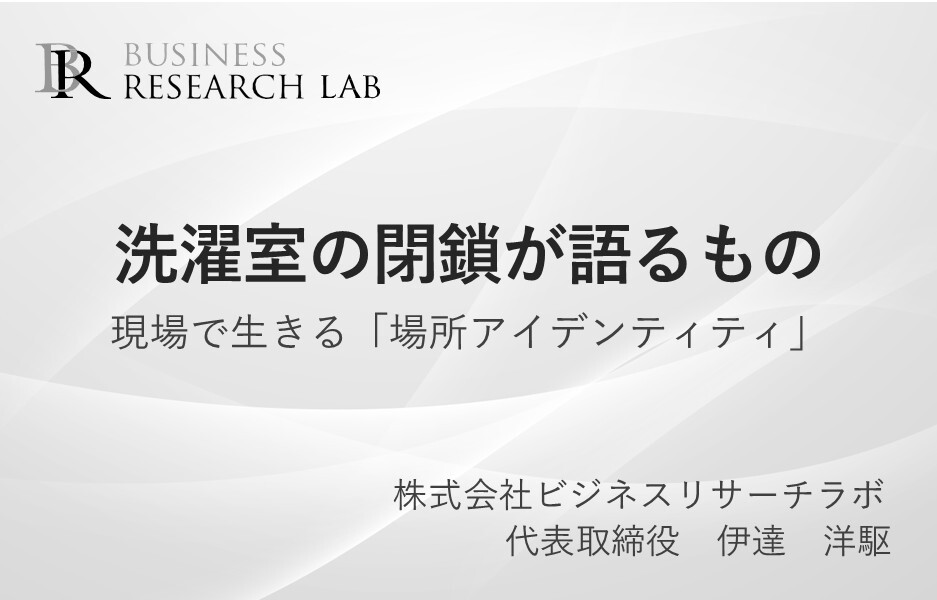2026年1月20日
洗濯室の閉鎖が語るもの:現場で生きる「場所アイデンティティ」
自分が働くオフィスや工場、あるいは通い慣れた店舗。私たちは日々、特定の「場所」で多くの時間を過ごしています。その場所は、単に業務をこなすための物理的な空間でしょうか。おそらく、多くの人にとって答えは「いいえ」でしょう。
窓から見えるいつもの景色、長年使っているデスクの傷、同僚たちと交わした何気ない会話が聞こえてきそうな休憩室。そうした一つひとつが積み重なり、その場所はいつしか、私たちにとって特別な意味を持つ「居場所」になっていきます。それは、自分という人間の一部を形作る、かけがえのない構成要素にさえなり得るのです。
この感覚は、職場に限った話ではありません。学生時代の教室、部活動で汗を流したグラウンド、家族と暮らした家。特定の場所と結びついた記憶や感情は、私たちの自己認識、すなわちアイデンティティと結びついています。では、組織という文脈において、従業員が抱くこのような「場所への思い」は、一体どのような働きをするのでしょうか。組織が大きな変革に見舞われたとき、その思いは人々の心をどう揺さぶるのでしょう。その思いは、個人の仕事の成果や、ひいては企業全体の業績にまで結びつくものなのでしょうか。
本コラムでは、こうした素朴な問いを、いくつかの研究を手がかりに検討していきます。人々が場所に抱くアイデンティティが、組織やコミュニティの中でどのように生まれ、どのような作用をもたらすのか。その複雑で豊かなメカニズムを、具体的な調査や実験の結果を通して紐解いていきたいと思います。
現場の職員ほど働く場所へのアイデンティティが揺らぐ
企業の成長過程において、組織の変革は避けて通れないものです。オフィスの移転や工場の建て替え、あるいは働き方の見直し。こうした変化は未来への希望と共に語られがちですが、その渦中にいる人々は、変革をどのように受け止めているのでしょうか。特に、長年慣れ親しんだ「働く場所」が姿を変えるとき、従業員の心にはどのような波紋が広がるのでしょう。
この問いに光を当てる研究があります[1]。舞台は140年の歴史を持つ公立の精神科病院。この病院は、建物の大規模な建て替え、名称の変更、新しいケアモデルへの移行、全職員の再配置という大がかりな変革の最中にありました。職員には親子数代にわたってここで働く家族も多く、地域に根ざした、場所との結びつきが強い組織でした。
研究者たちは、この変革への認識を明らかにするため、上級管理職から現場の職員、さらには外部の政策立案者まで、合計34人にインタビュー調査を行いました。集められた膨大な語りのデータを解析し、言葉の使われ方や概念のつながりを分析しました。
そこから浮かび上がってきたのは、明快な事実でした。組織内での立場によって、変革に対する視点や場所への感覚が異なっていたのです。
例えば、政府の政策立案者といった外部関係者は、最も抽象的な視点を持っていました。国際的な政策という大きな文脈で病院を捉え、変革を地域のための前向きな機会と見なしていました。特定の物理的な建物への愛着といったものは、その語りからはほとんど見られませんでした。変革を計画する上級管理職も同様に、国内外の先進事例から学んだ理論に基づいて変革を推進しようとしており、過去からの脱却を肯定的に捉え、未来志向の姿勢が際立っていました。
一方で、組織の階層が下がるにつれて、場所へのまなざしは具体的で、感情を伴うものへと変化していきます。現場レベルで変革を実行する中間管理職は、物理的な「場所」よりも、そこで働く「人々」との関係性や仕事の進め方の変化に強い関心を寄せていました。長年培ってきた専門職としての誇りや、同僚との信頼関係が失われることへの懸念を口にしていました。
現場のチームを率いる監督者や、患者と直接向き合う非監督の職員たちの語りは、場所への非常に強く、具体的なアイデンティティに満ちていました。過去への郷愁や、家族ぐるみでの長年の勤務といった、この土地に刻まれた歴史への言及が数多く見られました。この人々にとって変革とは、抽象的な理念ではなく、日々の業務に直結する物理的な変化として認識されていたのです。
象徴的だったのは、多くの職員が「洗濯室の閉鎖」を変革が後戻りできない出来事として語っていたことです。日々の業務で当たり前に存在していた場所の喪失が、慣れ親しんだ世界の終わりを告げる印として心に刻まれていました。
この研究結果は、同じ変革を経験しながらも、立場によって異なる現実を生きている人々の姿を浮き彫りにします。考察によれば、その認識の断絶の根底には、「場所アイデンティティ」の性質の違いがあります。現
場に近い職員にとって、病院という場所は、長年の経験を通じて自己の感覚を育んできたアイデンティティの拠り所でした。その知識は具体的な経験に根ざしており、過去との連続性が断ち切られることに強い不安を感じていたのです。対照的に、上位階層の管理職や外部関係者にとって、場所はより抽象的なものでした。理論や他の場所での経験から導き出された知識を用いて変革を評価していました。
この経験に基づく「具体的な知識」と、理論に基づく「抽象的な知識」との間に生じた認識の溝が、変革の過程におけるすれ違いの一因となっていたのかもしれません。
場所と人のアイデンティティは、互いに意味を与え合う
組織が大きく変わるとき、現場で働く人々ほど、その「場所」に根ざしたアイデンティティが揺さぶられる様子を見てきました。それは、場所が私たちにとって、自己の一部となっていることの裏返しでもあります。それでは、人と場所はどのようにして一体化していくのでしょうか。この問いを探求した研究は、両者の関係が、一方向的なものではなく、互いに与え合い、共に形作られていくダイナミックなものであることを教えてくれます[2]。
この関係性を理解する上で、「空間(space)」と「場所(place)」という言葉を区別すると分かりやすいかもしれません。空間が客観的で幾何学的な広がりを指すのに対し、場所とは、人々がそこに関わることで、様々な記憶や感情、象徴的な意味が吹き込まれた、いわば「物語をまとった空間」のことです。
この「場所とアイデンティティ」の共生的な関係を鮮やかに描き出したのが、アイルランド共和国のボランティア救命艇隊員を対象とした事例研究です。この救命艇隊は、慈善団体「王立救命艇協会(RNLI)」の一部であり、その活動は数多くのボランティア隊員によって支えられています。隊員たちは、しばしば荒れ狂う嵐のような過酷な状況下で、危険を顧みずに救助活動に従事します。
研究者たちは、複数の救命艇拠点に足を運び、隊員たちへのインタビューや参与観察を行いました。調査を通じて明らかになったのは、隊員たちが自らのアイデンティティを語るとき、繰り返し「場所」という言葉に言及し、それが海の知識、家族、コミュニティ、伝統といった他の要素と結びついていることでした。
一つ目は、「海辺の場所」としての側面です。隊員のアイデンティティは、何よりもまず、活動の舞台である危険と隣り合わせの「海」によって形作られています。その土地固有の海の知識は、専門家としてのアイデンティティの「錨」のようなものです。熟練の船乗りであることは、特定の場所の海を隅々まで知り尽くしていることと、ほぼ同じ意味で語られます。
二つ目は、「私が育った場所」としての側面です。隊員のアイデンティティ形成においては、文字通りの「家族」が大きな存在感を放っています。
調査対象となったすべての拠点で、同じ家族の複数のメンバーが活動に関わっており、「父も祖父も救命艇隊員だった」と語る隊員は珍しくありませんでした。特定の場所で生まれ育つことで、物心ついたときから、家族が救命艇で海に出ていく姿を当たり前の光景として見て育つ。そうした経験が、自然な形でアイデンティティの素地を形成していくのです。これは、「場所が家族を作り、家族が場所を作る」という、世代を超えた循環的な関係性を示しています。
三つ目は、「私が来た場所」としての側面です。場所へのアイデンティティは、現在と過去をつなぐ「歴史と伝統」にも深く根ざしています。多くの救命艇拠点は、現在の大きな組織に統合されるずっと以前から、地域の人々による独立した救助隊として存在していました。その歴史的背景から、隊員たちは中央組織よりも、自分たちが所属する地域の拠点に対して、より強い一体感を抱いています。
これらの分析から見えてくるのは、場所とアイデンティティが、一方が他方を形成するという単純な関係ではないということです。両者は、互いに意味を与え合い、時間をかけて共に構築されていく、再帰的でダイナミックな関係にあります。隊員のアイデンティティは、危険な海という「場所」によって形成されます。しかし同時に、その「場所」の意味は、そこに住む人々のアイデンティティ、すなわち家族の物語やコミュニティの歴史、受け継がれてきた伝統によって、豊かに彩られているのです。
場所への思いの組み合わせが、企業の業績を高める
人と場所のアイデンティティが深く結びつき、相互に作用しあうものであることを見てきました。職場という「場所」に対する従業員の思いは、企業のパフォーマンスという具体的な成果に、どのようにして変換されるのでしょうか。この問いに、新たな角度から光を当てた研究があります[3]。舞台はファミリービジネス、焦点は創業者一族ではない「非同族」の従業員たちです。
この研究は、非同族従業員が企業にもたらす貢献のメカニズムを、「場所アイデンティティ理論」という視点を通して解き明かそうとしました。ここでの「場所」とは、物理的な建物だけでなく、人間関係や組織文化を含んだ社会的な環境としての「職場」を指します。人は、自らのアイデンティティが認められ、確かめられるような関係性を築こうとすると考えます。このプロセスが満たされることで、生産的な行動が引き出されるというわけです。
研究者たちは、このアイデンティティが確かめられる感覚を、三つの要素のセットとして捉えました。第一に「企業への同一化」(所属している感覚)。第二に「意思決定への参加」(価値を認められている感覚)。第三に「忠誠心」(一体である感覚)です。
これらの要素が、企業の業績にどう結びつくのかを検証するため、スペインのファミリービジネス159社で働く非同族の上級管理職を対象に、アンケート調査が実施されました。分析では、各要素が「独立して」どう作用するかを見る伝統的な手法と、要素が「どのように組み合わさる」ことで高い業績につながるかを探る、より新しいアプローチが併用されました。
分析の結果、二つの手法は、それぞれ異なる側面を明らかにしました。伝統的な分析では、企業の短期的な財務パフォーマンスに対しては「企業への同一化」だけが、革新的なパフォーマンスに対しては「意思決定への参加」だけが、それぞれ直接的なプラスの関連を持っていました。「忠誠心」は、単独では関連が見られませんでした。
ところが、「組み合わせ」を見る分析を行うと、現実はより複雑で、豊かな様相を呈してきました。高いパフォーマンスは、単一の要素によってもたらされるのではなく、複数の要素が特定の文脈で組み合わさることによって生まれていたのです。
例えば、高い革新性を達成するためには、いくつかの異なる成功パターンが見つかりました。そのパターンは、企業の歴史(設立からの年数)によって異なっていました。比較的若い企業では、三つの要素のいずれか一つが存在するだけでも高い革新性を達成できる道筋がありましたが、歴史の長い古い企業では、三つの要素すべてがそろうような、より強力な動機づけが必要でした。
高い財務パフォーマンスについても、同様に複数の組み合わせが見いだされました。典型的な成功パターンは、「企業への同一化」が核となり、「忠誠心」がそれを補完する形でした。従業員の帰属意識と心理的な愛着が、安定した財務基盤を支えるようです。また、伝統的な分析では関連が見られなかった「忠誠心」も、特定の条件下では、単独で高いパフォーマンスを導く核となり得ることが明らかになりました。
この研究が教えてくれるのは、従業員の場所への思いが企業の成果につながる道筋は、一本道ではないということです。ある要素が、ある状況では主役になり、別の状況では脇役になる。あるいは、他の要素と手を取り合うことで、その真価を発揮する。オーケストラで様々な楽器が組み合わさって一つのハーモニーを奏でるかのようです。
場所への同一化は、自信と地域貢献を経て成果へとつながる
「この土地が好きだ」「この職場は自分の居場所だ」という気持ちは、どのような心の動きを経て、その人自身の仕事の成果へとつながっていくのでしょうか。そのステップ・バイ・ステップの道のりを解き明かした研究があります[4]。
調査の対象となったのは、オーストラリアの地域社会で事業を営む、中小規模の観光事業者たちです。観光業は、その土地の魅力を商品とするビジネスであり、事業者と「場所」との関わりがとりわけ密接な領域といえるでしょう。研究者たちは、こうした事業者が抱く「その土地への同一化」が、個人のパフォーマンスにどう結びつくのか、その心理的な架け橋を探ろうとしました。
この研究のユニークな点は、土地への同一化が、直接的に成果につながるわけではないと考えたところにあります。そうではなく、二つの重要なステップを経由するという、因果の連鎖モデルを想定したのです。一つ目のステップは、個人の内面で起こる変化、すなわち「起業家としての自信」です。二つ目のステップは、個人の外面に現れる変化、つまり「地域社会への貢献行動」です。土地への愛着が、自信と貢献行動を生み出し、その二つがエンジンとなって、パフォーマンスを高める、という仮説です。
この仮説を検証するため、301の事業者を対象にアンケート調査が行われました。分析の結果、研究者たちの想定した因果の連鎖モデルは、データによって支持されました。土地への同一化からパフォーマンスへと至る道のりは、仮説通りの二つのルートをたどっていたのです。
土地への同一化の意識が高い事業者ほど、「起業家としての自信」が高いことが確認されました。「自分はこの場所の一員だ」という強い感覚が、「自分ならこの場所で事業をうまくやっていける」という内面的な確信の源泉となっていたのです。
土地への同一化は、「地域社会への貢献行動」を促していることも明らかになりました。「この土地が好きだ」という気持ちが、地域のイベントを手伝ったり、環境保全プロジェクトに参加したりといった、具体的な行動へと人々を駆り立てていました。
最も大切な発見は、この「自信」と「地域貢献」の両方が、事業者のパフォーマンスを高めていたという点です。高い自信を持つ事業者は、困難な課題にも粘り強く挑戦し、より良い成果を上げていました。また、地域に貢献する事業者は、地域社会からの信頼や好意的な評判を得て、それが間接的に自らの事業にも良い形で返ってきていたのかもしれません。
興味深いことに、土地への同一化からパフォーマンスへの直接のつながりは、統計的には見られませんでした。あくまで、「自信」と「地域貢献」という二つを媒介して、その力が発揮されていたのです。
この研究は、場所への思いが成果へと結実するまでの、心と行動の連鎖を描き出しています。「場所へのアイデンティティ」は、個人の内なるエネルギー、すなわち「自信」を醸成します。同時にそれは、外に向かうエネルギー、すなわち「貢献」という行動を生み出します。そして、この内と外、両方向のエネルギーが組み合わさることによって、初めて目に見える「成果」という果実がもたらされます。
脚注
[1] Rooney, D., Paulsen, N., Callan, V. J., Brabant, M., Gallois, C., and Jones, E. (2010). A new role for place identity in managing organizational change. Management Communication Quarterly, 24(1), 44-73.
[2] Grey, C., and O’Toole, M. (2018). The placing of identity and the identification of place: “Place identity” in community lifeboating. Journal of Management Inquiry, 29(2), 206-219.
[3] Llach, J., Sanchez-Famoso, V., and Danes, S. M. (2023). Unmasking nonfamily employees’ complex contribution to family business performance: A place identity theory approach. Journal of Family Business Strategy, 14, 100593.
[4] Hallak, R., Brown, G., and Lindsay, N. J. (2012). The place identity-performance relationship among tourism entrepreneurs: A structural equation modelling analysis. Tourism Management, 33(1), 143-154.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。