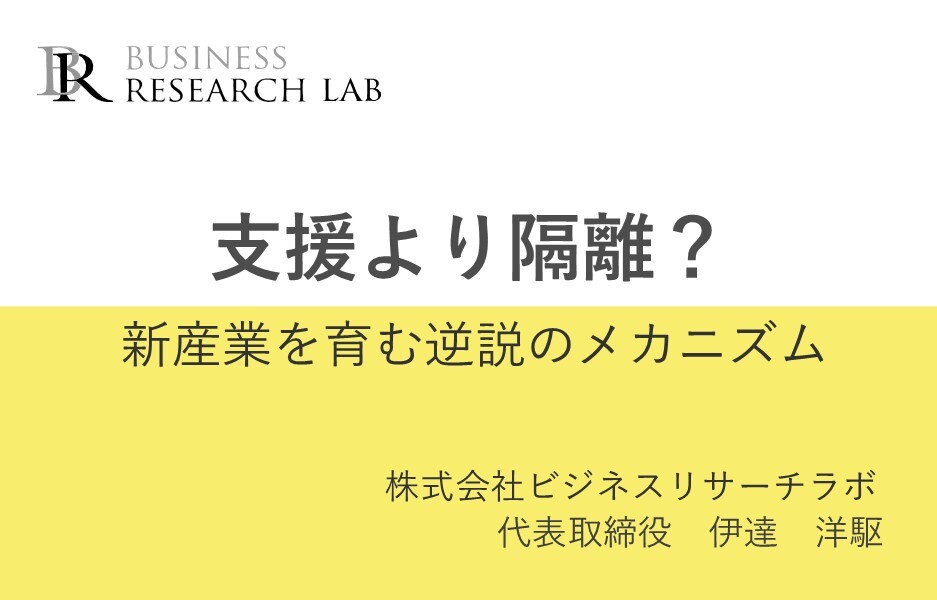2026年1月20日
支援より隔離?:新産業を育む逆説のメカニズム
私たちの働く組織や新しいビジネスは、社会から切り離された存在ではありません。国という大きな枠組みや時代の文化的な潮流と、複雑に関わり合いながら形作られています。普段、私たちは仕事や会社の動きに目を向けますが、その背後にはもっと大きな力が働いているのかもしれません。例えば、ある国が特定の産業を育てるために、起業家のように大胆な制度設計を行うことがあります。あるいは、社会全体の価値観が変化することで、昨日までは想像もできなかったような新しい市場が、自然発生的に生まれることもあります。
本コラムでは、組織や産業が、国家や社会というマクロな環境とどのように相互に作用しあっているのか、そのダイナミックなプロセスをいくつかの異なる角度から光を当てていきます。国家が巧みに制度を使い分ける姿、ゼロから社会システムを構築する過程、時には国家との距離が組織の力を育むという逆説。さらには、個人の意図を超えた文化の大きなうねりが、新たな分野を創出する物語。これらの探求を通じ、私たちの経済活動や組織のあり方を、より広い視野から見つめ直すきっかけを提供できればと思います。
国家は「自由区」で国際と国内の制度を分離する
国家とは、法律で国民生活を律したり、ビジネスに規制を課したりするだけの存在でしょうか。中東ドバイの歩みを追った研究は、国家が自ら「起業家」のように振る舞い、国際的なビジネスチャンスを創出するために制度を設計する、能動的な姿を浮かび上がらせます[1]。この分析は、ドバイの歴史的な出来事の連なりを詳細に再構築する手法を用いています。過去の文献や記録をたどり、重要な転換点となった出来事を時系列に並べることで、制度環境がどのように進化し、その中でどのような意思決定がなされたのかを解き明かそうと試みるものです。
この物語の核心にあるのが、「自由区」という仕組みです。ドバイは、海外の企業や資本を惹きつけるために、特別なルールが適用されるエリアを国内に設けました。そこでは、100%の外資所有、長期の税・関税免除、利益の全額本国送金など、国際ビジネスの基準に合わせた魅力的な条件が整えられています。これは、国内の法制度、例えばイスラーム法に基づく統治とは意図的に「切り離された」空間でした。
この「切り離し」が、ドバイの戦略の要でした。一方では、自由区という国際標準のビジネス空間を用意することで、海外の投資家や企業からの信頼、すなわち「国際的な正統性」を獲得します。そこでは自国に近い法的予測可能性や保護が受けられ、安心して活動できるからです。他方で、自由区の外側では、従来からの国内の規範や法体系を維持することで、国民からの支持、すなわち「国内的な正統性」を保ち続けます。こうして、内と外、二つの異なる方向からの期待に同時に応えるという、二重の正統性マネジメントを可能にしたのです。
この仕組みは、一朝一夕にできあがったわけではありません。その起源は20世紀初頭、地域の港の増税を機に、ドバイの統治者が自港を「自由港」として税を撤廃し、商人を呼び込んだことにさかのぼります。その後、石油資源に恵まれなかったドバイは、港の浚渫や大規模な港湾施設の建設へと投資を続けます。1980年代には世界最大級の人工港と自由区ジェベル・アリを完成させ、制度的な囲い込みを本格化させました。
その集大成ともいえるのが、2004年に設立されたドバイ国際金融センター(DIFC)です。ここは単なる税制優遇区ではなく、英米法に準拠した独自の司法制度と裁判所を持つ、いわば「法域の中の法域」です。これによって、国際金融の世界で標準とされる法的枠組みを、国内の法体系との摩擦を避けながら導入することに成功しました。連邦国家成立後もドバイが独自の司法権を維持した過去の決定が、この大胆な制度設計の土台となりました。過去の選択が未来の可能性を形作る、歴史の連続性がここに見て取れます。
ドバイの事例から見えてくるのは、国家が受動的な環境ではなく、国際的な起業活動を誘致するための制度の設計者、いわば「制度の建築家」となりうるという姿です。自由区という装置を用いて、国内制度との緩衝地帯を設けながら、国際社会のルールを取り込む。この二層構造の制度設計は、グローバル化の時代において、国家がどのように内外の期待に応え、経済発展の道を切り拓くことができるのか、一つのモデルを示しているのかもしれません。
国家はまず規制を作り、後から規範や文化を築く
社会に全く新しいシステムを導入するプロセスは、どのように進むのでしょうか。例えば、環境保護という考え方がまだ根付いていない国で、それを社会全体の仕組みとして確立するには、何から手をつければよいのでしょう。1972年から2001年にかけての中華人民共和国における環境保護システム構築の道のりを追った分析は、国家が主導する場合の制度構築の典型的な順序を明らかにしています[2]。この研究は、公式出版物などから環境関連の1700件以上の活動を特定し、それらが制度の三つの柱「規制」「規範」「認知文化」のいずれを形成したかを分類する、地道な歴史分析に基づいています。
ここでいう三つの柱とは、社会の仕組みを支える基本的な要素です。第一の「規制の柱」は、法律や政府の政策といった公式ルールです。強制力を伴い、罰則が科されることもあります。第二の「規範の柱」は、専門家の基準や業界慣行など、道徳的義務感に根差します。第三の「認知文化の柱」は、社会で共有される価値観や「当たり前」の考え方を指します。
中国における環境保護システムの形成過程は、大きく四つの段階に分けられます。第一段階は「啓蒙期(1972-1982年)」です。深刻な公害事件や国際会議への参加を機に、政府は環境問題を国家課題として認識し始めます。この時期は、まず問題の存在に気づき、対応の必要性を学ぶ段階でした。
第二段階は「規制承認期(1983-1988年)」で、ここから本格的な制度構築が始まります。この時期、国家は環境保護を憲法や法律に位置づけ、法的枠組みを整備しました。最初に打ち立てられたのは、「規制の柱」でした。トップダウンで「環境を守ることは国のルールである」と宣言し、その正統性を法によって確立しようとしました。
第三段階は「専門化期(1989-1997年)」です。法的な枠組みができた後、次に取り組んだのは、それを実効性のあるものにするための「規範の柱」の構築でした。環境保護を専門とする国家環境保護局(SEPA)の権限が強化され、全国的な監視網が作られました。企業への環境監査員配置など、専門的な基準や手順が整備され、専門家が育成されました。
第四段階は「社会的責任期(1998年以降)」です。規制が整備され、専門的な運用体制も整った上で焦点が当てられたのが「認知文化の柱」でした。環境問題は、もはや一部の汚染産業や行政機関だけの問題ではなく、社会全体で取り組むべき責任であるという認識を広めるための活動が活発になります。公衆の意識を高めるキャンペーンが行われ、市民団体やメディアも巻き込みながら、環境保護を社会の共通の価値観として根付かせようとする試みが進められました。
この「規制→規範→認知文化」という構築の順序は、例えばアメリカの環境保護の歩みとは対照的です。アメリカでは、市民運動などの規範的・認知的な圧力が先にあり、それが政府を動かして規制につながることが少なくありません。しかし、中国の事例が物語るのは、国家が強力な制度起業家として振る舞う場合、トップダウンでルールを作り、次に行政や専門家の体制を整え、最後に社会全体の意識変革へと働きかけるという道筋をたどる一つの傾向です。
国家からの優遇より、むしろ隔離が力を育む
新産業が生まれようとするとき、担い手たちが団結し、政策に働きかける業界団体を設立することがあります。どのような条件が整えば、そうした団結は成功しやすいのでしょうか。直感的には、政府が協力的で、資金援助などの優遇策を講じてくれる方が、組織化はスムーズに進むように思えます。しかし、ブラジルとメキシコのマイクロファイナンス分野の発展比較は、逆説的な結論を導き出します。国家との近すぎる距離は業界の団結を妨げ、むしろ国家から距離を置かれる「隔離」状態が組織の力を育むことがあるというのです[3]。
この分析は、「共進化」という視点を取り入れています。これは、国家と社会(この場合はマイクロファイナンス業界)が、互いに固定された存在ではなく、相互に作用し合いながら時間と共に形を変えていくと捉える考え方です。研究では、歴史的背景が似た二国を選び、なぜ業界組織化で異なる結果になったのか、そのプロセスを追跡しています。100件を超えるインタビューや、各種の公文書、協会の記録などを突き合わせることで、背後にあるメカニズムを解き明かそうとしました。
メキシコの事例は、「隔離による共進化」の物語です。メキシコのマイクロファイナンスは、1950年代に教会主導で始まりました。当初は国の規制の範囲外で成長しましたが、政府から違法性を指摘されるなど、敵対的な介入の兆しが見え始めます。この外部からの脅威が、組織に団結の動機を与えました。結果、1964年には全国的な協会が設立され、自己規制の仕組みを整え、専門性を高めていくことで、自律的な力を蓄えていきました。政府が業界を政策決定のプロセスから締め出し、「隔離」したことが、かえって内部の結束を強め、異質なアクターをも統合する力となったのです。
一方、ブラジルの事例は「取り込みによる共進化」として描かれます。ブラジルでは、政府、特に国立開発銀行が、マイクロファイナンス機関の主要な資金源でした。手厚い融資プログラムにより、業界は早くから国家資金に依存しました。また、政府の政策決定プロセスへのアクセスも比較的容易でした。個々の組織のリーダーは、政府関係者との個人的なネットワークを通じて、資金を得たり、意見を伝えたりすることができました。
しかし、この国家への近さが、業界全体の組織化にとっては足かせとなりました。各組織が個別に政府と交渉できるため、コストをかけて業界団体を作り、集合的に行動する必要性が薄れます。ブラジルでは業界団体の立ち上げが遅れ、団結した一つの声として政府に働きかける力が弱まりました。規制の枠組み作りも政府主導で進み、業界側が獲得できたものは限定的でした。国家による手厚い支援やアクセスの提供、すなわち「取り込み」が、皮肉にも業界の自律的な団結力を削いでしまったのです。
社会の物語の変化に乗り、偶発的に新制度を創出する
新しい産業や制度は、常に誰かの明確な意図や計画に基づいて生まれるのでしょうか。カナダ西海岸のビクトリアという街で、商業的なホエールウォッチング産業が誕生した経緯を追った研究は、個人の意図とは別の、より大きな力が働いていることを物語ります[4]。それは、社会全体で共有される「物語」、すなわちマクロな文化的言説の変化です。起業家は、その大きなうねりに乗り、意図せずして新分野を切り拓く存在として描かれます。
この研究は質的アプローチで、業界創設期の人々へ17件の詳細なインタビューを行い、その経験や意思決定の過程を明らかにしました。次に、規制の歴史、捕鯨に反対する言説の変遷、映画などのポピュラーカルチャーにおける鯨の描かれ方といった、より広範な社会の言説を分析しました。この二つの分析を組み合わせ、地域の出来事と社会全体の文化変化とのつながりを描き出しています。
この物語の背景には、過去150年における「鯨」という存在に対する社会の認識の変化があります。かつて小説『白鯨』のように、鯨は恐ろしい怪物で狩猟対象でした。しかし時を経て、鯨は保護すべき希少な生物、さらに知性や感情を持つ特別な存在と見なされるようになります。特に、映画『フリー・ウィリー』の大ヒットは、シャチ(キラーホエール)を、共感や愛情を寄せるべき対象として社会に広く印象づけました。このような、規制、反捕鯨運動、大衆文化の中で形成されてきた新しい「鯨の物語」が、ホエールウォッチング産業が生まれるための文化的基盤を整えていました。
ビクトリアにおける商業ホエールウォッチングは、1987年にジョン・サイプラスという人物が始めた事業に端を発します。彼は当初から「ホエールウォッチング」を計画していたわけではありませんでした。彼が提供しようとしたのは、高速ボートを使った野生動物ツアーでした。しかし、事業を始めてみると、顧客の関心は圧倒的に鯨に集中していました。これは、彼が作り出した需要ではなく、社会に既に存在していた、新しい鯨の物語によって育まれた需要でした。サイプラスは、この顧客の反応に応える形で、事業の焦点を鯨へとシフトさせていきます。
彼の決定の多くは、計画的というよりその場での対応でした。どのようなボートを使うか、どのように鯨の群れを見つけるか、他の業者とどう協力するか。この初期の試行錯誤が、意図せずして後の事業者の模倣対象となり、業界の「標準」の原型を形作りました。事業者が増えるにつれて、港の利用を管理するための協会や、業界の自主基準を設定するための団体が設立されます。こうして、一個人の偶発的ともいえる行動の連鎖から、一つの制度化された産業分野が創出されていきました。
この事例が示唆するのは、制度的企業家の、もう一つの側面です。それは英雄的なビジョンで未来を拓くのではなく、社会の文化変化の波を感じ取り適応する中で、結果として新しい仕組みを生む創発的で偶発的なプロセスです。起業家は、自ら波を起こすというよりは、既に来ている波にうまく乗るサーファーのような存在なのかもしれません。社会の大きな物語の変化が、個人の行動に意味をあたえ、その積み重ねが、誰も予期しなかった新しい制度的フィールドを出現させる。私たちの周りで起きる変化も、こうした目に見えない大きな文脈の中で捉え直すことができるかもしれません。
脚注
[1] Nasra, R., and Dacin, M. T. (2010). Institutional arrangements and international entrepreneurship: The state as institutional entrepreneur. Entrepreneurship Theory and Practice, 34(3), 583-609.
[2] Child, J., Lu, Y., and Tsai, T. (2007). Institutional entrepreneurship in building an environmental protection system for the People’s Republic of China. Organization Studies, 28(7), 1013-1034.
[3] Olsen, T. D. (2017). Rethinking collective action: The co-evolution of the state and institutional entrepreneurs in emerging economies. Organization Studies, 38(1), 31-52.
[4] Lawrence, T. B., and Phillips, N. (2004). From Moby Dick to Free Willy: Macro-cultural discourse and institutional entrepreneurship in emerging institutional fields. Organization, 11(5), 689-711.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。