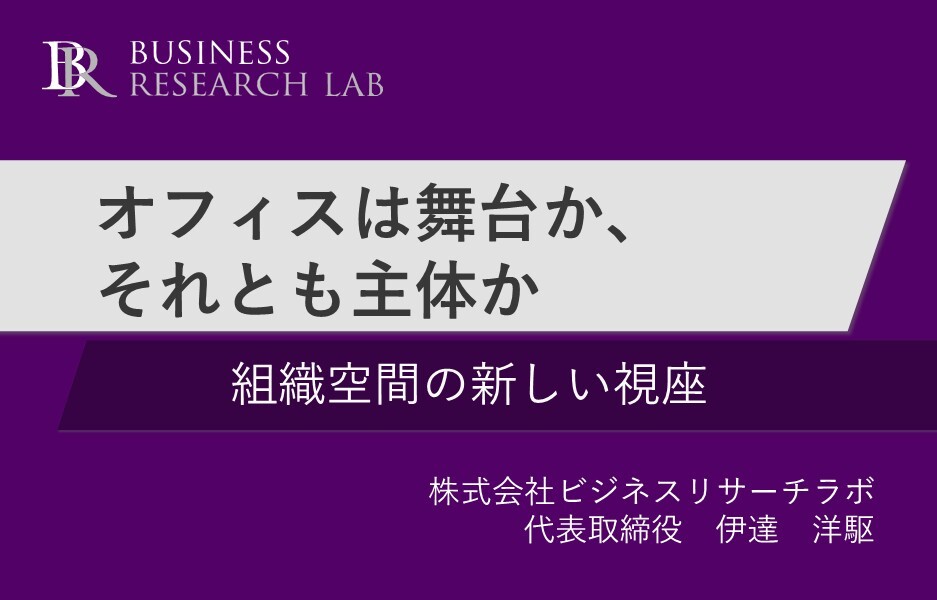2026年1月16日
オフィスは舞台か、それとも主体か:組織空間の新しい視座
日々働くオフィスや工場、店舗といった場所。その空間について、私たちはどれほど意識を向けているでしょうか。多くの人にとって、職場とは業務をこなすための背景、あるいは「入れ物」として認識されているかもしれません。しかし、その壁の配置、デスク間の隔たり、あるいは人々が何気なく通る廊下の幅は、私たちの働き方や思考、さらには組織全体の文化や創造性まで形作っています。
空間は、そこにいる人々の活動を受け止めるだけの受動的な舞台ではありません。見えない形で、人々の関係性に働きかけ、組織という生命体のあり方を方向づけている能動的な存在です。本コラムでは、普段は意識されることの少ない「組織と空間」の関係を検討します。
組織空間を「境界・距離・移動」で捉える
組織における空間の働きを理解しようとするとき、どこから手をつければ良いのでしょうか。空間はあまりに当たり前に存在するため、その輪郭を捉えるのは案外難しいものです。この問いに一つの道筋をつけたのが、組織空間に関する膨大な実証研究を整理・統合した試みです[1]。
その分析は、経営学や組織論の分野で発表された121本の論文を読み解くことから始まりました。研究者たちは、個々の研究が暗黙的、あるいは明示的にどのような観点から空間を捉えているかを抽出し、整理していきました。その結果、多様に見える組織空間の研究が、三つの基本的な要素に分解できることを見出しました。それが「境界」「距離」「移動」です。
一つ目の「境界」とは、空間を区切り、内と外を分ける仕組みのことです。これは物理的な壁やドアだけを指すわけではありません。例えば、ある部署と別の部署の間にある見えない心理的な仕切りや、正社員と非正規社員といった社会的な立場の違いによって生じる隔たりも、広義の境界と見なされます。
境界は、ある集団のアイデンティティを定め(「私たちはここまで」という区別)、空間内での振る舞いを整え(「この場所ではこう振る舞うべきだ」という秩序化)、人や情報、資源の出入りを管理する関門としての働きを担います。例えば、企業が老朽化した旧社屋からデザインを一新した本社ビルへ移転したとします。このとき、二つの建物の物理的なコントラストは、組織が過去と決別し、新しいアイデンティティを築こうとしていることの象徴として機能することがあります。
二つ目の「距離」は、二つの地点や空間の間にある「隔たり」を意味します。これもまた、単なる物理的な隔たりだけではありません。ある業務と別の業務の機能的な隔たり、役職による権力的な隔たり、あるいは文化や心理的な親近感の遠近といった、多様な次元の距離が存在します。
測り方も、客観的な絶対距離だけでなく、人々が主観的に感じる知覚的な距離や、時間やコストといった観点から見た相対的な距離も考えられます。多くの研究で、職場で席が近いといった物理的な近接性が、知識の交換を促したり、信頼関係を築いたり、あるいは公平感の醸成に関わったりすることが分かっています。
三つ目の「移動」は、ある場所から別の場所への位置の変化や、その軌跡を指します。オフィス内を歩き回ることから、在宅勤務への移行、あるいは海外赴任まで、様々なスケールの移動が考えられます。
移動は、それ自体が結果であると同時に、境界や距離を再編成する原因ともなります。例えば、働き方がオフィスから家庭へと移動すると、「仕事」と「家庭」という二つの空間を隔てていた境界は曖昧になり、両者の心理的な距離は縮まります。これによって、二つの空間は互いに作用し合い、新たな関係性へと再編成されていくでしょう。
これらの三要素「境界・距離・移動」を組み合わせることで、組織空間で起こる現象を体系的に理解することができます。先の分析では、多くの研究が四つの主要なテーマに関心を寄せていることも整理されました。
「空間内の分布」は、中心と周縁、見える場所と見えない場所といった配置の違いが活動にどう関わるかというテーマです。「空間の隔離」は、外部から遮断された場所が、通常とは異なる実践や学習をいかに可能にするかを探ります。「空間の分化」は、異なる特性を持つ空間が人々の活動にどう作用するか、また新しい空間がどう生まれるかを扱います。「空間同士の交差」は、複数の空間が重なり合う「狭間」で、境界が曖昧になることで生まれる創造性や権力の再配分を論じます。
空間は距離・権力・経験が絡み組織を形づくる
空間を「境界・距離・移動」という構成要素で捉える視点は、組織を分析するための道具となります。しかし、空間はそれだけでは語り尽くせません。空間は、そこにいる人々の経験や、社会に埋め込まれた権力関係と結びついています。空間をめぐる研究の歴史を紐解くと、そこには大きく三つの異なる捉え方が存在することが分かります[2]。これらは互いに排他的なものではなく、むしろ空間の多面性を照らし出す、異なる光のようなものと考えることができます。
第一の捉え方は、「距離としての空間」です。これは最も古典的で直感的な見方と言えるでしょう。物理的な点と点の間の隔たりとして空間を理解し、その配置が人々の行動や相互作用を決定するという考え方です。
例えば、オフィスレイアウトの研究では、デスクやパーティションの配置がコミュニケーションの頻度や質にどう関わるかが分析されてきました。オープンプランのオフィスが対話を促すという主張もあれば、逆に集中を妨げるといった議論もあります。産業レベルでは、企業がある場所に集積する現象が、資源や競合他社への地理的な近さが知識の伝播やイノベーションを促進するという観点から説明されます。
この見方は、空間配置を変更することで成果を変えられるかもしれないという実務的な含意を持ち、非常に分かりやすいものです。しかし、その一方で、人々が空間に込める意味や、その配置の背後にある力学を見過ごしてしまうという限界も持っています。
そこで登場するのが、第二の捉え方である「権力の物質化としての空間」です。この立場は、空間の配置がそうなっているのはなぜかと問い、その背後に権力や支配の関係性を見出します。
例えば、近代の工場は、労働者を効率的に管理し、規律を植え付けるための装置として設計されました。見通しの良い空間配置は、監視の視線を隅々まで行き渡らせ、労働者の時間や身体の動きをコントロールします。あるいは、職場と家庭という空間がはっきりと分断されていることも、近代社会における公私の分離という秩序を物質的に表現したものです。都市や地域といった大きなスケールでも、資本の論理に都合の良いように空間が構築されていきます。
この視点は、空間が中立的なものではなく、特定の意図や力関係を反映したものであることを教えてくれます。ただし、すべてを支配の論理で説明しすぎると、そこで生活する人々の主体的な営みや、設計者の意図を逸脱するような空間の使われ方を見落とす危険性も指摘されています。
この点を補うのが、第三の捉え方、「経験としての空間」です。この立場は、客観的な距離や権力関係を超えて、人々がその空間をどのように解釈し、感じ、経験するかに焦点を当てます。建物のデザインや内装、飾られたアート、あるいは人々の服装といった象徴的な要素が、組織の価値観や文化を物語る「語る空間」として分析されます。
また、人々は与えられた空間をそのまま受け入れるだけではありません。決められた用途とは違う仕方で空間を使いこなしたり、遊び心あふれる実践によって堅苦しい空間を創造的な場へと転換したりすることもあります。このように、空間をそこに住まう人々の主観的な経験の世界から捉えることで、その場の持つ豊かな意味の層を明らかにすることができます。一方で、この見方は、人々の解釈や感情を扱うあまり、物理的な制約や社会的な権力関係の存在を軽視してしまうことがあるかもしれません。
これら三つの潮流、「距離」「権力」「経験」は、それぞれ空間の一側面を切り取っていますが、それだけでは全体像は見えてきません。そこで、これらを統合する枠組みが提案されています。それは、空間を単一の視点から見るのではなく、身体的な「実践」(歩く、座るなど)、権力によって計画された「設計」(建築、都市計画など)、人々の物語や解釈による「想像」という三つのプロセスが絡み合って生まれる社会的な産物として捉える考え方です。
これに「スケール」という概念が加わります。個人の身体やデスク周りといったミクロなレベル、組織の内と外を分ける境界などのメゾレベル、都市や国家といったマクロレベル。これらの異なるスケールが相互に作用し合いながら、組織空間は絶えず生成されています。
空間配置が偶発的対話を生み、組織力を育む
空間が距離、権力、経験の絡み合いで成り立っていることを理解すると、次なる問いが生まれます。それは、空間の配置を工夫することで、組織の中に予期せぬ出会いや新しいアイデアが生まれるような状況を作り出すことはできるのだろうか、というものです。
この問いに分け入った研究は、建築物を「組織能力を生成する構成要素」として捉え直すことを試みます[3]。「形は機能に従う」という近代建築の原則がありますが、むしろ「機能が形に従う」こともあるのではないか、と発想を転換させます。あらかじめ定められた機能に合わせて空間を作るのではなく、新しい空間の形態が、これまでになかった新しい活動や関係性を生み出すという考え方です。
この発想の背景には、空間と権力の関係に関する洞察があります。監視や規律といった、人々をコントロールするための否定的な権力装置として空間を考えるのではなく、新たなつながりや知識を生み出す生産的な権力装置として空間を捉え直す視点です。空間の設計次第で、普段は接点のない人々の間に「弱い紐帯」が生まれ、部門や専門領域を超えた対話が促進されるかもしれません。その鍵となるのが、「意図せざるコミュニケーション」をいかにデザインするかです。
ある研究開発組織を対象とした調査では、興味深い結果が得られました。研究者たちのコミュニケーションが最も活発に行われていたのは、会議室や実験室ではなく、意外にもコピー機の前や給湯室、トイレといった共有設備のある場所でした。
人々は、本来の業務とは異なる目的でこれらの場所に移動する過程で、偶然他の部門の人間と顔を合わせ、何気ない会話を交わします。こうした偶発的な出会いが、新しい知識の交換や共同作業のきっかけとなっていたのです。このことから分かるのは、人々の動線が交差するような場所に共有設備を戦略的に配置することが、組織内のコミュニケーションを活性化させる上で有効であるということです。
しかし、空間のデザインはそう単純ではありません。例えば、ある航空会社が、偶発的な出会いを促進して創造性を高めるという意図のもと、壁を取り払った開放的な本社ビルを建設しました。ところが、その後の調査で、従業員の相互作用の多くは、結局のところ個室や限られた部署内で発生していたことが分かりました。
「オープンオフィス」といった名称や理念だけでは、人々の行動は簡単には変わらないのです。重要なのは、空間のラベルではなく、建物全体の配置における各空間のつながりやすさや、動線の連結性がいかに設計されているかです。個人の集中を確保するための閉じた空間と、偶発的な接触を促す開かれた空間が、建物全体の中で適切にバランスされている必要があります。
このような考え方を推し進めると、「ジェネレーティブ・ビルディング」という概念にたどり着きます。これは、予測可能性と偶然性が均衡した、秩序と混沌の間にあるような空間を指します。すべてが計画され尽くした空間は驚きを生まず、完全な無秩序は協働を困難にします。
ジェネレーティブ・ビルディングは、未来の使われ方を過剰に作り込まず、あえて用途を定めない「余白」を残します。そうした空間は、使う人々による自由な解釈や、当初の意図を超えた使いこなしを誘発します。また、階段や廊下といった、移動のための装置を、人々が立ち止まり、会話を交わすことができる滞留可能な場所へと転換させる工夫も凝らされています。
これとは対照的なのが、安全や監視を過度に重視するあまり、偶発的な出会いや混じり合いを排除してしまう「ターミナル・ビルディング」です。見通しが良すぎる空間や、厳格に管理された動線は、効率的かもしれませんが、新しい何かが生まれる可能性の芽を摘んでしまいます。組織の力を育む空間とは、人々がランダムに出会い、領域を超えた対話が生まれるような、適度な「遊び」や「余白」を持った空間なのかもしれません。
空間そのものが組織化を遂行する
これまで、空間を構成する要素、空間を理解するための視点、創造性を生む空間のデザインについて見てきました。これらの議論は、空間が組織にとって静的な背景ではなく、能動的な働きを持つことを明らかにしてきました。しかし、この関係をさらに掘り下げると、私たちは「空間が組織化を行う」という、よりラディカルな考え方に行き着きます。これは、空間が組織活動の「中で」使われるのではなく、空間が生成され、維持され、変容していくプロセスが、組織を「成り立たせる」営みであるという視点です[4]。
この考え方を理解するためには、空間を固定的な「モノ(space)」としてではなく、絶え間ない動きや実践によって生成され続ける動的な「プロセス(spacing)」として捉え直すことが必要です。この視点に立つと、組織空間をめぐる研究は、そのプロセスの捉え方の強弱によって、いくつかの異なる志向に分類することができます。
比較的弱いプロセスの見方として、まず「developing」な志向があります。これは、空間をある程度安定した物理的環境とみなし、オフィス改装やレイアウト変更といった出来事が、人々の行動や認知にどのような変化をもたらすかを分析するものです。例えば、パーティションを取り払うことで、部門間のコミュニケーションが増加した、といった研究がこれにあたります。
続いて、「transitioning」な志向です。これは、廊下や階段、あるいは社外のカフェといった、正規の業務空間の「狭間」や「合間」に焦点を当てます。こうした場所では、公式な規範が一時的に緩み、私的な会話や内省、あるいは既存の秩序への抵抗といった、非公式な活動が生まれることが示されます。
これに対し、より強いプロセスの見方は、空間そのものが関係性や実践の中から「立ち上がってくる」と考えます。その一つが「imbricating」な志向です。これは、人々、モノ、言葉、身体の動きといった多様な要素が、あたかも布を織るように絡み合い、折り重なることで、その場固有の空間が生成されていく様子を描き出します。人々が空間を本来の用途とは違う仕方で使いこなす(転用)実践などが、この視点から分析されます。
さらに、「becoming」な志向は、空間をリズムや速度、感情、身体的な経験が渾然一体となった「生成の真っ只中」として捉えます。ある瞬間には静かな会議室であった場所が、次の瞬間には活気あふれるワークショップの場へと質的に変貌する。その場の雰囲気や出来事性が、空間を絶えず作り変えていくのです。
最も強いプロセスの見方が、「constituting」な志向です。これは、空間を成り立たせ、組織というものを継続的に立ち上げていく秩序化の営みを追跡します。人、モノ、技術がどのように配置され、動きがどのように習慣化され、空間と時間がどのように調和されるか。こうした一連の活動を通じて、空間が組織を構成していくプロセスを記述します。空港の複雑な業務が、相反する秩序の衝突と調整の中から新しい空間のあり方を形成していく、といった事例がこれに当たります。
このようなプロセス視点から見ると、これまで静的な概念として扱われてきた「境界」や「移動」といった要素も、その意味合いが変わります。例えば、「境界」は固定的な壁ではなく、人々が区切ったり、ぼかしたり、広げたりといった交渉を続ける動的な「境界作業(boundary work)」として捉えられます。同様に、物理的な要素の組み合わせも、固定的な「配置」から、人やモノ、技術が流動的に結びつき続ける「アセンブリ(assemblage)」へと読み替えられます。
ローカルからグローバルへと続く階層的な「スケール」も、技術や言説によってその到達範囲が伸び縮みする動的な「スケーリング」として理解されるのです。
脚注
[1] Weinfurtner, T., and Seidl, D. (2019). Towards a spatial perspective: An integrative review of research on organisational space. Scandinavian Journal of Management, 35(2), 101009.
[2] Taylor, S., and Spicer, A. (2007). Time for space: A narrative review of research on organizational spaces. International Journal of Management Reviews, 9(4), 325-346.
[3] Clegg, S. R., and Kornberger, M. (2004). Bringing space back in: Organizing the generative building. Organization Studies, 25(7), 1095-1114.
[4] Stephenson, K. A., Kuismin, A., Putnam, L. L., and Sivunen, A. (2020). Process studies of organizational space. Academy of Management Annals, 14(2), 797-827.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。