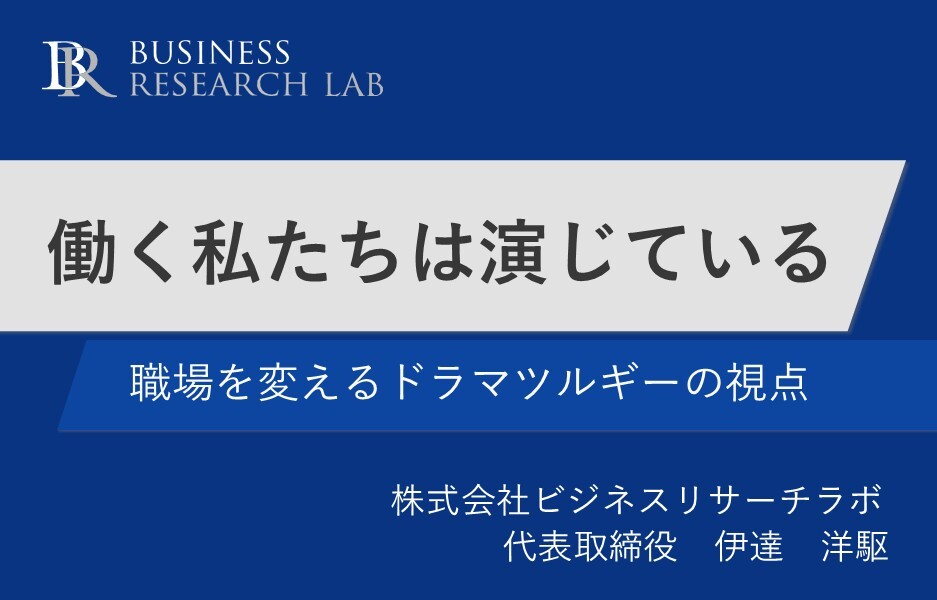2026年1月15日
働く私たちは演じている:職場を変えるドラマツルギーの視点
職場での日々の振る舞いは、見方を変えれば、一つの「演技」であると言えるかもしれません。会議で意見を述べる姿、上司や同僚と交わす何気ない会話、あるいは社運をかけたプロジェクトのプレゼンテーション。これら一つひとつの場面で、私たちは無意識のうちに、あるいは意識的に、ある種の「役」を演じているのではないでしょうか。
普段、私たちは組織を、規則や階層構造といった固い枠組みで捉えてしまいます。しかし、そこに集う人々の生きた相互行為、つまり「上演」という視点から光を当ててみると、これまで見えてこなかった組織の別の顔が浮かび上がってきます。本コラムでは、「上演」という切り口から、組織という舞台の裏側で何が起きているのかを探求していきます。組織が持つ力動的な側面と、その中で生きる私たちの振る舞いの意味を、新たな角度から見つめ直すきっかけを提供できれば幸いです。
非合法な抗議を説明し正当性を得る
社会の仕組みを根底から変えようとする団体が、時に法律の境界線を越えるような過激な行動に出ることがあります。常識的に考えれば、そのような行為は社会からの非難を浴び、孤立を深めるだけのように思えます。しかし、現実には、そうした団体が批判を乗り越え、かえって多くの支持を集め、その活動の「正当性」を認めさせてしまうことがあります。
一体、どのような仕組みが働いているのでしょうか。この逆説的な現象を解明するため、二つのラディカルな社会運動組織、環境保護を訴える「アース・ファースト!」と、エイズ問題に取り組む「ACT UP」の活動を追った研究があります[1]。
この研究では、両団体が関わったとされる、物議を醸す八つの行動が分析の対象となりました。研究者たちは、団体のメンバーへのインタビュー、新聞やテレビなどの膨大な報道記録、実際の会議の観察を通じて、非合法とも取れる行動が、いかに組織の正当性獲得へと転換されていくのか、その過程を一つのモデルとして描き出しました。
そのプロセスは五つの段階を経て進みます。第一の段階は、メンバーによる非合法的な行動が、メディアの関心を引くことから始まります。これらの行動は、その過激さゆえに報道機関の目を引きつけ、団体の名前と、その団体が訴える問題を社会に広く知らせるきっかけとなります。もちろん、最初の報道は、その行動自体への批判的な論調を含むことがほとんどです。
第二の段階で、事態は少し違う様相を呈します。報道を受けてメディアが団体に取材を試みると、そこで二つの意外な側面に遭遇するのです。
一つは、団体が驚くほど整った組織構造を持っていることです。メディアからの問い合わせに応じるための広報担当や専門知識を持つ委員会などが設けられており、他の一般的な組織と変わらない、理性的な対話が可能な相手であるという印象を醸し出します。もう一つは、問題となった過激な行動と、組織本体とを切り離す仕組みです。多くの場合、その行動は「組織として決定したものではなく、独立した小グループや個人の判断で行われた」という説明がなされます。
この二つの準備、「しっかりとした組織である」という体裁と、「問題行動は本体とは無関係である」という分離が、第三の段階で展開される言語的な戦略の土台となります。ここで登場するのが、組織のスポークスパーソンです。
スポークスパーソンは、二種類の説明を使い分けます。一つは「無実の弁明」です。先の分離の仕組みを利用し、「その行動に組織としての責任はない」と主張します。もう一つは「正当化」です。行動自体に問題があったかもしれない点は認めつつも、「その行動を取らざるを得なかった背景」や「その行動がもたらした社会的に良い結果」を強調します。例えば、「あらゆる合法的な手段を尽くした後の、最後の選択だった」といった主張です。これによって、人々の関心は、非難されるべき「手段」から、共感できる「目的」へと誘導されていきます。
第四の段階では、より能動的な印象操作が行われます。行動に対する否定的な見方が和らいだのを見計らい、スポークスパーソンは、その行動が社会全体にもたらした有益な結果を強調し始めます。例えば、「自分たちの抗議活動があったからこそ、薬の価格が下がり、多くの命が救われた」といった主張です。その功績は自分たちの団体あってのものだと宣言することで、団体の価値を高めていきます。
最後の第五段階で、組織は正当性を獲得するに至ります。一連のプロセスを通じて、当初は過激な「手段」に向けられていた社会の非難は徐々に忘れ去られ、スポークスパーソンが語り続けた共感しやすい「目的」が人々の心に残ります。結果、団体の掲げる大義に賛同する人々からの支援が集まり始めるのです。
分析によれば、行動直後の批判は短期間で収束する一方で、団体への支持は時間をかけて現れ、より長く続くことが分かっています。このように、一見すると自らの首を絞めるかのような非合法な行動も、周到に計算された「上演」と組み合わせることで、組織の生存に不可欠な正当性を手に入れるための一歩となり得ます。
朝食会の儀礼が権力関係を演出する
先ほど見たような、社会の耳目を集める過激な抗議活動は、計算され尽くした非日常の「上演」と言えるでしょう。しかし、「上演」は特別な場面だけで行われるわけではありません。むしろ、私たちの職場におけるごくありふれた日常風景の中にこそ、組織の力学を静かに、しかし確実に形作っている「上演」が潜んでいるのかもしれません。
ある広告代理店で、十ヶ月にわたって行われた参加観察研究は、フィラデルフィア中心部のレストランで開かれる定例のビジネス朝食会という相互行為の場に潜む力学を浮き彫りにしました[2]。
この研究は、「ドラマツルギー」という考え方を応用しています。これは、私たちの社会生活を一つの舞台になぞらえ、人々をその上で役割を演じる役者として捉える視点です。この視点から朝食会を観察すると、誰がどの席に着くか、誰が最初に口火を切るか、誰の冗談に皆が笑うかといった一つひとつの振る舞いが、偶然や個人の性格によるものではなく、その場の権力関係を演出し、再生産するための、意味を持った儀礼であることが見えてきます。
朝食会という舞台は、段取りに沿って幕を開けます。参加者が席に着く順番、交わされる最初の挨拶、定番の軽口。これらは、その日の会議の「場の空気」を設定する儀礼です。特に、その場を主宰する上位者は、会話のテンポを握り、話題の方向性を決めることで、舞台全体の調子を整えます。
座席の配置もまた、雄弁に力関係を物語ります。上位者は自然と、全員の顔が見渡せ、自分の声が隅々まで届く中心的な位置を占めます。その周りの席順は、社内の部門間の関係性や、非公式な人間関係を反映します。テーブルの端に座った者は、物理的に会話の中心から遠ざけられることで発言の機会を失いやすく、その存在は周縁化されていきます。
会話の流れも、見えないルールによって設計されています。誰が新しい議題を切り出すことができ、誰が議論を締めくくる権限を持つのか。誰が他者の発言に割り込み、それを要約して「公式な解釈」として定めることができるのか。これらの権限は、多くの場合、組織の序列の高い人物に集中しています。日常的に交わされる冗談やからかいでさえ、場の緊張を和らげる一方で、逸脱した言動をそれとなく戒める、柔らかな規律として機能します。
テーブルの上にあるモノの扱いも、関係性を可視化する小道具となります。誰がメニューの注文を取りまとめ、誰がコーヒーを注ぎ、そして最も象徴的なのは、誰が伝票を手に取り支払いをするか、という一連の所作です。支払いを引き受ける行為は、寛大さを示すと同時に、他の参加者に対して一種の「負い目」を生じさせ、穏やかな形で上下関係を固定化する働きを持ちます。
この研究が明らかにしたのは、組織における支配というものが、必ずしも上司からの直接的な命令や強制といった形を取るわけではないということです。朝食会のような非公式で日常的な儀礼の場で繰り返される、微細な「上演」の積み重ねを通じて、権力関係は参加者の身体に刻み込まれ、ごく自然なものとして受け入れられていきます。そこでは誰もが役者であり、観客でもあるのです。こうした日常に埋め込まれた「上演」は、組織の文化、要するに「何が普通で、何が適切か」という感覚を作り上げていきます。
企業シアターは演出技術で従業員の感情を方向づける
日常に溶け込んだ朝食会の儀礼が、半ば無意識のうちに組織の秩序を作り上げていく「上演」であるとすれば、企業が意図的に、コストをかけて作り上げる「上演」も存在します。それは、従業員の感情や考え方を特定の方向へと導くために、演劇の専門的な技術を駆使して行われるスペクタクルです。
ある英国の大手銀行が、二社の統合を記念して開催した大規模な社内イベントは、このような「テクノロジーとしての演劇」がどのように機能するのかを克明に記録した研究の舞台となりました[3]。
この研究は、八ヶ月にわたり、イベントの企画段階から、上演当日、その後の職場への波及効果までを追跡しました。このイベント「Your Life. Your Bank.」は、ただの祝賀会ではありません。それは、経営陣が描く「統合は素晴らしい成功であり、未来は希望に満ちている」という一つの物語を、従業員に深く疑いなく信じ込ませるための、緻密に設計された感情操作の技術だったのです。
その制作過程において、脚本の方向性を決定したのは経営の最上層部でした。現場の従業員が抱えるであろう統合への不安や疑問は物語の筋から慎重に排除され、「良いニュース」だけが並べられた、統合を礼賛するショーとして構成されていきました。クライマックスには、当時の人気バンドをサプライズで登場させ、高揚した感情が最高潮に達したところで、イベントのスローガンを全員で共有するという設計でした。
舞台の設計、すなわち「ミザンセーヌ」もまた、観客の感情を誘導するために周到に計算されていました。会場には巨大な特設ステージが組まれ、参加者は凱旋路のように長くデザインされた通路を通り、新銀行の輝かしい未来を象徴する展示を眺めながら、メインステージへと導かれます。
開演と同時に会場は暗転し、大スクリーンに統合までの道のりを描いた感動的な映像が流れ、カウントダウンが始まります。照明、音楽、映像、司会者の語りが一体となって、参加者を日常から切り離し、祝祭的な空間へと没入させていきます。言葉による説明だけでなく、空間や音、光といった身体感覚に直接訴えかける演出が、観客の解釈の幅を狭め、経営陣の望む一つの「感じ方」へと収斂させていきました。
この上演において、参加者は単なる「観客」ではありません。招待された従業員は、このイベントで語られた物語を職場に持ち帰り、同僚たちに伝える「メッセンジャー」としての役割を与えられていました。イベント後には、説明用の台本やビデオが詰まった「カスケード・パック」が手渡され、それぞれの職場でこの「上演」を再演する義務が課せられていたのです。
新CMの先行公開や出演俳優の登場といったサプライズ演出は、会場に熱狂的な拍手や歓声を引き起こします。こうした集団的な同調反応は、周囲に伝染し、会場全体に「統合は皆から歓迎されている」という一体感のある空気を作り出します。
この事例が示しているのは、企業シアターが、対話や異議申し立ての場を設けるのではなく、一方的に構成された物語と祝祭的な雰囲気によって、従業員の感情を方向づける洗練された技術であるということです。それは、組織が抱えるかもしれない矛盾や対立を覆い隠し、達成感や誇りといったポジティブな感情で満たすことで、経営層の視点を従業員に浸透させる装置として機能します。
組織生活は稽古と即興で刷新される上演である
これまで、私たちは組織における様々な「上演」の形を見てきました。非合法な行動を正当化する緻密な言語戦略、日常の儀礼に潜む静かな権力、従業員の感情を一つの方向に導く壮大なスペクタクル。これらを通して見えてくるのは、組織が静的な構造物ではなく、人々の相互行為によって絶えず生成され、変化していく動的な舞台であるという姿です。
この舞台の上で、私たちはどのような「演者」であれば良いのでしょうか。ここでは、組織での生活を一つのドラマと捉え直し、管理者の振る舞いを「演じること」として考える視点から、組織をより良く刷新していくための可能性を探ります[4]。
この視点は、ある研究者の長年にわたる学術的キャリアと実践の記録から導き出されています。その中心にあるのは、「管理とは演じる芸術である」という考え方です。管理者の仕事は、予め完璧に書かれた脚本をただ読み上げることではありません。市場の動向や組織の歴史、自分自身の価値観といった、不完全で、時には矛盾をはらんだテキストを解釈し、観客である従業員や顧客の反応を見ながら、即興を交えて演じ切ることです。
この「演じる管理」を豊かにするためには、演劇の世界から借りてきた二つの概念が助けとなります。
一つは「稽古(リハーサル)」です。日常業務のプレッシャーや上下関係から一時的に解放された安全な空間で、新しい振る舞いやこれまでとは違う関係性のあり方を、失敗を恐れずに試してみる場を指します。例えば、普段は発言しにくい若手社員が上司役を演じ、上司がその部下役を演じてみる。そうした実験を通じて、凝り固まった役割意識を解きほぐし、新たなコミュニケーションの可能性を発見することができます。「稽古」は、権力関係を一時的に棚上げした、特別な相互行為の場として機能します。
もう一つの概念は、「美的距離(aesthetic distance)」です。自分たちが普段行っている相互行為を、舞台上の演劇を観る観客のように、一歩引いた視点から客観的に眺めてみることです。例えば、会議の様子を録画し、後で参加者全員で視聴してみる。そうすることで、自分たちの議論のパターンや、無意識のうちに繰り返している発言の癖、誰かの意見を遮ってしまっている瞬間などを、当事者としての感情的なしがらみから離れて冷静に観察することができます。この距離感が、自分たちの「演技」を自覚し、改善していくための気づきを与えてくれるのです。
これらの考え方は、先ほど見た企業シアターとは対照的な組織変革のアプローチを示唆します。経営層が作り上げた一つの物語をトップダウンで浸透させるのではなく、現場のメンバー一人ひとりが自らの「演技」を自覚し、互いの演技について対話し、より良い共演の形を即興的に探っていく。そのようなプロセスを支えるのが、管理者の役割となります。
管理者は、絶対的な脚本家や演出家として振る舞うのではなく、メンバーが良い「上演」を作り出すための「稽古」の場を設計し、自分たちのドラマを客観的に見るための「美的距離」を保つ手助けをする存在となります。組織は固定されたものではなく、日々の「上演」を通じて常に新しく生まれ変わる可能性を秘めています。その刷新の鍵は、私たち一人ひとりが、自覚的な「演者」となることにあるのかもしれません。
脚注
[1] Elsbach, K. D., and Sutton, R. I. (1992). Acquiring organizational legitimacy through illegitimate actions: A marriage of institutional and impression management theories. The Academy of Management Journal, 35(4), 699-738.
[2] Rosen, M. (1985). Breakfast at Spiro’s: Dramaturgy and dominance. Journal of Management, 11(2), 31-48.
[3] Clark, T. A. R., and Mangham, I. (2004). From dramaturgy to theatre as technology: The case of corporate theatre. Journal of Management Studies, 41(1), 37-59.
[4] Mangham, I. L. (2005). Vita contemplativa: The drama of organizational life. Organization Studies, 26(6), 941-958.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。