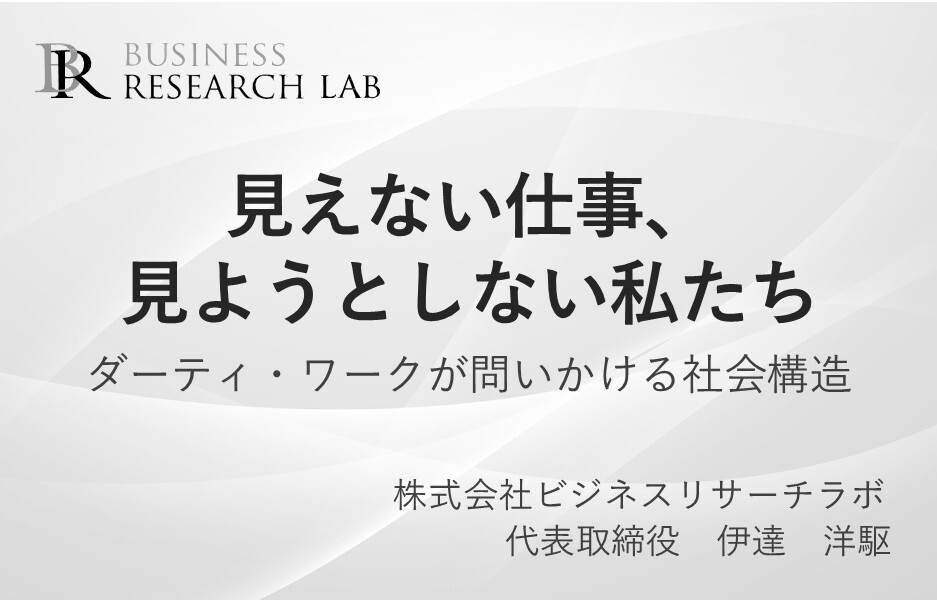2026年1月14日
見えない仕事、見ようとしない私たち:ダーティ・ワークが問いかける社会構造
「汚い仕事」と聞いて、私たちはどのような光景を思い浮かべるでしょうか。物理的な汚れや不快感を伴う労働を想像する人もいるかもしれません。それらは、「ダーティ・ワーク」と呼ばれる仕事の典型例です。しかし、この言葉が指し示す範囲は、それだけにとどまりません。
例えば、道徳的に非難されがちな仕事や、死を連想させ、人々から距離を置かれがちな仕事も含まれます。また、他者に奉仕する立場にあり、社会的に低い地位にあると見なされやすい仕事も、この概念の内にあります。これらに共通するのは、物理的、社会的、道徳的な「汚れ」のレッテルを貼られ、社会から敬遠されたり、見過ごされたりしやすい点です。
しかし、そうした仕事のほとんどは、私たちの社会が円滑に機能するために欠かすことのできないものです。誰かが担わなければ、私たちの生活は成り立ちません。にもかかわらず、その労働の現場や、そこで働く人々の姿は、日常生活の中から隠され、不可視化されています。
本コラムでは、ダーティ・ワークの世界に分け入ってみたいと思います。そこで働く人々は、自らの仕事にどのような意味を見出し、尊厳を保っているのでしょうか。他者から「見られない」という経験は、心に何をもたらすのでしょうか。歴史を遡ると、「誰が」そうした仕事を担ってきたのかという問いの先に、ジェンダーや人種といった、社会構造の課題が浮かび上がってきます。
ダーティ・ワークの担い手は、失われた力の誇りを知識で補う
社会から敬遠されやすい仕事に従事する人々は、自らの労働にどのような価値を見出し、誇りを育んでいるのでしょうか。その問いへの一つの答えを、英国の街角にある小さな精肉店、いわゆる「肉屋」の職人たちの語りから探ることができます[1]。彼らの仕事は、血や肉に触れ、重い枝肉を扱い、刃物や機械の危険と隣り合わせという、ダーティ・ワークの性質を帯びています。
かつて、精肉店の職人にとって、その誇りの源泉は圧倒的な身体性にありました。牛の半身を一人で担ぎ上げ、大きな骨を断ち切る腕力。冷たい食肉庫での長時間作業に耐える強靭な肉体。そうした「力」が、熟練の証であり、男性的な仕事の美学を体現するものでした。しかし、時代は変わります。BSE(牛海綿状脳症)問題以降、衛生規制は格段に厳しくなり、スーパーマーケットとの競争も激化しました。食肉処理の工程は大規模な工場に集約され、店舗に届くのは、あらかじめ切り分けられたブロック肉が中心になりました。
この変化は、職人たちの仕事から、かつての誇りの源泉であった「重く、汚く、危険」な側面を奪い去りました。インタビューに応じた26人の男性職人たちの多くは、過去を懐かしむように語ります。「昔は牛半丸を担いだものさ」「血と内臓にまみれた作業こそ腕の見せ所だった」と。それに比べ、現在の仕事は、細かな記録の作成、温度管理、そして絶え間ない清掃といった、どちらかといえば事務的で、身体的な迫力に欠けるものになったと感じています。
彼らの言葉の端々からは、自らの身体的な資本、要するに長年培ってきた肉体的な強さや技術の価値が、制度の変化によって一方的に切り下げられてしまったことへの喪失感がにじみ出ていました。
しかし、彼らは失われた過去を嘆くだけではありません。失われた身体的な誇りを埋め合わせるかのように、新たな価値の源泉を見出し、それを丹念に磨き上げていました。それは、「知識」という、もう一つの資本です。彼らは「本物の職人」であるという自負を強く持っています。その自負を支えるのが、肉のあらゆる部位に関する知識、骨を抜き、筋を引く繊細な技術、肉の熟成を見極める経験、顧客一人ひとりの要望に応じた調理法を助言できるコミュニケーション能力です。
有名シェフが登場する料理番組の隆盛も、彼らにとって追い風となりました。食文化への関心の高まりは、彼らの専門知識が正当に評価される機会を増やしたのです。「この部位は、こんな風に料理すると美味しいですよ」。顧客とのそんな何気ない会話が、販売行為を、専門知識が披露されるパフォーマンスの場へと変えます。失われた身体的な力の誇りは、顧客との対話の中で可視化される知識の誇りへと、見事に姿を変えていました。
ダーティ・ワークの不可視は、苦痛と安堵の両面を持つ
仕事の内容が変化する中で、知識を新たな誇りの源泉として尊厳を再構築する職人たちの姿を見てきました。しかし、ダーティ・ワークには、そもそも他者から「見られない」、あるいは「見ないようにされる」という問題がつきまといます。この「不可視性」という経験は、働く人々の心にどのような光と影を落とすのでしょうか。その複雑な内実を、米国の大学で働く清掃労働者たちの声から探ってみましょう[2]。
大学のキャンパスは、本来、学生や教職員が主役の舞台です。清掃労働者は、その舞台を裏方として支える不可欠な存在でありながら、しばしば「そこにいない」かのように扱われます。廊下ですれ違っても挨拶を返されない。目の前で平然とゴミを捨てられる。自分が透明人間にでもなったかのような感覚。これは、彼らが日常的に経験する「仕事の場での不可視」です。物理的には同じ空間を共有していても、その人格や存在が認められていないかのような疎外感をもたらします。
不可視性には、もう一つの側面があります。それは「仕事そのものの不可視」です。清掃という仕事の成果は、「汚れがない」という形で現れます。仕事が完璧に遂行されればされるほど、そこにあったはずの労働の痕跡は消え去り、その努力は誰の目にも留まりにくくなります。夜間の勤務体系や一人での作業が多いことも、この傾向に拍車をかけます。彼ら彼女らの労働は、その性質上、社会の営みの背景に溶け込み、見えなくなってしまうという性質を背負っているのです。
このような不可視の経験は、当然ながら、働く人々の心に苦痛を刻みます。自分の存在が軽んじられていると感じる屈辱感、良い仕事をしても誰にも気づかれないという無力感や悲しみ。特に、女性の清掃員からは、夜間の単独作業やトイレ清掃時に、他者の配慮が及ばない状況に置かれることへの、身の安全に対する不安や恐怖も語られました。不可視であることは、時として尊厳だけでなく、身体的な安全も脅かすのです。
ところが、彼ら彼女らの語りに耳をすませると、不可視性に対する意外な評価が聞こえてきます。それは、ある種の「安堵」や「解放感」です。
誰にも見られていないということは、裏を返せば、上司の過剰な監視や、顧客からの無遠慮な干渉を受けずに済むということでもあります。一部の労働者は、ヘッドホンで音楽を聴きながら、あるいはあえて他者と視線を合わせないようにしながら、自ら戦略的に「見えにくい」状況を作り出し、煩わしい人間関係から距離を置くことで、仕事上の平穏や自律性を確保していました。不可視性は、尊厳を脅かす脅威であると同時に、外部のストレスから身を守るためのシェルターとしても機能しうる、両義的な性格を持っています。
ダーティ・ワークに従事する人は、誇りと恥に引き裂かれやすい
他者から見られないという経験が、苦痛と安堵という両義的な感情をもたらすことを見てきました。ここでは、さらに働く人の内面に分け入り、ダーティ・ワークに従事する人々が抱える心のせめぎ合いについて考えてみたいと思います。それは、「誇り」と「恥」という、二つの相反する感情の間で引き裂かれる、複雑なアイデンティティの葛藤です[3]。
この葛藤を理解するために、二つの異なる心の働きを考えてみましょう。
一つは、社会に存在する序列や偏見を、当事者自身が受け入れてしまう働きです。私たちの社会では、職業は個人の自由な選択の結果であるという考え方が広く信じられています。そのため、ダーティ・ワークという社会的に低い評価を受けやすい仕事に就いている人々は、「それを選んだのは自分自身なのだから仕方ない」と、その否定的な評価を内面化してしまうことがあります。その結果、自分の仕事に対して心理的な距離を置き、自分自身をその職業から切り離そうとする状態に陥ることがあります。
しかし、人間にはもう一つの心の働きがあります。それは、自分が所属する集団に肯定的な価値を見出し、アイデンティティを守ろうとする働きです。外部から「汚い仕事だ」というレッテルを貼られると、人々はそれに抵抗しようとします。「この仕事は、社会にとって必要不可欠なのだ」と仕事の意味を捉え直したり、「給料は安いが、仲間との絆は何物にも代えがたい」と価値を置く基準をずらしたりします。このような創造的な再定義を通じて、集団としての誇りを守り、仕事への同一化を強めようとするのです。
ダーティ・ワークの現場では、この二つの力、すなわち社会の評価を受け入れそうになる力と、それに抵抗し誇りを打ち立てようとする力が、同時に作用しています。その結果、働く人々は、「世間は自分たちの仕事をつまらないものだと見ているだろう」という恥に近い認識と、「しかし、私たちの仕事には、私たちだけが知っている価値と誇りがある」という確信との間で揺れ動くことになります。誇りと恥が同居するアンビバレントな状態は、「両義的同一化」と呼ばれる、ダーティ・ワークに従事する人々に特徴的な心理状態です。
もちろん、ダーティ・ワークと一口に言っても、その「汚れ」の性質や度合いは様々です。仕事のほぼ全体が「死」という汚れのイメージと分ちがたく結びついている職業もあれば、普段の業務のほんの一部にだけ、不快な作業が含まれる職業もあります。仕事に占める汚れの「広がり」と「深さ」によって、このアイデンティティをめぐる葛藤の深刻さも変わってきます。
特に、仕事全体が強い汚れのイメージを持たれる職業では、外部からの偏見が「我々と彼ら」という境界線を強く意識させ、結果的に仲間内の結束を固めることがあります。そうした職場では、否定的な評価から自分たちの心を守るための、様々な知恵や実践が共有されていきます。
例えば、仕事の社会的な貢献度を強調する独自の物語を作り上げたり、外部の批判的な声は「何も知らない人間の戯言だ」と見なし、自分たちを理解してくれる一部の顧客からの感謝の言葉だけを心の支えにしたりします。あるいは、仲間内だけで通じるブラックユーモアを交わすことで、仕事のストレスを笑い飛ばすといったことも行われます。
性別の壁は崩れても人種の壁は残った
これまで、ダーティ・ワークに従事する人々の内面や、集団の中で尊厳を維持しようとする力学に光を当ててきました。しかし、ここで視点を広げ、そもそも「誰が」そうした仕事に就きやすいのかという構造的な問題に目を向ける必要があります。その担い手は、時代と共にどのように変化してきたのでしょうか。20世紀のアメリカの歴史をたどると、そこにはジェンダーと人種という二つの軸が織りなす、複雑な模様が浮かび上がってきます[4]。
分析の対象となるのは、生命を維持するために不可欠でありながら、育児のような情緒的なケアとは区別される「非養育型」の再生産労働です。
20世紀初頭、これらの仕事の主な舞台は、裕福な個人の家庭でした。いわゆる「家事使用人」として働く人々の大半が、この種の労働を担っていました。しかし、世紀が進むにつれて、社会は変化します。レストラン、ホテル、病院、学校といった大規模な施設が次々と生まれ、人々は食事や清掃といったサービスを、家庭の外で購入するようになりました。ダーティ・ワークの現場は、「私的」な家庭内から、「公的」な施設へと、その主戦場を移していったのです。
この働く場所の変化は、担い手の構成に変動をもたらしました。性別の構成が大きく変わりました。20世紀初頭には、これらの仕事の担い手の実に8割以上が女性でした。家事労働は「女性の仕事」という観念が、まだ強く社会を支配していた時代です。ところが、仕事の舞台が公的な施設に移ると、男性労働者が徐々に流入し始め、20世紀の終わりには、男女比はほぼ半々になりました。この領域において、「性別の壁」は、少なくとも数字の上では崩れたように見えます。
しかし、もう一つの軸、すなわち人種やエスニシティの構成に目を向けると、全く異なる景色が見えてきます。
20世紀を通じて、白人の人々は、これらのダーティ・ワークから相対的に離れていくという一貫した動向が確認できます。では、白人が去った後の担い手は誰だったのでしょうか。それは、アフリカ系、ヒスパニック系、アジア系といった、有色人種の人々や、新たに移り住んできた移民たちでした。時代が下るにつれて、その中心となるグループは変化しましたが、ダーティ・ワークの現場に、白人以外の人々が集中するという構造は、一世紀にわたって維持されたのです。
特に興味深いのは、仕事の現場が施設へと移行し、男性の担い手が増加したプロセスです。その内訳を見ると、増加分の大半を占めていたのは、ヒスパニック系をはじめとする有色人種の男性たちでした。起こっていたのは、仕事が性別を問わないものになったという単純な変化ではありません。それは、「白人女性」が担っていた役割を、主として「有色人種の男女」が引き継ぐという、ジェンダーと人種が複雑に絡み合った上での担い手の再編だったのです。
脚注
[1] Simpson, R., Hughes, J., Slutskaya, N., and Balta, M. (2014). Sacrifice and distinction in dirty work: Men’s construction of meaning in the butcher trade. Work, Employment and Society, 28(5), 754-770.
[2] Rabelo, V. C., and Mahalingam, R. (2019). “They really don’t want to see us”: How cleaners experience invisible ‘dirty’ work. Journal of Vocational Behavior, 113, 103-114.
[3] Kreiner, G. E., Ashforth, B. E., and Sluss, D. M. (2006). Identity dynamics in occupational dirty work: Integrating social identity and system justification perspectives. Organization Science, 17(5), 619-636.
[4] Duffy, M. (2007). Doing the dirty work: Gender, race, and reproductive labor in historical perspective. Gender & Society, 21(3), 313-336.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。