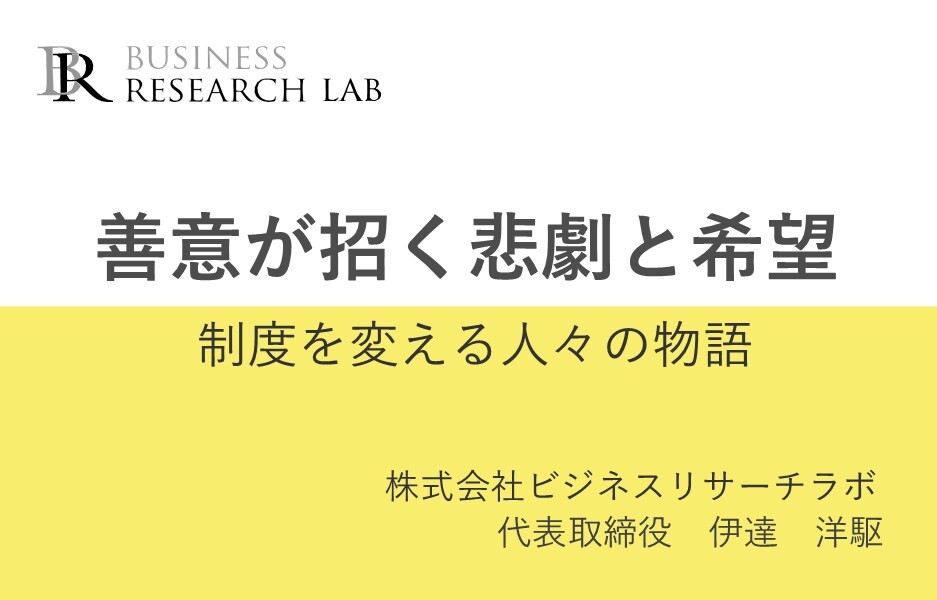2026年1月13日
善意が招く悲劇と希望:制度を変える人々の物語
社会をより良くしたいという純粋な願いが、時として思いもよらない悲劇を引き起こすことがあります。ある改革が特定の人々を救う一方で、別の人々を苦境へと追い込むのです。社会を変えるという行為が、単なる善意の実践ではなく、政治的な権力の駆け引きを伴う営みだからです。
私たちの周りには、ルールや「当たり前」とされる慣習、価値観が絡み合った「制度」が存在します。この見えない構造に働きかけ、新たな秩序を生み出そうとする人々を、本コラムでは「制度的企業家」と呼び、その活動の光と影に切り込みます。
制度的企業家の挑戦の裏側では何が起きているのでしょうか。ある者は大義名分の陰で誰かの犠牲の上に成功を築き、ある者は言葉や資源を緻密な戦略で組み合わせて勝利します。また、敵対する者同士をつなぐ「橋渡し役」を担う者や、曖昧なものに「測る」基準を与え、世界の「見方」を支配する者もいます。
児童労働問題解決の裏で女性を貧困化させた
社会正義の実現を目指す国際的な取り組みが、恩恵を受けるべき人々をかえって苦しめるという皮肉な現実があります。パキスタンの都市シアールコートで起きたサッカーボール産業の物語は、その複雑な実態を突きつけます[1]。この地域は世界のサッカーボール生産の一大拠点でしたが、多くの子どもたちが縫製作業に従事するという問題が存在しました。
状況が動いたのは1990年代半ば、アメリカのテレビ局が児童労働の実態を告発する番組を放映したことです。貧しい子どもたちが先進国の子どもたちのためにボールを縫う映像は世界に衝撃を与え、大規模な抗議運動へと発展しました。これは、国際世論が形成され、特定の問題に光を当てる力を持つことを示す一例となりました。
厳しい批判に直面した大手スポーツブランドや業界団体は、国連児童基金(UNICEF)などの国際機関や非政府組織(NGO)と連携し、児童労働を撲滅するプロジェクトを立ち上げます。解決策は、生産体制の変更でした。それまで各家庭で行われていた縫製作業を、外部から監視できる「スティッチング・センター」という作業所にすべて移管するのです。これによって、子どもが働いていないことを客観的に証明し、製品の汚名をそそぐことが目指されました。
この改革プロセスで、問題は巧みに「児童労働」という一点に絞り込まれます。特定の論点に光が当たると、他の重要な事柄は影に追いやられます。例えば、労働者が直面していた低い賃金や、社会に根強い性別間の不平等といった課題は議論のテーブルに上りませんでした。何が「問題」として認識され、何が無視されるのか。その選択自体が見えない権力の働きを示しています。
決定的なのは、改革で人生を左右される現地の縫製労働者やその家族の声が、意思決定の場から排除されていたことです。彼ら彼女らは国際会議で使われる言語を話さず、意見を表明する手段も持っていませんでした。調査によれば、労働者が最も望んでいたのは、児童労働の即時禁止ではなく、家族が暮らしていける「生活できる賃金」でした。しかし、その願いが改革の主導者に届くことはありませんでした。
公式には、このプロジェクトは大成功と報告されています。実際に、シアールコートから輸出されるボールの大半が、児童労働を介さずに生産されるようになりました。しかし、その輝かしい成果の裏で、深刻な事態が進行していました。
改革の最大の犠牲者は、縫製労働者の大多数を占めていた女性たちでした。自宅での作業からセンターでの労働への移行は、彼女たちの生活を覆します。自宅であれば、家事や育児の合間に自分のペースで働くことができましたが、センターの画一的な労働環境は、その柔軟性を奪いました。
保守的な農村社会では、女性が家の外で働くことに社会的な偏見も伴いました。村人からの中傷を恐れ、センターで働くことをためらう女性も多く、様々な理由が重なり、改革以前に働いていた女性の多くが事実上の失業状態に追い込まれたのです。
女性や子どもたちが収入の機会を失ったことで、多くの家庭の収入は減りました。児童労働をなくすための改革が、皮肉にもその地域の家族をより一層の貧困へと突き落としたのです。
この事例は、一連の改革の動機が、子どもたちの人権を守るという目的以上に、スキャンダルで傷ついた企業のブランド価値を回復し、欧米の消費者が罪悪感なく商品を購入できるようにする「浄化」のプロセスであった側面を浮かび上がらせます。その過程で、最も弱い立場にいた女性たちが最大の代償を払いました。
言説・物質・組織を組み合わせた戦略で権力を行使する
先ほどは、大義を掲げた改革が意図せず悲劇を招いた事例を見ました。そこでは問題の捉え方自体が権力によって規定され、声なき人々が犠牲となりました。変革を目指す人々が、より意識的に権力を行使する場合には、どのような手法が用いられるのでしょうか。社会という複雑なシステムを動かすには理想論だけでは不十分であり、状況を多角的に分析し、様々な要素を組み合わせる戦略性が求められます。
社会構造を「物質的」「言説的」「組織的」という三つの次元が絡み合ったものとして捉える視点があります。「物質的次元」とは技術や市場、資本といった経済活動の土台です。「言説的次元」とは価値観を形作る言葉や物語、正当化の論理を指します。「組織的次元」とは業界団体や政府、企業といった社会を動かすプレイヤーや制度です。
社会の安定は、これら三次元が調和し、一つの支配的な秩序を形成している状態だと言えます。社会変革とは、この組み合わせを解きほぐし、再構築する試みです。この困難な課題に挑む変革の担い手は、長期的な「陣地戦」と短期的な「機動戦」を使い分ける、「近代の君主」のような戦略家として描かれます。
この戦略的な権力行使の姿を、後天性免疫不全症候群(AIDS)の治療薬へのアクセスをめぐる国際的な闘いに見ることができます[2]。かつて、高額な薬価と特許制度が壁となり、有効な治療薬は開発途上国の多くの患者にとって手の届かない存在でした。この状況を打破するため、患者団体やNGOなどが連携し、巨大な製薬企業やそれを支持する先進国政府に挑みました。
彼ら彼女らの戦略は、三つの次元を組み合わせたものでした。「言説戦略」として、この問題を「医療のアパルトヘイト」と呼び、強烈な道徳的不正義を訴えました。この言葉は世論に強く響き、問題の緊急性を人々の心に刻みます。「物質戦略」として、後発医薬品(ジェネリック)によって治療薬のコストを下げられる事実を突きつけ、人命より企業の利益を優先する特許制度の正当性を揺さぶりました。「組織戦略」として、闘いの舞台を専門的な会議の場からメディアや議会といった開かれたアリーナへと移し、多くの人々を巻き込んでいきました。
こうした挑戦に対し、製薬企業側も戦略的に応答します。薬価を部分的に引き下げる限定的な譲歩(物質的対応)や、企業の社会的責任を強調する言葉の採用(言説的対応)、挑戦者側の一部を対話のテーブルに着かせる(組織的対応)ことで、急進的な要求をかわし、秩序の根幹を維持しようと試みました。
この事例が示すのは、社会変革が単純な善悪の対決や一方的な勝利で終わることは稀だという事実です。挑戦者と守護者の双方が、複数の次元で戦略を駆使してせめぎ合い、その結果、部分的な改革と既存構造の温存が同時に起こる「交渉された秩序」が生まれます。変革の成否を評価するには、目に見える成果だけでなく、社会の構造を支える地形を、長期的にどれだけ組み替えられたかという視点が求められます。
対立する陣営の「橋渡し役」となることで変革を導く
先ほどは、対立する陣営が戦略をぶつけ合う攻防の様子を見ました。しかし、変革への道筋はそれだけではありません。敵対する者たちの間にあえて身を置き、双方の言葉を翻訳し、信頼関係を築くことで、新たな秩序を生み出すアプローチも存在します。ここでは、対立を乗り越えるための「橋渡し役」の役割に焦点を当てます。
新しい技術や社会問題が登場したばかりの「新興フィールド」では、確立されたルールや権威が存在せず、すべてが手探りの状態です。このような不確実性の高い状況は、対立を激化させやすい一方で、新たな協力関係を築く好機も眠っています。
カナダにおける後天性免疫不全症候群(HIV/AIDS)の治療薬開発をめぐる、製薬企業と患者コミュニティの関係構築の歴史は、この「橋渡し」のプロセスを描き出しています[3]。1990年代、新薬開発をめぐり、開発を急ぐ製薬企業と、命のかかった患者コミュニティとの間には深い溝と不信感が存在しました。
この状況を変えたのは、両者の間に立つユニークな「立ち位置(サブジェクト・ポジション)」を築いた数人の制度的企業家でした。彼ら彼女らはHIV陽性という当事者であり、治療の専門知識を持つことで、患者コミュニティから絶大な信頼を得ていました。同時に、製薬企業に対しても敵対ではなく対話と協調の姿勢を明確にし、企業の論理にも理解を示しました。この「コミュニティの代弁者」と「企業との協調者」という二つの顔を併せ持つ稀有な立ち位置が、変革の基盤となったのです。
このポジションを確立した上で、彼ら彼女らは新しい協力の仕組みを築くため、説得と政治交渉を組み合わせた「理論化」を進めました。その中心は、製薬企業と患者コミュニティの代表が定期的に協議する、中央集権的な組織の設立構想です。
構想実現のため、彼ら彼女らはまず「説得」を用いました。その際、相手の立場や利害に合わせ、それぞれに響く複数の論拠(言説の束)を用意しました。患者には「交渉の負担が減り、治療に専念できる」と説き、企業には「窓口が一本化され、時間とコストを削減できる」と訴えました。
しかし、説得だけでは乗り越えられない利害対立には「政治交渉」を駆使しました。新しい協議会の代表枠を配分するなど、具体的な交渉を通じて、潜在的な反対勢力をあらかじめ仕組みの内側に取り込み、後から批判が出にくい安定した協力体制を築きました。
こうして生まれた新しい関係を永続的な「当たり前」として定着させる「制度化」も周到に行われました。企業の臨床試験設計や行政の薬事承認プロセスといった既存の日常業務の中に、患者コミュニティとの協議を「必ず通る関門」として組み込んだのです。この新しい仕組みが、各関係者の重視する価値観とも結びついていることを繰り返し強調しました。
このように、新興フィールドの変革は、対立する陣営の間に立ち、双方から信頼される「橋渡し役」を担うことから始まります。多角的な説得と巧みな政治交渉で協力の枠組みを作り、それを既存の業務プロセスに接続することで、新たな秩序は社会に根づいていくのです。
曖昧なものを「測定」する基準を作り権力を握る
これまでのところでは、目に見えやすい変革のプロセスを追ってきました。しかし、権力の行使には、より静かで、私たちの認識の根幹に働きかける形態が存在します。それは、世界の「見方」を規定する力、すなわち「測る力」です。ここでは、曖昧なものに「測定」という基準を与える行為が、いかに強力な権力の源泉となるのかを解き明かします。
「企業の社会的責任」という言葉を考えてみましょう。従業員を大切にし、環境に配慮する。理念には賛同できても、それをどう評価すればよいのか。A社とB社、どちらがより責任を果たしているか。この問いに答えるのは困難です。共通の物差しが存在しないからです。
何かを「測る」という行為は、客観的な記録作業ではありません。複雑な現実から特定の側面を抽出し、価値を与える一方で、他の側面を切り捨てる選択的な営みです。測定の基準が確立されると、それは私たちの思考の枠組みを形作ります。何が重要かという前提を規定するのです。
この「測定の力」が顕著に現れたのが、フランスで生まれた「社会的責任投資(SRI)」という産業の事例です[4]。SRIとは、財務情報だけでなく、環境や社会、企業統治といった非財務的な側面も評価して投資先を選別する手法です。
1990年代後半、この新しい投資手法は大きな壁に直面していました。根幹となる「企業の社会的パフォーマンス」という概念が曖昧で、金融業界から「信頼性に欠ける」と見なされていたのです。新興産業は、このように社会的な信頼、すなわち「正統性」を獲得できなければ成長できません。
この状況を打開したのが、「ARESE」という社会的格付け機関でした。ARESEは、誰も形にできなかった「企業の社会的パフォーマンス」を測定する独自の評価ツールを開発しました。企業の活動を複数のカテゴリーに分類し、詳細な項目に基づき点数化し、ランク付けするという定量的なアプローチでした。
この戦略は成果を収めました。第一に、SRI産業に「正統性」を与えました。客観性と数量化を重んじる金融業界の文化に、ARESEのツールは合致しました。これによって、SRIのファンドマネージャーは、自分たちの活動が金融業界の言語で説明可能な「信頼できる」投資手法だと証明できるようになりました。
第二に、ARESE自身の正統性と権力を確立しました。ARESEは、顧客の仕事のやり方に寄り添い、評価ツールを急速に業界内に浸透させました。ツールが業界の「標準」となるにつれ、より深く構造的な力が働き始めます。多くのファンドマネージャーが、ARESEの評価基準を「企業の社会的責任」と認識するようになり、投資先の選別もその評価に依存するようになりました。
最終的に、市場の大多数がARESEの評価を利用するようになると、ARESEはこの産業における「社会的責任」とは何かを定義し、管理する事実上の独占的な地位を築きました。誰かに直接命令するわけではないのに、業界全体の行動や思考を方向づける。これは、目に見えにくいために抵抗も難しい、強力な「システミック・パワー」と呼ばれる権力です。曖昧な概念に「測定」という形を与える戦略は、新しい活動に信頼をもたらす一方で、その基準を設定した者に、人々の認識を形作る絶大な権力を与えます。
脚注
[1] Khan, F. R., Munir, K. A., and Willmott, H. (2007). A dark side of institutional entrepreneurship: Soccer balls, child labour and postcolonial impoverishment. Organization Studies, 28(7), 1055-1077.
[2] Levy, D., and Scully, M. A. (2007). The institutional entrepreneur as modern prince: The strategic face of power in contested fields. Organization Studies, 28(7), 971-991.
[3] Maguire, S., Hardy, C., and Lawrence, T. B. (2004). Institutional entrepreneurship in emerging fields: HIV/AIDS treatment advocacy in Canada. Academy of Management Journal, 47(5), 657-679.
[4] Dejean, F., Gond, J.-P., & Leca, B. (2004). Measuring the unmeasured: An institutional entrepreneur’s strategy in an emerging industry. Human Relations, 57(6), 741-764.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。