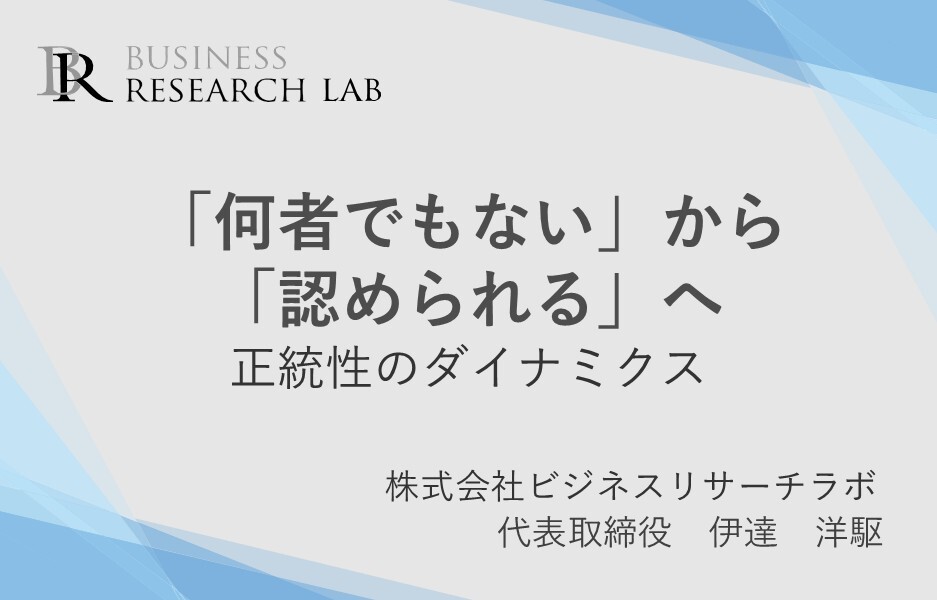2026年1月9日
「何者でもない」から「認められる」へ:正統性のダイナミクス
新しい商品や職場に新たに着任したリーダーに対し、私たちはどこか半信半疑な目を向けることがあります。実績も評判もまだ固まっていないからです。そのような「何者でもない」状態から、一つの存在は、いかに社会の中で「信頼できる、当たり前の存在」へと変わるのでしょうか。その鍵を握るのが「正統性」という、目には見えない力です。
正統性とは、ある存在が、社会の価値観や規範に照らして「望ましく、適切で、正当である」と広く認知されている状態を指します。この認知を得ることで、組織は活動に必要な資源を集めやすくなり、人々からの協力を得て物事を前に進められます。それは社会から「お墨付き」をもらうようなものです。
しかし、この「お墨付き」は自然に与えられるものではありません。そこには、コミュニケーションや行動の積み重ね、時には既存の価値観との交渉といったプロセスが存在します。本コラムでは、新しい組織や考え方が社会に「認められる」までのプロセスを検討していきます。事業が「物語」で存在意義を訴える過程、「勝利」が信頼の証となる仕組み、「言葉」で常識を変えようとする試み、「分類」からはみ出すことの厳しい現実。これらの探求を通じ、私たちの身近にある「認められる」という現象の裏にある力学に迫ります。
起業家の物語が、新規事業のアイデンティティと正統性を構築する
新しい事業を始める起業家が直面する大きな壁は、信頼の欠如です。実績のない状況で、投資家、人材、顧客の支持を得るのは容易ではありません。この不確実性を乗り越える道具が「物語」です。
新しい事業の正統性獲得における物語の機能を分析した試みがあります[1]。そこでは、事業の成功は、資源獲得や戦略だけでなく、物語を語るという文化的な活動に左右されると捉えられています。物語は、事業の「アイデンティティ」、すなわち「私たちは何者か」という自己認識を形作り、それが社会に受け入れられることで正統性が生まれ、資源獲得につながるという循環が描かれます。物語は、起業家が持つ資源と、業界の常識やルールとを結びつけ、意味のある活動として社会に提示するのです。
どのような物語が信頼を勝ち取るのでしょうか。物語は聴衆の価値観や信条に訴えかけ、「もっともらしい」と感じさせる「ナラティブの忠実性」を持つ必要があります。その上で、語る内容は二つの方向性をバランス良く含むべきです。一つは、事業がいかに「ユニーク」で他にはない価値を持つかを強調する方向。もう一つは、既存の業界ルールやカテゴリーにいかに「適合」しているかをアピールする方向です。この「独自性」と「適合性」のバランスを状況に応じて見極めることが鍵となります。
物語の説得力は、起業家が持つ資源によって高まります。特許や資格、技術、人脈といった資産は物語の核心的な素材です。特に三つの要素が機能します。第一に、中立的な第三者機関からの認証や受賞歴。第二に、社会的に評価の高い人物や組織とのつながり。第三に、起業家自身の過去の成功実績です。これらは、事業が有望であることのシグナルとして働きます。ある著名なハイテク起業家は、新しい会社の立ち上げに際し、有名なベンチャーキャピタルや一流企業の名前を物語に織り交ぜ、まだ実績のない会社の信頼性を高めて巨額の資金調達に成功しました。
物語の戦略は、参入する業界の成熟度に応じた調整も求められます。例えば、ミューチュアルファンドのような新しい金融商品が生まれた黎明期には、個別の商品の優位性よりも、「株式を共同所有すること自体の価値」といった、産業の正統性を社会に訴える物語が有効でした。市場全体の理解と受容を育てることが先決だったからです。一方で、パーソナルコンピュータのように競合がひしめく成熟市場では、ある企業が「世界を変える」という壮大なビジョンを掲げ、既存の常識を覆す独自性を訴える物語で多くの資源を引き寄せました。
結局のところ、新しい事業が正統性を得るプロセスは、「他とどう違うのか」と「他といかに同じなのか」という問いに、信頼のシグナルをちりばめた説得力ある物語として答え続けることと言えます。
自動車産業の黎明期、レース勝利が企業の正統性を構築した
先ほどは、新しい事業が「物語」の力で社会的な信頼を勝ち取る過程を見ました。しかし人々は次に、物語が夢物語ではないという「証拠」を求めます。そこで、具体的な行動や成果が、いかに組織の正統性を確固たるものにするかを探ります。その舞台は、社会のルールや評価基準が未整備だった、ある産業の黎明期です[2]。
企業の評判がどう形作られるかを解明する中で、「認定コンテスト」という仕組みが分析されました。これは第三者が企業や製品を評価し、順位付けする競争です。現代のレストラン格付けなどがこれにあたります。このようなコンテストが、組織の正統性を確立し、良い評判を築く上で決定的な働きをすることがあります。
分析対象は、19世紀末から20世紀初頭のアメリカ自動車産業です。当時は自動車という技術自体が新しく、品質基準も確立されていませんでした。数多くのメーカーが乱立し、市場は混沌としており、消費者が信頼できる車を見分けるのは至難の業でした。このような状況下で、自動車愛好家やメディアが主催する、耐久性や速さを競うコンテストが数多く開催されました。専門的な評価機関がなかった当時、これらは事実上の「製品認定機関」として機能し、勝利は技術力を社会に証明する絶好の機会となったのです。
コンテストでの勝利は、いくつかの仕組みを通じて企業の正統性を構築します。第一に、それは認知的な妥当性を与えます。「勝者は敗者よりも優れている」という分かりやすい論理で、企業の能力が証明されます。
第二に、参加組織の間に地位の階層を作り出します。一度「勝者」という高い地位を得ると、その後も有利な立場を享受しやすくなる「マタイ効果」が働きます。
第三に、自己強化的なプロセスを引き起こします。レースでの勝利という出来事が、リスクを避けたい消費者や投資家の信頼を集め、それがさらに評判を高めて企業の存続可能性を上げるという好循環を生みます。
これらの考えに基づき、「コンテストでの勝利を重ねた企業ほど、倒産する確率は低くなる」という仮説が立てられました。この仮説を検証するため、1895年から1912年までのコンテスト優勝記録と、同期間の全自動車メーカーの存続データが収集され、統計的に分析されました。
分析の結果は仮説を裏付けました。コンテストでの累積勝利数が多い企業ほど、倒産する確率が有意に低いことが確認されたのです。この関係は、企業の設立形態や技術の種類といった他の要因を考慮しても揺るぎないものでした。混沌とした市場の中で、レースでの勝利が企業の能力を証明するシグナルとして機能し、その存続に結びついていたという事実です。物語を語るだけでなく、それを裏付ける具体的な勝利を手にすることが、不確実な時代を生き抜くため、もう一つの道筋でした。
新組織の正統性は、変化をめぐる説得的な言説の競争で決まる
「物語」を語り、「勝利」で実績を示す。これらは自らの価値を社会にアピールするプロセスです。しかし、新しい存在が社会に深く根付いた既存のルールや常識と衝突する場合、正統性の獲得は、どちらが「正しい」のかをめぐる、言葉と言葉の闘い、すなわち「言説(レトリック)の競争」という様相を呈します。
この言説の競争が、いかに新しい組織形態の正統性を左右するのかを解き明かした分析があります[3]。舞台は1990年代後半、大手会計事務所が法律事務所を買収して生まれた「多職種統合組織(MDP)」をめぐる論争です。会計と法律という、高度な専門性と倫理を持つプロフェッションの統合という前例のない試みは、社会に大きな波紋を広げました。
この分析は、賛成派と反対派の主張を、社会の根本的な価値観、すなわち「プロフェッションとはどうあるべきか」という制度の論理を、言葉の力で自らに有利に再定義しようとする戦略的な試みとして捉えました。分析の対象は、公聴会の議事録など1300ページを超える公式記録です。
分析から、両者が用いる「言葉の武器庫」の違いが浮かび上がりました。賛成派(会計事務所など)は、「消費者の利益」「ワンストップ・ショッピング」「効率性」といった言葉を多用し、顧客の便益を強調して市場の論理で正当化しようとしました。一方、反対派(弁護士会など)は、「中核的価値」「職業倫理」「公共の利益」「独立性」といった言葉を前面に出し、会計監査人の客観性と弁護士の依頼人への義務は両立し得ないと主張。この統合がプロフェッションの道徳的な基盤を揺るがすと訴えました。
両者の対立は、この変化そのものをどう語るかにも現れていました。分析から、変化を語る典型的な「変化の理論化」が特定されました。
反対派は、二つのものが本質的に両立不可能だと主張する「存在論的」な語りや、過去からの伝統や連続性を持ち出して急進的な変化を戒める「歴史的」な語りを多用しました。一方、賛成派は、将来の危機回避のためには改革が必要だと訴える「目的論的」な語りや、変化を「グローバル化」のような誰も抗えない時代の必然として描く「宇宙論的」な語りを用いました。両者とも、善悪といった道徳評価に直接訴える「価値基盤型」の語りを駆使し、どちらの価値が社会にとって優先されるべきかを争いました。
このように、正統性をめぐる争いは、どのような「言葉」を選び、どのような「変化の物語」を構築するかの競争です。この事例が明らかにするのは、新しい組織や制度が社会に受け入れられるプロセスが、支配的な価値観や常識をめぐる、高度に政治的で言語的な闘争であるという事実です。正統性の獲得とは、時に、社会が何を「適切」と見なすか、その判断基準自体を言葉の力で書き換えていく試みでもあります。
カテゴリーが曖昧だと正統性を欠き、株価が不当に割引される
これまでの努力はすべて、社会の中で自らの確固たる「居場所」を確保するためのものです。もし組織がこの「居場所」を明確に示すことに失敗したら何が起こるのでしょうか。ここでは、社会が用意した「分類(カテゴリー)」の枠組みにうまく収まらないことがもたらす厳しい結果を、株式市場を舞台に見ていきます。
私たちの社会は、企業を産業で区分けするなど、無数のカテゴリーで成り立っています。この分類は、複雑な世界を理解し評価するための精神的な近道であり、社会の構成員は、確立されたカテゴリーに自らを適合させるよう無言の圧力を受けます。どのカテゴリーにも属さない曖昧な存在は、他者から正しく理解されず、評価の対象から外されてしまうからです。
この力学を証券市場で実証的に分析した研究があります[4]。中心的な主張は、市場参加者から「何屋なのかが分かりにくい」と見なされた企業は、実力とは無関係に、株価が不当に低く評価される「非正統性の割引」というペナルティを受けるというものです。この理論を検証する鍵が、証券アナリストです。アナリストは特定の産業を専門とする「批評家」であり、その分析レポートの対象となることは、企業がその産業カテゴリーの「正統な一員」として公に認められたことを意味します。
逆に、企業が主張する事業内容と、実際にその企業をカバーするアナリストの専門分野がずれている「カバレッジのミスマッチ」が生じている場合、その企業のアイデンティティは市場で混乱していると見なされます。このような企業は、投資家の信頼を得にくく、株価が本来の価値より割り引かれてしまう、というのがこの分析の仮説です。
この仮説を検証するため、1985年から1994年までのアメリカ上場企業を対象に、企業の財務・株価データと、どのアナリストがどの企業をカバーしているかのデータが分析されました。各企業について、株価が理論値と比べてどう評価されているかを示す「超過価値」と、「カバレッジのミスマッチ」の度合いが測定されました。
分析結果は仮説を裏付けました。カバレッジのミスマッチが大きい、すなわち「何屋なのか」が曖昧な企業ほど、株価が統計的に有意に低く評価される「非正統性の割引」を受けていました。このペナルティは、企業の実際の業績とは独立して存在していました。ある多角化企業の事例では、ミスマッチが解消されれば企業価値が数億ドル増加する可能性が試算されており、この割引の現実的な大きさが分かります。
この結果が示すのは、市場がいかに社会的な分類の論理に縛られているかという事実です。企業が自らをどう認識しているかではなく、市場の評価者たちがどう分類するかが、企業の価値に影響を及ぼします。社会で正統な存在として認められるには、自らのアイデンティティを明確に定義し、それが他者からも同じように認識されるよう働きかけることが、現実的な意味で大切なのです。
脚注
[1] Lounsbury, M., and Glynn, M. A. (2001). Cultural entrepreneurship: Stories, legitimacy, and the acquisition of resources. Strategic Management Journal, 22(6?7), 545-564.
[2] Rao, H. (1994). The social construction of reputation: Certification contests, legitimation, and the survival of organizations in the American automobile industry: 1895-1912. Strategic Management Journal, 15(S1), 29-44.
[3] Suddaby, R., and Greenwood, R. (2005). Rhetorical strategies of legitimacy. Administrative Science Quarterly, 50(1), 35-67.
[4] Zuckerman, E. W. (1999). The Categorical Imperative: Securities Analysts and the Illegitimacy Discount. American Journal of Sociology, 104(5), 1398-1438.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。