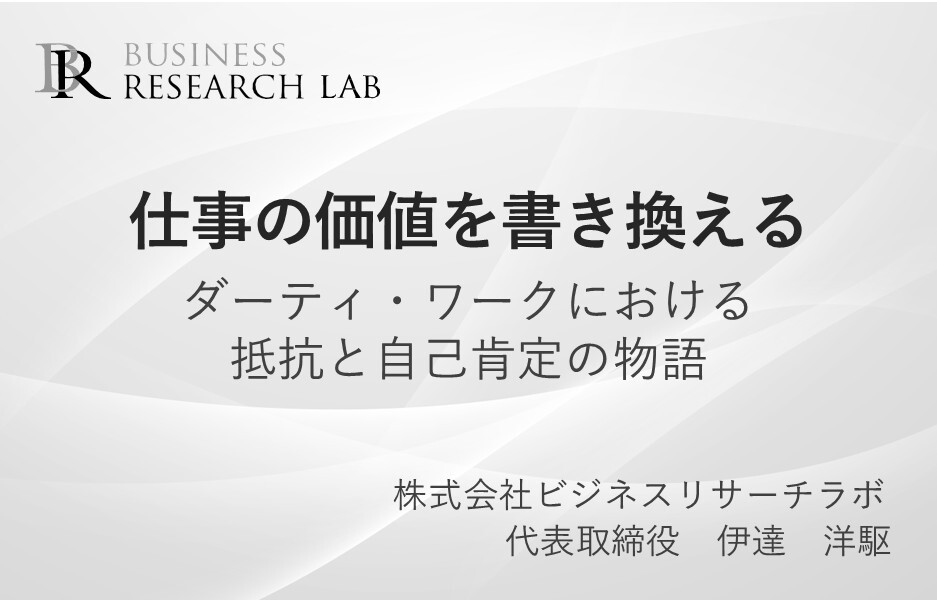2026年1月7日
仕事の価値を書き換える:ダーティ・ワークにおける抵抗と自己肯定の物語
私たちの社会は、無数の仕事によって成り立っています。その中には、多くの人が憧れを抱くような仕事もあれば、一方で、社会から時に敬遠されながらも、その営みを維持するためには欠かせない仕事も存在します。そうした仕事は、時に「ダーティ・ワーク」と呼ばれます。この「汚れ」という言葉が指し示すのは、物理的な不潔さではありません。社会的に低い地位にあると見なされたり、道徳的に好ましくないと考えられたりすることも、一種の「汚れ」として人々の心に映ります。
社会に不可欠でありながら、敬遠されがちなこれらの仕事。そこに従事する人々は、自らの仕事と、自分自身と、どのように向き合っているのでしょうか。外部から向けられる否定的なまなざしを、どう乗り越えようとしているのでしょうか。この問いを探求していくと、単に特定の職業の話に留まらない、より一般的なテーマに行き着きます。それは、人がいかにして仕事に意味を見出し、自らの尊厳を保つのかという問いです。
本コラムでは、ダーティ・ワークをめぐるいくつかの研究を手がかりに、この複雑な現象に光を当てていきます。特に、社会に根強く存在する「男らしさ」といったジェンダーの規範が、仕事の経験とどのように結びついているのかを見ていきます。人々は、社会的な規範を利用して仕事の価値を再定義し、時にはそれを「誇り」や「勲章」へと転換させます。しかしその一方で、その規範が新たな葛藤を生み出すこともあります。
ダーティ・ワークの世界を覗き見ることは、私たちが普段意識することのない、仕事と社会、人間の尊厳をめぐる複雑な関係性を映し出すこととなるでしょう。
汚れの種類で、非人間化のされ方が決まる
ダーティ・ワークと聞くと、私たちは漠然と「汚い」「きつい」といったイメージを思い浮かべるかもしれません。しかし、その「汚れ」の内実は、決して一枚岩ではありません。物理的に汚れている仕事、社会的に地位が低いとされる仕事、道徳的に問題があると見なされる仕事。これらの性質の違いは、その仕事に従事する人々に対する社会のまなざしを、質的に異なる方向へと導くことが分かっています。
イタリアで行われた研究は、この問題を掘り下げました[1]。関心の中心は、ダーティ・ワークが持つ三つの汚れの側面、すなわち「身体的な汚れ」「社会的な汚れ」「道徳的な汚れ」が、それぞれどのような形で働く人々を人間的でないものとして捉える認識、いわゆる「非人間化」と結びつくのかを明らかにすることでした。
予備的な調査として、大学生たちに「汚いと感じる職業」を自由に挙げてもらい、頻繁に名前が挙がった27の職業をリストアップしました。次に行われた本調査では、別の大学生たちが、この27職種の中からランダムに選ばれた職業について評価を求められます。その際、「あなた個人の考え」ではなく、「イタリア社会一般では、これらの職業がどのように見なされているか」という視点で回答するように指示されました。これは、回答者が社会的に望ましい意見に流されるのを避け、より率直な社会的イメージを捉えるための工夫でした。
評価項目は主に二つです。一つは、それぞれの職業が三種類の汚れをどの程度伴うかと見なされているかの評定。もう一つは、三種類の非人間化の度合いを測る評定でした。具体的には、働く人々が「ウイルス」や「汚染」といった言葉で連想されるか(生物学化)、「道具」や「物体」といった言葉で連想されるか(物化)、「動物」や「獣」といった言葉で連想されるか(動物化)を、それぞれ評定してもらいました。
分析の結果、27の職業はその汚れの特性によって、きれいな四つのグループに分類されました。一つは身体的な汚れが突出して高いグループ。二つ目は社会的な汚れ(従属性)が高いグループ。三つ目は道徳的な汚れが高いグループでした。四つ目は三種類すべての汚れが極めて高い、特異なクラスターとして浮かび上がりました。
この研究の中心的な発見は、これらの汚れのタイプと、非人間化のタイプとの間に対応関係が見られたことでした。身体的な汚れが強いと見なされている職業グループは、働く人々を「ウイルス」や「汚染」といった生物学的なメタファーで捉える認識が、他のグループに比べて高かったのです。同様に、社会的な汚れが強い職業グループでは、「道具」や「物体」として捉える「物化」の認識が、道徳的な汚れが強い職業グループでは、「動物」や「獣」として捉える「動物化」の認識が、それぞれ最も高くなっていました。
この結果から考えられるのは、人々が無意識のうちに、汚れの性質とその源泉を結びつけて、働く人のイメージを構築しているということです。例えば、身体的な汚れを扱う仕事は、人々に感染への恐怖を想起させ、働く人そのものをウイルスのような存在として見るまなざしにつながるのかもしれません。一方で、他者の指示に従わなければならない社会的な従属性は、その人が自己の意思を持たない「道具」であるかのような認識を助長する可能性があります。
不正な手段を用いると見なされる仕事は、人間性の核とされる道徳性の欠如と結びつけられ、理性のない「動物」のような存在として描かれることにつながるのでしょう。
ダーティ・ワークは男らしさで「勲章」に転換される
ダーティ・ワークに従事する人々は、その仕事の性質に応じて、社会から様々な否定的なまなざしを向けられることがあります。しかし、働く人々はそうしたスティグマにただ耐えているわけではありません。自らの経験に新たな意味を与え、仕事の価値を書き換えることで、尊厳を保とうとします。その際、社会的に共有された「男らしさ」という観念が資源となることがあります。過酷な経験が、そのフィルターを通すことで、誇るべき「勲章」へと転換されるのです。
カナダの総合病院で働く男性警備員の日常を描き出した研究は、このプロセスを捉えています[2]。研究者の一人が、調査対象である病院でかつて警備員として勤務していたため、元同僚へのインタビューに加え、研究者自身の経験を記述するオートエスノグラフィという手法が用いられ、現場の生々しい感覚が伝えられています。
病院の警備には、二種類の主要な「汚れ」が伴います。一つは、遺体や血液に直接触れる身体的な汚れ。もう一つは、医療専門職の指示に従わなければならない、組織内での従属的な立ち位置から生じる社会的な汚れです。警備員たちは、これらの汚れを「男らしさ」という文化的な資源を駆使して管理し、乗り越えていきます。
例えば、研究者自身の経験として、勤務して間もない頃に遺体と対面する場面が描かれています。病理解剖室で遺体から角膜を摘出する処置に立ち会った新人警備員は、内心動揺します。しかし、そばにいる先輩警備員の「どうだ?」という問いかける視線に晒される中で、弱さを見せることは許されません。平静を装い、冗談めかしてその場を乗り切ります。
この経験は、嫌悪や恐怖といった感情を表に出さず、死を冷静に受け止められるかを試される「テスト」として機能します。このテストを通過したと見なされることで、彼は集団の中で一人前の警備員、そして規範的な意味での「男」として認められていきます。ここでは、死との対峙が、度胸の証、すなわち「男らしさの証明」へと意味を転換されています。
インタビューからは、他の警備員たちも同様の語りの戦略を用いていることが分かります。遺体に触れた経験を、「平気だった」「興味深かった」と語ります。このように、本来であれば嫌悪の対象となる経験を、無感情や好奇心といった肯定的な価値へと再定義するのです。こうした語りを通じて、仕事の過酷さは「男らしさのバッジ」へと昇華されます。
この文化の中では、嘔吐などの反応を示してしまう同僚は、暗黙のうちに「弱い」「女性的」と見なされ、集団内での地位が下がります。身体的な汚れをいかに処理できるかが、男性警備員たちの間での序列を決定づける基準となっています。
しかし、この「男らしさ」の物語は、常にうまく機能するわけではありません。当初は「慣れた」と冷静に語っていた警備員も、インタビューが深まるにつれて、その語りに亀裂が生じ始めます。特に、幼い子どもの遺体を扱った経験などを語る時、彼らの言葉には、抑えきれない動揺や無力感が滲み出ます。「自分でなくてよかった」という防衛的な感情や、やりきれない思いが、強靭さを装う物語の裏側から漏れ出してくるのです。
これは、感情を麻痺させて「平気」を装う行為が、決して無償ではないことを示しています。その裏では、精神的なコストが静かに蓄積されているのです。
ダーティ・ワークの男らしさは、誇りであると同時に人を縛る錨
「男らしさ」の規範は、ダーティ・ワークの否定的な側面を乗り越え、仕事への誇りを生み出す装置となり得ます。身体的な困難に耐えることを「男らしい」と価値づけることで、人々は仕事に肯定的な意味を見出せます。しかし、その誇りが、逆説的にも人々をより困難な状況に留め、変化の可能性を閉ざしてしまう「錨」として機能することはないのでしょうか。この「男らしさ」が持つ二面性を、英国のごみ収集員と街路清掃員を対象とした研究は浮き彫りにしています[3]。
この研究が行われた英国の地方自治体では、清掃サービスの民営化の結果、労働者の賃金は低下し、雇用は不安定になっていました。研究者たちは、こうした厳しい状況に置かれた清掃作業員たちの職場に身を置き、実際に作業に同行しながら、彼らの日常を観察し、インタビューを行いました。
調査に参加した作業員の多くは、自らを「労働者階級」と位置づけ、オフィスで働く人々と自身が置かれた社会構造上の違いを認識していました。こうした階級的な劣位性と、ごみを扱うという仕事のスティグマ。この二重の負荷に対抗するため、彼らが拠り所としたのが、伝統的な「男らしさ」でした。
彼らは、身体的な強靭さや持久力を誇り、厳しい肉体労働に耐え抜くこと自体に価値を見出していました。また、家族を養う「稼ぎ手」としての責務を果たすことに、強い自負心を抱いていました。家族を支えるという倫理が、彼らの自己評価を支える中心的な柱となっていたのです。
さらに、彼らは自らの価値を高めるために、他者との比較という手法を用いていました。例えば、「この仕事は女性には向かない」とか、「ホワイトカラーの人間なら、二時間ももたないだろう」といった語りです。こうした比較を通じて、身体的な強靭さという独自の価値基準を打ち立て、その基準において自分たちが優位にあることを確認し、自尊心を保っていました。このように、「男らしさ」の実践は、彼らが階級的・職業的なスティグマに抗い、尊厳を維持するための抵抗の戦略となっていたのです。
しかし、この研究が明らかにしたのは、その抵抗の戦略が持つ逆説的な側面でした。彼らが抱く現在の厳しい労働環境への不満は、しばしば「昔は良かった」というノスタルジックな語りへとつながっていきます。労働組合の力が強かった過去を懐かしむことで、現在の不安定さへの批判が表明されます。ですが、この「古き良き男らしい労働者の世界」への憧憬と、身体労働への強いこだわりは、結果的に彼らを現在の低賃金で不安定な労働市場に縛り付けることになります。
身体的な強さを誇り、「男らしく」働き続けることに固執するがゆえに、他のキャリアの可能性を探ったり、現状を構造的に変えるための行動を起こしたりすることが困難になるということです。自尊心の源泉であったはずの「男らしさ」が、皮肉にも、彼らを劣位な状況から抜け出させなくする重い「錨」としても機能してしまっている。この研究が描き出したのは、抵抗の資源が、同時に自らを拘束する檻にもなりうるという、ダーティ・ワークを生きる人々の複雑な現実でした。
警察は「公務」と語ることで、個人の責任を回避する
ダーティ・ワークの中には、物理的な不潔さや社会的な低位性とは異なる、道徳的な曖昧さという「汚れ」を伴うものが存在します。人々の自由を奪い、時には物理的な力を行使する警察官の仕事は、その典型例と言えるでしょう。社会の秩序を維持するために不可欠な行為でありながら、それは常に権力の乱用といった道徳的な非難と隣り合わせです。このような状況で、警察官は、自らの行為をどのように理解し、他者にどう説明するのでしょうか。
この問いを探求した英国の研究は、警察官が研究者とのインタビューという、いわば「公的な舞台」で、強制力の行使というデリケートなテーマについてどのように語るのかを分析しました[4]。ここでの着眼点は、同僚同士で内輪話をするような「楽屋裏」での語りとは異なり、外部の批判的なまなざしを意識した際に、どのような言葉の戦略が用いられるかという点です。
分析から浮かび上がってきたのは、警察官たちの語りに共通する、「責任の再配置」でした。彼ら彼女らは、強制力の行使を、決して「自分個人の意思や感情」に基づいて行っているのではないと強調します。その代わりに、その行為の源泉を、自分という個人を超えた、より大きく正当な存在、すなわち「組織」「国家」「社会」といったものに帰属させるのです。これによって、行為に伴う道徳的な責任は、個人から切り離され、公的な制度へと転移されます。
この責任の再配置は、主に二つの異なる論理によって精緻化されていました。一つ目は、若手の女性の語りに見られます。彼女は、逮捕という行為が相手の自由を奪うものであることを認識しています。しかし、それは個人的な憎悪から行うのではなく、法によって「許可」された職務として遂行しているのだと語ります。逮捕という強制的な行為の後には、お茶を出すなど、相手を「人として扱う」配慮を欠かさないと強調します。
ここでの彼女の語りは、強制力の行使を、個人の感情から切り離された専門的な手続きとして描き出し、人道的な配慮を付け加えることで、その行為の道徳的な汚れを洗浄しようと試みています。
二つ目は、より経験を積んだ男性の語りから見出されます。彼は、強制力を行使する際に、自らを「私個人」としてではなく、「組織の権威の体現者」として位置づけます。そして、相手に対して「これは私があなたにしているのではない。あなた自身の行為が招いた結果であり、私は社会のためにこれを執行しているのだ」と伝えると語ります。
ここでの正当化は、単なる「許可」よりも強い、社会全体からの「付託」という論理に基づいています。行為の責任を相手自身に帰し、自らの行為を公共の善に奉仕するものとして位置づけることで、道徳的な正当性をより強固に確立しようとします。
これらの語りの戦略は、強制力の行使という、道徳的に非難されかねないダーティ・ワークを、個人の恣意的な暴力という領域から引き離し、「公務」という客観的で正当化された枠組みの中へと再配置する、洗練された言葉の技術です。
研究者という外部の視線に晒された「公的な舞台」において、彼ら彼女らは内輪で語られるような武勇伝ではなく、自由や権利、社会秩序といった公的な価値観に訴えかける言葉を選び、自らの行為を再翻訳してみせます。この言語的な実践を通じて、彼らは職務の道徳的な境界線を維持し、説明責任を果たそうとします。
脚注
[1] Valtorta, R. R., Baldissarri, C., Andrighetto, L., and Volpato, C. (2019). Dirty jobs and dehumanization of workers. British Journal of Social Psychology, 58(4), 955-970.
[2] Johnston, M. S., and Hodge, E. (2014). “Dirt, death and danger? I don’t recall any adverse reaction…”: Masculinity and the taint management of hospital private security work. Gender, Work & Organization, 21(6), 546-558.
[3] Slutskaya, N., Simpson, R., Hughes, J., Simpson, A., and Uygur, S. (2016). Masculinity and class in the context of dirty work. Gender, Work & Organization, 23(2), 165-182.
[4] Dick, P. (2005). Dirty work designations: How police officers account for their use of coercive force. Human Relations, 58(11), 1363-1390.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。