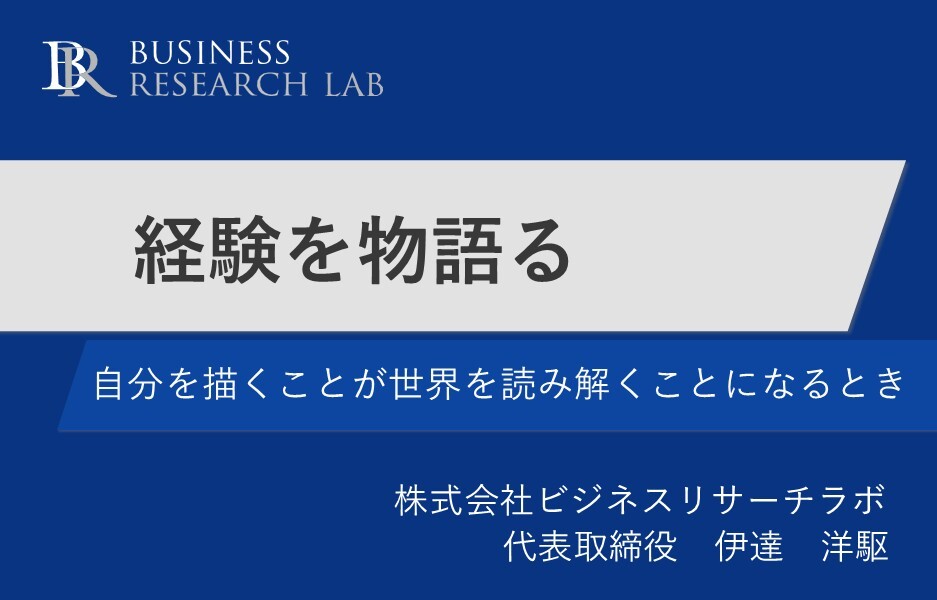2026年1月5日
経験を物語る:自分を描くことが世界を読み解くことになるとき
自分自身の経験に深く目を向けることで、社会や文化のありようを理解しようとすることがあります。そのようなアプローチがあるとしたら、何が見えてくるでしょうか。私たちは日々、組織の一員として、家族の一員として、あるいは専門家として、様々な出来事に遭遇し、感情を揺さぶられ、数々の決断を下しています。その個人的な体験の渦中で感じた喜び、葛藤、苦悩は、本人だけのものでありながら、実は同じような状況に置かれた多くの人々と通底する何かを宿しているのかもしれません。
オートエスノグラフィーとは、「自分自身の経験」を丹念に記述し、分析することで、より大きな社会や組織の動き、文化のありようを解き明かそうとする試みです。それは、客観的なデータや統計が描き出す世界とは少し異なり、生身の人間の息づかいや感情の機微、意思決定の裏側にある物語を浮かび上がらせます。
本コラムでは、このオートエスノグラフィーという視点から、多様な分野でどのような知見が得られているのかを探求していきます。学者の世界、リーダーの学習、家族経営の承継といった異なる舞台で、人々が自らの経験とどう向き合い、そこからいかに洞察を引き出していくのか。その実践の軌跡をたどってみましょう。
オートエスノグラフィーは学者の二重性を映す鏡
学問の世界に身を置く人々は、時に二つの自己の間で引き裂かれるような感覚を抱くことがあるかもしれません。一つは、純粋な知的好奇心に導かれ、真理の探究や社会への貢献を志す理想的な自己。もう一つは、業績評価や昇進、人脈形成といった現実的なキャリアの成功を追い求める自己です。ある研究では、二人のビジネススクール研究者が、この内なる二重性を、自らの学会参加経験を通して描き出しました[1]。
この探究のために、二人は対照的な二つの国際学会を舞台に設定しました。一つは、数千人が集う巨大な年次大会です。会場は豪華なホテルで、企業の採用面接や出版社のパーティーが公式プログラムに組み込まれ、多くの参加者がビジネススーツに身を包んでいます。そこは、学術的な議論の場であると同時に、キャリアを競う市場としての側面が色濃く漂う空間でした。
もう一つは、大学のキャンパスで開かれる、より小規模な学会です。参加者の服装は自由で、リラックスした雰囲気が流れ、採用活動のような催しはありません。そこでは、個人の経験に基づいた発表や、社会的な問題意識を共有する対話が中心となっていました。
二人はまず、それぞれの学会での経験を「第一の物語」として記述します。
小規模な学会に参加した一人は、人種差別という重いテーマを扱ったワークショップの経験を綴りました。参加者が自らの体験をパフォーマンスとして表現し、共有する過程で、深い共感と自己理解が生まれる様子を感動的に描いています。肩書や業績を離れた人間的な交流の中に、学問が本来持つべき理想の姿を見出したのです。一方、巨大な学会に参加したもう一人は、街の文化には魅了されつつも、学会自体には企業的で就職活動のような雰囲気を感じ、強い違和感を覚えたと記しました。
この「第一の物語」では、理想と現実、純粋さと世俗性という、分かりやすい二項対立の構図が提示されます。
しかし、この探究はここで終わりません。しばらく時間を置いた後、二人は同じ経験をまったく異なる視点から「第二の物語」として書き直します。
巨大な学会に疎外感を覚えていたはずの一人は、実はその場で有力な研究者と巧みに関係を築き、自身のキャリアにとって大きな糧を得ていたことを告白します。名刺交換やパーティーでの立ち振る舞いの一つひとつが、計算された戦略であったことを克明に記しました。理想的な場として描かれた小規模な学会に参加した一人もまた、その場が自身の研究の評価を高め、次の仕事につながる人脈を形成するための絶好の機会であったことを明かします。
批判的な立場を表明することさえ、学術的な世界で「名を上げる」ための自己演出として機能していた、というのです。
この二重の記述を通して、理想を語る自己の背後には、常にキャリアの成功を計算するもう一人の自己が存在することが浮かび上がります。そして、この自己暴露的な記述が、自分たちを「成功した学者」として見せる新たな演出になっていないか、という深い自己省察へと向かっていきます。学会での社交が、性別や価値観によって誰かを無意識に排除していないかという問いも立てられます。このように、個人の経験を異なる時間軸から二重に描き、相互に批判し合うことで、単なる自己満足的な告白に終わらない、分析的な視座が生まれるのです。
オートエスノグラフィーはリーダー学習を関係的実践として描く
先ほど見たように、個人の内なる葛藤を映し出すオートエスノグラフィーは、人が新しい立場に適応していく過程を解き明かす上でも力を発揮します。特に、組織のリーダーという役職に就いた人物が、いかにその役職を担うにふさわしい実践知を身につけていくのか。その学習のプロセスは、研修テキストを読むことや決められた手順を覚えることとは異なります。
ある研究では、企業の最高執行責任者(COO)に就任した実務家と研究者が協力し、就任後最初の数か月間の経験を詳細に記録することで、リーダーシップが「関係性の中での実践」として学ばれていく様子を明らかにしました[2]。
この物語の主人公は、厳しい経営環境にある企業で、突然COOへの就任を要請された人物です。彼は、危機的な状況の中で、リーダーとして振る舞うことを学びながら、同時にリーダーになっていくというプロセスに身を投じることになります。この研究が光を当てるのは、彼が経験した一連の具体的な出来事、いわばリーダーになるための「状況に応じたカリキュラム」です。
学習の旅は、一本の電話から始まります。それは、会社の今後を左右するような、きわめて機密性の高い人事情報を投資家から直接伝えられるという経験でした。この瞬間、彼は初めて経営の中枢にいる人々だけがアクセスできる情報の円の内側に入ります。情報を共有されることで信頼の証を得る一方で、誰に対してどこまで話すべきかという重い責任を負い、既存の人間関係との間で葛藤を覚えます。これは、リーダーとしての学習カリキュラムの最初の関門、すなわち「情報の扱い方」と「新たな人間関係の構築」を学ぶ場面でした。
その後、CEOとの会話では、それまでとは明らかに異なる、対等なパートナーとしての空気が生まれます。周囲の同僚との間にも微妙な距離感が生まれ、誰もが新しい関係性に慣れようと手探りを始めます。こうした日々のやり取りの中で、彼は「リーダーとして振る舞うこと」への自信を少しずつ深めていきます。
社内に不穏な噂が広がった際には、情報の透明性を保つべきだと主張する一方で、どの情報を開示し、どの情報を伏せるかという難しい判断を迫られます。現場の動揺を鎮めるために自ら動き、部下を励まし、時には叱責する。こうした行動を通して、周囲は彼をリーダーとして頼るようになり、彼の権威が形作られていくのです。
このプロセスで特に大きな学びとなったのは、新しくやってきた会長との初会談でした。彼は、会長の言葉遣い、笑顔、間の取り方といった細かな振る舞いを注意深く観察します。そして、既存のCEOとのやり方と比較することで、組織内の力学の変化や、これから求められるであろう新しいルールの存在を読み解いていきました。これは、他者の実践を間近で観察し、解釈し、自身の行動を微調整していくという、極めて高度な学習です。
これらのエピソードをたどることで見えてくるのは、リーダーの学習とは、個別のスキルを習得することではなく、絶えず変化する人間関係の網の目の中で、信頼を築き、情報を管理し、権威を根付かせていくという、一連の「関係性の作法」を身体で覚えていくプロセスであるという事実です。オートエスノグラフィーは、この目に見えにくい学習の道のりを、当事者の内面から描き出してみせました。
オートエスノグラフィーは企業承継で動機と自己脚本の再構成を示す
リーダーシップの学習が、人間関係という複雑な文脈の中で進むものであることを見てきました。この複雑さは、その組織が「家族経営」である場合に、一層深まります。なぜなら、そこでは仕事上の役職と家族内での立場、経営上の合理性と個人的な感情、他者からの期待と自分自身の願いが、分かちがたく絡み合っているからです。ある研究は、この家族経営の承継という局面で、後継者候補が直面した深い苦悩と、そこからの脱却の過程を、当事者自身の語りを通して描き出しています[3]。
この物語の主人公は、父親が創業した会社の経営を引き継ぐことを期待されていました。しかし、会社は厳しい経営環境にあり、彼は会社の将来に強い不安を抱いていました。それ以上に彼を苦しめていたのは、この仕事を続けることへの動機が揺らいでいるという事実でした。彼は、専門のカウンセラーとの対話を通じて、この苦悩の根源を探る旅に出ます。
最初の面談で、カウンセラーは彼の心の奥底にある、行動の原動力となっている目標を探ります。そのために用いられたのは、幼い頃の記憶を呼び覚ますという手法でした。彼が語ったのは、家族でステーキを囲んでお祝いをした五歳の頃の記憶です。父親の成功が家族の喜びであり、長男である自分の誇りでもあった。この記憶から、「自分は勇敢であるときに価値を感じる」「勝利が望むものを与えてくれる」「父のように勝ち方を知りたい」といった、彼自身も無自覚だった人生のテーマが浮かび上がってきます。
カウンセラーは、彼が幼い頃から「父の期待に応え、勝利する救世主」という人生の脚本を内面化し、他の選択肢を考えることなく、その脚本通りに生きようとしてきたのではないかと問いかけます。
この気づきは、彼が抱える問題の捉え方を大きく変えるきっかけとなりました。「どうすれば会社を立て直せるか」という問いから、「自分は本当にこの場所で働くことに動機づけられているのか」という、より根源的な問いへと焦点が移っていったのです。
そこで彼は、動機づけに関する理論の枠組みを使って、自身の状況を冷静に分析します。「努力すれば、この会社で成功を達成できるか」という見込みは、市場環境の厳しさから低いと判断しました。「成功を達成すれば、望む報酬が得られるか」という点については、父からの賞賛や地位は得られるだろうと考えました。
しかし、最後の「その報酬は、自分にとって本当に魅力的か」という問いに対して、彼は、金銭や地位が本質的な動機ではなく、本当に求めているのは「自分自身のやり方で成し遂げたという感覚」であり、「父からの承認」ではないという結論に達します。
この分析を通して、彼は、たとえこの会社で成功したとしても、それは父の用意した舞台の上でのことであり、自分が心の底から求める達成感は得られないだろう、ということを言語化できたのです。彼が本当に目指すべき目標は、「自分の尺度で成功を創り出し、尊敬されること」でした。この発見は、彼を「会社を継ぐか、継がないか」という二者択一の苦しみから解放しました。会社を去ることは、敗北ではなく、自分自身の人生の脚本を新たに書き直すための、主体的な選択なのだと捉え直すことができたからです。
この物語は、リーダーシップが、場の要請に応える意志と同じくらい、自分自身の内なる目標と職業選択が一致することから生まれるものであることを、静かに伝えています。
分析的オートエスノグラフィーは経験を理論化する
これまで見てきたように、オートエスノグラフィーは、学者のアイデンティティ、リーダーの学習、家族経営の承継といった、複雑で個人的な経験の内実に光を当ててきました。しかし、これらの物語が、単なる個人的な体験談や自己満足的な告白に終わらず、多くの人にとって洞察に富む知識となるためには、どのような条件が必要なのでしょうか。経験を学術的な探究へと昇華させるためには、方法論的な規律が求められます。ここでは、「分析的オートエスノグラフィー」と呼ばれるアプローチが持つ、五つの特徴について解説します[4]。
第一に、研究者が、調査対象となる世界の「完全な成員」であることです。これは、研究者が外部の観察者としてその世界に出入りするのではなく、一員としてその中で生活し、活動していることを意味します。この立場にいるからこそ、長期にわたる深いアクセスが可能になり、表面的な観察では得られない厚みのある経験を捉えることができます。
第二に、「分析的な自己省察」を実践することです。成員である研究者は、その世界の利害に直接関わっています。そのため、自分自身の存在や行動が、周囲の人々やそこで起きる出来事にどう関わっているのかを、常に内省し続ける必要があります。自己の理解が深まることと、他者や世界の理解が深まることとが、相互に作用し合う関係性を自覚する姿勢が不可欠です。
第三の特徴は、研究者自身の姿を、記述の中で可視化することです。伝統的な研究報告では、書き手である研究者の姿は見えないことが通例でした。しかし、分析的オートエスノグラフィーでは、研究者自身の感情の動きや考えの変化、葛藤といった内面的な経験を、分析の一部として読者に提示します。ただし、自己の語りが過剰になることは避けなければなりません。自己の経験の開示は、あくまでも理論的な洞察を導き出すために行われます。
第四に、自己以外の人々との対話を続けることです。オートエスノグラフィーは、自分一人の経験だけに閉じてしまっては、その分析的な力を失います。自分自身の経験を出発点としながらも、インタビューや日常的な観察を通して、他の成員の経験や視点と絶えず対話させることが求められます。自己の内省を、他者から得られるデータによって検証し、豊かにしていくプロセスが、記述の偏りを和らげ、多角的な理解を可能にします。
第五に、「理論的な分析への貢献」を目指すことです。分析的オートエスノグラフィーの目標は、経験をありのままに記述することや、読者の感情に訴えかけることではありません。得られた豊かな経験データを手がかりとして、既存の社会的な理論を洗練させたり、新しい概念的な理解を発展させたりすることにあります。個別の物語を、より広い社会現象を説明するための足がかりとして用いるのです。
これら五つの特徴は、個人的な経験という主観的な素材を、客観的な知の世界へと橋渡しするためのものだと言えるでしょう。
脚注
[1] Learmonth, M., and Humphreys, M. (2012). Autoethnography and academic identity: Glimpsing business school doppelgangers. Organization, 19(1), 99-117.
[2] Kempster, S., and Stewart, J. (2010). Becoming a leader: A co-produced autoethnographic exploration of situated learning of leadership practice. Management Learning, 41(2), 205-219.
[3] Yarborough, J. P., and Lowe, K. B. (2007). Unlocking foreclosed beliefs: An autoethnographic story about a family business leadership dilemma. Culture and Organization, 13(3), 239-249.
[4] Anderson, L. (2006). Analytic autoethnography. Journal of Contemporary Ethnography, 35(4), 373-395.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。