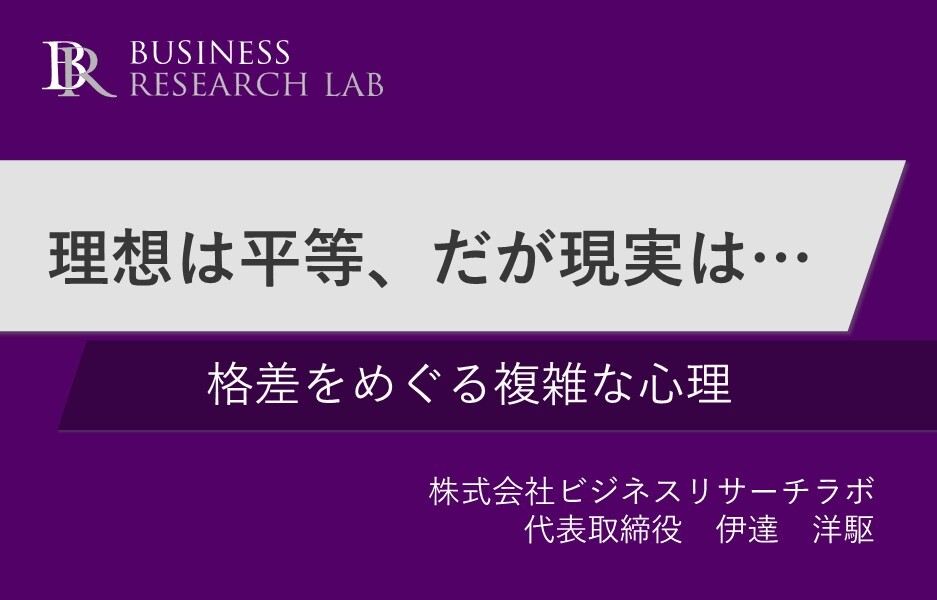2025年12月29日
理想は平等、だが現実は・・・:格差をめぐる複雑な心理
自分が社会のどのあたりにいるのか、考えたことはありますか。私たちの多くは、日々の生活の中で、自分と他者を比較しながら、自身の経済的な立ち位置を漠然と捉えています。そして、その認識は、私たちが社会のあり方についてどう考え、どのような政策を支持するかに関わっています。格差の問題が世界中で議論される現代において、人々が格差をどのように「見て」いるのかを理解することは、社会の未来を考える上で有用な視点です。
本コラムでは、アメリカとドイツという、歴史的背景も社会制度も異なる二つの国の人々が、自国の格差をどのように認識し、評価しているのかを、複数の実証研究を手がかりに探っていきます。人々は、現実のデータを正しく理解しているのでしょうか。それとも、そこには何らかの思い込みや願いが反映された、体系的な認識のずれが存在するのでしょうか。
アメリカの事例からは、「アメリカン・ドリーム」という言葉に象徴される、努力が報われる社会への強い期待が、現実の数値を上回る楽観的な認識を生んでいる様子が見えてきます。同時に、人々が思い描く理想の社会は、自らが認識している現状よりも、はるかに平等なものであることも分かります。一方、ドイツの事例は、人々が自身の社会的な位置付けを正確に把握していない点は共通しつつも、再分配への強い支持が、自身の利害に直接関わる情報に触れたときに変化するという、複雑な心理を映し出します。
アメリカ人は社会的流動性を実際より高く見積もる
「アメリカン・ドリーム」は、個人の努力と才能が成功を決定づけるという、機会の平等に根差した社会の理想像を体現してきました。この物語は、アメリカ社会の根幹をなす価値観の一つであり、多くの人々にとって希望の源泉となってきました。しかし、人々が抱くこの「機会の国」というイメージは、現実の姿を正確に反映しているのでしょうか。この問いに答えるため、アメリカの成人を対象とした全国規模の調査が行われました[1]。
調査では、参加者にアメリカ社会における階層間の移動、すなわち社会的流動性について、いくつかの側面から推定を求めました。例えば、「最も貧しい20%の家庭に生まれた人が、成人して最も裕福な20%の仲間入りをする確率はどのくらいか」といった問いです。参加者の回答を実際の公的な統計データと比較した結果、あらゆる側面で、人々は社会的流動性を実際よりも高く見積もっていることが判明しました。特に、底辺の階層からトップの階層へと駆け上がる「上方移動」の可能性は、現実の数値を大幅に上回って楽観的に捉えられていました。
この楽観的な認識は、どのような人々においてより顕著なのでしょうか。分析を進めると、収入や学歴といった客観的な指標で高い社会階層に位置する人や、自身の社会的地位が高いと主観的に感じている人ほど、流動性を高く見積もるという関連が見られました。政治的な志向も関連しており、保守的な考えを持つ人々の間でも、同様に過大評価が強く観察されました。
このことから、自らが成功している、あるいは現行の社会システムを肯定的に捉えている人々にとって、社会は公正に機能しており、努力が報われる場所であると信じたいという心理が働いている可能性が考えられます。
このような認識のずれはどこから生まれるのでしょうか。一つは、人々が社会の仕組みについて十分に知らない、すなわち情報が不足しているという点です。もう一つは、社会が公正であってほしいと願う、動機づけの側面です。これらの要因を切り分けるため、一連の実験が設計されました。
ある実験では、参加者を二つのグループに分け、一方には「人の特性は遺伝的に決まっており、変わりにくい」、もう一方には「人の特性は環境や努力によって変わりうる」という内容の文章を読んでもらいました。これは、社会階層を固定的と見るか、可変的と見るかという、人々の世界観に働きかける試みです。
結果、社会階層は固定的であるという考え方を促されたグループでは、流動性の過大評価が弱まり、推定値は現実のデータに近づきました。逆に、階層は可変的であると強調されたグループでは、過大評価が維持、あるいは強まりました。このことは、流動性に対する信念が、知識の有無だけでなく、物事をどう捉えるかという思考の枠組みに左右されることを示唆しています。
続いて、知識そのものの影響を確かめる実験が行われました。参加者の一部に、社会的流動性に関する正確な統計情報を事前に提示してから、改めて推定を求めたのです。すると、正しい情報を与えられたグループでは、推定値が実際値に近づき、過大評価の度合いが減少しました。また、流動性に関する知識を問うクイズでは、正答率が低い人ほど推定の誤差が大きいことも確認されました。これらの結果は、情報不足が過大評価の一因であることを裏付けています。
しかし、たとえ正確な情報を与えられた後でも、なお人々は流動性を実際より高く見積もりました。ここには、情報だけでは解消しきれない心理的なメカニズムが働いているようです。
そのメカニズムを探るため、最後の実験では、人々の「動機」に焦点を当てました。参加者に社会の階層を示すはしごを想像してもらい、一部には自分より「上」の人々と比較させ(主観的地位が下がる状況)、別の一部には自分より「下」の人々と比較させました(主観的地位が上がる状況)。その直後に流動性を推定してもらったところ、自分は社会の上の方にいると感じさせられた人々は、流動性の過大評価をより強めることが分かりました。
この一連の研究から見えてくるのは、調査に参加したアメリカの人々が抱く社会的流動性への楽観的な見方が、二つの柱によって支えられているという構図です。一つは、統計的な事実に関する知識の不足という「情報」の側面。もう一つは、自らの成功や社会のあり方を正当化したいという「動機づけ」の側面です。
アメリカ人は平均所得を低く見積もり不平等を誇張する
社会を駆け上がるチャンスは豊富にあると考えるアメリカの人々は、自国の経済的な格差、特に所得の分布について、どのようなイメージを抱いているのでしょうか。社会的流動性への楽観的な見方とは対照的に、所得格差については、現実とは異なる側面を持つ認識が広がっていることが、複数の調査から明らかになっています[2]。
ある調査では、アメリカの成人を対象に、国内の所得分布について尋ねました。2010年時点での年収を三つの階層に分け、それぞれの階層に属する世帯が全体の何パーセントを占めると思うかを推定してもらったのです。
結果、参加者は、低所得層の割合を実際よりも多く見積もり、逆に高所得層の割合を少なく見積もりました。例えば、高所得層の実際の割合は約32%であるのに対し、人々の推定の平均は約23%でした。これは、多くの人が、アメリカ社会を実際よりも「平均的に所得が低い」と認識していることを意味します。この認識のずれは、政治的にリベラルな考えを持つ参加者の間で、より強く見られました。
同じ調査で、所得格差が時間とともにどう変化してきたかに関する認識が調べられました。参加者には、1970年から2010年にかけての各年代で、所得上位20%と下位20%の世帯の平均所得の比率を推定してもらいました。
その結果、過去については比較的現実に近い推定がなされたものの、現在に近づくにつれて、人々は格差の拡大を過大に評価していることが分かりました。2010年の実際の格差比が約15倍であるのに対し、参加者の推定は約31倍にも達していました。人々は、所得格差が現実をはるかに超えるスピードで拡大していると捉えていたのです。
この所得格差の拡大を過大に評価する認識は、何によって引き起こされているのでしょうか。原因を探るため、別の調査では、測定の方法を変え、上位20%と下位20%の「平均世帯所得の金額そのもの」を直接推定してもらうアプローチが取られました。
ここから得られた結論は明快でした。人々が格差の拡大を過大に見積もる原因は、ほぼ完全に「上位20%の所得を、現実離れした金額にまで膨らませて考えている」ことにあったのです。下位20%の所得については、どの年代でもかなり正確に推定できていました。しかし、上位20%の所得となると、その推定額は現実の数値をはるかに上回り、2010年には、実際の約15万9000ドルに対し、推定額は約211万ドルという、桁違いの数字になっていました。
この上位層に対する認識のずれは、別の角度からの質問でも確認されました。「上位1%の富裕層になるための最低年収はいくらか」という問いに対し、多くの人が実際の金額よりもはるかに高い選択肢を選びました。また、年収100万ドルを超える「超高所得層」が人口全体に占める割合についても、実際にはごくわずかにもかかわらず、人々はその何倍もの割合を推定しました。
これらの調査結果を総合すると、アメリカの人々が抱く所得分布のイメージは、二つの特徴的な側面を持つことが分かります。一つは、社会全体の平均的な所得水準を実際よりも低く見積もる点。もう一つは、トップ層が稼ぐ金額を非常に大きいものと考え、所得格差の大きさを過大に評価する点です。
アメリカ人は現実より平等な富の分配を望む
所得格差を現実以上に大きいものとして捉えているアメリカの人々。では、どのような社会のあり方を「理想」として思い描いているのでしょうか。所得という一年間の経済的な流れだけでなく、これまでに蓄積されてきた富の分配については、どのような考えを持っているのでしょうか。この問いに答えるため、全国の成人を対象としたオンライン調査が実施されました[3]。
調査の最初の課題は、参加者に、自分がどの社会に属したいかを直感的に選んでもらうというものでした。参加者の前には、富の分配が異なる三つの社会の姿が、ラベルのない円グラフで示されました。一つは富が完全に均等な社会、もう一つは現実のアメリカの富の分配、三つ目はアメリカより格差が小さいスウェーデンの所得分配をモデルにしたものです。参加者には、「自分がこの社会のどこかにランダムに配置されるとしたら、どの社会に加入したいですか」という、ロールズが提唱した「無知のヴェール」と呼ばれる思考実験の状況が設定されました。
結果は圧倒的で、全体の92%もの人々が、現実のアメリカ型の分配よりも、スウェーデン型のより平等な分配の社会を選びました。この選択は、性別や所得水準、支持政党によってもほとんど変わりませんでした。共和党支持者も民主党支持者も、その9割以上がスウェーデン型の社会を選好しました。このことは、調査に参加したアメリカの人々が、政治的な立場の違いを超えて、現状よりも格差の小さい社会を望んでいることを示唆しています。
調査は次に、より具体的な形で、人々の現状認識と理想像を探る課題へと移りました。参加者には、アメリカの富が五つの階層にどのように分配されていると思うか、その割合を推定してもらいました。その上で、次に、自分自身が「理想的」だと考える富の分配の割合を回答してもらいました。
ここでも二つの発見がありました。第一に、人々は現実の富の不平等を過小評価していました。実際のデータでは、最上位20%が国富の約84%を保有しているのに対し、参加者の推定では、その割合は約59%にとどまりました。
第二に、人々が思い描く「理想の分配」は、その誤って低く見積もった現状認識よりも、さらに平等的であったという点です。理想の社会として人々が構築した富の分配は、最上位20%の取り分が約32%となり、残りの富が他の階層に手厚く配分されるというものでした。人々は「自分たちが思っているよりも現実は不平等だ」という事実を知らないだけでなく、その「自分たちが思っている現状」すらも、理想とはかけ離れていると考えていたのです。
この理想の分配の姿についても、属性による違いはほとんど見られませんでした。所得の高い層も低い層も、共和党支持者も民主党支持者も、皆が同じ方向性を共有していました。それは、「現状よりも格差を小さくすべきだ」という願いと、同時に「完全な平等ではなく、ある程度の差は認めるべきだ」という、バランスの取れた感覚です。
ドイツ人は格差を誤認するが自分が負担側と知ると再分配支持が下がる
アメリカで見てきたような、人々の格差認識と現実とのずれは、他の国ではどのように現れるのでしょうか。舞台をヨーロッパに移し、ドイツの事例を見てみましょう。ドイツの一般市民を対象に行われた調査実験は、人々が自国の所得格差をどのように捉え、再分配についてどう考えているのか、その内面を明らかにしました[4]。
この調査では、参加者に「あなたの世帯の生活水準は、ドイツ全体の中で下から何割くらいに位置すると思いますか」と尋ね、自身の社会における相対的な順位を推定してもらいました。その結果、ここでも系統的な認識のずれが見られました。所得が低い階層の人々は自分の順位を実際よりも高く評価する一方、所得が高い階層の人々は自分の順位を低く評価するというパターンが現れました。
その結果、人々が思い描く所得分布の全体像は、現実とは異なり、中央に凝縮された、実際よりもはるかに平等なものとなっていました。興味深いことに、人々は自身のこの推定にあまり自信がなく、多くが「よく分からない」と自覚していました。
このような自己認識にもかかわらず、所得の再分配に対する考え方は、驚くほど一貫していました。情報が与えられる前の時点で、回答者の83%が「所得の再分配をもっと進めるべきだ」と考えており、「行き過ぎだ」という回答はわずか6%でした。この「より平等に」という強い志向は、所得階層による違いがほとんどなく、社会全体で広く共有された規範であることがうかがえます。
この調査実験の核心は、ここから始まります。参加者を無作為に二つのグループに分け、一方のグループにだけ、ドイツの所得分布の正確な情報と、回答者自身の「本当の順位」を教えました。このように正しい情報を提供された人々は、再分配への考え方を変えるのでしょうか。
結果は、多くの人の予想と異なるものだったかもしれません。正しい情報を与えられても、人々の再分配に対する支持の度合いは、平均的に見てほとんど変化しませんでした。自分の順位を実際より低く見積もっていた人が「自分は思ったより上だった」と知っても、社会はもっと平等であるべきだという基本的な考え方は揺るがなかったのです。格差の事実に関する一般的な知識は、人々の根強い規範的な態度を動かすには力不足であるようでした。
しかし、実験はもう一段階、踏み込みます。情報を与えられたグループに対してのみ、追加の情報が提示されました。それは、「あなたは、税金や社会保障の制度全体で見て、差し引きで『受益する側』ですか、それとも『負担する側』ですか」という、より直接的に自身の利害に関わる情報です。分析の結果、所得上位層にあたる「負担側」にいると知らされた人々は、再分配への支持を有意に低下させることが分かりました。一般的な格差の情報では動かなかった態度が、「自分の財布」に直結する情報に触れた途端、変化したのです。
このドイツでの実験が描き出すのは、格差に対する態度の持つ二つの側面です。「社会はもっと平等であるべきだ」という規範的な信念は非常に強固で、少々の事実知識では揺らぎません。しかし、その再分配のコストが「自分の負担」として具体的に突きつけられたとき、その信念は変化し、自身の利益を勘案した判断へと傾くのです。
脚注
[1] Kraus, M. W., and Tan, J. J. X. (2015). Americans overestimate social class mobility. Journal of Experimental Social Psychology, 58, 101-111.
[2] Chambers, J. R., Swan, L. K., and Heesacker, M. (2014). Better off than we know: Distorted perceptions of incomes and income inequality in America. Psychological Science, 25(2), 613-618.
[3] Norton, M. I., and Ariely, D. (2011). Building a better America: One wealth quintile at a time. Perspectives on Psychological Science, 6(1), 9-12.
[4] Engelhardt, C., and Wagener, A. (2016). What do Germans think and know about income inequality? A survey experiment (ECINEQ Working Paper No. 2016-389). Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ).
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。