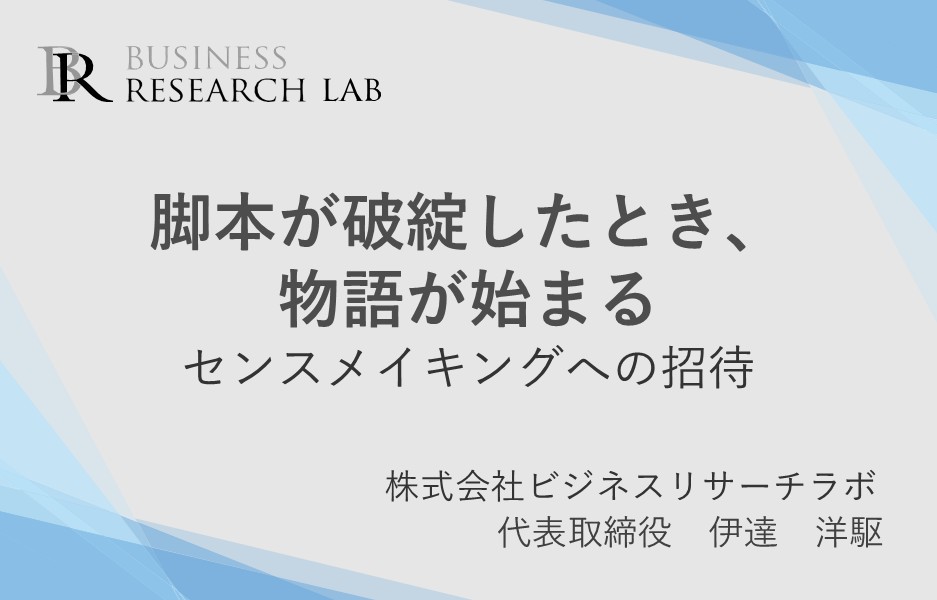2025年12月26日
脚本が破綻したとき、物語が始まる:センスメイキングへの招待
私たちの日常は、大小さまざまな「意味づけ」という行為で満たされています。朝のニュースを見て今日の予定を考え直したり、同僚の何気ない一言からその意図を推し量ったり、私たちは周囲の出来事を解釈し、自分なりの納得解を見つけながら行動しています。ほとんどの場合、このプロセスは無意識のうちに、ごく自然に行われます。
しかし、ある日突然、これまで当たり前だと思っていた前提が崩れるような出来事に遭遇したらどうなるでしょうか。例えば、新しい職場への異動、予期せぬプロジェクトの始動、社会全体を揺るがすような大きな変化。そうした場面で、私たちは「何が起きているのか」「これからどうなるのか」という問いの渦に投げ込まれます。
このような、曖昧で驚きに満ちた状況の中から、手探りで「筋の通った話」を紡ぎ出し、新たな現実の地図を描き出そうとする営み、それが「センスメイキング」です。センスメイキングは、単に情報を処理することとは異なります。過去の経験と目の前の手がかりを照らし合わせ、他者との対話を通じて、バラバラだった断片を一つの物語へと編み上げていくプロセスです。
本コラムでは、センスメイキングを通して、人と組織が、いかに混乱を乗り越え、新たな意味と秩序を創造していくのかを探求します。個人が未知の環境に適応する瞬間から、チームが未来のビジョンを描き出す過程、社会が大きな出来事の意味を構築していく力学まで、研究の知見を旅しながら、その世界を紐解いていきたいと思います。
驚きが新参者のセンスメイキングを促し適応を導く
新しい環境に足を踏み入れたとき、誰もが少なからず戸惑いを覚えるものです。「聞いていた話と違う」「こんなはずではなかった」。こうした感覚は、なぜ生まれるのでしょうか。組織に新しく加わった人々が経験する内面的なプロセスを掘り下げた研究があります[1]。その研究は、これまで主流であった二つの考え方に疑問を投げかけるところから始まります。
一つは、新参者の離職を「入社前の期待が高すぎた」あるいは「入社後の現実が期待を下回った」という期待のズレだけで説明しようとする考え方です。もう一つは、組織に馴染んでいく過程をいくつかの段階に分け、その段階ごとに組織がどのような手立てを準備すべきかという制度設計に焦点を当てる考え方です。
これらの考え方は、新参者が直面する現実の一側面を捉えてはいますが、肝心な点を見過ごしているのではないか、と研究者は指摘します。新参者自身が、目の前で起きる出来事をどのように解釈し、意味づけし、次にとるべき行動を選んでいくのか、というプロセスです。そこで、この研究では、新参者の経験を三つの要素から捉え直すことを試みます。それは「変化」「対比」「驚き」です。
「変化」とは、以前の環境と新しい環境との間にある、客観的な事実の違いを指します。住む場所や肩書き、給与、あるいは人間関係といった、記録に残すことのできる差異です。「対比」とは、新しい環境の中で、その人にとって主観的に際立って感じられる違いのことです。同じ変化であっても、何が心に引っかかるかは人によって異なります。そして、重要なのが「驚き」です。これは、事前の予測や思い込みと、実際に経験したこととの間に生じるギャップを指します。
「驚き」は、「期待外れ」のような否定的なものだけではありません。予想をはるかに上回る良い出来事もまた、驚きの一種です。また、驚きは仕事の内容そのものについて生じることもあれば、組織の雰囲気や、あるいは「自分はこういう人間だと思っていたけれど、実は違った」といった自己認識について生じることもあります。このように、驚きは非常に多面的な現象であり、従来の「期待が満たされなかった」という一面的な見方では捉えきれない豊かさを持っています。
そして、この「驚き」が、人の思考を駆動させる引き金となります。私たちは普段、慣れ親しんだ脚本に沿って半ば自動的に行動していますが、予測と現実が食い違う「脚本の破綻」が起きると、立ち止まって「これはどういうことか」と考えることを余儀なくされます。これがセンスメイキングの始まりです。
驚きを検知した人は、過去の経験やその場の状況、周囲の人々から与えられる解釈などを手がかりに、何が起きたのかを診断し、自分なりの説明を組み立てます。そして、その解釈に基づいて次の行動を選択し、結果を受けて、もともと持っていた期待や前提を更新していくのです。この一連の循環を通じて、人は新しい環境に適応していきます。
しかし、新参者はこの意味づけのプロセスで特有の困難に直面します。一つは、その組織で暗黙のうちに共有されている「ローカルな解釈の辞書」を持っていないことです。例えば「主体的に動く」という言葉一つをとっても、その意味合いは組織文化によって異なります。以前の環境の物差しで物事を判断してしまうと、意図せず誤解を生んだり、評価を下げられたりすることがあります。
もう一つの困難は、信頼できる相談相手がいないことです。何か出来事が起きたとき、経験豊富な内部者であれば、それが一時的な問題なのか、組織の構造的な課題なのかを判断する手助けをしてくれます。しかし、人間関係がまだできていない新参者は、出来事の意味を過度に自分自身の責任に帰してしまったり、その重要性を見誤ったりします。
素材実践が個人の気づきを集団の未来志向センスメイキングへ変える
先ほどは、個人が未知の環境に直面した際に、内面で繰り広げられる意味づけのプロセスを見てきました。視点を個人から集団へと移してみましょう。新製品のコンセプトを練ったり、会社の新しい戦略を立案したりと、組織ではまだ形になっていない未来をチームで描き出す場面が数多くあります。このような未来に向けた活動において、人々の頭の中にある漠然としたアイデアは、どのようにして一つの共有されたビジョンへと結晶化していくのでしょうか。
この問いを探求した研究は、私たちの目を「モノ」へと向けさせます[2]。従来のセンスメイキング研究の多くは、過去に起きた予期せぬ出来事を人々が後からどう解釈するかという点に光を当ててきました。また、その分析の中心は、人々が交わす「会話」や「言葉」に置かれていました。
しかし、未来を構想するデザインや戦略策定の現場では、言葉だけでなく、スケッチや図、写真、模型といった多種多様な「モノ」が重要な働きをしています。この研究は、そうした「素材」を介した実践、すなわち「素材実践」が、個人の気づきを集団の共有理解へと橋渡しする上で、決定的な役割を担っていることを明らかにしました。
この知見は、ある国際的なデザインコンサルティング会社で行われた、長期にわたる詳細な観察調査から導き出されました。研究者の一人が約10ヶ月間、現場に深く入り込み、数多くの会議を観察し、関係者にインタビューを重ねることで、創造のプロセスを内側から記録したのです。その結果、未来を構想するセンスメイキングは、大きく四つの段階を繰り返しながら進んでいくことが見えてきました。それは、「気づきと括り出し」「語り始め・カテゴリ化」「統合・精緻化」「影響・説得」というサイクルです。
最初の段階は、現場での体験や観察を通じて得られた気づきを、写真やメモ、製品サンプルといった「素材」の形にして流れから「括り出す」ことから始まります。続いて、それらの素材を手がかりに、抽象的な概念に具体的な意味を与え、仮の分類や名前付けを行います。第三段階では、そうして生まれた個別の理解の断片を互いに結びつけ、より複雑で整合性のある構造、つまりチームで共有された考え方の枠組みへと編み上げていきます。最後の段階で、出来上がりつつある解釈を、顧客などに提示するための説得力のある物語へと再構成するのです。
このプロセスを駆動するのが、会話と並行して行われる三種類の素材実践です。一つ目は「素材による分類・意味づけ」です。例えば、壁一面に写真や雑誌の切り抜きを貼り付けたイメージボードを作成し、それらを見ながら「無機質」「安心感がない」といった言葉を引き出し、抽象的な感覚を視覚情報と結びつけて共有します。あるいは、インタビューで得た発見を書き込んだカードを、物理的に並べ替えたりグループ分けしたりすることで、分類の仕方を試行錯誤し、物事の輪郭を浮かび上がらせます。
二つ目は「可視的統合」です。これは、バラバラの気づきの間に「つながり」を見出し、検証するための実践です。メンバーがそれぞれ小さなラフスケッチを描いてアイデアの断片を素早く形にしたり、それらの関係性を矢印や図で整理したフレームワークを作成したりします。壁に貼られたスケッチに他のメンバーが加筆修正を重ね、互いのアイデアに乗りながら一つの集合知を形成していく光景も見られます。
三つ目は「素材の記憶化」です。プロジェクトルームの壁全体を、写真やカード、スケッチで埋め尽くし、いわば「共有の頭脳」として活用します。これによって、議論の過程が可視化され、メンバーはいつでも文脈に立ち戻ることができます。また、壁に貼られた断片同士が偶然結びついて新たな発想を生んだり、個人の作業に無意識のうちにヒントを与えたりもします。
この研究が描き出すのは、集団による創造が決して整然とした会話だけで進むのではない、という実像です。言葉にならない個人の曖昧なひらめきが、まず「モノ」という形に置き換えられる。そして、そのモノをチーム全員で動かし、並べ替え、描き加え、関係づけるという身体的な作業を通じて、徐々に一つの「もっともらしい」未来像へと練り上げられていくのです。そこでは、モノは思考を外部に記録する装置であり、対話の足場であり、新たな結合を促す触媒として機能しています。
活気と統制の配置がセンスメイキングの型と成果を決める
組織の中で、重要な決定が下される場面を想像してみてください。ある時は、関係者が集まり、活発な議論の末に全員が納得する結論が導き出されるかもしれません。またある時は、トップリーダーが一部の側近と話を進め、決定事項として静かに発表されることもあるでしょう。あるいは、議論が紛糾するばかりで一向に収束せず、結局何も決まらないまま時間だけが過ぎていくという経験をした人もいるかもしれません。こうした違いは、一体どこから生まれるのでしょうか。
この問いに答えるため、ある研究は、組織内で多様な人々が関わり合いながら時間をかけて「何が起きているのか」を理解していく社会的なプロセスを、長期間にわたって追跡しました[3]。これまでのセンスメイキング研究は、個人の認知の働きに光を当てたり、あるいは危機的な状況での対応に焦点を当てたりすることが多かったのですが、この研究は、より日常的で、多数の利害関係者が関わる、長期的な意味づけのプロセスを解明しようとした点に特徴があります。
調査の舞台となったのは、英国にある三つの交響楽団です。研究者は2年以上にわたり、楽団の理事会や管理職会議、演奏者の委員会といった様々な会議を観察し、数多くの関係者にインタビューを行い、文書資料を分析しました。そして、レパートリーの編成や指揮者の選任、コスト削減といった楽団が日常的に直面する課題について、誰がどのように意見を表明し、議論がどのように進み、どのような結論に至ったのかを、一つひとつ丹念に記述していきました。
その詳細な分析から、組織におけるセンスメイキングの社会的なプロセスを特徴づける、二つの重要な軸が浮かび上がってきました。一つは「アニメーション(活気)」です。これは、主にリーダー以外の多様な関係者が、どれだけ活発に情報を共有し、継続的に議論に参加しているかという度合いを指します。もう一つは「コントロール(統制)」です。これは、主にリーダーが、議論の場をどれだけ計画的に設定し、一対一の対話などを通じてプロセスを方向づけているかという度合いを指します。
この二つの軸の組み合わせによって、センスメイキングのプロセスは四つの異なる型に分類できることが見出されました。
第一の型は「ガイデッド(誘導型)」と呼ばれます。これは、活気と統制がともに高い状態です。多様な関係者から様々な意見や情報が活発に提供される一方で、リーダーがそれらを丁寧に拾い上げ、個別の対話や計画的な会議を通じて一つの方向にまとめていきます。その結果、豊かで一貫性のある一つの意味づけが形成され、それに基づいた着実な行動が実行されていきます。
第二の型は「フラグメンテッド(断片型)」です。これは、活気は高いものの、統制が低い状態です。多くの人々がそれぞれに意見を述べますが、それらを統合する仕組みや場が欠けているため、議論が発散するばかりです。結果、複数の異なる解釈が併存し、それぞれがバラバラの行動をとるため、組織としての一貫した動きが生まれません。
第三の型は「リストリクテッド(限定型)」です。これは、統制は高いものの、活気が低い状態です。リーダーが選ばれた少数の人々と水面下で話を進め、意思決定を行います。広範な議論は行われないため、物事は迅速に進みますが、その背景にある意味づけは、一部の人々の視点に基づいた狭いものになりがちです。
第四の型が「ミニマル(最小型)」です。これは、活気も統制もともに低い状態です。誰も積極的に動こうとせず、議論は停滞します。何か外的なきっかけがない限り物事は動かず、たとえ動いたとしても、その場しのぎの妥協的な行動が取られるにとどまります。
この研究が明らかにしたのは、組織における意味づけのプロセスは決して一様ではないということです。どのような意味が生まれ、どのような行動につながるのかは、リーダーと他の関係者との相互作用が、これら四つの型のうちのどれに近いかによって左右されます。
公共的注目が表象と理論化のセンスメイキングを促す
社会を揺るがすような大きな出来事が起きたとき、私たちの物の見方はどのように変わるのでしょうか。例えば、画期的な技術の登場、大規模な法改正の動き、あるいは業界の根幹を揺るがすような事件。こうした出来事は、それ自体が変化をもたらすだけでなく、人々の注意を一点に集め、業界全体の「当たり前」とされてきた考え方や行動様式、すなわち「制度ロジック」を書き換えるきっかけとなることがあります。
ある研究は、このような社会的な注目が、いかに制度ロジックの変容を引き起こすのか、そのメカニズムを解き明かそうと試みました[4]。分析対象として選ばれたのは、1990年代に米国で議論されたクリントン政権の医療保険改革です。この改革案は、最終的に議会を通過せず、法制化には至りませんでした。しかし、この研究は、改革の成否そのものではなく、改革を巡る一連の出来事が社会の強い注目を集めた結果、米国の病院業界の支配的なロジックが転換したプロセスに光を当てます。
長年、米国の病院業界は「専門職権威」というロジックに支配されていました。これは、医師が持つ専門的な裁量が尊重され、病院は医師の指示に従い、保険者はその費用を受動的に支払うという考え方です。しかし、改革を巡る議論が巻き起こる中で、これに代わる新しいロジック、「マネージドケア」が台頭してきます。これは、コストと質の管理を重視し、保険者や雇用者がより能動的に医療サービスに関与し、病院や医師はネットワークの中で効率的な医療を提供することが求められるという考え方です。
なぜ、法案が成立しなかったにもかかわらず、このようなロジックの転換が起きたのでしょうか。研究者は、その鍵が、出来事への注目によって誘発される二種類のセンスメイキングの働きにあると論じます。一つは「理論化」です。これは、物事を説明するための抽象的なモデルや理屈を構築する営みです。改革議論の初期には、政府が提示した「マネージド・コンペティション」といった政策モデルが、この理論化の核となりました。
しかし、もう一つ、これまでの研究では見過ごされがちだったメカニズムがあります。それが「表象」です。これは、具体的な事例や、環境の中の目立った特徴に光を当て、それを通じて物事を理解しようとする営みです。改革議論が深まるにつれて、人々の関心は、政府が示す抽象的なモデルの是非を問うことから、自分たちの目の前で起きている市場の変化、例えば特定の保険プランの拡大や病院同士の統合、あるいは先進的な取り組みで知られる地域の事例など、具体的な現象へと移っていきました。
この研究は、業界誌の記事を長期間にわたって分析することで、出来事の進行に伴って意味づけの重心が変化していく様を描き出しています。改革への「期待期」には、政策モデルという「理論化」が議論の中心でした。しかし、計画が具体化し、様々な意見が交わされる「熟議期」に入ると、目の前の市場の変化や具体的な成功事例といった「表象」への言及が増えていきます。そして、人々はそれらの現象を一般化し、それらを説明する新たな「理論化」、すなわちマネージドケアという新しい市場のロジックを自ら紡ぎ出し始めたのです。
最終的に、政治的な改革が頓挫した後の「回顧期」には、当初の政策モデルはもはや語られなくなりました。その代わりに、市場主導で変化が進んでいくという、現場から生まれた新しい物語が業界の支配的なロジックとして定着していきました。
この研究が示すのは、業界全体の常識というような大きな変化が、必ずしもトップダウンの制度変更だけで起こるわけではないということです。社会的な注目というエネルギーを浴びる中で、現場の人々が目の前の変化の兆候や事例に意味を与え、それを説明するもっともらしい物語を集合的に紡ぎ出す。そのプロセスを通じて、フィールド全体の物の見方が書き換えられていくのです。
審問報告書の語りは制度正当化のセンスメイキングである
組織や社会を揺るがすような不幸な事件が起きた後、第三者委員会や公的な審問機関が設置され、詳細な調査の末に報告書が公表されます。私たちはその報告書を、何が起きたのかという「真実の記録」として受け止めるかもしれません。しかし、そのテキストは本当に、事実をありのままに映し出す鏡なのでしょうか。ある研究は、こうした報告書を、事実の記述ではなく、特定の意味を構築し、社会的な秩序を回復するために編まれた「センスメイキングの産物」として読み解くことを試みます[5]。
分析対象となったのは、1990年代初頭に英国のある病院で、一人の看護師によって引き起こされたとされる乳幼児の連続急変・死亡事件に関する公的な審問報告書です。この研究は、報告書のテキストを精密に分析し、その語りが、いかに一つの「もっともらしい」物語を構築し、それによって特定の社会的な機能を果たしているかを明らかにしました。
研究者が発見したのは、報告書の語りを貫く、相互に関連し合う三つの戦略です。第一の戦略は「正常化と悪魔化」です。報告書は、犯人とされた看護師の経歴を詳述するにあたり、彼女の過去の欠勤の多さや、度重なる通院歴といった、後から見れば危険の兆候ともとれる事実を、「同世代の若者には珍しくない振る舞い」として文脈づけ、その深刻さを薄めていきます。これによって、なぜ病院や養成機関は彼女の危険性を見抜けなかったのかという問いに対して、「外見上、異常はなかったのだから見抜けなくて当然だった」という説明が成り立つようになります。出来事を「正常」の範囲内に位置づけることで、組織の責任が問われにくくなるのです。
第二の戦略は「観察と識別」です。報告書は、事件が次々と発生していた病棟で、なぜ医療スタッフはもっと早く異常な事態に気づけなかったのかという問いに答えます。その語り口は、個々の出来事は観察されていたものの、それらが一つのパターンとして認識されるまでには時間がかかった、という段階的なプロセスを描写します。これは、人間が予期せぬ出来事に直面した際に、既存の知識の枠組みに当てはめて理解しようとし、なかなか新しい解釈に移行できない、というセンスメイキングの知見とよく一致しています。
第三の戦略が「非難と免責」です。報告書は、現場での数多くの見落としや不適切な対応を列挙しつつも、最終的な結論として、個々の医療者の判断ミスを厳しく追及することは避けます。代わりに、問題の原因を、コミュニケーション不足や責任体制の不明確さといった「管理上の欠陥」に帰着させるのです。これによって、個人の責任は限定され、医療専門職という制度全体の正当性が守られます。問題は、個人の資質ではなく、改善可能なマネジメントの問題として再定義されるのです。
この分析が示すのは、審問報告書が、単に事実を報告するだけではないということです。それは、一つの物語を提示することで、他の解釈の可能性を封じ込め、社会の不安を和らげて、傷ついた制度への信頼を回復するという、社会的な機能を担う修辞的な構築物なのです。不可解な惨事を、理解可能で、将来的には管理可能な出来事として語り直す。それによって、私たちは再び秩序への信頼を取り戻すことができます。
脚注
[1] Louis, M. R. (1980). Surprise and sense making: What newcomers experience in entering unfamiliar organizational settings. Administrative Science Quarterly, 25(2), 226-251.
[2] Stigliani, I., and Ravasi, D. (2012). Organizing thoughts and connecting brains: Material practices and the transition from individual to group-level prospective sensemaking. Academy of Management Journal, 55(5), 1232-1259.
[3] Maitlis, S. (2005). The social processes of organizational sensemaking. Academy of Management Journal, 48(1), 21-49.
[4] Nigam, A., and Ocasio, W. (2010). Event attention, environmental sensemaking, and change in institutional logics: An inductive analysis of the effects of public attention to Clinton’s health care reform initiative. Organization Science, 21(4), 823-841.
[5] Brown, A. D. (2000). Making sense of inquiry sensemaking. Journal of Management Studies, 37(1), 45-75.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。