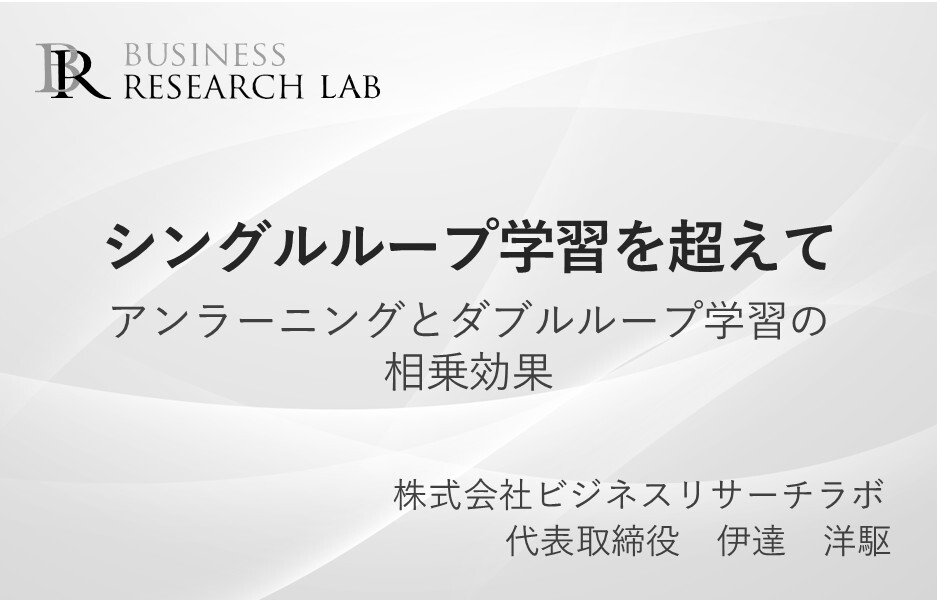2025年12月25日
シングルループ学習を超えて:アンラーニングとダブルループ学習の相乗効果
私たちの周りの世界は、絶えず姿を変え続けています。新しい技術が生まれ、市場のルールが書き換えられ、人々の価値観も変化します。このような環境の中、組織が生き残り、成長を続けるためには、新しい知識やスキルを学び続けることが不可欠です。しかし、本当にそれだけで十分でしょうか。新しいことを学ぶ一方で、私たちは知らず知らずのうちに、過去の成功体験や古くなった常識に縛られていることがあります。かつては有効だったやり方が、いつの間にか足かせとなり、変化への対応を遅らせてしまうのです。
そこで浮かび上がってくるのが、「アンラーニング」という考え方です。これは、既にある知識や信念、行動様式を意図的に手放し、新しいものを取り入れるための余白を作るプロセスを指します。学習が新しい知識を「足し算」する行為だとすれば、アンラーニングは不要になった知識を「引き算」する行為と言えるかもしれません。しかし、これは忘れることや捨てることだけを意味するのではありません。むしろ、これまで当たり前だと思っていたことを一度立ち止まって見つめ直し、その有効性を問い直す営みです。
アンラーニングは、個人の成長だけでなく、組織全体の能力を高める上でも可能性を秘めています。組織に深く根付いた慣習や固定観念をどのように見直し、変化への適応力を高めていけば良いのでしょうか。本コラムでは、アンラーニングが組織の中でどのように働き、どのような価値をもたらすのかを、いくつかの実証的な分析を手がかりに探求していきます。
アンラーニングが技術知と関係知を統合する
組織が日々の活動を進める上では、多種多様な知識が活用されています。その中には、ITシステムや専門機器を扱うための「技術知」と、顧客や患者といった他者とのコミュニケーションを通じて築かれる「関係知」があります。
これら二つの知識は、どちらも組織にとって欠かせないものですが、その性質は異なります。技術知が効率性や標準化を求めるのに対し、関係知は個別性や柔軟性を求めます。そのため、両者の間には時として対立や緊張が生まれることがあります。例えば、医療現場において、電子カルテの入力作業に集中するあまり、患者との対話がおろそかになってしまうといった状況が考えられます。このような二種類の知識のバランスを、組織はどのように取っていけばよいのでしょうか。
この問いに一つの手がかりをあたえる調査があります[1]。スペインの在宅急性期ケアを提供する医療機関に所属する、医師と看護師合わせて117名を対象に行われたものです。この調査では、組織の「技術知」と「医師・患者知(関係知)」の水準が、アンラーニングを促す環境、最終的な「医療サービスの質」とどのように結びついているのかが分析されました。
ここでいうアンラーニングを促す環境とは、組織に根付いた価値観や行動、当たり前だと思われていることを見直すための基盤を指します。具体的には、既存のものの見方を点検する「レンズの点検」、誤った習慣や考え方を変えていく「個人習慣の変容」、新しい理解を実際の業務に組み込んで定着させる「理解の定着」という三つの要素で構成されます。
分析の結果、明らかになったのは、技術知の水準が高い組織ほど、そして医師・患者知の水準が高い組織ほど、アンラーニングを促す環境が整っているという関係でした。これは、どちらかの知識に偏るのではなく、両方の知識を高いレベルで蓄積している組織において、既存のやり方を見直そうという機運が高まることを示唆しています。
優れた技術を持っていても、それを患者との関係性の中でどう生かすかを考えなければなりませんし、逆もまた然りです。両方の視点があるからこそ、現状の課題が見えやすくなり、見直しの必要性が認識されるのかもしれません。
このアンラーニングを促す環境が整っている組織ほど、医療サービスの質が高まるという結果も得られました。アンラーニングの環境は、技術知と関係知という二つの異なる知識が対立するのではなく、互いに補完し合いながら、より良いサービスへと統合されていくための触媒として機能しているように見えます。古い前提やどちらか一方に偏った慣習を手放すことで、新しい技術を豊かな人間関係の中で生かしたり、深い人間関係から得られた気づきを技術開発にフィードバックしたりといった、創造的な循環が生まれるのです。
特に、アンラーニングを構成する三つの要素の中では「理解の定着」、すなわち新しいやり方を実際の業務やプロジェクトに落とし込み、組織全体で共有していくプロセスが、質の向上に強く結びついていました。このことから、アンラーニングは、気づきや個人の態度の変化に留まらず、組織の仕組みとして新しい理解を根付かせていく実践が鍵となることがうかがえます。
アンラーニングはダブルループ学習と結びつく
アンラーニングが、組織の中にある異なる種類の知識を統合する働きを持つことが見えてきました。続いては、組織の「学び方」に目を向けてみましょう。
組織の学習は、一枚岩ではありません。一つは、設定された目標や既存のルールの中で間違いを正していく学習です。もう一つは、その目標やルール、あるいはその背景にある前提を問い直す、より根本的な学習です。前者を「シングルループ学習」、後者を「ダブルループ学習」と呼びます。より深い次元での学習であるダブルループ学習と、アンラーニングはどのように関わっているのでしょうか。
この関係性を探るため、香港で建設プロジェクトに携わるコンサルタントや施工会社の専門家95名を対象にした調査が行われました[2]。建設業界では、プロジェクトを通じて多くの経験が蓄積されるにもかかわらず、それが組織全体の成果に結びつきにくいという課題が指摘されてきました。その一因として、過去の成功体験や確立された手順から抜け出せない、アンラーニングの不足が挙げられます。
この調査では、組織が実践している学習のタイプ(シングルループ学習/ダブルループ学習)とアンラーニングの実践度合いが、サービス品質や利益、コスト目標の達成といった組織の成果にどう結びつくのかが検証されました。
分析を進めると、ダブルループ学習とアンラーニングの間に強い結びつきがあることがわかりました。特に、「現行の実務を評価し、新しいアプローチを採用する」といった、前提を問い直す学習は、顧客の関心事や利用可能な技術に関する古い信念を手放したり、開発の進め方やフィードバックの活用法といった既存のルーティンを変革したりするアンラーニングの動きと並行して起こりやすいことが確認されたのです。一方で、シングルループ学習とアンラーニングの間には、そのような関連は見られませんでした。
組織の成果との関係に目を向けると、この構造は一層はっきりと浮かび上がってきます。組織の成果を有意に高めていたのは、ダブルループ学習とアンラーニングが組み合わさって作用した場合でした。
例えば、利益目標の達成という成果は、「根本原因を特定する」や「新しいアプローチを採用する」といったダブルループ学習が、「顧客の本当の要求を再認識する」や「利用可能な技術に関する思い込みを捨てる」といった信念のアンラーニングと同時に実践されることで、より高まるという関係が見いだされました。シングルループ学習とアンラーニングの組み合わせでは、このような成果への好ましい作用は見られませんでした。
この結果が意味するものを考えてみましょう。シングルループ学習は、既存の前提やルールの中で効率的に問題を解決しようとする学びです。そのため、その前提自体を疑い、手放すことを求めるアンラーニングとは、そもそも相性が良くないのかもしれません。日々の細かな修正には、過去のやり方を捨てる必要はないからです。
それに対して、ダブルループ学習は、まさにその前提自体を問い直す学習です。古いやり方が通用しなくなった根本原因を探り、新しいやり方を模索するプロセスでは、過去の信念や慣習を手放すアンラーニングが不可欠なパートナーとなります。この二つが手を取り合うことで、組織は表面的な改善に留まらない根本的な変革を遂げることができ、それが利益やコストといった実質的な成果に結びついていくのです。
危機管理の整備を最も促すのはアンラーニング
ここまでは、組織が平時において、その内部の知識をまとめたり、学習の質を高めたりする上でアンラーニングがどのように働くかを見てきました。しかし、組織を取り巻く環境は常に穏やかであるとは限りません。時には、事業の存続を揺るがすような予期せぬ危機に直面することもあります。このような不確実な事態への「備え」、すなわち危機管理という観点からアンラーニングを捉え直すと、どのような側面が見えてくるでしょうか。
イスラエル国内の営利・非営利組織を含む82の組織を対象に、どのような経営の志向が危機への備えを促すのかを調べた調査があります[3]。
この調査では、各組織の経営志向が、人材マネジメント、組織構造、戦略、エンジニアリング、アンラーニングという五つの側面から測定されました。そして、これらの志向が、危機管理計画の策定や対応手順の整備といった、組織の危機準備度とどう関連しているのかが分析されました。ここでいうアンラーニング能力とは、組織が重要な目標を見直す頻度や、目標を達成した際に自社の成功の論理を再考する姿勢などを通じて測られています。
回帰分析によって、五つの経営志向が危機準備度をどの程度説明できるかが検証された結果、三つの志向が有意な関連を持つことがわかりました。それは、人材を尊重し多様な意見を許容する「人材マネジメント志向」、ビジョンを持ち環境に適応しようとする「戦略志向」、そして「アンラーニング能力」でした。
中でも、危機準備度の高さを最も強く予測していたのが、アンラーニング能力だったのです。過去の成功体験から生まれた自社の「ビジネスの理論」を定期的に見直し、必要であればそれを手放して新しいものに作り替えていく力を持つ組織ほど、危機をあらかじめ想定し、それに備えるための計画や訓練、仕組みをきちんと整えているという関係が見いだされました。
この結果は、組織が危機に陥るメカニズムを考えると、深くうなずけるものです。多くの危機は、組織が過去の成功体験に固執し、環境の変化が発する警告のサインを見過ごすことから始まります。「これまでこのやり方でうまくいってきたのだから、これからも大丈夫だろう」という過信が、変化への対応を遅らせ、小さな問題を大きな危機へと発展させてしまうのです。
アンラーニング能力が高い組織は、このような硬直性に陥ることを自ら防ぎます。目標を達成したときこそ、その成功がなぜもたらされたのかを冷静に分析し、その成功の論理が今後も通用するのかを問い直す。このような自己修正の仕組みが組織に備わっていると、未知の危機に対しても謙虚に向き合い、万が一の事態を想定した準備を怠らない姿勢が生まれるのでしょう。アンラーニングは、平時の組織能力を高めるだけでなく、組織を未来の不確実性から守るための、いわば免疫システムのような働きも担っていると言えます。
連続的なアンラーニングが危機回避の鍵となる
アンラーニングが、危機への事前の備えを促す上で中核的な働きをすることがわかりました。視点を変えて、実際に危機に陥ってしまった組織、あるいはそれを回避できた組織の内部では、何が起きているのでしょうか。アンラーニングを、より動的なプロセスとして、危機の発生と克服の文脈で捉えてみましょう。
企業の長期的な存続は、決して容易なことではありません。ある統計によれば、米国の企業で20年間存続できるのは約1割に過ぎないとされています。多くの組織が時代の変化の中で淘汰されていく背景には、過去の学習が足かせとなって環境変化に対応できなくなる、という構造的な問題があります。この点に着目し、危機に陥った複数の企業の事例を分析した研究があります[4]。
その分析によると、業績悪化などの危機の兆候に直面した企業の多くは、当初、コスト削減や投資の延期といった、その場しのぎの対症療法に終始する傾向がありました。組織の根幹にある事業の進め方や商品構成といった前提を見直す提案が出ても、経営層はそれを真剣に受け止めず、既存のやり方に固執します。これは、アンラーニングが機能していない典型的な状態です。こうした小手先の対策が尽きたとき、組織はより深刻な事態へと追い込まれていきます。
一方で、危機からの脱却に成功した事例では、しばしばトップマネジメントの交代という、非常に抜本的な変化が起きていました。新しい経営陣は、前任者たちが囚われていた過去の成功体験や業界の常識といった「認知構造」を持っていません。そのため、社内に埋もれていた技術の可能性を再発見したり、市場の潜在的な需要に気づいたりすることができ、事業の方向性を大胆に転換させることができました。
トップの交代という荒療治によって、組織が半ば強制的にアンラーニングを経験したと見ることができます。個人の意識改革に頼るのではなく、支配的なものの見方を組織から取り除くことで、新しい学習のための道が拓かれたのです。
このことは、二つの重要な点を示しています。一つは、危機というものは、アンラーニングの欠如から生まれるということ。もう一つは、危機が深刻化してからアンラーニングを行おうとすると、トップの交代のような大きな痛みを伴う手段に頼らざるを得なくなる、ということです。
そうであるならば、組織が持続的に生き残り、成長していくために本当に求められるのは、危機に追い込まれてから慌てて過去を捨てることではありません。危機に陥る前に、平時から自らの学びを絶えず見直し、更新し続ける仕組みを組織の日常に組み込んでおくことでしょう。異論に真摯に耳を傾ける、予期せぬ出来事を学びの機会と捉える、新しい試みを「実験」と位置づけて小さな失敗を許容する。このような「連続的なアンラーニング」の実践が、組織を硬直化から守り、危機を回避する鍵となります。
脚注
[1] Cegarra-Navarro, J.-G., Cepeda-Carrion, G., and Eldridge, S. (2011). Balancing technology and physician?patient knowledge through an unlearning context. International Journal of Information Management, 31(5), 420-427.
[2] Wong, P. S. P., Cheung, S. O., Yiu, R. L. Y., and Hardie, M. (2012). The unlearning dimension of organizational learning in construction projects. International Journal of Project Management, 30, 94-104.
[3] Sheaffer, Z., and Mano-Negrin, R. (2003). Executives’ orientations as indicators of crisis management policies and practices. Journal of Management Studies, 40(2), 573-606.
[4] Nystrom, P. C., and Starbuck, W. H. (1984). To avoid organizational crises, unlearn. Organizational Dynamics, 12(4), 53-65.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。