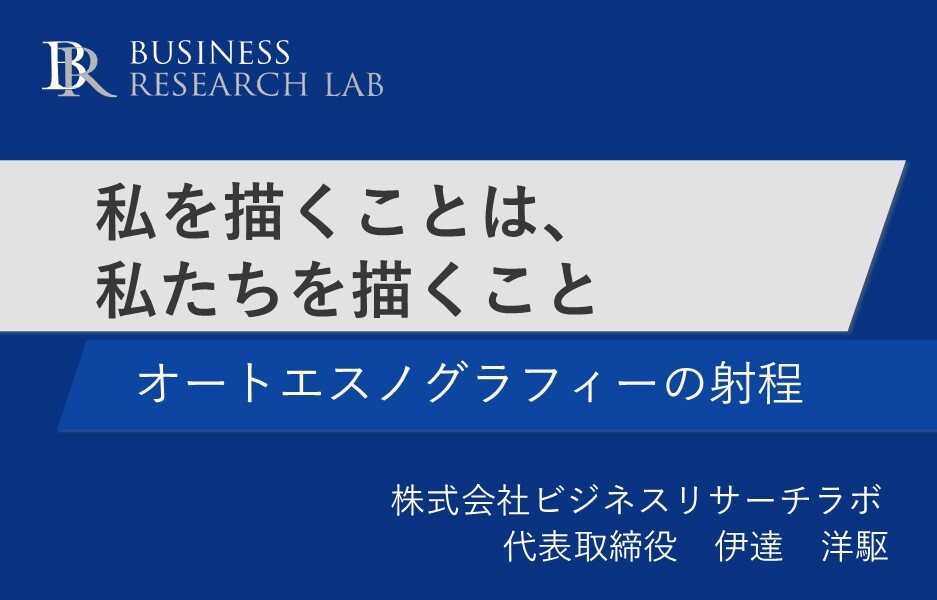2025年12月23日
私を描くことは、私たちを描くこと:オートエスノグラフィーの射程
自分の身に起きたこと、心が動いた瞬間、忘れられない記憶。私たちは皆、自分だけの物語を持っています。普段、それは個人的な体験として胸のうちにしまわれているかもしれません。しかし、その個人的な物語が、自分だけでなく、他の誰かや、私たちが生きる社会、そして文化を理解するための鍵になるとしたら、皆さんはどう感じますか。
「オートエスノグラフィー」は、自分自身の経験を深く見つめ、それを記述し、分析することを通じて、より大きな社会や文化の文脈と結びつけていく探究のアプローチです。個人の小さな物語が、どうして社会の理解につながるのでしょうか。このアプローチは、客観性を求める従来の科学とは異なり、研究者が一人の人間として自らの経験や感情、葛藤さえも探究の対象とします。そこでは、個人の声が持つ力、物語が持つ豊かさが改めて見直されます。
本コラムでは、オートエスノグラフィーという窓を通して、個人の経験が持つ可能性の広がりを探ります。自分自身の物語が、他者や世界と響き合い、社会や文化をより深く理解するためのヒントとなりうる。そんなオートエスノグラフィーの射程を、これから検討していきたいと思います。
オートエスノグラフィーは自己経験を文化理解へ架橋する方法
オートエスノグラフィーとは、どのようなものでしょうか。この言葉は、「自己(auto)」「文化(ethno)」「記述(graphy)」という三つの要素から成り立っています。自分自身の経験を素材にしながら、それがどのような文化的背景のなかで形作られたのかを、文章などの形で探究していく試み、と捉えることができます[1]。
この手法が議論され始めた1980年代、社会科学では従来の客観性への問い直しが起きました。研究者は本当に自らの価値観から自由になれるのかという反省です。研究者の存在が調査に作用を及ぼすことは避けられないという認識から、主観性を隠すのではなく探究の資源として受け止め、自己の経験に根ざす研究が模索されました。
オートエスノグラフィーを実践する際、そのプロセスは個人的な回想と、文化を理解するための民族誌的な手法が組み合わさります。書き手は自身の過去を振り返り、人生の転機となった出来事などを中心に、日記や写真を手がかりに記憶を紡いでいきます。
しかし、それは自分語りには留まりません。その経験を、社会や文化という広い文脈で捉え直す作業が伴います。例えば、人々を観察し、話を聞く民族誌の手法を援用し、自分の経験に現れる感情や語りのパターンが、所属する集団や社会の特徴とどう結びつくかを分析します。
書き上げられた成果物も独特です。読者がその場にいるかのように対話や情景を生き生きと描写する部分(ショーイング)と、引いた視点から状況を解説し理解を助ける部分(テリング)が織り交ぜられます。これによって、読者は書き手の経験を追体験しながら、その背後にある文化的な意味を理解できるのです。
このようなアプローチの価値は、統計的な一般化とは異なる物差しで測られます。問われるのは、その記述が「もっともらしいか」、要するに読者が「そうあり得ることだ」と感じられるか、そしてその物語が他者との対話や読者自身の生活を豊かにするために「役に立つか」という点です。書き手の経験が読者自身の経験と響き合い、他者理解を深めるきっかけとなること。そこに、このアプローチの価値が見出されます。
オートエスノグラフィーは自己語りで組織文化を照らす方法
この自己を探求するアプローチは、私たちが日常的に身を置く「組織」という舞台で、とりわけ豊かな光景を映し出します。組織には、規則や目標だけでなく、独特の慣習や人間関係といった、言葉にしにくい「文化」が存在します。オートエスノグラフィーは、組織の一員としての個人的な経験を通して、この目に見えない組織文化を描き出す手法となり得ます[2]。
組織におけるこの手法も、歴史のなかで言葉のニュアンスを変えてきました。当初は内部者による文化記述の正当性を主張するものでしたが、次第に自己の経験と文化の記述との相互性が意識され、現在では自己の語りを前面に出すスタイルが主流です。
組織における経験を語る際、研究者がとる立場によって、その内容は大きく三つに分類できます。一つは、感情や身体感覚で読者の心に訴える「情動的解釈主義」。二つ目は、組織の一員として自己経験を客観的に分析し、理論的考察へつなげる「分析的リアリズム」。三つ目は、個人の経験から組織内の権力構造や矛盾を可視化する「ポストモダン批判」です。これらは排他的なものではなく、重なり合うこともあります。
もちろん、このアプローチには、自己中心的で分析が甘いのではないかといった批判も寄せられます。しかし擁護する立場からは、これまで声を発することが難しかった人々の経験を可視化する手段としての意義が強調されます。個人の経験は、それが組織文化のある側面を照らし出す限りにおいて、探究の対象として有効であるという考え方です。
組織を舞台にした実践には、いくつかの典型的な形があります。大学の研究者が自らの経験を通して大学組織の現実を描き出すことや、過去の職場経験を振り返り、当時の組織規範を照らし出すこと。また、研究者と実務家が協働し、当事者の経験と学術的視点を往復させながら一つの作品を共著する「共同制作型」も考えられます。
この手法を用いる上で、倫理的な配慮は避けて通れません。自己の物語を語ることは、必然的に同僚や組織を記述に巻き込むため、プライバシーの保護はもちろん、関係者への十分な配慮と対話が求められます。書き手自身が経験を公にすることのリスクも自覚し、時には表現を工夫するなどの編集上の判断も必要になるでしょう。
オートエスノグラフィーは個人の語りで組織文化と権力関係を批判的に照らす方法
組織文化を照らし出す自己の語りは、時にその内部に潜む権力の構造をも浮かび上がらせます。組織は、人々が協力する場であると同時に、様々な力学が働く政治的な空間でもあります。オートエスノグラフィーは、一個人の経験という視点を通して、組織のなかで何が「当たり前」とされ、誰の声が通りやすいのかを、批判的に探究する力を持っています[3]。
近年、このアプローチは、ビジネス領域から差別やハラスメントといった課題まで、また民間企業から行政まで、多様な組織とテーマで実践が広がっています。これは、個人の経験を掘り下げる手法が、多様な組織の複雑な現実を解き明かす上で有効だと認識され始めていることの現れでしょう。
ここでの探究の中心にあるのは、「個人と組織の関係」です。組織における経験を語ることは、組織の制度や文化が、一人の人間のアイデンティティや感情、健康にどう作用するのかを具体的に明らかにします。例えば、うつや不安による休職経験を日記から分析した研究では、組織環境の中で個人のアイデンティティが揺らぎ、再構築される過程が克明に描かれています。
こうした個人の語りは、組織内の見えにくい権力関係や規範を可視化します。イギリスの大学のリーダーシップを、ある教員の視点から旧ソ連の権力構造と比較し、改革の美名のもとで進む権力闘争を自己の物語を通して照射した研究があります。また、二人の女性研究者が対話形式で互いの経験を語り合い、制度の変容がもたらすジェンダーにもとづく不均衡を批判的に論じた実践もあります。個人の経験は、社会的な文脈と結びつくことで、制度的な問題を鋭くえぐり出す力を持つのです。
このような批判的な探究は、必然的に倫理的な難しさを伴います。特に組織内の軋轢や規範から外れた経験を語る場合、書き手や関係者をリスクに晒す可能性があります。ある研究では、同性愛嫌悪が個人の健康に及ぼす作用が、深刻な個人的被害の経験を通して論じられました。書き手は自身を開示しつつ、他者が特定されることを避けるために細心の配慮を払っています。
このアプローチの実践は、研究成果の流通にも政治的な側面をもたらします。ある学術誌では、著者の匿名出版の希望をめぐり、出版社と法的な開示可能性について交渉が必要となりました。個人の経験を語る行為が、研究者と周囲を社会的なリスクに晒しうる現実が、そこに示されています。
オートエスノグラフィーは生活と研究を結ぶ協働的実践である
個人の経験を深く掘り下げる探究は、一人だけで完結するとは限りません。他者との対話を通じて豊かになる、協働的な営みとしての側面も持っています。この視点は、研究を客観的な知識生産のプロセスとしてだけでなく、人々の生活と結びついた、コミュニティを形成していく実践として捉え直すものです[4]。
根底には、研究は研究者の人生や経験と切り離せないという前提があります。この研究と生活の不可分性を探究の中心に据え、自己をデータとして「自己と他者のつながり」を理解しようとします。自己は社会から孤立して存在するのではなく、他者との関係性の網の目のなかに置かれているからです。
オートエスノグラフィーは、一人の書き手によるものが主流ですが、近年、複数の研究者が共同で取り組む実践が増えています。そのモデルは大きく二つ。一つは、誰かが書いた文章に次の人が書き足す「逐次型」。もう一つは、共通テーマを決め、各自が独立して記述し、持ち寄って共有・対話する「並行型」です。
ある実践例では、三名の女性教員が並行型の協働に取り組みました。彼女たちはテーマに合意し、各自が記述を作成。その後、定期的に集まって文章を共有し、対話しました。この対話自体もデータとし、「記述(発散)」と「対話(収束)」のサイクルを繰り返すことで、一人では得られない多角的な理解を深めていきました。
このような協働的なプロセスは有益です。対話を通じて個人の経験がより広い文化的文脈と結びつけられやすくなります。また、同じような経験を持つ他者と語り合う場は、書き手にとって精神的な支えとなり、コミュニティ形成につながります。研究プロセスが、参加者の学びや成長、さらには制度変革への主体的な関わりへとつながる可能性もあります。
協働オートエスノグラフィーは、大学教員のアイデンティティ形成、母子の経験、人種やジェンダーの問題など、多様なテーマを探究してきました。個人の語りが他者の語りと交差するとき、そこには足し算以上の、豊かで複雑な知が生成されます。
オートエスノグラフィーは自己経験を社会文脈へ結び評価基準を再定義する
個人の経験から社会を読み解こうとする試みは、学術の世界でどのように受け入れられるのでしょうか。オートエスノグラフィーは、客観性や再現可能性といった従来の科学的な研究評価の基準としばしば緊張関係に立たされます。
ある研究者が経験した論文の投稿プロセスは、この問題を象徴的に物語っています[5]。大学教員としての自身の経験を記述した論文は、三つの雑誌で不採録となり、四つ目でようやく採択されるという困難な道のりを辿りました。その過程で寄せられたコメントは、このアプローチがどのような評価の目に晒されるかを示していました。
ある査読者は、語りを認めつつも「研究としての厳密さ」や「信頼性・妥当性の手続きの明示」を求めました。これは伝統的な質的研究の評価観にもとづく要求です。別の査読者はより懐疑的で、「自己を研究対象とすることは賢明ではない」「『私』が多すぎる」と主張し、客観的なデータを求めました。
これに対して著者は、オートエスノグラフィーに伝統的な評価基準を機械的に当てはめることは適切ではないと応答します。そして評価の軸足を、研究の「後から」手続きをチェックするのではなく、研究の「過程」で書き手がいかに誠実に探究に取り組んだかに移すべきだと論じました。その上で、社会的な貢献、美的価値、自己省察の深さ、読者への作用、経験の厚みといった、別の評価基準を提示します。
「データ源が自己のみである」という批判には、個人の経験の記述は社会的な経験の記述でもあるという考え方で反論します。個人の経験は、その人が生きる社会の制度や文化から切り離しては存在し得ないからです。したがって、オートエスノグラフィーは、自己という窓を通して社会を照らし出す試みであり、文化や制度の文脈へと必然的につながると主張するのです。
この経験は、新しいアプローチが既存の研究文化の中で正当性を獲得していくことの難しさを示唆しています。しかし同時に、一枚岩の基準に固執するのではなく、研究のジャンルに応じた多元的な評価のあり方を模索する必要性を教えてくれます。個人と文化をつなぐ語りが学術的な知として育っていくためには、書き手と評価する側の双方による、粘り強い対話が不可欠です。
脚注
[1] Ellis, C., Adams, T. E., and Bochner, A. P. (2010). Autoethnography: An overview. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 12(1), 10.
[2] Doloriert, C., and Sambrook, S. (2012). Organisational autoethnography. Journal of Organizational Ethnography, 1(1), 83-95.
[3] Sambrook, S., and Herrmann, A. F. (2018). Organisational autoethnography: Possibilities, politics and pitfalls. Journal of Organizational Ethnography, 7(3), 222-234.
[4] Ngunjiri, F. W., Hernandez, K. C., and Chang, H. (2010). Living autoethnography: Connecting life and research. Journal of Research Practice, 6(1), E1.
[5] Holt, N. L. (2003). Representation, legitimation, and autoethnography: An autoethnographic writing story. International Journal of Qualitative Methods, 2(1), 18-28.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。