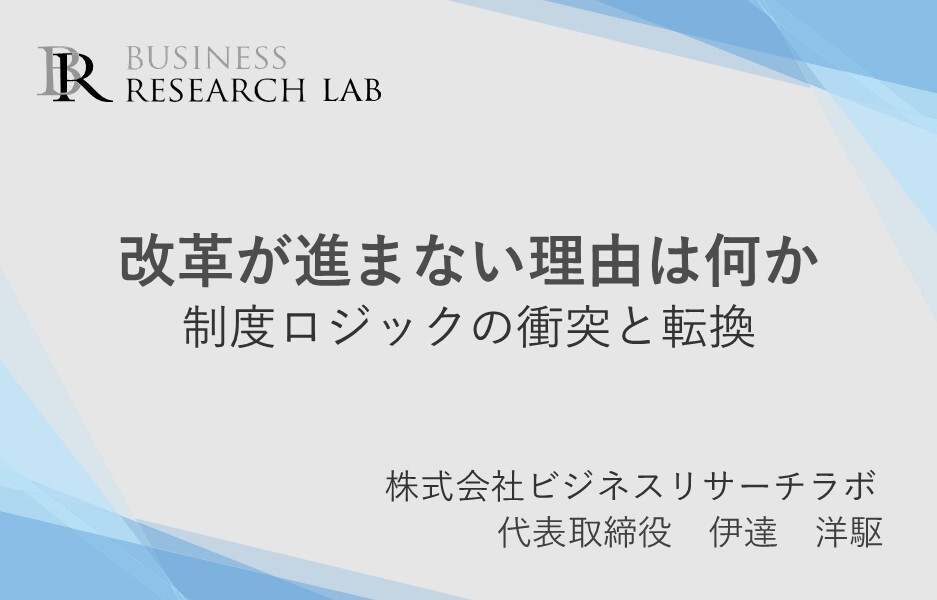2025年12月23日
改革が進まない理由は何か:制度ロジックの衝突と転換
私たちの社会や組織は、時に巨大な船のように、目には見えない潮流や風に動かされています。その潮流や風の正体は、法律や規則といった明文化されたものだけではありません。その場の「当たり前」として人々の間で共有されている価値観や物事の考え方、信条のほうが、私たちの行動や意思決定を方向づけていることがあります。
このような社会や組織に深く根ざした、実践と象徴の組み合わせを「制度ロジック」と呼びます。それは、人々が世界をどのように認識し、何が正しく、何が道理にかなっているかを判断するための、いわば「思考のOS」のようなものです。
このOSは、一つだけではありません。一つの組織の中に、あるいは一つの社会の中に、複数の異なるOSが同時に稼働していることが珍しくありません。それらのOSが互いに相容れない目的や価値観を持っているとき、衝突が起こります。あるOSがバージョンアップし、新しいOSへと置き換わっていくこともあります。このような制度ロジックの衝突や転換が織りなす力学は、私たちの身の回りで起こる様々な出来事の背後にあるメカニズムを解き明かす鍵を握っています。
例えば、鳴り物入りで始まった改革がなぜか現場でうまく進まない、あるいは、失敗したはずの政策が意図せずして社会に大きな変化をもたらす、といった現象です。本コラムでは、学術研究を手がかりに、制度ロジックがぶつかり合い、移り変わっていく過程を検討します。
制度ロジックの衝突が医療IT導入の遅延を招いた
英国の国民保健サービス(NHS)において、かつて壮大な国家プロジェクトが立ち上げられました。全国の医療機関をネットワークで結び、すべての国民の診療記録を電子化して共有し、予約や処方もオンラインで行えるようにする「国家的ITプログラム(NPfIT)」です。これは、21世紀の医療を実現するための試みであり、技術的には大きな可能性を秘めていました。
しかし、この巨大プロジェクトは深刻な遅延に見舞われます。その原因は、コンピューターの技術的な課題や予算の問題だけではありませんでした。医療という現場に渦巻く、複数の異なる「正しさ」の衝突に、その根源があったのです。
このプロジェクトが進められた医療現場には、歴史的に形成されてきた複数の制度ロジックが併存していました。
一つは、医師をはじめとする専門職の自律性を尊重する「専門職のロジック」です。この考え方では、個々の患者に最善の医療を提供するための臨床的な判断が最優先されます。二つ目は、1970年代以降に強まった、組織運営の効率性や成果、規律を求める「経営主義のロジック」です。ここでは、限られた資源をいかに効率よく配分し、コストを管理するかが問われます。三つ目は、ITベンダーなど民間企業が持ち込む「市場のロジック」で、契約の遵守や利益の確保が行動原理となります。最後に、近年になって加わった、患者自身の選択権や公共全体の価値を前面に押し出す「公共価値のロジック」です。
NPfITの導入は、これらの異なる価値観がぶつかり合う舞台となりました。例えば、オンラインで患者が自由に病院や医師を選べる電子予約システムは、「公共価値のロジック」から見れば、患者の利便性を高める仕組みです。しかし、「専門職のロジック」に立つ医師たちからすれば、これは看過できない問題でした。医療の質に関する十分な情報を持たない患者が安易に選択を行うことへの懸念や、自分たちの診断や治療の裁量が損なわれることへの抵抗感が生まれたのです。
一方で、政府や経営層は「経営主義のロジック」に基づき、過去の無駄なIT投資をなくし、全国標準のシステムを導入することで効率化を図ろうとします。ITベンダーは「市場のロジック」に従い、契約通りにシステムを納入することを目指します。
ある研究では、この状況を解明するために、2001年から5年間にわたり、臨床医、病院の管理者、IT企業の担当者など、立場のことなる120人の関係者に繰り返し聞き取り調査を行いました[1]。政策文書や監査報告といった資料も分析の対象とされました。その結果、描き出されたのは、それぞれのロジックが自らの「正しさ」を主張し合い、互いに譲らないことで、現場に混乱と不信感を生み出している姿でした。
中央で設計された画一的な計画は、地域や病院ごとの多様な実務慣行や複雑な契約関係といった現場の実態と乖離していました。現場の医師たちは、このプロジェクトを「上からの押し付け」と感じ、その導入に協力的ではありませんでした。結果、プロジェクトの目的や意味づけをめぐる争いが生じ、関係者の納得を得ることができないまま、計画は停滞していったのです。
この事例は、新しい制度や技術を導入する際、その技術的な優劣だけでなく、その背景にある価値観が、現場に根付く既存の価値観とどのように相互作用するのかを洞察することの必要性を物語っています。
制度ロジックは改革注目で語彙変化を通じ転換した
先ほどは、複数の制度ロジックが衝突し、改革が停滞する様子を見てきました。そこでは、それぞれの価値観が固定化され、互いに譲らない状況が描かれていました。では、あるロジックが力を失い、新しいロジックが支配的になっていく「転換」は、どのような仕組みで起こるのでしょうか。法律や規制といった強制的な力がなくても、社会の「当たり前」が変わることがあります。ここでは、ある大きな出来事に対する社会的な関心が、人々の使う「言葉」を変化させ、それがやがて社会全体の認識の枠組みを書き換えていく過程を追跡した研究をみていきます[2]。
舞台は、1990年代前半のアメリカです。当時、クリントン政権は国民皆保険を目指す大がかりな医療保険改革を打ち出しました。この改革案は、議会での激しい議論の末、最終的には法制化されることなく頓挫します。しかし、この「失敗した改革」は、意図しない形でアメリカの医療界に変化をもたらしました。
その変化のプロセスを解明するため、ある研究では、1991年から1995年にかけて発行された病院業界の主要な専門誌の記事、399本を分析しました。注目したのは、記事の中で「改革」や「マネジド・ケア」といった言葉が、時間の経過とともにどのように使われ、その意味合いがどう変わっていったかです。
分析が始まった改革の議論以前の時期、記事の中で「改革」という言葉は、主に政府が主導する「政治的な提案」を指すものとして使われていました。しかし、大統領選挙を経て、改革案の議論が本格化すると、状況は変化し始めます。人々の関心は、政治の舞台で議論される抽象的なモデルから、HMO(健康維持組織)と呼ばれる医療保険プランの普及や、病院同士の統合といった、市場で現実に起きている動きへと移っていきました。
この過程で、一つの言葉の意味が拡張されます。それは「マネジド・ケア」という言葉です。もともとこの言葉は、HMOのような特定の医療保険の形態を指す専門用語でした。ところが、改革への関心が高まる中で、この言葉は組織形態を指すだけでなく、「医療業界全体を覆う新しい秩序」や「変化を駆動する力」といった、大きな意味合いで使われるようになっていきました。
改革法案が議会で否決され、政治的な取り組みが終わりを迎えた後、興味深い現象が起きます。政治主導の改革は消え去ったにもかかわらず、専門誌の記事では「改革」という言葉が使われ続けました。ただし、その意味はすっかり変わっていました。今や「改革」とは、政府によるものではなく、「市場の力によって駆動される変化」を指す言葉として定着したのです。そして、「マネジド・ケア」は、コスト管理と効率性を第一とする、医療界の新しい支配的な価値観、すなわち新しい制度ロジックを指す言葉として確立されました。
この一連の出来事が描き出すのは、制度ロジックが転換していく一つの道筋です。大きな社会的イベントは、人々の注意を特定の現象に集めます。その中で、人々は現実を理解し、意味づけるための新しい言葉を見つけ出し、共有するようになります。言葉の使われ方が変わることは、表現の変化にとどまりません。それは、何が問題で、何が解決策なのかという、人々の認識の枠組みそのものが変わることを意味します。
この事例では、政治改革の失敗という出来事が、結果的に市場主導のロジックを医療界に根付かせるという、逆説的な帰結をもたらしました。制度の転換は、必ずしも誰かの意図通りに進むのではなく、社会的な注意とそれに伴う言葉の変化というプロセスを通じて進行することがあるのです。
制度ロジックの転換が出版業の組織構造選択を反転させた
言葉の変化を通じて新しい制度ロジックが生まれる過程を見てきました。では、ひとたび社会や業界の支配的なロジックが転換すると、個々の企業の意思決定にどのような変化がもたらされるのでしょうか。例えば、どのような組織構造が「優れている」と見なされるか、といった企業のあり方までもが変わってしまうことはあるのでしょうか。ここでは、ある業界で支配的な価値観が移り変わったことで、企業の成功法則や組織のあり方までもが反転してしまった事例を掘り下げていきます[3]。
その舞台となったのは、1958年から1990年にかけての米国の高等教育向け出版業界です。この30年あまりの間に、この業界は職人的な気風の漂う世界から、現代的なビジネスの世界へと姿を変えました。
この変化の背景には、二つの異なる制度ロジックの交代劇がありました。1970年代半ばまでこの業界を支配していたのは、「編集ロジック」と呼べるものでした。これは、「出版は専門的で文化的な営みである」という価値観に基づいています。創業編集者の個人的な名声や、著者との固い信頼関係がビジネスの源泉であり、組織は比較的小規模で、それぞれの個性が尊重されるのが当たり前でした。
しかし、1970年代半ばを境に、業界は「市場ロジック」の時代へと突入します。これは、「出版はビジネスである」という価値観です。市場シェア、利益率、他社の買収による規模の拡大といった事柄が経営の中心的な関心事となりました。個々の編集者の個性よりも、CEOの経営判断や株主の意向が組織の方向性を決定する、企業的な組織のあり方が正当なものと見なされるようになりました。
ある研究では、このロジックの転換が、出版社の組織構造の選択に与えた変化を検証しました。766社の中から無作為に抽出した230社の出版社を対象に、33年間のデータを追跡し、どのような要因が、伝統的な組織から多部門制(M-form)という近代的な企業組織への移行を促したのかを分析しました。そして、時代を「編集ロジック期」と「市場ロジック期」の二つに分けて比較することで、興味深い事実が浮かび上がりました。組織のあり方を決定づける要因の効果が、時代の変化とともに逆転していたのです。
例えば、「編集者個人のブランド力」について見てみましょう。編集ロジックの時代において、強い個性とネットワークを持つスター編集者の存在は、その出版社の独立性を象徴するものであり、企業的な組織への移行を「抑制」する力として働いていました。しかし、市場ロジックの時代に入ると、その意味合いは一変します。高いブランド力を持つ編集部門は、むしろ他社からの買収の格好のターゲットとなり、企業的な組織の一部に組み込まれることを「促進」する要因へと変わってしまったのです。
もう一つ、「販売網のあり方」も同様の反転を見せました。編集ロジックの時代には、販売を外部の流通業者に委託することはごく一般的な慣行でした。しかし、市場ロジックの下では、自社で販売チャネルをコントロールすることが競争上有利になります。その結果、販売を外部に依存している出版社ほど、自前で販売機能を持つ企業的な組織へと移行する強い圧力を受けるようになりました。
この分析が明らかにしたのは、組織はただ客観的な環境に適応しているわけではないということです。支配的な制度ロジックという文化的なフィルターが、経営者が環境の中のどの情報に注意を払い、それをどう解釈し、どのような戦略を「合理的」だと判断するかを規定しています。競争の激しさといった同じ経済的な事実を前にしても、編集ロジックの時代には問題とされなかったことが、市場ロジックの時代には組織の存亡をかけた課題として認識されるようになります。
文化的な価値観の転換が、経済合理性の基準を書き換え、組織のあり方までも変えてしまう。この過程が、歴史的なデータから描き出されています。
制度ロジック研究の盲点を補う枠組みを提示
これまで、制度ロジックが衝突し(医療IT)、転換し(クリントン改革)、組織のあり方を反転させる(出版業)という、比較的大きなスケールの現象を見てきました。これらの物語は、社会や組織を動かす見えざる力の存在を教えてくれます。
しかし、ここで一つの問いが浮かび上がります。これらのマクロな変化は、日々の現場で、どのような人々のやり取りから生まれてくるのでしょうか。価値観の異なる人々が対立したとき、いかに互いを説得し、あるいは妥協点を見出し、新しい「当たり前」を築き上げていくのでしょうか。こうしたミクロな相互作用に光を当てるための新しい理論的な視座を紹介します[4]。
制度ロジックという考え方は、社会の大きな構造や歴史的な変化を捉える上で強力ですが、いくつかの点を見過ごしがちである、という指摘があります。例えば、現場で人々が繰り広げる議論や交渉の具体的な中身、正しさをめぐる闘いの詳細なプロセス、その背後にある道徳的な信念、そして、議論の場で使われる報告書やデータ、技術といった「モノ」が果たす働きなどです。こうした、いわば制度が生まれる瞬間の微視的なメカニズムを捉えるための道具立てが、これまでの枠組みには不足していました。
この課題に応えるものとして、フランスの社会学から生まれた一つの考え方が紹介されています。それは、人々が日常生活の中で、自らの行動を正当化したり、他者を説得したりする際に、無意識のうちにいくつかの異なる「価値の世界」の基準を使い分けている、という洞察です。この理論は、人々が頼りにする「正しさ」の源泉として、主に六つの「世界」を提示します。
一つ目は、創造性やひらめきを尊ぶ「霊感の世界」。二つ目は、伝統や人間関係、信頼を重んじる「家政の世界」。三つ目は、世間的な評判や知名度が価値を持つ「名声の世界」。四つ目は、公共の利益やルールを第一とする「市民の世界」。五つ目は、価格や競争、利益を基準とする「市場の世界」。六つ目は、効率性や客観的なデータ、専門知識を絶対とする「産業の世界」です。
重要なのは、対立や問題が生じたとき、人々はこれらの異なる「世界」の物差しを持ち出して、どちらの主張がより正当であるかを争うという点です。この争いは「テスト」と呼ばれます。例えば、ある新製品の開発をめぐって、開発チームは「産業の世界」の基準(技術的な完成度)でその価値を主張するかもしれません。一方で、営業チームは「市場の世界」の基準(売上予測)で判断を下そうとします。経営者は「市民の世界」の基準(企業の社会的責任)を持ち出すかもしれません。
このような「テスト」の結果、必ずしも白黒がつくわけではありません。ある一つの世界の論理が完全に勝利することもあれば、それぞれの領域を侵さないように「住み分け」がなされることもあります。あるいは、双方の「正しさ」を部分的に取り入れた、新しい共通のルールや評価指標といった「妥協」の産物が生まれることもあります。この妥協の産物は、しばしば報告書のフォーマットや会議の運営方法、新しいITシステムといった具体的な「モノ」や「手続き」として結晶化し、組織の新しい現実となっていきます。
この「価値の世界」という考え方を通して見ると、制度ロジックが変化していくプロセスが、より生々しい人間の営みとして見えてきます。マクロなレベルでのロジックの転換は、日々の無数の「テスト」と「妥協」の積み重ねの結果として生じているのかもしれません。この視点は、大きな制度の動きと、現場にいる一人ひとりの行為とをつなぐ、貴重な架け橋となります。
脚注
[1] Currie, W. L., and Guah, M. W. (2007). Conflicting institutional logics: A national programme for IT in the organisational field of healthcare. Journal of Information Technology, 22, 235-247.
[2] Nigam, A., and Ocasio, W. (2010). Event attention, environmental sensemaking, and change in institutional logics: An inductive analysis of the effects of public attention to Clinton’s health care reform initiative. Organization Science, 21(4), 823-841.
[3] Thornton, P. H. (2002). The rise of the corporation in a craft industry: Conflict and conformity in institutional logics. Academy of Management Journal, 45(1), 81-101.
[4] Cloutier, C., and Langley, A. (2013). The logic of institutional logics: Insights from French pragmatist sociology. Journal of Management Inquiry, 22(4), 360-380.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。