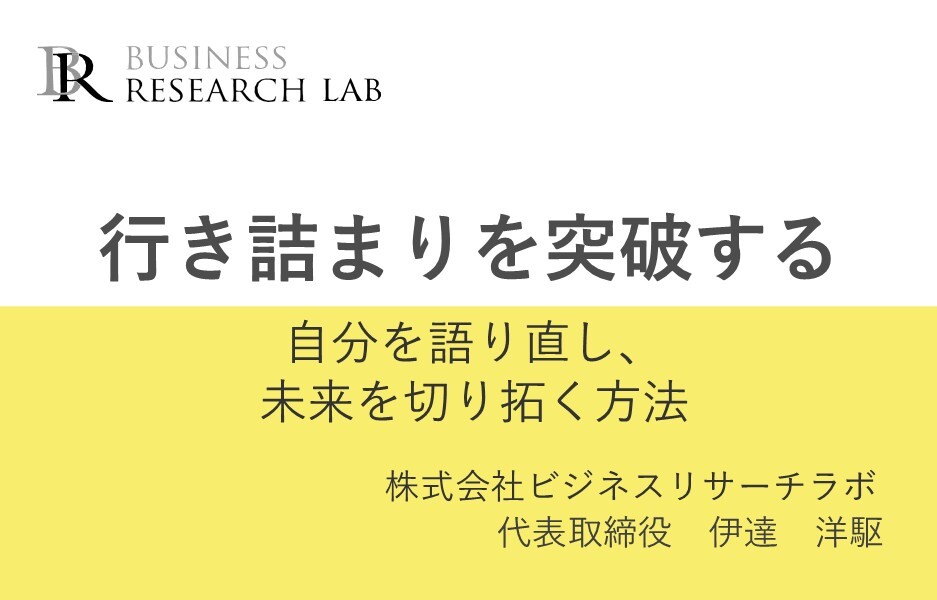2025年12月23日
行き詰まりを突破する:自分を語り直し、未来を切り拓く方法
私たちの人生は、予期せぬ困難や脅威と無縁ではいられません。キャリアの行き詰まり、人間関係の軋轢、あるいは自らの尊厳が揺るがされるような出来事。そうした壁に突き当たったとき、私たちは無力感に苛まれ、未来への希望を見失いそうになります。困難や脅威は、一刻も早く取り除きたい「障害物」です。
しかし、その見方を少しだけ変えることができるとしたら、良いと思いませんか。それらの困難が、内なる強さを引き出し、本当に大切な価値観を再発見させ、「新しい自分」を形作るきっかけになるとしたら。脅威は、望ましい自己へと向かう治癒的で創造的なプロセスの出発点にもなりうるかもしれません。傷つき、迷いながらも、自分自身の物語を再び紡ぎ直そうとする、人間のしなやかな営みです。
本コラムでは、人々が脅威や困難と対峙し、自己を再構築していくプロセスを探求します。プロスポーツ選手、職場いじめの経験者、組織で生きる管理職、困難な状況で発揮される「勇気」。様々な角度から光を当てることで、人がより統合された自己へと向かう道のりの複雑さと豊かさを検討していきましょう。
脅威は除去対象でなく望ましい自己を語る資源となる
人生で直面する困難は、見方を変えれば自己を形作る材料になりうるのかもしれません。その一つの姿を、極限の環境に身を置くプロスポーツ選手たちの世界から見ていきましょう。ある質的調査が、英国のプロ・ラグビーリーグに所属する選手たちの語りに耳を傾けました[1]。この調査の関心は、選手たちが自らの職業的アイデンティティに対する「脅威」を、望ましい自己像を作り上げるための資源としてどのように用いているのかを明らかにすることにありました。
調査は、あるクラブチームに研究者が約一年間滞在し、日常を観察するとともに、一軍の全選手を含むクラブ関係者47名にインタビューを行うという手法で進められました。選手たちは、幼い頃からの夢を叶え、好きなことで生計を立てている喜びを語る一方、食事や睡眠といった生活の隅々までがクラブの規律によって管理される窮屈さも認識していました。「ラグビー選手である自分」は、喜びと拘束が入り混じった複雑な感覚を伴うものでした。
彼らの語りから、共通する三つの大きな「脅威」が浮かび上がってきました。一つ目は「短い選手生命」です。キャリアは三十歳前後で終わり、契約は実質的にいつでも打ち切られうるという不安定さが常にありました。二つ目は「負傷」です。激しい接触を伴う競技において、怪我は「明日にもキャリアが終わるかもしれない」という恒常的な現実でした。三つ目は「パフォーマンスと選抜」です。絶え間ない競争と期待が、自分を点検し続けなければならないというプレッシャーを生み出していました。
興味深いのは、選手たちがこれらの脅威にどう向き合っていたかです。彼らは脅威にただ怯えるのではなく、それを利用して「プロのラグビー選手らしい自己」を語っていたのです。
「短い選手生命」という脅威に対し、多くは将来設計を語るのを避け、「今この瞬間に集中する」という現在への没入を強調しました。この語り口は、将来の不安から目をそらし、今現在の仕事へ全身全霊で打ち込む姿勢を際立たせます。それは「熟考より行動」という、その競技の場でよしとされるあり方とも合致していました。
「負傷」という脅威に対しては、「タフであること」や「自分の身体はプロとしての道具だ」といった、自律的なプロフェッショナリズムを強調する語りが用いられました。怪我の痛みや身体の脆さを、自己犠牲やチームへの献身といった言葉で意味づけ直し、不安を乗り越えようとしていたのです。
「パフォーマンスと選抜」という脅威は、「試合に勝つ」「タイトルを獲得する」といった、勝利や栄光を強く求める物語へと転化されていました。達成が難しい現実から目をそらすと同時に、終わりなき努力と上を目指し続ける姿勢を正当化する、未来に向けた自己像が語られていました。
ここから見えてくるのは、脅威が外部からやってくる客観的な出来事ではないということです。選手たちは、数ある不安の中からこの三つの「語りやすい脅威」を選択的に取り上げ、理想とするプロフェッショナルな自己像を構築するための「資源」として活用していました。
何を脅威として選び、どう語るかということ自体が、アイデンティティを作り上げる営みの一部だったのです。もちろん、この語りはクラブによる監視や規律の中で形作られています。脅威は除去すべき対象であるだけでなく、自己を語るための柔軟な材料にもなりうるということが示唆されます。
職場いじめは集中的救済的アイデンティティ・ワークを促す
予測可能な脅威を、自己確立の資源としていたプロスポーツ選手たち。しかし、脅威が予測不能で理不尽な形で個人を襲い、尊厳を傷つけるものだったとしたら、人は自己の物語をどう立て直すのでしょうか。職場いじめという深刻な経験からの治癒的なプロセスを追った研究を見ていきます[2]。
この研究は、いじめを経験した二十名の人々にライフストーリーを聞き取るインタビューを通じて行われました。いじめがもたらすトラウマ(心的外傷)とスティグマ(社会的烙印)に直面した人々が、ばらばらになりかけた自己の物語を、いかに意識的な努力によって立て直すのか、その過程を解き明かそうとしました。研究者はこの営みを「集中的救済的アイデンティティ・ワーク」と名付けました。
自己とは、自分がどう生きてきたかを語る内なる物語のようなものです。いじめのようなトラウマ的な出来事は、その物語の連続性を根底から揺さぶります。不当な扱いと、周囲からの不名誉な烙印、内的な自責の念が結びつき、自己の土台である基本的な安心感が崩壊してしまうのです。
分析から、自己の物語を立て直すプロセスが、いじめの前・最中・後という三段階にまたがり、七種類の異なるアイデンティティ・ワークを通じて展開することが明らかになりました。
第一段階は、いじめが本格化する前の予兆の時期です。「第一次安定化」として、噂や態度の変化といった曖昧な状況で高まる不安を、自分の見せ方を調整するなど小さな行動修正で抑えようとします。並行して「意味づけ」も始まります。自分の違和感が正しいか、何が起きているかを同僚などと話し合い、状況の原因を探ろうとします。
第二段階は、攻撃が明白になる、いじめの最中です。ここでは、より複雑なワークが展開されます。一つは「折り合い」です。恐怖を感じる自分と「こうありたい」自分との矛盾や、過去の有能だった自分と現在の不当な扱いとのギャップに直面し、過去の成功体験を繰り返し語ることで認知的な不協和を減らそうとします。
次に「修復」という社会的なワークが行われます。傷つけられた評判に対抗し、同僚や管理者に自分の価値と被害の深刻さを認めてもらおうと働きかけます。他者の認識を転換させ、支援を得るための必死の試みです。この時期には「第二次安定化」も行われます。「組織は自分を守ってくれる」といった信念が崩壊するほどのショックに直面し、仕事に注ぐエネルギーを減らすなど、痛みを伴う再調整で心の均衡を取り戻そうとします。
最後の第三段階は、いじめが終わった後の回復と再編の時期です。「喪失の反芻・処理」として、失われた評価、自信、公正な世界への信頼に向き合い、その意味を考え、受容していく感情的な作業が行われます。同時に、仕事以外の「自分」を再発見していきます。
そして最終的に「再編成」に至ります。この辛い経験を自らの人生の物語の中に統合し、そこから何かを学んだと肯定的に位置づけ直します。ただし、すべての人が成功するわけではなく、自己が断片化したまま長期化するケースもあり、被害の破壊的な力を物語っています。
個人の困難と状況が交差しアイデンティティ・ワークを形づくる
職場いじめは、個人に内面での集中的な立て直しを迫りました。しかし、個人の苦悩は、その人だけの閉じた世界で完結するのでしょうか。個人の葛藤が、組織や社会といったより大きな構造と響き合っている様子を、ある製造企業の管理職の経験を通じて探る研究があります[3]。この研究は、「社会学的想像力」、つまり個人の「私的な悩み」を大きな歴史的・構造的文脈と結びつけて理解する視点を、アイデンティティ研究に持ち込もうとします。
研究者は、ある製造企業を舞台に、参与観察、当事者の自伝、インタビューを組み合わせ、管理職の日々を詳細に描き出しました。この研究の核心は、アイデンティティ・ワークを、自己の内面を整える「内向き」の営みと、他者や社会が提供する役割像(ペルソナ)に働きかける「外向き」の営みの連関として捉え直す点にあります。
私たちは「マネジャー」や「専門職」といった社会的な役割像、いわばペルソナの「台本」に囲まれて生きています。アイデンティティ・ワークとは、こうした外的な台本を取り込んだり、それと距離を置いたりしながら(外向き)、自己の一貫性を保とうとする内面的な営み(内向き)が、相互に作用しあうプロセスだと考えられます。
この視点を、上級管理職だったレナードという人物の物語から見てみましょう。彼は自伝で、管理職であることの核心は「責任を引き受け、物事を統制する」姿勢であり、それはキャリアの過程で身につけたものだと語ります。彼の物語には、職場で蔓延していた「粗暴な言葉遣い」に適応していく自分への違和感と、その振る舞いが家庭にまで滲み出たことへの後悔が刻まれていました。ここに、職場での「外向き」のワーク(粗野な言葉遣い)が、レナードの内面に作用し、自己像を変えてしまったプロセスが読み取れます。
この「外向き」のワークが日常でどう展開されたか、ある会議の場面がそれを切り取っています。複数の男性管理職が激しく議論する中、同席していた若手女性人事マネジャーのケイの存在に気づいた一人が、突然「言葉遣いを改めよう」と提案します。ケイは「私は気にしませんから」と応じ、議論を実務的な論点へ引き戻しました。
この短いやりとりの中に、複数のアイデンティティ・ワークが凝縮されています。レナードは「紳士的な人物」という評判を保とうとし、ケイは「細かいことは気にしない有能な女性管理職」というペルソナを演じることで発言権を確保しようとしました。人々は状況に応じて、社会的に利用可能な役割像を巧みに操作するのです。
レナードの個人的な困難は、さらに大きな構造的な緊張関係とも結びついていました。当時、人事部門が主導する改革に対し、製造現場の管理職であるレナードは「現場を知らない人間のやることだ」と強く反発していました。この対立はただの感情的な問題ではなく、労働力の効率的な活用と人間的な関係性の維持という、社会に内在する構造的な緊張の現れでした。個人のアイデンティティをめぐる営みは、決して孤立したものではなく、社会の構造と絡み合いながら形作られていく、ということが示唆されます。
職場の勇気は葛藤を調停し自己を統合する
個人の困難が社会構造と交差する中で、時に既存の規範や権力との間に緊張が生まれます。こうした緊張に直面したとき、人が自らの価値観に忠実であろうとする行為、すなわち「勇気」は、自己の統合にどのような働きをするのでしょうか。職場における勇気ある行動の内実に迫った研究を紹介します[4]。
この研究は、「職場での勇気」を、アイデンティティを作り、保ち、修復するための実践、つまりアイデンティティ・ワークの一環として捉え直そうとしました。研究者は、社会人学生から集めた89件の「勇気ある行動」に関する体験談を分析しました。ここで言う勇気とは、「道徳的に価値のある目標のために、リスクや脅威を承知の上で、意図的に行動すること」と定義されます。
分析の結果、勇気が発揮される物語の核心には、ほとんどの場合、個人が大切にする複数のアイデンティティ間の「緊張」が存在することがわかりました。例えば、個人の倫理観(自己)と、不正な指示に従うべきだという圧力(役割)との葛藤です。これらの緊張は当事者に不安をもたらし、勇気ある行動とは、まさにこの緊張を乗り越え、調停しようとする試みです。
その勇気ある行動が展開する物語には、大きく分けて五つの異なるストーリーラインが見出されました。
最も多かったのは「抵抗」の物語です。上位の権力者や多数派に対し、たとえ自らの雇用が危うくなるリスクを冒してでも、「筋を通す」ために異議を申し立てるというものです。その背景には、公正さや誠実さといった、自らが深く信じる原理を守りたいという強い動機があります。
次に多かったのは「反応」の物語です。自分や他者が引き起こした問題や危機に対し、正直さや他者を助けるといった原則に基づいて即座に対応する行動です。自らのミスをすぐに申告したり、危険な状況で同僚を助けたりといった行為が含まれます。
三つ目は「創造」の物語です。革新や起業といった高リスクの機会をあえて掴み、これまでにない新しいアイデンティティを自ら作り上げていこうとする挑戦的な行動です。
四つ目は「耐久」の物語です。変えることのできない逆境の中、価値ある目標のために、自己を犠牲にしながらも粘り強く耐え抜くというものです。
最後に、これらとは対照的な「勇気なし」の物語も存在しました。行動を回避してしまった後悔の語りです。これらの物語ではアイデンティティ間の緊張は解消されないまま残りますが、語り手は「自分は臆病者ではない」と語り、望ましくない自己像から距離を置こうとしていました。
この研究から見えてくるのは、勇気という行為が、私たちの内なるアイデンティティを蒸留するプロセスであるということです。複数のアイデンティティ間の緊張は、私たちにとって本当に大切なものは何かを浮き彫りにします。そして、勇気ある行動を通じて、どの価値を優先し、どの境界線を守るのかを自ら決定することで、ばらばらになりかけていた自己を再び一つに統合していきます。その結果、人は自己に対する誠実さや自信、心の安らぎを取り戻します。勇気とは、葛藤を調停し、より調和のとれた自己へと向かうための、能動的で創造的な営みです。
脚注
[1] Brown, A. D., and Coupland, C. (2015). Identity threats, identity work, and elite professionals. Organization Studies, 36(10), 1315-1336.
[2] Lutgen-Sandvik, P. (2008). Intensive remedial identity work: Responses to workplace bullying trauma and stigmatization. Organization, 15(1), 97-119.
[3] Watson, T. J. (2008). Managing identity: Identity work, personal predicaments and structural circumstances. Organization, 15(1), 121-143.
[4] Koerner, M. M. (2014). Courage as identity work: Accounts of workplace courage. Academy of Management Journal, 57(1), 63-93.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。