2025年12月22日
「誰とやるか」が道を拓く:人との共創で進める中小企業の国際化
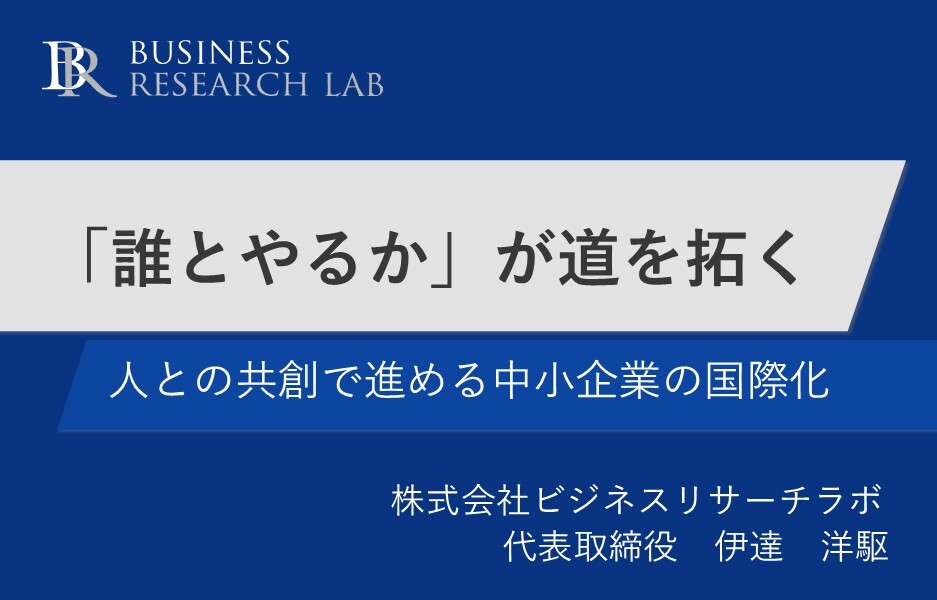
企業の海外進出と聞くと、どのようなイメージを思い浮かべるでしょうか。分厚い事業計画書、綿密な市場調査、競合分析、そして周到に準備された戦略といった、緻密な計画の数々を思い浮かべるかもしれません。成功は、いかに正確に未来を予測し、計画通りに物事を進められるかにかかっている。そう考える人もいるでしょう。しかし、現実はどうでしょうか。特に、まだ体力のない中小企業や、全く新しいビジネスを立ち上げる新興企業にとって、予測不能な海外市場は、計画通りに進むことの方が稀な、不確実性に満ちた世界です。
計画を立てることよりも、今手元にあるもので何とかする力、予期せぬ出来事を味方につける力が、成功の鍵を握るとしたらどう思いますか。本コラムで紹介するのは、「エフェクチュエーション」という、まさにそのような考え方です。壮大な目標から逆算して手段を選ぶのではなく、「自分は何者か、何を知っているか、誰を知っているか」という手持ちの資源から出発し、関わってくれる人々と共に、進むべき道、そしてゴールそのものを創り上げていくアプローチです。
この考え方は、予測が困難な状況で真価を発揮します。計画通りに進まないことを前提とし、偶然の出会いや予期せぬ失敗すらも、新たな価値を生み出すための材料として捉え直すのです。本コラムでは、このエフェクチュエーションという視点を通して、企業の国際化のリアルな姿を解説していきます。新興企業の立ち上げから、中小企業の海外拠点設立、人と人とのつながりが事業を動かしていく過程まで、研究知見を紐解きながら、計画を持たずに、いかに未知を乗り越えていくのか、その知恵を探求していきたいと思います。
新興企業の初期行動で一貫して観察された
新しいビジネスが産声を上げる瞬間、その舞台裏では何が起きているのでしょうか。一般的には、優れたアイデアを元に市場の機会を見つけ、それを実現するための事業計画を練り、資金を調達して実行に移す、という筋書きが想像されます。しかし、実際の起業家たちの足跡を丹念に追ってみると、少し異なる風景が見えてきます。
ある研究で、消費者向けのインターネットビジネスを手がける6つの企業の創業期が分析されました[1]。この分析は、創業者自身が語ったインタビューの記録や、当時の報道記事といった資料を基に行われています。分析の目的は、企業の初期行動が、あらかじめ目標を定めて最適な手段を選ぶ「計画的なアプローチ」と、手持ちの資源から出発して試行錯誤する「エフェクチュエーション」のようなアプローチの、どちらによって説明できるかを探ることでした。
その結果、明らかになったのは、創業初期に緻密な市場調査や競合分析、詳細なマーケティング計画といった計画的な行動を主軸に据えていた企業は、6社中ごく少数に限られていたという事実です。むしろ、多くの企業で見られたのは、「まず製品の原型を作ってみる」「利用者の反応を見る」「手元にある技術や知識を組み合わせて何とかする」といった、行動を先行させる姿でした。
例えば、社内業務を効率化するために作ったツールが、予想外に外部から評価され、それを製品として販売するに至ったケース。あるいは、本業の傍らで、細切れの時間を使って開発した個人的なプロジェクトが、いつしか多くの利用者を獲得し、一つの事業として独立したケースなどです。
計画的なアプローチが見られた企業においても、その行動は単独で存在していたわけではありませんでした。市場分析を進める傍らで、同時にプロトタイプの開発と実験を繰り返すなど、二つの異なるアプローチが並行して走っていました。このことは、ビジネスの黎明期において、一つの決まったやり方だけが正しいわけではないことを物語っています。
なぜ、新しいビジネスの始まりにおいては、計画よりも行動が先行するのでしょうか。一つの理由は、資源の制約です。創業期の企業は、時間も資金も人材も限られています。壮大な計画を立てて、その実現に必要なすべての資源を揃えるのを待つよりも、今あるもので始められる一歩を踏み出す方が、現実的な選択です。
そして、この「制約」が、創造性の源泉になることも、創業者たちの言葉から浮かび上がってきます。資金が潤沢でないからこそ、製品の核となる機能は何かを考え抜き、無駄を削ぎ落とした優れたものが生まれる。時間が限られているからこそ、完璧を目指すのではなく、まずは動くものを世に問い、利用者からのフィードバックを元に改善を重ねるという、迅速な学習サイクルが回っていく。
新しいビジネスが生まれる現場では、未来を予測して計画を立てるというよりも、手元の資源を最大限に活かし、行動しながら学ぶというプロセスが広く見られます。それは、不確実な未来に対する、しなやかで力強い生存戦略と言えるのかもしれません。
SMEは不確実な海外市場で迅速に拠点形成できる
先ほど見た、手持ちの資源から行動を始めるアプローチは、予測が難しい海外市場へ中小企業が進出する際にも、有効です。海外展開というと、本来であれば入念な準備と計画が不可欠に思えます。しかし、実際には「計画外」の出来事がきっかけで、予想もしなかった国に、驚くほど短期間で拠点を構えるに至るケースは少なくありません。こうした一見すると行き当たりばったりのように見えるプロセスは、果たして単なる幸運や偶然の産物なのでしょうか。
この問いに答えるため、東ヨーロッパに製造子会社を設立したイタリアの中小企業5社の事例を追った研究があります[2]。研究者たちは、創業者や現地の責任者にインタビューを重ね、海外進出を決意した瞬間から、拠点が立ち上がるまでの意思決定の軌跡を遡りました。その結果、5社すべてに共通していたのは、進出を決めた当初、現地の市場に関する詳細な知識や、具体的な事業計画を持ち合わせていなかったという事実です。
では、計画がない中で、どうやって大きな投資判断を下したのでしょうか。その鍵を握っていたのが、「許容損失」という考え方でした。これは、将来得られるかもしれない最大の利益を追い求めるのではなく、「最悪の場合、失っても事業の存続には響かないのは、どのくらいの資源か」を先に決めるアプローチです。彼ら彼女らは、この範囲内で小さく一歩を踏み出しました。例えば、現地の企業に部品の製造を委託してみる、販売代理店を探すために一度現地を訪れてみる、といった具合です。
この小さな行動が、予期せぬ連鎖反応を引き起こします。ある企業は、低コストの委託先を探しに現地へ赴いたところ、その取引先が倒産するという危機に直面しました。しかし、それを機に、その工場を自社で買収することを決断。結果、外注先ではなく、アフターサービスまで手掛ける本格的な生産拠点を手に入れることになりました。また別の企業は、ある国で販売代理店を探していたところ、商談会で偶然隣国のバイヤーと出会い、意気投合。その場で合弁会社の設立を決めてしまいました。
これらの事例が示すのは、不確実性の高い環境では、目標そのものが固定的ではないということです。当初の目的は、あくまで行動を起こすためのきっかけに過ぎません。現地での人々との出会いや、予期せぬ出来事との遭遇を通じて、当初は想像もしなかった新たな機会が生まれ、目標がより大きなものへと再定義されていくのです。
このプロセスは、企業が現地ネットワークの「部外者」であるという不利な立場を克服する上でも、決定的な意味を持ちます。行動を通じて現地の人々と関係を築き、信頼を得ることで、初めて得られる情報や協力があるのです。
一度、海外での拠点設立を経験すると、企業は大きな自信と、国際ビジネスに不可欠なノウハウという新たな「手段」を獲得します。その結果、二度目以降の海外展開は、より計画的に、複数の候補国を比較検討するといった、従来型の合理的なアプローチで進めることが可能になります。計画なき国際化は、非合理的な行動なのではなく、不確実な環境に適応するための、もう一つの合理的なプロセスです。
SMEの国際化を人脈起点の共創過程として説明する
海外展開の道のりが、想定外の出来事によって左右されることを見てきました。そのきっかけとなる「出会い」や「出来事」は、どのようにしてもたらされるのでしょうか。企業の国際化を深く見つめると、その中心には常に「人」の存在があり、人と人とのつながりが物語を動かしていく様子が浮かび上がってきます。
中小企業の国際化を、具体的な人間関係の構築プロセスとして捉え直した研究があります[3]。この研究では、不確実性が高いとされるロシア市場へ進出したフィンランドの中小企業7社が調査対象となりました。創業者や国際事業の責任者へのインタビューを通じて、彼ら彼女らがどのようにして国境を越えた人脈を築き、事業を軌道に乗せていったのか、その過程が描き出されています。
分析から見えてきたのは、多くの企業にとって、国際化の出発点が「どの国に進出するか」という市場選択ではなかったという事実です。「誰とビジネスをするか」というパートナーとの出会いが先行していました。
ある企業は、隣国でのビジネスを通じて知り合った人物から、その先のロシアのビジネスパートナーを紹介され、意図せずしてロシア市場への扉が開かれました。また、ある企業では、社内で採用したロシア語を話すインターン生が、現地のネットワークへの架け橋となりました。「人が先、国は後」という言葉が当てはまるパターンが、そこにはありました。
このアプローチにおいて、企業家は特定の成果をあらかじめ設定し、その達成のためにパートナーを選ぶわけではありません。そうではなく、「この人と組めば、何か面白いことができそうだ」という、関係性そのものが持つ可能性に賭けるのです。相手の自発的な関与や提案を歓迎し、共に事業の形を模索していく「共創」のプロセスが始まります。最初は小さな取引から始まり、互いの信頼関係が深まるにつれて、より大きなコミットメント、例えば合弁会社の設立といった形へと発展していきます。
このような進め方では、不確実性は排除すべきリスクではなく、新たな価値を生み出す源泉として捉えられます。事前に完璧な情報を集め、相手を徹底的に分析するよりも、まずは小さな協業を通じて「お互いを試す」のです。行動を共にすることで、書類上では決して分からない相手の人柄や能力、そして自社との相性が見えてきます。この実践を通じて、事後的に信頼が醸成されていきます。
この研究は、企業の国際化が、市場分析と戦略立案の結果だけで進むのではないことを教えてくれます。そこには、偶然の出会いを大切にし、人と人との信頼関係を育みながら、手探りで未来を創り上げていく、人間味あふれるドラマがあります。中小企業の国際化とは、そのような創造的なネットワーキングの過程として理解することができます。
国際化を関係共創の動的過程として説明する
これまで、企業の国際化が「手持ちの資源」や「人とのつながり」を起点に進む様子を見てきました。ここでは、そうしたアプローチを「エフェクチュエーション」という一つの理論的な枠組みとして捉え、国際化という現象に迫りたいと思います。この考え方は、国際化を「どこへ、いかに速く進出するか」という結果から見るのではなく、「どのようにして進むのか」というプロセスに光を当てます。
エフェクチュエーションの核には、未来は予測するものではなく、自らの行動によって創り出すものだという思想があります。環境を所与の条件として受け入れるのではなく、関わる人々と共に働きかけることで、環境を変えていくことができるという考え方です。このダイナミックなプロセスを理解するために、インドのある線香製造会社の三世代にわたる国際化の歴史を事例とした研究が参考になります[4]。
この会社は、もともと国内市場向けの家業として始まりました。二代目の経営者は、国内事業が順調であったにもかかわらず、未知なる世界への好奇心から輸出に挑戦します。当時はインターネットもなく、海外の情報は限られていました。彼は、手元にあるわずかな情報を頼りに世界中を飛び回り、現地の輸入業者と直接交渉することで、少しずつ販路を開拓していきました。これは、今ある手段からまず一歩を踏み出すという、エフェクチュエーションの姿勢そのものです。
その過程で、数々の予期せぬ発見がありました。ある国への小さな出荷がきっかけで、それまで想定していなかった層に、線香がルームフレグランスとして受け入れられることが判明しました。この偶然の発見を機に、新たな製品開発と市場開拓が進み、事業は拡大します。これは、予期せぬ出来事を失敗と捉えず、新たな機会へと転換する「レモネードの原理」と呼ばれる考え方を体現しています。
さらに特筆すべきは、彼ら彼女らが既存の制度に働きかけ、それを自らにとって有利な形に変えていった点です。当時、政府には輸出企業を支援する制度がありましたが、線香のような小規模な産品は対象外と見なされていました。しかし、経営者は諦めず、「法の趣旨に規模の要件はないはずだ」と当局と粘り強く交渉し、ついに認定を勝ち取ります。環境を単なる制約として受け入れるのではなく、自らの働きかけによって望ましい未来を創り出すという、エフェクチュエーションの能動的な側面を示しています。
この事例が教えてくれるのは、国際化とは、あらかじめ設計された青写真を実現する作業ではないということです。自分たちが何者であり、何ができ、誰とつながっているのかという自己認識を起点に、関与してくれるパートナーたちとリスクや利益を分かち合いながら、新しい現実を共に創り上げていくプロセスなのです。
脚注
[1] Fisher, G. (2012). Effectuation, causation, and bricolage: A behavioral comparison of emerging theories in entrepreneurship research. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(5), 1019-1051.
[2] Kalinic, I., Sarasvathy, S. D., and Forza, C. (2014). “Expect the unexpected”: Implications of effectual logic on the internationalization process. International Business Review, 23(3), 635-647.
[3] Galkina, T., and Chetty, S. (2015). Effectuation and networking of internationalizing SMEs. Management International Review, 55, 647-676.
[4] Sarasvathy, S. D., Kumar, K., York, J. G., and Bhagavatula, S. (2014). An effectual approach to international entrepreneurship: Overlaps, challenges, and provocative possibilities. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(1), 71?93.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。






