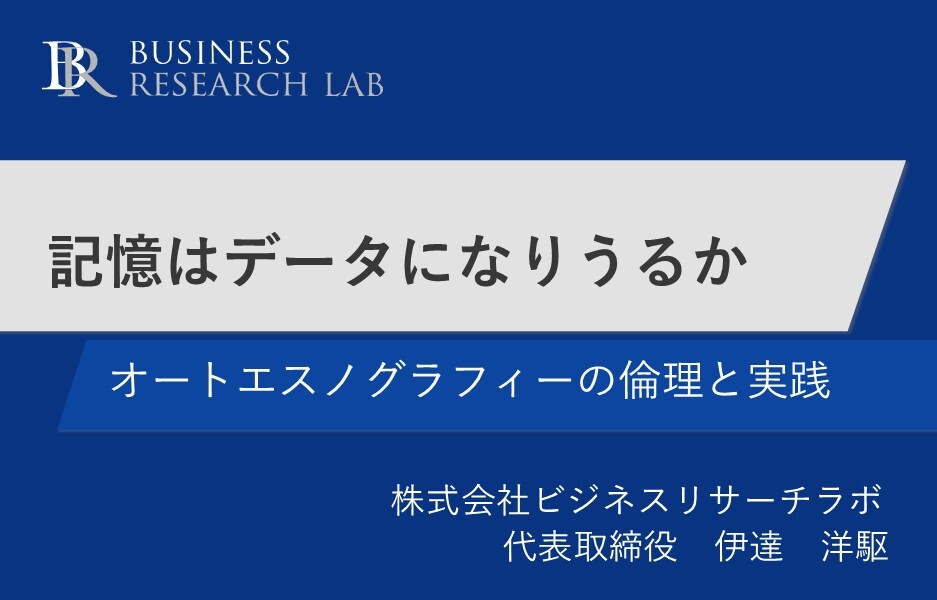2025年12月17日
記憶はデータになりうるか:オートエスノグラフィーの倫理と実践
自分自身の経験を見つめ、それを言葉にすることで、私たちが生きる社会や文化のありようを理解しようとする試みがあります。オートエスノグラフィーと呼ばれるこの方法は、客観的な事実や統計データだけでは捉えきれない、人間の生々しい実感や感情に光を当てます。そこでは、喜びや成功の記憶だけでなく、痛みやためらい、失敗の経験もが、世界を読み解くための手がかりとなります。
しかし、このアプローチは私たちに問いを投げかけます。個人の頭の中にしかない、形のない「記憶」というものを、研究のための「データ」として扱って良いのでしょうか。客観的な証拠とは言えない、主観に満ちた思い出を、どのように分析の対象とすれば良いのでしょう。
個人の物語は、決してその人一人のものではありません。私たちの経験は、家族や友人、同僚といった他者との関わりの中で形作られています。自分の経験を語ることは、必然的に他者の人生の一部を公にすることにもつながります。そのとき、語り手はどのような責任を負うべきなのでしょうか。語られる人々への配慮は、どこまで求められるのでしょうか。本コラムでは、オートエスノグラフィーという方法が直面する、こうした倫理的な課題について考えていきます。
記憶もデータとするオートエスノグラフィーは選択と責任を伴う
自分自身の経験を研究の出発点とするオートエスノグラフィーは、実践する者に対して、絶えず選択とそれに伴う責任を問いかけます[1]。それは、カメラのレンズを操作する作業に似ています。あるときは、個人の内面やごく私的な出来事に焦点を合わせる接写が求められます。
しかし、それだけでは単なる自分語りに終わってしまいます。同時に、その個人的な経験が、どのような社会的な文脈や文化的な背景の中で生じたのかを映し出すために、レンズを引いて広角で全体を捉える視点も不可欠です。この接写と広角の行き来、個人的なものと文化的なものの間のバランスをいかに取るかは、実践者が直面する最初の選択です。
この手法における問いの一つに、そもそも何を「データ」と見なすのか、という問題があります。日記や手紙、録音のような形に残る記録は、一般的にデータとして認められやすいでしょう。では、形のない「記憶」はどうでしょうか。
オートエスノグラフィーは、この記憶という主観的なものを、正当なデータとして扱います。そもそも、他者を対象とする伝統的な民族誌研究でさえ、研究者が現場で何を見聞きし、何を感じたかという「記憶」に依拠して記述されてきました。その意味で、記憶をデータとして用いることは、決して突飛なことではありません。むしろ、記憶が呼び起こす出来事や感情の連なりが、人間経験の豊かさを描き出すための資源となるのです。
また、この方法は一人だけで完結するとは限りません。自分一人の視点から語るだけでなく、他者と協働して一つの物語を編み上げていく実践も存在します。複数の声が重なり合うことで、物語はより多角的になり、一つの視点が絶対的なものとして扱われることを避けることができます。しかし、他者と共に語ることは、新たな難しさも生み出します。誰の人生の解釈に、誰がどこまで関わるのか。共同で作業を進める中で、互いの関係性が変化することもあり得ます。
語り口についても、選択が迫られます。読者の感情に強く訴えかけるような物語的な記述と、冷静に物事を分析し、理論的な考察を深める記述とでは、どちらが優れているのでしょうか。この問いに対して、多くの実践者は、両者が対立するものではないと考えています。感情を揺さぶる物語と、知的な分析は、車の両輪のようなものです。どちらか一方を選ぶのではなく、探求の目的に応じて両者を組み合わせ、行き来することが、より深い理解へとつながります。
最も繊細な配慮を要するのが、語りの倫理です。物語には、必ず他者が登場します。たとえ名前を変え、人物像をぼかしたとしても、文脈から誰のことか分かってしまうかもしれません。自分の経験を公にすることが、意図せずして他者の尊厳を傷つけたり、プライバシーを侵害したりする危険性と、研究者は向き合わなければなりません。
語られる人々から事前に同意を得るのか、原稿ができた後で確認してもらうのか。そもそも、完全に相手の理解を得た上での同意は可能なのか。そこには簡単な答えはなく、研究者は、語りに関わる人々への敬意と配慮を基本姿勢とし、ケアの倫理に根ざした判断を続けることが求められます。こうした実践は、自己満足的な内省だと批判されることもあります。しかし、研究者が自らの経験や弱さを開示することは、むしろ自身の立場を自覚し、説明責任を果たそうとする誠実な営みとして捉えることができます。
オートエスノグラフィーは記憶を正当なデータとし責任ある語りを求める
先ほど概観したオートエスノグラフィーの実践における課題は、具体的な研究の道のりにおいて、より切実な葛藤として現れます。ここでは、国際養子縁組という、個人的で繊細な主題に取り組んだある研究者の執筆過程をたどることで、記憶をデータとすることの意味と、他者を巻き込む語りの責任について考えてみましょう[2]。
この研究者は、自身の養子としての経験を社会学的な視点から理解し直すために、オートエスノグラフィーの執筆を始めました。しかし、書き進めるうちに、まず「どの自分を語るべきか」という問いに直面します。特に、それまでの人生でほとんど意識することのなかった、自分を産んだ母親の存在について、関連する文献を読み解くうちに、それまでとは全く異なる共感的な感情が芽生え始めました。
その結果、過去の自分と現在の自分との間に、埋めがたい隔たりが生まれます。この経験は、語られる「自己」というものが、あらかじめ存在する固定された実体なのではなく、書くという行為を通して初めて立ち現れてくる、流動的なものであることを明らかにしました。
執筆の過程では、「客観性」という壁にも突き当たります。指導教員からは、文章の感情的なトーンを抑え、もっと距離を置いた記述にするよう助言を受けました。研究者はその助言に従い、表現を和らげましたが、その結果、本当に伝えたかった論点が曖昧になり、読者に問題の複雑さを共有するという、オートエスノグラフィー本来の目的が損なわれてしまったのではないか、という省察に至ります。
感情を完全に排除することが客観性なのではなく、自らの感情の動きを誠実に記述し、それが分析にどう作用したのかを読者に開示することが、知的な誠実さにつながる場合もあります。
この研究が依拠した主要なデータは、形ある資料ではなく、研究者自身の「記憶」でした。これは、「他人が集めた記録はデータと見なされるのに、当人の記憶はデータと見なされにくい」という学問の世界の慣習に対する、静かな異議申し立てでもありました。
質的な研究においては、研究者が現場で得た記録だけでなく、その頭の中に蓄積された膨大な印象や感覚の総体、いわゆる「ヘッドノート」が、分析や解釈において本質的な働きをすることが知られています。この研究者は、その知見を拠り所に、自身の記憶という資源を研究の中核に据えることの正当性を主張しました。
しかし、個人的な語りが学術的な知として認められる道のりは、平坦ではありません。この研究者の原稿は、ある有力な研究者からは高く評価された一方で、学術誌の査読では「個人的すぎる」「一般性がない」といった理由で、何度も不採録の憂き目にあいます。物語としての力強さと、学術的な論文としての形式的な要請との間で、どのようにバランスを取るか。これは、多くの実践者が直面するジレンマです。
最も重い葛藤は、倫理をめぐるものでした。自身の経験を語ることは、必然的に家族、特に同じく養子である自分の子どもに関する情報を開示することになります。匿名にしても、文脈から身元が推測される可能性は拭えません。一度公にされた物語が、将来子どもにどのような影響をもたらすか、その不可逆性に研究者は悩みます。
この葛藤は、語りの倫理が、単に同意を得るという手続き的な問題にとどまらないことを教えてくれます。それは、自分の語りが社会でどのように読まれ、受け取られるかという、その後の波及効果まで想像力を働かせ、責任を引き受けることを求める、終わりなき問いかけなのです。
オートエスノグラフィーはヴィネットで研究者の感情と省察を鮮明にする
記憶や感情といった、形のない内的な経験を、いかに他者に伝えるか。この難題に応えるための一つの手法として「ヴィネット」があります。ヴィネットとは、特定の場面を切り取った短い描写のことです。特に、オートエスノグラフィーで用いられるヴィネットは、多くの場合、過去の出来事をまるで今ここで起きているかのように「現在形」で記述します。これによって、読者は単に物語を読む傍観者としてではなく、その出来事の渦中にいる当事者のような感覚で、書き手の経験を追体験することができます。
ここでは、ある研究者が自身のキャリア転換の道のりを、ヴィネットを用いて描いた実践を通して、この手法が持つ力を探ってみましょう[3]。
この研究者は、長年教育の現場にいた後、50代で研究中心の大学へと移った、いわゆる「非標準的」な経歴の持ち主でした。履歴書に記されるような経歴の裏側にある、迷いや不安といった人間的な側面を描き出すために、彼は三つのヴィネットを用いました。
一つ目は、大規模な国際学会で初めて口頭発表に臨んだ際の場面です。ヴィネットは、発表直前の彼の内的な独白を現在形で描き出します。「自分は本当の学者ではない」「完全に場違いだ」。そうした自己不信の念、口が渇き、手足が震えるといった身体の正直な反応が、生々しく綴られます。しかし、いざ発表が始まると、長年の教師経験で培われた話術が彼を助け、聴衆の反応が好転していく様子が描かれます。
このヴィネットは、キャリアの移行期に誰もが感じるであろうアイデンティティの揺らぎや脆弱さを、読者に身体感覚として共有させる働きを持っています。
二つ目のヴィネットは、その二年後、同じ学会に再び登壇した場面です。そこでは、以前とは打って変わって、場の空気に慣れ、共同発表者とのやり取りを主導し、即興的にジョークを交えて会場の笑いを誘う彼の姿が描かれます。この描写は、学術的な共同体という新しい環境に、一人の人間が徐々に社会化され、適応していくプロセスを生き生きと伝えます。
三つ目は、成功体験とは対照的な、学内での昇進審査に失敗した場面です。練習を重ねすぎたがゆえにプレゼンテーションが硬直し、普段は気心の知れた同僚たちの前で、かえって緊張してしまう。自己懐疑の声が、内面で渦巻く様子が描かれます。この失敗談の開示は、キャリアが常に順風満帆なわけではないという現実を示すと共に、失敗という経験から何を学び取るかという、実践的な洞察へとつながっていきます。
これらのヴィネットが描き出すのは、履歴書という骨格に、汗や笑い、羞恥といった血肉を与える作業です。自らの弱さや失敗を公の文章にさらすことには、ためらいや危険が伴います。しかし、それを行うことによって、知的な営みがいかに人間的な感情や身体性と結びついているかを見える化し、他者との共感や対話の回路を開くことができます。書き手自身も、ヴィネットを書くことを通して、自らの経験の意味を再解釈し、自己理解を深めていきます。
この手法は、個人のキャリアを語ることに限定されません。どのような質的研究であっても、客観的な観察記述の合間に、調査者自身の逡巡や身体的な感覚を短いヴィネットとして挿入することで、その知見がどのような立場から、どのような条件の下で生み出されたのかを読者に示すことができます。それは、知の生産過程を透明化するための、誠実な試みと言えるでしょう。
オートエスノグラフィーは物語を状況依存で柔軟に評価する道を示す
オートエスノグラフィーが描き出すのは、個人の記憶や感情に根差した、主観的な世界です。このような個人的な語りを、学問の世界ではどのように評価すれば良いのでしょうか。「科学的な正しさ」や「一般化できるか」といった従来の物差しでは、その価値を正当に測ることは難しいかもしれません。ここでは、固定的な基準を当てはめるのではなく、もっと柔軟に物語の価値を判断する道を探った、ある研究者の試みを見ていきましょう[4]。
この研究者は、アスリートであった自身の身体が、怪我と慢性的な痛みによってどのように変化していったかについて自伝的な物語を執筆し、学術誌に投稿しました。その過程で、彼は自身の論文に対する複数の査読者からのコメントを、論文の中でそのまま公開するというユニークな方法をとりました。
そこに現れたのは、「評価の現場」のありのままの姿でした。ある査読者は、物語が読者の感情に訴えかけ、倫理的な感受性を高める点を高く評価しました。一方で、別の査読者は、物語を理論的にどう位置づけるのか、既存の研究とどのように関連づけるのかが不明確だと指摘しました。また、文章の構成や結び方について、具体的な助言を与える査読者もいました。これらのコメントは、時に互いに矛盾さえしていました。
この試みが明らかにしたのは、評価基準というものが、絶対的で単一なものではなく、多様な視点から構成されており、実際の文章と読者との相互作用の中で立ち現れてくるという事実です。
オートエスノグラフィーに対しては、「自己満足に過ぎない」という批判がしばしば向けられます。しかし、この研究者は、自己について書くことは、孤立した内省ではなく、他者や世界との関係性の中で自己を理解しようとする営みであると主張します。読者もまた、物語を受け取るだけの受動的な存在ではありません。読者は物語に巻き込まれ、共感し、反発し、自らの経験と照らし合わせる参加者なのです。
したがって、物語の価値は、書き手の自己開示の度合いによって決まるのではなく、その物語がどれだけ読者との対話を生み出し、倫理的な応答を促すかによって判断されるべきだと論じられます。
こうした考えに基づき、研究者は、従来の評価基準に代わる新しい判断の枠組みを提案します。それは、次のような問いかけの形をとります。この物語は、読者である私自身の考えや行動に変化を促したか。描かれた世界は、私の知る現実に照らして、信じるに足るものだと感じられたか。物語は、他者の生を追体験する手がかりを与えてくれたか。ここで描かれた経験は、他の状況にも応用して考えられるような「転移可能性」を持っているか。
これらの問いかけは、物語を「真か偽か」という二元論で裁くのではなく、その物語が持つ、読者との関係を築く力、信頼性、実践的な応用の可能性といった、多面的な価値を評価するためのものです。最終的に、この研究者がたどり着いたのは、固定的なチェックリストではなく、状況に応じて柔軟に運用される評価のあり方でした。
研究の目的や文脈、対象とする読者共同体によって、物語に求められる資質は変わります。ある場合には論理的な整合性が、またある場合には表現の豊かさがより重視されるかもしれません。このような、しなやかさが、再現性や普遍性を前提としない自伝的な語りの評価に適しているのです。
脚注
[1] Winkler, I. (2018). Doing autoethnography: Facing challenges, taking choices, accepting responsibilities. Qualitative Inquiry, 24(4), 236-247.
[2] Wall, S. (2008). Easier said than done: Writing an autoethnography. International Journal of Qualitative Methods, 7(1), 38-53.
[3] Humphreys, M. (2005). Getting personal: Reflexivity and autoethnographic vignettes. Qualitative Inquiry, 11(6), 840-860.
[4] Sparkes, A. C. (2000). Autoethnography and narratives of self: Reflections on criteria in action. Sociology of Sport Journal, 17(1), 21-43.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。