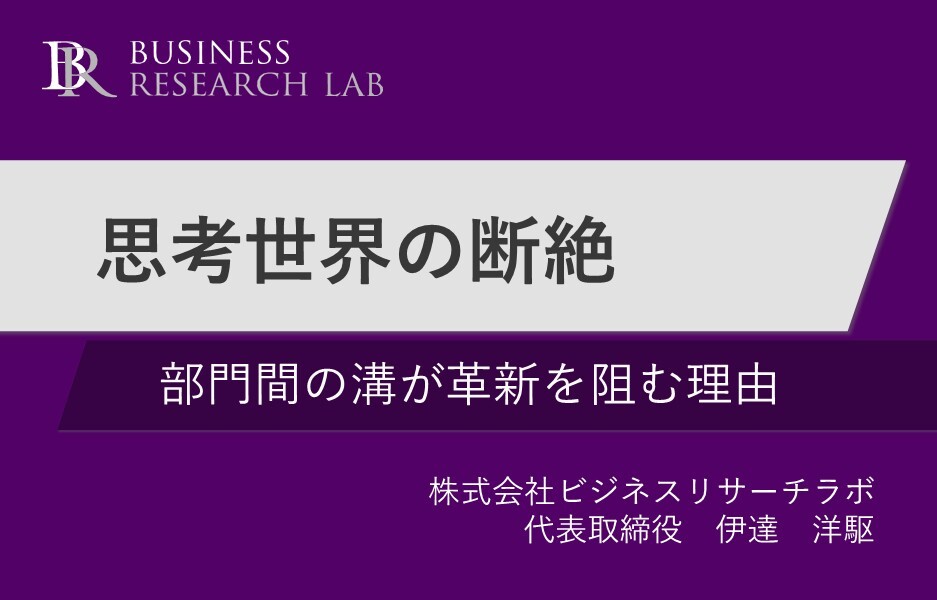2025年12月16日
思考世界の断絶:部門間の溝が革新を阻む理由
巨大な船がその進路をわずかに変えるだけでも、相当な時間とエネルギーを要するように、歴史と伝統を持つ大企業が自己を変革する道のりは、平坦ではありません。安定した事業基盤と確立された組織構造は、日々の業務を効率的に遂行する上での強みである一方、ひとたび外部環境が大きく変化したときには、その巨体そのものが足かせとなり、迅速な方向転換を困難にさせます。
組織の内部では、経営層の意図とは別に、現場の担当者たちの小さな試みや、部門間で交わされる何気ない会話、あるいは過去の成功体験から生まれた暗黙のルールといった、目には見えにくい無数の力学が働いています。それらは、時に変革の思わぬ起爆剤となり、またある時には、強固な抵抗勢力となって改革の前に立ちはだかります。
本コラムでは、大企業の変革をめぐる、こうした組織の内外で働く複雑な力学について、いくつかの学術的な知見を手がかりに検討していきます。
現場から生まれる小さな逸脱は、いかに企業全体の戦略を塗り替える可能性を秘めているのでしょうか。なぜ、一見すると些細な技術の変更が、業界のリーダーを没落させてしまうことがあるのでしょうか。部門間に存在する「ものの見方」の溝は、協力をどのように阻むのでしょうか。企業が外部の新しい知識を取り込み、自らの力に変えていくためには、何が必要なのでしょうか。これらの問いを通じて、巨大な組織が動く、あるいは動けなくなる背景にあるメカニズムに光を当てていきたいと思います。
現場発の小さな逸脱が企業戦略を塗り替える
企業の戦略は、一般的に経営トップが明確なビジョンを描き、それに基づいて策定されるものだと考えられています。組織の資源をどこに配分し、どの市場で競争するのか。そうした大きな方針が定められ、各部門はそれに従って具体的な計画を実行に移していきます。これは「誘導的戦略行動」と呼ばれる、いわば公式のプロセスです。しかし、大企業の内部では、もう一つの異なる流れが存在しています。それは、現場の従業員が日々の業務の中で抱いた疑問やアイデアから自律的に生まれる、計画外の「自律的戦略行動」です。
ある研究では、多角化経営を行う大企業を対象に、こうした現場から生まれる新規事業が、どのように認知され、やがて企業全体の戦略に組み込まれていくのか、そのプロセスが明らかにされました[1]。このプロセスは、「変異」「選択」「定着」という三つの段階で捉えることができます。
最初の「変異」の段階は、現場の技術者や営業担当者といった個人、あるいは小さなチームが、既存の事業領域の枠からはみ出すような新しいアイデアを思いつき、試行錯誤を始めることから始まります。これらの活動は公式の計画には含まれていないため、必要な資源は、業務の合間の時間や、上司に黙認された範囲での予算の流用など、非公式な形で確保されることがほとんどです。いわば、組織の「隙間」で、新しい可能性の芽が静かに生まれる段階です。
次に訪れるのが「選択」の段階です。生まれたばかりのアイデアは、そのままでは消えてしまうか、あるいは単なる個人の思いつきで終わってしまいます。それが組織的な取り組みへと発展するためには、社内の「選択環境」を生き残らなければなりません。
ここで大きな働きをするのが、そのアイデアの価値を信じ、推進役となる「プロダクト・チャンピオン」や、部門の壁を越えて政治的な支援や資源を提供する中間管理職などの「スポンサー」の存在です。彼ら彼女らは、小さな実験から得られたデータや試作品を基に、その事業の将来性を説き、社内の会議で議題に上げ、関連部署を巻き込みながら、徐々に支持の輪を広げていきます。
同時に、一部の顧客に試作品を使ってもらうなど、社外の市場という「外部選択環境」でもその価値が試されます。既存の制度は、過去の成功に基づいて作られているため、前例のない新しいアイデアに対しては、評価が厳しくなりがちです。そのため、自律的な取り組みは、標準的な審査プロセスを通過するのではなく、小さな成功を積み重ねて実績を作り、社内の支持者を増やしていくという、独自の生存戦略を必要とします。
そして「定着」の段階です。社内外での検証を通じて、その新規事業の技術的な実現可能性や商業的な有望性が十分に確認され、組織内での政治的な支持も固まると、トップマネジメントはそれを企業の公式な戦略の一部として認める決断を下します。これは、承認を与えるだけではありません。新しい事業部を設立したり、評価制度や資源配分のルールをその事業に合わせて変更したりするなど、組織の公式な仕組み、すなわち「構造的コンテキスト」を書き換えるプロセスを伴います。
こうして、かつては非公式な「逸脱」であった活動が、組織の正式な事業として認知され、安定した資源供給を受けながら成長していくための軌道に乗るのです。
ここから浮かび上がるのは、大企業の戦略が、トップダウンの設計だけで決まるのではなく、現場の自発的な試みが、社内の複雑な選択プロセスを通過し、生き残ることで、下から上へと押し上げられる形で形成されるという姿です。計画された秩序と、現場から生まれる混沌。この二つの流れの相互作用が、企業が環境の変化に適応し、自己を革新していく原動力となっているのかもしれません。
小さな結合変更が大企業を失敗へ導く
先ほどは、現場の小さな試みが企業全体の変革につながる可能性を見ました。しかし、変化、特に技術的な変化は、企業にとって諸刃の剣です。ある種の技術変化は、既存の企業が持つ強みを無力化し、業界の勢力図を一変させてしまうことがあります。厄介なのは、根本的な原理を覆すような派手な技術革新ではなく、一見すると既存技術の改良にしか見えない、静かな変化です。
この現象を解き明かすために、半導体の製造工程で使われる「フォトリソグラフィ用アライナー」という精密機械の産業史を分析した研究があります[2]。この産業では、約20年の間に何度もトップ企業が入れ替わるという変化が起きました。不思議なことに、敗れ去った企業も、次世代の技術開発に多額の投資を行っていたにもかかわらず、新興企業にその地位を奪われてしまったのです。
この謎を解く鍵は、製品の知識を二つの種類に分けて考えることにあります。一つは「コンポーネント知識」です。これは、製品を構成する個々の部品、例えばレンズや光源、モーターといった部分に関する知識です。もう一つは「アーキテクチャ知識」です。これは、それらの部品をどのようにつなぎ合わせ、全体として機能させるかという「組み合わせ」や「設計思想」に関する知識です。
この研究が明らかにしたのは、業界のリーダーを交代させた技術変化の多くが、「アーキテクチャ革新」と呼ばれるタイプのものだったということです。アーキテクチャ革新とは、製品を構成する個々のコンポーネントは大きく変えずに、それらの「組み合わせ方」だけを新しくするような革新を指します。部品そのものは既存の技術の延長線上にあるため、既存企業にとっては対応が容易なように見えます。しかし、ここに大きな罠が潜んでいます。
企業が特定の製品で成功を収め、生産を効率化していく過程で、その製品の「アーキテクチャ知識」、要するに最適な部品の組み合わせ方は、組織の隅々にまで深く浸透し、暗黙の前提となっていきます。例えば、「どの部署とどの部署が緊密に連携すべきか」「開発プロセスにおいてどの情報を優先すべきか」「問題が発生したときにどのような解決策を探すべきか」といった事柄が、いちいち意識されなくても業務がスムーズに進むような、コミュニケーションの経路や組織内の手続き、あるいは文化として定着していきます。
この「組織に埋め込まれたアーキテクチャ知識」は、既存の製品を改良し続ける上では力を発揮します。しかし、ひとたび部品の「組み合わせ方」の最適解が変わってしまうアーキテクチャ革新が起きると、この強みは一転して弱みとなります。過去の成功体験から生まれた暗黙のルールや定石が、新しいアーキテクチャを理解する上での妨げとなり、変化の重大さを見過ごさせたり、見当違いの対応をさせてしまったりするのです。
この産業で起きた事例を見てみましょう。ある時期、コンタクト方式のアライナーで高いシェアを誇っていたKasper社は、マスクとウェハをわずかに離して転写するプロキシミティ機能をいち早く製品に搭載しました。しかし、この機能は顧客にほとんど使われず、同社はやがて市場から撤退します。
プロキシミティ機能の性能を最大限に引き出すためには、ギャップを精密に制御する機構と、他の部品との連携を見直す、要するに装置全体のアーキテクチャを再設計する必要がありました。しかし、Kasper社は、この新しい機能を従来のアーキテクチャに単に「付け足す」という発想から抜け出せませんでした。一方で、後発のキヤノンは、この新しい結合関係を中心に据えて装置全体を設計し直し、市場の主導権を握ることに成功しました。
この分析から見えてくるのは、企業の硬直性が、単なる怠慢や能力不足から生じるのではないということです。過去の成功を効率的に再現するために磨き上げられた組織能力が、ある種の環境変化に対して適応を妨げる原因となり得ます。組織に根付いた「当たり前」が、静かに訪れる変化の足音をかき消してしまうのかもしれません。
部門間の解釈の断絶が大企業の革新を妨げる
新製品を市場に送り出し、成功させるためには、多様な専門知識の結集が不可欠です。技術部門は製品の実現可能性を探り、営業部門は顧客のニーズをつかみ、製造部門は品質とコストを管理し、企画部門は事業全体の戦略を描く。これらの部門が円滑に連携することで、革新的な製品は生まれます。しかし現実には、多くの大企業が部門間の連携に苦慮しています。その根源には、役割分担や立場の違いを超えた、より根深い問題が存在します。
5つの大企業における18の新製品開発事例を対象としたインタビュー調査は、この問題の核心に光を当てています[3]。この調査で明らかになったのは、部門ごとに、持っている知識が違うだけでなく、物事を理解し、意味づけるための枠組み、いわば「思考世界」が異なっているという事実です。
例えば、インタビューの中で各部門の担当者が何に関心を持ち、どのような言葉で語るかを分析すると、その違いは歴然としています。企画部門は市場規模や収益性といった「ビジネス」の言葉で語り、技術部門は設計や性能といった「技術」の言葉を多用します。営業部門の関心は顧客の具体的な使い方や課題にあり、製造部門は工場の生産能力や品質管理に話が集中します。これは当然のことと思われるかもしれません。
しかし、その違いは表面的な知識の差にとどまりません。未来をどう捉えるかという点においても、各部門の世界観は異なります。技術部門にとって未来とは、新しい技術の可能性を追求し、設計上の課題を解決していくプロセスの連続です。営業部門にとって未来は、日々変化する顧客の要求にいかに応えるかという、短期的で具体的な課題の連続体として現れます。企画部門は未来を、より抽象的なビジネス機会や市場の変化として捉え、製造部門は、工場の安定稼働という制約の中で未来を見通します。
彼ら彼女らは皆、自分たちの視点から製品開発の「全体」を見ていると考えています。しかし、実際にはそれぞれの「思考世界」という色眼鏡を通して、一部分を見ているに過ぎません。その結果、部門間の対話はすれ違いに終わります。営業が持ち帰った顧客の曖昧な要望は、技術部門にとっては設計に落とし込めない「雑音」に聞こえ、技術部門がこだわる性能の高さは、企画部門にとってはコストを押し上げるだけの「過剰品質」に映ります。
この部門間の分断を、乗り越えるどころか、むしろ固定化させてしまうのが、組織に深く根付いた「組織ルーティン」、すなわち決まりきった仕事の進め方です。調査対象となった事例のうち、成功した製品開発では、こうした既存のルーティンが意図的に破られていました。一方で、失敗した事例では、ルーティンが忠実に守られていたのです。
あるコンピュータ関連企業(SALECO社)での二つの対照的な事例が、この点を物語っています。成功した「System I」の開発チームは、社内の通常の開発プロセスから切り離され、部門の垣根を越えた小さな独立部隊として活動しました。メンバーは常に顔を合わせ、顧客と直接対話し、既存の価格設定や品質基準にとらわれずに、新しい市場に適切な製品をゼロから作り上げました。
ところが、その成功から1年も経たずに始まった後続製品「System II」の開発では、組織は再び元のルーティンに戻ってしまいました。開発は部門ごとに分断され、顧客との対話は間接的な市場データ分析に置き換わり、社内の標準的な基準が適用されました。その結果、完成した製品は技術的には高品質でしたが、顧客が求めるものとはかけ離れており、市場に受け入れられることはありませんでした。
この事例が示しているのは、大企業における革新の難しさが、組織図や業務フローといった目に見えるレベルの問題だけではないということです。人々の頭の中にあり、日々の業務の中で無意識に共有されている「ものの見方」や「仕事の進め方」こそが、異なる知識を結びつけ、新しい価値を創造する上での障壁となっています。
先行知識が外部知を生かす吸収能力を形づくる
現代のように変化のスピードが速い時代において、企業が持続的に成長していくためには、自社の中だけで知識や技術を生み出すことには限界があります。大学や研究機関、あるいは競合他社など、組織の外部で生まれる新しい知見をいち早く察知し、それを自社の製品やサービスに活かしていく能力が求められます。外部の知識を効果的に取り込む能力は、企業の「学習能力」とも言い換えられるかもしれません。
ある研究では、この能力を「吸収能力(absorptive capacity)」という概念で捉え、その性質と源泉が探求されました[4]。吸収能力とは、単に外部の情報にアクセスできるということではありません。「外部知識の価値を認識し、それを自社の中に取り込んで理解し、商業的な目的に応用する」という一連のプロセスを遂行する能力全体を指します。
そして、この能力の根幹をなすのが、企業がそれまでに蓄積してきた「先行する関連知識」であるとされます。直観的に言えば、「何かを知っているからこそ、関連する新しい事柄を理解し、その価値を見抜くことができる」ということです。基礎的な語彙や文法を知らなければ、新しい外国語の文章を読んでも意味を理解できないのと似ています。
組織としての吸収能力は、個々の従業員の能力を単純に足し合わせたものとは異なります。組織内の誰が、どのような外部の知識に触れ、その知識が組織内でどのように伝達され、共有されるのかという、コミュニケーションの仕組みが関わっています。
ここで、企業が行う研究開発(R&D)投資について、新たな見方が提示されます。一般的に、研究開発は新製品や新技術を生み出すための直接的な活動と見なされています。しかし、それと同時に、研究開発にはもう一つの側面があります。
それは、自社の研究開発活動を通じて特定の分野の知識を深めることで、その分野における世界最先端の動向を理解し、吸収するための能力、要するに吸収能力そのものを高めるという側面です。研究開発とは、いわば外部の知見を取り込むための「アンテナ」を構築し、その感度を高めるための学習活動でもあります。
吸収能力には、「経路依存性」という特徴があります。企業が過去にどの分野の知識に投資し、蓄積してきたかという歴史が、将来どの分野の新しい知識を吸収できるかを左右するのです。一度ある技術分野から撤退し、関連する知識の蓄積を怠ってしまうと、数年後にその分野で画期的な技術が登場しても、その価値を理解したり、活用したりすることができなくなってしまうかもしれません。これを「ロックアウト」と呼びます。日々の学習の積み重ねが、将来の学習能力を決定づけます。
この考え方を裏付けるために、米国の製造業を対象とした大規模なデータ分析が行われました。その結果、いくつかの興味深い事実が確認されました。例えば、大学などで生み出される基礎科学に関連する知識は、応用科学の知識に比べて、より抽象的で、直接的な用途が定まっていないため、企業がそれを理解し吸収するのは難しいと考えられます。
分析結果は、まさにこの点を裏付けており、基礎科学との関連性が強い分野で事業を行う企業ほど、それを理解するための吸収能力を構築するために、より多くの研究開発投資を行っているという関係が見られました。
ここから導かれるのは、企業の長期的な適応能力にとって、一見すると目先の利益には直結しないような基礎的な知識の蓄積や学習活動が、実は大切であるということです。今日の効率性や短期的な成果を追い求めるあまり、未来の可能性に備えるための学習、すなわち吸収能力への投資を怠ることは、変化の激しい環境の中で自らの選択肢を狭め、やがては適応不能に陥る危険性を伴っています。
脚注
[1] Burgelman, R. A. (1983). A process model of internal corporate venturing in the diversified major firm. Administrative Science Quarterly, 28(2), 223-244.
[2] Henderson, R. M., and Clark, K. B. (1990). Architectural innovation: The reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms. Administrative Science Quarterly, 35(1), 9-30.
[3] Dougherty, D. (1992). Interpretive barriers to successful product innovation in large firms. Organization Science, 3(2), 179-202.
[4] Cohen, W. M., and Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128-152.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。