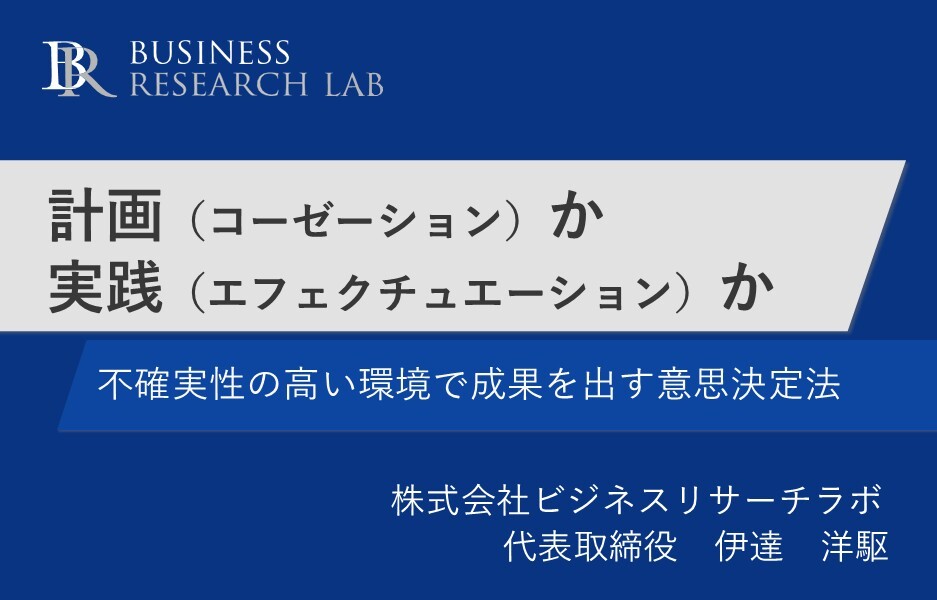2025年12月16日
計画(コーゼーション)か実践(エフェクチュエーション)か:不確実性の高い環境で成果を出す意思決定法
私たちは、先の見えない時代を生きています。市場の動向、技術の進化、社会の価値観は、目まぐるしく変化し続けています。このような環境の中で、新しい事業を始めたり、未知の課題に取り組んだりする際、どのように意思決定を下せばよいのでしょうか。
従来、ビジネスの世界で主流とされてきたのは、明確な目標を設定し、そこから逆算して詳細な計画を立て、資源を効率的に配分していくアプローチです。市場を調査し、競合を分析し、将来を予測することで成功への最短ルートを見つけ出そうとする考え方です。これは「コーゼーション(Causation)」と呼ばれ、多くの組織で当たり前のものとして実践されてきました。
しかし、未来の予測が困難な状況では、この計画中心のアプローチはうまく機能しないことがあります。緻密な計画が、予期せぬ出来事によって無価値になることも少なくありません。では、計画が役に立たないとき、私たちは何を頼りに一歩を踏み出せば良いのでしょうか。
ここに、もう一つの異なる意思決定のあり方が浮かび上がってきます。それは「エフェクチュエーション(Effectuation)」と呼ばれる考え方です。成功した起業家たちの行動を解き明かす中で見出されたもので、壮大な目標からではなく、まず「自分は何を持っているか」から出発します。そして、許容できる範囲のリスクを取りながら行動し、他者を巻き込みながら、思いもよらなかったゴールを創造していきます。
本コラムでは、このエフェクチュエーションという考え方に光を当てます。どのような状況で力が発揮されるのか。この捉えどころのない概念を、どう客観的に測るのか。そして、新しい理論としてどのような批判に直面しているのか。いくつか研究を手がかりに、その有効性、測定の試み、そして批判的視点を、順を追って掘り下げていきたいと思います。
制度的不確実性下で機会追求型なら成果を高める
未来の予測が難しい状況は常に存在しますが、その度合いが大きく高まる事態もあります。例えば、国家間の対立による突然の経済制裁は、企業にとってまさに青天の霹靂です。取引先との関係は断絶され、サプライチェーンは寸断され、事業計画は意味をなさなくなります。このような、ルールの根幹が揺らぐ「制度的不確実性」の中で、企業はどのように舵を取るのでしょうか。
この問いに答えるため、2014年の対ロシア制裁という現実に起きた出来事を舞台に、輸入依存度の高いロシアの中小企業が危機にどう対応したかを時系列で追跡した研究があります[1]。造船部材を扱うA社と食品原料を輸入するB社という、対照的な道を歩んだ2社に焦点を当て、経営者の意思決定プロセスが詳細に分析されました。分析は、制裁前、制裁直後の初年、その後の安定期という3期間に分けて行われています。
その結果、両社に共通していたのは、制裁という大きな環境変化に直面した当初、計画に基づいた意思決定が困難になり、エフェクチュエーション的な行動が増加した点でした。しかし、両社の運命を分けたのは、そのエフェクチュエーションの「質」の違いでした。
A社は、「機会追求型」のエフェクチュエーションを実践しました。西欧の取引先を失う危機に、自社の存在意義を「供給業者」から「部分的な製造も担うパートナー」へと捉え直しました。そして、社内で新しい知識を素早く習得し、既存の中国企業との関係を足がかりに、新たなサプライヤーを迅速に開拓したのです。
A社は、許容できる損失の範囲内で中国製エンジンを試験的に発注するなど、小さな実験を繰り返しました。うまくいかなければ撤退するという「安く学ぶ」方針で、リスクを管理しつつ可能性を探ったのです。景気後退で市場に出た熟練人材の雇用や、大手の撤退で生まれた市場の空白を捉えた大型案件の獲得など、偶然の出来事をも成長の糧に変えていきました。これらの行動は、新しい事業の方向性へと収斂していきました。
一方、B社が取ったのは「生存志向型」のエフェクチュエーションでした。米欧からの原料供給が絶たれ、イランやインドに切り替えようと試みましたが、品質や物流の問題に直面しました。旧来の知識が通用しなくなったことは認識していましたが、新しいスキルやネットワークの獲得は遅々として進みませんでした。
B社も損失を抑えようとしましたが、それは新しい挑戦のための投資というより、「撤退の可能性を計算する」という守りの姿勢に終始しました。結果、品質クレームや欠品が相次ぎ、顧客の信頼を失いました。個々の意思決定は場当たり的で関連性がなく、組織のエネルギーは消耗するばかりでした。
この2社の経験から見えてくるのは、不確実性の高い環境下では、計画を放棄するだけでは不十分だということです。危機を成長の機会とするには、手持ちの資源を創造的に捉え直し、小さな失敗を学習コストとして受け入れ、偶然を戦略的に取り込む「機会追求型」の姿勢が求められます。エフェクチュエーションという行動様式そのものではなく、その実践の仕方が企業の成果を左右するのです。
高革新R&Dで成果を高めることが示された
企業の成長の原動力となる研究開発(R&D)活動は、本質的に不確実性を伴います。これまでにない製品や技術を生み出そうとする「革新性の高い」プロジェクトでは、最終的に何が生まれるのか、事前には誰にも予測できません。このような状況は、先ほどの制度的ショックとは質が異なりますが、未来が見通しにくい点では共通しています。
こうしたR&Dの現場で、エフェクチュエーション的なアプローチと、伝統的な計画に基づいたアプローチ(コーゼーション)は、それぞれどのような成果をもたらすのでしょうか。この問いを検証するため、ドイツ企業が手掛けた400件のR&Dプロジェクトを対象に、その「革新性」の度合いに着目した調査が行われました[2]。市場や技術にとっての新規性が高い「高革新プロジェクト」と、既存の改良に近い「低革新プロジェクト」に分け、それぞれで有効なアプローチが異なるという仮説を立てたのです。
プロジェクトの「成果」も二つの側面から測定されました。一つは予算やスケジュール遵守といった「プロセス効率」、もう一つは新しい知識の獲得や成果物の価値といった「プロジェクトアウトプット」です。
分析の結果、プロジェクトの革新性によって、有効なアプローチが異なることが明らかになりました。
革新性が高いプロジェクトでは、エフェクチュエーション的なアプローチが力を発揮しました。具体的には、社内外のパートナーとの連携を重視する姿勢(パートナーシップ)や、予期せぬ出来事を新しい可能性として柔軟に受け入れる姿勢(予期せぬ事象の受容)が、「プロジェクトアウトプット」の向上に結びついていました。ゴールが不確かな旅では、計画に固執するより、多様な仲間と知恵を出し合い、偶然の発見から学ぶことが価値ある成果を生むのです。
また、許容できる損失の範囲をあらかじめ決めておくアプローチ(許容可能損失)は、「プロセス効率」を高めました。大きな失敗を防ぎ、手戻りのコストを抑えながら素早い意思決定を繰り返すことが、効率的な進行につながることを示唆しています。
一方で、革新性が低いプロジェクトでは、逆の結果が見られました。こちらでは、伝統的なコーゼーションのアプローチが有効だったのです。明確な目標を設定し(目標主導)、期待される収益に基づいて資源を配分し(期待収益)、計画から逸脱しないように予期せぬ事象を克服しようとする姿勢が、「プロセス効率」と「プロジェクトアウトプット」の両方を高めていました。ゴールが明確な漸進的改良プロジェクトにおいては、計画を立て、それを着実に実行していくことが、確実で効率的な方法であると言えます。
この研究が解き明かしたのは、R&Dマネジメントにおける「適材適所」の論理です。エフェクチュエーションもコーゼーションも、それ自体が絶対的に優れているわけではありません。プロジェクトが置かれている状況、すなわち不確実性の度合いに応じて、その有効性が変わるのです。
実験・損失許容・柔軟性の多次元構造で測定できる
エフェクチュエーションが特定のビジネス環境で有効である可能性が見えてきましたが、学術的な探求を深めるには、その概念自体をより明確に定義し、客観的に測定する手段が不可欠です。ある考え方を測る「ものさし」がなければ、その有効性を科学的に検証するのは難しいからです。ここでは、その「ものさし」作り、すなわちエフェクチュエーションの構造を解き明かし、測定可能な尺度を開発しようとした研究を取り上げます[3]。
この研究は、新規事業を立ち上げたばかりの起業家たちを対象に行われました。まず35人の起業家へのインタビューで得られた言葉を手がかりに質問項目を作成し、その後、2つの異なる業界の創業者300人以上を対象にアンケート調査が実施されました。集められたデータは、質問項目の背後にある共通の要素を探るために分析されました。
分析の結果、明快な構造が浮かび上がりました。
伝統的なアプローチであるコーゼーションについては、「長期的な機会を分析する」「競争相手を詳しく調べる」といった質問項目が一つのグループにまとまりました。コーゼーションが、計画と分析を中心とした一貫性のある単一の考え方として測定できることを意味します。
ところが、エフェクチュエーションは異なる様相を呈しました。関連する質問項目は、一つの大きな塊にはならず、それぞれ性質の異なる3つの独立したグループを形成したのです。エフェクチュエーションが複数の異なる行動原理から構成される、多面的な構造を持つことを明らかにしました。その3つの柱とは、以下の通りです。
第一の柱は「実験」です。一つのアイデアに固執せず、試行錯誤を繰り返しながら実行可能な道筋を見つけ出そうとする行動原理を指します。第二の柱は「許容損失」です。期待リターンを最大化するのではなく、最悪の事態でも耐えられる範囲内にリスクを抑えるという独自の判断基準です。第三の柱は「柔軟性」です。計画に縛られず、予期せぬ出来事や環境の変化に臨機応変に対応していく姿勢を指します。
加えて、「顧客や供給業者と事前に合意を取り付け、不確実性を減らした」といった「事前確約」に関する行動は、エフェクチュエーションとコーゼーションの双方に共通して見られることがわかりました。これは、他者を巻き込んでリスクを分担する行為が、異なる意思決定アプローチにとって有用な基盤となりうることを示唆しています。
この研究は、曖昧に語られがちなエフェクチュエーションに構造を与えました。それは、コーゼーションのような単一のロジックではなく、「実験」「許容損失」「柔軟性」という、複数の実践の束です。この多次元的な理解は、エフェクチュエーションをより深く、そして具体的に分析するための道を開きました。
有益だが理論要件を十分満たしていないと批判された
これまで、エフェクチュエーションが特定の状況で有効であることや、その概念が測定可能な構造を持つことを見てきました。しかし、学問の世界では、新しい考え方が「理論」として確立されるまでには、厳しい吟味と検証のプロセスを経る必要があります。ここでは、エフェクチュエーションは「起業の新しい理論」と呼ぶにふさわしいのか、という問いを、批判的な視点から検討した研究を取り上げます[4]。
この研究は、一つの理論として成熟するために、どのような点を強化する必要があるのかを明らかにしようとする試みです。そのために「3E」と名付けた独自の評価フレームワークが用いられました。これは、理論を「Experience(経験)」「Explain(説明)」「Establish(確立)」という三つの側面から評価するものです。
このフレームワークに沿ってエフェクチュエーションを評価した結果、いくつかの課題が浮かび上がりました。
第一に、「Experience(経験)」の側面では、エフェクチュエーションの核となるアイデアは、実はそれほど目新しいものではなく、過去の経営学における類似の概念との違いや関係性が十分に整理されていない、という批判がなされました。
第二に、理論の根幹である「Explain(説明)」の側面では、複数の論点が提示されました。一つは、理論モデルの網羅性に関する問題です。エフェクチュエーションのモデルは、起業家個人の意思決定に焦点が当てられていますが、競争相手の存在や市場のルールといった「外部からの対抗力」が十分に考慮されていません。これでは、競争が激しい環境下でなぜ成功できるのかを説明するのが難しくなります。
また、理論の条件が曖昧であることも問題視されました。どのような種類の不確実性のもとで、どの程度の資源制約があればエフェクチュエーションが有効なのか、その適用範囲が明確に定義されていないのです。これでは、実務家がいつこのアプローチを使うべきか判断するのも、研究者がその有効性を検証するのも困難になります。
第三に、「Establish(確立)」の側面では、実証と普及に関する課題が挙げられました。概念が複雑であるため、アンケート調査などで正確に測定することが難しく、客観的な検証が進みにくいという現実があります。また、実務家にとって「計画を軽視する」というメッセージが、資金調達の場面などでかえって不利に働くリスクも懸念点として示されました。
この研究の結論は、エフェクチュエーションを無価値だと断じるものではありません。不確実な状況で起業家がどのように行動するかを描写する「記述的な洞察」や、思考法を学ぶ上での「教育的な価値」は高く評価されています。しかし、一つの厳密な科学理論として認められるためには、競合の組み込み、条件の明確化など、乗り越えるべき課題がまだ残されている、というのがその評価なのです。
脚注
[1] Laine, I., and Galkina, T. (2017). The interplay of effectuation and causation in decision making: Russian SMEs under institutional uncertainty. International Entrepreneurship and Management Journal, 13, 905-941.
[2] Brettel, M., Mauer, R., Engelen, A., and Kupper, D. (2012). Corporate effectuation: Entrepreneurial action and its impact on R&D project performance. Journal of Business Venturing, 27(2), 167-184.
[3] Chandler, G. N., DeTienne, D. R., McKelvie, A., and Mumford, T. V. (2011). Causation and effectuation processes: A validation study. Journal of Business Venturing, 26(3), 375-390.
[4] Arend, R. J., Sarooghi, H., and Burkemper, A. C. (2015). Effectuation as ineffectual? Applying the 3E theory-assessment framework to a proposed new theory of entrepreneurship. Academy of Management Review, 40(4), 630-651.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。