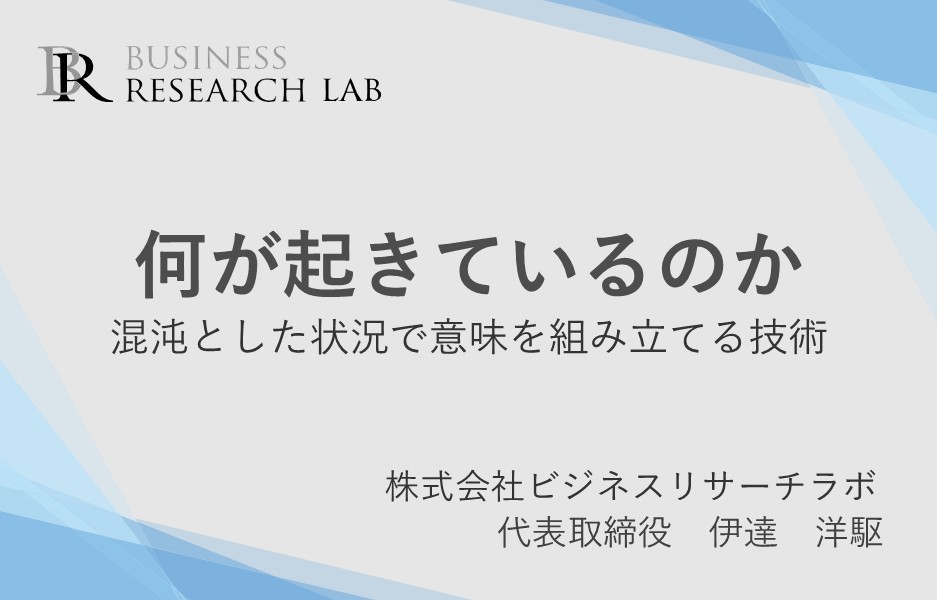2025年12月15日
何が起きているのか:混沌とした状況で意味を組み立てる技術
私たちの日常は、ある日突然、予期せぬ出来事によって断ち切られることがあります。大規模な災害や事故かもしれませんし、あるいは所属する組織を揺るがすような不祥事や経営危機かもしれません。そのような「危機」の渦中に置かれたとき、人々は一体どのようにして目の前で起きていることを理解し、次の一歩を踏み出そうとするのでしょうか。私たちは普段、自分が合理的に物事を判断していると信じています。しかし、極度の混乱と不確実性の中では、その自信はもろくも崩れ去ることがあります。
本コラムでは、「センスメイキング」という視点を通して、危機的状況における人間の営みを見つめていきます。センスメイキングとは、混沌とした出来事の中から手がかりを拾い上げ、それらを結びつけて「何が起きているのか」という、もっともらしい物語を組み立てていくことです。答えが一つに定まらない世界で、意味を生成していくプロセスと言えるでしょう。
過去の事例に関する緻密な研究を手がかりに、危機の中で私たちの「理解」がどのように作られ、共有され、時には致命的なまでに歪んでしまうのか、そのメカニズムを解き明かしていきます。なぜ、良かれと思って取った行動が事態を悪化させてしまうのか。なぜ、周到に準備されたはずの新しいルールが、かえって混乱を招くのか。これらの問いを探求することを通して、危機のただ中で起こる人間と組織の現実を、より深く知ることを目指します。
危機は行為による構築とセンスメイキングで拡大する
危機というものは、外部から突然やってくる脅威だと考えられがちです。しかし実際には、危機の一部は私たち自身の「行為」によって形作られ、拡大していく側面を持っています。私たちの行動が、意図せずして危機的な環境を生み出してしまうという、一見すると逆説的なプロセスが存在するのです。
このプロセスを理解する上で核となるのが、「センスメイキング」と「エナクトメント(行為による構築)」という考え方です。私たちは通常、「まず考えてから行動する」という順序で物事を捉えますが、先の見えない混乱した状況では、この順序が逆転することがあります。「まず行動してみて、その結果を振り返ることで、自分が何を考えていたのか、そして今何が起きているのかを理解する」というプロセスです。例えば、暗闇の中で手探りで壁に触れ、その感触から部屋の形を推測するように、私たちの行為が世界から情報を引き出し、その情報が私たちの理解を形作ります。この一連の営みが、センスメイキングをなしています。
この観点から、ある化学工場の事故を分析した研究があります[1]。この研究は、危機が人間の行為の連鎖によっていかに「構築」されていくのかを浮き彫りにしました。事故のきっかけはタンクへの水の浸入でしたが、その背景には、人間の判断に起因する数多くの小さな逸脱が積み重なっていました。例えば、配管清掃時に安全のための仕切り板を省略した判断。この行為が結果的に水の逆流を許し、破局的な化学反応へとつながる道を開きました。
この研究は、危機の拡大プロセスを、「コミットメント」「キャパシティ(対処能力)」「期待」という三つを通して分析しています。
一つ目の「コミットメント」は、一度下した決定や公言した立場に人々が縛られる心理的なメカニズムです。この工場では、危険物質に関する情報を「秘匿する」という方針がありました。このコミットメントが、異常事態発生時に警報を遅らせる行為を引き起こしました。また、「安全対策は是正済み」と公言していた手前、コスト削減のための冷却装置停止を危険ではないと思い込みやすかった可能性も指摘されています。過去の言動へのこだわりが、新たな情報を評価する際の「盲点」となり、危険な行為を正当化してしまうのです。
二つ目の「キャパシティ」は、組織や個人が持つ対処能力や資源です。人は自分が「対処できる」と信じる範囲の物事にしか注意を向けないことがあります。この工場では人員削減で現場の作業員が大幅に減り、異常の兆候を検知し行動する人的資源が枯渇していました。加えて、管理職に技術的な専門知識を持つ者が少なく、現場からの報告の意味を適切に解釈し、迅速な判断を下すことが困難でした。組織の知識や技能のレパートリーが乏しいと、そもそも何に注意すべきかというカテゴリー自体が貧弱になり、危険な兆候を見過ごしやすくなります。
三つ目の「期待」は、経営層などが抱く認識が自己成就的に現実を作り変えるプロセスです。この工場の親会社は、この工場を「重要でない」と見なしていました。このようなトップの期待は、現場のコスト削減圧力や安全への投資軽視、従業員の士気低下といった形で具現化します。結果、システムの予備能力が削られ、組織全体が些細なエラーにも耐えられない脆弱な状態に陥ります。ここで見逃せないのは、「安全」に関する直接的な期待だけでなく、「この組織は価値があるのか」といった期待が、組織の行動様式を通じて間接的に安全性を損なうという構造です。
新旧ルーティン重複が危機下のセンスメイキングを乱す
危機に備え、組織が新しいルールや手順、すなわち「ルーティン」を導入することは当然の対応に思えます。しかし、ある銃撃事件を詳細に分析した研究は、こうした「備え」が、時として意図せざる混乱を生み出し、現場のセンスメイキングを阻害する危険性を明らかにしました[2]。
この研究が取り上げたのは、2005年にロンドンの地下鉄駅で、警察官が無実の市民を射殺した事件です。当時ロンドン警視庁は、自爆テロの脅威に対応するため、「オペレーション・クラトス」という新しい対処ルーティンを導入していました。これは自爆テロ犯と特定された人物を即座に射殺して無力化するという厳しい内容でした。一方で、警察には容疑者を監視し安全に拘束するという従来からのルーティンも存在していました。事件当日、現場の警察官たちは、この新旧二つのルーティンが重なり合った曖昧な状況下で行動することを余儀なくされたのです。
事件の経過を追うと、現場の警察官たちのセンスメイキングが特定の方向へ導かれていったかが見えてきます。作戦前のブリーフィングでは、「通常とは異なる戦術」「司令室からの情報を信頼せよ」といったメッセージが伝えられ、特殊な弾薬が支給されました。これらの出来事は、現場の警察官たちにとって強力な「キュー(手がかり)」となり、「これは通常の監視任務ではない。テロリストに対処する特別な作戦なのだ」という解釈の枠組み、すなわち「フレーム」が強く形成されていきました。
その結果、監視対象の人物が本当にテロリストかについて、現場から「似ている」「識別不能」といった不確実な情報が上がっていたにもかかわらず、司令室や追跡チームはそれらを過小評価し、対象をテロリストと断定する方向に傾きました。そして、対象が駅に駆け込もうとしたとき、司令官から発せられた「彼を止めろ(Stop him)」という指示が引き金となります。本来この言葉は「停止させて拘束せよ」という意味合いで使われることが多いものです。しかし、「オペレーション・クラトス」という新しいフレームの中でこの言葉を聞いた現場の警察官たちは、それを「いかなる手段を使っても即座に阻止せよ」という意味だと解釈し、悲劇的な結末へと至りました。
この研究は、事件の背後にあるセンスメイキングの乱れを、三つの観点から分析しています。
第一に、「フレームとキューの結合の乱れ」です。作戦前の様々なキューが、現場のフレームを新しい対テロ作戦へと偏らせました。これにより、そのフレームに合致しない情報(対象がテロリストではない可能性を示唆するキュー)は聞こえにくくなり、認知的な偏りが生じました。同じ「止めろ」という言葉が、どのフレームで解釈されるかによって、異なる行為につながってしまったのです。
第二に、「新旧ルーティンの重なり」です。新しいルーティンは古いルーティンを消し去るわけではなく、多くの場合、併存します。この事件では、「監視し、安全に拘束する」という古いルーティンと、「即時に無力化する」という新しいルーティンが同時に稼働していました。一つの出来事に対して、もっともらしい解釈が複数同時に存在する「同義性(equivocality)」と呼ばれる状態が生まれました。複数の意味が競合することで一貫した行動が取れなくなる、より複雑な混乱状態だったと言えます。
第三に、「役割アイデンティティの揺らぎ」です。新しい対テロ作戦は、警察官の役割を、自律的な判断者から指示の遂行者へと変化させるものでした。しかし、長年の訓練で染みついた自己認識は簡単には消えません。その結果、現場の警察官たちは、「自分は今、誰としてここにいるのか」というアイデンティティの揺らぎに直面し、それが状況解釈と行動の不整合をさらに増幅させました。
この事例が私たちに伝えるのは、危機への「備え」がいかに難しいかということです。ルールや手順といった目に見えるものを新しくするだけでは不十分です。その新しい仕組みが、既存のやり方や人々の自己認識とどう作用し合うのか。そこまで洞察しなければ、良かれと思って導入した備えが、かえって悲劇の引き金になりかねないのです。
共有意味と感情が危機と変革のセンスメイキングを左右する
危機や組織の大きな変革といった激しい揺らぎのただ中で、人々はどのように状況を理解し、前に進むための足がかりを見つけるのでしょうか。私たちの理解を形作る上では、より内面的な、それでいて集団的な要素が決定的な働きをすることがあります。「共有された意味」と「感情」です。
センスメイキングに関する数多くの研究を横断的にレビューし、この二つのテーマの重要性を浮き彫りにした分析があります[3]。この分析によれば、危機と変革という異なる文脈で起こるセンスメイキングには、共通する構造が見出せるというのです。
まず一つ目の核となるテーマは、「共有された意味」です。これは組織のメンバーが共に抱いている信念や価値観、自己認識などを指します。この共有された意味は、人々を団結させる力を持つ一方で、組織を誤った方向へ導く危険性もはらんでいます。この研究は、共有された意味を「コミットメント」「アイデンティティ」「期待」という三つの側面から捉え直しています。
「コミットメント」は、公に表明された目標や約束です。危機的状況では、一度表明した判断への固執が適応を妨げる足かせになり得ます。しかし、危機後の再生期には、リーダーが示す未来への強いコミットメントが、組織を動員する力にもなります。
「アイデンティティ」は、「私たちは誰なのか」という問いへの答えです。危機や変革は自己認識を揺るがし、思考を停止させることがあります。また、現状に適合しなくなったアイデンティティへの固執は、外部からの新しい考え方を排除し、集団の学習能力を奪うことにつながりかねません。
「期待」は、将来への予測や見通しです。過度に楽観的な期待は危険な兆候を見過ごさせ、悲観的な期待は挑戦意欲を削ぎます。期待は変わりにくい「粘着性」を持っています。この粘着性に対抗するために大切になるのが、「更新(updating)」と「懐疑(doubting)」という二つの態度です。更新とは新しい情報に基づいて解釈を修正する柔軟さであり、懐疑とは自らの意味づけが常に暫定的なものだと自覚する姿勢を指します。
二つ目の核となるテーマが「感情」です。センスメイキングは冷静な認知作業と見なされがちですが、危機や変革の現場は強い感情に満ちています。この研究は、感情の種類とその「強度」がセンスメイキングに与える働きを区別して論じています。
恐怖や不安といった「否定的感情」は、注意の範囲を狭め思考を硬直させる傾向がありますが、物事を慎重に検討することを促す側面も持ち合わせています。希望や喜びといった「肯定的感情」は、思考や行動のレパートリーを広げ、困難に立ち向かうレジリエンスを高める資源となります。しかし行き過ぎれば、根拠のない楽観主義を生み、危険な兆候を過小評価する原因となり得ます。
ここから導き出される一つの示唆は、感情の良し悪しを論じるのではなく、その「強度」を管理することの必要性です。感情は重要な信号ですが、その強度が極端になると、冷静な判断に必要な認知的な資源を食いつぶしてしまいます。適度な強度の感情を保ち、自らの解釈を更新し、懐疑する余地を残しておくこと。それが、適応的なセンスメイキングの鍵となるのかもしれません。
役割構造崩壊が危機下のセンスメイキングを失わせた
組織とは、人々がそれぞれの「役割」を理解し、互いの行動を予測し合いながら連携することで成り立っています。もしこの拠り所となるべき役割構造そのものが、極度の危機の中で突然崩壊してしまったら、人々は何を頼りに状況を理解し、行動すればよいのでしょうか。1949年にアメリカのモンタナ州で起きた「マングルチの山火事」の悲劇は、この問いに対する、痛切な答えを私たちに突きつけます。
この事件を、組織におけるセンスメイキングの崩壊という観点から分析した研究があります[4]。この研究は、事件の当事者となった「スモークジャンパー」と呼ばれる精鋭の森林消防隊が、なぜ統制を失い、13名もの犠牲者を出すに至ったのか、そのメカニズムを解き明かそうと試みました。
事件の経過は、次のようなものでした。山火事の現場に降下した15名の隊員たちは、風向きの急変で猛烈な勢いで燃え広がる火に追い詰められます。絶体絶命の状況の中、隊長のドッジは、二つの不可解な命令を発しました。一つは、自ら草地に火をつけ、その焼け跡を避難場所とする「エスケープ・ファイア」。もう一つは、重い消火道具を「すべて捨てろ」という指示でした。
しかし、隊員たちのほとんどは、隊長の命令の意味を理解できませんでした。火から逃げるのが常識である消防士にとって、「火の中に入れ」という指示は理解不能でした。また、消火道具は、彼らが消防士であることの証そのものです。それを捨てることは、自らのアイデンティティを放棄するに等しい行為でした。混乱した隊員たちは命令に従わず、ただひたすらに斜面を駆け上り続け、そして、背後から迫る炎に飲み込まれていきました。
この研究は、この悲劇を単なるパニックとして片付けるのではなく、組織的なセンスメイキングの崩壊として捉えます。その崩壊は、二つのレベルで同時に進行しました。
第一に、「役割構造の崩壊」です。隊長の命令が理解されなかった瞬間、「指揮―服従」という基本的な役割関係が失われました。これによって、集団はもはや一つの統合されたチームとして機能しなくなり、個々人がバラバラに行動する「群れ」へと解体されてしまいました。
第二に、それに伴う「アイデンティティの崩壊」です。「道具を捨てろ」という命令は、隊員たちから「スモークジャンパーである自分」という自己認識を奪いました。自分たちが何者であるかという拠り所を失った人々は、最も原始的な反応、すなわち「ただ走って逃げる」という行動に退行してしまったのです。
このように、役割構造と個人のアイデンティティという、センスメイキングの二つの土台が同時に崩れ去ったとき、人々は「自分はどこにいるのか、何が起きているのか、何をすべきなのか」を理解する術を完全に失います。研究者はこの状態を「宇宙観の逸脱」と呼びました。
しかし、この悲劇の中にも、センスメイキングの崩壊を食い止め、生き延びるための手がかりを見出すことができます。この研究は、絶望的な状況から立ち直るための「レジリエンス」の源泉として、四つの要素を抽出しています。
一つ目は、「即興性とブリコラージュ」です。隊長が試みた「エスケープ・ファイア」は、その場のありあわせの資源を組み合わせて新しい解決策を生み出す、まさに即興的な行為でした。
二つ目は、「バーチャルな役割体系」です。たとえ公式の指揮系統が機能しなくても、メンバーの頭の中に組織全体の役割の地図が描かれていれば、互いに足りない部分を補い合いながら自律的に協働できます。
三つ目は、「賢慮の態度」です。これは、「自分はすべてを知っているわけではない」という謙虚さと、「しかし、それでも行動しなければならない」という意志を両立させる姿勢です。
四つ目は、「敬意ある相互作用」です。互いを尊重し、信頼し、正直に情報を交換し合う関係性です。これが意味と構造の両方を支える基本的な基盤となります。
マングルチの悲劇が物語っているのは、組織の強さは、完璧な計画や厳格なルールによってのみもたらされるのではないということです。予期せぬ事態に直面したときに即興的に協働できる柔軟性や、互いへの敬意といった、人間的なつながりの中に、崩壊の淵から立ち上がるための力が宿っているのです。
脚注
[1] Weick, K. E. (1988). Enacted sensemaking in crisis situations. Journal of Management Studies, 25(4), 305-317.
[2] Colville, I., Pye, A., and Carter, M. (2013). Organizing to counter terrorism: Sensemaking amidst dynamic complexity. Human Relations, 66(9), 1201-1223.
[3] Maitlis, S., and Sonenshein, S. (2010). Sensemaking in crisis and change: Inspiration and insights from Weick (1988). Journal of Management Studies, 47(3), 551-580.
[4] Weick, K. E. (1993). The collapse of sensemaking in organizations: The Mann Gulch disaster. Administrative Science Quarterly, 38(4), 628-652.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。