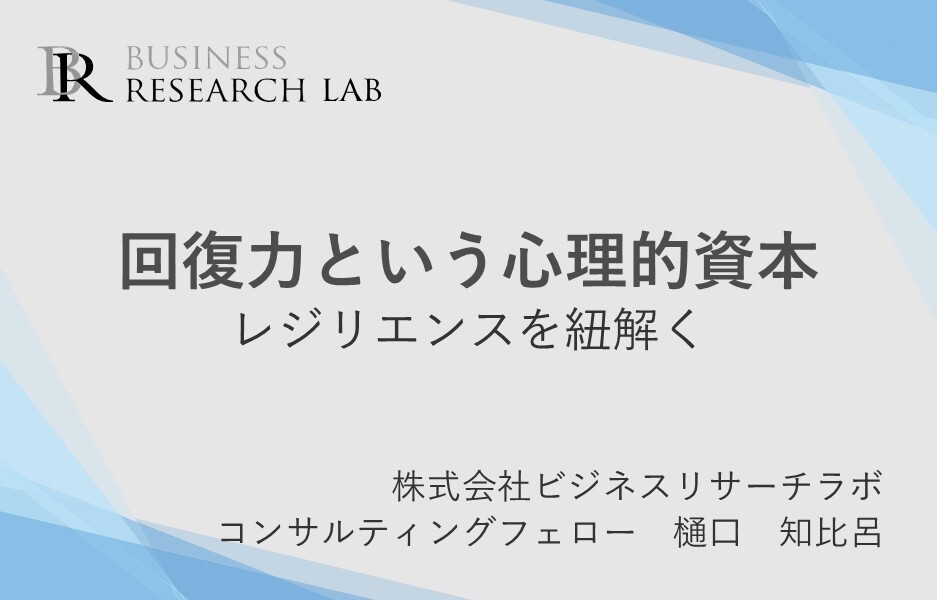2025年12月12日
回復力という心理的資本:レジリエンスを紐解く
組織の成果を左右する要素として、従業員の能力やスキル、モチベーションが挙げられることは多いですが、近年では「レジリエンス」、すなわち逆境からの回復力や適応力に対する関心が高まっています。これは単なる個人のストレス耐性を超え、チームや組織全体の持続可能性や柔軟性にも深く関係する概念として再評価されているからです。激しい環境変化や不確実性への対応が求められる現代のビジネス環境においては、成果を出し続ける力以上に、立ち直る力、回復する力、学び直す力が問われているといえるでしょう。
このような流れの中で、心理学や精神医学、社会学など多分野にわたる研究により、レジリエンスという概念はより多面的かつ実践的に整理されてきました。近年の研究では、レジリエンスを単なる「性格的な強さ」や「内面の特質」として捉えるのではなく、環境との相互作用や、支援的な人間関係、組織文化との関係性の中で変化しながら形作られるプロセスとして理解する視点が強調されています。
本コラムでは、こうした最新のレジリエンス研究をもとに、個人の成長や職場のパフォーマンス向上にどうつながるのか、そしてマネジメントの現場でどのように応用しうるのかについて考察していきます。職場におけるレジリエンスを考えるには、人間関係や環境、心のエネルギー、制度面までを含む多面的な視点が欠かせません。本コラムでは、これらの多面的な視点を踏まえながら、ビジネスの現場で実際に役立つレジリエンスのあり方について探っていきます。
希望・楽観性・レジリエンスが生む職場の好循環
ポジティブ心理学の流れを汲み、近年注目されているのが「ポジティブ組織行動(Positive Organizational Behavior:POB)」という概念です。POBの中核となる心理的資本である希望(hope)、楽観性(optimism)、レジリエンス(resilience)が、従業員の仕事における成果や満足度にどのような影響を及ぼすかを明らかにしようとした研究があります[1]。
研究はアメリカ中西部の複数業種にわたる組織に所属する従業員対象に行われました。自己申告による業務評価と上司からのパフォーマンス評価を用い、希望・楽観性・レジリエンスがパフォーマンス、仕事満足度、仕事幸福感、組織コミットメントに与える影響を検証しました。
分析の結果、希望、楽観性、レジリエンスはそれぞれ異なる形で業務成果に影響を与えていることが明らかになりました。とくに希望は、目標に向かう意欲とその達成経路の想定という2要素から成り、自己効力感や計画性を支える重要な資本であるとされました。楽観性は、困難な出来事を一時的かつ外的要因と捉えて、ネガティブな影響を和らげる機能があります。また、レジリエンスはストレスや失敗から立ち直るだけでなく、それらを成長の機会と捉える柔軟な適応力として作用していました。
こうした資本は後天的に伸ばせるものであり、訓練や職場環境によって開発することができる特性です。実際、短時間の介入によっても希望や楽観性、レジリエンスが高まりうることが過去の研究[2]からも示されており、これは従業員の持つポジティブな力を意識的に育てることが可能であることを意味します。
実践的な含意としては、組織においてこれらの心理的資本を育むための施策が、従業員のパフォーマンスや満足度を高めるうえで有効である点が挙げられます。たとえば、困難を振り返り、学びに変えるプロセスを支援するような振り返りの場は、レジリエンスの醸成に貢献するでしょう。
マネジメントへの応用としては、これらの心理的資本を人事評価や人材育成の観点に取り入れることが挙げられます。例えば、単なる成果主義に依らず、「目標達成に至るまでの工夫」や「失敗からの学びの質」なども評価軸とすることで、希望やレジリエンスといった内在的資本を正当に評価し、育成する文化を育むことができます。また、リーダー自身が粘り強さを示すことで、チーム全体にポジティブなモデルを提供することも期待されます。
この研究が示すように、希望、楽観性、レジリエンスはそれぞれ異なる視点から働きかけ、従業員の内発的動機づけや持続的なパフォーマンスを支えています。組織における人材マネジメントにおいては、これらの心理的資本を可視化し、育成していく視点を持つことが、結果として組織全体の健全な発展と競争優位の確立につながると考えられるでしょう。
保護因子が導くレジリエンスの仕組み
仕事や人生で大きなストレスや困難に直面したときに、人はどうすれば心のバランスを保てるのか。この問いに対する答えを探ったレジリエンスに関する研究を、紹介します[3]。この研究は、精神障害への抵抗性と、それに関わる保護因子(protective factors)の働きを明らかにすることを目的とし、子どもから大人まで幅広い対象における心理学的・社会的データを基に、多数の研究を統合して論じられています。保護因子とは、困難な状況やストレスを乗り越える力を指します。
研究では、ストレスや逆境に直面してもすべての人が心理的に傷つくわけではなく、むしろ多くの人が状況に適応しながら前向きに対処しているという事実に注目しました。特に、精神障害のリスクが高いとされる家庭環境に育った子どもたちの中にも、問題を抱えずに成長するケースが少なからず見られることから、この研究では保護因子の存在を理論的に整理し、レジリエンスの根本的な仕組みに迫っています。
調査の結果、保護因子は主に三つのタイプに分類されました。第一に、良好な人間関係や愛着関係などの対人支援です。これは、親や配偶者との安定した関係が、ストレス時の精神的ダメージを和らげるというものです。第二に、認知的枠組みや自己効力感、つまり自分を価値ある存在と捉え、困難にも対処できるという信念です。第三に、対処行動、すなわち状況に応じて適切な行動をとる能力です。これらは単独で作用するのではなく、発達の過程において相互に影響を与えながら機能するとされています。
この研究から得られる実践的な含意は、レジリエンスは生まれつきの強さではなく、後天的に培われるものであるということです。たとえば、過去に成功体験がある人ほど、ストレスに対して前向きに対処する傾向があるとされています。ただし、ある特性がある場面では役に立っても、別の場面では必ずしも同様の効果を持たないことが指摘されています。すなわち、文脈やタイミングが極めて重要なのです。
マネジメントの視点からは、この知見を人材育成や職場環境の設計に活用することが有効です。例えば、社員が困難な状況にあるときには、自己責任として放っておくのではなく、信頼できる上司や同僚との関係を大切にしたり、適切なフィードバックをしたり、そして裁量を持って自分の判断で行動できる環境を整えることで、レジリエンスを高めることができます。また、過去の達成経験を積ませるキャリア支援や、意味のある役割を与える人材配置は、自己効力感を高め、困難に立ち向かう力を引き出す可能性があります。
この研究が示すのは、レジリエンスを高める取り組みが、一時的な対処スキルの習得にとどまらず、長期的な発達プロセスの中で支えられるという点です。そのため、個人を取り巻く環境や人間関係に配慮しながら、経験を通じた成長の機会を与えることが、ビジネスの現場においても持続可能なパフォーマンス向上につながるでしょう。
レジリエンスは環境と共に育つ
子どもから大人までの発達の過程において、心理的な適応や問題行動がどのように生じ、変化していくのかを、発達の視点から理解しようとする学問として発達精神病理学があります。発達精神病理学とポジティブ心理学の接点に着目し、レジリエンスがどのように定義され、何によって支えられているかを体系的に整理した研究があります[4]。この研究では、レジリエンスが単なる個人の資質ではなく、重大な困難に直面しても前向きに乗り越えようとする力やそのプロセスとして捉えることが大切だと考えています。
この研究は、子どもから成人に至るさまざまな年齢層の人たちを対象にしています。親の病気や貧困、暴力など厳しい環境の中でも心身の健康を保ちながらうまく適応している人にはどんな特徴や周囲の支えがあるのかを明らかにしようとしたものです。特に、時間の経過とともに人の変化を追う研究や、ストレスの原因とそれを和らげる要素の関係に注目し、個人の能力や性格だけでなく、家族・学校・地域といった周囲の環境がどのように影響し合っているかを詳しく分析しています。
調査から分かったのは、レジリエンスは常に同じように発揮されるわけではなく、置かれた状況やタイミングによって強くもなれば弱くもなる、場面ごとの性質を持っているということです。すなわち、ある子どもが学業には適応している一方で、感情的には不安定であることもある、というように、レジリエンスは単一ではなく多面的な性質を持っています。
また、レジリエンスは生まれつきの性格ではなく、実際の行動や反応として現れるものです。そしてそれを評価するには、困難な状況があったことと、その中で思った以上にうまく適応できていたことの両方が必要になります。
この知見は、ビジネス実務においても重要な含意を持ちます。たとえば、従業員のストレス対処力や問題解決力を高めようとする際には、個人の特性を評価するだけでなく、その人が直面している職場のリスク因子(例:ハラスメント、役割の曖昧さ、過度な業務負担など)と、保護因子(例:心理的安全性、上司の支援、仲間意識)を併せて捉える必要があります。
マネジメントの観点からは、レジリエンスを育成するものとして捉え、状況に応じた支援を設計することが効果的です。たとえば、困難な状況にあるチームに対しては、単にポジティブ思考を促す研修ではなく、信頼関係のある対話の場を提供したり、リーダーが積極的に支援者として機能することが重要になります。また、業務外のサポート(例:メンター制度や社内コミュニティー、クラブ活動支援など)も、長期的にレジリエンスを高める基盤となるでしょう。
この研究の示唆する最大のポイントは、強さそのものよりも、それを支える環境要因との相互作用を重視すべきということです。レジリエンスは個人の内面に閉じた力ではなく、周囲とのつながり、そしてそこに与えられる意味づけによって育まれるものであるため、組織としては従業員一人ひとりが持つ力を発揮しやすい環境を整える取り組みが、結果的に持続可能な成長と健康的な職場文化の醸成につながっていくといえるでしょう。
多層的な視点から捉えるレジリエンス
レジリエンスの定義と構成要素を包括的に見直し、臨床および公衆衛生における実践的意義を探った研究があります[5]。この研究は、カナダで発表されたレポートを出発点とし、文献レビューを通じて、レジリエンスの定義や要因に関する主要な研究成果を抽出しました。
調査の結果、レジリエンスは「逆境に直面しても精神的健康を保つ、あるいは回復する能力」と定義されていますが、その性質は生まれつきに決まっている固定的な特性というよりも、生涯を通じて環境や経験によって変化・成長していく柔軟な力であることが明らかになりました。
さらに、レジリエンスは個人の特性(例:自己効力感、感情調整力)、生物学的要因(例:神経伝達物質の働き)、環境的要因(例:家族・地域の支援)、そしてこれらの相互作用によって形成されるとされています。特に、幼少期の養育環境や社会的支援が、成人期のレジリエンスに及ぼす影響は大きいことが分かっています。また、支えとなる人間関係はストレスに対する体と心の反応に長期的な影響を及ぼすことも示されています。
こうした知見は、ビジネス現場にも応用できる示唆を含んでいます。例えば、職場におけるレジリエンスの促進には、単に個人のストレス対処能力を高める研修だけでなく、上司との良好な関係や心理的安全性、支援的な同僚ネットワークの構築といった環境面の配慮が効果的です。
加えて、従業員のライフステージや文化的背景に応じた多様な支援策の設計も求められます。例えば、メンタルヘルス研修や1on1ミーティングの充実、柔軟な働き方の導入などが、個々のニーズに応じたレジリエンス強化に役立ちます。
マネジメントの観点からは、レジリエンスを個人の性格や能力の問題として片づけるのではなく、組織がレジリエンスを支える土台となることが重要です。たとえば、失敗を許容する文化や、キャリアの中断・再出発を肯定的に受け入れる制度設計は、従業員の長期的な回復力を支える土台となります。また、個人だけでなくチーム全体の回復力を高めることにも注目が集まっています。たとえば、プロジェクトがうまくいかなかったときに、チームでどう立て直すかをサポートする仕組みを整えることが、チームの強さにつながります。
この研究は、レジリエンスという概念を一面的に理解するのではなく、個人、社会、文化、生物といった多層的な視点から統合的に捉える必要性を示しています。そのうえで、レジリエンスの育成は、パーソナリティやストレス対処力の強化だけでなく、よい組織のあり方や社会政策にまで視野を広げることで、より持続可能で包括的なウェルビーイング(心も体も社会的にも良い状態)を実現する手がかりとなるでしょう。
レジリエンスを免疫システムとして捉える発想
レジリエンスをより包括的な「精神の免疫システム」として再構築する試みをした研究があります[6]。精神疾患の発症リスクがある状況において、なぜ一部の人々が心理的健康を維持できるのかという問いを出発点に、この研究は、生物学的、心理学的、社会的な側面など、さまざまな観点からレジリエンスの仕組みを整理し、その全体像を理論的にまとめています。
この研究の結果、レジリエンスは単なる疾患の不在ではなく、リスクに直面した際に健康を保持・回復・促進する多層的なプロセスであることが明らかになりました。具体的には、個人レベルではストレス耐性を高める自己調整力や感情制御能力が鍵となり、社会的レベルでは支援的な対人関係や文化、価値観、伝統、宗教、地域のつながりなどが重要な役割を果たします。
さらに、私たちのストレスへの反応は、脳内の物質やホルモンの働き、さらには遺伝的な体質と育った環境との組み合わせによって大きく影響を受けることが分かってきています。特に注目されるのは行動免疫化(behavioral immunization)という概念で、過去の適度なストレス経験が、その後のストレスへの耐性を高めるというものです。
このように、レジリエンスを防御機構としてとらえることで、個々の対処力を評価するだけでなく、予防・介入の観点からも介入可能なポイントが明確になります。実践的には、たとえば従業員のメンタルヘルス支援において、ポジティブな経験やちょうどよいレベルの挑戦の機会を用意することで、将来的にストレスに耐える力を育てることができると考えられます。また、社会的支援の質や量を増やすことで、ストレスに対する初期反応の緩和や、長期的なレジリエンスの向上が期待できます。
マネジメントへの応用としては、この精神の免疫モデルをもとにした組織設計が挙げられます。例えば、失敗や困難を単なる問題として捉えるのではなく、それを乗り越える経験を通じてレジリエンスを形成する成長の機会として位置づける組織文化の醸成が有効です。
また、ストレス負荷の高い業務に従事する従業員には、定期的な対話の機会や感情の共有を通じて、感情調整や意味づけを支援するような制度設計も効果的です。さらに、異なるストレス反応性を持つ人材に対し、柔軟な働き方や支援体制を用意することは、個別最適化されたレジリエンス支援につながるでしょう。
この研究は、レジリエンスを単なる性格的な強さではなく、多層的に発達・変化する機能として捉える必要性を強調しています。この視点を取り入れることで、従業員一人ひとりの心理的健康を支えるだけでなく、変化の激しいビジネス環境においても柔軟に適応できる組織づくりが可能になると考えられます。
多層的視点から捉えるレジリエンスの仕組み
ストレスへの強さや心の回復力がどのように成り立っているのかを探るために、遺伝的な体質、脳の働き、育ち方や性格、さらには周囲の人間関係や社会環境までを幅広くまとめて分析した研究をご紹介します[7]。対象となったのは、臨床研究から動物実験までを含む最新の研究成果であり、特にPTSD(心的外傷後ストレス障害)やうつ病の予防に資するレジリエンスの理解を深める構成となっています。
この研究から明らかになったのは、レジリエンスが単一の特性ではなく、心や体、思考などの複数のシステムが連動して働く柔軟で適応的な反応の集合体であるということです。まず遺伝的要因として、ストレス応答に関連する神経伝達物質(セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリン)に関与する遺伝子の多型が、脆弱性や耐性に関与していることが示されています。
また、エピジェネティクス(DNA配列の変化を伴わない遺伝子発現の調節)により、幼少期の環境要因が成人後のストレス応答に長期的影響を及ぼす可能性も指摘されています。たとえば、幼少期に虐待や育児放棄などの強いストレスを受けた子どもは、脳内のストレス応答に関わる遺伝子にエピジェネティックな変化が起こることがあります。加えて、発達期の経験や育児環境がHPA軸(ストレスホルモン調整システム)や脳の可塑性に及ぼす影響は、後年の精神的回復力の基盤になるとされます。
こうした科学的知見には、実践的な含意が多く含まれています。レジリエンスを高めるためには、内面の強さに注目するだけでなく、ストレスに耐えられる環境づくりや、過去の経験から学ぶ力を養う支援が効果的であると考えられます。たとえば、ストレス接種訓練という手法では、あえて軽度の困難を経験させ、それに成功裏に対処することで、後の困難に対する耐性を育む効果があるとされています。これは、心理的なワクチンのような役割を果たすとされ、実際に警察官や医療従事者など、高ストレス環境下の職業においても応用が進められています。
マネジメントの観点からも、レジリエンスを理解することは有用です。たとえば、業務負荷が高まる時期には、心理的安全性の高いコミュニケーションを意識的に設計することが効果的です。また、従業員が困難な経験を意味あるものと再解釈できるように支援する仕組み、たとえばフィードバック面談やリフレクションの場の設計も、認知的再評価力(物事の受けとめ方を前向きに切り替える力)を高める助けになります。
この研究は、レジリエンスを個人の資質に還元するのではなく、生物学・心理・社会といった複層的な仕組みとして捉える視点を提供しています。こうした包括的な理解は、従業員一人ひとりのパフォーマンスを支えるだけでなく、変化の激しいビジネス環境にも柔軟に対応できる、いわゆる組織レジリエンスの形成にもつながると考えられます。
文脈を無視したレジリエンスがもたらすリスク
レジリエンスをめぐる主流の心理学的理解に対して、心理学・精神医学におけるレジリエンス概念を対象とし、その理論的前提と社会的文脈に焦点を当てた批判的分析をした研究を紹介します[8]。特に、個人の資質としてのレジリエンスが強調されすぎることで、社会構造や文化的背景といった文脈が無視されがちである点を問題視しています。
この研究ではレジリエンスの定義と、それに寄与すると考えられる要因の範囲をレビューし、臨床ケアと公衆衛生へのいくつかの含意を検討しました。研究手法としては、言説分析(人々の言葉の使い方や表現を通じて、社会にどのような考え方や価値観が広まっているのかを読み解く分析手法)を取り入れました。
この調査の結果、従来の心理学が「レジリエンスは個人の内在的資質に依存する」と捉え、自己効力感や楽観性といった個人の特性が重視されてきたことが明らかになりました。
しかし、この研究ではそのような考え方が、かえって支援を必要とする人々に努力不足という印象を与え、社会的な格差や支援の不足といった背景要因を見落としてしまうリスクがあると指摘しています。例えば、経済的・社会的な支援が得にくい人たちは、本来レジリエンスを発揮するための土台が整っていないにもかかわらず、レジリエンスが低いと判断されてしまうことがあるのです。
こうした視点から得られる実践的含意は、レジリエンスの育成において個人の内面強化だけに注目するのではなく、その人が置かれている社会的・経済的文脈を十分に考慮する必要があるということです。例えば、困難な状況にある従業員へのメンタルヘルス支援を行う際には、もっと前向きになろうといった励まし以上に、職場の労働環境や人間関係、報酬制度などの構造的要因を見直すことが効果的です。
マネジメントの観点からは、レジリエンスを個人の問題として矮小化せず、組織全体で回復力のある環境づくりを行うことが重要です。例えば、社員が失敗や困難を経験しても再挑戦できるような心理的安全性を保証すること、また、ジェンダーや経済的背景による不公平を是正するための制度的な工夫を講じることは、組織としてのレジリエンス向上にもつながります。さらに、チームや部署単位での集団レジリエンスを育む視点を持つことで、単なる個人対応を超えた、持続可能な人材マネジメントを実現できる可能性があります。
この研究が示すように、レジリエンスとは決して普遍的な心理的資本ではなく、社会的文脈と密接に結びついた概念です。そのため、ビジネスの現場においても、表面的なメンタルタフネスではなく、人と人との関係性や職場環境のあり方を見直すことこそが、本質的な回復力を高める鍵になると言えるでしょう。
レジリエンスは個人の資質から組織の土壌へ
本コラムでは、近年注目を集めるレジリエンスという概念を、多様な研究知見に基づき多角的に掘り下げてきました。従来、レジリエンスは個人の内在的な特性、すなわち生まれつきの強さとして理解されがちでしたが、現在ではそれが環境との相互作用によって形成される動的なプロセスであることが明らかになっています。具体的には、信頼できる対人関係、自己効力感、柔軟な対処行動といった保護因子が、個人のレジリエンスを支える基盤となりうることが複数の研究で示されました。
また、レジリエンスを精神の免疫システムとして捉える視点では、脳の可塑性や神経伝達物質、エピジェネティクスなどの生物学的要因も含めて、その仕組みが多層的であることが示されました。さらに、希望、楽観性、レジリエンスといった状態的な心理的資本が、職場におけるパフォーマンスや満足度を支えているという実証的な知見も得られています。
一方で、レジリエンスを強調しすぎることで、課題の責任をすべて個人に押し付けしまい、職場の制度設計や社会的な支援体制といった構造的な課題を見落とす可能性があるという批判的な視点も重要です。
これらの知見を踏まえると、ビジネスの現場においてレジリエンスを支援するためには、個人の特性を強化するだけにとどまらず、職場環境の設計や組織文化の見直しが求められます。レジリエンスは固定的な能力ではなく、経験を通じて育まれるプロセスであることを理解し、支援的な人間関係、失敗を許容する文化、柔軟な働き方といった土壌を整えることが、持続可能な組織の基盤となるでしょう。レジリエンスをめぐる理論と実践の接点を意識することが、これからのマネジメントにおいてますます重要になっていくと考えられます。
脚注
[1] Youssef, C. M., & Luthans, F. (2007). Positive organizational behavior in the workplace: The impact of hope, optimism, and resilience. Journal of management, 33(5), 774-800.
[2] Finch, J., Waters, A. M., & Farrell, L. J. (2023). Developing the HERO within: Evaluation of a brief intervention for increasing Psychological Capital (PsyCap) in Australian female students during the final year of school in the first year of COVID-19. Journal of affective disorders, 324, 616-623.
[3] Rutter, M. (1985). Resilience in the face of adversity: Protective factors and resistance to psychiatric disorder. The British journal of psychiatry, 147(6), 598-611.
[4] Luthar, S. S., Lyman, E. L., & Crossman, E. J. (2014). Resilience and positive psychology. In Handbook of developmental psychopathology (pp. 125-140). Boston, MA: Springer US.
[5] Schwarz, S. (2018). Resilience in psychology: A critical analysis of the concept. Theory & psychology, 28(4), 528-541.
[6] Davydov, D. M., Stewart, R., Ritchie, K., & Chaudieu, I. (2010). Resilience and mental health. Clinical psychology review, 30(5), 479-495.
[7] Wu, G., Feder, A., Cohen, H., Kim, J. J., Calderon, S., Charney, D. S., & Mathé, A. A. (2013). Understanding resilience. Frontiers in behavioral neuroscience, 7, 10.
[8] Herrman, H., Stewart, D. E., Diaz-Granados, N., Berger, E. L., Jackson, B., & Yuen, T. (2011). What is resilience?. The Canadian Journal of Psychiatry, 56(5), 258-265.
執筆者
 樋口 知比呂 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー
樋口 知比呂 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー
早稲田大学政治経済学部卒業、カリフォルニア州立大学MBA修了、UCLA HR Certificate取得、立命館大学大学院博士課程修了。博士(人間科学)。国家資格キャリアコンサルタント。ビジネスの第一線で30年間、組織と人に関する実務経験、専門知識で、経営理論を実践してきた人事のプロフェッショナル。通信会社で人事担当者としての経験を積み、その後、コンサルティングファームで人事コンサルタントやシニアマネージャーを務め、さらに銀行で人事部長などの役職を歴任した後、現在はFWD生命にて執行役員兼CHROを務める。ビジネスと学術研究をつなぐ架け橋となることを目指し、実践で役立つアプローチを探求している。