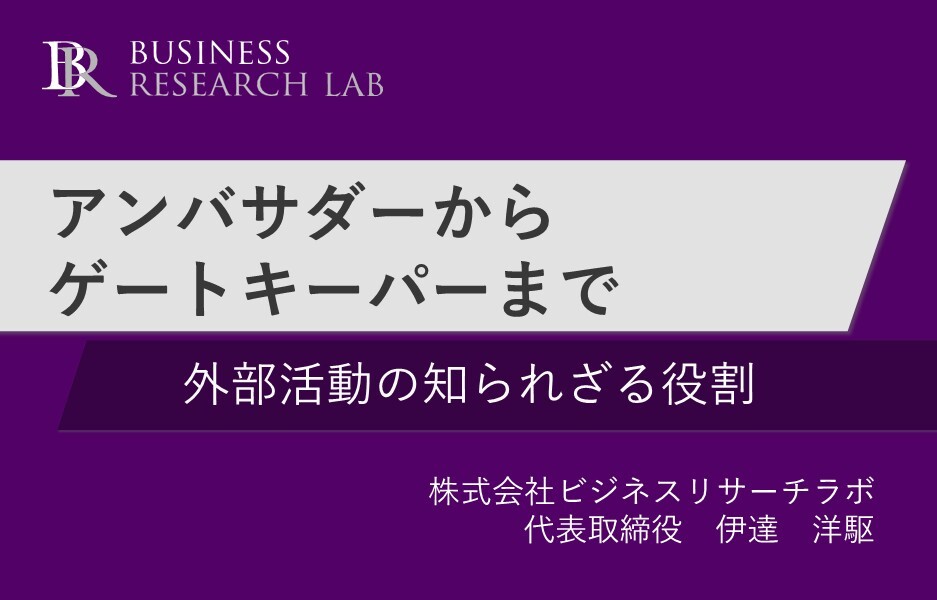2025年12月11日
アンバサダーからゲートキーパーまで:外部活動の知られざる役割
多くの組織において、チーム内の協力をいかに高めるかという点に関心が寄せられています。メンバー同士の円滑な意思疎通、明確な目標の共有、互いの信頼関係。これらがチームの成果を生み出す原動力であることは、誰もが認めるところでしょう。しかし、私たちの目は、ややもするとチームの「内側」にばかり向きすぎてしまいます。チームの運命を左右するもう一つの要因、それはチームが自らの境界を越えて、「外側」の世界とどのように関わっているかにあります。
チームは組織という大きな生態系の中に浮かぶ島ではありません。上位の経営層、隣接する他の部門、あるいは市場や技術の動向といった外部環境と、絶えず情報を交換し、交渉し、協調しながら活動しています。この外向きの活動が、チームの短期的な目標達成から長期的な革新性の創出に至るまで、様々な側面に関わっています。
チームの成果を高めるためには、外部との接触を増やしさえすればよいのでしょうか。それとも、そこにはもっと繊細で複雑な構造が隠されているのでしょうか。本コラムでは、チームの外部活動がその成果にどう結びつくのかという問いを多角的に掘り下げていきます。活動の種類や組み合わせ、境界を越える個人の働き、時間の経過がもたらす変化といった側面から、チームと外部世界との関係性を解き明かしていきます。
外部活動の質と組合せがチーム成果を左右する
チームの成功を考えるとき、外部との関わり方が一つの鍵となりますが、その関わり方にはどのような種類があり、それらがどう成果に結びつくのでしょうか。この問いに光を当てるため、ある調査がハイテク企業で新製品開発に携わるチームを対象に行われました[1]。新製品開発という環境は、チームが組織内の他部署や経営層、市場の動向といった外部と連携しなければならないため、この問いを探るには恰好の舞台です。
調査は、複数の手法を組み合わせて行われました。38チームのマネジャーにインタビューを行い、チームの活動の実態を把握しました。そのうちの2チームについては、日々の活動記録を追跡して、時間の使い方を分析しました。そして、45チーム、合計409人のメンバーを対象とした質問票調査を実施し、外部とのコミュニケーションに関するデータを集めました。
この質問票のデータを分析したところ、チームの外部活動は四つの異なるタイプに分類できることがわかりました。
一つ目は「アンバサダー活動」です。これは、上位の経営層に働きかけ、プロジェクトへの支援や資源を確保したり、進捗を報告してチームの正当性をアピールしたりする、上方向への活動を指します。二つ目は「タスク・コーディネーター活動」で、他の部門と設計について協議したり、業務の調整や交渉を行ったりする、実務的な水平方向の連携です。三つ目は「スカウト活動」で、新しい技術や市場の動向、競合の情報を広く収集する探索的な活動です。最後は「ガード活動」と呼ばれ、チームの機密情報を守るなど、情報の流れを統制する活動でした。
チームがこれらの活動をどのように組み合わせて行っているのかが分析されました。その結果、特徴的な四つの戦略パターンが見出されました。一つは、アンバサダー活動に特化する「アンバサダー型」。二つ目は、スカウト活動を中心に、一部タスク調整も行う「テクニカル・スカウティング型」。三つ目は、すべての外部活動が低調な「アイソレーショニスト(孤立)型」。四つ目は、アンバサダー活動とタスク調整の両方を高い水準で実行する「コンプリヘンシブ(包括)型」です。
これらの戦略とチームの成果との関係を調べました。成果は、プロジェクト開始から約10ヶ月後の短期的な時点と、約2年後の長期的な時点で、それぞれ上位の管理職によって評価されました。短期的な成果、すなわち予算やスケジュールの遵守という点では、「アンバサダー型」と「コンプリヘンシブ型」のチームが高い評価を得ていました。経営層からの支持を取り付けることが、目先の目標達成に直結することを示唆しています。
しかし、長期的な成果、すなわち製品の革新性や品質という点に目を向けると、様相は一変します。「コンプリヘンシブ型」のチームだけが、一貫して高い成果を出し続けていたのです。長期的な成功のためには、上層部への働きかけと、他部門との実務的な連携という、垂直・水平両面での活動を高いレベルで両立させることが必要であると解釈できます。
一方で、スカウト活動については、異なる側面が見られました。設計段階が進んでからもこの活動を続けることは、短期的な予算・スケジュール遵守や、長期的な革新性の両方に対して、マイナスの関連性を持っていました。チームメンバーによる自己評価とも負の関係にあり、内部の結束や計画遂行のプロセスを阻害する可能性が確認されました。
このことからわかるのは、外部とのコミュニケーションは、その量だけを増やせばよいというものではない、ということです。実際、コミュニケーションの総量そのものは、成果と明確な関係を持ちませんでした。「誰と、何の目的で、どの時期に」関わるかという、活動の質と組み合わせが、チームの成果を左右します。特に、上層部からの支援確保と、現場レベルでの部門間調整を両立させるコンプリヘンシブ戦略が、長期的な革新を生み出すための鍵であると言えます。
ゲートキーパーの効果はタスク特性で逆転する
チームの外部活動には様々な種類があり、その組み合わせが成果を左右することを見てきました。このことは、次に「誰がその活動を担うのか」という問いを導きます。チームと外部世界との境界をつなぐ上で、特別な働きをする個人は存在するのでしょうか。この点を探る調査が、ある大企業の総合研究所に所属する61のプロジェクトを対象として行われました[2]。
この調査の中心にあるのが、「ゲートキーパー」と呼ばれる存在です。ゲートキーパーとは、所属するチーム内で多くのメンバーから頼られ、かつ、大学や学会といった組織外の専門家とも情報交換を行う個人のことです。組織の内部と外部、両方の情報ネットワークの中心に位置する人物と定義されます。
組織というものは、部門ごとに専門化が進むと、それぞれ独自の言語や思考の枠組みを発達させるものです。これは内部での効率的な意思疎通を助ける一方で、異なる言語を持つ外部との間にコミュニケーションの壁、いわば「意味のノイズ」を生じさせます。ゲートキーパーは、この壁を乗り越える翻訳者のような働きをすると考えられました。外部の新しい知識を組織内の文脈に合うように翻訳し、チーム内に広めるという流れです。
しかし、調査者たちは、このゲートキーパーの有効性が、プロジェクトが扱うタスクの性質によって変わるのではないかという仮説を立てました。タスクは二つに大別されました。一つは「ユニバーサルなタスク」です。これは基礎研究のように、そこで扱われる知識や評価の基準が、世界中の専門家コミュニティで共有されているような仕事を指します。もう一つは「ローカルなタスク」で、特定の製品開発のように、その組織固有の事情やプロセスに深く関わる仕事を指します。
ユニバーサルなタスクでは、内外で共通の言語が使われているため、チームの各メンバーが外部の専門家と直接やりとりする方が効率的かもしれません。逆に、ローカルなタスクでは、内外の言語差が大きいため、ゲートキーパーによる翻訳が不可欠になるはずです。
調査では、15週間にわたって、誰と誰が業務上の会話を交わしたかが記録されました。このデータからゲートキーパーが特定され、各プロジェクトのタスクの性質(研究、開発、テクニカルサービス)や、上位管理者による業績評価と突き合わせられました。
分析の結果は、仮説を裏付けるものでした。基礎研究のようなユニバーサルなタスクを担うプロジェクトでは、ゲートキーパーの存在は、業績とマイナスの相関関係にありました。媒介者を置くことが、かえって情報の流れを阻害していた可能性が考えられます。対照的に、製品開発のようなローカルなタスクを担うプロジェクトでは、ゲートキーパーの存在は、業績と強いプラスの相関関係にあったのです。組織固有の課題解決には、外部知識を翻訳するゲートキーパーの働きが有効であったことがうかがえます。
この調査はもう一つの発見をもたらしました。ローカルなタスクにおいて、ゲートキーパーがいないプロジェクトでは、チームが外部とコミュニケーションを取れば取るほど、業績が下がるという関係が見られました。外部との会話が、混乱や遅延を招いていただけのようです。ところが、ゲートキーパーがいるプロジェクトでは、ゲートキーパー本人だけでなく、他のチームメンバーの外部コミュニケーションもまた、業績とプラスの関係にありました。
この事実は、ゲートキーパーが情報を運ぶだけでなく、周囲のメンバーが外部と上手にやりとりできるよう手助けする、コーチのような働きもしていることを示唆しています。誰に、何を、どのように聞けばよいかを導くことで、チーム全体の外部対応能力を引き上げていたのかもしれません。ちなみに、公式な監督者という立場だけでは、この翻訳機能は果たせませんでした。監督者であっても、ゲートキーパーとしての特性を持たない限り、その外部コミュニケーションは業績とマイナスの関係にあったのです。
在籍が長期化すると外部接触が減り業績が低下する
外部との関わり方には、活動の種類やそれを担う個人の特性が関わっていることを見てきました。ここでは、さらに「時間」という軸を加えて考えてみたいと思います。チームが結成されてから時が経つにつれて、外部との関係はどのように変化していくのでしょうか。
この問いを探るため、先ほどと同じ研究所を舞台に、今度は50のプロジェクトチームを対象とした分析が行われました[3]。調査の焦点は、長年同じメンバーで活動を続けるチームが、外部の新しいアイデアに対して閉鎖的になる、いわゆる「Not Invented Here(ここで発明されたものではない)」症候群と呼ばれる現象が、実際にデータで確認できるかという点にありました。
調査では、各メンバーが現在のプロジェクトに在籍している期間(プロジェクト在籍年数)と、チームの業績評価の関係が調べられました。コミュニケーションのパターンも、前回と同様の手法で追跡されています。
分析から浮かび上がったのは、在籍年数と業績の間に存在する曲線関係でした。チームの業績は、メンバーの平均在籍年数が2年から4年のあたりで最も高くなり、それを過ぎると一貫して低下していくのです。特に、結成から5年以上が経過したチームの業績は、平均して有意に低い水準にありました。この低下は、メンバー個人の年齢や、会社への在籍年数といった要因を考慮に入れても、なお残りました。問題は個人の老化ではなく、同じ集団が長く固定化されること自体にあるようです。
この業績低下の裏では何が起きているのでしょうか。コミュニケーションのデータが、そのメカニズムを解き明かす手がかりを与えてくれます。チームの平均在籍年数が2.5年を超えたあたりから、二つの特定のコミュニケーションが著しく減少していくことが判明したのです。
一つは、大学や学会といった「外部の専門家コミュニティ」との接触です。そしてもう一つは、意外なことに、「チームの内部」でのメンバー同士のコミュニケーションでした。新しい知識の源泉である外部との接点と、チーム内で問題を練り上げるための内部での対話、その両方が細っていきます。
この結果は、「Not Invented Here」症候群がどのように生まれるかを描き出しているように見えます。長く続いたチームは、次第に外部から新しい情報を探すことをやめてしまい、内向きになっていきます。そして、確立されたやり方や役割分担に安住し、メンバー同士でさえ、問題解決のための深い対話を交わさなくなっていくのかもしれません。こうして、チームはかつての成功体験に固執し、変化する環境への適応力を失っていくのでしょう。
この調査は、チーム内の在籍年数のばらつきにも目を向けています。その結果、業績が最も高かったのは、全員がベテラン、あるいは全員が新人といった均質なチームではなく、在籍年数に程よいばらつきがあるチームでした。これは、知識の継承を担うベテランと、新しい視点をもたらす新人が混在する状態が、チームの活力を維持する上で望ましいことを物語っています。定期的なメンバーの入れ替わりが、チームの孤立化を防ぎ、外部への窓を開き続ける上で、何らかの働きを持つのかもしれません。
弱い紐帯は探索に有効だが複雑な知識移転には不利
これまで、外部との関わりについて、活動の戦略、それを担う個人、時間の経過という観点から見てきました。ここでは、外部との「つながりの性質」に焦点を当ててみたいと思います。すべてのつながりは、等しく価値があるのでしょうか。
この問いに答えるため、ある大手エレクトロニクス企業内で行われた、120件の新製品開発プロジェクトを対象とする調査が行われました[4]。この調査が特に注目したのは、同じ企業内の異なる部門間で知識が共有される際のプロセスです。
調査の理論的な土台となったのは、「弱い紐帯の強さ」という考え方です。社会的なつながりには、頻繁に会い、親密な関係にある「強い紐帯」(例えば、同じチームの同僚)と、たまにしか会わず、関係性も希薄な「弱い紐帯」(例えば、他部門の知人)があります。一般に、新しい情報やアイデアは、自分とは異なる社会集団に属している人がもたらすことが多いため、弱い紐帯を通じて得られることが多いとされています。
しかし、この調査を行った研究者は、知識を共有するプロセスを「探索」と「移転」の二つに分けて考える必要があると主張しました。探索とは、組織内に散らばる有益な知識が「どこにあるかを見つけ出す」段階です。一方、移転とは、その見つけ出した知識を「自分たちのプロジェクトで使えるようにする」段階です。
さらに、知識の「複雑性」というもう一つの次元が導入されました。知識には、マニュアルなどで簡単に文書化できるものもあれば、文書化が難しく、実践を通じてしか伝えられない暗黙的なものもあります。また、他の技術やシステムに依存していて、単独では機能しない複雑な知識もあります。
これらの概念を組み合わせ、次のような仮説が立てられました。知識の「探索」段階では、広く多様な情報源にアクセスできる弱い紐帯が有利である。しかし、複雑な知識を「移転」する段階では、深い相互理解や密なやりとりが必要になるため、信頼関係に基づいた強い紐帯の方が有利になるだろうというものです。
調査では、部門間のつながりの弱さ(交流頻度の低さや、業務上の距離感で測定)が、プロジェクトの完成までにかかる時間にどう関わるかが分析されました。
分析の結果は、この仮説を支持するものでした。他部門からの知識移転を伴うプロジェクトにおいて、弱い紐帯を持つことは、一般的にプロジェクトの完成を早めることにつながりました。これは、広いネットワークを通じて、必要な知識を素早く見つけ出せる「探索の利益」を反映しています。
ところが、移転される知識が複雑な(文書化が困難、あるいは他システムへの依存度が高い)場合に限っては、この関係が逆転しました。複雑な知識を弱い紐帯を通じて移転しようとすると、プロジェクトの完成はむしろ遅れてしまったのです。希薄な関係性の中では、複雑な知識のニュアンスを伝えきれず、その移転に時間と労力を要したため、探索で得た時間の利益を帳消しにしてしまったのでしょう。
ちなみに、他部門からの知識移転を伴わないプロジェクトでは、部門間の紐帯の弱さは、プロジェクトの完成時間に系統的な影響を与えませんでした。このことは、弱い紐帯の利点が、組織の壁を越えて知識を探し、獲得するという文脈において発揮されることを裏付けています。
この結果は、組織における知識共有の問題を浮き彫りにします。新しいアイデアを見つけるのに最適なネットワーク(広範な弱い紐帯)と、そのアイデアが複雑な場合にそれを実行に移すのに最適なネットワーク(密な強い紐帯)は、同じではないのです。探索に適したつながりと、移転に適したつながりを、同じように扱おうとすると、思わぬ非効率を招く可能性があることを、この調査は教えてくれます。
脚注
[1] Ancona, D. G., and Caldwell, D. F. (1992). Bridging the boundary: External activity and performance in organizational teams. Administrative Science Quarterly, 37(4), 634-665.
[2] Tushman, M. L., and Katz, R. (1980). External communication and project performance: An investigation into the role of gatekeepers. Management Science, 26(11), 1071-1085.
[3] Katz, R., and Allen, T. J. (1980). An empirical test of the Not Invented Here (NIH) syndrome: A look at the performance, tenure, and communication patterns of 50 R&D project groups (Working Paper No. WP1114-80). Cambridge, MA: MIT Sloan School of Management.
[4] Hansen, M. T. (1999). The search-transfer problem: The role of weak ties in sharing knowledge across organization subunits. Administrative Science Quarterly, 44(1), 82-111.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。