2025年12月10日
自己の語りから社会へ:オートエスノグラフィーの力
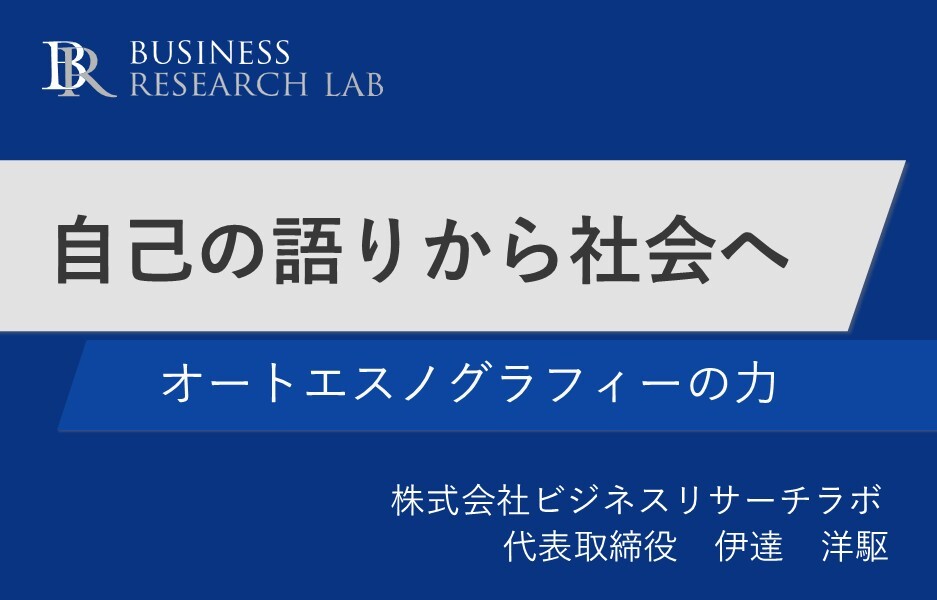 誰かの深い悲しみや喜びに触れたとき、統計データや分析報告だけでは伝わらない「何か」を感じた経験はないでしょうか。人の心を動かし、時にその人の行動まで変えるのは、個人の切実な「語り」であることが少なくありません。社会や文化を理解しようとするとき、私たちはつい大きな主語で物事を捉えてしまいがちです。しかし、その大きな社会は、一人ひとりの個人的な経験の集合体でもあります。
誰かの深い悲しみや喜びに触れたとき、統計データや分析報告だけでは伝わらない「何か」を感じた経験はないでしょうか。人の心を動かし、時にその人の行動まで変えるのは、個人の切実な「語り」であることが少なくありません。社会や文化を理解しようとするとき、私たちはつい大きな主語で物事を捉えてしまいがちです。しかし、その大きな社会は、一人ひとりの個人的な経験の集合体でもあります。
自分自身の経験を深く見つめ、それを社会や文化との関わりの中で描き出すことで、他者への深い理解や共感、そして倫理的な想像力を育むことができるとしたら、どう思いますか。
本コラムで紹介する「オートエスノグラフィー」は、そのような探究の方法論です。研究者自身が生活の中で経験した出来事、感じた想い、抱えた葛藤を「物語」として描き出し、読者をその経験の内側へと誘います。それは、個人的な語りを通して、私たちと他者、社会とのつながりを、新しい光のもとで照らし出す試みです。
オートエスノグラフィーは物語で共感と倫理を拓く
ある研究者たちが、テレビでハリケーン・カトリーナの報道を見ていました。画面には、故郷を失い、愛する人を亡くした人々の悲痛な姿が映し出されています。その言葉に、記者の流す涙に、研究者たちは心を揺さぶられます。ここには、どんなに洗練された分析レポートも敵わない、圧倒的な「現実感」がありました。この経験から、一つの問いが生まれます。社会科学は、このような生々しい苦難や経験に、どう向き合うことができるのだろうか、と。
オートエスノグラフィーという方法論を支持する論者たちは、この問いに対して「物語の力」を押し出します[1]。一般化や理論化を急ぐのではなく、個人の経験に深く寄り添い、その語りを通して読者の心に直接働きかけること。それが、自分たちの目指す道だと位置づけました。
この立場は、オートエスノグラフィーをより分析的に捉えようとする考え方とは、目指すものが異なります。分析的なアプローチは、個人的な経験を、より広い社会現象を説明するための理論的な理解へとつなげることを目指します。しかし、物語を重視する立場からは、そうした方向性は、オートエスノグラフィーが持つ、他者との親密さや、書き手の弱さの開示といった性質を薄めてしまうのではないか、という懸念が示されます。
もちろん、物語を語ることが、理論化や分析そのものを否定するわけではありません。むしろ、優れた物語は、それ自体が独自の分析の形式を持っていると考えられています。物語は、物事を固定的な定義に押し込めることなく、その意味の豊かさを明らかにすることができます。登場人物、感情の動き、出来事の展開、そこから浮かび上がる教訓を通じて、読者を経験の世界へといざないます。開かれた解釈の余地を残しながら、読者一人ひとりが倫理的な問いと向き合うきっかけを作ります。
この点で、分析的な報告がしばしば一方的な「独白」になりやすいのに対し、物語は読者との「対話」を生み出す性質を持っています。書き手自身の迷いや感情、人間関係の揺らぎを隠さずに示すことで、読者はその経験を追体験し、共に考える仲間となります。書き手の弱さの開示は、読者の弱さと響き合い、そこに共感的なつながりが生まれるのです。
この立場において、文章を書くという行為は、研究成果を報告するための手段にとどまりません。書くこと自体が、世界を探求し、他者と関わるための方法となります。読者が経験の世界に伴走できるような語りのスタイルを追求することが、研究の質を高める道だと考えられているのです。最終的に、このアプローチは、異なる立場や考え方を論破するのではなく、共感を通じて共に生きる道を探る対話的な空間を、学問の世界に開こうとする試みと言えます。
物語は、他者への配慮を呼び覚まし、ばらばらになった共同性を再び編み直すための作法となり得ます。オートエスノグラフィーの社会的な意義は、この点にあるのかもしれません。個人の声に耳を傾け、その物語を深く味わうことから、他者への想像力は育まれていきます。
オートエスノグラフィーは自己語りを倫理的な共同実践へ拓く
ある著名な音楽家が、自身の私的な体験をもとにした作品を発表したとします。その歌は多くの人々の心を打ち、社会的な議論を巻き起こすかもしれません。このとき、彼の語りはもはや個人のものではなく、公共の空間で意味を持つようになります。語られた内容は、彼自身の人生だけでなく、その物語に登場する周囲の人々の人生にも光を当て、社会に何らかの変化をもたらす可能性があります。
この例が示すように、自己の経験を語るという行為は、それが公になった瞬間に、他者への責任を伴うようになります。オートエスノグラフィーもまた、この関係から逃れることはできません。どれほど内省的な語りに見えても、それは常に他者や世界との関わりを含んでおり、本質的に倫理的な問いと向き合わざるを得ないのです[2]。
「オートエスノグラフィー」という言葉の語源を分解してみると、この方法論の二重性が見えてきます。「オート」は「自己」を、「エスノ」は「人々」を、そして「グラフィー」は「記述」を意味します。つまり、この方法は本来、「自らが一員である人々について、その共同体の生活を自己の視点から書くこと」を指します。自己と人々、この二つの要素は切り離すことができません。
しかし、実践においては、このバランスが崩れ、「エスノ」の部分が忘れられ、「オート」、自己の語りに偏ってしまうことがあります。自己の感情の揺れや葛藤の吐露に終始してしまい、他者への配慮や、自身が生きる共同の世界への眼差しが失われてしまうのです。ある論者は、こうした実践は自己愛的な慰めに陥る危険があり、他者を考慮しないという点で、倫理に反する象徴的な暴力にさえなりうると警鐘を鳴らします。私たちの自己は、他者との関係性の中で初めて成立するものであり、自己だけを切り離して語ることは、本来不可能です。
倫理とは何でしょうか。それは、抽象的なルールや規範のリストではありません。具体的な人間関係の中で生まれる実践的な知恵と考えることができます。哲学の文脈では、私たちがこの世界に関与する以前から、他者に対する無限の責任を負っている、という考え方が示されてきました。研究倫理審査のような手続きとは別に、自身の経験を公に語った瞬間、その表現行為自体が世界を少しだけ変えてしまうため、書き手には倫理的な責務が生じます。
言語を用いて何かを書くという行為は、それ自体が他者とのコミュニケーションです。私たちが使う言葉は他者から受け取ったものであり、書かれたものは他者に届けられ、読み手の行動を変えるかもしれません。自己中心的に見える記述でさえ、他者との関係を免れることはできず、倫理的な問いを内包しています。
この課題に応えるため、複数の人々が対等な立場で対話し、共同で一つの理解を編み上げていくような実践が提案されています。例えば、学校の関係者(校長、教員、生徒)と研究者が集まり、それぞれの立場から語り合い、誰か一人の声を特権化することなく報告書をまとめるといった方法です。そこでは、報告の書き方まで、多声的に構成することが試みられます。このように、オートエスノグラフィーは、自己の語りを社会に開かれた共同の実践へと高めていく道を模索しています。
オートエスノグラフィーは心を込めた語りで共感と倫理を拓く
ある大学の研究室を、一人の大学院生シルヴィアが訪れます。彼女は乳がんのサバイバーであり、自身の博士論文として乳がんに関する調査を計画していました。しかし彼女は、自らの辛い罹患経験は、客観的であるべき研究からは切り離さなければならないと固く信じていました。研究者であるエリスは、その考え方に問いを投げかけます。当事者としての経験を抑圧するのではなく、それを研究の出発点とし、深い洞察へとつなぐことはできないだろうか、と[3]。
この対話から、「ハートフル・オートエスノグラフィー」という考え方が浮かび上がってきます。これは、研究に「心」を取り戻そうとする試みです。研究者の弱さ、感情、身体的な感覚といった要素を隠すのではなく、それらをすべて含み込んだ物語として民族誌を書き上げ、読者の共感と倫理的な想像力を呼び起こすことを目指します。
その中心にあるのは、「ズームイン・ズームアウト」という往復運動です。レンズを広角にして社会や文化という外側の世界を捉え、次にはレンズを狭めて書き手自身の内なる世界(弱さや感情)に焦点を合わせる。この二つの視点を行き来することで、自己と社会の境界が溶け合い、多層的な物語が生まれます。
このようなアプローチは、従来の社会科学が持っていた「データ」や「妥当性」といった概念の捉え直しを促します。例えば、データは調査時に記録された客観的な記録だけを指すのではありません。人生の転機となったような強い出来事の記憶は、後からでも感情と共に鮮やかに蘇ってくることがあります。ここで求められるのは、歴史的な事実を正確に再現することだけではなく、読者がまるでその場にいたかのように感じられるような、物語としての真実味です。
研究の妥当性も、客観的な正しさによって測られるのではありません。読者がその物語に「ありえることだ」と共鳴し、自身の人生や他者との関係を考える上で何らかの気づきを得られるかどうか。それが、この方法における妥当性の基準となります。一般化についても同様です。一つの物語から統計的な法則を導き出すのではなく、読者がその物語を自分の経験に重ね合わせ、新たな意味を見出すことができるかどうかが問われます。
この実践は、書き手に自身の弱さ(不安、恥、痛みなど)と向き合う勇気を求めます。弱さをさらけ出す語り手は、同じように弱さを抱える読者と響き合い、そこから相互のケアや変容が生まれる可能性があります。インタビューのような調査場面でも、共感や配慮は「バイアス」として排除されるべきものではなく、引き受けるべき倫理的な務めだと考えられます。
シルヴィアとの対話を通して示されるのは、研究計画の立て方から分析の仕方まで、すべてがこの「心ある」アプローチに基づいていることです。少数の人々と長期的に対話を重ね、書き起こした記録を本人に返して一緒に読み解き、時には参加者同士が互いの物語について語り合う場を設ける。そうしたプロセスを通じて、物語は参加者と研究者の共同作業として、共に構成されていきます。
この方法は、研究が私たちの生活から切り離された専門的な技術ではなく、他者や世界と関わることを通じて、共感や理解を生み出すための実践であることを、対話という物語形式をもって教えてくれます。
オートエスノグラフィーは身体表現で知と倫理を再構築する方法
これまでの議論では、主に「書くこと」や「語ること」を中心にオートエスノグラフィーを考えてきました。しかし、私たちの経験は、心や言葉の中だけで完結するものではありません。それは、身体を通して生きられるものです。この身体的な次元を、研究の中でどのように扱うことができるのでしょうか。この問いに答えるのが、「パフォーマンス・オートエスノグラフィー」という方法です。
これは、自己の物語と民族誌的な探究を、舞台上演のような身体表現と交差させる試みです。研究者の身体を、知を生み出し、解釈し、表現するための中心的な媒体として捉え直します。文字として書かれたテキストが持つある種の硬直性を乗り越え、「生身の身体 対 生身の身体」という形での対話を目指すのです。
この方法論を説明するある論文は、非常にユニークな構成を取っています[4]。作者自身の摂食障害の経験や、研究現場での葛藤を綴った詩的で身体的なテキストと、その方法論的な意味を冷静に分析するテキストが、交互に配置されています。これによって、読者は具体的な語りの力に引き込まれると同時に、その語りがどのようにして関係性や倫理、権力の問題を浮かび上がらせるのかを、客観的に理解することができます。
この実践の核となるのが、「対話的な上演」という考え方です。上演者は、自分や他者の語りに対して、一方的に解釈を下すのではなく、それによって自らが揺さぶられ、問い直され、変わっていくことを受け入れます。目的は、特定の文化的な文脈の中で「自己と他者がどのように交錯するのか」を、自らの身体を通して理解することにあります。このとき、自己と他者の境界は揺らぎ、上演者は「他者としての自己」を経験することになります。これは、異なる価値観を持つ人々が対話できる空間を作り出そうとする、倫理的な実践でもあります。
このアプローチは、身体感覚を排除し、理性や論理に偏りやすい学術の世界のあり方への挑戦でもあります。身体を通して生み出される知を、詩や非定型な語りといった形式で記述へと取り戻すことで、知は頭と身体、理性と感情の分断を乗り越えて、再び統合されることを目指します。
何が「良いパフォーマンス・オートエスノグラフィー」なのでしょうか。その評価基準も提示されています。文学的な完成度と社会科学的な論証の両方に耐えうる、説得力のある表現であること。感情に訴えかける力と、自己のあり方を社会との関係の中で批判的に省察する視点を両立させていること。そして、理論的な洞察と物語が、互いを高め合う形で織り合わされていることなどが挙げられます。
あるエピソードが、この方法の倫理的な自己点検のあり方を示します。研究者が調査地でビデオカメラを使う場面です。その研究者は、カメラが持つ「権力の視線」を自覚し、調査する者と調査される者の間に存在する非対称な関係や、研究資金といった利害の構造を、自ら批判的に吟味します。自身の特権性や欲望をさらけ出すことで、オートエスノグラフィーがいかに倫理的な緊張感の中で行われるべきかを示すのです。
このように、身体を通して語り、考えることを方法の中心に据えることで、オートエスノグラフィーは、学術の世界から見過ごされがちだった身体や声に、再びその場所を取り戻そうとします。そのとき私たちは、自らがどのように現実を構築しているのかを、いわば「目撃する私」として、見つめ直すことになるでしょう。
脚注
[1] Ellis, C. S., and Bochner, A. P. (2006). Analyzing analytic autoethnography: An autopsy. Journal of Contemporary Ethnography, 35(4), 429-449.
[2] Roth, W.-M. (2008). Auto/Ethnography and the question of ethics. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 10(1), 38.
[3] Ellis, C. (1999). Heartful autoethnography. Qualitative Health Research, 9(5), 669-683.
[4] Spry, T. (2001). Performing autoethnography: An embodied methodological praxis. Qualitative Inquiry, 7(6), 706-732.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。






