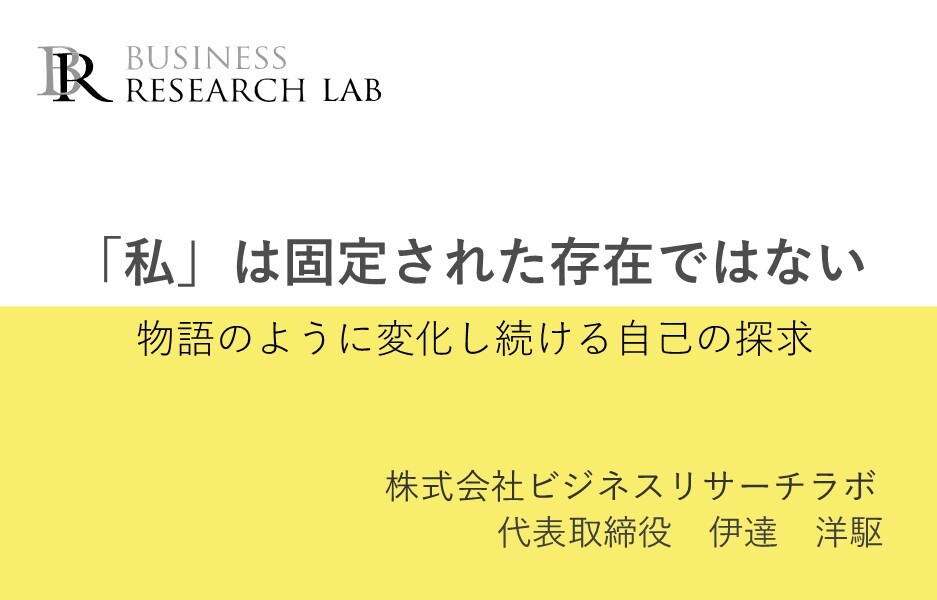2025年12月10日
「私」は固定された存在ではない:物語のように変化し続ける自己の探求
「自分とは、何者なのだろうか」。この問いに、私たちは人生の様々な場面で向き合います。自分の中に揺るぎない「本当の自分」を見つけ出そうとする人もいます。しかし、「自分」が固定的なものではなく、物語のように日々、他者や社会との関わりの中で絶えず編みなおされ、変化し続けるものだとしたら、皆さんはどう感じるでしょうか。
私たちの自己認識は、決して真空の中では生まれません。家族や友人との会話、職場の言葉、書物や映画からのメッセージ、社会の価値観。そうした無数の外部の声に耳を傾け、内面で対話し、時に受け入れ、時に抵抗しながら、私たちは「わたし」という物語を書き換えています。自己を形成し、維持し、変容させていく絶え間ない営みは、「アイデンティティ・ワーク」と呼ばれます。
本コラムでは、この動的で創造的なプロセスに光を当てます。様々な事例を通して、「わたし」が他者や社会との対話の中でいかに柔軟に、そして力強く再構築されていくのかを探求します。人生という物語を新たな視点から見つめ直す内容となればと思います。
自伝的語りは社会的物語を取り込み自己を形づくる
自分の人生を振り返る時、私たちは出来事を並べて意味を見出そうとします。この「自分史」は、完全にオリジナルな創作物なのでしょうか。それとも社会にあふれる物語から、筋書きや型を借りてきているのでしょうか。ある元管理職の男性が記した長大な自伝を丹念に読み解いた研究は、個人の内的な自己形成が、社会に流通する物語と結びついていることを明らかにしています[1]。
この研究は、大手通信機器メーカーの元上級管理職による自伝を精読し、書き手がいかに社会的に利用可能な物語の資源を使い、自身のアイデンティティを築いたかを追体験しようと試みました。自伝には象徴的なエピソードがあります。管理職キャリアの途中で入院した彼が、不安がる隣の患者を一晩かけて励ました時のことです。
夜が明けた頃、患者から「あなたは、マネジャーですか?」と尋ねられます。この問いかけは、内面の自己認識と、他者の目に映る自分の姿が一致した瞬間でした。自分の振る舞いが「マネジャー」という社会的役割像そのものだと、他者の言葉を通じて自覚したのです。この経験は、後年の執筆という内省的な作業の中で改めて意味づけられ、「私はマネジャーである」という自己認識を強固にしました。
この自伝は、「エンジニアにはなりたくなかった」という逆説的な言葉を主題に据えています。貧しい家庭に生まれ、挫折を経て偶然入社した会社で工場労働者から管理職へと昇進していく。当初の希望とは異なる道を進む現実との間に生じたねじれを、いかに肯定的な自己の物語として統合するかが、彼のアイデンティティ・ワークの核心でした。
物語の紡ぎ方も興味深いものです。少年期にいじめっ子に立ち向かった経験が、職場で理不尽な上司と対立する場面で反響します。彼は幼い頃の「不正に屈しない自己」を、成年後の「責任ある管理者」像に接続し、時間を通じた自己の一貫性を語ります。この物語形成は、彼個人の内面からだけ生まれるのではありません。冒険映画や文学、政治的な言説、詩の一節といった社会に流通する文化資源が、彼の経験を解釈する枠組みを提供しました。職場の対立は、「暴君と闘う正義の主人公」という、一般的で道徳的な物語の型にはめ込まれていったのです。
この事例から見えてくるのは、私たちの自己物語が決して閉じたものではないという事実です。それは社会という図書館から言葉や筋書きを借りて編まれるテクストのようです。内なる自己認識と、社会が提供する役割や物語が交差し、対話する動的なプロセスの中に、私たちのアイデンティティは形づくられていきます。
アイデンティティ・ワークは外部との対話で自己を組み替える
個人の物語が社会の大きな物語と響き合う様を見てきました。では、他者との直接的な対話の中で、自己認識はどのように揺さぶられ、形を変えるのでしょうか。ある文化組織を舞台にした長期調査は、アイデンティティが対話を通じて形成され、時には組み替えられていく過程を浮き彫りにしています[2]。
この研究は、国際フェスティバルを運営する組織のリーダー、ロニーという人物に焦点を当てました。調査で明らかになったのは、ロニーをめぐり、全く異なる二つの人物像が組織内で同時に語られていたことです。ロニー自身の自己認識は「アーティストの味方」。芸術を最優先し、予算や手続きは二の次で、仕事は個人的な信頼関係で進めるスタイルでした。彼は自分とチームを、芸術を守る「家族」だと語っていました。
一方、経営陣はロニーを「マネジャーではない人」と見なしていました。芸術と事業運営の両立を求める経営陣にとって、手続きを軽んじる彼のやり方はプロとは言えない逸脱した振る舞いでした。組織内では、ロニー本人が語る英雄的な自己像と、経営側が語る問題児としての他者像が、常に対立していました。
この状況を動かしたのが、ある年のフェスティバルでの事件です。開幕公演が契約不備を理由に直前キャンセルとなったのです。この失敗は、ロニーをめぐる二つの対立する物語の力関係を一変させました。経営陣はこの「否認しようのない事実」を根拠に、彼を翌年のプログラム編成から外すことを決定します。
この研究は、こうしたアイデンティティの変容が対話的なプロセスで起こることをモデル化しています。私たちは他者の言葉や出来事に対し、いくつかの方法で応答します。自分の考えと一致する言葉は受け入れ、自己像を強化します。ロニーがアーティストから「あなたは芸術の側の人だ」と言われるたびに、彼の自己認識は強固になりました。逆に、自分の考えと対立する言葉は拒絶します。経営陣の「予算が第一だ」という声に、ロニーは常に対抗することでアイデンティティを守っていました。
なぜ、ある物語が別の物語に取って代わられるのでしょうか。研究は、変化を左右する四つの力を指摘します。一つ目は好き嫌いや共感といった「情動的な力」。二つ目は何が正しいかという価値観に関わる「認知的な力」。三つ目は誰が説得力のある説明ができるかという「権力的な力学」。四つ目は英雄譚や悲劇といった人々の心に響きやすい「物語の様式」です。
公演キャンセルという事件は、これら四つの力を経営陣の側に一気になびかせ、ロニーの英雄譚を悲劇へと転換させる契機となりました。この事例は、アイデンティティが内面に静かに存在するのではなく、他者の声が響く対話の場で生成され、組み替えられていく現象であることを示しています。
アルムナイは過去経験を多様に再演し現在の自己を形づくる
過去の経験との対話は、現在の自己形成にどう関わるのでしょうか。組織を離れた後、過去は単なる思い出なのでしょうか。それとも現在の自分を支える資源となりうるのでしょうか。あるグローバル企業の同窓会(アルムナイ・ネットワーク)のメンバーを対象とした研究は、人々が過去の経験をただ懐かしむのではなく、多様な方法で「再演」し、現在の自己を積極的に形づくっている実態を明らかにしています[3]。
この研究は、強い企業文化で知られる大手消費財メーカーの元従業員たちで構成される同窓会に参加する21名にインタビューし、彼らが「アルムナイ」としての自己認識をいかに維持しているかを分析しました。その結果、過去と現在をつなぐ四つのアイデンティティ・ワークの方略が浮かび上がりました。
一つ目は「ノスタルジア」です。同窓会イベントに参加し、過去の「良き時代」の雰囲気や、生き生きと働いていた自分を再体験する行為です。これは思い出話ではなく、実際に集い交流するという実践的な再演を通じて、かつての創造的でエネルギッシュな自己像を現在の自分に再び取り込みます。
二つ目は「再生産」です。かつて所属した組織で身につけた仕事のやり方を、現在の職場で意図的に実践し、再現する行為です。根底には、過去に培った規範やスキルが現在も有効であり、成果につながるという強い確信があります。
三つ目は「正当化」です。現在の環境で得られる肯定的な評価を用いて、過去の経験の有効性を確認し、自己の物語を補強する営みです。他者からの承認によって、過去の自分のあり方が今も価値を持つことを確認し、自己の一貫性と肯定感を保ちます。
四つ目は「組合せ」です。過去の価値観を全面的に肯定も否定もせず、現在の組織文化と批判的に比較し、自分なりの折衷的なスタイルを築く、より成熟したアプローチです。過去の経験を選択的に継承し、現在の環境に適応させていくことで、職業人としての自己を更新し続けます。
この研究から見えてくるのは、過去の経験とは静的なものではなく、現在の自己を形づくるために活用される資源であるという事実です。アルムナイの人々は、これら四つの方略を使い分け、過去と現在の自分をつなぐ物語を紡ぎ続けています。過去との対話は、現在の自己を豊かにし、未来を切り拓く創造的な実践となり得ます。
高齢失業者は課されたラベルを交渉し働く自己を保ち続ける
職を失い、社会から「失業者」や「高齢者」といった否定的なラベルを貼られたとしたらどうでしょうか。逆境の中で、人はどのように「自分は働く人間である」という感覚を保ち続けるのでしょうか。英国スコットランドの高齢失業者を対象とした研究は、困難な状況の中で人々がいかに粘り強く、創造的に自己の物語を維持しようと奮闘しているかを描き出しています[4]。
この研究は、50歳以上で失業状態にある66名を対象に、グループでの話し合いを通じて彼ら彼女らの経験を聴き取りました。分析から、彼ら彼女らが「働くアイデンティティ」を維持するために行う、三つの実践が浮かび上がりました。
第一の実践は、「課されたアイデンティティ」との交渉です。参加者は、就労支援の担当者などから「もう年だから」「病気だから」といった言葉を投げかけられます。ここでは「年齢」や「障害」が、働く能力と両立しない固定属性として押し付けられます。これに対し、当事者たちは巧みに抵抗します。例えば、障害を永続的な本質ではなく「一時的な状態」として語り直します。社会から貼られたラベルをそのまま受け入れず、その意味を解釈し直し、自己の物語から引き剥がそうと交渉を続けているのです。
第二の実践は、「働くアイデンティティの創出」です。賃金を得る仕事に就いていなくても、「自分は社会の役に立つ、能動的な存在だ」という自己像を積極的に創り出そうとします。毎朝決まった時間に起き、勉強し、ボランティア活動に参加する。こうした日々の規律ある活動を通じて、「雇われてはいないが、自分は働いている」という感覚を維持します。過去の職業人としての経歴と現在の活動を結びつけ、「働く人」としての自己の物語を延長させる試みです。
第三の実践は、「望ましくない働くアイデンティティの拒否」です。支援機関から、過去の経歴とは無関係な低賃金の仕事を紹介されることがあります。長年かけて築いた専門性や誇りを無視される提案に、彼ら彼女らは反発します。これは選り好みではなく、自身の人生の物語との一貫性を損ない、自尊心を傷つける就労像を拒否する、アイデンティティを守るための抵抗です。
この研究が照らし出すのは、失業という状態がアイデンティティの単純な喪失を意味するわけではないという事実です。逆境の中にあってこそ、人々は過去を資源とし、課されるラベルと交渉して、日々の実践を通じて、必死に「働く自己」の物語を紡ぎ続けようとします。その営みは、尊厳をかけた力強い闘いです。
家族企業では日常的な語りと行為で境界が柔軟に調整される
より複雑な境界線が引かれる「家族企業」に目を向けましょう。そこでは、「家族」という私的な論理と、「ビジネス」という公的な論理が日常的に交錯します。このような環境で働く人々は、公私の間にある見えない境界線を、どのように引き、越えているのでしょうか。米国の家族企業を対象とした研究は、その境界が規則や制度で固定されているのではなく、日々のささやかな言葉や行動を通じて、柔軟に調整されていることを明らかにしています[5]。
この研究は、4つの家族企業で働く44名へのインタビューに基づいています。分析の結果、人々が「家族」と「ビジネス」の境界を管理するために用いる、多様なアイデンティティ・ワークの戦術が浮かび上がりました。それらは、個人が自身の振る舞いを律する戦術と、組織全体のあり方に向ける戦術に大別できます。
初めに、個人レベルの戦術です。非常に微細なものに「会話の調整」があります。ある従業員は、仕事の話題では叔父をファーストネームで呼び、プライベートな話題では「叔父さん」と呼ぶ、というように呼称を使い分け、その場の関係性を切り替えていました。また、「この会議では親子ではなく上司と部下だ」と明確に宣言する「再範疇化」という戦術もあります。これは、家族的な甘えが業務に持ち込まれるのを防ぐ試みです。
続いて、組織全体の文化を形づくる戦術です。ある企業では、「オフィスのドアをくぐったら、家族の役割は外に置いてくる」という比喩が日常的に語られていました。このような「境界の強調」によって、仕事の場では業務上の合理性を優先するという共通認識が維持されます。
その一方で、重要な意思決定の場に非親族の幹部を積極的に参加させる「包摂」や、「社員全員が拡大家族の一員だ」という物語を共有する「家族の拡張」といった戦術も観察されました。これらは所属意識を育む一方で、業務上の規律が緩まないよう、境界の強調とバランスを取りながら用いられていました。
この研究が描き出すのは、家族とビジネスの境界が、就業規則や組織図といった制度ではなく、日々の会話や振る舞い、共有される物語といった生きた相互作用の中で、絶えず引き直され、更新され続けているという現実です。人々は公私の役割を場面に応じて演じ分け、時には統合しながら、この複雑な境界線を日々マネジメントしているのです。
脚注
[1] Watson, T. J. (2009). Narrative, life story and manager identity: A case study in autobiographical identity work. Human Relations, 62(3), 425-452.
[2] Beech, N. (2008). On the nature of dialogic identity work. Organization, 15(1), 51-74.
[3] Bardon, T., Josserand, E., and Villeseche, F. (2015). Beyond nostalgia: Identity work in corporate alumni networks. Human Relations, 68(4), 583-606.
[4] Riach, K., and Loretto, W. (2009). Identity work and the ‘unemployed’ worker: Age, disability and the lived experience of the older unemployed. Work, Employment and Society, 23(1), 102-119.
[5] Knapp, J. R., Smith, B. R., Kreiner, G. E., Sundaramurthy, C., and Barton, S. L. (2013). Managing boundaries through identity work: The role of individual and organizational identity tactics. Family Business Review, 26(4), 333-355.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。