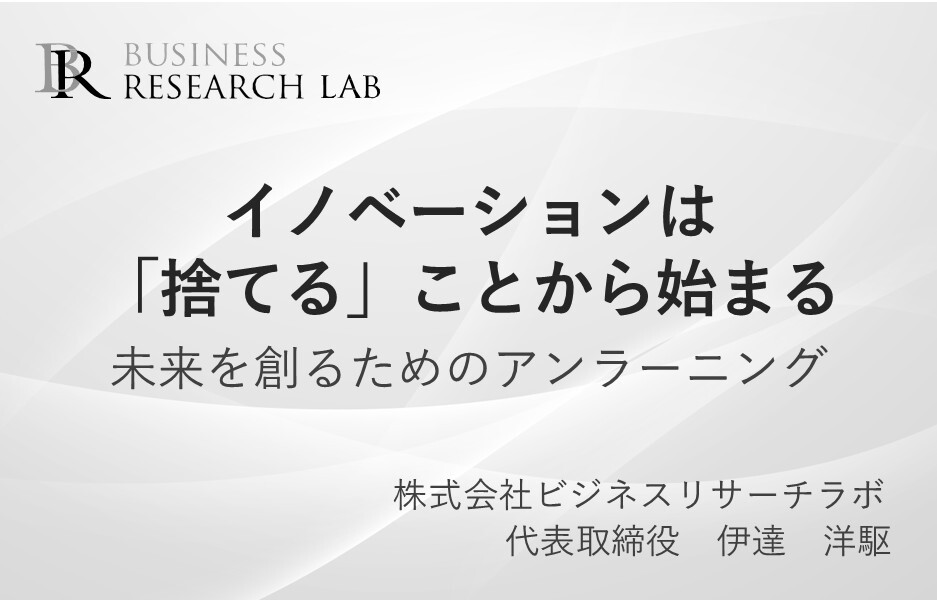2025年12月9日
イノベーションは「捨てる」ことから始まる:未来を創るためのアンラーニング
現代のビジネス環境は、予測不能な変化の連続です。昨年までの常識が今年には通用しなくなり、かつての成功方程式が未来の成長を約束してくれるとは限りません。このような時代にあって、私たちは新しい知識やスキルを「学ぶ」ことの必要性を強く意識しています。しかし、本当にそれだけで十分なのでしょうか。
コップに新しい水を注ぐためには、まず古い水を捨てなければならないように、組織や個人が新しい環境に適応し、革新を生み出し続けるためには、これまで蓄積してきた知識や経験、成功体験を意図的に手放す営みが必要になります。これが「アンラーニング(学習棄却)」と呼ばれる考え方です。過去の成功は、時として新しい発想を妨げる足かせとなり、変化への対応を遅らせる「経験の罠」になり得ます。この罠から抜け出し、持続的にイノベーションを創出する組織になるために、アンラーニングは避けて通れないテーマです。
本コラムでは、このアンラーニングが具体的にどのようにイノベーションにつながるのか、そのメカニズムを実証研究や理論的考察を手がかりに掘り下げていきます。組織の中でアンラーニングが機能するプロセスを解き明かすことで、変化の時代を乗り越えるための新たな視点を提供できれば幸いです。
新製品成功の鍵はアンラーニングの実装
アンラーニングという概念に触れたとき、多くの人がまず思い浮かべるのは、具体的な成果、とりわけ新製品開発の成功との関連性かもしれません。市場のニーズが絶えず変化し、技術の進歩がめまぐるしい現代において、開発チームが過去のやり方に固執することは、致命的な結果を招きかねません。古い考えや手順を手放すことは、どのように新製品の成功に結びつくのでしょうか。この問いに、ある実証研究が道筋を描き出しています[1]。
この研究は、319件の新製品開発プロジェクトを対象に、プロジェクトを率いるリーダーたちへのアンケート調査を通じて行われました。調査では、プロジェクトを取り巻く市場や技術の変化の激しさ、チームが感じている危機感や不安の度合い、チームがどれほど過去のやり方を見直したか、といった点が尋ねられました。
ここで「アンラーニング」は、二つの側面から捉えられています。一つは、技術的に何が可能か、市場は何を求めているかといった「信念」の変化です。もう一つは、開発の進め方や意思決定のプロセスといった、日々の業務における「ルーティン」の変化です。
分析の結果、市場の顧客の好みが移ろいやすかったり、関連技術が急速に進化したりするような、変化の激しい環境に置かれているチームほど、アンラーニングが進みやすいことがわかりました。
変化の波は、チームに「このままではいけない」という危機感や、将来に対する健全な不安を抱かせます。その環境変化の圧力と、そこから生まれる危機感や不安とが、チームに「思い込みを捨て、いつものやり方を見直そう」と促す力となっていたのです。硬直化した思考や行動は、平時では効率的に機能するかもしれませんが、不確実な状況下では適応の妨げになります。適度なストレスや緊張感が、その殻を破るきっかけとなる様子がうかがえます。
しかし、この研究が明らかにした重要な発見は、別にありました。それは、信念やルーティンを見直す、要するにアンラーニングを行った「だけ」では、新製品の成功には直接結びつかないという事実です。分析の結果、アンラーニングから新製品の成功への直接的な関係性は見られませんでした。
何が成功の鍵を握っていたのでしょうか。それは「実装」というステップでした。実装とは、見直された新しい信念やルーティンを、実際のプロジェクト計画、使用するツール、日々の意思決定プロセスといった、具体的な業務運営の中にきちんと組み込むことを指します。考え方を変えただけでは不十分で、その変化が行動や仕組みのレベルにまで落とし込まれて初めて、売上や利益、顧客満足度といった市場での成功確率が有意に高まる、という経路が示されたのです。
競争激化でアンラーニングが革新性を高める
先ほどは、アンラーニングが新製品開発の現場で「実装」というプロセスを通じて成功に結びつく様子を見てきました。ここでは視点を少し引き上げ、企業を取り巻く「競争の激しさ」という外部環境が、組織の学習行動にどのような変化を促し、それがどのような種類の革新につながっていくのかを解き明かした研究を紹介します[2]。
特にこの研究は、組織の学習行動を二つの異なるタイプに分けて比較している点が特徴的です。一つは、社内外の知識を組み合わせ、有効に活用しようとする「知識統合」です。もう一つが、本コラムのテーマである、陳腐化した慣行や信念を捨て去る「アンラーニング」です。
この研究は、中国の製造業242社を対象としたアンケート調査に基づいて進められました。調査の信頼性を高めるため、一つの会社で上位管理者と中間管理者の両方から回答を得るという工夫がなされています。上位管理者には競争環境や組織の学習行動について、中間管理者には新製品開発の成果について尋ねることで、一人の回答者の主観にデータが偏ることを防いでいます。
分析では、競争の激しさが「知識統合」と「アンラーニング」のそれぞれをどの程度促すのか、それらの学習行動が、新製品開発における「スピード」と「革新性」にどう結びつくのかが検証されました。
分析から得られた第一の発見は、競争が激しい環境に身を置く企業ほど、「知識統合」と「アンラーニング」の両方を活発化させるというものでした。ライバル企業との競争が厳しくなると、企業は生き残りのために、使える知識はすべて動員しようと努めると同時に、もはや通用しなくなった古いやり方を捨て去る必要に迫られます。この二つの学習行動が同時に促進されるというのは、直観的にも理解しやすい結果です。
興味深いのは、企業の規模によって、どちらの学習行動により強く傾くかが異なっていた点です。従業員数が多く、組織構造が確立されている大企業では、競争が激化すると、既存の資源やネットワークを駆使して知識を効率的に組み合わせようとする「知識統合」を強める反応が見られました。一方で、従業員数が少なく、身軽な小企業では、競争のプレッシャーが、古い慣習や固定観念を捨て去る「アンラーニング」をより強く促すことが明らかになったのです。
この背景には、大企業が持つ豊富な資源と、それに伴う組織的な慣性の大きさが関係していると考えられます。大企業は知識を統合する力に長けていますが、何かを「やめる」意思決定には時間がかかります。対照的に、小企業は資源こそ乏しいものの、意思決定が迅速で、過去のしがらみが少ないため、大胆な方針転換、すなわちアンラーニングを実行しやすいのでしょう。
二つの学習行動がもたらす成果の種類にも違いが見られました。「知識統合」は、新製品を市場に投入するまでの時間を短縮する「スピード」の向上と強く結びついていました。既存の知識を効率的に組み合わせることで、問題解決が早まり、開発プロセス全体が迅速化するためだと解釈できます。
それに対して、「アンラーニング」は、これまでにない全く新しい製品やサービスを生み出す「革新性」の向上により強く貢献していました。既存の枠組みや常識を一度壊すことで、従来の発想の延長線上にはない、飛躍的なアイデアが生まれやすくなるためと考えられます。この研究は、組織が置かれた状況や目指す成果によって、とるべき学習戦略が異なることを示唆しています。とりわけ革新性を求める場面において、アンラーニングが持つ独自の価値を浮き彫りにしたと言えるでしょう。
暗黙知のアンラーニングが革新を促す
これまでの議論では、組織の信念やルーティン、あるいは制度化された慣行といった、ある程度は意識上にあり、言葉で表現できるレベルのアンラーニングを扱ってきました。しかし、組織や個人の行動を深く規定しているのは、明文化されたルールや手続きだけではありません。長年の経験を通じて身体に染みついた「勘」や、チーム内で共有されている「あうんの呼吸」のような、言語化することが難しい「暗黙知」が存在します。
暗黙知は、他社には模倣困難な競争力の源泉となる一方で、一度環境とずれてしまうと、変化への見えない抵抗勢力となり、イノベーションを阻害する要因にもなり得ます。このように捉えどころのない暗黙知を、私たちはどのようにして手放すことができるのでしょうか。
この難問に対して、理論的な考察を通じて一つの道筋を示した論考があります[3]。この論考は、新たなデータを収集した実証研究ではなく、既存の知見を統合し、暗黙知のアンラーニングを可能にするための概念的なフレームワークを提示するものです。
その出発点には、暗黙知が持つ二面性の認識があります。熟練工の技術のように、それは組織の宝となり得ますが、同時に、市場や技術が変化した際には、最も手放しにくい「過去の遺物」にもなり得るのです。特に、経済体制が大きく転換した国々では、旧体制下で有効だった経験知が、新しい競争環境では足かせになるという現実的な問題が背景にあります。
この論考が提案する暗黙知のアンラーニングプロセスは、直接的ではなく、間接的なアプローチを取る点に特徴があります。暗黙知そのものを直接操作することはできないため、その暗黙知から生まれる「行動」を観察することから始めます。例えば、「明確な理由は説明できないが、この部署では昔からこうすることになっている」といった慣習的な行動や、会議で特定の話題がなぜか避けられる雰囲気、あるいは説明がほとんどないにもかかわらず仕事が滞りなく進んでいく様子など、日々の業務に現れる具体的な現象に着目するのです。
次のステップは、観察された行動について、当事者たちの間で対話を行うことです。対話を通じて、行動の背後にある暗念の前提や価値観を、できる範囲で言語化し、共有する試みです。「なぜ私たちはいつもこのやり方を選ぶのだろうか」と問い直すことで、これまで自明視されてきた暗黙のルールが姿を現し始めます。
可視化された暗黙知が、現在の環境においてイノベーションを促進するものなのか、それとも阻害するものなのかを吟味し、選別します。ここで重要なのは、すべての暗黙知を否定するわけではないという点です。組織の強みとなっている暗黙知は維持・強化しつつ、陳腐化してしまった、あるいは変化の妨げとなっていると判断されたものだけを、意図的に手放す対象とします。
古い暗黙知を手放した後に生まれる空白に、新しい知識や行動様式を学び、実践を通じて新たな暗黙知として定着させていく。この一連のサイクルを回すことが、暗黙知のマネジメントの中核であると、この論考は主張します。
この考え方は、アンラーニングが単なる破壊ではなく、創造的な再構築のプロセスであることを教えてくれます。目に見えないからといって諦めるのではなく、観察可能な行動を手がかりに、組織の深層に根ざした思考様式に働きかけていく。そうした地道な営みが、組織を内側から変え、持続的な革新を可能にするのかもしれません。
アンラーニングは柔軟性を介して革新力を高める
私たちはこれまで、アンラーニングが「実装」を経て成果に結びつくこと、競争環境下で「革新性」と関わること、「暗黙知」という厄介な対象をいかに扱うか、といった多角的な視点からアンラーニングの姿を捉えてきました。ここでは、これまでの議論を統合する形で、アンラーニングが組織にもたらす中間的な効能に着目します。すなわち、アンラーニングは、組織のどのような能力を高め、最終的にイノベーションへとつながっていくのか。その媒介役として「組織の柔軟性」という概念を導入し、一連の関係を解き明かした研究を紹介します[4]。
この研究は、中国の中小企業248社へのアンケート調査データを用いて、アンラーニング、組織の柔軟性、イノベーション能力の三者の関係性を検証しました。ここでいう「組織の柔軟性」とは、環境の変化に対応して、通常の手順から逸脱することを許容したり、戦略を素早く変更したりできる、組織のしなやかさを指します。「イノベーション能力」は、既存製品の改良といった小幅な改善を指す「漸進的イノベーション」と、業界の常識を覆すような新しい技術や製品を生み出す「急進的イノベーション」の二種類に分けて測定されました。
分析によって得られた第一の結論は、組織的なアンラーニングが「組織の柔軟性」を顕著に高めるという関係性の確認でした。古い信念や時代遅れの慣行を意図的に手放す組織は、変化に対してしなやかに対応できる能力が高いという仮説が、データによって裏付けられたのです。アンラーニングは、組織を縛っていた過去の慣性から解放し、新しい行動様式を取り入れるための土壌を整えます。
続いて、アンラーニングが最終的なイノベーション能力に結びつく経路が分析され、イノベーションの種類によってそのメカニズムが異なることが明らかになりました。
業界に大きな変化をもたらす「急進的イノベーション」の場合、アンラーニングの効果は、「組織の柔軟性」を経由してのみ発揮されていました。古いやり方を捨てたという事実だけでは急進的なイノベーションには直接つながらず、アンラーニングによって得られた組織のしなやかさを活用し、資源を大胆に再配分したり、部門を横断して新しい組み合わせを試みたりして初めて、大きな変革が生まれるという構造が見えてきたのです。
一方で、既存製品の改善などを指す「漸進的イノベーション」の場合は、少し様相が異なります。アンラーニングは、「組織の柔軟性」を介して漸進的イノベーションを促進する経路に加えて、柔軟性を介さずに直接的にイノベーション能力を高める経路も併せ持っていました。日々の小さな改善であれば、組織全体の大がかりな再編成を待たずとも、個々の現場レベルで不要な前提を一つ外すだけでも進展することがあるためでしょう。
この研究は、アンラーニングの効能を最大化するためには、それを「組織の柔軟性を高めるための手段」として位置づける視点が有効であることを教えてくれます。捨てること自体が目的化するのではなく、それによって得られる組織の機動力や適応力を、どのようなイノベーションに結びつけていきたいのか。その意識を持つことが、アンラーニングを戦略的な活動へと昇華させるでしょう。
脚注
[1] Akgun, A. E., Lynn, G. S., and Byrne, J. C. (2006). Antecedents and consequences of unlearning in new product development teams. Journal of Product Innovation Management, 23(1), 73-88.
[2] Lyu, C., Zhang, F., Ji, J., Teo, T. S. H., Wang, T., and Liu, Z. (2022). Competitive intensity and new product development outcomes: The roles of knowledge integration and organizational unlearning. Journal of Business Research, 139, 121-133.
[3] Rebernik, M., and Sirec, K. (2007). Fostering innovation by unlearning tacit knowledge. Kybernetes, 36(3-4), 406-419.
[4] Wang, X., Lu, Y., Zhao, Y., Gong, S., and Li, B. (2013). Organisational unlearning, organisational flexibility and innovation capability: An empirical study of SMEs in China. International Journal of Technology Management, 61(2), 132-155.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。