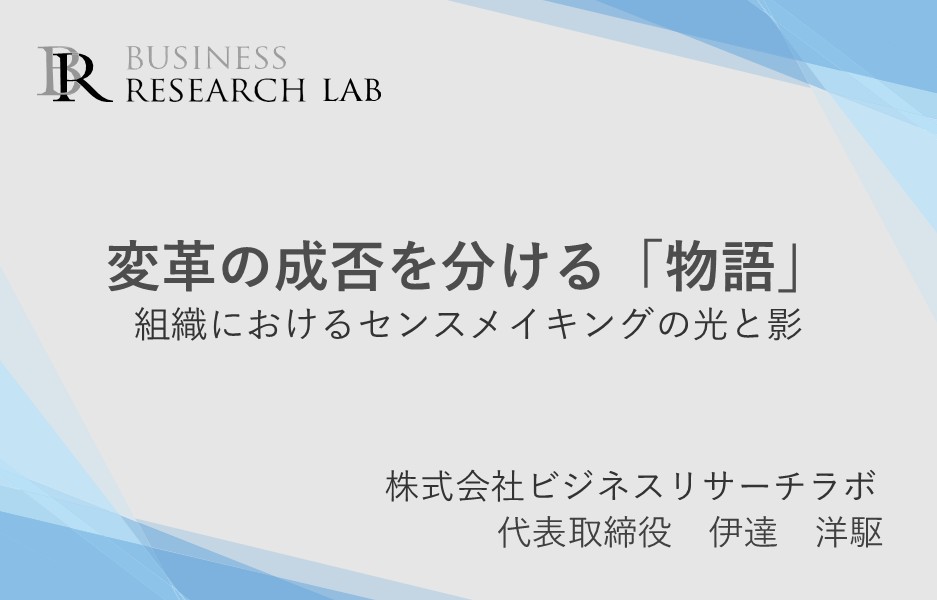2025年12月9日
変革の成否を分ける「物語」:組織におけるセンスメイキングの光と影
組織を変えようとするとき、しばしば精緻な計画や戦略の策定に心血を注ぎます。しかし、どれほど完璧に見える計画も、現場では思い通りに進まないことが少なくありません。抵抗、誤解、無関心。こうした壁に突き当たったとき、計画そのものの欠陥を疑う前に、一度立ち止まって考えてみるべきことがあります。それは、変革の渦中にいる一人ひとりの頭の中で、いったい何が起きているのかということです。
人は誰でも、自分の周りで起きている出来事に対して、自分なりの「意味」を見出そうとします。曖昧で混沌とした現実を、納得のいく物語に仕立て上げようとする、ごく自然な営み。これを「センスメイキング」と呼びます。センスメイキングは、私たちが変化に適応し、他者と協力して行動するための土台となるものです。
しかし、このプロセスは必ずしも組織にとって良い方向に働くとは限りません。同じプロジェクトを経験したはずのメンバーが、後になって全く異なる思い出を語ることがあります。ある人にとっては「挑戦と成長の物語」が、別の人にとっては「混乱と失敗の物語」になっている。なぜ、このような食い違いが生まれるのでしょうか。
本コラムでは、組織変革という舞台の裏側で繰り広げられる、人々のセンスメイキングの光と影に焦点を当てていきます。変革の現場でうごめく、複雑で、時にもろく、しかし創造的でもある人間的なプロセスを、いくつかの研究を手がかりに見つめていきたいと思います。
アイデンティティ維持が食い違うセンスメイキングを生む
ある小規模なゲーム開発会社で、一つのプロジェクトが進行していました。海外のクライアントから携帯端末向けのゲーム開発を受託し、限られた時間と資源の中で、チームはなんとか納期に間に合わせて製品を納品しました。この出来事について、プロジェクトの中心メンバーであった4人に話を聞くと、奇妙なことがわかります[1]。全員が共有している「公式の物語」と、それぞれが内心で抱いている「個人の物語」との間に隔たりがあったのです。
メンバーの誰もが、クライアントの要求に応え、既存のプログラムを基盤に開発を進めたこと、携帯端末の厳しい容量制限に苦しんだこと、見栄えを良くするために背景にアニメーションを加える工夫をしたこと、最終的に納期を守ったことについては、同じように語ります。この共有された物語は、会社として「私たちは制約の中でもやり遂げられるプロ集団だ」という自己認識を支え、今後の開発に活かせる実践的な知識を蓄積する上で、なくてはならないものでした。
しかし、話が核心に近づくにつれて、物語は分岐し始めます。プロジェクトの「目標」は何だったのか。マネージャーは「納期遵守が最優先だった」と語りますが、アーティストは「デザインの品質を最大限に高めること」、若手のプログラマーは「新しいスキルを学ぶ機会」、ベテランのプログラマーは「既存のコードを改良すること」が自分の目標だったと認識していました。
プロジェクトで直面した「問題の原因」についても、解釈は異なります。マネージャーは、アーティストの意欲不足でアートの品質が上がらなかったことや、テスト不足を問題視します。一方のアーティストは、時間不足や技術的な制約、自分の警告が軽視されたことを原因に挙げます。若手プログラマーはクライアントの度重なる要求変更や技術的な困難さを強調し、ベテランは若手の技術的な未熟さが根本原因だと考えていました。
この食い違いは、いったいどこから来るのでしょうか。ある研究では、この現象を解き明かす鍵として、人が無意識のうちに行っている「アイデンティティを守る」という営みを指摘しています。人は誰しも、「自分は有能であり、正しい判断ができる人間だ」という自己像を維持したいと願っています。そのため、何かうまくいったことがあれば、それは自分の手柄だと考え、うまくいかなかったことは、自分以外の誰かや、環境のせいにする心理的な働きがあります。
このゲーム開発プロジェクトの事例では、まさにそのメカニズムが働いていました。マネージャーは、初期デザインの功績は自分にあるとし、品質低下の責任はアーティストにあると語ります。アーティストは、制約さえなければ素晴らしいものができたはずだと、自分の能力を擁護します。プログラマーたちも同様に、自らの貢献を強調し、問題の原因を自分以外の要因に求めていました。それぞれの語りは、客観的な事実の報告である以上に、自身の有能さや正当性を、自分自身と他者に対して証明するための「自己弁護の物語」となっていたのです。
パラドックスへの転換が変革期のセンスメイキングを促す
個人のアイデンティティを守るための物語が、時に組織の協調を難しくすることを見てきました。では、組織変革のように、矛盾した要求が四方八方から飛び交い、個人のアイデンティティさえ揺さぶられるような状況では、人々はどのようにして協働可能な意味を見出していくのでしょうか。特に、上層部からの指示と現場の現実との板挟みになりがちな中間管理職は、その混乱の最前線に立たされます。
デンマークの玩具メーカー、レゴ社が大規模な組織再編に乗り出したとき、現場の管理職たちは行き詰まりを感じていました[2]。管理階層は削減され、チームは自律的に動くことを求められる。管理職は、部下に権限を委譲して自律性を尊重するよう求められる一方で、これまで通りチームの成果には全責任を負わなければなりません。「任せるべきか、管理すべきか」「効率を追求すべきか、チームの育成を優先すべきか」。このような二者択一の問いが、管理職たちを精神的に追い詰めていました。
この困難な状況を乗り越えるために、ある興味深い試みが行われました。それは、外部の専門家が管理職と一対一、あるいはチームで対話を行う「スパーリング」と呼ばれるセッションです。このセッションの目的は、解決策を提示することではありません。管理職たちが抱える混乱した悩みを、対話を通じて徐々に解きほぐし、彼ら彼女ら自身が新しい意味を見出す手助けをすることでした。
対話は、体系的な質問法を用いて進められます。まず、「何が起きていますか」といった直線的な質問で、漠然とした悩みを具体的な「問題」として言語化します。次に、「もしあなたが部下の立場だったら、この状況をどう見ますか」といった循環的な質問で、視点を変え、問題の多面性を浮かび上がらせます。この段階で、管理職たちは「AかBか」という「ジレンマ」に直面している自分に気づきます。
ここからが、このアプローチの核心部分です。専門家は、「任せると同時に、責任も負う、という矛盾した状況を、あなたはこれまでどう扱ってきましたか」といった反省的な質問を投げかけます。この問いは、二者択一の思考から抜け出し、「Aでもあり、Bでもある」という矛盾した状態、すなわち「パラドックス」として状況を捉え直すことを促します。統制と自律は、どちらかを選ぶものではなく、両立させなければならないもの。この認識の転換が、行き詰まりを打破する突破口となります。
例えば、ある管理職は、部下に権限を委譲しつつも、定期的に進捗を共有する場を設けることで、自律性と責任の両方を担保するという行動を見出しました。これは完璧な解決策ではありません。しかし、矛盾を抱えながらも、試行錯誤を続けながら前に進むための「やっていける確かさ」と呼べるような、実践的な足場を獲得したのです。
この研究は、組織の中で生じるパラドックスを、「遂行(生産性と育成など)」「所属(チームの一体性と個人の自立など)」「組織化(安定と変化など)」の三つの領域に分類しています。これらの領域における矛盾は、個別の問題としてではなく、相互に連関し合うものとして捉える必要があります。一つの領域でパラドックスを乗り越える試みが、他の領域にも良い循環を生み出す可能性があるのです。
変革期の混乱は、人々から意味を奪い、無力感をもたらします。しかし、その混乱の中から、二者択一ではない、より豊かな意味を紡ぎ出すことも可能です。矛盾から逃げるのではなく、それを直視し、両立の道を探る。その地道な意味づけのプロセスが、組織が変化を乗り越え、新たな段階へと進むための原動力となるのかもしれません。
センスメイキングとセンスギビングの循環が変革初動を形づくる
矛盾した状況を乗り越えるための、個々人やチームレベルでの意味づけのプロセスを見てきました。今度は視点を大きく変えて、組織全体の変革がまさに始まろうとする「初動」の瞬間に目を向けてみましょう。特に、差し迫った危機があるわけではない平時において、リーダーはどのようにして組織に変化の必要性を伝え、新しい方向へと導く「うねり」を作り出していくのでしょうか。
この問いに答えるヒントを、ある公立大学で新学長が就任した直後から始まった改革の事例に見出すことができます[3]。この事例を詳細に追った研究は、変革の始動が、リーダーによる「意味づけ(センスメイキング)」と、その意味を組織に広める「意味の付与(センスギビング)」という、二つの活動の循環的なプロセスとして展開していく様子を捉えています。
プロセスは四つの段階を経て進みます。第一段階は「構想化」です。新学長は就任前から学内外の多くの人々と対話し、資料を読み込むことで、大学が置かれている状況を自分なりに解釈し、理解しようと努めました。これは、リーダー自身が、これから進むべき道について納得のいく物語を作り上げる、内的なセンスメイキングの過程です。その結果、「全米トップ10の公立大学になる」という、シンプルで象徴的なビジョンが結晶化しました。
第二段階は「シグナリング」です。就任直後、学長は改革を宣言し、幹部人事を刷新するなど、目に見える形で変化の意思を組織に示します。これは、リーダーから組織に向けた最初のセンスギビングです。この時点でのメッセージは、意図的にある程度の曖昧さを含んでいます。その狙いは、既存の安定した意味の世界に揺さぶりをかけ、「何かが変わる」という期待と緊張感を生み出し、人々を新しい意味の探求へと駆り立てることにありました。
当然、このような急な変化には抵抗が生まれます。これが第三段階の「再構想化」です。教職員など、学内の様々な人々が、学長の打ち出したビジョンを自分たちの立場から解釈し始めます。賛成、反対、懐疑的な意見が噴出する中で、リーダーはこれらの反応を受け止め、当初のビジョンを微修正する必要に迫られます。ここでは、組織のメンバーによるセンスメイキングが活発化し、その結果がリーダーへとフィードバックされていきます。
最後の第四段階が「エナジャイジング」です。学長は、全学的なタスクフォースを設置し、より多くの人々を改革の議論に巻き込んでいきます。当初のビジョンは、様々な意見を取り込みながら、より具体的で実行可能な計画へと練り上げられていきます。このプロセスを通じて、ビジョンはもはやリーダー一人のものではなく、組織全体の共有財産となり、変革を実行するためのエネルギーが組織全体に満ちていきます。組織のメンバーが主体となって、変革の意味を周囲に広げていく、広範なセンスギビングの段階といえるでしょう。
この一連の流れからわかるのは、変革の始動が、リーダーが考えた計画を一方的に実行するプロセスではないということです。リーダー自身の「理解」から始まり、組織への「働きかけ」へと展開し、組織からの反応を受けて再び「理解」を深め、最終的に組織全体の「行動」へとつながっていくという循環的な対話のプロセスなのです。平時における変革は、合理的な計画の提示以上に、象徴的なビジョンを掲げ、意味をめぐる対話の場を設計することによって、その第一歩を踏み出すのかもしれません。
M&A後統合は曖昧さと政治化のセンスメイキングで停滞する
リーダーが主導するセンスメイキングとセンスギビングの循環は、変革を始動させる上での一つの理想的な姿かもしれません。しかし、異なる文化を持つ組織同士が一つになるM&Aのような場面では、意味づけのプロセスははるかに複雑な様相を呈し、しばしば深刻な停滞を引き起こします。計画では輝かしいシナジー効果が謳われていたにもかかわらず、現場ではなぜ統合が遅々として進まないのか。その背景には、意味づけをめぐる問題が横たわっています。
フィンランドの大手家具メーカーが、隣国スウェーデンの同業他社を買収した事例は、その典型的な困難さを描き出しています[4]。買収側の狙いは、スウェーデン市場での販路拡大や、両社の製品ラインを統合することによる効率化でした。しかし、統合に向けた議論はなかなか前に進みません。この停滞のメカニズムを解き明かすと、四つの相互に関連し合う要因が浮かび上がってきます。
第一に、「固有の曖昧さ」です。「統合」という言葉が、それぞれの立場の人にとって異なる意味を持っていました。買収側の本社はグループ全体の最適化を考えますが、買収されたスウェーデン企業の経営者は自社の自律性を守ることを第一に考えます。フィンランド国内の事業部門は、自社製品の輸出拡大を期待する一方で、スウェーデン製品が国内市場に入ってくることには警戒心を抱きます。同じ言葉を使いながら、頭に描いている未来が異なっているため、議論はかみ合いません。
第二に、「文化的混乱」がその曖昧さを増幅させます。フィンランド側は、会議で合意すればすぐに行動に移す文化を持っていましたが、スウェーデン側は、何度も議論を重ねて丁寧な合意形成を目指す文化でした。そのため、フィンランド側は一度の会議で相手が「同意した」と解釈しても、スウェーデン側はそれを「議論の始まり」と捉えている、といったすれ違いが頻発しました。言語の壁も、細かなニュアンスの共有を妨げ、誤解を生む温床となりました。
第三の要因は、「組織的偽善」と呼べる現象です。戦略会議の場では、「連携を強化しよう」「知識を共有しよう」といった耳障りの良い言葉が繰り返されます。しかし、日常の意思決定の場では、これまで通りのやり方が優先され、統合に向けた具体的な行動は後回しにされます。特に、買収先の業績が良い間は、「うまくいっているものを、あえて壊す必要はない」という論理がまかり通り、変革の緊急性が失われてしまいます。
最後に、これらの問題が長期化するにつれて、「論点の政治化」が進行します。統合によって自分たちの仕事や権限が脅かされると感じた各部門は、自らの利益を守るために、統合に反対するためのあらゆる論拠を探し始めます。「相手の国の製品は、こちらの市場の品質基準に合わない」「長年付き合いのある取引先を変えることはできない」。こうした主張は、客観的な事実というよりも、自部門の正当性を守るための政治的な道具となります。こうして、当初は協力の可能性があったはずの組織間に、深い溝が刻まれてしまうのです。
この事例が示すのは、M&A後の統合の失敗が、計画の不備や実行力の欠如によるものではないということです。それは、異なる意味の世界に生きてきた人々が、共通の物語を紡ぐことに失敗した結果といえます。曖昧さが誤解を生み、きれいごとが行動を伴わず、やがて不信感が権力闘争へと発展していく。この負の連鎖が、統合という困難な事業を、さらに深い迷宮へと誘い込んでしまいます。
脚注
[1] Brown, A. D., Stacey, P., and Nandhakumar, J. (2008). Making sense of sensemaking narratives. Human Relations, 61(8), 1035-1062.
[2] Luscher, L. S., and Lewis, M. W. (2008). Organizational change and managerial sensemaking: Working through paradox. Academy of Management Journal, 51(2), 221-240.
[3] Gioia, D. A., and Chittipeddi, K. (1991). Sensemaking and sensegiving in strategic change initiation. Strategic Management Journal, 12(6), 433-448.
[4] Vaara, E. (2003). Post-acquisition integration as sensemaking: Glimpses of ambiguity, confusion, hypocrisy, and politicization. Journal of Management Studies, 40(4), 859-894.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。