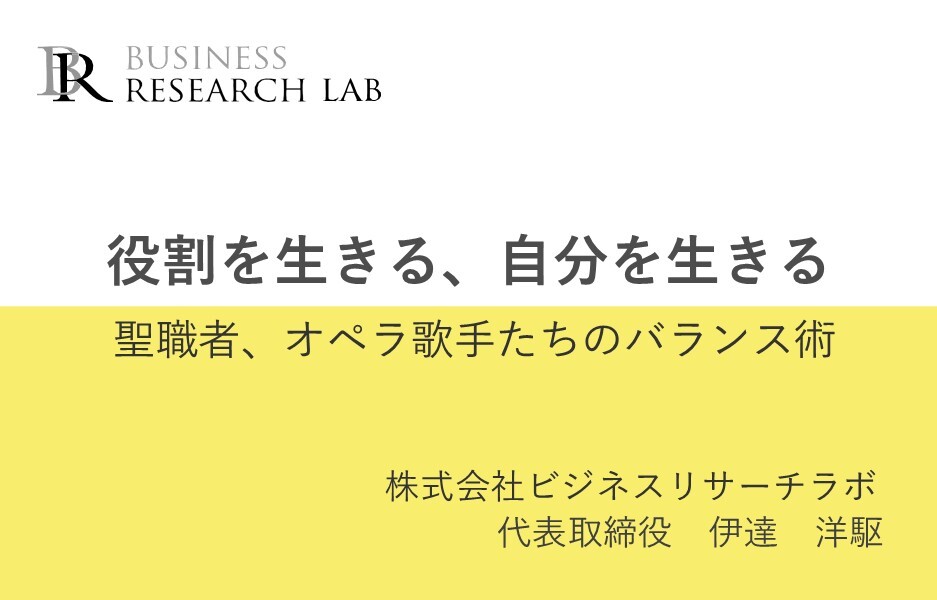2025年12月5日
役割を生きる、自分を生きる:聖職者、オペラ歌手たちのバランス術
「自分らしく生きる」という言葉を、私たちは当たり前のように口にします。しかし、その「自分らしさ」とは、一体どこから来て、どこへ向かうのでしょうか。私たちは、生まれた瞬間から、家族、学校、職場、社会全体が発する無数の「かくあるべし」というメッセージのシャワーを浴びて生きています。それは時に、尊敬すべき理想像として私たちの成長を促し、また時には、息苦しい規範として私たちの個性を押しつぶそうとします。
本コラムは、そうした抗いがたい理想や規範の力と、その中で「自分であろう」ともがき続ける人間の姿を、いくつかの具体的な現場を通して描き出します。ここで覗き見るのは、精鋭部隊の兵士、刑務所の受刑者、オペラの稽古に励む芸術家、自らの音楽を追求するミュージシャン、人々の信仰に仕える聖職者たちの物語です。彼らが置かれた環境は極端に見えるかもしれませんが、そこで繰り広げられる自己をめぐる葛藤や探求は、組織や社会の中で生きる私たち自身の姿を映し出す鏡となるはずです。
人が規範と出会うとき、何が起きるのか。理想は、どのようにして私たちの内面に入り込み、私たちを形作っていくのか。本コラムが、読者の皆さんにとって、終わることのない「自分になる」という旅を、新たな角度から見つめ直すきっかけとなれば嬉しく思います。
到達困難な理想像が規律を通じて兵士の自己を作り続ける
組織が掲げる理想の人間像は、個人の内面に浸透し、その人の生き方そのものを方向づけることがあります。イギリス陸軍の精鋭部隊であるパラシュート連隊に所属する兵士たちを対象とした調査は、組織の理想が個人の強い憧れと結びつき、終わりなき自己形成の原動力となる様子を明らかにしています[1]。
インタビューの中から浮かび上がってきたのは、「自分は本物のパラトルーパーになれたのだろうか」という、絶え間ない問いでした。昇進を重ねたベテランでさえ、「まだ自分を証明しなくてはならない」「これは終わりなき梯子だ」と語ります。彼ら彼女らにとって、連隊への所属はゴールではなく、理想の兵士であり続けるための果てしない自己証明の旅の始まりです。この「決して完全には到達できない」という感覚が、彼ら彼女らを常に駆り立てる力の源泉となっているように見受けられます。
この理想像は、主に三つの言葉によって形作られています。一つ目は「プロフェッショナリズム」であり、自らを高い専門技術を持つ存在と認識し、いかなる状況でも厳しく律する内面的な基準となります。二つ目は「エリート性」で、「我々は軍で随一だ」という誇りが、あらゆる任務を「より速く、より長く、より厳しく」やり抜く精神的な支柱となります。三つ目は「マチズモ」、すなわち戦闘への強い志向であり、実戦経験こそが本物の証しであるという価値観が、彼ら彼女らの行動を方向づけています。
このような理想像は、いかに兵士たちの内面に植え付けられるのでしょうか。初めに、「生成の儀礼」とも呼べる過酷な選抜課程があります。これを通過した者だけが連隊の象徴を手にでき、このプロセスは「パラトルーパー」という新しい自己を作り上げる儀式として機能します。
部隊配属後も「監視と相互査定」の環境が続きます。常に同僚から観察される無数の視線は、やがて内面化された監視官となり、誰も見ていない場所でも自らを規律するよう促します。そして、「ストーリーテリング」が理想像に血肉を与えます。語り継がれる英雄譚は具体的なロールモデルとなり、「どう振る舞うべきか」を教え、次世代の若者に憧れを抱かせます。
こうした仕組みを通じて、兵士たちは組織の規律に一方的に従わされているだけではなくなります。組織が提示する理想像を、彼ら自身が強く「欲する」ようになるのです。規律はただの抑圧ではなく、望む自己を実現するための道筋となり、彼ら彼女らはその枠組みの中で主体的に自己を形成し続けます。組織の理想が個人の欲望と結びつくことで、絶え間ない自己形成が促されるのです。
受刑者の自己語りは組織の正統性を支える資源となる
精鋭部隊では、組織の高い理想が兵士たちの自己形成を促していました。対して、自由が剥奪された刑務所という環境で、人はどのように「自分」を語るのでしょうか。フィンランドの厳戒刑務所で行われた調査は、受刑者たちの自己に関する語りが、同時に刑務所という組織の「正当性」をめぐる語りにもなっている事実を明らかにしました[2]。彼ら彼女らの語りは、この組織が妥当な場所であるかを内側から定義する力を持っていたのです。
受刑者たちの語りは、刑務所のあり方を肯定する方向と、それに異議を唱える方向の二つに分かれました。肯定的な語りには三つの側面があります。
第一に、実利的な計算に基づく肯定です。禁酒や健康回復といった機会を「自分のためになる」と捉え、刑務所を有益な場所として語ります。第二に、道徳的な価値判断に基づく肯定です。個別に作られる更生計画を「自分をより良くしてくれる正しい仕組み」と受け止め、自己改善のプロセスに参加することで、刑務所の理念を承認します。第三に、それが当たり前であるという感覚に基づく肯定です。厳格な日課がもたらすリズムが心の安定を生み、将来を描くための足場となるのです。
一方で、刑務所のあり方に異議を唱える語りも、同様に三つの側面からなされます。
第一に、実利的な観点からの異議です。娯楽や学習機会の不足、特に家族との関係維持の困難さは、「自分の利益にならない」経験として語られ、組織の妥当性を疑わせます。第二に、道徳的な観点からの批判です。更生という理念が、現実には「管理の道具」に過ぎず、服従を強いる偽善ではないかと告発します。第三に、当たり前であるという感覚の崩壊です。日々の生活が「意味のない繰り返し」と感じられ、職員の対応に一貫性がない経験が重なると、刑務所は意味のある場所としての基盤を失います。
この調査から見えてくるのは、受刑者たちの自己をめぐる語りが、個人の感想にとどまらないということです。それは、刑務所という組織の内部的な正統性を、日々組み立て、あるいは崩す営みとなっています。興味深いことに、多くの受刑者が肯定と否定の両方の語りを併せ持っていました。この複雑で矛盾をはらんだ無数の語りの総体として、刑務所の秩序は維持されているのです。個人のミクロな自己語りが、組織というマクロな安定に結びついている様子がうかがえます。
オペラ稽古の緊張は自己と他者の役割を組み替える
創造的な活動の現場では、多様な個性が協働するため、予期せぬ緊張が生まれやすくなります。そうした緊張は、時に人々の自己認識や関係性を、劇の一幕のように作り変えてしまうことがあります。あるオペラ公演の稽古場で起きた出来事は、そのプロセスを鮮やかに描き出しています[3]。
この事例は、オペラ「フィガロの結婚」のリハーサル過程を、研究者が内部から参与観察することで記録されました。分析から見えてきたのは、稽古場に常に存在していた三種類の緊張関係でした。
一つ目は、なりたい自分を演じようとすることから生じる緊張です。演出家は「歌手に寄り添う」理想像と「全体をまとめる」責任の間で、主役ソリストは「役への没入」と「キャリア形成」の間で揺れていました。二つ目は、なりたくない自分から距離を取ろうとすることで生まれる緊張です。ソリストは「わがままな歌姫ではない」と振る舞おうとすることが、かえってそのイメージを強化してしまう皮肉な状況にありました。三つ目は、複数の役割を同時に担うことから生じる緊張です。指揮者は、演出家に指示される立場と、組織の上位者である理事という二つの顔を持っていました。
こうした緊張が渦巻く中、決定的な出来事が起こります。演出家が、主演ソリストであるベラの歌の解釈に苛立ち、強い口調で叱責したのです。ベラは涙し、彼女の私生活の困難を知る周囲は同情的な雰囲気になりました。この瞬間、場の空気は一変します。稽古の主導権は事実上、演出家から、仲裁に入った指揮者の手に移りました。
この現象は「再ナレーション」、すなわち物語の書き換えとして理解できます。叱責という行為によって、それまでの物語は一瞬で書き換えられました。新しい物語では、ベラは悲劇の「被害者」、演出家は「加害者」、指揮者は「救助者」という役柄が、その場にいた全員の共通認識として瞬時に成立したのです。
一度この新しい配役が共有されると、それは強力な現実となり、以降、演出家は孤立し、その指示は力を失いました。自己をめぐる語りは、自分一人で完結するのではなく、他者との関係性の中で、ある種の「事件」をきっかけとして、これほどダイナミックに書き換えられてしまうことがあります。
未解決の葛藤を抱え続けることが創作を支える
これまでの事例では、人々が自己を安定した形にまとめようとしたり、緊張を解消したりする営みを見てきました。しかし、あえて自己の中の矛盾や葛藤を解消せず、その不安定な状態を抱え続けることで前に進む人々もいます。インディー・シーンで活動するミュージシャンたちの創作活動は、そのあり方を考える上で示唆に富んでいます[4]。
ヨーロッパのインディー・ミュージシャンたちを対象とした調査から見えてきたのは、彼ら彼女らのアイデンティティ・ワークが、自己をめぐる葛藤を「解消」するのではなく、むしろ「持続」させることを特徴としている姿でした。この未解決の葛藤は、ミュージシャンの仕事が循環する三つの状況で現れます。
第一の状況は、一人で行うソングライティングです。多くのソングライターは、創作のために意図的に自らの「暗い場所」へと降りていき、不快な感情や自己への疑念と向き合います。ここでの目標は完璧な自己表現ではなく、自己への問いを続けること自体が創作のプロセスと結びついています。
第二の状況は、バンドでの編曲と練習です。個人の表現は集団の論理と衝突し、「自分の表現の純粋さを守りたい」思いと、「他者の貢献を取り入れて曲を良くしたい」思いの間で引き裂かれます。この緊張関係の中から、個人だけでは到達しえなかった音楽的な高みが生まれることも事実です。
第三の状況は、ライブパフォーマンスです。観客との一体感を求めつつも、評価や拒絶への恐怖から自分を守るため、ある種の「舞台用の人格」を作り上げます。自己をさらけ出すことと、それを守ることの間の絶え間ない緊張を抱えたまま、彼ら彼女らはステージに立ち続けます。
これらの三つの状況は循環し、一つの局面で生まれた葛藤は解消されず次の局面へと持ち越されます。ミュージシャンたちにとって、自己をめぐる問いや葛藤は、乗り越えるべき障害ではなく、創作活動を駆動し続けるエネルギー源です。「作品は自分自身である」という強い結びつきがあるからこそ、彼ら彼女らは自己の不安定さから目をそらさず、それを作品へと昇華させようとします。問い続ける状態を維持すること、そのプロセス自体が創造性を支えていると言えるでしょう。
聖職者は自分らしさと役割の均衡を多様な戦術で保つ
聖職者のように「公的な役割」が個人の生活全体に浸透する職業では、「役割としての自分」と「ありのままの自分」との間で、どのように折り合いをつけるかが切実な課題となります。米国の聖公会司祭を対象とした調査は、彼ら彼女らが強い職業的アイデンティティの要求の中で、いかに最適なバランスを見つけ出そうとしているのかを明らかにしました[5]。
調査から、多くの司祭が役割と自己の間で三つの典型的な緊張を経験していることが浮かび上がりました。一つ目は、役割が自己のすべてを覆い尽くす「過同一化」。二つ目は、職業上の役割が私的な領域にまで侵食してくる「アイデンティティ侵入」。三つ目は、「本当の自分」を見せられないと感じる「透明性の欠如」です。
司祭たちはこうした緊張に対し、多様な「戦術」を意識的に使い分けていました。それらは大きく二つの方向に分類できます。一つは、「差異化戦術」と呼ばれる、役割と自己を意図的に切り離す営みです。例えば、「すること」と「であること」を区別し、場面に応じて役割の仮面を着脱したり、仕事のオンとオフを意識的に切り替えたりします。趣味など全く別の役割に没頭することも有効です。
もう一つの方向は、「統合戦術」と呼ばれる、役割と自己をあえて重ね合わせる営みです。叙任を機に「存在論的に変わった」と受け入れたり、過去の職歴や個人的な経験を司牧の場で積極的に活かし、「自分らしくあること」が良い司祭であるための条件だと再定義したりします。
興味深いのは、これらの戦術がキャリアの進行と共に変化していくことです。最適なバランスとは固定された点ではなく、状況に応じて「切り離す」戦術と「重ね合わせる」戦術をダイナミックに使い分けながら、常に探し求め続ける流動的な状態なのです。
脚注
[1] Thornborrow, T., and Brown, A. D. (2009). “Being regimented”: Aspiration, discipline and identity work in the British Parachute Regiment. Organization Studies, 30(4), 355-376.
[2] Brown, A. D., and Toyoki, S. (2013). Identity work and legitimacy. Organization Studies, 34(7), 875-896.
[3] Beech, N., Gilmore, C., Cochrane, E., and Greig, G. (2012). Identity work as a response to tensions: A re-narration in opera rehearsals. Scandinavian Journal of Management, 28(1), 39-47.
[4] Beech, N., Gilmore, C., Hibbert, P., and Ybema, S. (2016). Identity-in-the-work and musicians’ struggles: The production of self-questioning identity work. Work, Employment and Society, 30(3), 506-522.
[5] Kreiner, G. E., Hollensbe, E. C., and Sheep, M. L. (2006). Where is the “me” among the “we”? Identity work and the search for optimal balance. Academy of Management Journal, 49(5), 1031-1057.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。