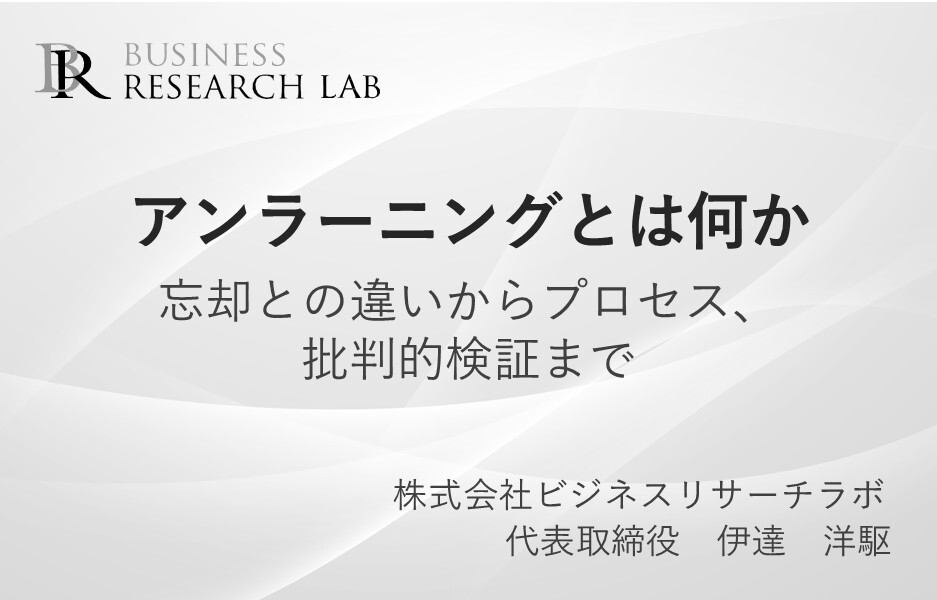2025年12月4日
アンラーニングとは何か:忘却との違いからプロセス、批判的検証まで
私たちは日々、新しい知識やスキルの習得に価値を置いています。学習は、成長や適応に不可欠な営みとして、個人のキャリアから組織戦略に至るまで奨励されます。しかし、変化の速い現代、新しい知識を積み重ねるだけで、本当に前に進めるのでしょうか。過去の成功体験や長年慣れ親しんだ「当たり前」が、気づかぬうちに新しい挑戦への足かせとなっているとしたら。そのとき求められるのは、新たな知識を「加える」ことではなく、古い知識を「手放す」ことなのかもしれません。
この「手放す」営みは「アンラーニング」と呼ばれ、近年、組織変革などの文脈で語られる機会が増えました。言葉の響きから「学習の反対」「忘れること」を想像するかもしれませんが、本質はより複雑です。アンラーニングとは、これまで有効だった思考の枠組みや行動様式を、意図的・意識的に脇に置く知的なプロセスです。それは記憶の消去ではなく、新しい可能性のために自らスペースを創り出す行為です。
本コラムでは、アンラーニングという概念の核心に迫るため、いくつかの学術的な探求の軌跡をたどります。アンラーニングとはそもそも何で、「忘却」とどう違うのか。どのようなプロセスで進むのか。そして、この概念自体は確かなものとして捉えられるのか。まずはこの現象そのものを多角的に解き明かします。
アンラーニングは旧ルーティンを意図的に捨てる営み
変化に対応するには新しい知識の学習が必要ですが、古くなったやり方をやめることは、それ以上に難しいかもしれません。この「やめる」という行為、すなわちアンラーニングは、物忘れとは異なる、明確な意図を持った営みとして捉えられます。
ある研究は、組織のアンラーニングを「古いルーティンを捨て去り、必要であれば新しいルーティンのために道を空けること」と述べます[1]。ルーティンとは個人の癖ではなく、複数のメンバーが関わり合いながら繰り返し行う、仕事上の手順やパターンです。ここで肝心なのは「捨てる(discard)」という言葉であり、人が辞めて知識が失われるような偶発的な「忘却(forgetting)」とは区別される、主体的な選択を意味します。
アンラーニングは「時代遅れの」「誤った」知識を捨てるといった価値判断を含めて語られることもあります。しかし、この考え方では、新しいやり方が必ずしも古いものより優れているとは限らず、移行期に一時的にパフォーマンスが低下しうる現実が見過ごされます。そのため、アンラーニングは価値的に中立な「捨てる」という行為と捉える方が、本質を正確に理解できます。
「ルーティンを捨てる」とは何を捨てることでしょうか。ルーティンには二つの側面があると考えられます。一つは「オステンシブ」な側面で、業務マニュアルや規則など、形で公式に示される「建前」のやり方です。もう一つは「パフォーマティブ」な側面で、現場の人々が実際に行っている「本音」の行動を指します。
アンラーニングが成立するには、両側面が組織から取り除かれる必要があります。例えば、新しい業務システムを導入しても(オステンシブな側面の変更)、現場が古いやり方を続ければ(パフォーマティブな側面が残存)、アンラーニングは完了しません。
この二側面は、組織の記憶の保管場所とも関連します。組織の記憶は「人」(経験や習慣)と「人以外」(規則やデータベースなど)に蓄えられます。オステンシブな側面は両方に記録されますが、パフォーマティブな側面は主に「人」の中に根付いています。だからこそアンラーニングは難しいのです。歴史の長い組織ほど、長年の経験が従業員に染みつき、変化への惰性が生まれやすくなります。
アンラーニングの起こり方には二つのパターンがあります。一つは、日常業務の改善が積み重なる中で起こる「連続的な変化」です。例えば、経費精算の方法を少し変える場合、マニュアルを更新し、新しい手順を練習する中で、古いやり方は徐々に使われなくなります。これは比較的スムーズに進みます。
もう一つは、技術革新や経営トップの交代といった大きな出来事をきっかけとする「断続的な変化」です。これはより戦略的で広範囲にわたる意図的なアンラーニングです。この種の変革では、過去の成功体験への固執や組織の惰性が大きな障壁となります。時には経営危機などが引き金となり、抜本的な見直しが進むこともあります。新しい知識の学習と古い知識のアンラーニングは、しばしば同時に進行しますが、その順序は一様ではないのです。
アンラーニングは気づき・手放し・再学習の循環で進む
アンラーニングが「意図的に古いルーティンを捨てる営み」であることは確認しましたが、その「意図的な手放し」は、どのようなプロセスで進むのでしょうか。ある研究は、このプロセスを一つの循環サイクルとして捉える枠組みを提示しています[2]。それによれば、アンラーニングは「気づき」「手放し」「再学習」という三段階を経て、個人、グループ、組織という異なるレベルをまたぎながら進んでいくとされます。
この考え方は、アンラーニングをより厳密に捉え直すことから始まります。データの消失などで知識が失われる偶発的な出来事と、時代遅れになった知識や価値観を意識的に見直し、使わないようにする「意図的アンラーニング」とを区別します。この意図的なプロセスは、古着を処分して新しい服のスペースを作る行為に喩えられます。肝心なのは、必ずしも完全に記憶を「消去」する必要はなく、意識的にアクセスしにくくする、要するに「使えない状態にする」ことでも実質的なアンラーニングは達成されるという点です。
この意図的アンラーニングは、三つのサブプロセスから構成されると考えられています。第一は「気づき」で、自分たちが拠って立つルールや前提が、もはや現状に適合していないと認識する段階です。第二は「手放し」で、誤りの原因となっている暗黙知を明らかにし、同じ過ちを繰り返さないように、そのやり方をやめる段階。第三は「再学習」で、新しいやり方を実践しながら、古い知識を意識的に脇に置いていく段階を指します。これら三つは必ずしも順番通りではなく、日々の仕事の中で同時並行的に展開します。
この内的なプロセスが円滑に進むには、それを支える組織的な文脈が求められます。この研究は三つの文脈的要素を挙げています。
一つ目は、個人レベルで作用する「レンズの点検」です。従業員一人ひとりが自身の物事の見方を点検し、「自分は間違っているかもしれない」という可能性を受け入れる機会を持つことです。
二つ目は、グループレベルで作用する「個人習慣の変容」です。チームなどの小集団で、具体的な行動や態度の変え方を練習し、互いに後押しする場を設けることを意味します。失敗が許される雰囲気や、円滑な情報共有がこれを支えます。
三つ目は、組織レベルで作用する「理解の定着」です。個人やグループで生まれた新しい理解を、組織全体の公式なルールや手順に組み込んでいくプロセスです。
これらの要素が組み合わさり、「アンラーニング・サイクル」という大きな循環が生まれます。このサイクルは、個人から組織へ向かう流れと、組織から個人へ向かう流れが同時に回ることで駆動します。例えば、個人の失敗への「気づき」が、組織全体のルーティンが時代遅れであることの発見につながることがあります。逆に、経営陣が新しい戦略方針を打ち出すことで、各部署や個人がやり方を見直さざるを得なくなることもあります。
アンラーニングと忘却を意図性と深さの二軸で体系化する
アンラーニングは意図的な営みであり、組織内を循環する動的なプロセスですが、「知識を手放す」という現象は多様な形で起こります。ここで一度、アンラーニングと「忘却」を含めた知識喪失のプロセス全体を整理するための一つの地図を広げてみましょう。
ある学術的なレビューは、組織におけるアンラーニングと忘却に関する過去の研究を整理し、知識が失われる現象を「意図性」と「知識喪失の深さ」という二つの軸で分類する枠組みを提示しました[3]。
横軸の「意図性」は、知識の喪失が意識的な選択の結果か(アンラーニング)、偶発的か(忘却)を示します。縦軸の「知識喪失の深さ」は、失われた知識の種類を示します。「浅い」知識とは、業務手順やマニュアルといった技術的な知識です。「深い」知識とは、組織文化や価値観、支配的な考え方といった、より根源的で変えにくいものを指します。
この二軸を組み合わせることで、知識喪失の現象を四つの象限に分類できます。
- 第一は「テクニカル・フォゲッティング」(非意図的・浅い)。たまにしか使わない業務手順を忘れるといったケースです。
- 第二は「テクニカル・アンラーニング」(意図的・浅い)。業務効率化のために古い作業手順を公式に廃止する行為などです。
- 第三は「アダプティブ・フォゲッティング」(非意図的・深い)。組織文化が徐々に風化したり、創業時の精神が失われたりする現象です。
- 第四は「アダプティブ・アンラーニング」(意図的・深い)。組織が根本的な変革のために、これまで拠り所としてきた価値観や成功体験を意識的に手放そうとする営みです。最も困難なアンラーニングと言えるでしょう。
この四象限の地図は、組織が直面する「知識を手放す」という課題がどの領域に位置するのかを特定するのに役立ちます。それが手順変更(テクニカル・アンラーニング)で済むのか、それとも価値観の見直し(アダプティブ・アンラーニング)まで踏み込む必要があるのかを判断する手助けになります。
このレビューでは、アンラーニングや忘却の引き金や結果についても整理されています。アンラーニングは既存のやり方の非効率性への気づきや市場環境の激変が引き金となります。忘却は人員流出や時間の経過で起こります。結果、アンラーニングは変革の土台となり革新につながる一方、有益な知識まで失う危険も伴います。興味深いことに、否定的と見なされがちな忘却にも、過去の失敗による士気低下を和らげるといった肯定的な側面があり得ると指摘されています。
アンラーニング概念は実証根拠に乏しい
ここまでアンラーニングを肯定的な視点で探求してきましたが、学問の世界では批判的な検証が求められます。ここで、アンラーニングという概念の土台を揺るがす、「そもそも経験的な根拠に基づいた、確かなものなのか」という問いを投げかけた研究に目を向けましょう[4]。
この批判的レビューは、経営学で広く受け入れられているアンラーニングの考え方が、(1)学習と独立した「知識の破棄」過程である、(2)学習に先行する、(3)後続の学習を助ける、(4)意図的に管理可能である、という四つの命題に基づくと整理しました。そして、これらの主張の科学的妥当性を徹底的に検証したのです。
アンラーニング概念がしばしば根拠とする心理学の文献を詳細に調査しました。その結果、心理学の専門用語の公式な索引に「アンラーニング」という言葉は見当たらず、記憶が失われる現象は「抑制」「干渉」「消去」といった既存の用語で十分に説明されることが判明しました。
さらに、経営学論文で根拠として引用された心理学論文を再読すると、その解釈に誤解があることも明らかになりました。その論文が扱っていたのはある学習が別の学習を妨げる現象であり、新しいことを学ぶ前に古い知識を「破棄」する必要があるとは主張していませんでした。要するに、経営学で語られるアンラーニング概念の心理学的な裏付けは、実は存在しなかったのです。
次に、検証の目は経営学・組織論の分野に向けられました。影響力の大きい論文を複数選び出し、そこで提示された事例やデータが本当に「知識の意図的な破棄」を証明しているかを精査しました。例えば、ある研究で「管理されたアンラーニング」の証拠とされたホテルの事例は、単に「新しいやり方に切り替えるべきだ」という主張が書かれているだけで、知識が破棄されたデータはありませんでした。また、別の逸話も、新しい証拠に基づいて考えを改めた「理論の変更」という、ごくありふれたプロセスを描写しているに過ぎませんでした。
このレビューは、経営学で「アンラーニング」と呼ばれている現象の多くが、実際には「これまでとは違う考え方を受け入れること(理論変化)」や「古いやり方をやめて新しいやり方を採用すること(実践の廃止)」を、別の言葉で言い換えているに過ぎないと結論づけています。日常会話で使われる比喩的な言葉が、いつの間にか科学的な実体があるかのように扱われてしまったのではないか、と指摘するのです。
もちろん、この研究はアンラーニングという現象の存在を完全に否定するものではありません。しかし、それを独立した科学的概念として主張するなら、より厳格な実証が求められると釘を刺しています。この批判的な視点は、私たちが流行の経営用語に飛びつく前に、その言葉が本当に何を指しているのかを冷静に見極めることの必要性を示唆していると言えるでしょう。
脚注
[1] Tsang, E. W. K., and Zahra, S. A. (2008). Organizational unlearning. Human Relations, 61(10), 1435-1462.
[2] Cegarra-Navarro, J. G., and Wensley, A. K. P. (2019). Promoting intentional unlearning through an unlearning cycle. Journal of Organizational Change Management, 32(1), 67-79.
[3] Klammer, A., and Gueldenberg, S. (2019). Unlearning and forgetting in organizations: A systematic review of literature. Journal of Knowledge Management, 23(5), 860-888.
[4] Howells, J., and Scholderer, J. (2016). Forget unlearning?: How an empirically unwarranted concept from psychology was imported to flourish in management and organisation studies. Management Learning, 47(4), 443-463.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。