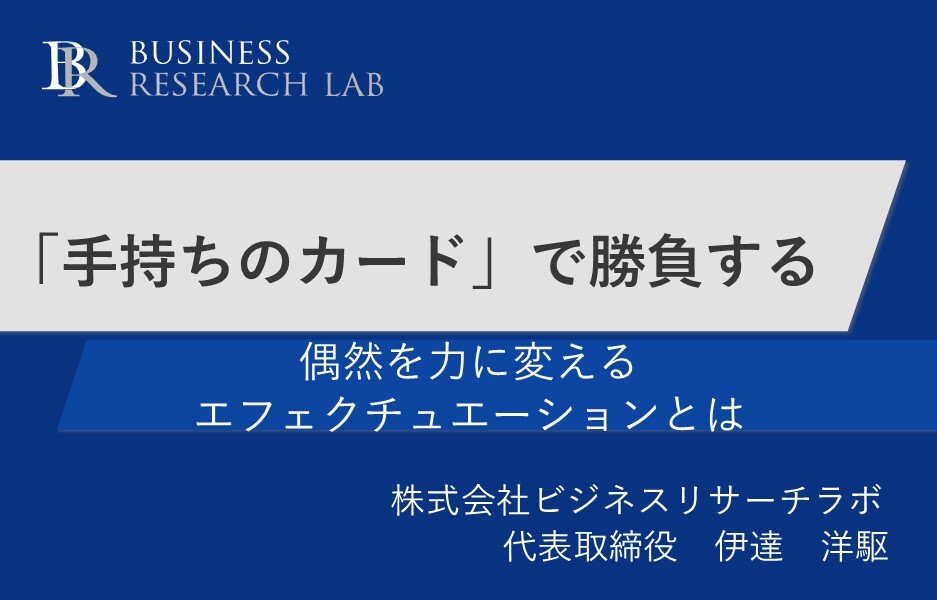2025年12月4日
「手持ちのカード」で勝負する:偶然を力に変えるエフェクチュエーションとは
私たちの多くは、ビジネスの世界で成功を収めるためには、未来を正確に予測し、それに基づいて綿密な計画を立てることが不可欠だと教わってきました。市場の動向を分析し、競合の動きを読み、緻密な事業計画書を作成する。ゴールから逆算して、最短距離でそこへ至る道筋を描く。この考え方は論理的で説得力があるように思えます。
しかし、現代のように変化が激しく、少し未来さえ見通すことが難しい時代において、そのアプローチは本当に万能なのでしょうか。計画通りに物事が進むことの方が稀で、予期せぬ出来事によって当初の前提が覆されてしまう経験は、誰にでもあるはずです。計画との乖離に悩み、予測の不確かさに翻弄される中で、立ち往生してしまうことがあります。
ここで、ある優れた起業家たちの思考法に目を向けてみましょう。彼ら彼女らは、必ずしも未来を正確に予測しようとはしません。予測できないことを前提とし、「今、自分の手元にあるもの」から出発します。周囲の人々を巻き込み、対話を重ねながら、進むべき道や創り出すべき価値を「共創」していきます。未来を予測するのではなく、自らの手でコントロールしていくという考え方は「エフェクチュエーション」と呼ばれています。
本コラムでは、エフェクチュエーションとは一体どのような考え方なのか、その基本的な概念を、いくつかの研究を手がかりに検討していきます。計画通りに進まない現実に直面し、新たな一歩を踏み出すためのヒントを探している方々にとって、本コラムが新しい視点を得る一助となれば幸いです。
熟達起業家が新市場を創造する変換過程を示す
最初に、熟達した起業家が、どのように新しい市場を生み出すのかを見ていくことにしましょう。彼ら彼女らの頭の中では、どのような思考が繰り広げられているのでしょうか。この問いに答えるため、熟達した起業家と、経営学を学んだMBA学生の思考プロセスを比較した、ある実験に光を当ててみます[1]。
この実験では、認知心理学の分野で用いられる「思考発話法」という手法が採用されました。参加者は、課題を解きながら頭に浮かんだことをすべて声に出して話します。研究者はその発話を録音し、分析することで、思考の道筋を客観的に捉えようと試みました。参加したのは、平均して7社の創業経験を持ち、少なくとも1社を株式公開に導いた経験のある熟達起業家27名と、ビジネススクールで学ぶMBA学生37名です。
彼ら彼女らに与えられたのは、架空の起業シミュレーション製品を題材とした市場創造の課題でした。製品の潜在的な顧客は誰か、競合はどこか、どのような価格で、どの販売チャネルを通じて市場に投入すべきか。意思決定の助けとなるように、市場規模や想定される顧客層の支払い意欲、販売チャネルごとの初期コストといった、現実的なデータも提供されました。
分析の結果、両者の間にはいくつかの違いが見られました。一つは、顧客や関係者との関わり方です。熟達起業家たちは、MBA学生に比べて、事業に関わる人々を単なる取引相手としてではなく、事業を共に創り上げていく「パートナー」として捉える発言を多くしていました。例えば、初期の顧客と密接な関係を築き、製品開発のプロセスに巻き込んでいくといったアイデアが、彼らの口から自然と語られたのです。
最も顕著だったのは、生み出された市場アイデアの数と多様性でした。MBA学生の多くは、課題で与えられた教育市場やゲーム市場といった「想定内の領域」で思考を巡らせる傾向がありました。一方で、熟達起業家たちは、その枠組みを飛び越えていきました。同じ製品から、ビジネスパーソンの能力を評価するためのツール、企業の研修プログラム、あるいは地域開発機関向けの教材といった、当初は全く想定されていなかった新しい市場の可能性を次々と見出していきました。
この違いはどこから生まれるのでしょうか。研究者たちは、熟達起業家が「変換(トランスフォーメーション)」と名付けられた、特有の思考操作を駆使している点に着目しました。彼ら彼女らは、与えられた製品や市場の定義を固定されたものとは考えません。粘土をこねるように、その機能の一部を削ぎ落としたり、新しい要素を付け加えたり、あるいは全く異なる文脈に当てはめてみたりすることで、その価値を柔軟に作り替えていきました。
例えば、教育ツールという元の用途から離れ、人材の「評価・選抜ツール」へとその使い道を変える発想。これは、既存のものを別の用途へ転用する「逸用」と呼ばれる変換です。また、起業家を目指す人々ではなく、「起業家ごっこを体験して楽しみたい人々」を新たなターゲットとして見立てる。これは、対象の見方を反転させる「反転」という変換の一例です。
このような思考プロセスは、既存の選択肢の中から最も良いものを選び出す「探索・選択」という伝統的なモデルとは根本的に異なります。熟達起業家にとって、市場とは、どこかに客観的に存在し「発見」されるものではありません。それは、手元の資源と、関わり合う人々との相互作用を通じて、自らの手で「創り出される」ものです。「変換」という創造的なプロセスが、予測不能な世界で新しい価値を生み出す原動力となっているのかもしれません。
未来を予測せず共創的に戦略を構築する方法
熟達した起業家が、固定された市場の定義に縛られず、関係者と共に新しい価値を「創り出す」ように、未来そのものを予測の対象としてではなく、自らの働きかけによって形づくっていく対象として捉える考え方は、個人の思考法に留まらず、組織全体の戦略立案にも応用することができます。これまで企業の戦略論は、未来をいかに正確に予測し、それにどう適応していくかを主な論点の一つとしてきました。しかし、予測に頼らない新しい戦略のあり方とは、どのようなものなのでしょうか。
この問いを探求するにあたり、まず「予測」と「コントロール」という二つの概念を分けて考えるという、視点の転換が求められます[2]。コントロールとは、自らの働きかけによって、環境や将来の結果を意図した方向へ形づくっていくことを指します。私たちはこれまで、「未来を予測できれば、それをコントロールできる」と考えがちでした。
しかし、予測が原理的に不可能な状況、例えば、製品や市場の枠組み自体がまだ存在しないような場面では、この前提は成り立ちません。そのような状況では、予測に頼るのではなく、直接的に行動し、他者との関係を編み上げていくことによって、未来を形づくることができるのです。
この「予測」の度合い(高いか低いか)と、「コントロール」の可能性(高いか低いか)を二つの軸として組み合わせることで、戦略のアプローチを四つのタイプに整理することができます。
一つ目は、未来の予測は可能だが、自社で環境をコントロールするのは難しいと考える「計画戦略」です。ここでは、緻密な分析に基づいて最適な市場でのポジションを確保することが目標となります。二つ目は、予測もコントロールも難しいと考える「適応戦略」です。ここでは、計画を短く持ち、変化に対して素早く学習し対応することが求められます。三つ目は、予測もコントロールも可能だと考える「ビジョナリー戦略」です。ここでは、明確な未来像を掲げ、それを実現するために資源を集中投下します。
四つ目が、未来の予測は不可能だが、コントロールは可能だと考える「トランスフォーマティブ戦略」です。これこそが、エフェクチュエーションの考え方を組織戦略に応用したものです。このアプローチにおいては、未来の市場や環境はまだどこにも存在しないものと捉え、今ある手段から出発し、他者と目標を共に創り上げながら、市場を構築していくことを目指します。
トランスフォーマティブ戦略の中核をなすエフェクチュエーションのプロセスは、二重の循環として描くことができます。一つは「資源の拡張サイクル」です。これは、起業家が持つ「自分は誰か(アイデンティティ)」「何を知っているか(知識)」「誰を知っているか(人脈)」という手持ちの資源から始まります。これらを元に行動を起こし、他者から具体的な協力の約束、すなわちコミットメントを引き出すことで、利用可能な資源が雪だるま式に増えていきます。
もう一つは「目標制約の収束サイクル」です。多くの人々がプロジェクトに関与するようになると、それぞれの利害や考えを調整する必要が生じます。このプロセスを通じて、当初は曖昧だった事業の目標が、徐々に具体的で明確な形へと定まっていきます。目標は最初から存在するのではなく、多くの人々との相互作用の結果として生まれてくるのです。
このプロセスを動かす実践原理として、「手段駆動」「許容損失」「偶発の活用」の三つが挙げられます。あらかじめ設定された目標から逆算するのではなく、手持ちの手段で何ができるかを考える。期待されるリターンを計算して投資額を決めるのではなく、「この範囲内なら失っても構わない」と許容できる損失額で小さく始める。そして、計画通りに進まないことを失敗と捉えるのではなく、予期せぬ出来事を新しい機会として積極的に活用する。
このアプローチは、戦略を「未来を当てる」ゲームから「未来を創る」ゲームへと転換させます。予測にかかるコストを減らし、大きな失敗のリスクを抑えながら、より創造的な結果を生み出すための、一つの合理的な方法といえるでしょう。
偶発を活かし市場や目標を共創する理論
ここまで、熟達起業家の思考法や、予測に頼らない戦略構築のアプローチを見てきました。これらの議論の根底には、エフェクチュエーションという一貫した考え方が流れています。ここでは、その理論をもう少し体系的に掘り下げ、従来のビジネスの常識とされている考え方と、どこがどのように違うのかを明らかにしていきたいと思います[3]。
ビジネスにおける意思決定の論理(ロジック)は、大きく二つの種類に大別できるとされています。一つは「因果(Causation)ロジック」です。これは、私たちが学校やビジネスの世界で学んできた、伝統的な経営学が前提とする考え方です。まず達成すべき目標を明確に設定し、その目標を達成するために最も効率的で最適な手段を選択するという、ゴールから手段へと向かう思考の流れをたどります。この背景には、「未来を予測できるのであれば、望ましい結果をコントロールできる」という世界観があります。
これに対して、もう一つの論理が「効果創発(Effectuation)ロジック」です。これが、エフェクチュエーションが依拠する考え方です。こちらでは、特定の目標をあらかじめ固定しません。まず、自分の手元にある利用可能な手段が何かを確認することから始めます。その手段を使って何ができるかを考え、行動を起こします。その過程で出会う人々を巻き込みながら、目標を一緒に創り上げていくという、手段からゴールへと向かう思考の流れをたどります。この背景には、「望ましい結果をコントロールできるのであれば、未来を予測する必要はない」という、因果ロジックとは異なる世界観が存在します。
この二つのロジックの違いを、架空のカレー店「Curry-in-a-Hurry」の例え話で考えてみましょう。もしあなたが因果ロジックに従うなら、まず市場調査を行い、どの地域にどのようなカレーの需要があるかを予測します。そして、その分析結果に基づいて、最も収益が見込める立地を選び、ターゲット顧客に合わせたメニューを開発し、満を持して店を開店するでしょう。
一方、もしあなたが効果創発ロジックに従うなら、違うアプローチを取るかもしれません。まず、自分が得意なカレーを作り、友人や近所の人々に試食してもらうことから始めます。もし「美味しい」と言ってくれる人がいれば、その人たちの意見を聞きながらレシピを改良したり、口コミで評判を広げてもらったりするでしょう。そのうち、誰かが「会社のイベントでケータリングしてほしい」と頼んでくるかもしれません。あるいは、別の誰かが「そのレシピを本にしてはどうか」と提案してくるかもしれません。
こうして、当初は想像もしていなかったような、ケータリングサービスや料理教室、書籍の出版といった事業へと、自然な形で展開していく可能性があります。
効果創発のプロセスは、一つの循環的なサイクルとして描かれます。その出発点は、常に「自分は誰か」「何を知っているか」「誰を知っているか」という三つのカテゴリーに分類される手段です。この手段を元に行動を起こし、他者からの「事前確約(プレコミットメント)」、単なる口約束ではない、具体的な協力の約束を取り付けます。この事前確約が、次の行動のための新たな手段や、あるいは目標を形づくる制約となります。
このサイクルを回していく中で、予期せぬ出来事、すなわち「偶発」が起これば、それを計画からの逸脱として排除するのではなく、新しい方向性を生み出すためのきっかけとして活用します。
このサイクルを支えるのが、「手段起点」「許容損失」「事前確約とパートナーシップ」「偶発の活用」という四つの実践原理です。因果ロジックと効果創発ロジックは、どちらか一方が絶対的に優れているというものではありません。両者は、状況に応じて使い分けるべきものです。市場が安定し、未来がある程度予測可能な状況では、因果ロジックが効率的でしょう。しかし、未来が不確実で、目標さえも曖昧な創業期や新規事業開発のような場面では、効果創発ロジックが、道を切り拓くための指針となります。
起業研究を越えて多領域へ拡張する理論へ
エフェクチュエーションは、もともと優れた起業家たちがどのように意思決定を行っているのかを説明するために生まれた理論でした。しかし、その根底にある思想は、起業という特殊な文脈だけに留まるものではありません。予測が困難な状況にどう立ち向かい、他者と協力しながら新しい価値をいかに創り出すかという問いは、現代を生きる私たちにとって一般的な課題です。近年、この理論はどのように発展し、他の分野へとその応用範囲を広げているのでしょうか。
エフェクチュエーションに関する研究は、二十年以上の時間をかけて多くの知見を積み重ね、今や一つの確立された学術分野として成熟しつつあります[4]。当初は起業家個人の思考法に焦点が当てられていましたが、その射程は次第に広がり、組織レベルの戦略論、イノベーションのプロセス、さらには災害からの復興といった、多様なテーマを分析するための視座として用いられるようになっています。
この理論に関する理解を深めるためには、孤立した概念として捉えるのではなく、隣接する他の考え方との関係性の中で位置づけてみることが有効です。例えば、「ブリコラージュ」という概念があります。これは、「ありあわせの道具や材料で、何とかやりくりして新しいものを作り出す」という考え方で、手元にある資源を独創的に組み合わせて問題解決を図る点で、エフェクチュエーションの「手段起点」の発想と通じ合っています。
また、近年広く知られるようになった「リーンスタートアップ」という手法も、エフェクチュエーションと響き合う部分を多く持っています。リーンスタートアップは、最小限の機能を持つ製品を素早く市場に投入し、顧客からのフィードバックを元に仮説検証を繰り返しながら、製品と事業を改善していくアプローチです。大きな賭けに出るのではなく、許容できる範囲で小さな実験を重ねる「許容損失」の考え方や、顧客との相互作用を重視する姿勢と共通しています。
「デザイン思考」も関連の深いアプローチです。これは、製品やサービスの利用者への共感から出発し、試作品を作り、利用者の反応を見ながら解決策を練り上げていく手法です。これもまた、最初から完璧な答えを目指すのではなく、関係者との共創を通じてゴールを形づくっていくエフェクチュエーションのプロセスと、その精神を共有しています。
近年の研究では、これらの多様なアプローチを一つの大きな枠組みの中で統合的に捉えようとする試みが進んでいます。「どのような状況(文脈)において」「どのような思考法や実践(ヒューリスティクス)が用いられ」「それが、イノベーションや企業の成長、あるいは存続といった、どのような結果につながるのか」という関係性を解き明かそうとしているのです。
例えば、不確実性の高い状況では、予測に頼るのではなく、コントロールを志向するエフェクチュエーション的なアプローチが、イノベーションの成果を高める、といった関係性が明らかにされつつあります。
これらの動向は、エフェクチュエーションが起業家の特殊なスキルセットを説明する理論ではなく、不確実な世界を航海するための、より一般的な知恵へと進展していることを示しています。予測不能な未来に直面したとき、私たちはただ計画を精緻化するだけでなく、手元にあるものから出発し、他者と共に新しい現実を創り上げていくという、もう一つの力強い選択肢を持っている。この理論の広がりは、そのことを私たちに教えてくれます。
脚注
[1] Dew, N., Read, S., Sarasvathy, S. D., and Wiltbank, R. (2011). On the entrepreneurial genesis of new markets: Effectual transformations versus causal search and selection. Journal of Evolutionary Economics, 21, 231-253.
[2] Wiltbank, R., Dew, N., Read, S., and Sarasvathy, S. D. (2006). What to do next? The case for non-predictive strategy. Strategic Management Journal, 27(10), 981-998.
[3] Sarasvathy, S. D. (2001). Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, 26(2), 243-263.
[4] Alsos, G. A., Clausen, T. H., Mauer, R., Read, S., and Sarasvathy, S. D. (2020). Effectual exchange: From entrepreneurship to the disciplines and beyond. Small Business Economics, 54, 605-619.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。