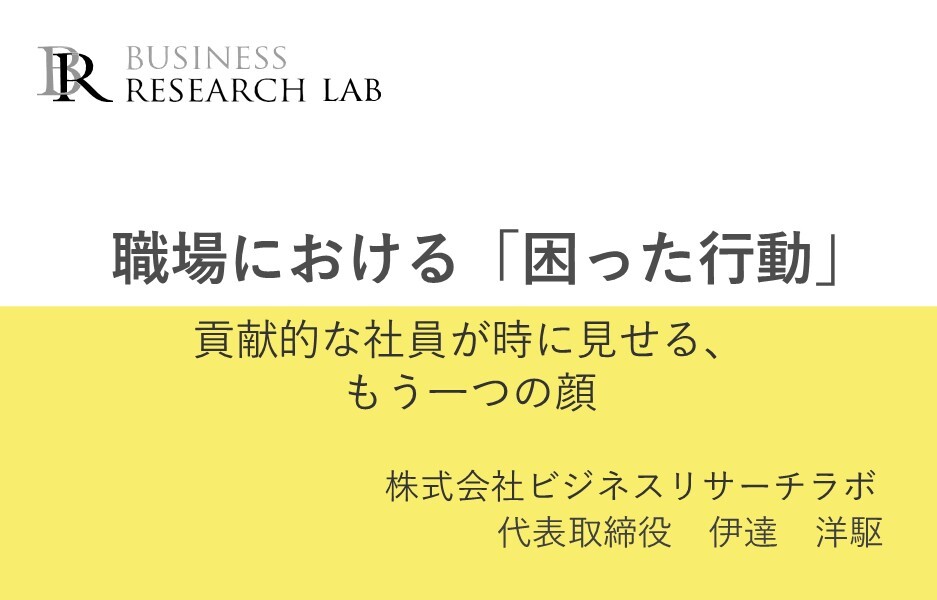2025年12月3日
職場における「困った行動」:貢献的な社員が時に見せる、もう一つの顔
職場を見渡してみると、私たちの周りには実に様々な人がいます。組織のために率先して汗を流す人がいる一方で、残念ながら、組織の生産性を損なうような行動をとる人がいることもあります。例えば、業務時間中に頻繁に私的なウェブサイトを閲覧する、備品を断りなく持ち帰ってしまう、同僚の悪口を広める、あるいは意図的に作業の手を抜く、といった行動です。こうした行動は、組織の業績に直接的な損害をもたらすだけでなく、職場の士気や人間関係をも蝕んでいく厄介な問題と言えます。
私たちは直感的に、このような「組織にとって望ましくない行動」は、献身的な態度や協力的な姿勢といった「望ましい行動」の正反対に位置するものだと考えます。良い行動をしない人が悪い行動をするのであり、両者は一つの物差しの両端にあるという見方です。しかし、この理解は本当に正しいのでしょうか。人間の行動は、それほど単純に割り切れるものなのでしょうか。良いことをする人は、決して悪いことをしないのでしょうか。
本コラムでは、学術的に「非生産的職務行動」と呼ばれるこれらの行動について、その概念と測定をめぐる研究を紐解いていきます。この行動は、貢献的な行動とどのような関係にあるのか。どのような状況で生じやすいのか。そもそも、どのようにすれば正確に捉えることができるのか。これらの問いを探求することを通じて、職場で起こる「困った行動」の複雑な本質に迫りたいと思います。
非生産的職務行動は組織市民行動と独立する
組織のために進んで貢献する「良い行動」と、組織に害をなす「悪い行動」。この二つは、光と影のように、互いに裏表の関係にあると考えるのが自然かもしれません。一方が増えれば、もう一方は減る。こうした素朴な見方が正しいのかどうかを、膨大なデータを集約することによって検証した研究があります[1]。
この研究は、過去に行われた38件の研究、総勢1万6千人を超える働く人々を対象としたデータを統計的に統合する「メタ分析」という手法を用いています。ここでいう「良い行動」とは、契約上の義務ではないにもかかわらず、組織の機能を円滑にするために自発的に行われる「組織市民行動」を指します。例えば、困っている同僚を助けたり、組織の発展のために建設的な提案をしたりする行動がこれにあたります。対する「悪い行動」が、組織やそのメンバーの正当な利益を意図的に損なう「非生産的職務行動」です。
分析の結果、これら二つの行動の間には、弱い負の関係しか見出されませんでした。組織市民行動をとる人が非生産的職務行動を全くしないわけではなく、その逆もまた然り、という複雑な実態が浮かび上がってきました。行動の矛先を「同僚」や「組織」といった対象別に分けて分析しても、この基本的な関係性は大きく変わりませんでした。
さらに、これらの行動がどのような心理的要因と結びついているのかも調べられました。例えば、仕事に対する満足度や、組織に対する公正感、個人の誠実さといった要因は、組織市民行動を促し、非生産的職務行動を抑制するという関係性を持つ部分が見られました。しかし、すべての要因がそうではありませんでした。特に、ネガティブな感情を抱きやすいという個人の特性は、非生産的職務行動と強く結びついていましたが、組織市民行動との結びつきは非常に弱いものでした。
この研究からは、もう一つ注目すべき点が報告されています。それは、誰が行動を評価するかによって、二つの行動の関係性の見え方が変わるという事実です。本人が自己評価したデータでは上記のような弱い関係が見られるのに対し、上司が部下の行動を評価したデータでは、両者の負の関係が強く観測されました。これは、上司が個々の行動を細かく観察しているというよりも、「あの部下は全般的に良い働きをする」あるいは「あまり良くない」といった包括的な印象に基づいて評価を下している可能性を示唆しています。
これらの結果を総合すると、組織市民行動と非生産的職務行動は、一本の物差しの両極に位置する単一の概念と見なすのは適切ではない、という結論が導かれます。両者は関連しつつも、それぞれが独立した側面を持つ、別個の現象として捉えるべきだと言えます。良い行動を増やすためのアプローチと、悪い行動を減らすためのアプローチは、必ずしも同じではないのかもしれません。
非生産的職務行動は組織市民行動と同時に高まることがある
先ほどは、組織にとっての「良い行動」と「悪い行動」が、単純な裏表の関係ではなく、それぞれ独立した現象である可能性を見てきました。この点をさらに推し進めると、ある特定の状況下では、同じ一人の従業員が良い行動と悪い行動を同時に増やす、という事態も起こり得るのではないでしょうか。この直観に反するような問いに、測定方法の観点から切り込んだ研究が存在します[2]。
この研究の出発点は、従来の「良い行動」、すなわち組織市民行動を測定する尺度に対する疑問でした。これまでの尺度には、「些細なことで不平を言わない」「組織の決定に文句を言わない」といった質問項目が含まれていることがありました。しかし、よく考えてみると、これらは貢献的な行動の存在を尋ねているというよりも、非生産的職務行動という「悪い行動」の不在を確かめているに過ぎません。このような項目が混入していると、測定上、二つの行動が強い負の関係にあるように見えてしまうのは当然です。
そこで研究者たちは、こうした問題のある項目を一切排除し、「同僚の仕事を手伝った」「業務改善の提案をした」といった純粋な貢献行動の実行「頻度」だけを尋ねる、新しい組織市民行動の測定尺度を開発しました。この新しい尺度を用いて、五つの異なる組織で働く従業員とその同僚からデータを集め、非生産的職務行動との関係を調べ直しました。
その結果は、これまでの常識を覆すものでした。新しい尺度で測定した場合、組織市民行動と非生産的職務行動の間には、弱いながらも統計的に意味のある「正の関係」が確認されたのです。さらに、職場の業務プロセスが円滑に進まない「組織的制約」や、職場での「対人葛藤」といったストレッサーが多い状況ほど、従業員は組織市民行動と非生産的職務行動の両方を増やすという関連も見出されました。
この結果が描き出すのは、現実的な職場の姿です。例えば、人手不足や設備の不備といった障害のために仕事がうまく進まない状況を想像してみてください。このような時、責任感の強い従業員は、その穴を埋めるために同僚の仕事まで引き受け、身を粉にして働くかもしれません(組織市民行動の増加)。
しかし、その一方で、そのような状況を生み出している組織への不満や、過剰な負担からくるストレスによって、会社の悪口を言ったり、作業効率を意図的に落としたりすることもあるでしょう(非生産的職務行動の増加)。困難な状況が、一人の人間の中に「助ける行動」と「害する行動」を同時に生み出してしまうのです。
この発見を確かなものにするため、より大規模なサンプルで追試が行われました。そこでは、新しく開発された尺度と、問題のある従来の尺度とが直接比較されました。結果、従来の尺度を用いると非生産的職務行動との間には強い負の関係が見られたのに対し、新しい尺度では再び正の関係が観測されました。職場の障害といったストレッサーは、新しい尺度で測定した組織市民行動を増やす一方で、従来の尺度で測定した組織市民行動はむしろ減らすという、逆のパターンを示したのです。
非生産的職務行動は自己報告が他者報告より高く出やすい
社会的に望ましくないとされる行動について尋ねられたとき、人はありのままを正直に話すものでしょうか。特に、非生産的職務行動のようなデリケートなテーマでは、自分をよく見せようとして、本当のことよりも少なく申告してしまうのではないでしょうか。そのため、研究の世界では、本人による自己報告データの信頼性が疑問視されてきました。では、上司や同僚といった他者からの報告と比べることで、何が見えてくるのでしょうか。この問いに、過去40の研究を統合したメタ分析が光を当てています[3]。
この研究では、非生産的職務行動に関する自己報告と他者報告がどの程度一致するのか、そして、それぞれが個人の性格や仕事への満足度といった他の変数とどのように関連するのかが検証されました。
初めに、自己報告と他者報告の一致度についてです。分析の結果、両者の一致度は中程度であることが分かりました。これは、両者が全く無関係ではないものの、完全に同じものを捉えているわけでもないということを意味します。一致度は行動の種類によって異なりました。同僚への暴言や嫌がらせといった、他者の目につきやすい「対人向け」の行動は、自己報告と他者報告が比較的よく一致していました。
それに対して、意図的な手抜きや備品の窃盗といった、観察されにくい「組織向け」の行動では、一致度が低くなる傾向がありました。また、回答の匿名性がしっかりと確保されている調査ほど、両者の一致度が高まることも確認されました。
最も意外な発見は、報告される行動の「量」に関するものでした。平均して、自己報告の方が他者報告よりも「多くの」非生産的職務行動を報告していたのです。自分を良く見せたいという動機が働くなら、結果は逆になるはずです。このことは、他者、特に上司は、従業員が行っている非生産的職務行動のすべてを把握できているわけではないという現実を浮き彫りにします。特に、他者から見えにくい組織向けの行動において、自己報告と他者報告の乖離は大きくなっていました。
自己報告と他者報告では、非生産的職務行動を生み出す要因の見え方も異なるのでしょうか。この点について分析したところ、個人の性格特性、組織の公正さ、仕事への満足度といった様々な要因との関連パターンは、自己報告と他者報告で全体として非常に似通っていることが分かりました。この結果は、これまで自己報告データに基づいて積み上げられてきた研究知見が、概ね妥当なものであったことを裏付けています。
自己報告の価値が再確認された一方で、他者報告が全く無意味というわけではありません。分析によると、自己報告で得られる情報に加えて他者からの報告を用いると、特に対人向けの行動領域において、その行動を予測する精度がわずかながら向上することが示されました。
この研究が私たちに教えるのは、非生産的職務行動を測定する上で、自己報告は決して信頼性の低い情報源ではなく、むしろ他者には観察できない行動を捉えるための手段であるということです。他者からの報告は、公の場における対人行動を把握するのに優れています。どちらか一方が優れているというよりも、両者は異なる側面を照らし出しており、組み合わせることで、対象者の行動をより立体的に理解できると言えます。
非生産的職務行動には共通因子と標的別の束がある
「非生産的職務行動」という一つの言葉で括られていますが、その中身は多彩です。会社の備品を盗む行為から、同僚の陰口を叩く行為、わざと仕事を遅らせる行為まで、その種類は多岐にわたります。これらの異なる行動は、たまたま同じ職場で起きるだけで、互いに無関係なのでしょうか。それとも、そこには何らかの秩序や構造が隠されているのでしょうか。この行動の内部構造を、二つの異なる角度から解き明かそうとした研究があります[4]。
この研究では、一つ目のアプローチとして、働く人々自身に、66項目に及ぶ様々な非生産的職務行動について「もし状況が許すならば、その行動をとる可能性はどのくらいあるか」を尋ねました。これらの自己評定データを用いて、どの行動とどの行動が一緒になされやすいのか、その共変関係を分析しました。
その結果、調査対象となった11種類の非生産的職務行動カテゴリー(例えば「盗難」「財産の破壊」「不適切な言動」など)のすべてが、互いに正の相関関係にあることが分かりました。これは、ある一つの種類の逸脱行動に手を染めやすい人は、他の種類の逸脱行動にも手を染めやすいという強い傾向の存在を物語っています。個人の行動傾向のレベルで見ると、様々な非生産的職務行動を貫く、一本の太い共通の軸、「一般非生産的職務行動因子」とでも呼べるものが存在するのです。
しかし、この研究はここで終わりません。二つ目のアプローチとして、同じ対象者に、今度は視点を変えて、11種類の行動カテゴリーの全てのペアについて「これらの行動が、同じ一人の人物によって同時に行われることは、どのくらい起こりやすいと思いますか」と、共起のイメージを尋ねました。人々の頭の中にある「行動のまとまり」に関する地図を描き出そうとしたのです。
このデータを「多次元尺度法」という手法で分析すると、先ほどの自己評定データとは少し異なる、より複雑な構造が見えてきました。人々の認識の中では、非生産的職務行動は二つの軸によって整理されていました。
一つ目の軸は、その行動の矛先が「人」に向かうか「組織」に向かうか、という「対人―組織」の軸でした。例えば、不適切な身体的行為や言動は「対人」側に、欠勤や会社の資源の不正使用は「組織」側に位置づけられました。
二つ目の軸は、その行動が「仕事の遂行そのもの」に直接的に関わるかどうか、という「タスク関連性」の軸でした。例えば、質の低い仕事をする、欠勤する、といった行動はタスクに直結する側に、一方で、盗難や財産破壊といった行動は、タスクの遂行とはやや独立して起こりうる側に位置づけられました。
この二つのアプローチの結果を合わせると、非生産的職務行動の二重構造が浮かび上がります。個人の行動レベルでは、様々な逸脱を根底でつなぐ一般的傾向が存在します。
しかし、それらの行動がどのようなまとまりとして認識され、発生しやすいかを考える際には、「誰に対して(対人―組織)」「仕事とどう関わるか(タスク関連性)」という二つの軸で区切られる「行動の束」で捉えることが有効です。例えば、「組織に向けられた、タスクに直結する行動の束」(例:欠勤、手抜き、品質低下)や、「人に向けられた、タスクから独立した行動の束」(例:ハラスメント、暴言)といったまとまりが見えてくるのです。
脚注
[1] Dalal, R. S. (2005). A meta-analysis of the relationship between organizational citizenship behavior and counterproductive work behavior. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1241-1255.
[2] Fox, S., Spector, P. E., Goh, A., Bruursema, K., and Kessler, S. R. (2012). The deviant citizen: Measuring potential positive relations between counterproductive work behaviour and organizational citizenship behaviour. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 85, 199-220.
[3] Berry, C. M., Carpenter, N. C., and Barratt, C. L. (2012). Do other-reports of counterproductive work behavior provide an incremental contribution over self-reports? A meta-analytic comparison. Journal of Applied Psychology, 97(3), 613-636.
[4] Gruys, M. L., and Sackett, P. R. (2003). Investigating the dimensionality of counterproductive work behavior. International Journal of Selection and Assessment, 11(1), 30-42.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。