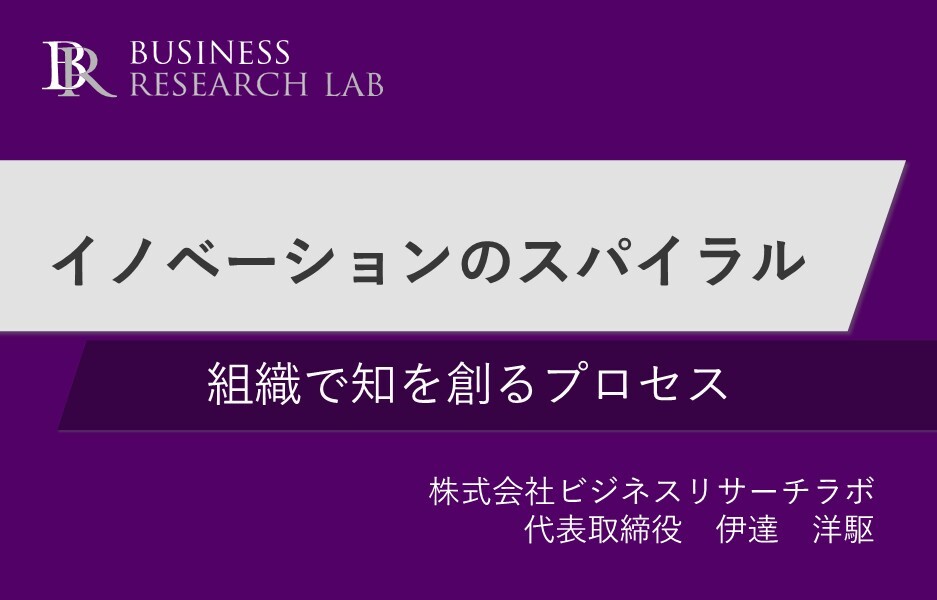2025年12月2日
イノベーションのスパイラル:組織で知を創るプロセス
私たちの周りでは、日々新しい製品やサービスが生まれ、世の中を豊かにしています。こうしたイノベーションは、一体どこからやってくるのでしょうか。一人の天才的な発明家が、ある日突然、画期的なアイデアを思いつく。そんなイメージを抱いている人も少なくないかもしれません。しかし、現代の組織で生まれるイノベーションの多くは、個人のひらめきだけに依存するものではありません。それは、組織の中で、人々が互いに関わり合い、知識を交換し、試行錯誤を繰り返す中で育まれていくプロセスです。
本コラムでは、組織の中で新しい知識やアイデアが生まれ、それがやがてイノベーションとして結実していくメカニズムについて光を当てていきます。そもそも組織の中で「知識」はどのようにつくられていくのか。その知識を具体的な製品開発へとつなげる際、どのような進め方が有効なのか。そして、人々の創造性を引き出すためには、どのような職場環境が求められるのか。これらの問いを、研究知見を手がかりに検討していきます。
知識は暗黙知と形式知の対話で組織的に創造される
組織の中で新しいアイデアや価値が生み出される過程を考えるとき、私たちは「知識」そのものについて理解を深める必要があります。知識には、大きく分けて二つの種類があります。
一つは、言葉や数式、図などを用いて客観的に表現できる「形式知」です。マニュアルや設計図、報告書といった形で共有される知識がこれにあたります。もう一つは、個人の経験や勘、身体的な技能といった、言葉にするのが難しい「暗黙知」です。例えば、熟練の職人が持つ「コツ」や、優れた営業担当者が顧客の心の機微を察知する感覚などがそれに当たります。
組織における知識創造とは、この性質の異なる二つの知識が、相互に変換され、影響を及ぼし合うダイナミックな対話のプロセスであると捉えることができます。このプロセスは、四つの異なる変換モードを経由して、螺旋を描くように進んでいきます[1]。
最初のモードは「社会化」と呼ばれるもので、暗黙知から暗黙知への変換です。これは、弟子が師匠の技を見て学ぶように、あるいは新人が現場での実務トレーニング(OJT)を通じて先輩の仕事の進め方を体で覚えるように、共通の経験や観察、模倣を通じて、言葉にならないコツやノウハウが人から人へと伝わっていく段階です。ここでは、同じ「場」で時間を共にし、空気を共有することが、知識の移転を円滑にします。
次に訪れるのが「表出化」のモードで、これは暗黙知を形式知へと変換する試みです。個人が体得した暗黙知を、何とかして言葉や概念、図やモデルといった形に表現しようとするプロセスです。
このとき、比喩(メタファー)が大きな助けとなります。直接的な言葉では表現しきれない複雑な感覚や直感を、比喩を用いることで、その本質的な特徴を捉え、他者と共有可能なイメージの入り口を開きます。比喩による直感的な結びつきは、論理的な類推(アナロジー)によって整理され、最終的には矛盾のない具体的な「モデル」、例えば新しい製品のコンセプトや仕様書といった、共有可能な形式知へと結晶化していきます。
三つ目のモードは「結合」です。これは、形式知と形式知を組み合わせて、より体系的で複雑な新しい形式知を生み出すプロセスです。会議で様々な部署から持ち寄られたデータを統合して新たな市場分析レポートを作成したり、既存の技術文書を組み合わせて新しいシステムの設計図を完成させたりする活動がこれに該当します。ここでは、既存の知識を再分類したり、異なる文脈に置いたりすることで、新たな発見が生まれます。
最後のモードが「内面化」で、形式知から暗黙知への変換を指します。文書化された計画やマニュアルを、人々が実践を通じて自分のものにしていくプロセスです。例えば、新しい業務マニュアルを読み、実際にその業務を繰り返し行うことで、最初は意識的に行っていた手順が次第に無意識にできるようになり、自分なりの工夫や応用が利くようになります。これは、形式知が個人の身体的な経験と結びつき、再びその人固有の暗黙知として定着していく過程と言えます。
これらの四つのモードは、一度きりで完結するわけではありません。社会化、表出化、結合、内面化というサイクルが繰り返されることで、知識は個人からグループへ、そして組織全体へと、螺旋階段を駆け上がるように質を高めながら広がっていきます。
この知識創造のスパイラルを駆動するためには、個々人の内面的な動機づけも欠かせません。組織や個人が何を成し遂げたいのかという「意図」は、膨大な情報の中から何に光を当てるべきかを定め、知識創造の方向性を与えます。また、従業員一人ひとりが自律的に行動できる「自律性」は、予期せぬ発見や学びの機会を増やします。外部環境の変化や内部での意見の対立といった「揺らぎ」は、既存の考え方を見直すきっかけとなり、新たな対話を生み出します。
不確実な環境では反復と実験が新製品開発を速める
組織の中で生み出された新しい知識は、新製品やサービスの開発という形で具現化されます。競争が激しい現代の市場において、開発の「速さ」は企業の生命線を握ることも少なくありません。この開発スピードを上げるための方法として、大きく二つの対照的なモデルが考えられてきました。一つは「圧縮モデル」、もう一つは「体験モデル」です。
「圧縮モデル」は、製品開発をあらかじめ計画可能な一連の工程の連なりと見なす考え方です。リレー走のように、設計、試作、製造といった各工程をできるだけ効率化し、また、工程同士が重なり合う部分を増やす(並行化する)ことで、全体の時間を短縮しようとします。
このモデルでは、入念な事前計画を立てること、部品などを供給するサプライヤーに早い段階から開発に参加してもらうこと、コンピュータ支援設計(CAD)ツールを駆使して設計作業を迅速化することなどが、速さを生み出すための手段とされます。このアプローチがうまく機能するのは、市場のニーズや必要な技術がある程度予測可能で、開発プロセスが見通しやすい状況です。
一方、「体験モデル」は、製品開発を、先が見えない霧の中を手探りで進むようなプロセスと捉えます。特に新しい市場や未知の技術に取り組む場合、最初に完璧な計画を立てることは不可能です。このモデルでは、むしろ不確実であることを前提とし、短いサイクルでの試作とテストを何度も繰り返す(反復する)ことで、実践の中から正解を学んでいこうとします。頻繁に進捗を確認し、計画を柔軟に見直すための短い間隔での節目(マイルストーン)の設定や、チームをまとめ、迅速な意思決定をくだすプロジェクトリーダーの存在が、このアプローチの鍵となります。
これら二つのモデルのどちらが、あるいはどのような要素が、実際に製品開発の短縮に結びつくのかを明らかにするため、ある調査が行われました[2]。この調査では、欧米およびアジアのコンピュータ関連企業36社が開発した、パソコン、プリンターなどの周辺機器、そしてより大型のメインフレームコンピュータなど、合計72のプロジェクトが対象となりました。
研究者たちは、各プロジェクトの関係者にアンケートへの記入を依頼し、さらに現地を訪問して情報の裏付けをとるという方法でデータを収集しました。そして、プロジェクトの様々な特徴(計画にかけた時間の割合、サプライヤーの関与度、設計の反復回数など)と、実際の開発に要した期間との関連性を分析したのです。
分析の結果、72のプロジェクト全体を平均して見ると、開発期間の短縮と一貫して結びついていたのは、「体験モデル」に属する要素でした。設計の「反復回数」が多いほど、全期間に占める「テスト」の割合が高いほど、そして「マイルストーン」の間隔が短いほど、開発は速く進むという結果が得られました。
これに対して、「圧縮モデル」の要素の多くは、開発期間の短縮にあまり結びつかないか、場合によってはむしろ期間を延長させてしまうこともありました。例えば、事前計画に時間をかければかけるほど、開発が遅くなるという関連が見られたのです。ただし、「圧縮モデル」の要素の中で唯一、様々な専門分野のメンバーを集めた「機能横断チーム」の編成は、開発期間の短縮に安定して貢献していました。
この調査の分析はここで終わりません。研究者たちは、製品分野によって市場や技術の不確実性が異なる点に着目し、サンプルを二つに分けて分析し直しました。一つは、技術が成熟し、市場がある程度予測可能なメインフレームやミニコンピュータのグループ。もう一つは、技術革新が速く、市場の変動が激しいパソコンや周辺機器のグループです。
すると、予測可能性の高いメインフレームなどの分野では、「圧縮モデル」が有効に機能することが確認できました。サプライヤーの早期関与やCADの活用、工程の並行化が、開発期間の短縮に結びついていました。対照的に、不確実性の高いパソコンなどの分野では、「体験モデル」の有効性が際立っていました。反復とテスト、短いマイルストーンが、開発を速める上で極めて大きな力を持っていたのです。
この結果から、開発を速めるための万能薬は存在しないことがわかります。そして、不確実な状況においては、机上で完璧な計画を練り上げようとすることよりも、まず動いてみて、そこから得られるフィードバックをもとに素早く方向修正を繰り返していくアプローチの方が、結果的により早くゴールに到達できる可能性が高いのです。試行錯誤を繰り返すことは、一見すると遠回りに見えるかもしれませんが、それは未知の領域で最善の解を発見するための、最も効率的な「学習」のプロセスです。
職場の環境要因が創造性を大きく左右する
これまで見てきたように、組織におけるイノベーションは、知識が対話を通じて生まれるプロセスと、不確実性の中で試行錯誤を繰り返す開発のアプローチによって支えられています。しかし、これらのプロセスが円滑に機能するためには、その土台となる職場の「環境」が整っている必要があります。従業員が安心して新しいアイデアを口にし、失敗を恐れずに挑戦できるような環境は、どのように作られるのでしょうか。
この問いに答えるため、ある研究チームは、職場の創造性に作用する環境要因を体系的に解明し、それを測定するための「ものさし」を開発することに取り組みました[3]。この研究の背景には、創造性は個人の才能や性格だけの問題ではなく、その人が置かれている職場環境によって左右されるという考え方があります。研究チームは、これまでの研究成果や実際の職場にいる人々へのインタビューを通じて、創造性を高める要因と、逆にそれを損なう要因を洗い出していきました。
その結果、創造性を支える環境は、いくつかの異なる次元から成り立っていることが明らかになりました。創造性を「刺激する要因」として、六つの側面が特定されました。
第一に、会社全体として新しい挑戦やリスクを取ることを奨励し、アイデアを公正に評価する文化があるかという「組織による奨励」。第二に、直属の上司が明確な目標を示しつつ、部下の自主性を尊重し、外部からの圧力から守ってくれるかという「上司による奨励」。第三に、チームのメンバーが互いに信頼し、多様な意見をオープンに交換できるかという「ワークグループの支援」です。
第四の要因として、従業員が仕事の進め方についてある程度の裁量を持っているかという「自由度」。第五に、業務を遂行する上で必要な人員、時間、予算、情報といった「十分な資源」が提供されているか。第六に、その仕事自体が従業員の能力に見合っており、やりがいを感じられるものであるかという「挑戦度」が挙げられました。
一方で、創造性を「阻害する要因」も二つ特定されました。一つは、過剰な手続きや社内政治、保守的な雰囲気といった「組織的阻害」。もう一つは、非現実的な納期や過剰な業務量による「作業負荷圧力」です。
研究チームは、これらの環境要因(刺激要因6つ、阻害要因2つ)を測定するための質問項目を作成しました。そして、この調査票を用いて、様々な業種・職種の企業で働く多数の従業員を対象に、自分たちの職場環境がどのように感じられているかを調査しました。同時に、その職場からどれくらい創造的な成果が生まれているか、また、生産性(仕事の量や速さ)はどの程度かについても、従業員の認識を尋ねました。
収集されたデータを分析した結果、この「ものさし」が、職場の創造性を測る上で信頼性が高く、的確であることが確認されました。理論的な想定通り、六つの刺激要因は、従業員が感じる職場の創造性の高さとプラスの関係にありました。特に、組織や上司からの奨励、挑戦的な仕事、ワークグループからの支援は、創造性を説明する上で大きな力を持っていることがわかりました。逆に、二つの阻害要因は、創造性の認識とマイナスの関係にありました。
この分析は、創造性と生産性の関係についても興味深い視点を提供してくれます。二つは必ずしも同じ要因によって高まるわけではないのです。例えば、適度な時間的制約は、集中力を高め、仕事の効率、すなわち生産性を向上させるかもしれません。しかし、その圧力が過度になると、従業員の視野は狭まり、じっくりと新しい可能性を探る余裕が失われて、創造性が犠牲になる可能性があります。
この研究が明らかにしたのは、創造性は、偶然や個人の才能に頼るものではなく、設計可能な「環境」の関数であるということです。組織全体の方針、日々のマネジメント、チーム内の人間関係、個々の仕事の与え方といった一つひとつの要素が、複雑に絡み合いながら、その職場の創造的なポテンシャルを決定づけています。
奨励や自由といった要素は、従業員の内面的なやる気を引き出し、心理的な安全性を確保することで、新しいことへの挑戦を後押しします。逆に、障害となる要因は、アイデアを形にするためのエネルギーを奪い、思考を硬直化させてしまうのです。
脚注
[1] Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization Science, 5(1), 14-37.
[2] Eisenhardt, K. M., and Tabrizi, B. N. (1995). Accelerating adaptive processes: Product innovation in the global computer industry. Administrative Science Quarterly, 40(1), 84-110.
[3] Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., and Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Journal, 39(5), 1154-1184.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。