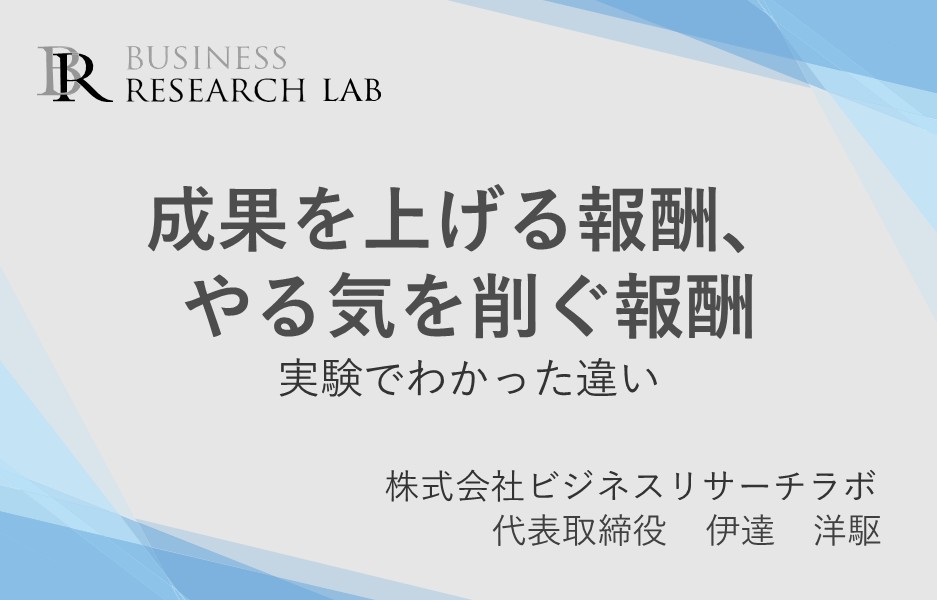2025年12月1日
成果を上げる報酬、やる気を削ぐ報酬:実験でわかった違い
「給料を上げれば、社員のやる気は上がるはずだ」。経営者や管理職の中には、そう信じている人もいるかもしれません。業績に連動したボーナス、目標達成時の報奨金、販売数に応じたコミッション。私たちの働く環境には、金銭を用いた動機づけの手法が溢れています。お金は、生活を支え、欲求を満たすための強力な道具です。だからこそ、それを報酬として提示すれば、人はより一層仕事に励むだろう、と考えるのは自然なことでしょう。
しかし、人間の心は、それほど単純なものでしょうか。もし、良かれと思って導入した報酬制度が、かえって社員の意欲を削いでしまったとしたら。もし、組織全体の生産性を高めるためのインセンティブが、社員の間に見えない溝を生み、格差を広げるきっかけになっていたとしたら。金銭というツールは、その力が大きいがゆえに、私たちの意図とは異なる、予期せぬ副作用をもたらすことがあります。それはまるで、強い光が濃い影を落とすかのようです。
本コラムでは、「報酬があれば人は動く」という素朴な常識に一度立ち止まり、科学の光を当ててみたいと思います。複数の緻密な社会実験の結果を読み解きながら、金銭的インセンティブが人の行動にもたらす「光」の側面と、見過ごされがちな「影」の側面の両方を掘り下げていきます。
行動基準に即した金銭が称賛・成績通知を上回る効果
金銭的な報酬が人の働き方を変える力を持つことは、多くの人が実感するところでしょう。しかし、その力を最大限に引き出すためには、どうやら「渡し方」に秘訣があるようです。同じ金額であっても、それがいつ、どのような理由で手渡されるかによって、受け取る側の行動は変わってくるのかもしれません。まずは、金銭的インセンティブが持つ「光」の側面、すなわち人のパフォーマンスを向上させる力について、その条件を探ることから始めましょう。
この問いを解き明かすため、ある興味深いフィールド実験が行われました[1]。舞台となったのは、アメリカの大手企業でクレジットカードの請求処理を行う業務部門です。ここでは、日々大量の伝票を処理する従業員たちの働きぶりを、より高める方法が模索されていました。研究チームは、この職場で働く182名の従業員を、くじ引きのような形で四つのグループに分け、それぞれ異なる働きかけを一ヶ月間にわたって実施しました。
一つ目のグループは、「慣例的な出来高払い」を経験しました。これは多くの企業でみられるもので、一定の基準を超えて処理した作業量に応じて、追加の報酬が支払われるというものです。
二つ目のグループには、「行動科学の知見に基づいた金銭インセンティブ」が適用されました。このグループでは、まず「望ましい職務行動」が具体的に定義され、従業員がその行動をとったことを上司が確認すると、ほぼ間髪を入れずに報酬が支給されました。ここでのポイントは、報酬が特定の行動と時間的・内容的に固く結びつけられている点です。何となく成果が上がったから報酬を与えるのではなく、「この行動をしたから、この報酬を得られた」という関係性を明確に従業員が学習できるように設計されていました。
三つ目のグループは、金銭ではなく「社会的な承認」をインセンティブとしました。このグループの上司は、部下が望ましい行動をとっているのを見かけると、その場ですぐに「先ほどの顧客への対応、とても丁寧で良かったですよ」というように、具体的な行動を挙げて称賛の言葉をかけました。
四つ目のグループは、「成績のフィードバック」のみを受け取りました。従業員には、日々の自分の作業頻度や成果が数値化されたグラフが提示されます。そこには上司からの評価や称賛の言葉は一切なく、客観的なデータだけが示されるのです。
一ヶ月後、それぞれのグループのパフォーマンス、すなわち時間あたりの請求処理枚数はどのように変化したのでしょうか。実験開始前の一ヶ月間のデータを基準として比較したところ、四つのグループの間で違いが観察されました。
最も大きな成果を上げたのは、二つ目の「行動科学に基づいた金銭インセンティブ」のグループでした。その処理量は、平均して31.7%も増加したのです。一方で、一つ目の「慣例的な出来高払い」のグループの伸びは11%に留まりました。金額の多寡だけではない、報酬の「与え方」が差を生んだことは注目に値します。
では、金銭以外のインセンティブはどうだったのでしょうか。三つ目の「社会的な承認」グループは24%増、四つ目の「成績フィードバック」グループも20%増と、いずれも慣例的な出来高払いを上回る成果を上げました。この結果は、人が必ずしもお金のためだけに働くわけではないことを物語っています。
賃上げで出勤は増えるが勤務中努力は減る
先ほどは、適切に設計された金銭的インセンティブが、人のパフォーマンスを力強く引き上げる「光」の側面を持つことを見てきました。行動と報酬をしっかりと結びつけることで、望ましい働き方を促すことができるようです。しかし、物事には常に両面があります。報酬という魅力的なニンジンが、常に私たちの期待通りに作用するとは限りません。ここからは、金銭がもたらすもう一つの顔、つまり私たちの直感に反するような、予期せぬ「影」の側面へと足を踏み入れていきましょう。
「給料が上がれば、人はもっと一生懸命働くはずだ」。この素朴な期待は、本当に正しいのでしょうか。この問いに答えるため、スイスのチューリッヒで、あるユニークな実験が行われました[2]。実験の協力者となったのは、自転車で街中を駆け巡り、書類や小包を届けるメッセンジャーたちです。彼らの収入は固定給ではなく、配達で得た売上高から一定の割合を受け取る完全歩合制。働く日や時間は比較的自由に選べるため、賃金の変動に対して、その働き方を柔軟に変えることが可能な人々でした。
研究チームは、44名のメッセンジャーをランダムに二つのグループに分け、時期をずらしながら、片方のグループの歩合率だけを期間限定で約25%引き上げるという介入を行いました。すなわち、一時的に「稼ぎやすい」状況を作り出したのです。研究の目的は、この一時的な賃上げが、メッセンジャーの働き方にどのような変化をもたらすかを、「働くか、働かないか(シフトへの参加)」という側面と、「どれだけ頑張って働くか(シフト中の努力)」という側面に分けて観察することでした。シフトへの参加は会社の記録から、そしてシフト中の努力は、その日の売上高を代理の指標として測定されました。
まず「働くか、働かないか」という点について、賃金が上がった期間、メッセンジャーたちは、明らかにより多くのシフトに入るようになっていました。稼ぎやすい時期を逃すまいと、普段より多く出勤したのです。ここまでは、経済学の標準的な予測通りであり、私たちの直感にも合致します。
しかし、問題は「どれだけ頑張って働くか」という点です。一時的に歩合率が上がっている期間中、メッセンジャーたちの1シフトあたりの平均売上高は、有意に減少していたのです。出勤はするものの、仕事中のペースはむしろ落ちていた、ということになります。稼ぎやすくなっているにもかかわらず、なぜか頑張らなくなってしまったのです。
この一見矛盾した結果を、どのように理解すればよいのでしょうか。研究者たちは、この現象を説明するために、「参照依存性」と「損失回避」という心の働きに光を当てました。これは、人が無意識のうちに「今日一日は、これくらい稼ごう」といった、日々の収入目標のようなものを心の中に設定している、という考え方に基づいています。
この「日次収入目標」というメガネを通して結果を眺めると、謎が解けてきます。賃金(歩合率)が上がると、この目標金額には、普段より短い時間や少ない労力で到達できるようになります。そのため、シフトに参加すること自体の心理的なハードルは下がり、結果として出勤日数が増える、と考えられます。
一方で、ひとたびその日の目標金額を達成してしまうと、それ以上頑張って働こうという意欲が、急に低下してしまうのかもしれません。目標を超えた領域での追加的な収入は、目標に満たない領域での収入に比べて、心理的な価値が低いと感じられるのです。これが、賃金が上がったにもかかわらず、シフトあたりの売上高が減少した理由として考えられます。楽に目標を達成できるようになった分、早めにペースを落としてしまった、というわけです。
管理職歩合導入で生産性が上がる一方、労働者間格差が拡大
金銭的インセンティブは、それを受け取る個人の行動を変えるだけではありません。組織という人の集まりの中に投じられたとき、それは波紋のように広がり、人々の関係性や組織全体の構造にまで変化を及ぼすことがあります。先ほどは、個人の心の内側で起こる報酬の複雑な作用を見ましたが、ここからは視点を広げ、ある特定の人物へのインセンティブが、その周囲の人々にどのような事態を引き起こすのかを探っていきます。特に、管理職への報酬体系の変更が、その部下である労働者たちの間に、どのような光と影を落とすのかを見ていきましょう。
この問いを検証するため、イギリスにある大規模なベリー農場が実験の舞台となりました[3]。この農場では、一人の最高執行責任者(COO)と10名の現場管理職(フィールドマネジャー)が、約200名の季節労働者たちの日々の作業を監督しています。労働者の仕事は、熟したベリーを一つひとつ手で摘み取ることで、その賃金は収穫量に応じた出来高払い(ピースレート)でした。
研究チームは、この農場の協力を得て、収穫シーズンの最中に、管理職の報酬体系を変更するという大胆な介入を行いました。シーズンの前半は、管理職とCOOは固定給で働いていました。しかし、シーズンの後半から、彼らの給与に新たなボーナス制度が導入されたのです。そのボーナスは、担当するチームの「一日あたりの平均生産量」が、あらかじめ設定された基準値を超えた場合にのみ支払われ、超過分が大きければ大きいほど、ボーナスの額も増えるという仕組みでした。重要なのは、労働者自身の賃金体系は、シーズンを通して一切変更されなかったという点です。変わったのは、あくまで管理職の懐事情だけでした。
管理職に成果連動型のボーナスが導入された後、農場では何が起こったのでしょうか。まず確認されたのは、組織全体の生産性の大幅な向上でした。ボーナス導入後、労働者一人あたりの時間あたり収穫量は、平均して21%も増加したのです。管理職に新たな動機づけを与えたことが、チーム全体の成果を見事に引き上げたと言えます。これは、インセンティブがもたらした「光」の側面です。
しかし、その光の裏側で、もう一つの変化が進行していました。それは、労働者たちの間での生産性の「ばらつき」の増大です。ボーナス導入後、労働者間の生産性の変動係数(ばらつきの度合いを示す指標)は、38%も拡大していました。これは、一部の労働者の生産性が著しく向上した一方で、他の労働者はそれほどでもなかった、あるいはむしろ低下した可能性を示唆します。チーム全体の生産性は上がったものの、その代償として、労働者間の「格差」が広がってしまいました。
生産性向上という成果の裏で、なぜ格差は広がってしまったのでしょうか。研究者たちは、そのメカニズムを解明するためにデータを詳細に分析し、二つの要因を突き止めました。
一つは、「ターゲティング(標的化)」と呼ばれる現象です。ボーナスという新たな目標を得た管理職は、チームの平均生産性を最も効率良く高める方法を考えます。その結果、限られた監督の時間や労力を、もともと生産性の高い、いわゆる「できる」労働者に優先的に振り向けるようになります。彼ら彼女らに的を絞って助言を与えたり、良い場所を割り当てたりするのです。その結果、優秀な労働者はさらに生産性を伸ばしますが、一方で、もともと生産性の低い労働者は、管理職の注意の輪から外れてしまい、両者の差はますます開いていくことになります。
もう一つの要因は、「セレクション(選別)」です。このインセンティブは現場の管理職だけでなく、農場全体の責任者であるCOOにも適用されていました。COOは、農場全体の平均生産性を高めるために、より直接的な手段に訴えるようになります。そもそも生産性の低い労働者を、収穫チームから排除してしまうのです。実際に、ボーナス導入後、それまで働いていた労働者のうち、特に生産性の低かった人々が解雇されたり、仕事を与えられなくなったりするケースが増加したことが確認されました。
管理者成果給で生産性向上し格差も拡大した
先ほど明らかになった、管理職へのインセンティブがもたらす「生産性向上」と「格差拡大」という二つの側面。この現象は、その一度きりの実験だけで見られた、特殊な出来事だったのでしょうか。あるいは、組織力学の一つのパターンなのでしょうか。科学的な知見の信頼性を高める上で、異なる状況や異なる分析方法を用いても、同じ結果が再現されるかどうかを確認する作業は欠かせません。ここでは、先ほどと非常によく似た環境で行われた、もう一つの研究を取り上げ、この光と影のパターンの再現性を探っていきます。
この研究もまた、イギリスのソフトフルーツ農園を舞台としています[4]。対象となったのは、管理職と、その下で働くベリー摘みの労働者たちです。実験のデザインも先ほどのものと同じで、収穫シーズンの途中から、管理職に対して、チームの平均生産量に連動したボーナスを導入するというものでした。この介入が、労働者一人ひとりの生産性や、労働者間の生産性のばらつきにどのような変化をもたらすかを観察しました。
結果、管理職にボーナスが導入された後、チーム全体の平均生産性は向上した一方で、労働者間の生産性のばらつきも拡大しました。この研究は、再現に留まらず、いくつかの新たな分析を加えることで、この現象の理解をさらに深めています。
一つは、翌年のデータとの比較です。実験が行われた翌年、この農場では管理職へのボーナス制度は導入されませんでした。その年のデータを分析したところ、シーズン途中で生産性が急上昇したり、格差が拡大したりするような現象は見られませんでした。このことは、前年に観察された変化が、ベリーの旬や天候といった単なる季節的な要因によるものではなく、明らかにボーナス制度の導入によって引き起こされたものであることを証明しています。
もう一つ興味深いのは、労働者の個人的な特性にまで踏み込んだ分析です。インセンティブ導入後の労働者の反応は、一様ではありませんでした。例えば、もともと「お金を稼ぎたい」という動機が強いと自己申告していた労働者や、プライベートでスポーツの習慣があるといった競争的な性格を持つと見られる労働者は、管理職のボーナス導入後に生産性が大きく向上しました。一方で、そうした特性を持たない労働者たちは、生産性が横ばいか、場合によっては低下するという、正反対の反応が観察されたのです。
脚注
[1] Stajkovic, A. D., and Luthans, F. (2001). Differential effects of incentive motivators on work performance. Academy of Management Journal, 44(3), 580-590.
[2] Fehr, E., and Gotte, L. (2002). Do workers work more if wages are high? Evidence from a randomized field experiment (Working Paper No. 125). Institute for Empirical Research in Economics, University of Zurich.
[3] Bandiera, O., Barankay, I., and Rasul, I. (2006). Incentives for managers and inequality among workers: Evidence from a firm-level experiment (IZA Discussion Paper No. 2062). Institute of Labor Economics (IZA).
[4] Shearer, B. (2003). Piece rates, fixed wages and incentives: Evidence from a field experiment (CIRPEE Working Paper No. 03-15). Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques economiques et l’emploi.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。