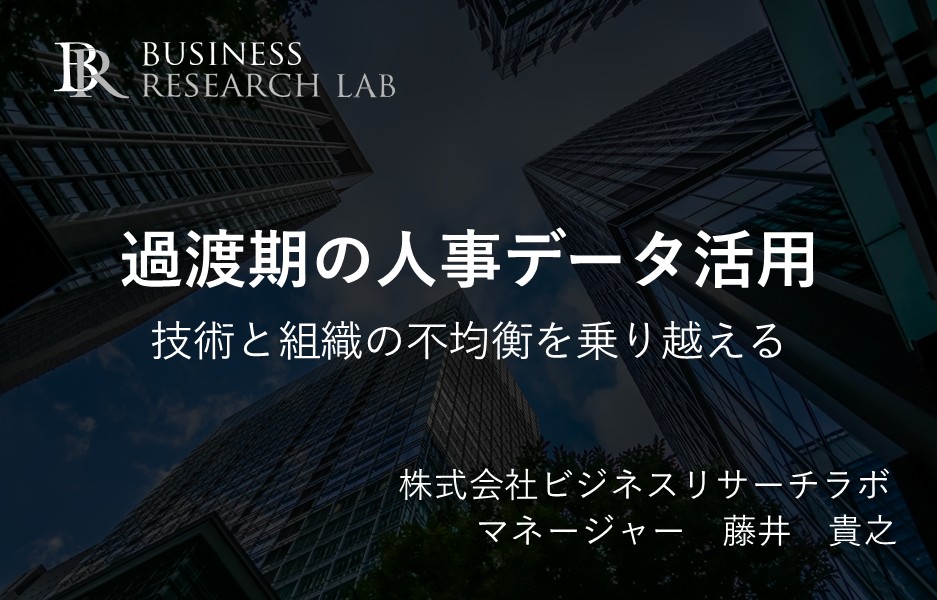2025年11月28日
過渡期の人事データ活用:技術と組織の不均衡を乗り越える
株式会社ビジネスリサーチラボが2025年8月に公開した『2025年版 人事データ白書』は、現代の日本企業における人事データ活用の「現在地」を、解像度高く映し出しています。その調査結果からは、日本企業は「過渡期」の真っただ中にいる、ということが明らかになりました。しかし、この「過渡期」という停滞は、ただ時間が経てば解決する問題なのでしょうか。
本コラムではこの現状をもう少し深く掘り下げ、急速に進歩する「技術の仕組み」(テクノロジーやツールなど)と、その変化に追いついていない「組織の仕組み」(組織文化、人間関係など)との間に生じた、深刻なアンバランスとして捉え直してみたいと思います。
この考え方のヒントをくれるのが、白書のコメントでも触れている「社会技術システム論(Socio-Technical Systems Theory;STS)[1]」です。この理論が教えてくれるのは、組織のパフォーマンスは、技術と組織のどちらか一方だけを良くしてもダメで、両方の足並みがそろって初めて最大化されるということです。言い換えれば、準備ができていない組織に最新のテクノロジーを導入しても、価値が生まれないばかりか、かえって組織内に新たな軋轢や反発を招く原因にもなりかねないのです。
本コラムでは、まず白書のデータを使って、この「技術と組織のアンバランス」が実際に起きていることを見ていきます。次に、白書で見つかった4つの企業タイプを、このアンバランスがもたらす異なる状態として読み解き、皆さんが自社の立ち位置を知るためのヒントを提示します。そして最後に、このアンバランスを解消し、データが本当に活きる組織風土を育むための、3つの実践的なアプローチを提案します。
「社会技術システム」不均衡の実態
多くの企業では人事関連のテクノロジーへの投資が進み、一見するとデータに基づいた組織へと変わりつつあるように見えます。しかし、その水面下では、働く「人」に関わる組織の仕組みの成長が遅れており、両者のギャップが広がっています。この章では、白書のデータを基に、そのアンバランスの実態を明らかにします。
先行する技術的仕組み:整備された基盤
まず、企業の「技術の仕組み」が一定のレベルに達していることは、データから明らかです。特に、人事業務の土台となるテクノロジーは広く普及しており、企業が技術投資に消極的なわけではないことがわかります。
白書の調査によれば、「給与計算システム」は90.1%、「勤怠管理システム」も82.5%の企業で導入されています。これは、いわば人事業務の「守り」を支える部分です。データを集める仕組みも整いつつあり、例えば「勤怠データ」は94%以上、「評価・報酬データ」も9割以上の企業が集めています。
これらの数字は、多くの企業が人事データを扱うための「器」をすでに手にしていることを示しており、表面的にはデータ活用の準備は万端に見えます。しかし、投資がこうした管理業務のシステムに集中しているとすれば、それ自体がより根深い「組織の仕組み」の問題、つまり「人事部門に何を期待するか」という組織の認識を映し出しているとも言えそうです。
なぜ、「守り」のシステム導入は進むのに、戦略的な人材活用を支える「タレントマネジメントシステム」(41.5%)や、高度な分析を可能にする「BI/分析ツール」(30.7%)の導入はなかなか進まないのでしょうか。
これは単に導入の順番の問題ではなく、経営層や他部門が人事部門に期待する役割として、今もなお「労務管理と法令遵守」という管理機能に留まっていることが考えられます。この旧来の認識が残っていると、人事部門を「守り」の役割に固定してしまうような方向性での技術投資となります。技術は前に進んでいるようで、実は旧来の組織の仕組みによって、本来進むべき道から逸れてしまっているのかもしれません。
遅れる「組織の仕組み」:準備ができていない組織文化
「技術の仕組み」が進んでいる一方で、それを使いこなし、価値に変えるための「組織の仕組み」は大きな遅れを見せています。スキル、文化、コミュニケーションといった、いわば「人」に関わるインフラが未整備なままでは、どれほど優れた技術も宝の持ち腐れになってしまいます。
白書が示す深刻な課題は、多くの企業で見られるスキル不足です。「分析に必要な人材・スキルの不足」は、74.6%もの企業が課題だと感じており、データ活用を阻む最大の壁となっています。具体的に見ると、「統計学に基づく分析の知識」を持つ担当者は少なく、約4割が「ないと思う」か「どちらともいえない」と回答しており、高度な分析能力が不足していることがわかります。
さらに、客観的なデータよりも、これまでのやり方が根強く残っていることも、組織の未熟さを示しています。人事部門や管理職の中には、「データよりも経験や勘を重視する」と感じる人が今なお3割を超えており、旧来の組織の文化がなかなか変わっていないことがうかがえます。
こうした昔ながらの文化が、データに基づいた話し合いの機会を奪っているのかもしれません。分析結果を現場レベルで共有し、意見交換する場を「精力的に実施している」企業はわずか14.0%であり、多くの企業では、分析結果は経営層へ一方的に報告されるだけとなっています。つまり、組織全体でデータを共有し、課題を話し合い、同じ方向を向くためのプロセスがうまく機能していないのです。
そして、このアンバランスは、ただギャップがあるというだけでは済みません。組織内に「摩擦」というマイナスの状況を生み出します。分析スキルを持たず、経験と勘を重んじる文化の中に高度な分析ツールを導入すれば、現場からは「数字だけでは現場のことは分からない」という不信感が、分析担当者からは「分析しても誰も聞いてくれない」という無力感が生まれます。この「技術と組織の軋轢」は、意思決定を遅らせ、組織の活力を削ぎ、変化への抵抗感をさらに強くするという、目に見えないコストとなります。結果として、多額を投じた技術への投資は、プラスの資産ではなく、マイナスの負債に変わってしまうのです。
不均衡がもたらす4つの顔:企業タイプを読み解く
技術と組織のアンバランスは、すべての企業で同じように現れるわけではありません。ここでは、白書の第10章で見つかった4つの企業タイプについて、このアンバランスがもたらす異なる状態として読み解いてみたいと思います。このフレームワークは、皆さんが自社の現在地を知り、直面している課題の本質を理解するための地図になるはずです。
類型化の再定義
各タイプを、「技術システムの成熟度」と「組織システムの成熟度」という二つの軸で整理し、それぞれがどのような状態にあるのかを以下のように定義します。
未活用タイプ(全体の46.3%):低技術/低社会
これは「停滞」の状態です。技術(戦略システムの導入率が低い)と組織(データ活用への関心・スキルが低い)の両方が未発達な段階にあります。変化のきっかけとなる技術導入が進んでいないため、大きな軋轢はまだ表面化していませんが、データ活用のスタートラインで立ち止まっている企業群です。
抵抗模索タイプ(全体の21.2%):中技術/低社会
これは「摩擦」の状態です。タレントマネジメントシステム等の導入を試みるなど、技術の仕組みを良くしようと「模索」はしているものの、スキル不足や組織の抵抗といった、準備ができていない組織の仕組みに阻まれている状態です。技術と組織のアンバランスが最も典型的に現れており、担当者のストレスやプロジェクトの頓挫といった問題に直面しています。
抵抗積極タイプ(全体の9.3%):高技術/対立的社会
これは「葛藤」の状態です。BIツールの導入率が65.5%に達するなど、高度な技術を積極的に推進する強力なリーダーがいる一方で、それに対する組織的な「抵抗」も極めて強いという特徴を持ちます。新しい技術と古い文化が激しく衝突し、組織のあり方そのものが問われている、エネルギーに満ちあふれつつもリスクの高い変革期にあると言えます。
積極活用タイプ(全体の23.2%):高技術/高社会
これは「均衡」の状態です。高度な技術の仕組みと、それを支える組織の仕組み(低い抵抗感、高いスキルと関心)がうまく調和しています。安定して高い成果を出しており、技術と組織がうまく連携している理想的な状態です。
この整理が示すのは、企業が直面する課題は個別の問題ではなく、システム全体の構造から生まれているということです。例えば、「抵抗模索タイプ」が苦労しているのは、担当者の能力不足というより、システム間の「摩擦」という構造的な問題に原因があると言えます。
さらにこの分析は、組織変革の道のりが一本道ではないことを教えてくれます。一般的には、「摩擦」を経験する「抵抗模索タイプ」から、対立を避けて「積極活用タイプ」へ移行するのが理想と考えがちです。しかし、白書が示すように、最も高い成果を上げているのは、激しい「葛藤」の真っただ中にいる「抵抗積極タイプ」なのです。
この事実は、旧来の文化が深く根付いた組織にとっては、痛みを伴う葛藤の時期を経ることが、本当の意味での変革を達成するために不可欠なプロセスである可能性を示唆しています。「積極活用タイプ」はもともと変化への壁が少なかった組織であり、「抵抗積極タイプ」は、より根本的な組織の変化を遂げつつある姿なのかもしれません。調和や安定だけがゴールではないのです。
また、「均衡」が最終目的地ではないという点も重要です。完全にバランスが取れたシステムは、次の環境変化に対応できず、硬直化してしまう危険性があります。「積極活用タイプ」の現在の成功が、未来の変化の波に対する油断につながることはないでしょうか。本当の目標は、永続的な安定を手に入れることではなく、変化に対応しながら、常に技術と組織のバランスを取り続ける力、いわば「変化への対応力」を組織に備えることにあるのです。
システムのバランスをとる:データが活きる組織風土を育む3つのアプローチ
技術と組織のアンバランスを解消し、両者のバランスを取るためにはどのようなアプローチが有効なのでしょうか。ここでは、白書の分析結果にも裏打ちされた、3つの実践的なアプローチを提案します。
アプローチ1:使う人が一緒に作る(参加型の再設計)
技術の仕組みを組織にフィットさせる最も効果的な方法は、その仕組みを使う人自身が設計プロセスに参加することです。人事やIT部門が一方的にシステムを作り、現場に「使ってください」と押し付けるのではなく、現場の管理職や従業員が、課題の発見から仕事の進め方の設計まで、初めの段階から主体的に関わる「共創」のプロセスへと転換することが求められます。
このアプローチが有効であることは、白書の分析結果も示しています。「従業員が経営に参加するスタイルの企業」はデータ活用の成果を実感しやすく、逆にトップダウンで一方的な意思決定を行う企業は成果が出にくい傾向にあることがわかっています。
具体的なアクションとしては、分析担当者、IT専門家、そして何よりも現場から信頼されている管理職など、部門の垣根を越えたプロジェクトチームを作ることが考えられます。
アプローチ2:データを「対話のきっかけ」にする
組織の仕組みの重要な機能の一つは、情報を解釈し、意味を生み出すことです。このプロセスにおいて、データは専門家が提示する「絶対的な正解」ではなく、異なる背景を持つ人々がそれぞれの視点から議論し、より豊かな共通理解を築くための「対話のきっかけ」として位置づけられるべきです。
この考え方の重要性は、白書の分析結果も力強く裏付けています。「分析結果を共有し報告する」という活動は、「部署間のコミュニケーションの活性化」や「経営層との協力関係の構築」といった成果との関連性が示されています。これは、データの分析そのものだけでなく、それを共有し対話する行為こそが価値を生むことを物語っています。
実践的には、報告の場を、一方的に聞くだけの静的な報告会から、活発な意見交換を促す対話の場へと変えることが求められます。主要な分析結果が出たら、報告会ではなく「ワークショップ」を企画するのも一案です。そこでの分析担当者の役割は、結論を伝えることだけではありません。「データはこのように示していますが、皆さんが現場で感じている実感と、どこが同じで、どこが違いますか?」といった問いを投げかけることで、議論を盛り上げることができ、参加者にとってのデータ活用の「自分事化」も進むでしょう。
アプローチ3:「そもそも、これで良いのか?」と前提を問う
組織が変化に強くなるためには、より深いレベルでの学習と自己修正の能力が必要です。「やり方を改善する」学習だけでなく、「そもそも、この目的は本当に正しいのか」と前提や目的そのものを問い直す学習が求められます。データは、この両方の学習を後押しするために活用するものと考えることができます。
白書の分析では、「人事データ活用の目的」が明確であることが、成果の実感と強く関連していることが示されました。深い学習とは、この「目的」そのものを、データに基づいて常に見直し、より良くしていくプロセスに他なりません。「離職率の低下」という当初の目的は、今も最も重要でしょうか。それとも、データはむしろ「中途入社者が早く活躍できるよう支援すること」にこそ力を入れるべきだと示してはいないでしょうか。
これを組織的に実践するためには、例えば、人事データ活用のプロジェクトが終わるたびに、公式な「振り返りの場」を設けることが有効です。そしてその場では、目標を達成できたかを評価するだけでなく、「今回の学びを踏まえると、当初の目標設定や仮説は正しかったか。次は、何を、どのように調べるべきか」というテーマを必須の議題とする、といったことが考えられます。
データを「組織の学習エンジン」へ
本コラムが示してきたのは、「過渡期」を乗り越えるための道筋は、さらなる技術投資や、一人の優秀な専門家の採用だけでは見つからない、ということです。技術システムと組織システムという2軸に注目し、人事データ活用を、技術と組織の両方を含む、会社全体の組織開発という、より大きな視点から捉え直す考え方をご紹介しました。
人事データ活用の本当の価値は、単に業務を効率化することだけではありません。組織を、変化に強く、より賢く、そしてより人を大切にするチームへと変えていく可能性を秘めています。技術への投資と並行して、それを支える組織の仕組みを意識的にデザインし、育んでいくことが、「過渡期」を抜け出し、データに基づいた継続的な組織学習の未来へと至る道筋となるでしょう。
脚注
[1] Trist, E. L. (1981). The evolution of socio-technical systems. Occasional Paper, 2, Ontario Quality of Working Life Centre.
執筆者

藤井 貴之 株式会社ビジネスリサーチラボ マネージャー
関西福祉科学大学社会福祉学部卒業、大阪教育大学大学院教育学研究科修士課程修了、玉川大学大学院脳情報研究科博士後期課程修了。修士(教育学)、博士(学術)。社会性の発達・個人差に関心をもち、向社会的行動の心理・生理学的基盤に関して、発達心理学、社会心理学、生理・神経科学などを含む学際的な研究を実施。組織・人事の課題に対して学際的な視点によるアプローチを探求している。