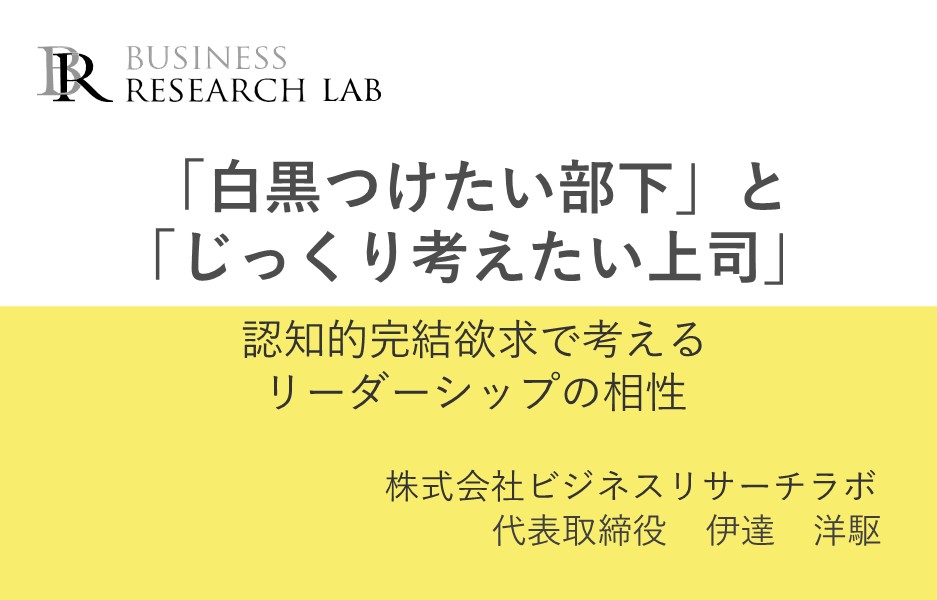2025年11月28日
「白黒つけたい部下」と「じっくり考えたい上司」:認知的完結欲求で考えるリーダーシップの相性
私たちの周りには、決断が早く物事を白黒はっきりさせたい人もいれば、多様な可能性を吟味し、じっくり時間をかけて結論を出したい人もいます。このような個人の思考スタイルの違いは、組織や職場という集団の中で、どのような化学反応を引き起こすのでしょうか。特に、リーダーと部下という関係性においては、その特性の違いが、チームの成果や働く人々の心の健康にまで関わってくることがあります。
本コラムで光を当てるのは、「認知的完結欲求」と呼ばれる心理的な特性です。これは、曖昧で不確実な状態を避け、早く明確で安定した答えを得たいと望む心の働きを指します。この欲求が強い人は、複雑な問題を前に迅速に結論に飛びつき、一度決めたことを変えたがらない行動をとることがあります。逆に、この欲求が弱い人は、性急な判断を避け、新しい情報に対して心を開き、柔軟に考え方を変えることができます。
この「答えを求める欲求」の強弱が、リーダーがどのような手法で部下を導こうとするのか、部下がどのようなリーダーシップを心地よく感じるのか、さらにはストレスへの対処法や組織変革への態度にまで、広範囲にわたって結びついていることが解き明かされつつあります。「良いリーダーシップ」に唯一絶対の正解がないとすれば、その鍵を握っているのは、私たち一人ひとりの心の中に宿る、この欲求なのかもしれません。本コラムでは、この認知的完結欲求というレンズを通して、リーダーシップと組織マネジメントの世界を探求していきます。
認知的完結欲求に応じた権力戦術が成果を左右する
リーダーシップが発揮される場面で、リーダーは部下に働きかけます。その方法は、報酬や罰、地位といった権威を背景にする「強硬な戦術」と、専門知識や人間的魅力を通じて内面に訴える「柔軟な戦術」に大別できます。どちらの戦術が選ばれるかは、リーダーの個性や価値観に根差していると考えられます。ここで、「早く明確な答えが欲しい」という認知的完結欲求が、リーダーの戦術選択にどう関わるかを探った調査があります[1]。
この調査は、イタリアの医師や警察官、合計220名を対象に行われました。参加者には、自身の認知的完結欲求の強さと、好んで用いる権力戦術を評価する尺度に回答してもらいました。分析の結果、認知的完結欲求が高い人ほど、強硬な戦術を好むという関係性が見出されました。逆に、柔軟な戦術には好意的な態度を示しませんでした。この関係は、個人の権威主義的な性格を統計的に調整した後でも保たれており、強硬な戦術を好む背景には、物事を迅速に確定させたいという動機が存在することを示唆しています。
この発見をより確かなものにするため、あるエネルギー企業の27部署で別の調査が行われました。27人の上司に自身の認知的完結欲求を、その部下106人に上司が用いる権力戦術を評価してもらったのです。異なる情報源を組み合わせることで、客観的な分析が試みられました。結果は最初の調査を裏付け、認知的完結欲求が高い上司は、部下からも強硬な戦術を多用する人物と認識されていました。
これらの結果から、認知的完結欲求の強いリーダーが強硬な戦術に傾くメカニズムを考察できます。この欲求が高い人は曖昧さを嫌い、不確実な状況を苦痛に感じます。対話を要する柔軟な戦術は、結論までに時間がかかり、不確実な状況を生む可能性があります。対照的に、強硬な戦術は権限に基づき一方的に指示するため、議論の余地が少なく、物事を迅速かつ明確に決定できます。この「迅速性」と「明確さ」が、欲求の高いリーダーにとって好ましい状態をもたらすのかもしれません。
認知的完結欲求は満足が低いと問題焦点、高いと回避策を選ばせる
リーダーのスタイルと部下の特性との適合関係に目を向ける前に、個人が困難な状況に直面したとき、認知的完結欲求がその人の行動をどう方向づけるかを理解しておくことが有益です。職場では予期せぬ問題に遭遇することもあります。そのような状況での対処法は、その後の適応や心の健康を左右します。認知的完結欲求は、このようなストレス状況での個人の行動選択にも関わっています。
この点を明らかにするため、イタリア在住のクロアチア移民146名を対象とした調査が行われました[2]。参加者には「語学講座の受講を雇用主に拒否された」というストレス場面を想定してもらい、どう対処するかを尋ねました。対処法は、問題解決に直接働きかける「問題焦点型」、問題から距離を置く「回避型」、感情を発散させる「情動焦点型」の三つに分類されました。
この調査では、認知的完結欲求の強さと共に「現在の仕事に対する満足度」も測定されました。個人の基本的な動機が、仕事に満足しているか否かという状況評価によって、異なる形で行動に現れるのではないかと考えられたからです。
分析の結果、認知的完結欲求が高い人々の中で、現在の仕事に満足していない人々は、「問題焦点型」の対処法を最も強く選択しました。現状を積極的に変えようとする行動に出やすいことが示されたのです。これは、認知的完結欲求が持つ「早期把握」の側面が働いた結果と解釈できます。現状が不満足で「開かれた」問題と認識されると、それをいち早く解決し、安定した状態に到達したいという動機が強まります。
一方で、同じく認知的完結欲求が高い人々でも、現在の仕事に満足している場合は、異なる行動パターンを示しました。彼らは「回避型」の対処法を最も強く選択したのです。波風を立てるのを避けようとしました。この背景には、認知的完結欲求のもう一つの側面である「恒常化」の働きがあると考えられます。現在の好ましい状態が、問題への介入で脅かされるのを避けたい。得られた安定を維持したいという動機が、現状維持的な行動につながったと考えられます。
認知的完結欲求と上司戦術の適合がバーンアウトを左右する
職場におけるストレスやバーンアウトは、個人と組織の双方に損失をもたらす問題です。その発生源として、上司と部下の関係性は要因とされます。一般に、部下の意見に耳を傾ける「柔軟な」リーダーシップが望ましいと見なされてきましたが、本当にそうなのでしょうか。部下の側が持つ「答えを求める欲求」の強さによっては、この常識が覆る場面もあるかもしれません。
この「上司の戦術と部下の欲求の適合」を、バーンアウトやストレスの観点から検証した研究があります[3]。一つ目の調査は、イタリアの病院に勤務する90名の看護師を対象としました。参加者には、自身の認知的完結欲求、直属の上司が用いる権力戦術、そして自身のバーンアウトの度合いを測定する尺度に回答してもらいました。
分析の結果、上司の戦術と部下の認知的完結欲求の間に、相互作用が見られました。一般に敬遠されがちな「強硬な戦術」ですが、認知的完結欲求が高い部下に対して用いられた場合、バーンアウトのレベルを低下させました。明確な指示が、彼ら彼女らにとっては安心材料となり、心理的負担を軽減していたと考えられます。ところが、同じ戦術でも、認知的完結欲求が低い部下に対しては、逆にバーンアウトを増大させていました。
「柔軟な戦術」については、逆のパターンが見られました。認知的完結欲求が低い部下に対して用いられると、バーンアウトは低減しました。対話的なスタイルが彼ら彼女らの思考様式と合致したのでしょう。しかし、この柔軟な戦術も、認知的完結欲求が高い部下に対しては、バーンアウトを増大させました。結論の出ない曖昧な状況が、彼ら彼女らにとっては混乱や不安を引き起こし、精神的な消耗につながったのかもしれません。
この発見を確かめるため、サービス業の従業員112名を対象に二つ目の調査が行われました。部下に自身の認知的完結欲求とストレスを、上司に自らの権力戦術を回答してもらう工夫がなされました。分析の結果は、一つ目の調査を再現しました。認知的完結欲求が高い部下には強硬な戦術が、低い部下には柔軟な戦術が、それぞれストレスを和らげる関係が見られたのです。
これら二つの調査は、「柔軟なリーダーシップが常に最善である」という画一的な考えに再考を促します。リーダーシップの有効性は、それを受け止める部下の心理的な特性との「相性」によって大きく左右されます。この「適合」という視点は、リーダーシップのあり方をより深く捉え直すきっかけとなります。
認知的完結欲求が高いほど、集団原型的リーダーが成果を高める
リーダーシップの源泉は、指示の出し方だけではありません。リーダーが、所属する集団の価値観や規範、要するに「その集団らしさ」を体現する存在、「集団の典型(プロトタイプ)」として認識されているかも、部下の意欲や満足度に関わっています。リーダーが「我々の代表だ」と感じられるとき、人は一体感を覚え、その導きに従いやすくなります。この「リーダーの集団原型性」の効果は、すべての人に等しく現れるのでしょうか。ここでも認知的完結欲求が、その関係性を調整する鍵を握っている可能性があります。
この問いに答えるため、イタリアの三つの企業に勤務する242名の従業員を対象とした調査が実施されました[4]。参加者には、自身の認知的完結欲求、リーダーの集団原型性、リーダーシップの有効性や仕事満足度といった様々な組織成果に関する指標に回答を求めました。
分析の結果、リーダーの集団原型性が、それ自体で多くの肯定的な結果と結びついていることが確認されました。リーダーが「チームらしい」と認識されるほど、部下はそのリーダーシップを有効だと評価し、仕事への満足度やパフォーマンスも高く、離職を考えることは少ない、という関係です。
この研究の核心は、リーダーの集団原型性と部下の認知的完結欲求との間に、相互作用が見られるかを検証した点にあります。結果は、調査された四つの成果指標すべてにおいて、相互作用の存在を示しました。認知的完結欲求が高い部下であるほど、リーダーの集団原型性がもたらす肯定的な効果が、より一層強まるというパターンが明らかになったのです。
例えば、リーダーシップの有効性について、認知的完結欲求が低い部下の間でも、リーダーの原型性が高いほど評価は高まりましたが、欲求が高い部下の間ではその関係がさらに顕著でした。なぜ、このような関係が生まれるのでしょうか。認知的完結欲求が高い人々は、不確実性を嫌い、判断のための明確な手がかりを求めます。「原型的なリーダー」は、彼ら彼女らにとって信頼できる情報源として機能します。「このリーダーに従えば間違いない」という確信が、曖昧さからくる不安を和らげ、安心して業務に集中できる心理状態を生み出すのでしょう。
認知的完結欲求と同一視が原型的リーダーへの変革受容を高める
組織が成長を続けるには、時に大規模な変革が避けられません。変革は従業員に大きな不確実性と不安をもたらし、その成功は従業員の受容と協力にかかっています。しかし、多くの変革は従業員の「抵抗」によって頓挫します。抵抗の根源には、変化によって自分たちのアイデンティティが脅かされることへの恐れがあると言われています。
このような状況で、リーダーの存在は決定的な意味を持ちます。「集団の典型」としてのリーダーは、変化の荒波の中、集団のアイデンティティの連続性を保証する灯台となりえます。このリーダーの原型性が、変革への抵抗をどう和らげるのか、そこに従業員の認知的完結欲求やチームへの愛着(チーム同一視)がどう絡むのかを探求した調査があります[5]。
調査は、大きな組織変革を経験したイタリアの大手航空宇宙企業の従業員102名を対象に行われました。参加者には、自身の認知的完結欲求、チームへの同一視、リーダーの原型性、変革の受容度を測定しました。
分析の結果、非常に複雑ながらも理論的な予測と合致する関係性が浮かび上がりました。初めに、リーダーの原型性が高いほど、またチームへの同一視が強いほど、変革は受け入れられやすい傾向にありました。一方で、認知的完結欲求の高さ自体は、変革受容を妨げる方向に働いていました。
この研究の興味深い点は、これら三つの要素(リーダーの原型性、認知的完結欲求、チーム同一視)が絡み合った、三者間の相互作用を検証した点にあります。リーダーの原型性が変革受容に与える肯定的な効果は、部下の認知的完結欲求が高いほど、そして同時にチームへの同一視も高い場合に、最大化されることが明らかになったのです。
この複雑な関係を解きほぐしてみましょう。チームへの愛着が強い従業員にとって、組織変革はアイデンティティを揺るがす脅威です。しかし、リーダーが「原型的な」人物であれば、そのリーダーはアイデンティティの守護者として信頼され、不安を和らげます。
この効果は、認知的完結欲求が高い従業員において顕著でした。彼ら彼女らは、変革がもたらす曖昧な状況を嫌い、確かな指針を渇望します。チームへの愛着が強く、答えを求める欲求も強い。この二つの特性を併せ持つ従業員にとって、「我々らしさ」を象徴するリーダーが示す変革の方向性は、暗闇を照らす光のように感じられます。そのリーダーが変革を支持するなら、それは信頼できる「確定的な答え」として受け入れられ、抵抗は受容へと転換します。
脚注
[1] Pierro, A., Kruglanski, A. W., and Raven, B. H. (2012). Motivational underpinnings of social influence in work settings: Bases of social power and the need for cognitive closure. European Journal of Social Psychology, 42(1), 41-52.
[2] Kosic, A. (2002). Need for cognitive closure and coping strategies. International Journal of Psychology, 37(1), 35-43.
[3] Belanger, J. J., Pierro, A., Barbieri, B., De Carlo, N. A., Falco, A., and Kruglanski, A. W. (2015). One size doesn’t fit all: The influence of supervisors’ power tactics and subordinates’ need for cognitive closure on burnout and stress. European Journal of Work and Organizational Psychology, 25(2), 287-300.
[4] Pierro, A., Cicero, L., Bonaiuto, M., van Knippenberg, D., and Kruglanski, A. W. (2005). Leader group prototypicality and leadership effectiveness: The moderating role of need for cognitive closure. The Leadership Quarterly, 16(4), 503-516.
[5] Pierro, A., Cicero, L., Bonaiuto, M., van Knippenberg, D., and Kruglanski, A. W. (2007). Leader group prototypicality and resistance to organizational change: The moderating role of need for closure and team identification. TPM: Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, 14(1), 27-40.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。