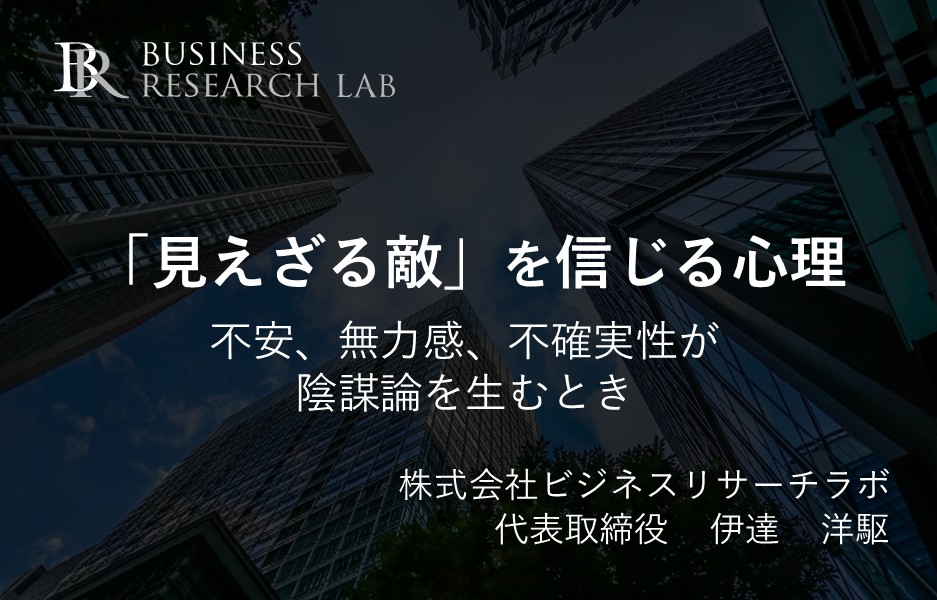2025年11月28日
「見えざる敵」を信じる心理:不安、無力感、不確実性が陰謀論を生むとき
私たちの社会に、陰謀論の影が静かに広がっています。インターネットを通じて情報が拡散する現代において、陰謀論はもはや対岸の火事ではなく、私たちの考え方や社会のあり方そのものを揺るがしかねない、身近な現象となりつつあります。大統領選挙の結果から、パンデミックの原因、さらには身近な組織内の出来事に至るまで、様々な事象が「裏で糸を引く誰か」の存在によって説明されようとします。
このような陰謀論的な世界観は、どのようにして人々の心に根を下ろし、社会にどのような波紋を広げていくのでしょうか。それは、情報を鵜呑みにしやすい人々の問題なのでしょうか。あるいは、私たちの心の中に潜む、より一般的な心理メカニズムが関係しているのでしょうか。
本コラムでは、「陰謀論はなぜ広がり、社会の安定をいかにして損なうのか」という問いに対して、近年の社会心理学が蓄積してきた複数の実証的な研究を手がかりに、その背後にある心の動きと社会的なプロセスを検討していきます。陰謀論を信じる心が権力への敵意を育み、社会制度への不信を招き、私たちの日常的な人間関係にまで浸透していく。その複雑で多層的なメカニズムを研究データと共に探求します。
陰謀的思考は権力者への敵意を高め行動を促す
陰謀論に惹かれる人々の心の中には、どのような特徴的な世界観が広がっているのでしょうか。社会心理学の世界では、特定の陰謀(例えば「ある歴史的事件は公表されている内容とは違う真相がある」といったもの)を信じることとは別に、より根源的なレベルで、「世の中の重要な出来事は、強力な集団による秘密の企みによって引き起こされている」と考える一般的な心の構えが存在すると考えられています。これを「陰謀メンタリティ」と呼びます。
これは、個別の事件に対する信念というよりも、世界を解釈するためのレンズのようなものと言えます。このレンズを通して世界を見ると、物事の表面的な説明では満足できず、その裏に隠された意図や計画を探ろうとする思考が働きます。
陰謀メンタリティが、他の政治的な態度、例えば伝統や権威を重んじる「右派権威主義」や、社会内の集団間にある階層構造を肯定する「社会的支配志向」とは、性質を異にする独立したものであることを検証した一連の研究があります[1]。研究者たちは陰謀メンタリティを測定するための質問項目を作成し、オンラインで数百人を対象に調査を行いました。分析の結果、陰謀メンタリティは、権威主義や社会的支配志向とはほとんど関連がないことが分かりました。陰謀メンタリティが、既存の政治的態度の枠組みでは捉えきれない、独自の心理的構成要素であることを示唆しています。
陰謀メンタリティを持つ人々は、社会に存在する様々な集団に対して、どのような感情を抱くのでしょうか。研究者たちは、この点を明らかにするために調査を行いました。参加者に、社会における力の強い集団(例えば、資本家、アメリカ人、ユダヤ人)と、力の弱い集団(例えば、イスラム教徒、ロマ)に対する偏見の度合いを測定してもらったのです。
その結果、陰謀メンタリティが高い人ほど、力の強い集団に対して強い偏見を抱くというパターンが見られました。一方で、力の弱い集団に対する偏見とは関連がありませんでした。これは、権威主義や社会的支配志向が高い人々が、力の弱いマイノリティ集団に対して偏見を抱きやすいのとは、全く対照的な結果です。陰謀メンタリティは、力の弱い者への蔑視ではなく、力を持つ者への敵意と結びついています。
この「力を持つ者への敵意」というパターンが、一部の集団に限定されたものではないことを確かめるため、別の研究が行われました。そこでは、32の多様な社会集団(政治家、経営者から、失業者、フェミニストまで)をリストアップし、参加者にそれぞれの集団が持つ「力」「好ましさ」「脅威」の度合いを評価してもらいました。各参加者の中で、「力がある集団ほど、どの程度好ましくないと感じるか」また「力がある集団ほど、どの程度脅威に感じるか」という関連の強さを分析しました。
結果、陰謀メンタリティが高い人ほど、「力を持つ集団は好ましくなく、脅威的である」という認識の結びつきが強いことが分かりました。
このような思考は、頭の中にとどまるだけなのでしょうか。それとも、実際の行動に結びつくのでしょうか。研究者たちは、2011年の福島第一原子力発電所事故の直後にドイツで行われた調査のデータを分析し、この問いに答えようとしました。この調査では、事故の原因をどう捉えているか(意図的な不正行為か、過失か、偶然か)、そして反原発の行動(デモへの参加や、非合法的な抗議活動への参加意志など)にどの程度関心があるかが尋ねられていました。
分析の結果、陰謀メンタリティが高い人ほど、事故の原因を単なる過失や偶然ではなく「意図的な不正行為」の結果と見なし、政府に原発からの撤退を求め、抗議行動に参加する意欲が高いことが分かりました。
制度への不信と陰謀論は社会的信頼や協力を低下させる
既述の通り、陰謀論的な世界観は、力を持つ者への敵意と結びついています。この敵意の矛先は、特定の政治家や企業家だけでなく、より広く、私たちの社会生活の基盤をなす政府、司法、科学、メディアといった「制度」そのものに向けられることがあります。「政府は国民を欺いている」「科学者は真実を隠している」といった考えは、制度に対する不信の表れです[2]。
社会制度が円滑に機能しているとき、それは私たちに二つの大きな恵みをもたらしています。一つは「安全の保障」です。法律や警察は犯罪から私たちを守り、社会保障制度は病気や失業といったリスクから私たちを保護してくれます。これによって、私たちは「この社会は自分を守ってくれる」という安心感を得ることができます。
もう一つは「規範と価値のモデル」としての働きです。公正な裁判や透明性のある行政手続きは、「この社会では公正さが重んじられる」「協力や遵法が善いことである」というメッセージを発信し、人々がそれらの価値を内面化する手助けをします。
しかし、制度への不信や陰謀論が広がると、これらの機能はうまく働かなくなります。制度が「無能だ」あるいは「悪意を持っている」と見なされると、「守られている」という感覚は失われ、代わりに世界は危険で予測不可能な場所に見えてきます。その結果、人々は見知らぬ他者に対して警戒心を強め、社会から排除されることへの不安を高めます。「上の人間は腐敗しているのだから、自分が正直にルールを守っても意味がない」という考えが広まると、社会全体の規範意識は低下します。利己的な行動やルール違反が正当化されやすくなり、協力や互恵の精神は失われていくでしょう。
多くの研究が、制度への不信が社会関係を損なう証拠を提示しています。例えば、ある実験では、参加者に政府が陰謀を企てているという内容の文章を読んでもらいました。すると、そうでない文章を読んだ参加者に比べて、その後の「信頼ゲーム」で見知らぬ相手に渡す金額が少なくなりました。制度への不信が、直接的な面識のない他者への不信にまで波及することを示しています。様々な国で行われた調査からは、政治への不信感が強い人ほど、納税を逃れたり、公共交通機関で不正乗車したりすることを容認しやすいという関連が見出されています。
この問題は個人の行動レベルを超え、集団間の関係にも及んでいきます。欧州連合(EU)で行われた調査では、自国の制度を信頼していない人ほど、移民に対しても不信感を抱きやすいという関連が見られました。別の分析では、このような移民への不信感が、英国のEU離脱(ブレグジット)への投票行動を後押しした可能性が指摘されています。
陰謀論は、特定の集団を「敵」として描き出すことで、社会の分断を煽り、政治的な対立を先鋭化させる可能性があります。職場という身近な環境でも、経営陣や上司に関する陰謀論を信じている従業員は、仕事への満足度が低く、会社を辞めたいと考える度合いが高いことも報告されています。
陰謀論は無力感や不信感など複数の心理特性と結ぶ
ここまで、陰謀論的な思考が権力への敵意や制度全体への不信と結びついていることを見てきました。それは、社会の安定を内側から揺るがす力となりえます。それでは、どのような心理的な背景を持つ人々が、こうした陰謀論的な世界観に惹かれやすいのでしょうか。この問いに答えるため、ある研究が、陰謀論への信念と個人の多様なパーソナリティ特性との関連を包括的に調査しました[3]。この研究は、陰謀論という現象を個人の内面から理解しようとする、初期の重要な試みの一つです。
この研究では、アメリカの大学生を対象に、質問紙調査が実施されました。調査内容は多岐にわたり、陰謀論に関する信念だけでなく、アノミー(社会の規範が崩壊していると感じる感覚)、権威主義、敵意、自己評価の高さ、そして「自分の人生は自分以外の力によってコントロールされている」と感じる度合い(外的統制感)など、11種類もの個人差が測定されました。
この研究の興味深い点は、陰謀論への信念を二つの異なるタイプに分けて捉えたことです。一つは、「特定の陰謀論への信念」です。これは、ケネディ大統領暗殺の真相や、ある有名人の死の真相など、具体的な出来事の背後に陰謀があったと信じる度合いを指します。もう一つは、「一般的な陰謀への態度」です。これは、個別の事件とは関係なく、広く「世の中の出来事は、往々にして陰謀によって動かされている」と考える世界観そのものへの賛同度を測るものです。
分析の結果、陰謀論への信念と個人の心理特性との間には、大きく分けて二つの異なる結びつきのパターンが存在することが浮かび上がってきました。
第一のパターンは、「特定の陰謀論への信念」と強く関連していました。このタイプの信念を抱きやすい人々は、心理特性として、特に「アノミー」のスコアが高いことが特徴でした。社会のルールや価値観が乱れ、自分がどこにも所属していないかのような感覚を強く抱いているのです。それに加えて、「低い自己評価」、「権威主義的な傾向」、そして「無力感」も関連していました。この組み合わせが描き出す人物像は、社会からの疎外感に苦しみ、自分に自信が持てず、強いリーダーシップを求める一方で、自分自身の力では何も変えられないという無力さを感じている姿です。
このような心理状態にあるとき、特定の事件の背後に「邪悪な敵」の存在を想定する陰謀論は、自らの不満や不幸の原因を分かりやすく説明し、非難の対象を与えてくれる物語として魅力的に映るのかもしれません。
第二のパターンは、「一般的な陰謀への態度」と結びついていました。こちらの世界観を持つ人々は、心理特性として、とりわけ「他者への信頼感が低い」こと、そして「外的統制感が高い」ことが際立っていました。特定の敵を想定するというよりも、広く人間一般や社会システムそのものを信じておらず、自分の運命は自分以外の何かによって決められているという諦観に近い感覚を持っているようです。他者に対する「敵意」の高さも、このパターンと関連していました。世界全体に対する根源的な不信と警戒心に基づいた、より全般的な陰謀観と言えるでしょう。
職場でのいじめ経験は陰謀論への傾向を高める
無力感や社会への不信といった心理的な状態が、人々を陰謀論へと向かわせることを見てきました。こうした感覚は、社会全体の大きな動きの中から生まれることもありますが、私たちの生活に根ざした、より個人的な対人関係のストレスによって引き起こされることも少なくありません。その典型的な例が、「職場でのいじめ」です。ここでは、この身近でありながら深刻な問題が、どのように陰謀論的な思考と結びつくのかを探求した研究を紹介します[4]。
職場でのいじめとは、無視や情報隠し、悪意のある噂、あるいは業務上の妨害といったネガティブな行為が、一人の従業員に対して繰り返し行われる状況を指します。このような経験は、被害者の心に深い傷を残します。絶え間ない不安や、脅威に対する過剰な警戒心、そして「自分は周囲から悪意をもって狙われているのではないか」という被害妄想的な感覚を育むことがあります。
これらの心理的な反応は、陰謀論を信じやすい人々の心性と多くの共通点を持っています。この点に着目した研究者たちは、「職場でのいじめという被害体験が、陰謀論的な世界観を形成する引き金になるのではないか」という仮説を立てました。
この仮説を検証するため、横断調査が行われました。イギリスで働く数百人の社会人を対象に、オンラインでアンケートを実施し、過去半年間に職場でのいじめを経験したかどうか、被害妄想的な考えを持つ度合い、一般的な陰謀論をどの程度信じているかを尋ねました。
分析の結果、いじめの被害経験が多い人ほど、陰謀論を信じる度合いが高いという関連が確認されました。分析を進めると、この「いじめ経験」と「陰謀論への信念」との間の関係は、「被害妄想」という心理状態によって、その多くが説明できることが分かりました。これは、「職場でいじめられる」という経験が、「他人は自分を陥れようとしているのではないか」という疑心暗鬼(被害妄想)を生み出し、その疑いの目がやがて、社会で起こる様々な出来事の背後にも悪意ある計画があるのではないか、と考える陰謀論的な思考へとつながっていく、という連鎖の存在を示唆しています。
ただし、このような調査だけでは、いじめが原因で陰謀論を信じるようになったのか、あるいは元々陰謀論を信じやすい人がいじめの被害を報告しやすいだけなのか、分かりません。
そこで、研究者たちは実験を行いました。オンラインで募集した参加者を無作為に二つのグループに分け、一方のグループには「職場で上司や同僚から無視されたり、噂を流されたりする場面」を、もう一方のグループには「同僚から仕事を手伝ってもらったり、励まされたりする支援的な場面」を、それぞれ想像してもらいました。その後、両方のグループに、いくつかの陰謀論に対する信念の度合いを測定する質問に回答してもらったのです。
結果は、仮説を支持するものでした。いじめられる場面を想像したグループは、支援的な場面を想像したグループと比較して、陰謀論を信じる度合いが統計的に有意に高かったのです。この結果は、いじめのようなネガティブな対人関係の経験が、陰謀論的な思考を一時的にであれ引き起こす原因となりうることを示しています。
この実験で興味深いのは、いじめを想像したグループでは被害妄想の度合いも高まったものの、それが陰謀論への信念を強める直接的な仲立ちとなっているという証拠は見られなかった点です。このことは、いじめという体験が、被害妄想を介するルートだけでなく、もっと直接的に、あるいはコントロール感を失うといった他の複雑な心理プロセスを通じて、陰謀論的な思考につながる可能性を示唆しています。
不確実な状況では権威の道徳性で陰謀論が左右される
社会が大きな変動に見舞われたり、経済の先行きが不透明になったりすると、人々は心の中に言いようのない不安を抱えます。このような「不確実性」の高い状況では、私たちは何とかして事態を理解し、コントロール感を取り戻そうとします。陰謀論は、複雑で分かりにくい出来事に対して、「すべては裏で糸を引く誰かの計画なのだ」という、一見すると明快な説明を与えてくれるため、こうした状況で魅力的な選択肢として浮上することがあります。
しかし、話はそう単純ではありません。不確実な状況が、常に人々を陰謀論へと駆り立てるわけではないのです。ある研究では、不確実性がむしろ人々を既存の権威や制度に頼らせる方向に動かすことも報告されており、一見すると矛盾した結果が存在していました。
この矛盾を解き明かす鍵は、どこにあるのでしょうか。ある研究者たちは、その鍵が「権威の道徳性」にあるのではないかと考えました[5]。研究者たちが立てた仮説はこうです。
人は、先行きが見えず不安な「不確実な」状況にあるときほど、判断の拠り所として、権威を持つ存在(例えば、政府や大企業)が「道徳的」に行動しているか、「不道徳的」に行動しているかという情報に敏感になる。権威が道徳的だと判断されれば陰謀論を退け、不道徳だと判断されれば陰謀論を強く支持するようになるというものです。不確実性が、いわば道徳性を評価する心のスイッチを入れるのではないかと考えたのです。
この仮説を検証するために、二つの実験が行われました。最初の実験では、大学生に参加してもらい、参加者の一部に、過去に自分が「不確実だ」と感じた個人的な経験について文章を書いてもらうことで、意図的に不確実な心理状態を作り出しました。比較のためのグループには、最近見たテレビ番組について書いてもらいました。
次に、全員にある大手石油企業に関する短い記事を読んでもらいました。記事の内容は二種類あり、一方はその企業が「開発途上国で環境保護や人権尊重に努めている」という道徳的な内容、もう一方は「環境を破壊し、劣悪な労働条件で人々を搾取している」という不道徳な内容でした。最後に、イラク戦争の背後にはこの石油企業の陰謀があったとする説をどの程度信じるかを尋ねました。
結果、不確実な気持ちにさせられた参加者の間でのみ、読む記事の内容によって陰謀論への支持度が大きく分かれました。企業の不道徳な側面を読んだ人々は陰謀論を強く支持したのに対し、道徳的な側面を読んだ人々はその説を退けました。一方で、不確実でない心理状態の参加者たちは、記事の道徳的な内容にそれほど判断を左右されることはありませんでした。
研究者たちは、この結果が特定の企業や政治問題に限定されたものではないことを確認するため、第二の実験を行いました。今度は、参加者のほとんどが事前知識を持っていないであろう、架空のアフリカの国を舞台に設定しました。手続きは研究1とほぼ同じです。まず参加者を不確実な心理状態に導いた後、その国の政府について、「汚職が蔓延している」という不道徳な新聞記事か、「国の財政を公正に運営している」という道徳的な記事を読ませました。そして、その国で起きた野党指導者の交通事故死が、実は政府による暗殺だったのではないか、という陰謀論への支持度を測定しました。
ここでも、研究1と同じパターンが再現されました。不確実な状況下に置かれた参加者は、政府が不道徳であるという情報に触れると陰謀論を信じやすくなり、政府が道徳的であるという情報に触れると信じにくくなったのです。これらの実験が明らかにしたのは、不確実性という心理状態が、それ自体で直接的に陰謀論を生み出すわけではない、ということです。不確実性は、私たちが世界を理解するためのコンパスとして、「権威の道徳性」という情報に強く依存するよう、心のモードを切り替える働きをしていました。
脚注
[1] Imhoff, R., and Bruder, M. (2014). Speaking (un-)truth to power: Conspiracy mentality as a generalized political attitude. European Journal of Personality, 28(1), 25-43.
[2] van Prooijen, J.-W., Spadaro, G., and Wang, H. (2022). Suspicion of institutions: How distrust and conspiracy theories deteriorate social relationships. Current Opinion in Psychology, 43, 65-69.
[3] Abalakina-Paap, M., Stephan, W. G., Craig, T., and Gregory, W. L. (1999). Beliefs in conspiracies. Political Psychology, 20(3), 637-647.
[4] Jolley, D., and Lantian, A. (2022). Bullying and conspiracy theories: Experiences of workplace bullying and the tendency to engage in conspiracy theorizing. Social Psychology, 53(4), 198-208.
[5] van Prooijen, J.-W., and Jostmann, N. B. (2013). Belief in conspiracy theories: The influence of uncertainty and perceived morality. European Journal of Social Psychology, 43(1), 109-115.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。