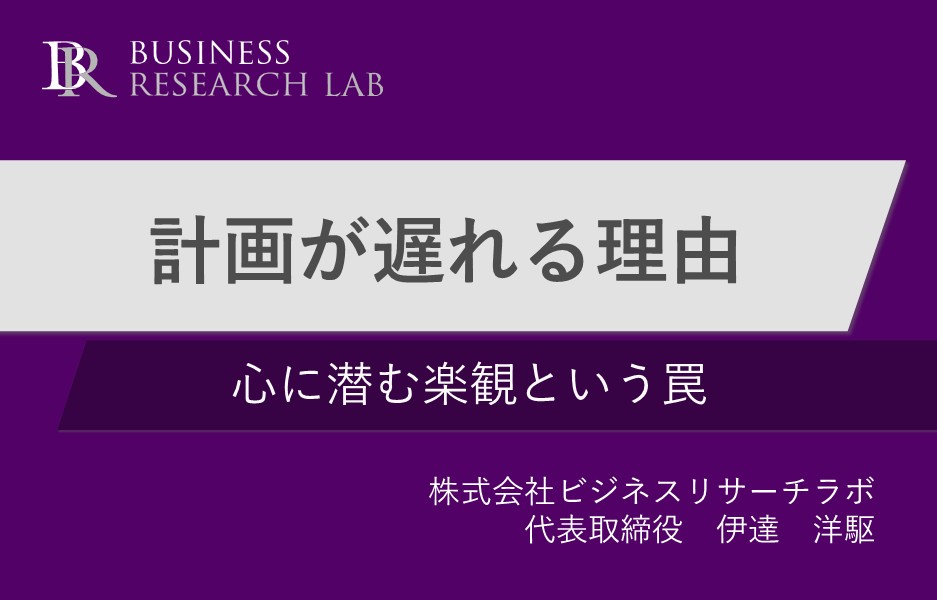2025年11月27日
計画が遅れる理由:心に潜む楽観という罠
職場で「このタスクなら数日で終わります」と宣言したものの、締め切り間際に連日残業でなんとか帳尻を合わせた経験。一度はこのような計画の遅延に頭を悩ませたことがあるのではないでしょうか。私たちはなぜ、計画通りに物事を進めるのが苦手なのでしょうか。能力が足りないからでしょうか。それとも、やる気に問題があるのでしょうか。
もちろん、それらが一因である場合もあるでしょう。しかし、計画が遅れる原因は、もっと根深い人間の心の働きに潜んでいるのかもしれません。それは例えば、「自分だけは大丈夫」という根拠のない自信です。この感覚は、私たちが未来を予測する際に、無意識のうちに物事を自分に都合の良い方向へと解釈させてしまう「楽観バイアス」と呼ばれる心理的な罠の一端です。
本コラムでは、計画の遅延を引き起こす厄介な心の癖の正体を、多角的に考察していきます。私たちがどのような思考の落とし穴にはまりやすいのか、そのメカニズムを観察することから始めたいと思います。自分や他者の計画がなぜ遅れるのか、その背景にある心の働きを理解することは、日々の仕事や生活における様々な「うまくいかない」ことへの見方を変える、第一歩となるはずです。
自分は楽観、他者は悲観で予測する
私たちは、自分自身の未来については明るい見通しを立てる傾向があります。一方で、他人の未来については、どこか冷静で、時として厳しい視線を向けてしまうことがあります。この態度の使い分けは、一体どこから来るのでしょうか。自分自身の計画を立てる際の楽観的な視点と、他者を観察する際の悲観的な視点。この二重基準が、計画錯誤の謎を解く鍵となります。この現象を、学業や恋愛といった二つの領域から探った一連の研究があります[1]。
この研究は、人々が自分自身の課題完了にかかる時間や、恋愛関係が続く確率をどのように予測するのかを調べたものです。大学生に卒業論文や毎週の課題といった学業タスクを対象に、それがいつ終わるかを予測してもらいました。そして、実際にそのタスクが完了した日付を記録し、予測と現実のずれを比較しました。その結果、学生たちの予測は、実際にかかった時間の平均して約半分と、著しく楽観的でした。ほとんどの人が、自分が想定していたよりもずっと多くの時間を要していました。
しかし、予測は楽観的に外れてはいたものの、予測した完了日と実際に完了した日の間には、しっかりとした関連が見られました。「早く終わる」と予測した人ほど、実際に早く終わらせるという、相対的な順序は保たれていたのです。人々が自分の能力や課題の難易度をまったく理解していないわけではなく、全体的に時間感覚が楽観的な方向へとずれていることを物語っています。
なぜこのような楽観的なずれが生じるのでしょうか。研究者たちは、予測を立てる際の思考プロセスにメスを入れました。参加者に、予測をしながら考えていることをすべて口に出してもらうという手法を用いました。すると、思考内容の大部分が、「まずこの部分を終わらせて、次にこれをこうして・・・」といった、理想的な未来のシナリオを組み立てることに費やされていることがわかりました。
一方で、「過去に似たような課題で遅れた経験」への言及や、「予期せぬトラブルが起こる可能性」といった潜在的な障害の想起はほとんどありませんでした。私たちの頭の中は、物事がスムーズに進む計画図で埋め尽くされ、過去の失敗や未来の障害といったネガティブな情報が入る余地はなかったのです。このような、自分の計画の内側から未来を構想する視点を「内的視点」と呼びます。
「内的視点」の対極にあるのが、自分を客観的に見て、過去のデータや一般的な確率に基づいて判断する「外的視点」です。この違いを確かめるために、研究者たちは、当事者ではない第三者(観察者)に、同じ学生の課題完了を予測させました。
すると、観察者の予測は、当事者本人よりもずっと控えめで、悲観的でした。その予測は当事者の楽観的な予測よりも、実際の完了日時に近いものでした。観察者は、当事者のように未来の計画に没入するのではなく、「この学生の過去の成績はこうだから」「一般的にこの種の課題はこれくらいかかるものだ」といった、客観的な分布情報、つまり「外的視点」から判断する傾向がありました。
この自己と他者での予測の非対称性は、恋愛関係の将来予測という異なる領域でも再現されました。研究では、交際中のカップル本人(アクター)と、そのカップルのことを全く知らない人々(オブザーバー)に、その関係が将来どれくらい継続するかの確率を予測してもらい、その後2年間にわたって追跡調査を行いました。結果、アクターである当事者たちは、自分たちの関係の未来を過度に楽観視していました。一方で、オブザーバーたちの予測は一貫して悲観的で、実際よりも低く見積もっていました。
問題は、予測の出発点となる基準が、当事者は楽観的な方向に、観察者は悲観的な方向に、それぞれずれていたことにあります。観察者の悲観は、情報が足りないから生じたのではありません。むしろ、「一般的に言って、若いカップルの関係は長続きしないものだ」という、世の中の平均的なデータを適用した結果だと考えられます。
悲観シナリオを軽視し、楽観見積で作業が遅延
私たちが自分の計画を立てる際、いかに未来の理想的なシナリオ、つまり「内的視点」に頼りがちであるかを見てきました。過去の失敗や起こりうる障害といったネガティブな情報は、思考の片隅へと追いやられてしまいます。もし強制的に「最悪の場合」を考えさせられたとしたら、私たちの楽観的な予測は、より現実的なものへと修正されるのでしょうか。この問いに答えるため、ある研究者グループが、5つの連続した実験を通じて、悲観シナリオを考えることの有効性を検証しました[2]。
最初の実験では、大学生に、3週間以内に提出するレポート課題について、完了予定日を予測してもらいました。その際、参加者をグループに分け、あるグループには「課題が最も順調に進んだ場合のシナリオ(ベストケース)」を、別のグループには「最も問題が起こった場合のシナリオ(ワーストケース)」を、最後のグループには「最も現実的にありそうなシナリオ」を、それぞれ文章で記述してもらいました。その上で、最終的な完了予測日を尋ねました。
結果は、悲観シナリオの有効性に疑問を投げかけるものでした。「現実的なシナリオ」を書いたグループの内容は、「ベストケース」のシナリオと似通っており、楽観的な見通しに満ちていました。多くの学生にとって、現実とは順調に進むことだったのです。一方、「ワーストケース」を書いたグループは、確かに「体調を崩すかもしれない」「他の課題が忙しくなるかもしれない」といった様々な障害を列挙しました。
しかし、いざ最終的な完了予測を立てる段になると、自ら書き出したはずのその悲観的なシナリオを「信頼性が低い」「まあ、こんなことは起こらないだろう」と判断し、予測にはほとんど反映させませんでした。結果的に、どのグループも平均して楽観的な予測を立て、計画錯誤は解消されませんでした。
シナリオを一つだけでなく、複数考えさせたらどうでしょうか。二つ目の実験では、学生に「もし別の展開があるとしたら」と促し、一つの課題について合計三つの異なるシナリオを自由に生成させました。すると、興味深い順序性が現れました。学生たちが最初に思いつくのは、決まって最も楽観的で、問題点への言及が少ないシナリオでした。二番目、三番目と進むにつれて、徐々に悲観的な内容になっていきました。
しかし、ここでも問題が起きます。最終的な完了予測を立てる際、参考にしたのは一番目と二番目のシナリオであり、最も悲観的で、そして実は最も現実に近い予測を導き出せたはずの三番目のシナリオは無視されてしまったのです。
悲観的なシナリオが無視されるのは、それが後から出てくるからかもしれません。三つ目の実験では、この順序の作用を検証しました。あるグループには「ベストケース」を考えてから「ワーストケース」を、別のグループには「ワーストケース」を考えてから「ベストケース」を考えてもらい、予測を立てさせました。しかし、結果は変わりませんでした。最初に悲観的なシナリオを突きつけられても、最終的な予測は楽観的なシナリオの方に引きずられ、ワーストケースはまたしても考慮の外に置かれてしまいました。
もしかしたら、問題はシナリオの楽観・悲観という性質そのものではなく、その「もっともらしさ」にあるのかもしれません。四つ目の実験では、この点を検証するために、より統制された状況が設定されました。課題は、多くの人にとって馴染み深い「税の申告」です。研究者たちは、楽観的なシナリオ(例:4月上旬に郵送完了)と悲観的なシナリオ(例:締切間際の4月下旬に郵送完了)を用意し、それぞれに「もっともらしい理由」と「もっともらしくない理由」を付けて参加者に提示しました。
結果、シナリオの「もっともらしさ」が予測に作用したのは、楽観シナリオの場合だけでした。もっともらしい楽観シナリオを読むと、人々は予測をさらに早めました。一方、悲観シナリオは、たとえどれだけもっともらしい理由が付けられていようとも、やはり無視されるという結果になりました。
これまでの実験はすべて、課題の当事者を対象としていました。最後の五つ目の実験では、視点を変え、当事者ではない第三者(観察者)に、四つ目の実験で使われたシナリオを読ませて予測を立ててもらいました。すると、様相は一変します。観察者の予測は、読んだシナリオの内容に素直に動かされたのです。楽観シナリオを読めば楽観的に、悲観シナリオを読めば悲観的に予測しました。当事者にとっては「ありえない」と無視された悲観的な情報が、利害関係のない観察者にはすんなりと受け入れられました。
粉飾された最悪案ほど採択される
個人の計画における楽観的な見積もりの誤りは、締め切り前の苦労や個人的な信用の失墜といった、比較的小さな代償で済むかもしれません。しかし、この「自分は大丈夫」という思考の歪みが、多くの税金が投入され、人々の生活に長期的な影響をあたえる大規模インフラプロジェクトの意思決定にまで及んだとしたら、その結果は計り知れないものとなります。ここでは、世界中の公共事業で常態化している天文学的なコスト超過と需要予測の失敗に目を向け、その背後で働く力学を解き明かした研究を紹介します[3]。
この研究は、なぜこれほど多くのインフラ計画が、完成する頃には当初の予算を大幅に上回り、期待されたほどの利用者を集められないのか、という問いに、大規模なデータセットを用いて挑んだものです。分析対象は20か国、258件に及ぶ鉄道、橋、トンネル、道路などの巨大プロジェクト。その結果、一部の失敗例が平均値を引き上げているのではなく、実に9割ものプロジェクトが程度の差こそあれコスト超過を経験するという、構造的な問題があることがわかりました。
需要予測の精度は、さらに深刻です。例えば鉄道の実際の利用者数は、事前の予測を下回っていました。そして問題なのは、これらの誤差が、過去70年間にわたって一向に改善されていないという事実です。技術が進歩し、予測モデルが洗練されても、計画と現実の乖離は埋まらないままです。
なぜ、このような事態が繰り返されるのでしょうか。研究では、その原因として三つの可能性が検討されました。一つ目は、データ不足や予測モデルの限界といった「技術的な不備」です。しかし、もしこれが主たる原因であれば、誤差はコストが下振れしたり、需要が上振れしたりと、プラスとマイナスの両方向に現れるはずです。常にコストは超過し、需要は不足するという一方向への偏りは、この説では説明がつきません。
二つ目は、計画担当者が純粋に「このプロジェクトはうまくいく」と信じ込んでしまう「心理的な楽観バイアス」です。確かに、これまでで見てきたように、人間の心にはそうした性質があります。しかし、専門家たちが何十年もの間、同じ失敗を繰り返しながら、全く学習しないというのは非現実的です。
そこで、最も説得力のある説明として浮上するのが、三つ目の「政治経済的な要因」、すなわち「戦略的な粉飾」です。これは、限られた予算や資金を獲得するための熾烈な競争の中で、プロジェクトの関係者が、意図的にコストを過少に、便益を過大に見せかけるという行為です。見栄えの良い分析を提示することが、プロジェクト承認への切符となる。このインセンティブ構造が、計画段階での予測を歪ませているというのです。
個人の計画における楽観バイアスが、社会的なプロジェクトの文脈では、予算獲得という動機によって増幅され、意図的な「粉飾」へと姿を変える。この事実は、楽観的な見通しを持つことへの「動機」が、私たちの判断をいかに大きく狂わせるかを示唆しています。
早く終えたい願望が過去の軽視を招き予測だけが早くなる
私たちはこれまでのところで、計画を立てる際に未来の理想的なシナリオに偏ってしまう思考の癖や、たとえ考え出したとしても悲観的な情報を無視してしまう心の働きを見てきました。そして、大規模なプロジェクトにおいては、「予算を獲得したい」という動機が、予測を意図的に歪ませる「戦略的粉飾」にまでつながることを見てきました。最後に、再び私たちの身近な計画に視点を戻し、「早く終わらせたい」という、誰もが持つごく自然な願望そのものが、いかにして私たちの判断を曇らせ、楽観的な予測を生み出し、計画の遅延を招いてしまうのか、その心の仕組みを解き明かした研究に光を当てます[4]。
この研究が探求したのは、「動機づけられた推論」が計画錯誤に果たす役割です。「動機づけられた推論」とは、私たちが何かを強く望むとき、その望ましい結論を支持するような情報ばかりを集め、解釈してしまう心の働きを指します。研究者たちは、「早く課題を終わらせたい」という動機が、どのようにして思考プロセスそのものを変化させ、楽観バイアスを増幅させるのかを、現実の課題と実験室での統制された実験の両面から検証しました。
最初の調査は、カナダの一般市民を対象とした、年に一度の「所得税の申告」という現実的な課題を舞台に行われました。この課題には、動機を自然に操作できる仕組みがあります。それは還付金の存在です。申告を早く済ませれば、それだけ早く還付金が手元に戻ってくるため、「還付を期待している人々」は、そうでない人々に比べて、「早く申告を終わらせたい」という動機が強いと考えられます。研究者たちは、この「還付期待群」と「非還付群」で、申告書の提出予定日(予測)と、実際に投函された日(現実)を比較しました。
結果、「早くお金が欲しい」という動機を持つ還付期待群は、非還付群に比べて、提出予定日を早く予測していました。還付期待群が締切の平均27.5日前に提出すると予測したのに対し、非還付群の予測は平均16.9日前でした。しかし、実際の提出日を見てみると、両方のグループで統計的な差はほとんど見られませんでした。「早く終わらせたい」という強い動機は、実際の行動を早めることにはつながらず、予測だけを非現実的に早めていたのです。その結果、予測と現実の乖離、すなわち楽観バイアスは、還付期待群において大きくなりました。
この「動機づけられた推論」のメカニズムを詳しく調べるため、実験室で大学生を対象とした実験が行われました。参加者には、いくつかの単語パズルを解いてもらい、その完了時間を予測させました。ここで、動機が操作されます。あるグループには、課題を早く終えるほど高額の報酬が与えられ(スピード報酬)、別のグループには、予測が正確であるほど報酬が与えられました(正確性報酬)。
結果としては、スピード報酬、すなわち「早く終わらせたい」という動機を与えられたグループは、完了予測時間を短く設定し、楽観バイアスが大きくなるという結果が出ました。一方で、正確な予測をすることに報酬が与えられたグループは、より慎重に時間を予測し、バイアスが抑制されました。
この研究の面白いのは、なぜ動機がバイアスを生むのか、その思考プロセスの中身にまで踏み込んだ点にあります。参加者が予測を立てる際に考えていたことを自由に記述してもらった内容を分析したところ、違いが見られました。スピード報酬を与えられた人々は、「過去のトライでどれくらい時間がかかったか」といった過去の経験を思い出す記述が少なく、その代わりに「次はこうすればもっとうまくやれる」といった、未来の行動計画に関する記述が多かったのです。
これは、「早く終わらせたい」という動機が、私たちの注意の焦点を、苦い教訓を含むかもしれない「過去」から、希望に満ちた「未来」へとシフトさせることを示しています。過去の失敗経験を思い出すという、本来であれば現実的な予測に不可欠なプロセスが抑制され、その代わりに理想的な未来のシナリオだけが頭の中を占めるようになります。この思考内容の変化が、動機が楽観バイアスを増幅させるメカニズムだったのです。
脚注
[1] Buehler, R., Griffin, D., and Ross, M. (1995). It’s about time: Optimistic predictions in work and love. European Review of Social Psychology, 6(1), 1-32.
[2] Newby-Clark, I. R., Ross, M., Koehler, D. J., Buehler, R., and Griffin, D. (2000). People focus on optimistic scenarios and disregard pessimistic scenarios while predicting task completion times. Journal of Experimental Psychology: Applied, 6(3), 171-182.
[3] Flyvbjerg, B. (2009). Survival of the un-fittest: Why the worst infrastructure gets built -and what we can do about it. Oxford Review of Economic Policy, 25(3), 344-367.
[4] Buehler, R., Griffin, D., and MacDonald, H. (1997). The role of motivated reasoning in optimistic time predictions. Personality and Social Psychology Bulletin, 23(3), 238-247.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。