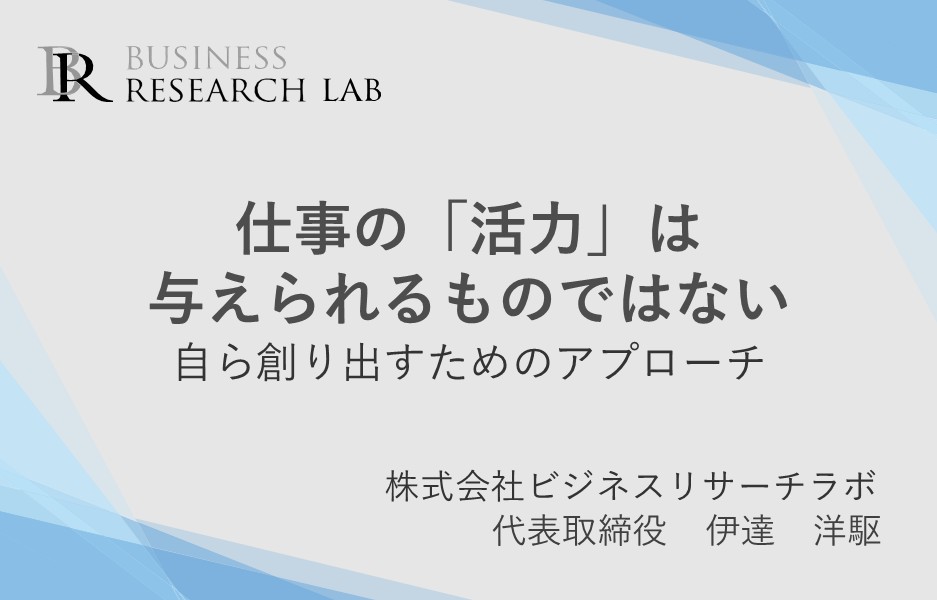2025年11月27日
仕事の「活力」は与えられるものではない:自ら創り出すためのアプローチ
私たちはキャリアを通じて、多くの時間を仕事に費やします。その時間を、ただ漫然と過ごすのではなく、生き生きと、そして何かを学びながら過ごしたいと願う人もいるでしょう。近年、このような状態を指し、「スライビング(thriving)」という概念が取り上げられるようになっています。これは、一時的な高揚感や満足感とは一線を画すものです。スライビングしている人とは、仕事を通じて「活力」にあふれ、同時に、新しい知識やスキルを身につけている「学習」の実感も得ている人を指します。
どうすれば仕事においてスライビングできるのでしょうか。生まれ持った才能や性格だけに左右されるのでしょうか。それとも、職場環境や人間関係がすべてを決めてしまうのでしょうか。この問いに答えることは、個人の幸福な職業人生にとってはもちろん、組織全体の活力を高める上でも、避けては通れない課題です。
本コラムでは、人がスライビングするに至るプロセスを検討していきます。特に光を当てるのは、「個人の主体的な行動」と、それを支える「他者との関係性」です。自ら動くことの力強さと、人とのつながりがもたらすエネルギーが、どのように絡み合い、私たちの内なる活力と学びの炎を燃え上がらせるのか。その繊細で力強いメカニズムを解き明かしていきます。
探索行動が文化を超え最大要因としてスライビングを高める
人が仕事で生き生きと学びながら働く「スライビング」という状態は、どのような要因によって育まれるのでしょうか。この問いに答えるため、世界中の研究者たちが、職場の環境、上司のリーダーシップ、個人の性格など、様々な角度から調査を行ってきました。しかし、個別の研究だけでは、どの要因が特に強く結びついているのか、その全体像を把握することは困難でした。そこで、これまでに蓄積されてきた研究成果を統合し、スライビングを生み出す要因の地図を描き出すことを試みた分析があります[1]。
この分析は、過去に行われた67件の研究、合計で28,000人を超える働く人々から得られたデータを集約する「メタ分析」という手法を用いています。研究者たちは、スライビングに関連する可能性のある要因を、大きく四つのカテゴリーに分類しました。一つ目は、裁量権の大きさや職場の支援体制といった「ユニット文脈特性」。二つ目は、上司からの支援や仕事の意味づけといった「仕事中に生成される資源」。三つ目は、自ら新しい知識を探し求めるなどの「主体的行動」。四つ目が、生まれ持った楽観性や誠実さといった「パーソナリティ特性」です。
分析の結果、これら四つのカテゴリーに含まれる多くの要因が、スライビングと正の関連を持つことが確認されました。例えば、自分の仕事の進め方を自分で決められる「自律性」や、上司や同僚から有益なフィードバックを得られる環境は、スライビングを後押ししていました。部下を力づけ、支援するようなリーダーシップや、自分の仕事に前向きな意味を見出すことも、同様に活力と学習の感覚を高めていました。個人の性格に目を向けると、自分ならできると感じる「自己効力感」や、物事の明るい側面を見る「楽観性」も、スライビングと結びついていたのです。
しかし、これらの数多くの要因の中で、とりわけ強い結びつきを示したのが、「主体的行動」のカテゴリーに含まれる「探索行動」でした。探索行動とは、現状に安住せず、新しい知識やスキル、より良い仕事のやり方などを自ら探し求める行動を指します。この自発的な探求の営みが、他のどのような環境要因や個人的特性よりも、スライビングという心理状態を予測する結果となりました。
さらに、文化の違いが、これらの関連の強さにどう作用するかも検証されました。特に「個人主義―集団主義」という文化的な価値観の軸で比較が行われました。その結果、アメリカや西ヨーロッパのような個人主義的な文化圏では、「個人の裁量」や「支援的な風土」がスライビングとより強く結びつくのに対して、アジアやラテンアメリカのようないくつかの集団主義的な文化圏では、「組織の公正さ」や、ここで述べた「探索行動」が、スライビングとの関連を一層強めるというパターンが見られました。
これらの結果から何が読み取れるでしょうか。まず、探索行動が最も強い関連を持っていたという事実は、スライビングが、誰かから与えられるのを待つ受動的な状態ではなく、自らの能動的な働きかけによって勝ち取られるものであることを物語っています。新しい知識を求め、未知の領域に足を踏み入れる行為が、スライビングの構成要素である「学習」を直接的に満たします。その挑戦を通じて小さな成功を積み重ね、自身の成長を実感することが、もう一つの構成要素である「活力」の源泉となるのでしょう。
仕事の意義付けが日内スライビングを高める
様々な要因の中でも個人の「探索行動」がスライビングと最も強く結びついていることを見ました。これは、スライビングが個人の能動的な営みであることを教えてくれます。しかし、私たちの意欲やエネルギーは、常に一定ではありません。ある日は朝から活力に満ちているのに、別の日には何となく気分が乗らない、という経験は誰にでもあるでしょう。このことから、スライビングは固定的な特性というよりも、日々の経験によって揺れ動く、動的な心理状態であると捉えることができます。
この「スライビングの日内変動」という側面に光を当てた研究があります[2]。この研究の目的は、1日という短い時間単位の中で、仕事始めに経験することが、その日の終わりのスライビングにどう結びつくのか、そのプロセスを解き明かすことでした。研究者たちは、スライビングは「資源」→「主体的行動」→「スライビング」という流れで生まれるのではないか、という仮説を立てました。ここでいう「資源」とは、仕事を通じて得られるポジティブな経験のことで、具体的には「仕事のポジティブな意味づけ」「良好な人間関係」「新しい知識」の三つが想定されました。
この仮説を検証するために、ドイツの社会福祉サービスで働く121人の従業員を対象とした、「日記式調査」という手法が用いられました。参加者は、月曜日から金曜日までの連続5日間、毎日3回、ウェブ上のアンケートに回答するよう求められました。測定のタイミングは、始業から2時間後の「朝」、昼休み後の「昼」、そして「終業時」です。朝の調査では、その日の仕事から得られる「資源」について尋ね、昼の調査ではタスクへの集中や探索といった「主体的行動」について、終業時の調査で「スライビング(活力と学習)」のレベルを測定しました。このように時間差を設けることで、「朝の経験が、昼の行動を介して、夜のスライビングにつながる」という流れを捉えようとしたのです。
分析の結果、朝の時点で「今日の自分の仕事には、他者や社会にとって良い意味がある」と感じていた日ほど、その日の終業時に報告された「活力」と「学習」の感覚、すなわちスライビングのレベルが高いことがわかりました。朝の時間帯に新しい知識を得る機会があった日も、終業時の「学習」の実感が高まっていました。一方で、朝の時点で同僚との関係が良好であると感じることは、その日のスライビングのレベルとは直接的な関連が見られませんでした。
さらに分析を進めたところ、「仕事のポジティブな意味づけ」は、スライビングを直接高めるだけでなく、昼の時点での「タスクへの集中」や「探索行動」を促し、それらの行動が終業時のスライビングを高める、という間接的な経路が確認されました。朝に「自分の仕事は価値がある」と感じることが、その日一日の仕事への向き合い方を変え、より集中し、より探求的にさせることで、最終的に充実した1日の終わりをもたらしていたのです。
この結果は、私たちに何を教えてくれるでしょうか。それは、1日の始まりに自分の仕事の意義や価値を心に抱くことが、その日全体の心理的なエネルギー循環における「点火プラグ」のような働きをするということです。大きな目標やキャリアプランも大切ですが、それと同じくらい、「今日この日」の仕事が持つ意味をかみしめることが、日々の活力を生み出す上で欠かせないのかもしれません。
変革的上司は開放的な部下のスライビングを高め、燃え尽きを防ぐ
個人の主体的な行動や日々の意味づけが、どのようにスライビングという豊かな状態を生み出すかを見てきました。しかし、これらの内的なプロセスは、職場の人間関係、特に上司と部下という関係性から切り離して考えることはできません。上司からの働きかけは、部下の心に火を灯すこともあれば、逆にその火を消してしまうこともあります。ここでは、特定のリーダーシップスタイルが、部下のスライビングを促し、ひいては精神的な消耗状態である「バーンアウト」を防ぐ上でどのような働きをするのか、そのプロセスがすべての部下に等しく当てはまるのかを探ります。
この問題意識に基づき、ある研究が「資源保存理論」という枠組みを用いて、一連のプロセスを検証しました[3]。この理論は、人々は自らにとって価値のある「資源」(エネルギー、スキル、良好な人間関係など)を維持・獲得しようと努めており、この資源が脅かされたり失われたりしたときにストレスを感じ、バーンアウトに至ると考えます。この研究では、上司の「変革型リーダーシップ」が部下にとっての重要な「資源」となり、それがスライビングという別の「資源」を生み出し、バーンアウトという資源の枯渇を防ぐのではないか、というモデルを想定しました。
「変革型リーダーシップ」とは、魅力的なビジョンを掲げて部下を鼓舞し、知的な好奇心を刺激して、一人ひとりの成長に配慮するようなリーダーのあり方を指します。この研究のユニークな点は、リーダーシップの効果が、部下のパーソナリティ、特に「経験への開放性」によって変わるのではないかと考えた点です。経験への開放性とは、新しい経験やアイデアに対する好奇心が強く、知的な探求を好む性格特性のことです。
調査は、ドイツの中規模製造業に勤める148人の従業員を対象に、2週間の間隔をあけて2回にわたって行われました。1回目の調査では、直属の上司の変革型リーダーシップの度合い、自分自身のスライビングの状態、経験への開放性などの性格特性を測定しました。2週間後の2回目の調査で、バーンアウトのレベルを測定しました。このように時間をずらして測定することで、「リーダーシップがスライビングを高め、それが後のバーンアウトを低減させる」という時間的な流れを検証しようとしました。
分析の結果、仮説を支持する一連の関連が明らかになりました。変革型リーダーシップを実践していると部下が認識しているほど、部下はスライビングを経験していました。また、スライビングを経験している部下ほど、2週間後のバーンアウトのレベルが低いという関係も見られました。これは、変革型リーダーが部下の活力と学習を促進することを通じて、間接的に心の消耗を防いでいることを意味します。
しかし、このプロセスは誰にでも当てはまるわけではありませんでした。部下の「経験への開放性」が、この連鎖の強さを左右していました。具体的には、経験への開放性が高い、つまり好奇心旺盛で新しい物事を好む部下に対しては、変革型リーダーシップはスライビングを強く引き出していました。一方で、経験への開放性が低い部下、つまり慣れ親しんだやり方を好み、変化に対して慎重な部下に対しては、変革型リーダーシップはスライビングを十分に高めることができていませんでした。
この結果が物語るのは、上司からの働きかけという「資源」も、それを受け取る部下側の準備や特性によって、その価値が変わるということです。変革型リーダーが提供する「知的な刺激」や「新しい視点での挑戦の促し」は、もともと新しい経験を渇望している開放性の高い人にとっては、まさに待望の恵みとなります。その恵みを受け取ることで、活力と学習のサイクルが回り始め、スライビングに至るのでしょう。しかし、安定を求める人にとっては、同じ働きかけが過度な刺激やストレスと受け取られてしまう可能性も否定できません。
信頼がつながりを介しスライビングと革新行動を高める
これまで、個人の主体的な行動、日々の意味づけ、上司との関係性といった、スライビングを育む様々な要因を個別に見てきました。最後に、これらの要素を統合し、より大きな視点からスライビングが生まれる生態系を捉えてみたいと思います。その生態系の根底に流れる水脈ともいえるのが、職場における「信頼」です。この目には見えない信頼という基盤が、人々の関係性の質を高め、それが個人のスライビングを促し、組織全体の活力となる「革新的な行動」へと結実していく。このダイナミックな連鎖を検証した研究があります[4]。
この研究が目指したのは、スライビングがもたらす成果を、個人のパフォーマンスや幸福感にとどまらず、組織の未来を切り拓く「革新的行動」にまで広げて捉えることでした。革新的行動とは、新しいアイデアを生み出し、それを実現するために周囲を巻き込み、最終的に形にしていく一連の自発的な行動を指します。この革新的行動の源泉としてスライビングがあり、さらにそのスライビングを生み出す土壌として、職場における「信頼」と、他者とオープンに関わり、共に何かを生み出そうとする「コネクティビティ(質の高いつながり)」が存在するのではないか、というモデルを定めました。
このモデルを検証するため、イスラエルの多様な業種で働く172人の従業員を対象とした調査が行われました。この調査も、時間的な前後関係を捉えるために、3週間の間隔をあけて2回にわたって実施されました。1回目の調査では、従業員が自分の組織をどれだけ信頼しているか、そして職場の同僚たちとどれだけ質の高いつながりを持っているか(コネクティビティ)を測定しました。3週間後の2回目の調査で、スライビングのレベルと、革新的な行動をどの程度とっているかを尋ねました。
分析から浮かび上がってきたのは、まさに仮説通りの連鎖でした。第一に、自分が所属する組織に対して高い信頼感を抱いている人ほど、職場の同僚たちとオープンで、互いに学び合えるような建設的な関係、すなわち質の高い「コネクティビティ」を築いていることがわかりました。組織という「場」が安全であると感じられるからこそ、人々は安心して心を開き、他者と深く関わることができるのでしょう。
第二に、この質の高いコネクティビティを持つ人ほど、3週間後の時点で、活力と学習に満ちたスライビング状態にあることが確認されました。他者とのオープンな交流は、新しい視点や知識をもたらし「学習」を促します。同時に、互いに認め合い、支え合う関係性は、心理的なエネルギー、すなわち「活力」を与えてくれます。
第三に、スライビングを経験している人ほど、新しいアイデアの創出やその実現に向けた行動、「革新的な行動」を多くとっていました。内側から湧き上がる活力と、学習によって得られた新しい視点が、現状をより良く変えようとする前向きな行動へと人々を駆り立てるのです。
これらの結果を統合すると、「組織への信頼が、質の高いコネクティビティを育み、そのコネクティビティが、個人のスライビングを促し、そしてスライビングが、革新的な行動の引き金となる」という、一連のプロセスが実証されたことになります。この研究は、目に見える革新という成果の根底に、個人の内的な心理状態(スライビング)があり、さらにその下には人間関係の質(コネクティビティ)、最も深い層には、組織全体を包む「信頼」という土壌が存在することを描き出したのです。
脚注
[1] Liu, D., Zhang, S., Wang, Y., and Yan, Y. (2021). The antecedents of thriving at work: A meta-analytic review. Frontiers in Psychology, 12, 659072.
[2] Niessen, C., Sonnentag, S., and Sach, F. (2012). Thriving at work: A diary study. Journal of Organizational Behavior, 33(4), 468-487.
[3] Hildenbrand, K., Sacramento, C. A., and Binnewies, C. (2018). Transformational leadership and burnout: The role of thriving and followers’ openness to experience. Journal of Occupational Health Psychology, 23(1), 31-43.
[4] Carmeli, A., and Spreitzer, G. M. (2009). Trust, connectivity, and thriving: Implications for innovative behaviors at work. Journal of Creative Behavior, 43(3), 169-191.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。