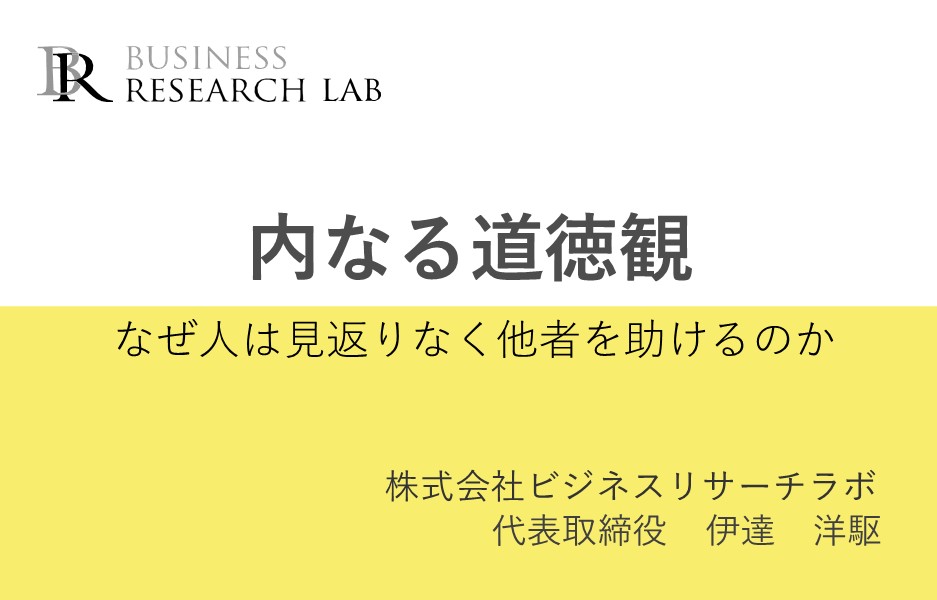2025年11月26日
内なる道徳観:なぜ人は見返りなく他者を助けるのか
私たちは、なぜ見返りを求めず他人を助けることがあるのでしょうか。あるいは、誰も見ていない場所で、ルールを破りたいという誘惑に駆られたとき、何が私たちの心にブレーキをかけるのでしょうか。社会は法律や規則、賞罰といった外的な仕組みによって秩序を保っていますが、それだけでは説明しきれない人間の行動があります。私たちの内側には、静かでありながらも確かに存在する「道徳」なるものがあるのかもしれません。
この内なる声は、時に私たちを励まし、善い行いへと背中を押してくれます。またある時には、過ちを犯さぬよう、強く私たちを引き留めます。しかし、この目に見えない道徳観が、具体的にどのような仕組みで私たちの行動を導いているのか、そのメカニズムはあまり知られていません。同じ状況に置かれても、ある人はためらわずに善行を選び、またある人は不正に手を染めてしまうのは、一体どうしてなのでしょうか。
本コラムでは、人の心の内側にある「道徳的な自己認識」が、私たちの行動にどのように結びついているのかを、社会心理学の様々な研究成果を手がかりに解き明かしていきます。自分とは異なる人々への配慮、実際の善行への一歩、不正を食い止める心の壁。こうした現象の背後にある、人間の心に秘められた仕組みを探求していきましょう。
強い道徳心は、自分と異なる人々への配慮を広げる
人間は、自分たちが所属する集団、例えば家族や友人、同じ国の人々に対しては、自然と親近感を抱き、好意的に振る舞う性質を持っています。一方で、自分たちとは異なる集団に属する人々、すなわち外国人や異なる文化を持つ人々に対しては、警戒心を抱いたり、距離を置いたりしやすいことも、古くから知られていました。この「身内びいき」は、人間の生存本能に根差した、ある意味で自然な心の働きともいえます。
しかし、もし誰もがこの性質に抗うことができなければ、社会の分断や対立は避けられないでしょう。では、この本能的な壁を乗り越え、より広い範囲の人々にまで思いやりを広げることを可能にする心の力は存在するのでしょうか。
この問いに答える鍵として、ある研究者たちは「モラル・アイデンティティ」という概念に光を当てました[1]。これは、「自分は思いやりがあり、公正で、正直な人間である」といった道徳的な価値観を、自分という存在の根幹にどれだけ置いているか、という自己認識の度合いを指します。この内なる道徳観が強い人ほど、配慮の輪を自分とは異なる人々、要するに「外集団」にまで広げられるのではないか、という仮説が立てられました。この仮説を検証するため、一連の調査や実験が行われました。
最初の調査では、大学生たちに、外国人や異なる宗教を信じる人々といった、自分たちの「外集団」にあたる人々に対して、どの程度の道徳的な義務を感じるかが尋ねられました。その結果、自分のことを道徳的だと強く認識している人ほど、これらの人々に対しても助けの手を差し伸べるべきだと考える度合いが強いことが分かりました。別の調査では、経営学を学ぶ大学院生たちに、ある資源(ここでは愛情や尊敬といった、お金では買えない個人的なもの)を、「親しい友人」と「全くの見知らぬ人」のどちらに与えるべきかと尋ねました。
多くの人が友人を優先しがちなこの問いに対し、道徳的な自己認識が強い人々は、見知らぬ人に対しても、友人と変わらないくらいの義務感を抱いていました。これは、彼ら彼女らの心の中では、見知らぬ人でさえも、配慮すべき対象として認識されていることを物語っています。
続いて、より厳しい状況下での心の働きが調べられました。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件から数ヶ月後という、社会全体が特定の集団に対する緊張感を抱えていた時期に、ある実験が行われました。参加者である学生たちに、国連が行う難民救援活動に関する記事を読んでもらい、その活動の妥当性を評価してもらったのです。救援の対象は、テロ事件と間接的に関連づけられていたアフガニスタンの難民と、無関係なトルコの難民の二つのグループが設定されました。
ここでも、道徳的な自己認識の強い人々は、救援活動をより高く評価しました。その傾向は、人々が複雑な感情を抱きやすいアフガニスタン難民への支援を評価する際に、特に顕著に見られました。対立を想起させるような状況であっても、その道徳観は揺らぐことなく、人道的な支援の必要性を認識させていたのです。
実際の行動との関連も調べられました。ある実験では、参加者に3ドルの現金を渡し、その一部あるいは全部を二つの団体に寄付してもらうという課題が与えられました。一つは自国であるアメリカの消防士や警察官の遺族を支援する団体(内集団)、もう一つはユニセフのアフガニスタン救援活動(外集団)です。同時に、参加者が自分を「アメリカ人である」とどれだけ強く思っているか(ナショナル・アイデンティティ)も測定されました。
結果、アメリカ人としての意識が強い人ほど、外集団への寄付額は少なくなるという、予想通りの結びつきが見られました。しかし、それとは別に、道徳的な自己認識が強い人ほど、外集団であるアフガニスタンのために、より多くのお金を寄付していました。道徳心は、時に愛国心のような強い感情と拮抗しながらも、人々の善意を国の境界線を越えて届けさせる力を持つことが示されました。
最後に、最も困難な問いが投げかけられました。テロ事件の悲惨な写真を見せた後、参加者に、軍事的な報復によって生じるかもしれない、敵対する集団の民間人の犠牲者を、何人までなら許容できるかと尋ねたのです。また、加害者を「いかなる手段を使っても殺すべきだ」という意見と、「許すべきだ」という意見のどちらがより道徳的だと思うかも評価してもらいました。
ここでも、道徳的な自己認識の強い人々は、一貫した姿勢を見せました。許容できる民間人の犠牲者数は少なく、報復的な殺害を非道徳的だと判断し、むしろ「許し」の方に道徳的な価値を見出していました。
内なる道徳観が、実際の善行を生む
「自分は道徳的でありたい」という自己認識が、自分とは異なる人々への配慮を広げる力を持つことを見てきました。この力の源である「モラル・アイデンティティ」は、一体どのようにして私たちの心の中に存在し、どのようにして具体的な行動へと変換されるのでしょうか。この概念の構造を解き明かし、それが実際の善行と結びつくまでの道のりを追った研究のプロセスを見ていきます[2]。
研究者たちはまず、「道徳的な人」とはどのような特徴を持つ人なのかを明らかにすることから始めました。多くの大学生に自由な言葉で表現してもらったところ、「思いやりのある」「憐れみ深い」「公正な」「親切な」「気前の良い」「助けになる」「勤勉な」「正直な」といった言葉が頻繁に挙げられました。これらの言葉は、私たちが共通して抱く道徳的な人物像の核となる要素といえるでしょう。
これらの道徳的な特徴を、人が自分自身のアイデンティティとしてどれだけ強く認識しているかを測るための、信頼できる「ものさし」を作る試みが行われました。その結果、モラル・アイデンティティには、大きく分けて二つの異なる側面があることが分かってきました。
一つは「内面化(Internalization)」と呼ばれる側面です。これは、道徳的な価値観が、その人の自己認識の中心的な部分を占めている度合いを指します。他人が見ていようが見ていまいが、自分自身の信念として、思いやりや正直さを深く内面に取り込んでいる状態です。もう一つは「顕示化(Symbolization)」と呼ばれる側面で、こちらは、道徳的な人間であることを、服装や行動、所属するグループなどを通じて、公に示したいという欲求の度合いを指します。周囲から「あの人は道徳的な人だ」と見られることで、自己認識を確かめようとする側面と言えるかもしれません。
この「内面化」と「顕示化」という二つの側面を持つ尺度の信頼性を確かめるため、研究者たちは多角的な検証を行いました。例えば、言葉の連想を利用した心理テスト(IAT)では、「私」という言葉と、「思いやり」などの道徳的な言葉を、人々が無意識のうちにどれだけ強く結びつけているかを測定しました。その結果、尺度の「内面化」の得点が高い人ほど、この無意識レベルでの結びつきが強いことが分かりました。これは、「内面化」が、単なる建前ではなく、その人の心の奥深い部分に根差した自己認識であることを裏付けています。
この尺度が他の心理的な特性とどのような関係にあるかも調べられました。その結果、例えば他者への共感性が高い人や、宗教性が高い人、あるいは高度な道徳的判断ができる人ほど、モラル・アイデンティティの得点も高いという、理論的に予測される通りの関連が見られました。一方で、自尊心の高さや、社会的な不安の強さといった、直接的には関係が薄いと考えられる特性とは、ほとんど関連が見られませんでした。
さらに、高校生に「自分自身について自由に紹介してください」と書いてもらうという調査も行われました。その数ヶ月前に測定しておいたモラル・アイデンティティの「内面化」の得点が高い生徒ほど、その自己紹介文の中に、道徳的な価値観に関する記述が自然と多く現れることが分かりました。これは、彼ら彼女らにとって道徳性が、自身を語る上で欠かせない要素となっていることを物語っています。
この内なる道徳観は、実際の行動にどれほど結びついているのでしょうか。ある調査では、大学の卒業生たちに、過去2年間にボランティア活動を行った経験があるかどうかを尋ねました。すると、「内面化」の得点が高いほど、ボランティアを経験している確率が高いことが分かりました。「顕示化」の得点が高いこともボランティア経験と関連していましたが、特に「内面化」の結びつきの強さが際立っていました。
最も説得力のある証拠の一つは、実際の寄付行動を観察した研究から得られました。高校でフードドライブ(食料品の寄付を募る活動)が実施された際、研究者たちは、どの生徒が、どれくらいの量の食料品を寄付したのかを、教師の協力を得て秘密裏に記録しました。その結果、事前に測定されていたモラル・アイデンティティの「内面化」の得点が高い生徒ほど、実際に寄付を行う確率が高く、また、寄付する食料品の量も多いことが確認されました。自己申告のアンケートだけでなく、客観的に観察された善行に対しても、内なる道徳観ははっきりとした結びつきを持っていたのです。
道徳的な人にとって善行は、行動につながる感動を生む
私たちはこれまでのところで、自分自身の内なる道徳観が、いかにして善行の種となるかを見てきました。しかし、善行のきっかけは、自分の中から湧き上がるものだけではありません。私たちは、他人が成し遂げた素晴らしい行為を見聞きしたときにも、心を揺さぶられ、何か善いことをしたいという気持ちに駆られることがあります。
ここでは、他者の卓越した善行が私たちの心に引き起こす特別な感情、「モラル・エレベーション」に焦点を当てます[3]。そして、内なる道徳観が強い人ほど、この感動をより強く経験し、それが次の善行へとつながっていくというメカニズムを解き明かしていきます。
「モラル・エレベーション」とは、他者の道徳的に優れた行為、例えば、大きな自己犠牲を払って他者を救う行為や、憎しみを乗り越えて相手を許す行為などに触れたときに生じる、特有の心の状態を指します。それは、胸が温かくなるような感覚、畏敬の念、そして「自分ももっと善い人間になりたい」という動機づけを伴うポジティブな感情体験です。この感動が、単純な気分の高揚とは異なり、利他的な行動を促すのではないかと考えられました。そして、この感動の度合いは、受け取る側のモラル・アイデンティティ、特にその「内面化」の強さによって変わるのではないか、という仮説が立てられました。
この仮説を検証するため、ある実験が行われました。参加した学生たちは、いくつかのグループに分けられ、それぞれ異なる短い記事を読んでもらいました。あるグループが読んだのは、学校で銃乱射事件を起こした犯人の家族を、被害者であるアーミッシュの共同体が赦し、さらには経済的な支援まで申し出たという、並外れた善行に関する実話でした。他のグループは、美しい夕日を眺めるという、道徳とは関係のないポジティブな体験や、日常的な親切に関する記事を読みました。
その後、参加者たちの感情や考えを尋ねたところ、予測通りの結果が得られました。並外れた善行の記事を読んだグループは、他のグループに比べて、格段に強いモラル・エレベーションを経験していました。そして、この感動の度合いは、もともとモラル・アイデンティティの「内面化」のスコアが高かった参加者において、特に強く現れました。
実験室の外での実体験との関連が調査されました。カナダの成人を対象とした調査で、過去に目撃したり聞いたりした「並外れた善行」について、自由に思い出して記述してもらったのです。ここでも、モラル・アイデンティティの「内面化」が強い人ほど、そのような善行の記憶を思い出す確率が高いことが分かりました。彼ら彼女らの心には、善行の記憶が深く刻み込まれやすいようです。分析を進めると、「内面化」の強さが、モラル・エレベーションという感動体験を引き起こし、その感動が「自分も誰かのために何かをしたい」という利他的な動機へとつながる、という一連の連鎖が統計的に確認されました。感動が、善意を行動へと橋渡しする役割を担っていたのです。
この道徳心を一時的に活性化させただけでも、行動は変わるのでしょうか。別の実験では、参加者に単語探しパズルを行ってもらい、あるグループのパズルには「親切」「正直」といった道徳的な言葉を、別のグループには中立的な言葉を紛れ込ませることで、無意識のうちに道徳心を刺激しました。その後、全員に卓越した善行に関する記事を読んでもらい、最後に、実験の謝礼として渡された20ドルを、自分と見知らぬ他者とで自由に分け合うという課題に取り組んでもらいました。結果、事前に道徳心を刺激されていた参加者は、そうでない参加者に比べて、見知らぬ他者に対して、より多くのお金を分け与えました。
最後の実験では、より現実的な状況設定で、このメカニズムが検証されました。参加者は、二種類のミュージックビデオのどちらかを見ました。一つは、ある歌手がビデオの制作費を全額慈善団体に寄付するという、善行そのものをテーマにした内容でした。もう一つは、同じ歌手の、情緒的ではあるものの道徳的なテーマとは無関係なビデオです。視聴後、参加者はモラル・エレベーションの度合いを評価され、その後、実験の謝礼の一部を、非営利団体に寄付するかどうかを尋ねられました。
ここでも、善行をテーマにしたビデオは、モラル・アイデンティティの「内面化」が強い参加者の心に、特に強いモラル・エレベーションを引き起こしました。そして、この高まった感動が、実際の寄付額の増加へと直接結びついていました。内面化のスコアが低い参加者では、どちらのビデオを見ても寄付額に変化はありませんでした。
人間不信は、不正を正当化する言い訳を生みやすい
これまでは、人の内なる道徳観が善行を促す光の側面を探求してきました。しかし、人間は常に道徳的でいられるわけではなく、時に良心に背を向け、不正な行為に手を染めてしまうことがあります。一体なぜ、人は悪いことだと知りながら、そうした行動をとってしまうのでしょうか。その背景にある「モラル・ディスエンゲージメント(道徳的関与の解除)」という心理的なメカニズムに焦点を当てます。これは、人が不正を働くために、自分自身に対して巧妙な「言い訳」を作り出し、罪悪感を麻痺させる心の働きです。どのような人がこの言い訳に頼りやすいのか、その個人差を探っていきます。
「モラル・ディスエンゲージメント」とは、本来であれば自分を律するはずの内なる道徳基準の働きを、一時的に停止させるための認知的な仕掛けの総称です。その手口は様々です。例えば、「これは会社のためだ」と行為の目的をすり替えて正当化したり、「みんなやっていることだ」と責任を周りに分散させたりします。あるいは、「大した損害は出ていない」と結果を過小評価したり、「相手にも落ち度があった」と被害者を非難したりすることもあります。これらの心の操作によって、人は自身の行為を非道徳的ではないと再解釈し、罪悪感という内的な制裁から逃れるのです。
では、どのような人が、この「モラル・ディスエンゲージメント」という心の罠にはまりやすいのでしょうか。この問いに答えるため、ある研究者たちは、大学に入学したばかりの学生たちを対象に、時間を追って調査を行う縦断的な研究を実施しました[4]。研究の最初に、学生たちの様々な個人的な特性を測定し、数週間後にモラル・ディスエンゲージメントの傾向を、そしてさらに数ヶ月後に、不正行為を行う可能性を尋ねるという設計でした。
その結果、モラル・ディスエンゲージメントを促進する、いくつかの個人特性が浮かび上がってきました。その一つが、「特性シニシズム」、すなわち人間性に対する根深い不信感です。「どうせ人間なんて、自分の利益のためにしか動かない利己的な存在だ」と考える傾向が強い人ほど、不正を正当化する言い訳を受け入れやすいことが分かりました。彼ら彼女らにとっては、「やられたらやり返すのが当然」であり、被害者が出ても「自業自得だ」と捉えやすいため、道徳基準を解除することへの抵抗が少ないのかもしれません。
また、「自分の人生で起こることは、ほとんど運や偶然によって決まる」と考える、運命論的な世界観を持つ人も、モラル・ディスエンゲージメントに陥りやすいことが示されました。自分の行動の結果を自らの責任と捉えないため、「自分一人が頑張っても仕方がない」と責任を放棄しやすくなるのです。
一方で、この道徳的な自己欺瞞に対する抵抗力となる特性も明らかになりました。その筆頭が、他者の感情や立場を理解し、共感する能力の高さです。他者の痛みを我がことのように感じられる人は、その痛みを引き起こすような行為を正当化することが困難になります。共感性は、被害を矮小化したり、被害者を非難したりする「言い訳」に対する防波堤となります。
そして、これまでに見てきた「モラル・アイデンティティ」も、この抵抗力の一つであることが確認されました。自分を道徳的な人間だと強く認識している人は、非道徳的な行為を正当化する認知的な歪みを受け入れにくく、自身の道徳基準から逸脱することに強い不快感を覚えます。内なる道徳観は、不正への誘惑に対する自己監視システムとして機能しています。
この研究の最終段階では、モラル・ディスエンゲージメントの傾向が、実際の不正な意思決定にどう結びつくかが検証されました。学生たちに、大学生活で起こりうる様々な不正行為のシナリオ(例えば、友人のレポートを写す、簡単なカンニングをするなど)を提示し、自分がその状況に置かれたら、その行為を行う可能性がどれくらいあるかを尋ねました。結果、モラル・ディスエンゲージメントの傾向が強い人ほど、これらの不正行為に手を染める可能性が高いと回答しました。
詳細な分析によって、個人の特性(人間不信や共感性など)と不正行為との関係は、この「モラル・ディスエンゲージメント」という言い訳のメカニズムによって橋渡しされていることが分かりました。人間不信が直接的に不正を引き起こすというよりは、人間不信が「言い訳」をしやすい心の土壌を作り、その「言い訳」が不正行為への心理的なハードルを下げている、という構造が見えてきたのです。
能力が低い人ほど、道徳観が不正行為の歯止めになる
内なる道徳観が善行を促し、また不正への「言い訳」を食い止める力を持つことを見てきました。最後に、この道徳の力が、どのような状況で特に強くその価値を発揮するのかを掘り下げていきます。手がかりとなるのが、「アイデンティティ理論」です。この理論を通して、道徳観は、私たちが「自分は有能だ」という自信を失いそうになったときにこそ、不正への誘惑に対する最後の砦として機能するという、興味深い心の仕組みが明らかになります。
アイデンティティ理論は、私たちの心を一種の制御システムとして捉えます。人それぞれ、「自分はこうありたい」という基準(アイデンティティの基準)を持っており、現実の状況の中で知覚される自分の姿が、その基準と一致しているかを監視しています。例えば、「私は有能な学生でありたい」という基準を持っている人が、テストで悪い点を取ってしまうと、基準と現実の間に「ズレ」が生じます。
このズレは、私たちに不安や失望といった不快な感情を引き起こし、私たちはその不快感を解消するために、ズレを修正しようと行動します。もっと勉強するかもしれませんし、あるいは、そのズレから目をそらす別の方法を探すかもしれません。
この理論を道徳的な行動の理解に応用した研究があります[5]。研究者たちは、まず大学生を対象とした調査で、彼ら彼女らが過去に経験した道徳的なジレンマ(例えば、カンニングの誘惑にかられた経験や、拾った財布をどうするか迷った経験など)について尋ねました。そして、「自分は道徳的な人間でありたい」という内なる基準と、その状況で「他人は自分のことを道徳的だと評価してくれただろう」という認識との間にズレがあったかどうかを調べました。
その結果、このズレが大きいほど、すなわち、自分の行動が理想の道徳的な自己像から離れていると感じた人ほど、罪悪感や恥ずかしさといったネガティブな感情を強く経験していたことが分かりました。道徳的な自己像を維持することが、心の安定にとって大切であることを示しています。
この調査に続いて、より統制された実験が行われました。同じ学生たちを数週間後に実験室に呼び、模擬試験を受けてもらったのです。この試験は、キーボードのあるキーを押せば、いつでも正解が表示されるように設定されていました。実験者は、あたかも偶然その機能に気づいたかのように振る舞いながらも、「この機能を使うことは禁止です」と告げ、学生たちがカンニングをするかどうかを観察できる状況を作り出しました。
実験の結果、試験の成績が悪かった学生ほど、カンニングに手を出す回数が多いという、ある意味で予想通りの結びつきが見られました。「有能な学生でありたい」という自己像を維持できないプレッシャーが、不正行為への誘惑を高めたと考えられます。しかし、この研究の本当に重要な発見は、ここからでした。事前に測定されていたモラル・アイデンティティ、「自分は道徳的な人間でありたい」という思いが強い学生は、たとえ試験の成績が悪くても、カンニングを思いとどまる傾向が見られました。
この結果は、「能力が低い人ほど、道徳観が不正行為の歯止めになる」という、一見逆説的に聞こえるかもしれない心の働きを明らかにしました。これは、一つのアイデンティティが脅かされたとき、人は別の、よりどころとなるアイデンティティを固く守ろうとすることで、自己全体の尊厳を維持しようとする心の働きと解釈できます。
この実験の状況では、テストの成績が悪いことで、「有能な自分」というアイデンティティが危機に瀕しました。そのとき、強い道徳観を持つ人々にとって、「道徳的な自分」というもう一つの重要なアイデンティティが、自身を支える最後の砦となったのです。能力という資源が乏しい状況で、彼ら彼女らは道徳性という別の資源に頼ることで、自己の一貫性を保ち、不正という安易な道に流されることを防ぎました。
脚注
[1] Reed II, A., and Aquino, K. (2003). Moral identity and the expanding circle of moral regard toward out-groups. Journal of Personality and Social Psychology, 84(6), 1270-1286.
[2] Aquino, K., and Reed, A. II. (2002). The self-importance of moral identity. *Journal of Personality and Social Psychology, 83(6), 1423-1440.
[3] Aquino, K., McFerran, B., and Laven, M. (2011). Moral identity and the experience of moral elevation in response to acts of uncommon goodness. Journal of Personality and Social Psychology, 100(4), 703-718.
[4] Detert, J. R., Trevino, L. K., and Sweitzer, V. L. (2008). Moral disengagement in ethical decision making: A study of antecedents and outcomes. Journal of Applied Psychology, 93(2), 374-391.
[5] Stets, J. E., and Carter, M. J. (2011). The moral self: Applying identity theory. Social Psychology Quarterly, 74(2), 192-215.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。