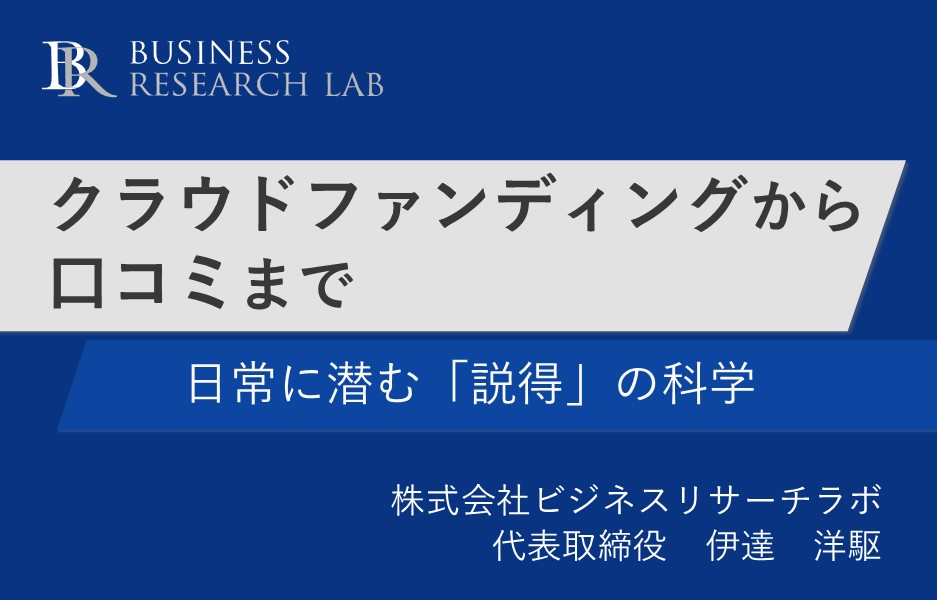2025年11月26日
クラウドファンディングから口コミまで:日常に潜む「説得」の科学
私たちの日常は、誰かを説得したり、誰かに説得されたりする場面の連続で成り立っています。家族に夕食のメニューを提案するささやかな交渉から、職場で自らの企画の魅力を伝え、承認を得ようとするプレゼンテーションまで、私たちは意識的、無意識的に、他者の心に働きかけ、行動を促そうと試みています。しかし、自分の思いや考えが、いつもすんなりと相手に受け入れられるわけではありません。同じことを伝えているはずなのに、ある人の言葉心に響き、人を動かす一方で、別の人の言葉は空しく響くだけで終わってしまうのは、一体どうしてなのでしょうか。
人を動かす力の源泉は、必ずしも話術の巧みさや、声の大きさにあるわけではありません。むしろ、私たちの心の奥深くにある、情報を処理し、意思決定を下すためのメカニズムに、その鍵が隠されています。相手がどのような心理状態でいるのか、何を求めているのか、どのような情報の提示の仕方が相手の心に届きやすいのか。こうした問いに対する答えを、近年の研究が少しずつ解き明かし始めています。
本コラムでは、人が他者の言葉によって心を動かされ、行動へと駆り立てられる際の、心の動きの裏側を探求していきます。クラウドファンディングにおける支援者の心理、ネットの口コミを信じる際の判断基準、ECサイトのおすすめ機能が購買意欲に与える仕組み、人の善意が悪用されるソーシャルエンジニアリングの罠。これら四つの異なる角度から、説得をめぐる人間の心の働きを見ていきます。
少額支援には夢を、高額支援には事実を語る
新しいアイデアや製品の実現を目指す人々が、インターネットを通じて不特定多数の人から資金を募るクラウドファンディング。この仕組みは、多くの挑戦者にとって希望の光となっています。しかし、数多あるプロジェクトの中から、なぜあるプロジェクトには多額の資金が集まり、別のプロジェクトは人々の関心を引くことなく終わってしまうのでしょうか。その成否を分けるのは、アイデアの斬新さだけではないようです。そこには、支援を呼びかけるメッセージの伝え方と、それを受け取る人々の心理状態との間に、密接な関係が存在します。
この謎を解き明かすために、ある研究が行われました[1]。研究は、心理学における説得の理論である「精緻化見込みモデル」という考え方を手がかりにしています。このモデルは、人が説得的なメッセージを受け取ったとき、二つの異なる思考のルートをたどることを説明するものです。
一つは「中心ルート」と呼ばれ、メッセージの内容を注意深く、論理的に吟味するルートです。もう一つは「周辺ルート」と呼ばれ、内容そのものよりも、話し手の魅力や感情的な訴えかけといった、直感的な手がかりに頼って判断するルートです。どちらのルートをたどるかは、その人がその事柄にどれだけ深く関わっているか、関与度によって変わるとされています。
研究者たちは、この考え方をクラウドファンディングの文脈に当てはめました。実際のクラウドファンディングサイト「Kickstarter」で公開された383件のプロジェクトを対象に、その動画や説明文の内容を分析しました。
プロジェクトの提唱者が語る言葉を、「起業家の学歴や職務経験」「製品の品質や有用性」といった客観的な事実を伝える情報(中心ルートに訴える情報)と、「個人的な夢の語り」「支援者との一体感の強調」といった感情に訴える情報(周辺ルートに訴える情報)に分類しました。その上で、これらの情報が、プロジェクトの資金調達目標の達成とどう関連しているかを調べました。
分析の結果、支援者に求める金額が比較的少額のプロジェクトでは、「この事業は私の長年の夢です」といった夢の語りや、「皆さんと一緒にこの製品を育てたい」といった一体感を強調するメッセージが、資金調達の成功に結びついていました。少額の支援という、比較的関与度の低い状況では、人々は情報を細かく吟味するよりも、感情的な共感や直感的な魅力といった「周辺ルート」の手がかりに基づいて判断するためだと考えられます。
一方で、支援者に求める金額が高額になるにつれて、様相は変わります。高額な支援を募るプロジェクトでは、「起業家が持つ豊富な関連経験」や、「この製品がいかに高品質で、既存の製品と連携して役立つか」といった、客観的で具体的な事実に基づいた情報が、資金調達の成功を後押ししていました。高額の支援は、支援者にとって大きな決断です。
そのため、関与度が高まり、人々は感情的な訴えよりも、そのプロジェクトが本当に信頼でき、成功する見込みがあるのかを吟味する「中心ルート」をたどるようになります。事実に基づいた説得的な情報が、その判断を支える上で欠かせないものとなるのです。
この研究は、同じ目標を達成しようとする場合でも、相手の関与の度合いによって、響く言葉の種類が異なることを教えてくれます。大きな決断を促したいのであれば、夢を語るだけでは不十分で、その夢を裏付ける客観的な事実や論理的な根拠を示す必要があります。逆に、小さな一歩を踏み出してもらうためには、理屈を並べるよりも、共感を呼ぶストーリーや、心に響く情熱を伝えることが、人の心を動かすのかもしれません。
ネットの口コミは、誰が書いたかより詳しさが大事
私たちは今、レストランを探すにも、家電製品を選ぶにも、インターネットで口コミを調べるのが当たり前の時代に生きています。そこには、見ず知らずの他人が書き込んだ、無数の評価や感想が溢れています。匿名の声の中から、私たちは一体何を信じ、何を疑い、どの情報に基づいて「この店に行ってみよう」「この商品を買おう」と決断しているのでしょうか。書き手のプロフィールが詳らかでない状況で、情報の信頼性は何によって担保されるのでしょう。
この問いに答えるため、ある研究が、オンラインの顧客コミュニティにおける情報の採用プロセスに着目しました[2]。この研究もまた「精緻化見込みモデル」の考え方を応用した「情報採用モデル」という枠組みを用いています。このモデルは、人がオンライン上の情報を自分の意思決定に取り入れるかどうかは、主に二つの要素、すなわち「議論の質(情報の『中身』)」と「情報源の信頼性(情報を『誰が』書いたか)」によって決まると考えます。研究者たちは、この二つの要素が人々の行動にどう結びつくのかを検証しようと試みました。
調査の舞台となったのは、香港で広く利用されているレストラン情報サイトです。研究者たちは、このサイトの利用者154名に対してオンラインでアンケート調査を行いました。アンケートでは、レビューを読む際に、その内容の「自分との関連性」「情報の網羅性(詳しさ)」「正確性」「適時性(新しさ)」といった「議論の質」に関する側面をどう評価しているかを尋ねました。同時に、書き手の「専門性」や「誠実性」といった「情報源の信頼性」に関する側面についても質問しました。
これらの評価が、そのレビューを「有用だ」と感じる度合いや、最終的にそのレビューを参考にして実際にお店を訪れるといった「情報採用」の行動に、どのように関わっているのかを分析しました。
人々がレビューを「役に立つ」と判断し、それに基づいて行動を起こす上で、最も強い決め手となっていたのは、「議論の質」、特にその中でも「自分自身のニーズに合っているか(関連性)」と、「判断材料として十分なほど内容が詳しいか(網羅性)」という二つの点でした。例えば、ある人が「静かな雰囲気で食事ができる店」を探している場合、そのニーズに合致した情報や、お店の雰囲気、メニュー、価格帯などが詳細に記述されたレビューほど、有用だと感じられ、行動につながりやすかったのです。
その一方で、意外なことに、書き手の「専門性」や「誠実性」といった「情報源の信頼性」は、レビューの有用性の判断に直接的な結びつきを見せませんでした。匿名の投稿者が多いレストランの口コミサイトのような環境では、「誰が書いたか」ということよりも、「何が書かれているか」が判断を左右していました。
この結果が意味するのは、書き手の素性がはっきりしない状況では、人は情報の発信者を頼りにすることができないため、自ずと情報の中身そのものを吟味せざるを得なくなる、ということです。私たちは、書き手が本当に食通なのか、あるいは誠実な人物なのかを確かめるすべを持ちません。だからこそ、そのレビューが自分にとって価値があるかどうかを、内容の具体性や詳しさから判断しようとします。
無数の選択肢の中から一つを選ぶという認知的な負担が大きい状況では、自分の判断を支えてくれるだけの、リッチで詳細な情報が何よりも求められる、と言えるでしょう。
おすすめは、多すぎると逆効果になる
オンラインショッピングサイトを訪れると、「あなたへのおすすめ」といった形で、私たちの過去の閲覧履歴や購買データに基づいて選ばれた商品がずらりと並びます。こうしたパーソナライズ機能は、私たちの好みに合った商品を効率的に見つける手助けをしてくれる、便利な仕組みに思えます。しかし、あまりに多くの選択肢を一度に提示されて、かえってどれを選べばよいか分からなくなり、途方に暮れてしまった経験はないでしょうか。良かれと思って提供される情報が、時として私たちの判断を麻痺させることがあります。
ウェブサイト上のパーソナライズ機能が、どのようにして私たちの心に働きかけ、購買行動を促すのか。このメカニズムを解明しようと、ある研究が「精緻化見込みモデル」を情報システムの分野に応用しました[3]。研究者たちは、パーソナライズされた情報が、私たちの思考の「中心ルート」と「周辺ルート」の両方に働きかけると考えました。
私たちの好みにぴったり合った情報(例えば、好きなアーティストの新曲)が提示されれば、その情報の内容をじっくり吟味しようという意欲が高まります(中心ルートの活性化)。一方で、おすすめ商品の表示順序や、提示される商品の数といった「見せ方」そのものも、私たちの判断に無意識のうちに影響を与える手軽な手がかりとなりえます(周辺ルートの活性化)。
この仮説を検証するため、研究者たちは、モバイル着信音を販売するECサイトの模擬画面を用いた、複数の実験を行いました。参加者には、サイト上で着信音を探してもらい、その行動を観察しました。実験では、参加者の好みに合わせてパーソナライズされたおすすめ商品を提示するグループと、そうでないグループに分けたり、おすすめとして提示する商品の数を変えたりしました。参加者がどの商品を、どれくらいの時間をかけてクリックして詳細を確認したか(情報探索の深さ)、最終的にどの着信音をダウンロードしたいと思ったか(購買選択)を測定し、比較分析しました。
実験結果は、パーソナライズの効果の光と影を浮き彫りにしました。初めに予想通り、自分の好みに合った情報が提示された参加者は、そうでない参加者に比べて、より多くの商品を熱心に探索し、購買意欲も一貫して高くなることが確認されました。自分に関連性の高い情報は、私たちの知的好奇心を刺激し、深く考えて吟味する「中心ルート」へと誘います。
しかし、おすすめとして提示される商品の「数」については、単純な話ではありませんでした。商品の数が少ない場合から中程度に増えるまでは、参加者の情報探索行動は活発になりました。ところが、ある点を境に、提示される商品の数が多すぎると、参加者はかえって商品を探索するのをやめてしまうという曲線的な関係が見られたのです。
この現象は、私たちの脳が一度に処理できる情報量には限界があるという事実に基づいています。あまりに多くの魅力的な選択肢を一度に突きつけられると、一つ一つを比較検討し、最善のものを選ぶという作業は、大きな認知的な負担となります。この状態は「選択過多」あるいは「選択のパラドックス」と呼ばれ、情報処理の負担が限界を超えると、人は考えること自体を放棄してしまったり、あるいは選択そのものから逃避してしまったりするのです。せっかく自分のために最適化された情報も、その量が認知的な許容量を超えてしまうと、説得のプロセスは機能不全に陥り、逆効果にさえなり得ます。
信頼や忠誠心がソーシャルエンジニアリングの隙となる
企業や組織がどれほど高度なセキュリティシステムを導入しても、情報を盗み出そうとする攻撃が後を絶ちません。その手口の中でも、特に厄介なのが「ソーシャルエンジニアリング」です。これは、システムの脆弱性ではなく、人間の心理的な隙や、行動の癖を突く攻撃手法です。
例えば、情報システム部門の担当者を装って電話をかけ、「パスワードの再設定が必要です」と偽って情報を聞き出したり、取引先からのメールを巧妙に偽装して、ウイルスが仕込まれたファイルを開かせたりします。なぜ、多くの人がこのような手口に騙されてしまうのでしょうか。その根底には、私たちの持つ心理特性が関わっています。
従業員がソーシャルエンジニアリング攻撃に対して、なぜ無防備になってしまうのか。その心理的な要因を実証的に明らかにしようとした研究があります[4]。この研究は、人が脅威をどう認識するかという理論と、これまで見てきた「精緻化見込みモデル」における周辺ルートの考え方を統合し、人が騙されるプロセスを分析しました。攻撃に屈してしまうのは、脅威そのものを軽く見積もっている場合と、権威や信頼といった、深く考えずに頼ってしまう直感的な手がかりに流されてしまう場合がある、と仮説を立てたのです。
研究者たちは、ある企業の従業員588名を対象に、二つのアプローチを並行して実施しました。一つは、アンケート調査です。ここでは、「自分は人を信じやすい方か」「所属する組織に対して恩義や愛着を感じているか」「自分はセキュリティ攻撃の被害に遭いにくいと思っているか」といった、個人の心理的な特性を測定しました。
もう一つは、実際の行動を観察する実験です。研究者たちは、半年間という長期間にわたり、調査対象の従業員に対して、偽のフィッシングメールを送信したり、ヘルプデスクを装って電話をかけたりする、本物さながらの攻撃シミュレーションを仕掛けました。そして、従業員が実際にその偽の要求に応じてしまうかどうかを記録しました。
アンケートの結果と、行動観察の結果を照らし合わせた分析は、人が騙される際の心の脆さを明らかにしました。攻撃に屈してしまった人々に共通して見られた、強い心理的な特徴は、「人を信じやすい」という一般的な信頼傾向でした。人を疑うことを知らず、性善説に立って物事を考える人ほど、攻撃者の仕掛けた罠に無防備にはまりやすかったのです。
本来は組織にとって望ましいはずの特性が、皮肉にも脆弱性につながっていることも判明しました。例えば、「この組織に貢献したい」という強い恩義の念(規範的コミットメント)や、「この会社の一員であることが誇らしい」という組織への愛着(情動的コミットメント)が強い人ほど、攻撃に弱いという結果が出ました。これは、攻撃者が「組織のため」「急ぎの要件」といった口実を使うことで、従業員の持つ組織への忠誠心や善意を巧みに利用するためだと考えられます。
組織を思う気持ちが強いほど、「助けなければ」という思いが先に立ち、要求の正当性を冷静に吟味する(中心ルート)プロセスが省略され、直感的な判断(周辺ルート)で行動してしまいます。「自分は大丈夫だろう」という、根拠のない楽観的な自己評価も、油断を生み、攻撃を成功させる一因となっていました。
この研究は、私たちの持つ「信頼」や「忠誠心」といった人間的な美徳が、時として判断を曇らせ、悪意ある他者につけいる隙を与えてしまうという、不都合な真実を突きつけます。人を動かす心理的なメカニズムは、光の側面だけでなく、影の側面も併せ持っているのです。
脚注
[1] Allison, T. H., Davis, B. C., Webb, J. W., and Short, J. C. (2017). Persuasion in crowdfunding: An elaboration likelihood model of crowdfunding performance. Journal of Business Venturing, 32(7), 707-725.
[2] Cheung, C. M. K., Lee, M. K. O., and Rabjohn, N. (2008). The impact of electronic word-of-mouth: The adoption of online opinions in online customer communities. Internet Research, 18(3), 229-247.
[3] Tam, K. Y., and Ho, S. Y. (2005). Web personalization as a persuasion strategy: An elaboration likelihood model perspective. Information Systems Research, 16(3), 271-291.
[4] Workman, M. (2007). Gaining access with social engineering: An empirical study of the threat. Information Systems Security, 16(6), 315-331.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。