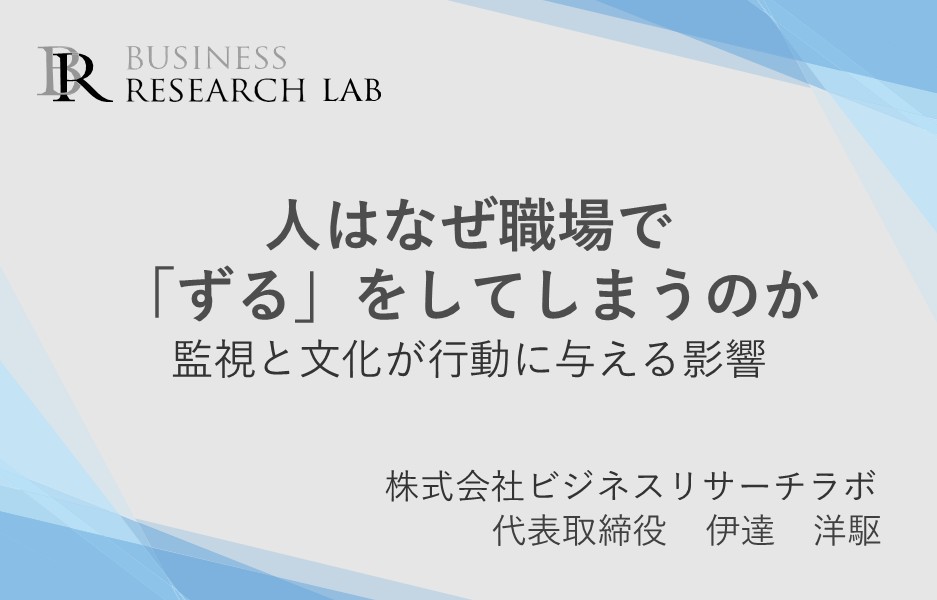2025年11月25日
人はなぜ職場で「ずる」をしてしまうのか:監視と文化が行動に与える影響
私たちは人生の多くの時間を職場で過ごします。その職場という空間が、私たちの考え方や行動にどれほど深く関わっているのかを、日常で意識する機会は少ないかもしれません。給与や役職といった目に見える条件だけでなく、職場の雰囲気や働き方の自由度といった形のない要素が、私たちのパフォーマンスや、時には倫理観にまで結びついています。
近年のある業界における不祥事は、個人の問題だったのでしょうか。それとも、業界特有の「文化」がそうした行動を誘発したのでしょうか。また、急速に普及した在宅勤務は、私たちの生産性をどう変えたのでしょうか。企業の成長の鍵は、潤沢な資金だけにあるのではありません。経営者の持つ知見やスキルといった、目に見えない資本の方が、組織を飛躍させるのかもしれません。
本コラムでは、こうした問いに答えるため、世界で行われた様々な調査や実験の結果を丹念に読み解きます。一見すると無関係に見える研究が、パズルのピースのようにつながる時、私たちは職場という環境が持つ強い力を再発見することになるでしょう。従業員の行動と企業の成果の背後にあるメカニズムを探求していきたいと思います。
銀行員は職業想起で不正行為が増える
経済活動が円滑に進むためには、取引相手への信頼が不可欠です。しかし、時にその信頼は揺らぎます。金融業界での事件が報道されるたび、私たちは個人の倫理観を問題にしてしまいますが、根源は別のところにあるかもしれません。例えば、業界特有の「ビジネス文化」そのものが、人の行動を特定の方向へ導いているという考え方です。この仮説を検証するため、ある実験が行われました[1]。
この実験は、「人は状況に応じて異なる自分を使い分ける」という考えに基づきます。私たちは家庭、友人関係、職場と、それぞれで異なる社会的な規範に沿って振る舞います。もし「銀行員」という職業的アイデンティティに、利益のためなら多少の不誠実も許されるという暗黙の規範が結びついていれば、自身が銀行員だと意識するだけで行動に変化が現れるかもしれません。
実験には、ある国際的な大手銀行の従業員128名が参加し、無作為に二つのグループに分けられました。一方のグループには、「勤務先の銀行名は?」といった職業に関する質問をし、「銀行員」というアイデンティティを際立たせました。もう一方のグループには、「週に何時間テレビを見ますか?」といった職業とは無関係な質問をしました。
その後、両グループは同じ課題に取り組みます。誰にも見られていない状況でコインを10回投げ、結果を自己申告するのです。各回のトスでは「表が出れば20ドル獲得」といった成功報酬が設定されていました。確率的には成功率は50%になるはずで、これを大幅に上回る申告は不正を示唆します。
結果、職業と無関係な質問をされたグループの成功申告率は51.6%で、確率的な予測とほぼ同じでした。彼らは総じて正直に行動したと言えます。ところが、「銀行員」であることを意識させられたグループでは、成功申告率が58.2%にまで上昇しました。計算上、このグループでは有利な虚偽申告が行われたことになります。自身の職業を思い出しただけで、不正な行動をとる人が増えたのです。
この行動変化の起因を探るため、いくつかの可能性が検討されました。競争心が刺激された可能性や、他の銀行員も不正をするだろうという予測が行動につながった可能性が考えられましたが、調査の結果、これらに変化は見られませんでした。
変化が見られたのは金銭的成功への価値観でした。「社会的地位は主に経済的成功で決まる」という考えへの同意度が、「銀行員」を意識したグループで高まっていました。そして、この価値観に強く同意する人ほど、不誠実な申告をする度合いが高いこともわかりました。
この現象が銀行業界に特有か確かめるため、他業種の人々や大学生に同じ実験を行いましたが、不正行為の増加は見られませんでした。
この一連の実験から、銀行業界に固有のビジネス文化が、無意識に「金銭的成功」の価値を活性化させ、正直さという規範を相対的に弱めてしまう可能性が浮かび上がります。これは個人の資質の問題というより、所属集団の文化が個人の行動を規定するという構造を物語っています。
監視弱化で不正が急増し、誠実な従業員は変わらず
先ほどは、目に見えない「文化」が人の行動を形作る様子を見てきました。対照的に、企業が古くから用いてきた直接的な手法が「監視」です。監視があれば真面目に働き、なければ手を抜くという考えは直感的ですが、人間の行動はそれほど単純なのでしょうか。この問いに答えるため、ある電話募金会社で行われたフィールド実験の結果を見てみましょう[2]。
この実験の目的は、現場で監視の強度を変化させ、従業員の「ずる」がどう変わるかを観察することでした。経済学のモデルによれば、人は見つかるリスクと利益を天秤にかけ、監視が弱まれば不正を増やすとされます。一方で、心理学のモデルでは、人は内なる規範に従うとされます。この実験は、現実の職場でどちらが妥当かを明らかにしようとしました。
実験の舞台は、全米16拠点に展開するコールセンターです。この会社では、寄付の約束が本物かを確認する「コールバック」という監視を、全コールの10%に実施していました。実験では、一部の拠点でこの監視率を5%に引き下げました。この変更は、従業員や直属の上司には知らされませんでした。不正の指標は「寄付が取り消された電話」の件数です。
結果、監視率が引き下げられた拠点では、不正な電話の比率が平均で2倍以上に跳ね上がりました。これは経済学のモデルの予測と一致し、監視が緩むと即座に不正が増加しました。個人レベルのデータでは、一度でも不正が発覚しなかった経験が、翌週のさらなる逸脱行動を促していました。
しかし、物語はここで終わりません。重要なのは、全従業員が同じように反応したわけではない点です。事前のアンケート調査から、従業員の多様な側面が見えてきました。「会社に好意的な態度」を持つ従業員は、監視が弱まっても不正の増加度合いは他の従業員の約半分でした。彼ら彼女らの行動は、外的な監視よりも内的な規範意識に支えられていました。
一方で、「今の会社を辞めても、すぐに同程度の仕事を見つけるのは難しい」と考える従業員ほど、監視が弱まると不正を増やす度合いが強いという関係も見られました。会社に留まらざるを得ない状況が、短期的な利益追求につながった可能性を示唆します。実際、不正な電話を記録した従業員は月収が平均より高く、短期的には「ずる」が経済的に報われる構造があったことも確認されました。
在宅勤務は成果を高め離職を半減させる
監視の目が届きにくい在宅勤務は、多くの経営者にとって生産性低下の懸念と結びついていました。オフィスから離れることで集中力が削がれるのではないか、という不安は根強いものがありました。この長年の疑問に、中国最大級の旅行会社で行われた実験が、一つの答えを与えてくれます[3]。
この研究の目的は、在宅勤務が従業員の業績や満足度、離職率にどのような結びつきを持つのかを厳密に検証することでした。実験の舞台は上海のコールセンターです。在宅勤務の希望者の中から、抽選という本人の能力とは無関係な方法で、「在宅勤務グループ」と従来通りオフィスで働く「出社グループ」に無作為に割り振りました。
在宅勤務グループは週4日在宅、1日出社で、両グループのITシステム、給与体系、評価基準は同一でした。この状態で9ヶ月間、両グループのデータを追跡しました。
実験の結果、在宅勤務グループのパフォーマンスは、出社グループに比べて全体で13%も高いことが分かりました。この内訳は、通話効率、つまり生産性が4%向上したことに加え、実質的な労働時間が9%増加したことが要因でした。通話の品質には差がなく、品質を落とさずに量を増やしたのです。
さらなる変化が離職率に見られました。9ヶ月の実験期間中、出社グループの離職率が35%だったのに対し、在宅勤務グループは17%と、半分以下にまで減少しました。従業員の定着率が改善したのです。また、在宅勤務者は仕事への満足度が高く、疲労感は低いと報告していました。
この好ましい結果の要因として、研究者たちは二つの点を指摘しています。一つは、往復平均80分の通勤時間がなくなったことによる時間的・精神的な余裕です。もう一つは、オフィスの喧騒から解放され、静かで集中できる自宅の環境です。
もちろん、良いことばかりではありません。在宅勤務者は昇進の機会が出社グループの約半分に減少するというキャリア上の不利益も確認されました。しかし、実験終了後に勤務場所を自由に選ばせたところ、在宅勤務で成果が上がらなかった従業員の半数が、自らオフィス勤務に戻ることを選択しました。その結果、在宅勤務を継続した人たちの平均業績は、実験期間中を上回る成果向上を見せました。これは従業員自身が、自分にとっての最適な働き方を判断する力を持っていることを示しています。
経営コンサル導入で中小企業の雇用が増加
企業の成長を阻む壁として、私たちは「資金不足」を思い浮かべるかもしれません。しかし、お金と同じくらい、あるいはそれ以上に企業の運命を左右する要素があります。それは、経営者が持つ知識やスキル、すなわち「経営能力」という目に見えない資本です。この無形の資本の不足を、外部の専門家が補うことで、企業は本当に成長できるのでしょうか。メキシコで行われた社会実験が、この問いに光を当てています[4]。
この実験の目的は、中小企業に経営コンサルティングを提供することが、企業の生産性、雇用、経営者の意識にどう変化をもたらすかを検証することでした。参加した432社の中小企業を無作為に二つのグループに分けました。一方のグループには、1年間、政府補助付きでコンサルタントによる個別指導を提供しました。もう一方のグループには支援は行いませんでした。
研究者たちは数年間にわたり、両グループの企業の動向を、自己申告のデータと社会保険庁が保有する公式の記録から追跡しました。結果、介入終了直後の1年後、コンサルティングを受けた企業は、受けていない企業に比べ、資源を効率的に利益へ結びつける生産性の指標が改善していました。行動面では、マーケティング活動や正式な会計帳簿の導入が増え、経営者自身の「起業家精神」も向上していました。
最も顕著な変化は3年後に現れました。公式データによると、コンサルティングを受けた企業は、受けていない企業と比較して、雇用している従業員の数が平均で44%(約4.4人)も増加していたのです。支払われる賃金総額も57%増えており、短期的な生産性改善が、企業の規模拡大と新たな雇用創出につながったことが示されました。
興味深いのは、成功の要因です。改善が見られた経営手法は企業ごとに異なり、「万能薬」は存在しませんでした。会計の整備、組織内の責任明確化、販売戦略の見直しなど、各社が固有の課題を解決していました。成功の鍵は、一律の処方箋ではなく、オーダーメイドの伴走型支援にありました。
この実験は、中小企業の成長にとって、経営能力という無形の資本がいかに根源的であるかを実証しました。専門的な知見という外部からの刺激が、経営者の行動と意識を変革し、数年を経て、雇用という社会全体の利益に結びつく過程を描き出したのです。
脚注
[1] Cohn, A., Fehr, E., and Marechal, M. A. (2014). Business culture and dishonesty in the banking industry. Nature, 516(7529), 86-89.
[2] Nagin, D., Rebitzer, J., Sanders, S., and Taylor, L. (2002). Monitoring, motivation and management: The determinants of opportunistic behavior in a field experiment (NBER Working Paper No. 8811). National Bureau of Economic Research.
[3] Bloom, N., Liang, J., Roberts, J., and Ying, Z. J. (2015). Does working from home work? Evidence from a Chinese experiment. Quarterly Journal of Economics, 130(1), 165-218.
[4] Bruhn, M., Karlan, D., and Schoar, A. (2013). The impact of consulting services on small and medium enterprises: Evidence from a randomized trial in Mexico (Policy Research Working Paper 6508). World Bank.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。