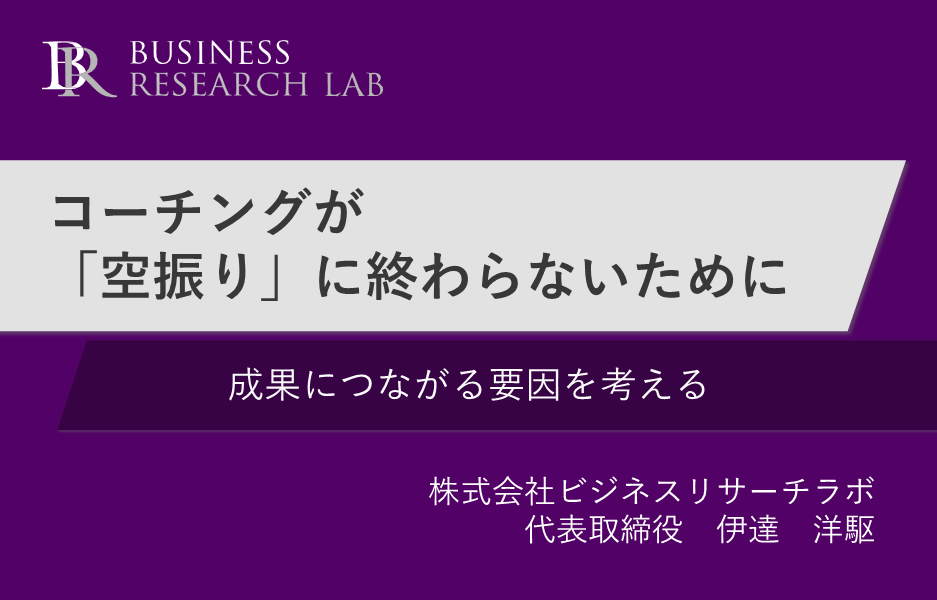2025年11月25日
コーチングが「空振り」に終わらないために:成果につながる要因を考える
なぜ、熱心に部下と向き合っても、コーチングが空振りに終わることがあるのでしょうか。普及が進んでいるコーチングですが、その効果は不安定な側面もあります。とはいえ、「あの人だからうまくいった」「うちの部署では無理だ」といった属人的な理由で片付けるのはもったいないでしょう。
本コラムは、コーチングの「成功確率」に悩むリーダーと人事担当者に向けたものです。近年の研究は、成果のばらつきがコーチの技術力だけで決まるのではないことを明らかにしています。成功の鍵は、コーチングを受ける側の心理状態、組織全体の支援体制、そしてコーチと部下の間に生まれる関係性といった要因に隠されています。
本コラムでは、コーチングの成否を分ける「5つの要因」を紹介します。精神論やテクニック論ではありません。コーチングという複雑で人間的なプロセスを解き明かし、その効果を最大限に引き出すための知見を見ていきましょう。
コーチングの成功は、本人の意欲や上司の支援などにも左右
コーチングが職場で広がりを見せる中、その効果を決める要因について調べた研究があります。この大規模な文献レビューでは、117の実証研究を検討し、コーチングがうまくいくかどうかを左右する7つの要因を特定しました[1]。
研究者たちは、コーチングという複雑な現象を理解するため、定性的研究から定量的研究まで幅広い研究手法を用いた論文を集めました。これまでのメタ分析が主に数値データに依存していたのに対し、この研究はより多角的な視点からコーチングの本質に迫ろうとしました。膨大な文献を体系的に整理した結果、浮かび上がってきたのは、多面的で相互に関連し合う要素群の存在です。
第一に重要なのは、コーチングを受ける人の「自己効力感」です。これは「自分は課題をうまく遂行できる」という自分自身の能力に対する信念を指します。自己効力感が高い人ほど学習への動機づけが強く、実際のパフォーマンス向上につながりやすいことが確認されています。この要因は、コーチングの効果を予測する先行指標であると同時に、コーチングによって育成される成果でもあるという二面性を持っています。
続いて、コーチングへの「動機づけ」が挙げられます。参加者がコーチングに積極的に関わり、学習し、変化しようとする意欲がなければ、どれほど優れたプログラムであっても効果は期待できません。この動機づけは、コーチングが強制的な研修として位置づけられるか、自発的な成長機会として認識されるかによって変わります。
個人の「目標志向」も要因となります。能力を向上させること自体を目的とする学習目標志向を持つ人は、他者からよく見られることを重視する遂行目標志向を持つ人と比べて、コーチングからより多くの恩恵を受けることが判明しています。前者は失敗を学習機会として捉える一方、後者は失敗を避けようとするため、学びが生まれにくいのです。
コーチとの関係性を決める要因として、「信頼」と「対人魅力」も欠かせません。信頼関係が築かれることで、コーチングを受ける人は安心して自己開示し、弱い部分を見せることができるようになります。また、コーチと被コーチが互いに好意を持ち、惹かれ合う程度も関係性の質を決めます。性別や価値観の類似性が、特に関係の初期段階で心地よさを生み出し、エンゲージメントを高めることが観察されています。
「フィードバック介入」の質とその受容性も、コーチングの成果を左右します。コーチが提供するフィードバックが建設的で実用的であること、そして被コーチがそれを素直に受け入れる姿勢を持つことが求められます。
最後に、組織的な要因として「上司からの支援」が重要な役割を果たします。直属の上司が、コーチングで学んだことを職場で実践することを支援し、励ますかどうかが、学習内容の定着と実際の行動変化を左右します。どれほど優れたコーチングを受けても、職場に戻った際に上司が理解を示さなければ、新しい行動は継続されません。
セッションを重ねるほど、部下への指導の自信を高める
コーチングの心理的メカニズムについて、縦断研究が実施されました。この研究は、管理職を対象とした8ヶ月間のリーダーシップ開発プログラムに参加した73名を追跡し、コーチングが管理職の「自己効力感」をどのように変化させるかを調べたものです[2]。
この研究の背景には、現代の変化する組織環境において、管理職に求められるスキルも変化していることがあります。指示命令型のマネジメントから、部下の自律性と学習を促すコーチング型のマネジメントへの転換が求められていますが、多くの管理職がこの新しい役割に自信を持てずにいます。
研究対象となったリーダーシップ開発プログラムは、3つの異なる手法を組み合わせて構成されていました。月に1回の集合研修では、理論的な知識を学習し、同じく月1回のアクション・ラーニングでは、参加者が実際の職場課題についてグループで議論しました。そして、各参加者に社内の認定コーチが個別につき、最大14回の1対1のセッションが実施されました。
研究者たちは、プログラムの開始前と終了後に調査を行い、参加者の部下に対するコーチング能力への自己効力感を測定しました。自己効力感とは、「特定の状況で目標を達成するために必要な行動をうまく遂行できる」という自分自身の能力に対する信念です。この概念は、学習した内容が実際の行動変化として現れる過程で中心的な役割を果たすことが知られています。
分析の結果、集合研修やアクション・ラーニングの参加度、さらには参加者の元々の自己効力感レベルの影響を統計的に取り除いた後でも、「コーチングセッションの回数」が、プログラム終了後の自己効力感と正の関係を示していました。コーチングを多く受けた管理職ほど、部下をコーチングする能力に対する自信が高まったことを意味します。
この効果は、単純にセッション数が多いからというだけでは説明できません。複数回のセッションを通じて、コーチと被コーチの間に深い信頼関係が築かれ、安心して自己開示できる環境が整うことが要因と考えられます。初回のセッションでは緊張や遠慮があっても、回を重ねるにつれて本音で話し合える関係性が形成され、より深い学びが可能になります。
コーチングの効果に寄与するその他の要因も特定されました。参加者が「この研修プログラムは自分の仕事に役立つ」と認識する程度、すなわち研修の有用性に対する主観的判断が、自己効力感の向上と関連していました。研修内容が実践的で、自分の課題解決に直結すると感じられるほど、学習への動機が高まり、結果として自信の向上につながります。
情緒的コミットメント、つまり組織の一員であることを誇りに思う気持ちも、自己効力感の向上を支えていました。組織への愛着が強い管理職ほど、新しいスキルを積極的に学び、それを職場で実践しようとする意欲を持ちます。
一方で、個人の学習志向や職場環境からの支援については、予想に反して直接的な効果は確認されませんでした。コーチングという1対1の密接な関係性の中では、より基本的な要因である信頼関係や研修の実用性が優先的に作用することを示唆しています。
コーチングの成果は、セッションの回数とは関連がない
先ほど見たコーチングセッション回数の重要性とは対照的に、別の大規模研究では異なる結果が報告されています。この研究は、コーチングの効果に関する厳格な科学的検証を行ったメタ分析です[3]。
この研究では、分析対象を「ランダム化比較試験(RCT)」に限定しています。RCTとは、参加者をランダムにコーチングを受けるグループと受けないグループに分ける研究手法です。コーチング研究の多くは、参加者の希望や組織の判断でコーチングの有無が決まる「準実験」的な研究が中心でしたが、そのような研究では、もともと意欲的な人がコーチングを受ける可能性が高く、効果を過大評価してしまう危険性がありました。
研究者たちは、1994年から2021年までの27年間に発表された37のRCT研究を厳選し、総計2,528名のデータを統合して分析しました。分析の結果、コーチングは確かに中程度の有意な効果を持つことが確認されました。厳格な基準でも、コーチングの有効性は実証されました。
その一方で、コーチングの効果の大きさは、セッションの回数とほとんど関係がないことがわかりました。3回のセッションでも、15回のセッションでも、統計的には同程度の効果が得られていました。「回数を増やせば効果も上がる」という直感的な考えとは正反対の結果です。
この現象を理解するために、研究者たちは「共調整(co-regulation)」という概念を取り上げています。コーチとクライアントが、与えられた時間の制約の中で最大限の成果を得ようと、お互いに調整し合うプロセスを指します。セッション回数が少ない場合は、両者とも限られた時間を活用しようと集中し、効率的な関わりが生まれます。一方、回数に余裕がある場合は、よりゆっくりとしたペースで進行するため、結果的に単位時間あたりの効果は同程度になるというのです。
この共調整は、コーチングが機械的なスキル伝達ではなく、人間同士の動的な相互作用であることを示しています。優れたコーチは、クライアントの状況や利用可能な時間に応じて、アプローチを柔軟に調整します。クライアントも、セッション数に応じて関わり方や学習への姿勢を無意識に調整します。この相互調整により、時間的制約に関係なく一定の効果が維持されるということです。
成果の測定方法による違いも明らかになりました。コーチングの効果は、クライアント自身による自己評価で測定した場合に最も大きく現れ、他者による観察評価や客観的指標による測定では相対的に小さくなりました。コーチングがまず内面的な自信や認識の変化をもたらし、それが外から見える行動変化として現れるまでには時間がかかることを示唆しています。
この研究が提示する重要なメッセージは、コーチングの成功は「量」ではなく「質」にあるということでしょう。セッション回数を機械的に増やすことよりも、コーチとクライアントが深い信頼関係を築き、限られた時間の中で価値を創造することが肝要です。
コーチングの業績向上効果は、組織階層が下がるほど強くなる
組織内でのコーチングの効果について、階層構造に焦点を当てた研究が行われました。この研究は、ある多国籍製造企業の営業部門を対象に、経営幹部から中間管理職、そして一般社員へと続く3つの階層にわたってコーチングの波及効果を検証したものです[4]。参加者は経営幹部32名、中間管理職114名、一般社員328名という形で構成されました。
従来のコーチング研究が主に一対一の関係に焦点を当てていたのに対し、この研究は組織を一つのシステムとして捉え、階層間の相互作用に注目しました。研究者たちは、上司のコーチング行動が部下の業績にどう影響するか、そして上層部のコーチング行動が下層部のマネージャーの行動に模倣効果をもたらすかという2つの問いを設定しました。
測定においては、各階層の部下が上司のコーチング行動の頻度と有効性を評価し、業績については実際の売上データが使用されました。分析の結果、上司のコーチング行動は部下の業績向上につながることが実証されました。中間管理職が一般社員に対して行うコーチングは、その部下の売上パフォーマンスに統計的に有意な正の影響を与えていました。同様に、経営幹部が中間管理職に対して行うコーチングも、その部下である管理職の業績向上に寄与していました。
印象深いのは、コーチングの効果が組織階層によって異なることです。中間管理職が一般社員に対して行うコーチングの効果は、経営幹部が中間管理職に対して行うコーチングの効果よりも大きかったのです。組織の下層部において、直属の上司からのコーチングはより強力な影響力を持っていました。
この階層による効果の違いには、いくつかの要因が考えられます。組織の上位に行くほど、職務の内容が複雑で抽象的になり、成果が目に見えるまでに時間がかかります。経営幹部の意思決定は組織全体に波及するため、その効果を短期間で測定することは困難です。一方、一般社員の業務は比較的具体的で、コーチングの効果も売上などの形で速やかに現れやすいのかもしれません。
物理的・心理的距離も影響していると考えられます。中間管理職と一般社員は日常的に密接な関係を持ち、頻繁なコミュニケーションを通じてコーチングの効果が継続的に強化されます。しかし、経営幹部と中間管理職の間では、相対的に距離があり、コーチングの機会も限定的になりがちです。
組織階層が上がるにつれて、個人の裁量権も拡大します。上位の管理職は、自分なりの判断でコーチングの内容を取捨選択し、実践する自由度が高くなります。この自律性は一方では創造性を促進しますが、他方ではコーチングの直接的な効果を薄める可能性もあります。
研究のもう一つの焦点であった「模倣効果」については、予想に反する結果が得られました。経営幹部のコーチング行動が、中間管理職のコーチング行動を促進するという証拠は見つからなかったのです。上司が良いコーチングを実践しているからといって、部下のマネージャーがそれを模倣するとは限らないということです。
この発見は、コーチングスキルの習得が、観察学習では不十分であることを意味しています。コーチングは高度な対人スキルであり、その習得には体系的なトレーニングが必要です。上司の行動を見るだけでは、その背景にある思考プロセスや意図を理解することは困難であり、表面的な模倣に留まってしまう可能性があります。
コーチングでの同調は、関係性を修復しようとする努力の表れ
コーチングの効果を生み出すメカニズムについて、これまでとは異なる角度からアプローチした研究があります。この研究は、コーチとクライアントの「非言語的同調性」という客観的な指標に注目し、それがコーチングプロセスの中でどのような機能を果たすのかを解明しました[5]。
研究チームは、国際的なコーチング組織の協力を得て、184組のコーチとクライアントペアによる実際のコーチングセッションを最長8ヶ月間にわたって追跡しました。各セッションはビデオで記録され、「モーション・エネルギー分析」という手法を用いて、両者の身体動作の同調度合いが数値化されました。この手法により、二人の相互作用を客観的に測定することが可能になりました。
脚注
[1] Bozer, G., and Jones, R. J. (2018). Understanding the factors that determine workplace coaching effectiveness: a systematic literature review. European Journal of Work and Organizational Psychology, 27(3), 342-361.
[2] Baron, L., and Morin, L. (2010). The impact of executive coaching on self-efficacy related to management soft-skills. Leadership & Organization Development Journal, 31(1), 18-38.
[3] De Haan, E., and Nilsson, V. O. (2023). What can we know about the effectiveness of coaching? A meta-analysis based only on randomized controlled trials. Academy of Management Learning & Education, 22(4), 1-21.
[4] Agarwal, R., Angst, C. M., and Magni, M. (2009). The performance effects of coaching: A multilevel analysis using hierarchical linear modeling. The International Journal of Human Resource Management, 20(10), 2110-2134.
[5] Erdos, T., and Ramseyer, F. T. (2021). Change process in coaching: Interplay of nonverbal synchrony, working alliance, self-regulation, and goal attainment. Frontiers in Psychology, 12, 580351.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。