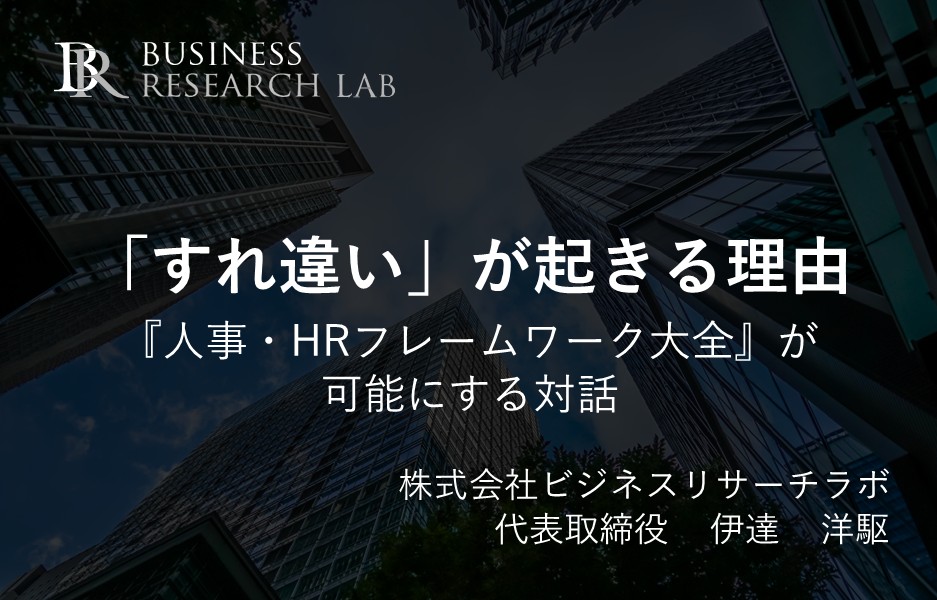2025年11月25日
「すれ違い」が起きる理由:『人事・HRフレームワーク大全』が可能にする対話
職場で日々繰り返される「話が噛み合わない」という瞬間。若手とベテラン、営業部門と開発部門、現場と経営層。私たちはなぜ、かくもすれ違うのでしょうか。その根源は、個人の能力や意欲の問題ではなく、組織に思考のOSとも言うべき「共通言語」がインストールされていないことにあるのかもしれません。
「もっと主体的に」「やる気が見えない」「それは前例がない」。こうした曖昧で、ときに感情的な言葉の応酬が、知らず知らずのうちに組織の活力を蝕んでいきます。互いの意図を誤解し、立場が違うだけで思考は断絶し、本来なら解決できるはずの問題が、人間関係のしこりへと変わっていく。この生産性のない「すれ違い」は、多くの組織が抱える停滞の要因です。
「すれ違い」というコミュニケーション不全がもたらすコストは、私たちが想像する以上に大きいものです。貴重なアイデアが共有されずに埋もれていく機会損失。誤解から生じる不信感が蔓延し、社員のエンゲージメントやメンタルヘルスを損なうリスク。優秀な人材が「この組織では建設的な対話ができない」と見切りをつけ、静かに去っていく離職の増加。これらは、対話の不在が生み出す、目に見えにくいながらも深刻な組織的損失です。
この度上梓した『人事・HRフレームワーク大全』は、こうした「すれ違い」の構造を解体し、組織に建設的な「対話」をもたらすための、いわば「対話のOS」をインストールするための実践の書です。本書に収録された83のフレームワークは、目に見えない心の問題や複雑な組織の力学に名前を与え、議論の土台を作る共通言語となります。
本コラムでは、良質な対話が職場でいかに起きるのか、具体的な会話のビフォーアフターを通じて、そのプロセスを追体験していただきたいと思います。
部下の「やる気」をめぐる、上司と部下のすれ違い
多くの管理職が頭を悩ませるのが、部下の動機づけの問題です。良かれと思ってかけた言葉が、なぜか部下の心を閉ざしてしまう。そんな「すれ違い」の場面から見ていきましょう。
【Before】ある個人面談の風景
- 上司:「最近、どうも◯◯さんの仕事は守りに入っているように見えますね。もっと積極的に、リスクを恐れず挑戦してほしいと思います」
- 部下:「(リスクを取って失敗したら評価が下がるじゃないか・・・)はい、挑戦できるよう頑張ります・・・」
この会話では、上司の「挑戦してほしい」という期待と、部下の「失敗したくない」という不安がすれ違っています。上司は良かれと思って檄を飛ばしますが、部下にとってはプレッシャーが増すだけで、具体的な行動にはつながりません。このやり取りは、部下の可能性を広げるどころか、萎縮させてしまう危険性があります。
ここで、上司が『人事・HRフレームワーク大全』を手に取り、部下の動機づけの「タイプ」や内面を理解するための視点を得たとします。これまで「やる気がない」「積極性がない」と一括りにしていた部下の状態を、より解像度高く分析するための言葉を、上司は手に入れるのです。
例えば「制御焦点理論」は、人の動機づけが、理想や成長を目指す「促進焦点」と、安全や義務を重視する「予防焦点」に分けられることを示唆します。上司は自分と同じ「促進焦点」を部下に求めていますが、部下は「予防焦点」の傾向が強いのかもしれません。この違いを理解することが第一歩です。
また、「情動的知能」の視点は、部下が抱える「不安」という感情をまず受け止める重要性を教えてくれます。「役割理論」に基づけば、上司と部下とで「期待される役割」の認識がズレている可能性も見えてきます。
特に「制御焦点理論」は、上司自身の思い込みを揺さぶる視点となります。例えば、同じ「新規顧客10件獲得」という目標に対しても、促進焦点の人は「新しい顧客との出会い」や「目標達成による賞賛」に心を躍らせる一方、予防焦点の人は「目標未達による叱責の回避」や「計画通りに業務を遂行する責任」に意識を向けます。どちらが良い悪いではなく、動機づけの源泉が異なるのです。
この上司は、自分が当たり前だと感じていた「挑戦=善」という価値観が、決して万人共通のものではないことに気づきます。部下の「慎重さ」は、やる気の欠如ではなく、責任感の現れである「予防焦点」の特性なのかもしれない。そう思考を切り替えることで、部下の内面で起きていることに想像力を働かせ、一方的な檄を飛ばすのではなく、対話のテーブルに着く準備が整います。
【After】「対話」が生まれる個人面談
- 上司:「私はどちらかと言うと新しい市場開拓など、どんどん攻めていきたいタイプなんですが、◯◯さんはむしろ、ミスなく着実に業務を進めるのが得意ですよね。その慎重さは、チームが大きな失敗をしないためにすごく重要です」
- 部下:「そうなんです。先の見えない挑戦ばかりだと、正直、不安で・・・」
- 上司:「その不安な気持ちに、これまで気づけていなかったです。◯◯さんに期待する役割は、ただ挑戦することだけではありません。その慎重さを活かして、新しい企画にどんなリスクが潜んでいるか洗い出す、という重要な役割を担ってもらえないですか」
この上司は、部下の特性を「守りに入っている」と否定的に見るのではなく、チームに不可欠な「慎重さ」という強みとして捉え直しました。フレームワークの知識は、相手の内面を深く理解し、その人に合った言葉で対話するための「思考の補助線」として機能します。これによって、一方的な指示が、個人の特性を活かすための協働的な対話へと変わります。
部門間の「壁」をめぐる、チーム同士のすれ違い
組織が成長するにつれて、専門性を持った部門が生まれます。しかし、その専門性が高まるほどに、部門間の連携は難しくなり、厚い壁が生まれることがあります。
【Before】ある部門間会議の風景
- 製造部長:「設計部はいつも理想ばかり追いかけて、製造現場のコストや実現性を考えていませんよね」
- 設計部長:「製造部はいつも『前例がない』ばかりで、新しい挑戦をしようとしない。だから競合に負けるんですよ」
ここでも、互いの立場からの主張がぶつかり合うだけで、建設的な議論に至りません。彼ら彼女らは同じ会社の成功を願っているはずなのに、いつしか互いを障害物と見なすようになっています。この対立を解消するためにも、フレームワークは有効な共通言語を提供します。
「分化・統合」というフレームワークは、部門ごとに専門性を高める「分化」が組織の強みである一方、それが行き過ぎると連携が失われるため、全体の目標に向かう「統合」の仕組みが必要だと教えてくれます。「分化」が進んだ組織は、しばしば「サイロ化」という壁に直面します。各部門が自部門の目標達成のみを追求するあまり、隣の部門が何に困っているのか、全社的な利益がどこにあるのかという視点が不足してしまうのです。これは部門のエゴイズムというより、組織構造が引き起こす帰結とも言えます。
「組織アイデンティティ」の視点は、部門ごとのプライドの衝突の背後で、「会社全体として我々は何者か」という共通の基盤が揺らいでいる可能性を示唆します。各部門のプライドは、「我々は設計のプロだ」「我々は製造のプロだ」という専門性に基づくもので、それ自体は尊重されるべきです。しかし、その上位に「我々は顧客に最高の品質を届けるチームだ」という共通のアイデンティティが確立されていなければ、専門性は協力ではなく対立の火種となってしまいます。
さらに、「メディアリッチネス」の考え方は、仕様書やメールだけのやり取りでは、複雑な問題に関する互いの真意が伝わりにくいことを明らかにします。これらの視点を得たファシリテーターは、会議の流れを変えることができるかもしれません。
【After】「協働」が生まれる部門間会議
- ファシリテーター:「両部門の専門性が高まっているのは、会社の強みです。ただ、今はその専門性がぶつかり合ってしまっているようですね。どうすれば両方の強みを活かして、会社全体として一つの目標に向かえるでしょうか。そもそも、会社として私たちがお客様に一番届けたい価値とは何だったか、もう一度そこに立ち返ってみませんか」
- 製造部長:「確かに。我々は『安定供給の担い手』という意識が強すぎたかもしれません」
- 設計部長:「一度、設計の初期段階から製造部の皆さんに入ってもらい、直接顔を合わせて話しましょう。仕様書だけのやり取りでは、どうしても伝わらない背景や意図がありますので」
このファシリテーターは、対立を個人の問題とせず、組織が成長する過程で自然に起こる構造的な課題として捉え直しました。より上位の共通目標に立ち返ることで、互いを責め合う関係から、共に解決策を探すパートナーへと関係性を再構築したのです。フレームワークは、部門の壁を越えた「我々」という視点を生み出し、対立を創造的な問題解決へと昇華させます。
会社の「未来」をめぐる、経営と現場のすれ違い
大きなすれ違いが起きやすい、経営層と現場との間の対話について考えてみましょう。経営者が壮大なビジョンを語っても、現場は冷めた反応しか示さない。多くの企業がこの種の問題に直面しています。
【Before】ある全社会議の風景
- 経営者:「3年後、我が社は業界のリーディングカンパニーとなります。そのためにDXを断行します」
- 現場社員:「(3年後なんて遠すぎて実感が湧かない・・・今日の業務で手一杯なのに・・・)・・・(他人事のような拍手)」
経営者が語る立派な理念やビジョンが、現場の日常業務と結びつかず、「お題目」として消費されていく。この乖離は、変革へのエネルギーは生まれず、現状維持の空気を組織に蔓延させます。このすれ違いの構造も、フレームワークを使えば理解しやすくなります。
「解釈レベル理論」は、人は対象との心理的な距離によって物事の捉え方が変わることを示します。経営者が語る「3年後」は距離が遠いため抽象的な「なぜ」の話になり、現場が考える「今日」は距離が近いため具体的な「どうやるか」の話になります。この認識のズレが、対話を困難にしているのです。
「組織変革」には、まず現状への固執を溶かす「解凍」、新しいやり方を試す「移行」、定着させる「再凍結」という段階が必要です。とりわけ重要なのが最初の「解凍」です。人は現状維持を望むもの。その固まった意識を丁寧に解かし、なぜ今変わらなければならないのかということを共有し、変化への必要性を腹落ちしてもらわない限り、どんなに優れた変革プランも「絵に描いた餅」で終わってしまうでしょう。
加えて、「VRIOフレームワーク」は、変革の土台となる自社の強みを客観的に分析する視点を提供します。これらの思考法を身につけた経営者の言葉は、自然と現場に届くものに変わります。
【After】「変革」が始まる全社会議
- 経営者:「今日は『3年後の未来』という大きな話だけでなく、それを実現するための『次の3ヶ月で私たちが具体的にできること』について、皆さんの知恵を貸してほしいと考えています。まず、なぜ今変わる必要があるのか、皆で危機感を共有することから始めたいです」
- 現場リーダー:「我々の現場のノウハウは、他社には簡単に真似できない強みのはずですが、それを活かす仕組みになっていない点が問題だと感じています」
- 経営者:「その通りですね。皆さんの意見を取り入れながら、まずは一部のチームで新しいやり方を試験的に導入してみたいと思います。そして、その成功事例を元に、全社の正式な制度として根付かせていきたい。このプロセス全体を、皆さんと共に歩んでいきたいと考えています」
経営者は、抽象的な未来と具体的な現在地とを意図的に結びつけました。そして、変革を一方的に宣言するのではなく、現場と共に段階的に進めていくプロセスを共有することで、現場の不安を和らげ、変革への当事者意識を引き出しました。フレームワークは、壮大なビジョンと日々の実践を結びつける機能を果たします。
対話の質を高めるフレームワーク
ここまで見てきたように、人と組織をめぐる問題の根源は、多くの場合「対話の質の低さ」にあります。私たちは同じ言葉を使いながら、まったく違う意味を思い浮かべ、互いの意図を汲み取れずにすれ違っています。
『人事・HRフレームワーク大全』が提供する価値の一つは、対話の質を向上させるための「共通言語」と「思考のOS」を組織に提供することにあります。83の多様な思考の道具は、様々な「すれ違い」の場面で、その構造を解き明かし、議論を建設的な方向へと導くための言葉と視点を与えてくれます。
この本は、一度読んだら終わり、という類のものではありません。皆さんの机の傍らに置かれ、日々の対話の中で繰り返し参照していただけると嬉しいです。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。