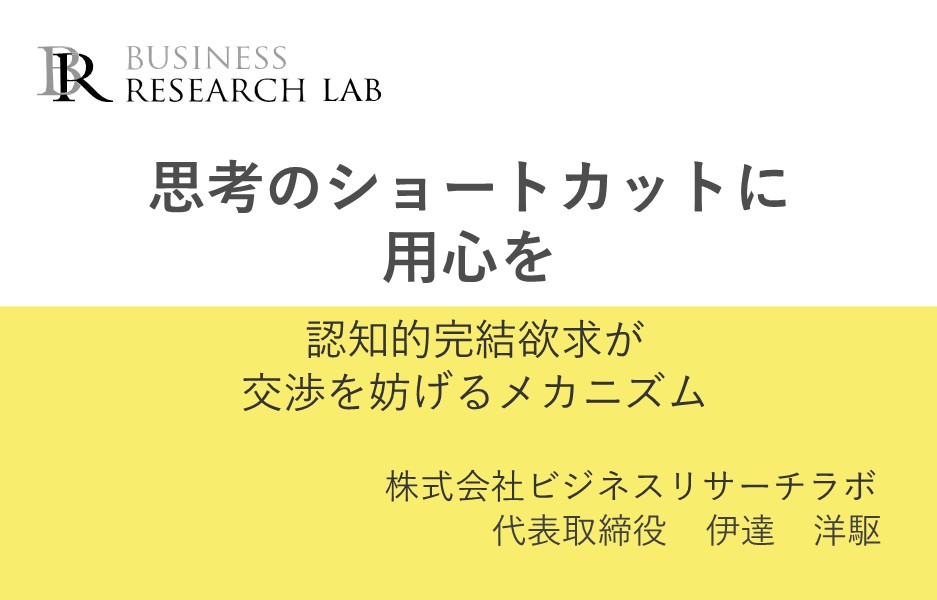2025年11月21日
思考のショートカットに用心を:認知的完結欲求が交渉を妨げるメカニズム
私たちは日々、大小さまざまな判断を繰り返しながら生きています。その際、自分の判断は論理的で客観的なものだと信じたいものです。しかし、もしその判断が、意識の及ばない心の奥底にある、ある一つの強い欲求によって静かに方向づけられているかもしれません。
その欲求とは、「早く答えが欲しい」「物事を白黒はっきりさせたい」という感覚に根差しています。心理学では、このような「曖昧さを避け、確固たる結論を求める動機」を「認知的完結欲求」と呼びます。この欲求は、複雑な世界で迅速に判断を下すための精神的なエネルギー源となる側面も持ちます。混沌の中から一つの確かな答えを見つけ出せた時の安心感は、大きなものでしょう。
しかし、この「確実性への渇望」が強すぎると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。急いで結論に飛びつくあまり、物事の一面しか見えなくなったり、一度信じたことを頑なに変えられなくなったりするのです。この心の働きは、私たちが他者や社会と関わる上でのさまざまな判断、例えば、所属集団への感情や他者との交渉の進め方などに作用を及ぼします。本コラムでは、このメカニズムがもたらす判断の偏り、すなわちバイアスを、科学的な研究を手がかりに解き明かしていきます。
認知的完結欲求が高いと自集団びいきや外集団軽視が強まる
私たちは人生の様々な場面で何らかの集団に所属し、自分が属する集団(自集団)には好意を、それ以外の集団(外集団)とは一線を画そうとします。この「身内びいき」の度合いが、「早く答えが欲しい」という認知的完結欲求の強さと関連しているとしたらどうでしょうか。この欲求が、私たちを分ける心の壁をどのように強固にするのかを探った研究があります[1]。
まず、多様な民族的背景を持つアメリカの大学生を対象とした調査が行われました。参加者は認知的完結欲求の強さを測る質問票に回答し、同時に自分の所属する民族集団とそれ以外の集団への好感度を評価しました。結果を分析したところ、認知的完結欲求のスコアが高い人ほど、自集団に高い好感度を報告する一方で、外集団には低い評価を下すという関係性が見出されました。
この結果の背後には何があるのでしょうか。認知的完結欲求が高い人々にとって、世界は明確で予測可能な場所であってほしいのです。しかし現実は複雑で曖昧です。この不安を和らげるための一つの方法が、自分たちが共有する価値観、要するに「共有された現実」に頼ることです。
その最も手近な源泉が、自分が所属する集団です。所属集団が提供する答えは、確実性を求める心に安心材料を与えます。その結果、安心感の源である自集団を高く評価し、その枠組みを脅かす可能性のある外集団を遠ざけることで、自分の信じる世界の安定を保とうとするのではないか、と考えられます。
しかし、この調査だけでは因果関係は不明確です。そこで、第二の研究として実験室での実験が行われました。参加した大学生をランダムに二人一組のチームに分け、別のチームと課題の成績を競わせました。ここで認知的完結欲求を実験的に操作するため、参加者の半分のチームには非常に厳しい時間制限を課しました。時間的プレッシャーは、一時的に認知的完結欲求を高めることが知られています。もう半分のチームには時間制限を設けませんでした。
この状況で、自分のチームメイト(自集団)と競争相手(外集団)への「一体感」や、課題解決の戦略をどちらから採用するかを測定しました。結果は予測通りでした。厳しい時間制限を課せられた参加者は、時間制限のない参加者に比べて、自分のチームメイトへの一体感を著しく高め、逆に対戦相手への一体感を低下させました。行動面でも、味方の提案を優先的に採用し、競争相手からの提案を退ける動きが強まりました。
この実験が示したのは、もともとの性格とは関係なく、状況によって「確実性を求める気持ち」が高まるだけで、即席の集団に対してさえ強い身内びいきと排他性が生まれるということです。不確実な競争状況というストレス下で、人々は手近な「味方」を確かな情報源とみなし、そこに固執することで精神的な安定を得ようとするのでしょう。これらの調査と実験は、認知的完結欲求が、私たちが所属する集団を現実理解の「確かな基準」として扱うことを促し、その結果、自集団を感情的・行動的に優先するという一貫したバイアスを生じさせることを示唆しています。
認知的完結欲求が高いと公正世界観と性差本質視で女性上司を否定
集団という枠組みで「仲間」と「そうでない人々」を区別する心理は、社会に存在するステレオタイプと結びついた時、何が起こるのでしょうか。「早く答えが欲しい」という認知的完結欲求が、特定の属性を持つ人々への偏見をどう育むのか。女性が管理職になることへの否定的な態度を例に、その心の連鎖を解き明かした研究を見ていきます[2]。
この研究は、認知的完結欲求が高い人ほど「女性は管理職に向いていない」と考えやすい現象の、心理的プロセスを探求しました。研究者たちは、両者の間にいくつかの「信念」が介在するとの仮説を立てました。
初めに、曖昧さを嫌い物事を単純な枠組みで捉えたい人は、「世界は基本的に公正な場所であり、努力は報われる」という考え方を魅力的に感じやすいのではないか、という点です。この「公正世界観」は、複雑な現実に「最終的には全てが然るべきところに収まる」というシンプルな秩序を与え、確実性を求める心に心地よく響きます。
続いて、「世界は公正だ」と信じる人は社会の現状を肯定しやすくなります。もし世の中が公正なら、現在の社会的な序列や役割分担にも理由があるはずだと考えるからです。この思考は、「男女の特性は生まれつき異なり、それぞれに適した役割も本質的に決まっている」という「性差本質主義」へとつながりやすくなります。
最終的に、この性差本質主義は「管理職の資質は本質的に男性的なものであり、女性には合わない」という結論を導き、女性管理職への否定的な態度として現れるわけです。認知的完結欲求から偏見までが、「公正世界観」と「性差本質主義」によって連鎖していく、というのが仮説でした。
この仮説を検証するため、イタリアの成人を対象にオンライン調査が行われました。参加者は認知的完結欲求、公正世界観、性差本質主義、そして女性管理職への態度を測る尺度に回答しました。分析の結果、まず認知的完結欲求が高い人ほど、女性管理職に否定的な態度を示す関係が確認されました。
しかし、この研究の真骨頂は、その関係性の内訳を分析した点にあります。統計的な分析で、仮説通りの連鎖が浮かび上がりました。認知的完結欲求の高さは、まず公正世界観を信じさせ、その公正世界観が性差本質主義を強め、それが最終的に女性管理職への否定的な態度につながる、という間接的な経路が判明したのです。これら二つの信念を考慮に入れると、認知的完結欲求から否定的態度への直接的な結びつきは見られなくなりました。認知的完結欲求が偏見を生むプロセスが、これらのイデオロギー的な信念によって説明されることを示唆しています。
この結果が描き出すのは、「白黒つけたい」という動機が、社会的なイデオロギーと結びつき、具体的な偏見として結晶化する心のプロセスです。不確実性を嫌う気持ちが「世界は公正だ」という分かりやすい物語を採用させ、それが「男女の役割分担も自然で公正だ」という現状肯定の論理を補強し、その先に差別的な結論を導き出してしまうのです。
認知的完結欲求が高いと交渉で初期手がかりに固執し譲歩が減る
個人と個人が向き合う「交渉」の場面に目を向けてみましょう。交渉の場は不確実性に満ちています。相手が何を考えているのか、どこまで譲歩するのか。限られた情報の中で最適な着地点を探す必要があります。このような曖昧な状況で、「早く結論が欲しい」という認知的完結欲求は、私たちの判断や行動にどのような作用を及ぼすのでしょうか。
ある研究では、認知的完結欲求が高い人ほど、交渉の初期段階で得た手がかりに飛びつき、その後の判断を変えようとしない「思考の硬直化」が起こるという仮説が立てられました[3]。このプロセスは「把握(seizing)」と「凍結(freezing)」で説明されます。「把握」とは、曖昧さから抜け出すために手近な情報に素早く飛びつく段階、「凍結」とは、一度判断を固めると追加情報を軽視し、当初の判断を維持しようとする段階です。このプロセスが交渉の柔軟性を妨げると考えられました。
これを検証するため、大学生が売り手役を演じる交渉シミュレーション実験が行われました。実験のポイントは、交渉前に与えられる「焦点値」という情報です。参加者の一部には高い利益を示唆する情報、別の一部には低い利益を示唆する情報が与えられ、何も与えられないグループもいました。参加者は事前に測定された認知的完結欲求のスコアで高低のグループに分けられました。
実験の結果、高い焦点値を与えられた参加者は、自分が確保したい利益のラインを高く設定し、譲歩額も少なくなりました。しかし、この研究の核心は、認知的完結欲求の高さでこの作用がどう変わるかでした。分析の結果、焦点値の作用は、認知的完結欲求が高いグループで明らかに強く現れていました。欲求が高い人々は、最初に与えられた数字に固執し、なかなか譲歩しませんでした。一方で、欲求が低い人々は焦点値にそれほど左右されず、より柔軟に交渉を進めました。
この硬直性は、相手へのステレオタイプのような社会的な情報でも生じるのでしょうか。二つ目の実験では、交渉相手が「ビジネス専攻(競争的というステレオタイプ)」か「神学専攻(協調的というステレオタイプ)」であると参加者に教えました。
結果は、ここでも認知的完結欲求の個人差を浮き彫りにしました。欲求が低い参加者は、相手の専攻によって譲歩の仕方に大きな違いは見られませんでした。対照的に、欲求が高い参加者の行動は、相手の専攻によって異なりました。相手が競争的とされるビジネス専攻だと知らされると、途端に態度を硬化させ、譲歩を渋ったのです。
これは、認知的完結欲求が高い人が、不確実な相手を理解する簡単な手がかりとしてステレオタイプに「飛びつき」、そのレッテルに基づいて硬直した戦略を「凍結」させたことを物語っています。早く確実な答えを得たいという気持ちが、複雑な状況を単純化するためのヒューリスティックへの依存を強め、交渉における柔軟な対応能力を損なわせる可能性があります。
認知的完結欲求尺度が高い信頼性と判断偏り予測力を示した
ここまで、認知的完結欲求が集団関係、偏見、交渉行動に及ぼすバイアスを見てきました。この「白黒はっきりさせたい」という動機は、どのように科学的に捉えられているのでしょうか。この欲求を安定した個人差として測定するための「物差し」を開発し、その信頼性と妥当性を検証した研究があります[4]。
この研究以前、認知的完結欲求は主に実験室で一時的に高められる状況的な変数として扱われていました。しかし研究者たちは、この欲求が安定した個人的特性として存在すると考え、その個人差を捉えるために「認知的完結欲求尺度(NFCS)」を開発しました。
尺度の開発にあたり、この欲求は(1)秩序志向、(2)予測可能性志向、(3)決断性、(4)両義性への不快、(5)閉鎖的思考という五つの側面に現れると理論づけられました。これらはすべて「曖昧さを避け、確実な答えを求める」という一つの根源的な動機から派生していると考えられます。多くの参加者への調査と統計分析を経て、信頼性の高い42項目が選抜されました。開発された尺度は、何度測定しても安定した結果が得られ、尺度全体として内的に一貫した概念を測定していることが確認されました。
この尺度の妥当性を確かめる検証が行われました。この尺度のスコアは、独断的な態度や権威主義とはある程度の正の関連を、曖昧さへの耐性とは負の関連を持つことが分かりました。これは概念的に近いものと確かに関連していることを示すものです。同時に、知的好奇心や知能指数とはほとんど関連が見られなかったことから、この尺度が「確実性を求める動機」の強さを測定していることが裏付けられました。
この尺度の予測力を試すため、一連の行動実験が実施されました。例えば、ある実験では、人物の性格に関する情報を順番に提示すると、認知的完結欲求のスコアが高い人ほど、最初に提示された情報に強く影響され、早々に印象を固めてしまうことが分かりました。別の実験では、状況的な制約があったとしても、認知的完結欲求が高い人はその制約を十分に考慮せず、文章の内容を書き手の本心だと結論づけてしまう「対応バイアス」と呼ばれる偏りを強く示しました。
これらの実験結果は、この尺度で測定される個人差が、人々の情報処理や社会的判断に一貫したバイアスをもたらすことを明確にしました。この尺度は、人々の日常的な判断の癖を予測する力を持つ、信頼できる「物差し」であることが証明されたのです。
脚注
[1] Shah, J. Y., Kruglanski, A. W., and Thompson, E. P. (1998). Membership has its (epistemic) rewards: Need for closure effects on in-group bias. Journal of Personality and Social Psychology, 75(3), 383-393.
[2] Baldner, C., and Pierro, A. (2024). The impact of the need for cognitive closure on attitudes toward women as managers: The sequential mediating role of belief in a just world and gender essentialism. Behavioral Sciences, 14(3), 196.
[3] de Dreu, C. K. W., Koole, S. L., and Oldersma, F. L. (1999). On the seizing and freezing of negotiator inferences: Need for cognitive closure moderates the use of heuristics in negotiation. Personality and Social Psychology Bulletin, 25(3), 348-362.
[4] Webster, D. M., and Kruglanski, A. W. (1994). Individual differences in need for cognitive closure. Journal of Personality and Social Psychology, 67(6), 1049-1062.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。