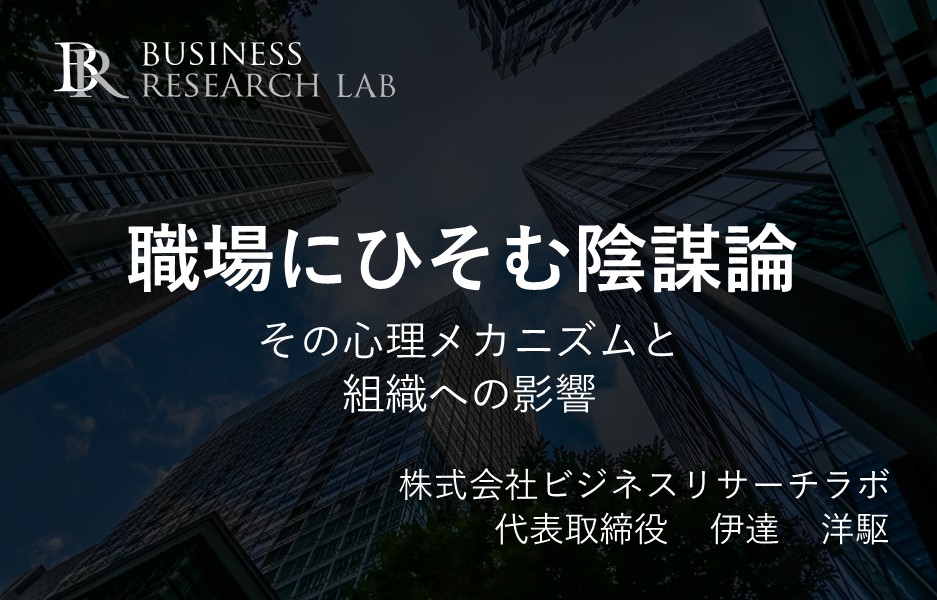2025年11月21日
職場にひそむ陰謀論:その心理メカニズムと組織への影響
私たちの周りには、真偽の定かではない情報が流れています。特に近年、特定の出来事の背後には、公にされていない強力な集団の意図が隠されているとする「陰謀論」が、社会的な関心事となる場面が増えました。こうした思考の様式は、私たちにとって最も身近な社会である「職場」にも静かに浸透している可能性があります。
なぜ、人は陰謀論的な見方に惹かれるのでしょうか。もし自らが働く組織の中で、「上層部は何かを隠している」「この不利益な決定は、一部の人間が裏で手を引いた結果だ」といった考えが蔓延したとしたら、そこでは一体何が起きるのでしょうか。従業員一人ひとりの心にはどのような変化が生じ、組織全体としてはどのような代償を払うことになるのでしょうか。
本コラムでは、職場における陰謀論という、これまであまり光が当てられてこなかった問題に迫ります。近年の研究成果を手がかりに、まず人が陰謀論的な発想に至る心の仕組みを解き明かし、それが個人の世界観をどのように形成するのかを見ていきます。その上で、舞台を職場に移し、組織内での陰謀をめぐる信念が、従業員の心や行動、ひいては組織と個人の関係性にどのような帰結をもたらすのかを紐解いていきます。
人は統制感が脅かされると敵の力を過大視する
私たちは日々の生活の中で、自分の力ではどうにもならない出来事に直面することがあります。大規模な自然災害、予期せぬ事故、あるいは世界経済の大きな変動など、個人の意思を超えた力によって自らの平穏が脅かされるという経験は、誰にとっても不安なものです。このような、自分を取り巻く環境を自分の力で制御できているという感覚、すなわち「統制感」が揺らいだとき、人の心の中では一体何が起こるのでしょうか。
この問いに答えるための手がかりとなる一連の心理学実験があります[1]。そこでは、人が「敵」という存在を、自らの心の安定を保つためにどのように利用するのか、そのメカニズムが探求されました。
最初の実験は、大学生を対象に行われました。参加者はまず、自分の人生をどれくらいコントロールできていると感じているかを測る質問に答えます。その後、二つのグループに分けられ、一方のグループは「自分ではコントロールしようのない要因で死に至るリスク(例えば、交通事故に巻き込まれる)」について考えるよう求められ、もう一方のグループは「自分自身の不注意や不健康な習慣が原因で死に至るリスク(例えば、不摂生な食生活)」について考えるよう指示されました。これは、前者のグループの統制感を意図的に脅かすための手続きです。
その後、全員に「あなたの個人的な敵、あるいはライバルと呼べる人物」か、もしくは「ただ単に好きではない、不快な人物」のどちらか一人を思い浮かべてもらい、その人物が自分の人生にどれほどの影響力を持っていると思うかを評価させました。
結果、自分ではコントロールしようのない死のリスクについて考えさせられた参加者のうち、もともと人生への統制感が低いと回答していた人たちだけが、「個人的な敵」の持つ影響力を非常に大きいものだと評価しました。一方で、同じ条件であっても「ただ不快な人物」の影響力は大きいとは評価されませんでした。
このことから、人は自分の手に負えない脅威にさらされて統制感を失うと、その原因を身近な「敵」に押し付け、その敵が強力な力で自分の人生を左右しているのだと解釈することで、漠然とした不安に対処しようとする心の動きがあると考えられます。世界に散らばる偶発的で捉えどころのない危険を、一つの人格を持った「敵」の仕業に集約することで、複雑な世界を少しでも理解しやすく、対処可能なものとして捉え直そうとしているのかもしれません。
この心の働きは、個人的な人間関係だけにとどまりません。次の実験は、アメリカ大統領選挙の投票日直前という、社会的な緊張感が高まる時期に行われました。参加者は、まず「自分の力では制御できない自然災害」に関する文章を読むグループと、そうでない対照グループに分けられました。これも統制感を操作するための手続きです。その後、自分が支持する候補者の「敵」にあたる、対立候補にまつわる陰謀論的な言説(例えば、「対立候補の陣営が、投票結果を不正に操作しようと企んでいる」)をどれくらい信じるかを尋ねました。
ここでも、統制感を脅かされたグループは、そうでないグループに比べて、対立候補が選挙を陰で操っているという陰謀論を信じることがわかりました。しかし、ここで注目すべきは、統制感を脅かされたからといって、対立候補そのものへの個人的な嫌悪感が強まったり、あるいは選挙とは無関係な一般的な陰謀論(例えば、「政府は宇宙人の存在を隠している」)を信じやすくなったりはしなかったという点です。
人はコントロールを失った不安を解消するために、手当たり次第に何でも信じるわけではないのです。その不安の原因を帰せる、はっきりとした「敵」が存在する場合に限り、その敵が持つ影響力を選択的に大きく見積もるという、的を絞った心の動きがあることがうかがえます。
「敵」への責任転嫁は、いつでも起こるのでしょうか。三つ目の実験は、この疑問に答えるものです。
この実験でも、参加者は最初に統制感を脅かす操作を受けます。その後、二つのグループに分かれ、一方は「アメリカの社会システムは非常に秩序立っており、政府は国民をしっかり守っている」という内容の文章を、もう一方は「アメリカの社会は混沌としており、システムはうまく機能していない」という内容の文章を読みました。その上で、日常生活で起こる様々なネガティブな出来事(例えば、仕事で失敗する、友人関係がうまくいかない)の原因が、「特定の敵のせい」「単なる偶然のせい」「友人のせい」のどれにあたると思うかを評価させました。
その結果、社会が「無秩序」であると聞かされた場合に限り、統制感を脅かされた参加者は、ネガティブな出来事を「敵のせい」にする考えを強めました。逆に、社会が「秩序立っている」と聞かされた参加者は、敵への責任転嫁を強めることはなく、代わりに「政府は強力で頼りになる」という認識を高めることで心の安定を保とうとしました。これは、自分を守ってくれる社会システムへの信頼が、漠然とした不安に対する防波堤として機能することを示しています。頼れるものが他にあると感じられるとき、人は必ずしも「敵」を必要とはしません。
最後に行われた四つ目の実験は、この「敵」の性質について、さらに掘り下げています。この実験でも参加者の統制感を操作した後、国際的なテロ組織について、三種類の異なる説明を提示しました。第一のグループには「テロ組織は、その目的や能力がはっきりとはわからない、曖昧だが強大な敵である」と説明しました。第二のグループには「テロ組織の目的や能力は明確であり、強大な敵である」と説明しました。そして第三のグループには「テロ組織は弱い敵である」と説明しました。
その後、参加者たちに、今後10年以内に自分の身に様々な不運が降りかかる確率を予測してもらい、同時に現在の統制感の度合いも測定しました。
ここでの発見は、統制感を脅かされた参加者が「曖昧で強大な敵」について読んだ場合に、将来自分に降りかかる不運の確率を低く見積もり、さらには自分自身の統制感が回復するという結果が得られたことです。敵の力が「明確で強大」あるいは「弱い」と説明された場合には、このような統制感の回復は見られませんでした。敵の存在が、かえって将来へのリスク認識を高めてしまったのです。
このことは、私たち人間が不安を和らげるために求める「敵」とは、単に力が強いだけの存在ではないことを物語っています。その目的や力の及ぶ範囲がはっきりしない、捉えどころのない「曖昧さ」をまとっているからこそ、世の中のあらゆる理不尽な出来事をその存在のせいにして説明することが可能になるのです。
陰謀論は個別の事件を超えた一貫した信念である
ある特定の事件について、「公式発表の裏には何かある」と疑う気持ちを持つことと、世の中の出来事の多くを陰謀と結びつけて考えることとは、同じなのでしょうか、それとも異なるのでしょうか。陰謀論に関するこれまでの研究の多くは、「ケネディ大統領暗殺事件の真相」や「アメリカ同時多発テロ事件の背後関係」といった、個別の歴史的事件に関する信条を尋ねることで、人々の陰謀論への傾倒度を測ってきました。
しかし、このアプローチにはいくつかの課題がありました。取り上げる事件が文化や時代によって異なり、普遍的な測定が難しいことや、心理学的な測定尺度としての信頼性や妥当性が十分に検証されてこなかったことなどが挙げられます。
そこで、こうした個別具体的な事件への言及を避け、「世の中の出来事は、しばしば権力者によって裏で操られている」といった、より一般的で抽象的な信念の度合いを測定する新しい試みがなされました[2]。この試みは、陰謀論への信奉が、個別の事件に対する散発的な疑いの集合体なのではなく、世界をどう見るかという、首尾一貫した考え方の枠組み、いわば「陰謀論的な世界観」とでも呼ぶべきものである、という考えに基づいています。
この新しい測定尺度を開発する過程は丁寧に進められました。まず、既存の学術文献や、広く一般に流布している様々な陰謀論に関する言説が幅広く収集・分析されました。そして、それらの言説から特定の事件名や固有名詞を取り除き、「政府は国民に隠れて不都合な活動を行うことがある」「ごく少数の人々が、世界的な出来事を秘密裏に操っている」といった、75個の汎用的な信念を表す項目が作成されました。
続いて、この75項目を含む質問紙調査が、数百人規模のオンライン参加者を対象に実施されました。集められたデータを分析した結果、これらの多様な信念は、大きく五つのグループに分類できることがわかりました。
一つ目は「政府の不正行為」に関する信念で、政府がテロを自作自演したり、国民を欺いたりするといった考えが含まれます。二つ目は「邪悪な世界的陰謀」で、国際的なエリート集団が世界を支配しているといった信念です。三つ目は「地球外生命体の隠蔽」、四つ目は「個人の自由と健康への脅威(例えば、新薬に隠された危険)」、五つ目は「情報の統制(例えば、メディアが重要な情報を隠している)」に関する信念でした。
これら五つの因子は、それぞれが独立しているわけではなく、互いに関連し合っていました。つまり、「政府は不正を働く」と信じている人は、「世界は秘密結社に支配されている」とか「メディアは情報を隠蔽している」といった他の陰謀論的な考えも同時に信じやすいという関係が見られたのです。このことは、陰謀論への信念が、やはり個別のテーマごとにバラバラに存在するのではなく、根底でつながった一つの大きな信念体系、いわば「一枚岩」のような構造を持っている可能性を裏付けています。
この新しく開発された尺度が、本当に信頼できるものなのか、そして的確に「陰謀論的な世界観」を捉えられているのかを確かめるために、さらなる検証が行われました。同じ大学生の集団に五週間の間隔をあけて二度、この尺度に回答してもらったところ、二回の結果は安定していました。この汎用的な尺度と、従来の「9/11事件の陰謀」といった具体的な事件に関する陰謀論尺度との関連が調べられました。その結果、両者には強い正の相関が見られました。つまり、一般的なレベルで「陰謀は存在する」と信じている人ほど、個別の事件についても「あれは陰謀だ」と信じやすいということです。
さらに、この陰謀論的な世界観が、他のどのような心理的な特性と結びついているのかも調査されました。その結果、陰謀論的な信念が強い人ほど、他人を信じにくい(対人信頼感の低さ)、社会はどんどん悪くなっていると感じている(アノミー感)、超常現象や非科学的な事柄を信じやすいといった特徴を持つことがわかりました。これらの関連性は、これまでの研究で指摘されてきた陰謀論を信じやすい人々の心理的特徴と一致しており、この尺度が理論的な観点からも妥当であることを補強しています。
逆に、個人の性格特性(外向性や協調性など)や、情動的な知性、スリルを求める感覚追求傾向といった、理論的に陰謀論とは直接関係がなさそうな特性とは、ほとんど関連が見られませんでした。
一連の検証から明らかになったのは、陰謀論を信じるという現象が、単発の出来事に対する孤立した疑念ではないということです。それはむしろ、「政府は信用できない」「世界は少数のエリートに支配されている」「真実は隠されている」といった、より抽象的で汎用的な信念が相互に結びつき、補強しあって形成された、一貫性のある世界観であると考えられます。
職場の陰謀的解釈は離職や内部告発を促進する
これまでのところで、人はなぜ陰謀論的な考えに至るのか、それが個別の疑いを超えた一貫した世界観を形成する過程を見てきました。ここからは、そのレンズを「職場」という私たちにとって身近な舞台に絞ってみたいと思います。情報が必ずしもすべてオープンにされるわけではなく、役職による権力の差が存在する職場という環境は、時に様々な憶測や不信感を生み出す場所ともなりえます。職場で起きる出来事や決定事項が、「これは上層部の一部の人々が、自分たちの利益のために裏で仕組んだことに違いない」といった形で解釈されるとしたら、それは組織と従業員の関係にどのような変化をもたらすのでしょうか。
この問いに答えるため、韓国の様々な業種で働くフルタイムの正社員600名を対象とした調査が行われました[3]。この調査の中心的な概念は、「職場における陰謀的帰属(Workplace Conspiracy Attribution)」と名付けられたものです。これは、従業員が職場で発生した問題や組織の重要な変化に直面した際に、その原因を「組織内の有力者が秘密裏に計画し、実行した結果だ」と見なす考え方の強さを指します。
この調査では、まず、どのような職場環境が、こうした陰謀的な解釈を生み出しやすいのかが探られました。特に注目されたのは、「双方向的なコミュニケーション」と「組織の倫理志向」という二つの要素です。前者は、従業員が経営陣に対して自由に意見を述べたり、質問したりできるか、経営陣がそれに真摯に耳を傾けるか、といったコミュニケーションのあり方を指します。後者は、組織が意思決定を行う際に、短期的な結果や利益だけを追い求めるのではなく、公正で透明性のある手続きやプロセスを重んじる姿勢をどれだけ持っているか、という点です。
分析の結果、「双方向的なコミュニケーション」が活発な職場であっても、それが直接的に「陰謀的な解釈」を減らすことにはつながらないということがわかりました。では、コミュニケーションは無意味なのでしょうか。そうではありません。双方向のコミュニケーションは、従業員が「この組織は、公正な手続きを重んじる倫理的な組織だ」と感じる認識(倫理志向)を高める上で、強い正の関係を持っていました。そして、この「組織は倫理的だ」という認識は、従業員の陰謀的な解釈を抑制する力を持っていました。
要するに、従業員との対話そのものが陰謀論を消し去るのではなく、対話を通じて育まれた「この組織は公正だ」という信頼感が、物事を裏で操られているかのように捉える見方を防ぐ防波堤として機能していたのです。公正なプロセスが可視化され、従業員に理解されている環境では、陰謀が入り込む余地が少なくなるという構造が見て取れます。
この調査では、職場での陰謀的な解釈が、従業員の行動にどのような結果をもたらすのかが検証されました。ここで焦点が当てられたのは、「離職意図」と「内部告発の可能性」です。離職意図とは、近い将来、現在の職場を辞めたいと考えている度合いを指します。内部告発の可能性は、もし組織内で不正や非倫理的な行為を知った場合に、それを外部の機関などに通報する可能性を意味します。
結果的に、職場の出来事を陰謀として解釈する考え方が強い従業員ほど、「この会社を辞めたい」という離職意図が高まることが確認されました。それと同時に、こうした従業員は「もし不正があれば内部告発も辞さない」と考える可能性も高いことがわかりました。陰謀的な解釈が蔓延することは、単に職場の雰囲気が悪くなるという問題にとどまりません。それは、組織が時間とコストをかけて育成してきた人材の流出に直結するということです。
職場の陰謀信念は組織への愛着を下げ離職を促す
職場で「経営陣は、従業員に隠れて何かよからぬことを企んでいるのではないか」という疑念が頭をもたげたとき、私たちの心にはどのような変化が起こるのでしょうか。先ほどは、そうした陰謀的な解釈が、最終的に離職という行動につながりうることを見ました。しかし、人が「会社を辞める」という大きな決断に至るまでには、多くの場合、いくつかの心理的な段階が存在します。ここでは、職場における陰謀への信念が、どのようにして従業員の心を組織から引き離していくのか、そのメカニズムを探求した一連の研究を紹介します[4]。
この研究の核心にあるのは、「組織内陰謀信念(organizational conspiracy belief)」という概念です。これは、自分が働く組織の経営陣や上層部が、一般の従業員には秘密で、従業員にとって不利益となるような計画を立て、実行していると信じる度合いを指します。研究者たちは、この陰謀信念そのものが直接的に離職を引き起こすというよりも、従業員の組織に対する感情的なつながりを断ち切り、離職意図が高まるのではないか、という仮説を立てました。感情的なつながりを代表する二つの重要な指標として、「組織コミットメント」と「職務満足感」が設定されました。
組織コミットメントとは、従業員が自分が所属する組織に対して抱く愛着や一体感のことです。組織の目標や価値観に共感し、「この組織の一員であり続けたい」と願う気持ちを指します。一方、職務満足感は、自分の仕事内容そのものや、給与、人間関係、労働環境など、仕事の様々な側面に対する肯定的な感情や満足の度合いを意味します。仮説は、組織内陰謀信念が高まると、これら二つの感情が損なわれ、その結果として離職への道が開かれるというものでした。
仮説を検証するために、アメリカで働く数百人の社会人を対象とした横断的な調査が行われました。参加者は、自身の職場に関する陰謀信念、組織コミットメント、職務満足感、離職意図について、それぞれ質問票に回答しました。分析の結果、組織内陰謀信念が高い人ほど、離職を考えている度合いが強いという関係が確認されました。そして、より詳細な分析によって、この関係の裏にあるメカニズムが明らかになりました。組織内陰謀信念は、従業員の組織コミットメントと職務満足感の両方を低下させていました。そして、この低下したコミットメントと満足感が、離職意図を高める原因となっていました。
しかし、このような調査だけでは、「陰謀信念がコミットメント低下の原因」なのか、それとも逆に「コミットメントが低いから陰謀を信じやすい」のか、という方向性を検討することは困難です。そこで、この因果関係をより明確にするために、二つの実験研究が計画されました。
最初の実験では、参加者はランダムに二つのグループに分けられ、架空の企業に関するシナリオを読むよう指示されました。一方のグループが読んだのは、従業員の意見が尊重され、公正な評価が行われる「ポジティブな組織風土」を持つ企業のシナリオでした。もう一方のグループが読んだのは、経営陣が情報を隠し、従業員を不公平に扱う「ネガティブな組織風土」を持つ企業のシナリオでした。後者のシナリオは、参加者の心に組織内陰謀信念を芽生えさせることを意図して作られています。
シナリオを読んだ後、参加者はその架空の企業に対する陰謀信念や、もし自分がそこで働いていたら感じるであろう組織コミットメント、職務満足感、そして離職意図を評価しました。
結果は予測通りでした。ネガティブな組織風土のシナリオを読んだグループは、ポジティブなシナリオを読んだグループに比べて、組織内陰謀信念を強く抱きました。それに伴い、組織コミットメントと職務満足感は低く、離職意図は高くなりました。この実験結果は、ネガティブで不透明な組織の状況に置かれることが、陰謀信念を生み出し、それが組織への愛着を失わせ、離職へとつながるという一連の連鎖が存在することを示唆するものです。
念を押すため、三つ目の研究として、より直接的に陰謀のシナリオを提示する実験が行われました。この実験でも参加者は二つのグループに分かれました。一方のグループは、「経営陣が、社内表彰の結果を自分たちのお気に入りの従業員が受賞するように不正に操作した」「経営陣が、自分たちのボーナスを確保するために、一般従業員の賃金を引き下げる計画を秘密裏に進めている」などといった、具体的な陰謀シナリオを読みました。もう一方の対照グループは、そうした陰謀とは無関係な、中立的な内容の文章を読みました。
ここでも結果は明白でした。具体的な陰謀シナリオに触れた参加者は、中立的な文章を読んだ参加者に比べて、離職意図が上昇しました。その背景には、やはり組織コミットメントと職務満足感の低下という二段階のプロセスが介在していることが確認されました。たった数分間、架空の陰謀に関する文章を読んだだけで、人の心の中では組織への愛着が薄れ、その場を離れたいという気持ちが生まれるのです。
脚注
[1] Sullivan, D., Landau, M. J., and Rothschild, Z. K. (2010). An existential function of enemyship: Evidence that people attribute influence to personal and political enemies to compensate for threats to control. Journal of Personality and Social Psychology, 98(3), 434-449.
[2] Brotherton, R., French, C. C., and Pickering, A. D. (2013). Measuring belief in conspiracy theories: The Generic Conspiracist Beliefs Scale. Frontiers in Psychology, 4, 279.
[3] Tam, L., Lee, H., and Kim, J.-N. (2025). Conspiratorial thinking in the workplace: How it happens and why it matters. Journal of Communication Management, 29(1), 17-34.
[4] Douglas, K. M., and Leite, A. C. (2017). Suspicion in the workplace: Organizational conspiracy theories and work-related outcomes. British Journal of Psychology, 108(3), 486-506.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。