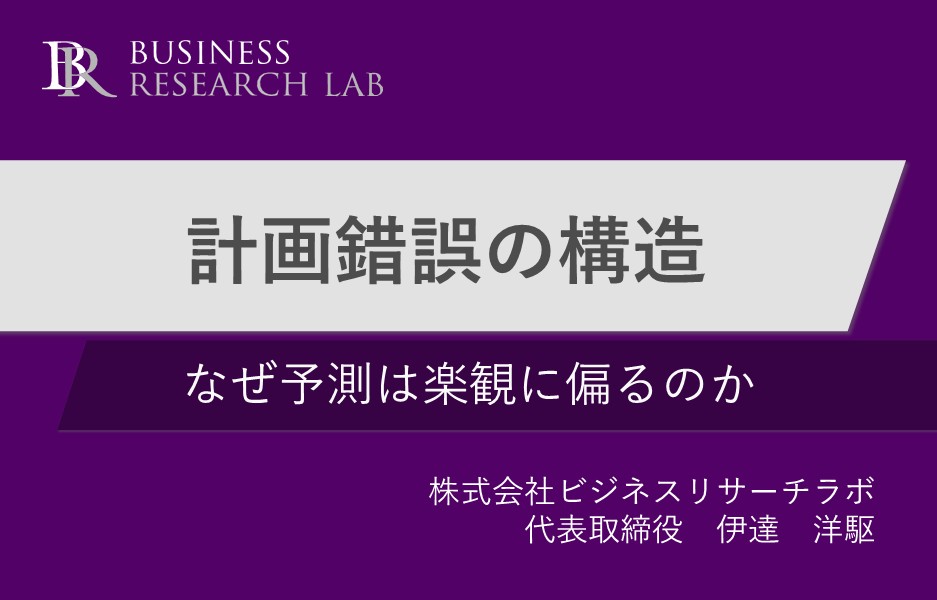2025年11月20日
計画錯誤の構造:なぜ予測は楽観に偏るのか
夏休みの最終日に、手つかずの宿題の山を前に呆然とした経験は、一定の人にとって懐かしい記憶かもしれません。あるいは、職場で「これなら一週間で終わるだろう」と高をくくったプロジェクトが、気づけば締め切りを過ぎていたという苦い経験をした人もいるでしょう。日常の買い物から国家的な大事業に至るまで、私たちの立てる計画は、なぜこれほどまでに楽観的に歪み、裏切られるのでしょうか。
計画の遅れを個人の能力不足や、やる気の欠如、あるいは不測の事態のせいだと考える人もいるかもしれません。しかし、この「計画通りに進まない」という現象は、特定の誰かに限った話ではなく、人間が抱える、ある種の思考の癖に根差していることが、心理学の研究からわかってきています。それは「計画錯誤」と呼ばれる、私たちの心に根ざした認知の歪みです。
本コラムでは、計画を立てる際に私たちの判断を狂わせる、目に見えない心理的な要因を検討していきます。「もっと慎重に考えればよかった」という後悔は、実は精神論だけでは乗り越えられない、巧妙な心の罠の結果なのかもしれません。記憶の仕組み、集団での話し合い、過去の失敗との向き合い方、社会的地位という観点から、計画が楽観的になるメカニズムを深掘りしていきます。
短く歪んだ記憶は未来の時間見積もりも短縮させる
計画を立てる際、私たちはごく自然に過去の経験を参考にします。「あの時と同じような作業だから、だいたい三時間くらいだろう」というように、過去の出来事の記憶が、未来を予測するためのものさしになります。このプロセスは合理的であるように思えます。しかし、もしその「ものさし」である記憶自体が、体系的に歪んでいるとしたらどうでしょうか。未来の予測もまた、その歪みに引きずられてしまうのではないでしょうか。この疑問を探求した一連の実験があります[1]。
最初の実験では、参加者である大学生に、これまで経験したことのない作業として、折り紙でウサギを三体作成してもらいました。ここで参加者は二つのグループに分けられました。一方のグループは、作業を始める前に、どれくらいの時間がかかるかを予測します。もう一方のグループは、作業を終えた直後に、実際にかかった時間を思い出して答えてもらいました。
結果、作業前に時間を予測したグループは、実際にかかった時間よりも平均で約25%も長く見積もっていました。未知の作業に対する慎重さがうかがえます。ところが、作業後に時間を思い出したグループは、実際にかかった時間よりも約30%も短く記憶していました。同じ作業を経験したにもかかわらず、未来への予測は過大に、過去の記憶は過小になるという、正反対の歪みが生じたわけです。
この結果は、馴染みのない作業と、一度経験した作業とでは、時間の感じ方が異なることを示唆しています。では、作業への「慣れ」は、時間見積もりにどのような作用を及ぼすのでしょうか。この点を調べるために、二つ目の実験が行われました。この実験では、折り紙の作成数を一体、三体、九体と変えることで、作業への経験の度合いを操作しました。そして、過去にかかった時間を思い出すグループと、これから追加で三体作るのにかかる時間を予測するグループに分け、それぞれの見積もりを比較しました。
そうしたところ、作業の経験を積めば積むほど、過去の記憶も未来の予測も、ともに「実際より短い」方向へとずれていきました。例えば、一体しか折ったことのない初心者の段階では、未来の予測はまだ少し長めでしたが、九体も折って熟練した段階になると、未来の予測は明らかに実際より短くなりました。過去の記憶についても、経験を積むほど、より短く思い出されるようになっていました。見積もりを出すまでの時間を十分間遅らせるという操作も、記憶をさらに短くする方向に働きました。
これらの実験から浮かび上がるのは、私たちが未来を予測する際に用いる「過去の経験」という記憶が、決して正確な記録ではないという事実です。経験を重ねることで、記憶は効率化され、圧縮されていきます。例えば、最初は一つひとつの手順を意識しながら行っていた作業も、慣れるにつれて一連の滑らかな動作として、大きな「かたまり(チャンク)」として認識されるようになります。
このように記憶が再構成される過程で、時間そのものの感覚も短縮されるのではないかと考えられます。あるいは、慣れた作業には注意をあまり払わなくなるため、心の中の時計の進みが遅くなり、時間を短く感じてしまうのかもしれません。
共同議論はタスク完了予測の楽観を増幅する
個人の記憶が歪んでいるのなら、複数の人間で知恵を出し合えば、より正確な判断ができるのではないか。これは、ごく自然な期待です。「三人寄れば文殊の知恵」という言葉が示すように、他者の視点を取り入れることで、一人の思い込みや見落としは訂正され、より客観的でバランスの取れた結論に至ると考えられています。多くの組織で、重要な計画が会議で議論されるのも、こうした集団の合理性を信頼してのことでしょう。しかし、ことタスクの完了時間を予測する場面においては、この期待は裏切られることがあります。
この点を検証するために、様々な状況設定で一連の研究が行われました[2]。長期的なプロジェクトから短時間の作業まで、個人が一人で立てた予測と、グループで話し合った後に立てた予測とが、どのように異なるのかを比較したのです。
最初の調査は、大学の授業で、学生たちがグループを組んで九週間かけて行うレポート課題を対象としました。学生一人ひとりが、課題の各章を仕上げるのにかかる日数と、最終的な提出日を予測しました。その後、グループで十分間のディスカッションを行い、グループとしての公式な予測を一つにまとめました。
結果、個人の予測の段階で、すでに実際にかかる時間よりも大幅に短い、楽観的な見積もりとなっていました。問題はその後です。グループで話し合って合意した予測は、個人予測の平均値よりも、さらに五日から九日も早い、一層楽観的なものへと変化していたのです。議論を経ることで、楽観性が修正されるどころか、増幅されてしまいました。
この現象が、長期的な課題に限ったものではないことを確認するために、実験室での研究も行われました。三人の参加者が一組となり、百ピースのジグソーパズルを完成させるという、比較的短時間で終わる作業です。この実験でも、グループで話し合った後の完了予測時間は、個人が単独で予測した時間よりも短くなるという、同じ結果が得られました。
なぜ、議論は予測をより楽観的にしてしまうのでしょうか。その謎を解く鍵は、議論の中で人々が「何に焦点を当てて話しているか」にありました。パズルの実験では、参加者が予測を立てる際に考えていることを声に出してもらう手法が用いられました。その内容を分析したところ、グループでの議論では、「この戦略でいこう」「角から攻めよう」といった成功のための計画や、「君はパズルが得意そうだ」といったメンバーの能力に関するポジティブな話題が会話の大半を占めていました。
その一方で、「ピースを探すのが大変そうだ」「途中で行き詰まるかもしれない」といった、起こりうる障害や困難についての言及は、個人で考えている時に比べて減少していたのです。
集団での議論は、成功に至るシナリオにばかり光を当て、計画の遂行を妨げる可能性のあるネガティブな情報を覆い隠してしまうフィルターのような働きをするのです。議論に参加しているメンバーの多くが「早く終わらせたい」という共通の願望を持っているため、その願望に沿った楽観的な意見が提示されやすくなります。
そうした意見が交わされるうちに、参加者は「やはりこの計画はうまくいく」と互いに確信を強め合ってしまいます。加えて、もし予測が外れたとしても、その責任は個人ではなくグループ全体に分散されるという安心感が、慎重な見積もりにブレーキをかけることをためらわせるのかもしれません。
人は過去の失敗を例外視し作業時間を短く見積もる
私たちは、これまでの人生で計画が思い通りに進まなかった経験を、一度ならず繰り返しているはずです。それにもかかわらず、新しい計画を立てる段になると、まるで初めて計画を立てるかのように、過去の教訓を忘れ、楽観的な見通しを立ててしまいます。この不可解な繰り返しは、人間の記憶力や学習能力に問題があるからなのでしょうか。あるいは、そこには過去の失敗を「なかったこと」にしてしまう、心の仕組みが働いているのでしょうか。
この問いに答えるため、ある研究者たちは、学生の日常的な課題を対象とした一連の実験を通じて、人が自らの過去の失敗をどのように解釈し、それが未来の予測にどう結びつくのかを丹念に調べました[3]。
卒業論文の提出を控えた学生たちに、いつ論文を提出できると思うか、最も楽観的な場合、現実的な場合、最も悲観的な場合を予測してもらいました。その結果、学生たちの現実的な予測の平均は提出期限の約三十四日後でしたが、実際の提出はその予測からさらに三週間も遅れました。半数以上の学生は、自らが設定した「最も悲観的なシナリオ」さえも守ることができなかったのです。この楽観的な歪みは、一週間以内に終える予定の学業や私的な課題でも同様に確認されました。
なぜ、これほどまでに予測は外れるのでしょうか。そのヒントは、予測を立てている最中の人々の頭の中にありました。実験参加者に、課題の所要時間を考えながら、頭に浮かんだことをすべて口に出してもらうという手法で思考プロセスを探ったところ、その内容の大部分、実に七割以上が、「まずこれをやって、次にこうして…」という、未来の計画を順序立てて思い描くことに費やされていました。
一方で、「そういえば前回は・・・」といった、過去の類似した経験に関する言及は、全体のわずか7%に過ぎませんでした。人々は、未来の成功シナリオを構築することに夢中になり、過去の経験という貴重なデータをほとんど参照していなかったのです。
さらに興味深いのは、過去の失敗経験に対する解釈の仕方です。参加者に過去の計画失敗を思い出してもらうと、多くの人がその原因を「たまたま邪魔が入った」「あの時は体調が悪かった」など、自分ではコントロールできない、外的で一時的な要因のせいにしました。ところが、他者の失敗については、「あの人は計画性がないからだ」というように、その人の内的な資質に原因を求める傾向がありました。自分の失敗は「例外的な不運」、他者の失敗は「起こるべくして起きた必然」と、都合よく解釈を使い分けているわけです。
この「失敗の例外視」が、学習を妨げる元凶です。この点を明らかにするために、研究者たちは実験を行いました。あるグループには、過去の失敗経験をただ思い出してから予測を立てさせました。別のグループには、過去の失敗を思い出した上で、「その経験が、今回の課題にどのように関連するのか」を意識的に文章化させました。そうしたところ、ただ過去を思い出すだけでは、楽観的な予測はまったく改善されませんでした。しかし、過去の失敗と現在の計画との間に自ら橋を架けさせた時、予測の楽観的な歪みはほぼ消え去りました。
この一連の研究が描き出すのは、計画錯誤の根深い心理的背景です。人は、自分の計画については「今回はきっとうまくいく」という希望に満ちた「内的視点」に没入します。そして、過去の失敗の記憶は、「あれは特殊なケースだった」というレッテルを貼られ、現在の判断材料から都合よく除外されてしまうのです。この無意識の「記憶のフィルター」と「自己本位な原因分析」こそが、私たちが同じ過ちを繰り返す理由と言えるでしょう。
権力者ほどタスク所要時間を短く見積もる
企業のプロジェクトであれ、行政の政策であれ、規模の大きな計画は、多くの場合、組織内で権力を持つ人物、すなわち管理職やリーダーによって承認され、あるいは主導されます。権力を持つ人は、持たない人に比べて多くの情報にアクセスでき、人や物といった資源を動かす力も持っています。そのため、直感的には、より現実的で達成可能な計画を立てられるように思えるかもしれません。しかし、心理学的な観点から見ると、「権力を持つ」という状態そのものが、人の認知や判断に特有の歪みをもたらす可能性が指摘されています。
権力は、人の思考をどのように変えるのでしょうか。ある研究者たちは、権力が人に目標達成への強い意欲をかき立てる点に着目しました[4]。目標が明確に見えていると、そこへ至る道筋、要するに計画の実行に意識が集中します。その結果、目標以外の情報、例えば、起こりうる障害、過去の失敗データ、計画を構成する細かなサブタスクといった、本来であれば考慮すべき周辺的な情報が視野から外れやすくなるのではないか。このように、権力が目標への過度な集中を促すことで、かえって時間予測の楽観性を強めてしまうのではないか、という仮説が立てられました。
この仮説を検証するために、いくつかの実験が行われました。最初の実験では、大学生を二つのグループに分け、一方のグループには、大学の制度改革について「自分の意見が50%の決定権を持つ」と信じ込ませることで、一時的に権力感を高めました。その上で、全員にレポート課題の完了にかかる時間を予測してもらったのです。結果、権力感を持たされた学生は、そうでない学生に比べて、実際に課題に着手するタイミングは早まりました。しかし、それ以上に完了予測が極端に楽観的だったため、予測と実績の誤差は、権力を持たない学生より膨れ上がってしまいました。
この効果が、実際に権限を与えられなくても、権力を持っていると「感じる」だけで生じるのかを確かめる実験も行われました。参加者に、過去に「自分が他者をコントロールできた経験」を思い出してもらうだけで、一時的に権力感を高めることができます。この操作を行った後、文書の体裁を整えるといった単純な作業の所要時間を予測させたところ、実際の作業時間に差はなかったにもかかわらず、権力感を高められたグループの予測は、対照グループよりも短くなりました。
権力が楽観的な予測を生む背後には、何があるのでしょうか。そのメカニズムを探る実験では、権力感を操作した上で、一部の参加者には、先ほど紹介したような「過去の失敗経験を思い出し、現在の計画と結びつける」という作業を行ってもらいました。すると、権力感が高いだけでは楽観的な予測が生まれましたが、過去の経験という「障害情報」に強制的に注意を向けさせると、その楽観性は打ち消されたのです。
このことから、権力が楽観的な予測を生み出すのは、人の注意を目標達成という一点に集中させ、過去の失敗といったネガティブな情報から目を逸らさせるためであることが示唆されました。
これらの知見は、調査でも裏付けられています。多くの学生を対象に、日常的に感じている権力感の強さと、学期中に課される複数の課題の完了予測、そして実際の結果を追跡調査しました。その結果、もともとの性格が楽観的であるかや、自分に自信があるかといった要因とは独立して、権力感が強い人ほど、タスクの完了予測を短く見積もり、実績との乖離が大きくなるという一貫した関係が見出されました。
脚注
[1] Roy, M. M., and Christenfeld, N. J. S. (2007). Bias in memory predicts bias in estimation of future task duration. Memory & Cognition, 35(2), 557-564.
[2] Buehler, R., Messervey, D., and Griffin, D. (2005). Collaborative planning and prediction: Does group discussion affect optimistic biases in time estimation? Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97(1), 47-63.
[3] Buehler, R., Griffin, D., and Ross, M. (1994). Exploring the “planning fallacy”: Why people underestimate their task completion times. Journal of Personality and Social Psychology, 67(3), 366-381.
[4] Weick, M., and Guinote, A. (2010). How long will it take? Power biases time predictions. Journal of Experimental Social Psychology, 46(4), 595-604.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。