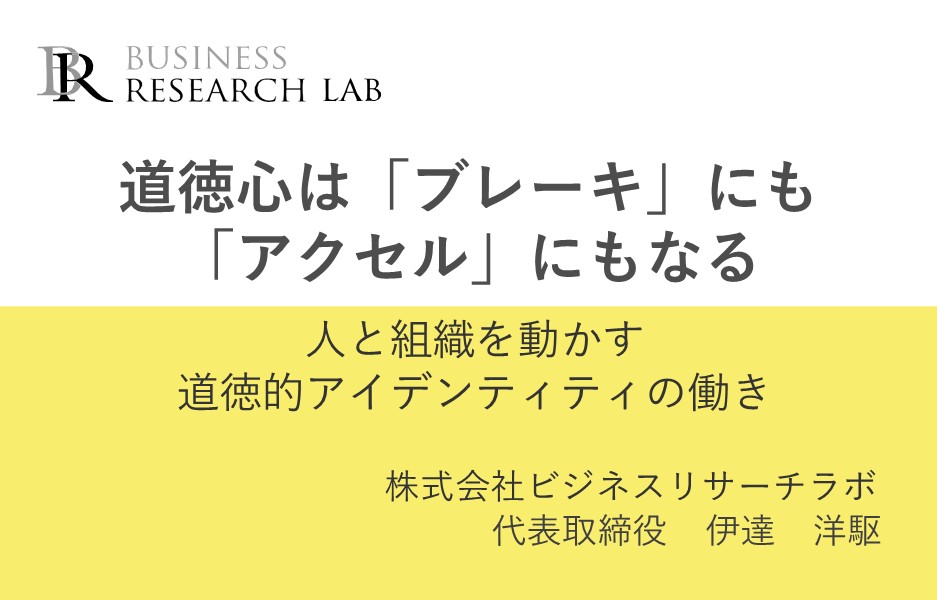2025年11月19日
道徳心は「ブレーキ」にも「アクセル」にもなる:人と組織を動かす道徳的アイデンティティの働き
私たちは日々、大小さまざまな「正しさ」に直面しながら生きています。困っている人に手を差し伸べるべきか、ルールを曲げてでも誰かを助けるべきか、自らの利益と社会の利益が対立したときにどう振る舞うべきか。こうした問いに対する答えの根底には、一人ひとりが持つ「道徳心」が存在します。
道徳というと、堅苦しく、どこか遠い世界の話のように聞こえるかもしれません。しかし、それは私たちの行動を決定づけ、人間関係を形作り、ひいては組織や社会全体のあり方を左右する、身近で強力な心の働きです。
ただ、一口に道徳心と言っても、その内実は1つではありません。心から他者を思いやり、自らの良心に従って行動する「本物」の道徳心がある一方で、他者から道徳的に見られたい、良い評価を得たいという動機から生まれる「見せかけ」の道徳心も存在します。
この2つは、表面的な行動だけでは見分けるのが難しいかもしれません。しかし、その根源にある動機が異なることで、もたらされる結果は変わってきます。本物の道徳心は、人と人との間に信頼を育み、組織に活気をもたらす源泉となり得ます。対照的に、見せかけの道徳心は、時として人間関係を歪め、正義の名の下に他者への攻撃を正当化する危険さえはらんでいるのです。
本コラムでは、この「本物」と「見せかけ」の道徳心が、私たちの仕事や社会生活の様々な場面で、どのように異なる結末を導くのかを探求していきます。リーダーの振る舞い、顧客との関係、慈善活動への向き合い方。いくつかの事例を通して、道徳心というものの複雑で奥深い性質を解き明かしていくことで、私たち自身の行動や、周りの人々の言動の裏にある真意を見つめ直すきっかけを提供できればと思います。
倫理的リーダーの成果は、関係・自信・一体感が生む
組織を率いるリーダーに求められる資質は数多くありますが、その中でも近年、そのあり方が問われているのが「倫理観」です。倫理的なリーダーシップとは、リーダー自身が公正さや誠実さといった規範的な行動を体現し、部下との対話や日々の業務を通じて、そうした姿勢を組織内に広めていく振る舞いを指します。このようなリーダーシップが、部下の不正行為を減らしたり、組織への貢献意欲を高めたりすることは、これまでの研究でも分かっていました。
しかし、部下個人の仕事の成果、すなわちタスク・パフォーマンスそのものを高めることにつながるのか、もしつながるのであれば、どのような心のプロセスが介在するのかについては、十分に解明されていませんでした。
この疑問を解き明かすため、ある調査が行われました[1]。対象となったのは、中国にある大手製薬企業で働く200名以上の部下と、その直属の上司72名です。調査では、部下たちに、自分自身の上司がどれほど倫理的に振る舞っていると感じるか、上司との関係の質はどうか、自分の仕事に対する自信はどの程度か、自分が所属する組織にどれだけ一体感を感じているか、といった点について回答してもらいました。一方で、上司には、それぞれの部下の仕事ぶりを客観的に評価してもらいました。
分析の結果、倫理的なリーダーシップは、確かに部下の仕事の成果を高める方向に関係していることが確認されました。しかし、その結びつきは単純なものではありませんでした。リーダーの倫理性が高いからといって、それが直接的に部下のパフォーマンスを向上させるわけではなかったのです。その間に、3つの心理的要因が橋渡しをしていることが明らかになりました。
1つ目は、リーダーと部下の間に築かれる「良好な関係性」です。倫理的なリーダーは、部下を公正に扱い、思いやりを持って接します。このような態度に触れることで、部下はリーダーに対して深い信頼感を抱きます。その信頼に応えたいという気持ちから、自発的に仕事への努力を惜しまなくなるのです。人が他者から受けた恩恵に対して、何らかの形でお返しをしたいと感じる「社会的交換」の心理に基づいています。
2つ目は、部下自身の「自信の高まり」です。倫理的なリーダーは、その一貫した言動や誠実な姿勢を通じて、部下にとっての優れた手本となります。部下は、そのようなリーダーの姿を間近に見ることで、「自分もこのように振る舞えるようになりたい」「自分にもこの仕事がやり遂げられるはずだ」という効力感を内面化していきます。リーダーが示す模範的な行動が、部下の「できる」という感覚を育み、潜在能力を引き出すきっかけとなります。
3つ目は、組織に対する「一体感の醸成」です。倫理的なリーダーが率いる組織は、高い道徳的基準を持つ、価値ある集団として従業員の目に映ります。すると、従業員は「自分はこの誇るべき組織の一員だ」という帰属意識を持つようになります。これが、組織全体の目標達成に向けて貢献しようという動機づけにつながり、個人のパフォーマンスをも高めることになります。
この調査が描き出したのは、倫理的リーダーシップが成果を生むための複合的な道のりです。リーダーの倫理観という「種」は、部下の心の中に「良好な関係」「自信」「一体感」という3つの「土壌」が育まれて初めて、パフォーマンスの向上という「果実」を実らせるのです。本物の倫理的リーダーシップとは、リーダー個人の資質の問題にとどまらず、部下の内面にどのようなポジティブな変化を生み出せるかという、関係性の中にこそ本質があると言えるでしょう。
顧客への報復は、上司の公正さと本人の道徳観で抑制可能
リーダーの倫理観が組織内部に良い循環を生む一方で、従業員は組織の外、とりわけ顧客との間で厳しい現実に直面することがあります。特にコールセンターや接客業など、日々多くの顧客と接する職場では、理不尽な要求や暴言といった、不公正な扱いに心を痛める従業員は少なくありません。このようなストレスにさらされたとき、従業員はどのように反応するのでしょうか。
中には、怒りや不満を内に溜め込むだけでなく、顧客に対して密かな「サボタージュ(破壊行動)」という形で報復してしまうことがあります。例えば、わざと電話を違う部署に転送したり、対応を遅らせたりといった行動です。これは組織にとって看過できない問題ですが、その発生には何が関わっているのでしょうか。
この問題を掘り下げるために、顧客からの不公正な扱い、上司の公正な態度、従業員自身の道徳観という3つの要素が、顧客への報復行動にどのように絡み合うのかを検証する研究が行われました[2]。調査は、個人主義的な文化を持つ北米と、集団主義的な文化が根強い韓国、それぞれの国のコールセンターで働く従業員、合計500名以上を対象に実施されました。
従業員たちは、日々の業務で顧客からどのような扱いを受けているか、直属の上司は自分に公正に接してくれるか、自分自身の道徳的な価値観をどの程度強く持っているか、といった質問に答えました。同時に、顧客に対して報復的な行動をどのくらいの頻度で行ったかについても回答を求めました。
両国の調査で共通して見られたのは、やはり顧客から不公正な扱いを受ける頻度が高い従業員ほど、顧客への報復行動に走りやすいという関係でした。しかし、この関係は決して一様ではありませんでした。上司の存在と、従業員本人の道徳観が、この負の連鎖を強めもすれば、断ち切ることもできる緩衝材のような働きをすることが分かったのです。
分析の結果、顧客への報復行動が最も顕著になったのは、「顧客から不公正な扱いを受け」、なおかつ「上司からも不公正に扱われている」と感じ、それに加えて「従業員本人の道徳観が低い」という、3つの悪条件が重なったケースでした。2重の不公正にさらされ、かつ自身の行動を律する内的な規範も弱い場合、不満は行き場を失い、最も手近な相手である顧客への攻撃という形で噴出してしまいます。
対照的に、たとえ顧客からどれだけ理不尽な扱いを受けたとしても、直属の上司が公正で、部下の話に耳を傾け、尊重する姿勢を見せてくれる場合、従業員の報復行動は大幅に抑制されました。上司の公正な態度は、顧客から受けた心の傷を癒し、不満の暴発を防ぐ「防波堤」のような機能を果たしていました。
最終的な行動の選択において鍵を握っていたのが、従業員自身の「道徳的アイデンティティ」でした。これは、人がどれだけ自分自身を「思いやりがある」「誠実である」といった道徳的な特性を持つ人間だと認識しているか、という自己概念です。
道徳的アイデンティティが強く、自らの行動を高い倫理基準に照らし合わせる習慣を持つ従業員は、たとえ顧客と上司の両方から不公正な扱いを受けるという最悪の状況に置かれたとしても、報復行動にはほとんど出ませんでした。その内なる道徳観が、外部からの否定的な刺激に対する「倫理的ブレーキ」として機能し、不適切な行動へと流されるのを防いでいました。この結果は、文化の壁を越えて確認されました。
見せかけの道徳心は、顧客への報復をかえって加速させる
個人の内面に根ざした道徳観が、不適切な行動に対する「ブレーキ」として機能することを見てきました。しかし、道徳心というものは、常にこのように建設的な形で現れるとは限りません。道徳心には、もう1つの側面が存在します。それは、他者から「道徳的な人間だ」と思われたい、社会的に望ましい自己イメージを演じたいという、いわば「見せかけ」の道徳心です。この2つの道徳心は、心の奥底にある「本物」の信念なのか、それとも他者の目を意識した「顕示的」なものなのかによって、全く異なる、時には正反対の行動を引き起こすことがあります。
道徳心の二面性が、顧客への報復行動にどのような結末をもたらすのかを検証した研究があります[3]。この研究も、カナダのコールセンターで働く300名以上の従業員を対象に行われました。
従業員たちは、顧客から受けた不公正な扱いの経験や、顧客へのサボタージュ行動の頻度について回答しました。それに加えて、彼らの道徳的アイデンティティが、どの程度「内面化」されているか(道徳的であることが自身の核心的な価値観となっているか)、そしてどの程度「顕示化」されているか(道徳的な人間であることを他者に見せることが、自分にとって重要か)を測定しました。さらに、調査から2ヶ月後の従業員の実際の業務成績データを人事部から入手し、サボタージュ行動が個人のパフォーマンスにどのような帰結をもたらすかまでを追跡しています。
分析の結果は、道徳心が持つ複雑な性質を浮き彫りにしました。これまでの研究と同様に、顧客からの不公正な扱いが、顧客へのサボタージュ行動を増やすという基本的な関係はここでも確認されました。問題は、道徳心の「内面化」と「顕示化」という2つの側面が、このプロセスにどのように作用したかです。
道徳的な価値観が「内面化」されている、すなわち本物の道徳心を持つ従業員の行動は、先ほど見た通りでした。たとえ顧客から不当な扱いを受けたとしても、サボタージュという行為そのものが自らの道徳基準に反すると考えるため、報復行動を強く抑制しました。ここでの道徳心は、やはり行動の「ブレーキ」として働いています。
ところが、道徳的であることを他者に見せびらかしたいという「顕示化」の欲求が強い従業員の場合、話は全く異なりました。特に、道徳観が十分に内面化されていない、つまり本物ではない従業員において、この顕示欲は危険な形で発揮されました。
不公正な扱いを受けると、「不正を許さない正義の執行者」という自己イメージを他者に対して演じ、守ろうとします。その結果、不当な顧客を罰することが、自らの道徳性の高さを証明する行為であるかのように捉え、かえって積極的にサボタージュで報復したのです。ここでの道徳心は、ブレーキではありません。むしろ、攻撃的な行動を正当化し、加速させるための「アクセル」と化してしまっていたのです。
そして、追跡調査によって得られた業績データは、冷徹な現実を突きつけました。顧客へのサボタージュという形で「正義」を執行した従業員たちの業務成績は、明らかに低下していました。密かに行われた報復行為は、巡り巡って自分自身の評価を損なうという結末を迎えていました。
道徳的な人ほど、時間での寄付を、お金より尊ぶ
これまで、職場という環境における道徳心の光と影を見てきました。リーダーシップを支える力となったり、不適切な行動のブレーキとなったり、時には攻撃性を加速させるアクセルになったり。では、より広い社会的な文脈、例えば慈善活動のような場面では、人の道徳観はどのように現れるのでしょうか。
私たちが誰かを助けたいと思ったとき、その手段には大きく分けて2つあります。「お金」を寄付すること、そして自らの「時間」と労力を提供するボランティア活動です。仮に、1万円を寄付することと、時給1000円の人が10時間働いて1万円分の価値を生み出すボランティア活動は、経済的には等価かもしれません。しかし、私たちの心は、この2つを同じものとして捉えているのでしょうか。
この「お金か、時間か」という慈善活動における選択と、個人の道徳観との関係を探るため、一連の調査と実験が行われました[4]。これらの研究群は、道徳心の本質を異なる角度から照らし出し、1つの統合された物語を紡ぎ出しています。
最初に行われた調査では、人々に、自分の余暇時間1時間あたりの金銭的価値を計算してもらった上で、その価値と等価の「お金の寄付」と「時間の寄付(ボランティア)」のどちらが、より道徳的で、心のこもった行為だと感じるかを尋ねました。結果、人々は金額的な価値が全く同じであっても、自らの時間と労力を捧げる行為のほうを、単にお金を差し出す行為よりも、はるかに道徳的で思いやりにあふれたものだと評価しました。この考え方は、もともと自分自身を道徳的な人間だと強く認識している人(道徳的アイデンティティが高い人)ほど、顕著に見られました。
次に、この視点を個人の行動から企業の社会貢献活動へと移して検証が行われました。ある企業が、同じ価値を持つ2つの選択肢、つまり「現金での寄付」と「従業員のボランティア活動の支援(時間の寄付)」のどちらかを選ぶというシナリオを提示し、どちらの企業をより高く評価するかを尋ねました。ここでも結果は一貫していました。特に道徳観の強い参加者ほど、従業員の時間を社会のために提供する企業のほうを、より倫理的で、真の社会市民であると評価しました。
しかし、現実の世界では、誰もが自由に時間を使えるわけではありません。特に、社会的地位が高く、多忙な日々を送る人々にとって、時間は希少な資源です。そこで3つ目の研究では、米国のビジネススクールを卒業した、現役のビジネスパーソンを対象に調査を行いました。予想通り、組織内での地位が高い人ほど、つまり時間的価値(時給)が高い人ほど、慈善活動としてはお金での寄付を選ぶという全体的な傾向が確認されました。
しかし、ここにも1つの例外が存在しました。それは、道徳的アイデンティティが高い人々です。彼ら彼女らは、自らの社会的地位や時間の希少性といった現実的な制約に左右されることなく、時間を使った貢献を厭わないという一貫した姿勢を示しました。彼ら彼女らにとって、道徳的行為の選択は、経済的な合理性だけでは測れない、より高次の価値判断に基づいていたのです。
最後に、実験的な手法を用いて、参加者の道徳心を一時的に高めるという操作が行われました。あるグループには、「思いやり」「公正」といった道徳に関連する言葉を使って短い物語を書いてもらい、意図的に道徳的な意識を活性化させました。その上で、道徳的な目的を持つ団体への寄付を募ったところ、道徳心を刺激された人々は、そうでない人々に比べて、お金での寄付ではなく、時間を提供するボランティア活動を圧倒的な割合で選択しました。
これら一連の研究が指し示すのは、なぜ時間での貢献が特別視されるのか、という問いへの答えです。それは、時間が「自己そのもの」のかけがえのない一部だからです。お金は代替可能で、誰が稼いだものであっても価値は同じです。しかし、時間とは、その人の人生そのものであり、二度と取り戻すことのできない個人的な資源です。それを他者のために捧げるという行為は、自己の一部を直接的に差し出すことに他なりません。
道徳観が強く、自身のアイデンティティと道徳的価値観が分かちがたく結びついている人にとって、この「自己の投入」は、自らの信念を純粋に表現する手段となります。それは、他者からどう見られるかという外面的な評価のためではなく、自己の内なる価値観と行動を一致させたいという欲求の発露なのです。
脚注
[1] Walumbwa, F. O., Mayer, D. M., Wang, P., Wang, H., Workman, K., and Christensen, A. L. (2011). Linking ethical leadership to employee performance: The roles of leader-member exchange, self-efficacy, and organizational identification. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 115(2), 204-213.
[2] Skarlicki, D. P., van Jaarsveld, D. D., Shao, R., Song, Y. H., and Wang, M. (2016). Extending the multifoci perspective: The role of supervisor justice and moral identity in the relationship between customer justice and customer-directed sabotage. Journal of Applied Psychology, 101(1), 108-121.
[3] Skarlicki, D. P., van Jaarsveld, D. D., and Walker, D. D. (2008). Getting even for customer mistreatment: The role of moral identity in the relationship between customer interpersonal injustice and employee sabotage. Journal of Applied Psychology, 93(6), 1335-1347.
[4] Reed II, A., Aquino, K., and Levy, E. (2007). Moral identity and judgments of charitable behaviors: A social identity perspective on giving time versus money. Journal of Marketing, 71(1), 178-193.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。